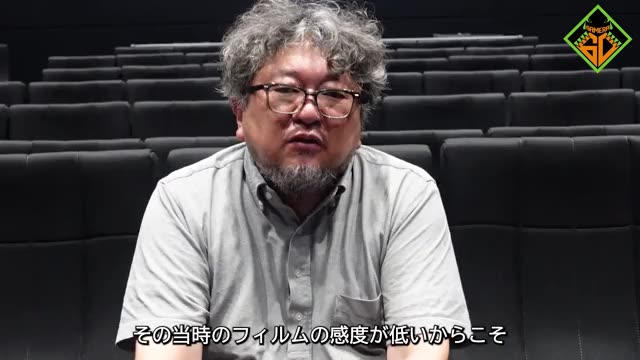大怪獣決闘 ガメラ対バルゴンのレビュー・感想・評価
全26件中、1~20件目を表示
愛すべきガメラ初の大怪獣バトルを4Kで堪能!
ガメラ生誕60周年記念「昭和ガメラ映画祭」にて。(4Kデジタル修復版)
ガメラ映画の第二弾。本作から総天然色(カラー)で制作されている。
昭和41年春、大映東京撮影所製作の本作と、大映京都撮影所製作の『大魔神』との〝特撮2本立て〟で公開された。
第一弾『大怪獣ガメラ』のヒットで傾きかけていた経営を建て直した大映が、さらなる期待を込めて巨費を投じた一大興行だった。
4Kデジタル修復版は今回の特集上映が初披露。
前作でロケットに乗せられて火星に向けて打ち出されたガメラだったが、ロケットが隕石と激突して解き放たれ、地球に再度飛来。黒部ダムを急襲、破壊して赤道直下の火山へと去っていく。
ダムの責任者が破壊者ガメラを見あげて「こりゃもう、どうにもならん」と絶望する。
オープニングでこの迫力のミニチュア・スペクタクルを見せたあと、怪獣はしばらく出てこない。
映画は、戦時中にニューギニアのジャングル奥地の洞窟に隠されたという宝石オパールを求めての、宝探し探検物語を描いてゆく。
裏切りによる殺人があるなど、このドラマ部分はちょっと恐い。
劇中で、ジャングルの現地住民を「土人」と呼ぶ。確かに、当時はそういう言葉があった。恐らく語源は「土着民」だと思うが、未開民族を侮辱する意味で使われていたはずだ。
主演は、宝探し隊チームの一員であるパイロット平田圭介役の本郷功次郎と、日本語を解する土人の娘カレン役の江波杏子。
本郷功次郎は目鼻立ちがはっきりした二枚目であり、意外と筋骨隆々として逞しい。
江波杏子はエキゾチックな顔立ちが異邦人らしいが、土人たちの中にいて唯一色白で、日本に来ると突然洗練されたレディに変貌している。
ドラマ部分にはこの二人のロマンスめいた雰囲気が織り込まれている。
脚本は前作に引き続いて高橋二三。昭和ガメラ8作の全てを書いている。
監督は本編をベテランの田中重雄が、特撮を前作では本編を担当した若手の湯浅憲明が担当。湯浅憲明は、大映社内でも二級品扱いされた『大怪獣ガメラ』を成功に導いた立役者だが、作品の位置付けが変わった続編プロジェクトでは本編を外され、さぞ悔しさがあっただろう。
音楽の木下忠司はガメラシリーズの仕事は本作だけだと思うが、木下恵介の実弟であり木下作品をはじめ多くの劇伴を手掛けたベテラン。あの、ビョョョロォォ〜ンという音を出している楽器は何なのだろう。オーケストラを使っていないスリラー系の映画などでたまに聞く音だ。
本作が公開された同年の暮れには、東宝はゴジラのシリーズ7作目『ゴジラ・エビラ・モスラ 南海の大決闘』という怪獣大集合のお祭り映画を公開しているから、ドラマ部分がオトナ中心の本作は、お子ちゃま路線に突き進むゴジラへのアンチテーゼともとれる。
しかし、ガメラ初の怪獣バトルは、第1ラウンドの大阪城決戦ではあっさりと凍らされて敗れ(仁王立ちで凍りついたガメラが可愛い)、第2ラウンドの琵琶湖決戦でリベンジを果たすが、人間によって得意技を無力化されたバルゴンに噛みついて琵琶湖に引きずり込むという、言えば地味な闘いだった。バルゴンは水に溶けてしまうという最大の弱点があったのだ。
そもそも、トカゲ型のバルゴンのデザインは、気持ち悪さは出ているもののダサすぎる。
背中から発する虹色光線や、溶けて紫色の泡になっていくなどは、カラー作品の効果を活かしたものだろう。
怪獣が両方とも四脚歩行なのが、肉弾戦に迫力を出せなかった理由ではないかとも思う。
やはり、大怪獣のバトルは東宝が何歩も先を行っていた。
黒部ダム、ポートタワー、大阪城などのミニチュアは手が込んではいるものの、東宝のゴジラシリーズと比較すると見劣り感は否めない。戦車や車両はおもちゃ感が見え見えだった。
とはいえ、ガメラにはゴジラにない得も言われぬ魅力があった。
形状が亀という親しみやすさに、鋭い牙をのぞかせるギャップだろうか。
ギロリと眼球を動かす目がまた、いかにも作り物っぽくて怖いようで可愛くもあるのだ。
もともと地球の生物なのに、手足を引っ込めてジェット噴射するという不可思議と、そのジェットで回転して飛ぶユニークさ。
これを「萌える」と言わずば何と言おう。
それにしても、勝利して飛び立っていったガメラの、その後の脅威に人々はどう備えるつもりなのだろうか…?
宇宙に行ったガメラが復活。前作の船越博士とかどこ行った?(笑) な...
『大怪獣決闘』の裏側で、もう一つの対決が…
大映ガメラシリーズの二作目。
誰も成功を期待せずカラー化する予算ももらえなかった前作『大怪獣ガメラ』の予想外のヒットを受け、大幅予算アップで製作された本作。もちろんカラー作品。
シナリオも前作と同じ作家が書いたとは思えないほど重厚で本格的。
核兵器の影響でガメラが復活するという設定以外メッセージ性皆無だった一作目と異なり、人間の強欲(利己主義)が招く悲劇が主要なテーマとなっていて、巨大オパールと誤解されるバルゴンの卵や5000カラットのダイヤがアイコンとして用いられている。
本作で新しく用意されたガメラの着ぐるみは目つきが鋭く口も大きく開き、より凶暴な雰囲気。
合成ではなく直火を使用したガメラの演出はあらためて見るとかなりの迫力。
前作ではアニメで表現される場面が多かった回転ジェットもすべて本物の火が使われていて、見応え十分。
ただし、いろんなものに引火して撮影現場は大変だったそうで、ガメラが大阪城で復活する場面でも本体に延焼しているのが確認できる。
今回登場する冷凍怪獣バルゴンはガメラの腹甲同様、焼き網模様の表皮のデザインがチープで造形的には今イチ。しかし、大映特有の凝ったカメラアングルや陰影を強調した撮影でカバーしていて、尻尾の操演もゴジラのスタッフがバイトで参加してるんじゃと勘繰りたくなるほどヴィヴィッドで生物的。
ダサいデザインに反して初戦ではガメラを圧倒し、人類が繰り出す攻撃にも倒れず意外と強い。
神戸港で巨大化したあとすぐに姿を見せず、倉庫を見下ろすようにして登場する場面の演出は秀逸。
海中でデカくなったのに水が弱点という設定には矛盾を感じるので、浸透圧の関係で淡水に弱いということにしておけばよかったのでは。
本作は旧大映シリーズのみならず、すべてのガメラ作品のなかで唯一子供がストーリーに絡まない大人向けの作風。
レビューを投稿された方の間でも賛否両論だが、本作のようにアダルトな方向性を継続させるべきだったかはギロン、いや議論を呼ぶところであろう。
主演の本郷功次郞はゲテモノ映画に出るのが嫌で、散々逃げ回った挙げ句に仮病で入院までしたのに、「治るまで待つ」と言われて観念したそう。
後年、彼はその時のことを「ほかの俳優がみんな逃げちゃって自分しか残ってなかった」という趣旨の発言をしているが、たぶん違うと思う。
当時の大映での本郷は看板俳優、市川雷蔵の弟分的立場。消去法的なキャスティングではなく、会社としては東宝における宝田明のような存在に彼を仕立て上げたかったのだろう。
柔道をやってただけあって、いいガタイしてる。
江波杏子が演じるカレンは場面ごとに衣裳が異なり、おしゃれでファッショナブル♡
本作の見どころの一つなので、「来日中の原住民の娘が何着服持ってるんだ」などと言い掛かりを付けてはイケナイ。
子供の頃、江波はすでに軸足をTVに移していて姉御的な役柄が中心。
あらためて大映時代の出演作を調べると、『女賭博師シリーズ』とか、女なんとかみたいなのばっかし。
本作こそ彼女の初期の代表作といってもいいような気もする。
医師の松下を演じた菅井一郎は溝口健二監督作品の常連にして、黒澤明の監督デビュー作『姿三四郎』(1943)をはじめ、彼の作品にもたびたび起用された名脇役。
出番は少ないが、老練な演技を見せてくれる。
上記の三人と藤岡琢也を除けば、出演陣はほぼ端役中心だが、大映誕生以前から活躍したベテラン監督の田中重雄が妥協のない演技を引き出している。
南国の原住民を日本人が演じるのは東宝特撮作品でも定番だが、本作は短いダンスシーンのためにプロの舞踊団を雇うなど本気度が非常に高い。
原住民部落の全景に使われたマットペイントなんて、出来映えはほとんど絵画作品。
本作は初公開当時、京都撮影所が製作した『大魔神』との併映。どちらの製作スタッフも互いの情報をある程度は把握していたはず。
大映の東西両撮影所は対抗意識が強かったことで有名(今風にいえばバチバチの関係)。
そもそも『大魔神』は『大怪獣ガメラ』を成功させた東京撮影所に対する競争心から生まれた企画で、本作が関西を舞台にしているのに関西弁がほとんど使われないのも東京撮影所の京撮に対する反発心が影響しているから。
『大怪獣決闘』の裏では「大映撮影所の対決」が行われていたとも言えるし、深読みすれば副題には京撮の『大魔神』と雌雄を決するという心意気が込められているという気も。
両撮影所が互いをライバル視して競い合った結果のケミストリーが、ともに完成度の高い作品を生み出したように思う。
ちなみに、どちらも大型予算を組んでもらったものの、本作は赤字、『大魔神』はトントンだったとか。
色彩美を意識した大映伝統の画面作りへの拘りは本作でも健在。
ガメラの炎やバルゴンの殺人光線(虹)を強調するため、両怪獣の二度の決闘はナイトシーンに限定され、怪獣の血やガメラの炎(火炎噴射は赤、回転ジェットは青で表現)の色分けといった細部まで徹底している。
原住民のダンスシーンの衣裳や楯もカラフル。
自分の推し場面はバルゴンが孵化するシーン。
赤外線治療器のクローズアップを執拗に繰り返すことで、ただの機械がまるで一つ目の怪物かHALー9000のように邪悪な意思を持つ存在に見え、機械文明への警告や、前作で言及されなかった放射能の危険性への隠喩にも思えてくる。
バルゴンはお目々パッチリでキュート
ガメラ生誕60周年記念昭和ガメラ映画祭にて鑑賞。
当時の印象はほぼ覚えていないが、あらためて観ると非常に真っ当につくられた直球勝負の怪獣映画で面白かった。脚本がしっかりしており、ドラマパートと特撮パートのバランスもよいが、冒頭に地球に帰還したガメラがひと暴れしたあと、しばらくは怪獣が登場しないため、当時の子供たちには退屈だったかも。
ミニチュアもよく作り込んであり、バルゴンが通過する背景の建物の中に人影が動いていたりと芸が細かい。特にバルゴン幼獣孵化のカットは、エイリアン誕生ばりの粘液ネッチョリの表現で、今見ても感心する出来栄え。
なお怪獣が登場するシーンは全て夜という設定で、おそらくは特撮のアラを隠すためだろうが、その甲斐あって当時結構コワかった記憶。まあバルゴンはお目々パッチリの3頭身体型(シッポ含まず)で意外とキュートですけど。
観たのは平日午前中の上映回だったが、客層はリタイアして時間(ヒマ)だけはありそうな60代ぐらいの男の子が大多数という殺伐とした雰囲気。マッツ・ミケルセン特集とはエラい違いだなあ(笑)。
4Kレストアはやりすぎ感のない自然な仕上がりでとても好感がもてた。
氷の街に架かる夜の虹!欲望渦巻く大人のガメラ映画。怪獣映画界のうなぎパイ。ミニチュア特撮の幸福。
私のベストガメラ映画です。ガメラにとって、シリーズ2作目にして最初の対戦映画であり、最初のカラー作品。
シリーズでは異色作。その特長は、欲望が渦巻く、大人のガメラ映画であることです。
子供が出てこない、9割が夜のシーン、ガメラの歌もない(ギャオス以降)、ガメラマーチも無い(ギロン以降)。
ガメラは人類の味方ではなく火炎エネルギーを求めて飛来し、出合ったために本能的に戦闘しただけ・・・など、あからさまに子供向けには作られていない点が良いです。
そして、初の対戦相手であるバルゴンがユニーク。
もっぱら特撮ファンの間で有名な話は、バルゴンの不思議について。
熱帯のニューギニア出身なのに冷凍怪獣!なのに水に弱い!周りを凍らせた氷が溶けたらどうするの!
自己矛盾してないか! などという愛ある突っ込みが出来るところが、また愛おしい。
高山良策氏(ウルトラシリーズでお馴染み)製作によるヌイグルミも、愛嬌があり、縦に閉じるまぶたがキュート。
また、本作ではガメラも凶悪な面構えと基本四足がカッコイイ。ゴジラで言うところのキンゴジに相当?
最も好きなのが、「大阪、夜の虹」!
大阪城でバルゴンが虹色光線を放射するシーン。
夜、凍る街で、いきなり虹を映し出す意外性と、その妖しい美しさ。
シネスコ画面を横断するスケールといい、本作でのベスト・シーンです!
他にも特撮では、冒頭のダム破壊、神戸港でのバルゴン誕生、大阪城冷凍、琵琶湖決戦など、シネスコの横長画面いっぱいに映える広大なミニチュアセットをロングで捉えていて、左右に2怪獣を配置する構図が見事です。
また、数カットですが、人と怪獣を一画面におさめた、きれいな合成も効果的です。
出演者では、江波杏子の日本人離れした容姿が美しい!現地人のコスプレも白いスーツもお似合いです!
本郷功次郎の正義漢は定番ですが、ヒロインとちょっといいムードになるのも憎い。
その他、大映俳優陣の方々もいい味を出してらっしゃいます。
一番親しみを感じるのが「ルビー殺人光線銃」※を開発した北原義郎演ずる天野教授で、バルゴンの断末魔の虹を解説します。
(※いいのかそんなもの作って!東宝はちゃんと気を使ってメーサー殺”獣”光線と言ってます。)
ギャオスでも同じく博士としてラストに出演されて、ギャオスの断末魔の音波光線でもまったく同じ解説をされるので、昔の名画座での連続上映では毎回拍手喝采でした。(^^)
ナレーションの若山弦蔵!(ショーン・コネリーなどの声優)もしぶいです。
「カットされた?幻のバナナの皮のギャグ」について
※今回のトークショーで樋口監督が言われていましたが。
ニューギニアからの帰り、洋上の船で、船員が船室から小野寺(藤山浩二)をマージャンに誘い出すときのシーン。
その船員が戦友の遺骨(と称した箱)にお供えしてあるバナナを1本とって食い、廊下で皮を捨てるのですが、その皮を踏む直前でカットが変わります。
どこにも証拠はありませんが、絶対皮を踏んですってんころりんというカットが絶対あったはずです。
あまりに古典的なギャグが流れに合わないので切ったのでしょう?
ちなみに併映は「大魔神」!
音楽は木下忠司(木下恵介の弟。「喜びも悲しみも幾歳月」(1957)他多数「特捜最前線」の巨匠。今回初めて気づきました。)
キャストでは、東宝なら、江波杏子さんは水野久美さん、本郷功次郎さんは佐原健二さんか宝田明さん、久保明さんですね。
昔のアクション映画には「怪しい中国人」が必ずいましたね。谷謙一さんの他にも藤村有弘さんとか、怪しい中国訛り?の日本語で。
【”皆、大好き怪獣映画。そして炎VS零下100度の冷凍液。”今作は、欲に駆られた人間が孵化させてしまったニューギニアの伝説怪獣バルゴンとガメラの決闘シーンは見応えがある作品なのである。】
■ニューギニアの奥地の洞窟に隠されていた巨大なオパールを、小野寺が仲間の平田、川尻を犠牲にして日本に持ち込む。
だがそれはニューギニアの伝説怪獣・バルゴンの卵だった。小野寺が水虫の治療で赤外線を使ったために(クスクス)孵化したバルゴンは突然変異により成長し、大阪を襲来する。零下100度の冷凍液を噴出して大阪城を氷結させる。そこへ、ガメラが現れるが冷凍液により凍ってしまう。
◆感想
・ガメラが人気なのは、人型ではなく円盤状の形態になり、グルグル回りながら飛ぶところだと思う。多数居る怪獣の中でも、その斬新な形態が魅力なのである。
・今作では、対決するバルゴンも爬虫類系で、こういう場合どのように動かすのかな?人が入っていたのなら、そりゃあ大変だ!
■怪獣あるある。…ムッチャ強いのに、意外な点が弱点という事。
⇒今作で言えば、バルゴンが水に弱いという所である。
・ガメラとバルゴンの対決は見応えがある。人型でなく爬虫類VS亀と言う所も斬新なのである。
<今作は、欲に駆られた人間が孵化させてしまった怪獣バルゴンとガメラの決闘シーンは見応えがあるガメラシリーズ第二弾である。>
巨大怪獣と大人の物語
BSトゥエルビの録画を観ようと思ったのですが、2025.11.9の放送時、津波注意報の表示が有り終盤まで画面に日本地図が入り込んでいて邪魔に感じたので、Huluの配信を観ることにしました。
大人の男女に焦点を当てたガメラ映画です。
前作は東京タワーでしたが、本作は大阪城や琵琶湖が登場します。
和風の琴の音色も大人っぽさを感じさせます。
ガメラが空から登場し、卵から孵った急成長バルゴンと戦います。
人間がヘリコプターを使用して人工的に天候を変えたり、バルゴンから出る虹を巨大な鏡で反射させたりと、バルゴン討伐のために様々なことをします。
異国を探検したり、現地に住む美女に助けられたり、宝石をめぐるプロットは面白いです。
ガメラ対ゴジラ
シリーズ過渡期の佳作
大映ガメラシリーズ2作目ということで
大映初の怪獣対決作品
敵怪獣バルゴンはニューギニア生まれなのに冷凍液出したり
生物なのに水に弱いという謎の生態の怪獣
特に設定はされてないが
もしかしたら太古の昔に隕石に乗ってやって来た
宇宙怪獣なのかも知れない
過去に現れた伝説が残ってるということは
あの島にはまだバルゴンの卵が眠ってるかも
ちなみに昔の怪獣図鑑で
動物図鑑みたいに何々科という分類があったのだが
バルゴンはゴジラ科という謎の分類されてた
光線出すトカゲ型怪獣だからだろうか?
また別の怪獣図鑑では
バルゴンの尻尾の破壊力について
「藤猛(当時のスーパーライト級世界チャンピオン)の何倍」
という記述に時代を感じさせる
当時の東宝怪獣の多くは
爪や牙や角や翼などの身体の部位や
怪力や飛行能力などの身体能力を除く
光線を吐くなどの特殊能力は大抵ひとつなのだが
(キングギドラの飛行能力は一応翼由来と考えて)
バルゴンは冷凍液と虹色光線のふたつ
ガメラも火炎放射と飛行能力のふたつなので
これ以降の大映怪獣の特殊能力は基本ふたつ以上が
本作で定着する
(尖がり頭だけが武器のバイラスみたいな例外もいるが)
バルゴン出現までの人間のドラマが凄く長く
それ以降も人間同士のバトルの方が
怪獣のバトルよりも迫力がある異常事態(?)に
小野寺のクズっぷりが清々しいレベルだが
根っからの極悪人と言うより
巨大なオパール(実はバルゴンの卵)に目が眩み
次第に暗黒面に堕ちて行く感じで
悪人だが人間的に許せてしまう気もする
バルゴンに喰われた時は「ざまああああwww」だったけど
その大人の醜いドラマが強い印象に残る一方で
子供が全く出ないのがシリーズとしては異色の作品
主役のガメラは前作で宇宙に追放されたものの
隕石衝突であっさり地球に帰還して黒部ダムで大暴れ
本作ではまだガメラは人類の味方ではなく
たまたまバルゴンに闘争本能を向けただけの感じ
本作以降ガメラは一回敵怪獣に負けて
後半で逆転勝ちのパターンが続く
何かの本で誰かが「ガメラは三本勝負」と言ってたが
一回負ける点では確かにその通り
本来のプロレスの三本勝負とは
負け役の相手にも一回は負けることで
相手の必殺技を観客に披露し
相手の顔も立ててあげる為の試合方式だが
ガメラも一回負けることで相手の強さを披露する
怪獣プロレスという点では東宝に勝ると思う
ダイヤモンドで誘導作戦やミラーで反射作戦など
対バルゴンの人間サイドの作戦も
なかなかシリアスでリアル
ガメラに活躍させる為に結果的に失敗するが
惜しい所まで行ってる
南方の原住民を日本人の役者がドーラン塗って演じ
日本語喋れるのは東宝作品に準ずるが
日本人の医師が住んでる辺り
その点に気を遣っている
江波杏子さん演じるカレンの日本語は
ちょっと流暢過ぎる気もするが
それにしても台詞に現在では使えない言葉多いなあ
土人に部落に奇形児
まあ59年前の作品だから仕方ないが
ガメラの初バトル!案外、強敵だったバルゴン!
子供の頃は怪獣博士と呼ばれてました。勿論、本作品も観た覚えはあるんですが、内容は全く記憶にありません。バルゴンは覚えてたんですが、こんなに着ぐるみ感満載だったんだと、驚いちゃいました。
まぁ、昔の映画ですからね。
ミニチュアといい、着ぐるみといい、チープ以外の何物でもありません。今、見るなら茶化しながら楽しむのが正解かな。
ガメラというと、子供の味方のヒーロー怪獣というイメージが強かったんですが、本作では全くその雰囲気が無かった事を改めて知りました。
【ネタバレ】
内容的には、前作の続きから始まります。火星へ飛ばすつもりが途中で隕石とぶつかり、ガメラは地球に戻ってきてしまう。
初っ端から、いきなり黒部ダムの破壊という大掛かりな特撮なんだけど、ちょっとショボかったかな。
戦時中に隠した宝石を取りに行くという、ちょっとしたアドベンチャーの雰囲気も醸し出すんですが、やっぱりこれもショボい。
結局、持ち帰った宝石が実はバルゴンの卵だったって事で、神戸の街がバルゴンに破壊されてしまう。
そこにガメラが登場するんだけど、やっぱり最初はやられちゃうんだよね。
一応、大人向けだったのかな。様々な作戦でバルゴン討伐に奔走する。まぁ、ご都合主義の子供だましって言っちゃえばそれまでだけど、結構マジメな作戦の数々だったと思う。
ただね、バルゴンの誕生からしてそうだったんだけど、ヒトの強欲があまりにも酷すぎる。自衛隊?の作戦中に一般市民が入り込んで、ダイヤを奪って作戦失敗なんて、あまりにも現実離れしてて呆れちゃいました。
クライマックスは、ガメラとの再戦!やっぱり怪獣映画はこれだよね。チープな着ぐるみプロレスであっても、怪獣大好きオヤジは満足です。
ガメラシリーズは、流血戦になるところが、なお好きです。
カラー化された初のガメラ
今だに観返すシリーズ9
箇条書きしてみる。
・ガメラ再来! ダムに体当たり、恨みが感じられる。
・バルゴン孵化! 血混じりの粘液、キッショ。
・シネスコ効果満点! 第1R、朦朧とする目の点滅、最後の一撃、ギャッギャッギャー!!
・傷口ゴポゴポ、最終Rは嬲り殺し?
・一人じゃないわ・・来るよ、きっと来るよ!(嘘)
とにかくヌメヌメ、紫、変な瞼、キモイ舌、バルゴンの気持ち悪さが際立つ。ギャッギャッギャー!!!
追記 最近、レビューのアイコンを大阪のシーン再現に変えました。
角川シネマ有楽町にて4K上映。
樋口カントク&監修小椋俊一トークイベントはちょっと寝ていたが、言われたガメラの発光する目に注目。確かに赤く見えたりしていた。
毒サソリが尾を震わせたりして、意外とちゃんと作られていた。
ダイヤ&小野寺を呑み込み、尻尾を振って上機嫌のバルゴンがちょっとカワイイ。
全席完売、杖無しで歩けないお客さんも多数。
0009 最終決着地は琵琶湖
1966年公開
のったりーまったりーするけど
重厚さのある怪獣映画といえばコレ!
とにかく画面の使い方が斬新。
左端のバルゴンの光線が画面の右端のガメラに炸裂!
ワンテンポ遅れてガメラが吹っ飛ぶ。
特撮が下手なのか演出が凄いのかわからんが
効果は抜群。
ガメラがバルゴンを強引に湖に沈めて決着をつけるが
木下忠司の荘重な音楽がようやく危機が去ったという
安堵感を醸し出す。
ガメラはさらなる強敵を求めてどこかに飛び立っていく。
70点
本作は「大魔神」が併映。
東京で「ガメラ」京都で「大魔神」を製作。
東宝では出来なかった特撮2本立てを実現する。
1作目より物語がしっかり
荒唐無稽だった前作「大怪獣ガメラ」よりも欲にまみれた人物が登場し、人間の因果な部分を見せられる為、子どもの観る怪獣映画と言うスタンスから離れた作品になっていると思う。
モンスターパニック映画に必須のキャラクターとして、怪獣より怪物な悪人がいるものだが、この作品には小野寺がいる。
一緒に探索に行った仲間を宝石を独り占めするために殺し、帰国したらさらに行方不明の圭介の兄夫婦まで手に掛ける。
果てはバルゴン誘導の為の巨大ダイヤモンドを奪い取ろうとする始末。
欲の張った人間の醜さが十分に伝わる。
そして本作品ガメラの初対決の相手、バルゴン。
初顔合わせではバルゴンの能力に一方的に敗れる ガメラの図式はこの作品から始まっている。
冷凍光線と殺人虹光線は強力であるが弱点が水なのに船沈没させて泳いだりするのだから、弱点と言うほどには弱点じゃないのか?と思ったり…。
バルゴンの瞼が左右から閉まるのはちょい変わってるし、逆にガメラは尖った眼をしているので前作とは表情も違うように感じる。
回転しながら飛ぶ時もアニメーションから実物が火を吹きながら回転するものに変わってた。
色々、変えてきたガメラ、内容も大人思考で意外に面白かった。
DVDでの観賞だったが、フィルムの縦キズや画面上部にゴミが引っ掛かっていたりして見えているのは元が16ミリフィルムなんだろうか?
当時の35ミリフィルムは作ったら、即大映直営か掛けてくれる映画館に送られ、マスターフィルムもどっかに行っちゃったのだろうか…と考えたりした。
前半の展開が
ガメラ初の怪獣バトル(短め)な大映ガメラ第2弾
お、カラーになった。元祖大映ガメラの第2作目です。前作からの直接の続編です。
ガメラさん、宇宙から黒部ダムへ直行!宇宙にいたのによくわかるもんですね。あれ?でも、これダム壊す必要なくない!?何でわざわざ壊したの?そのまま国外に行っちゃうしなぁ。
バルゴンの冷凍吐息って何気にスゴいですよね。って何!あの虹光線⁉️カッコいい‼️って思ったらそれがガメラを呼び寄せる原因になった。でもガメラにも圧勝。見た目はウルトラマンに出てくる怪獣っぽくって印象薄いけど強いぞバルゴン!
小野寺悪いやっちゃなぁっと思ってたら最後はバルゴンに食べられましたね。ん?バルゴンは人食うの?あれはダイヤを狙ってて、たまたま人も混じっただけ?そもそも、バルゴンは何を食べるのでしょうか?南の島ニューギニアの出身なのに物を冷凍させる能力って、どういう必要性があってその進化は起こったのでしょう?考えれば考えるほど不思議な生物です。でも、凍るせる能力って暑い南の島なら逆に重宝されそうだけどなぁ。
ガメラとバルゴン、どちらも人類の脅威って描かれ方だったのに最後はバルゴン倒して終了って、ガメラは放って置いても良かったのでしょうか?うーん、色々と謎が残るガメラ対バルゴンでした。
昭和シリーズ屈指の見応え
サンテレビ「アフタヌーンシアター」で鑑賞。
本作の大きな特徴は、子供が一切登場しないことであろう。ガメラが子供を助けると云った描写も無い。本作のガメラは徹頭徹尾、敵の立ち位置だ。
悪役が殺人を犯したり、主人公とヒロインがいい雰囲気になったりと云うアダルトな作風に子供が退屈したため、次から子供向けに戻したそうである。
大人になってから思い返すと、ドラマも特撮も、昭和シリーズの中でいちばん見応えがあるように思う。上手くバランスが取れていて、テンポも良い。
当時の大映スター、本郷功次郎氏が出演していてドラマに締まりが感じられる(本人は当初、怪獣映画に出演するのがとても嫌だったとのこと)。
特撮では、神戸や大阪を蹂躙するバルゴンの描写が素晴らしい。昭和シリーズ後半では予算の都合で無くなってしまう都市破壊を存分に楽しめた。
なぎ倒されるポートタワーや氷漬けにされてしまう大阪城など、関西出身の私に馴染みの深い建物が被害に遭うシーンはなんだかウキウキした。
バルゴンの舌を伸ばして放つ冷凍液や虹色殺人光線など、技もユニークだ。目が大きくてかわいらしいのに凶暴な性格なのもギャップがあって良い。
昭和シリーズでいちばんと言って良いほど自衛隊が怪獣撃滅作戦を頑張っているのも特徴だ。ニューギニア先住民のカレンが齎したヒントを元に様々な作戦を展開する。ダイヤモンド作戦やバックミラー作戦など、作戦の名称がユーモラスで面白い。
ガメラが、一度は敵に敗北するもリベンジマッチで勝利する図式が本作で確立している。大阪城で氷漬けにされるも琵琶湖で再戦し、勝利をおさめるのだ。バルゴンの断末魔が印象に残る。
人の欲望の醜さが描かれ、因果応報な結末を迎える悪人に子供ながらに衝撃を受けたことを覚えている。こんな大人にはならないぞと心に決めたが、果たしてなっていないか、とても心配である。
[追記(2020/05/24)]
偶然「黒部の太陽」を観た直後に鑑賞したため、黒部ダムが破壊されるシーンに心が痛んだ。
どれだけの犠牲の果てに出来たと思っているのだと、ダムに感情移入してガメラに怒りを覚えた。
[追記(2025/11/09)]
何故、ガメラはバルゴンと戦ったのか。その理由が全く明確でないことに気づかされた。動物としての本能から来る行動だったのだろうか。
昭和シリーズのガメラは子供を助けるために敵と戦う存在と云う印象があるが、本作には子供が登場しないため、その動機も考えられない。
バルゴンと戦わないと始まらないので、ご都合主義に目を瞑らないといけないのは分かるが、なんらかの理由づけは必要ではないかなと思う。
[鑑賞記録]
2001/??/??:サンテレビ「アフタヌーンシアター」
2020/05/24:Amazon Prime Video
2025/11/09:BS12(4Kデジタル修復版)
*初投稿(2018/10/11)
*再投稿(2020/05/25)
*修正(2025/11/09)
人間のエゴが怪獣を目覚めさせる
シリーズ2作目。1966年の作品。本作からカラーに。
2作目から“大怪獣決闘”モノで、舞台は大阪…あちらとの酷似はこの際いいとして、
話は前作の後日談。
半年前、日本に上陸し暴れ回り、“Zプラン”によって宇宙へ追放されたガメラ。
が! ガメラを封じ込めたロケットが驚異的な確率で隕石に衝突し、自由になったガメラは地球に舞い戻る。
そして何故か小さな島国・日本の黒部ダムを襲ってエネルギーを蓄え、再び何処へ飛び去った…。
序盤はツッコミ所多々だが、人間ドラマはシリアスな雰囲気になる。
自らの飛行機会社設立を夢見るパイロットの圭介は、今の会社を辞め、兄の計画に参加する。
戦時中、パプアニューギニアのジャングル奥地の洞窟で見付けたオパールを隠したという兄。戦争で足を負傷した兄に代わり、圭介と他2名で手に入れに行く。
現地に着くと日本語が話せる村の女・カレンに止められるが、制止を強引に振り切り、ジャングル奥地の洞窟を目指す。
遂に辿り着き、オパールを発見。喜びに沸くが、一人が毒サソリに刺されて死亡。それがきっかけでもう一人が裏切り、洞窟を爆破してオパールを持って逃げてしまう。
圭介はカレンに助けられ、「恐ろしい事が起こる」と怖れるカレンと共に日本へ。
実はオパールは…。
裏切り者が乗った船の中でオパールが赤外線に偶然当てられ、変化。
そしてその中から誕生する。
パプアニューギニアの魔境、“虹の谷”の伝説の怪獣、バルゴン!
オパールだと思っていたそれは、バルゴンの卵だったのだ。
急速に巨大化し、大阪で暴れ回る…。
バルゴン登場までの人間ドラマが前作から売って変わってアダルトな作風。
宝石に目が眩んだ欲深い裏切り者。
洞窟で仲間の一人の足に忍び込んだサソリを黙認。
日本に戻りうっかり洞窟で起きた事を口を滑らし、圭介の兄に問い詰められた挙げ句、殺める。
圭介と因縁の再会。取っ組み合い。
怪我した圭介の傷に口を当てるカレン。これ、本当に昭和ガメラだよね!?
終盤、対バルゴンのある作戦の最中、再び裏切り者が乱入。
欲と醜態の末路は…。
昭和ガメラでは唯一、子供が出て来ない。
その為公開時、観に来た子供は退屈し、怪獣が出てくるまで劇場を走り回ってたという逸話があるが、個人的には昭和ガメラで人間ドラマ部分は一番面白い。
言ってしまえば本作、“虹の大怪獣バルゴン”だけでも成り立つ話である。
長く伸びた舌の先から出す冷凍ガス、背中のヒレから出す虹の光線…バルゴンの猛威は圧倒的。
人類は“ダイヤモンド作戦”“人工雨作戦”“バックミラー作戦”で挑む。
前作以上に人類と怪獣の闘いが描かれていた気がした。
後一歩で倒す事が出来ない。
そこへ現れたのが、ガメラ。
寒さに弱いガメラはバルゴンの冷凍攻撃で一度は敗れるも、復活し再戦。
昭和ガメラの鉄板となるこの図式も本作から。
本作のガメラの立ち位置はまだ人間の脅威寄り。
しかし、更なる脅威が現れると、闘ってくれる…ゴジラでもお馴染みの怪獣映画の定番。
前作が大ヒットした事により、予算がアップ。それは特撮面で充分窺い知れる。
序盤の黒部ダムセット、メインの大阪セット、クライマックスの琵琶湖セット…大規模なセット。
一瞬にして凍る冷凍ガス攻撃、カラーを意識した虹の光線の特撮の見せ方もアイデア駆使している。
また、ガメラとバルゴンの闘いは基本四足で。これはゴジラ映画では無かった。
本作のみ特技監督を務めた湯浅憲明監督のこだわりで、動物らしさが出ている。
ワニとオオトカゲを合わせたというバルゴンの造形もまさにそう。
人間ドラマも特撮も昭和シリーズ随一。
人間のエゴが怪獣を目覚めさせる…という怪獣映画の真のテーマもしっかりと。
やはり、昭和ガメラでは一番!
本作は公開時、『大魔神』と同時上映だったとか。
何と贅沢な!
怪獣映画の水準が今後低下していくことを予感させる
ガメラ第2作
1966年4月公開
東宝特撮の独壇場であった怪獣映画がに遂に他社が挑戦を初めました
それが1965年11月のガメラ第1作大怪獣ガメラです
思いのほかの大ヒットでした
本作は、それをうけ早くも前作の5ヵ月後に公開された続編です
予算も大幅に増えてカラー作品です
冒頭は前作の粗筋紹介ですが、前作が白黒作品だったので回想シーンとして収まりが良いです
そしてカラーで本編の開始ですが、オレンジ色の火の海を背景に、青白い超高温のロケット噴射を行い回転飛行を始めるガメラが美しく、ガメラとはこうだったのか!という感激を上手く色彩の鮮やかさで表現しています
南海の島から怪獣を呼び寄せてしまうモチーフはモスラを思わせます
オープンセットの強い陽光の下での原住民のダンスシーンはスタジオセットでの撮影のモスラに勝る臨場感があります
ジャングルシーンもマタンゴより雰囲気が出ています
ドラマパートも本郷功次郎や江波杏子を始め脇役までなかなか頑張って良い演技を見せてくれます
特に本郷功次郎は嫌な仕事だと逃げ回っていた筈なのに、素晴らしい印象を残します
現に彼は本作以降ブレイクしてテレビドラマなどで売れっ子俳優になりました
江波杏子もクールビューティーぶりは素晴らしく、東宝の美女達に全く負けていません
脇役では藤岡琢也がさすがの名演技です
彼も本作以降売れっ子俳優になります
しかし前作での良い点であった子供の目線が全く忘れさられているのは残念なポイントです
とはいえ、脚本は前作につづき面白く、良い出来で最後まで興味を失いません
さて肝心の特撮シーンですが、序盤の黒四ダム破壊シーンはなかなかの迫力ですが、大阪城は冷凍にしてくれますが破壊してくれずフラストレーションがあります
神戸港のメリケン埠頭とポートタワーのシーンは良い出来映えで、ミニチュアセットも頑張っています
しかし、大阪市内のミニチュアセットはもうひとつ嘘臭い出来映えで破壊シーンも少なくつまらないです
大阪の皆の知る実在の場所を再現して破壊して見せようという意欲はまるで感じられません
琵琶湖大橋も破壊シーンはあってもそうハイライトが当たっていません
バルゴンの着ぐるみは頭部から上半身は良いのですが、後ろ足は完全に人間が四つん這いである事を隠してもいません
怪獣同士の闘争は流血シーンがあり、東宝特撮との違いを打ち出した演出をしています
特撮シーンの技術としては、東宝特撮の劣化コピーの印象ですが、普通の一般客なら十分な出来映えです
ただし怪獣映画の水準は、今後どんどん低下していくことを予感させるものです
このままでは厳しい
特に対戦相手の怪獣にもう一工夫がないと駄目だという反省が大映にも生まれたと思います
それは次回作、大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオスに結実します
しかしそれを待つことなく、実は本作の併映作品に日本の特撮映画の金字塔がもうすでに撮られていたのです
それは名作大魔神です
全26件中、1~20件目を表示