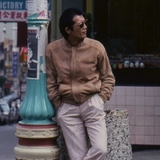フルメタル・ジャケットのレビュー・感想・評価
全101件中、1~20件目を表示
キューブリック作品の「戦争と狂気」の集大成。
◯作品全体
キューブリック監督の長編作品は全部で13作品あるが、そのうち3作が戦争映画だ。初長編作品である『恐怖と欲望』、キューブリックの名を映画界に売り込んだ『突撃』、そしてビッグネームとなった後に作られた『フルメタル・ジャケット』。同じキューブリック作品だが、キューブリックのキャリア、映像演出、作品構成…様々な要素はまったく異なる3作だ。
しかし、一貫して描かれているものもある。それが「狂気」だ。これは「キューブリックの戦争映画」という枠組みにとらわれずキューブリックの根幹にある題材だが、戦争という「狂気」にまみれた舞台で描くとき、キューブリックの「狂気」を描く視点は更に多彩になると感じた。
キューブリックの戦争映画において、『恐怖と欲望』では新米兵士の精神崩壊を描くことで戦場での緊張感や非日常の過酷さを表現した。『突撃』では死へ追いやる命令や、処刑へ追いやる側・処刑される側を作る戦争の仕組みがクローズアップされる。いずれも戦争は既に始まっていて、その中で「狂気」が顕在化する部分を抽出している。
同じ監督が手掛けた戦争映画だが、語られる「狂気」が全く異なるところに、多彩、という言葉が浮かぶ。
『フルメタル・ジャケット』は前2作品とさらに大きく異なり、戦争が始まる前の「狂気」を語っている。普通の若者が各々のヘアスタイルをバリカンで刈り上げ、「狂気」といえるハートマン軍曹のシゴきがあり、「Born to Kill」のヘルメットをかぶる。過酷で、少しユーモラスな訓練シーンはとてもキャッチ―だが、普通の若者が兵士となるまでの過程は冷静に見ると「狂気」でしかない。落ちこぼれのレナードが精神に異常をきたし自殺するが、そのまま生き残って戦場で狂うか、今この場で狂うかの違いだけであることを知らしめるかのような場面だった。行き着く先は同じ「狂気」という結末。それを強烈に印象付ける前半部分だった。
『ロリータ』や『時計仕掛けのオレンジ』も本作の前半部分同様、エスカレートする狂気が描かれていたが、戦争を舞台にした本作では、また一味違ったエスカレートを見せる。そこにもまた、キューブリックの「狂気」の多彩さが垣間見えた。
後半のベトナムを舞台にした実際の戦場では、狂った倫理観を様々な登場人物を通して描く。緊張感あるシーンが続くが、兵士のアドレナリンを表現するかのような挿入歌の入れ方や登場人物の個性の付け方がユーモラスを感じさせる。登場人物たちの見ている世界が「狂ったもの」だと映させない演出のようにも感じて、ユーモアの裏にある暗さの映し方が巧い。
ラストのミッキーマウスマーチはその集大成だった。兵士のシルエットとアップテンポなミッキーマウスマーチ。普通の若者であったはずの彼らと、狂ってしまった彼らをこのワンカットで描いてしまうところに、キューブリックの凄みがあると感じた。
〇カメラワークとか
・一点透視、シンメトリーチックの画面の無機質さとハートマン軍曹の熱量のコントラストがすごかった。今までのキューブリック作品にもない演出だったような。
・前作『シャイニング』では多用していた「キューブリックステア」は本作では控えめ。レナードが狂ってからの視線くらい。
・戦闘シーンの見やすさはカメラワークの巧さがあるからだろうな。一方でスナイパーに撃たれるシーンはイマジナリーラインをめちゃくちゃにしていて、混乱っぷりが伝わるカメラワークだった。
〇その他
・「ステア」を語るシーンがあった。ジョーカーが報道部にいる時の先輩兵士が、戦場を経験している目を語る。
「1000ミリ望遠の目つきさ 長くクソ地獄にハマったときの マジに あの世まで見通す目さ」
戦争での心理的障害の一つとして「1000ヤードの凝視」があるけれど、「キューブリックステア」の意図にも近い気がした。
・カウボーイが撃たれて死ぬまでの演技が素晴らしかった。目に力が入り続けていて、いつ死んだかがわかりづらい。傷口を見せず、露骨に「死んだ」っていう演技もせずに、動かなくなったことで死がわかる。カウボーイの状態の不確かさが画面に緊張感を作ってた。
ケチなんて付けたくないんだけど…
スタンリー・キューブリック監督が若い海兵隊員の視点を通してベトナム戦争を描いた異色作。
公開当時、衝撃的な内容のため(と言うべきか、にも関わらずと言うべきか)、さまざまなパロディや派生作品をも生んだ本作。
「惜しい」とか「残念」などとケチを付けるレベルではなく、よく出来たいい映画なんだが比較したくなる対象が多いことが難点。
ひとつはベトナム戦争を描いた映画としての対象。
戦争の狂気を圧倒的映像で視覚化した『地獄の黙示録』(1979)に勝ることは鬼才キューブリックでもやはり至難。
わずか1ヶ月半ほどでロンドンに再現したベトナム市街戦のセットも素晴らしいが、ロケを敢行した同作の迫力には及ばない。
戦死したカウボーイに代わって主導権を握ったアニマルマザーが狙撃兵の少女の処刑をジョーカーに押し付ける場面も、ウィラード太尉が罪のない重傷の少女を躊躇なく射ち殺すシーンと比べたくなる。
もうひとつはキューブリック監督自身の他作品との比較。
『2001年宇宙の旅』(1968)や『シャイニング』(1980)で描かれた、あまりにも現実とかけ離れた世界観と較べると、戦争ですら普通の光景に見えてしまうのは自分だけ?
『時計仕掛けのオレンジ』(1971)や『シャイニング』で描かれた残酷でありながら芸術的ともいえる暴力描写を、本作の戦争の狂気は果たして超えられただろうか。
本作の上映時間は2時間弱と、キューブリック作品にしては短めの印象。本来は三部構成の原作のうち二部までしか映画化していないらしい。
なぜ第三部を割愛したか知りたい気もするが、どうせなら第一部の訓練キャンプの場面に特化して、閉ざされた空間内での狂気や混乱にもっとスポットを当ててもよかったのではとも思う。
鬼教官ハートマン軍曹は新兵を口汚く罵り、本人だけでなく家族や故郷すら貶め人間性を奪おうとする。
戦争とは、人間性を喪失しない限り出来ない「作業」なのだと再確認させられる作品。
戦火の薄闇のなか、次の標的(ベトナム人)を屠るために「夢の国」のテーマソングである『ミッキーマウス』を歌いながら行進するラストシーンもまた、寓意的で黙示録的。
NHK-BSにて初視聴。
決して人ごとではない
フルメタル ジャケット
恐怖と狂気
ベトナム戦争映画というより米軍映画
『プラトーン』で始まった米国の第2次ベトナム戦争映画ブームの中で作られた映画の1本……なのだが、前半は米軍内部での鬼軍曹の過酷な訓練シーンが延々続く。それはそれで興味深いし映画としては面白いんだが、こっちはベトナム戦争の映画を観ようとして観たのでちょっと肩透かしだった。
後半でようやくベトナム戦争となるんだが、ベトナム戦争を描いた米国映画では珍しく都市戦闘が描かれている。ベトナム戦争映画で初めてジャングル以外での戦闘が描かれた!と喧伝する媒体もあったが、個人的には「それがどうした」と思ってしまった記憶。出てくるベトナム人もスナイパーの少女兵1人だけで、ベトナム戦争映画としては今ひとつピンと来なかった。
ちなみに前半の訓練シーンで、ゲーム『ファミコンウォーズ』のCMの元ネタはこれだったんだ!と知ったな。そっちのCMのほうを先に見てたんで(笑)。
鉛のような映画
わたくし、この映画は全くの初見でオリーバー・ストーン監督「プラトーン」は公開当時観に行ったのに
「フルメタル・ジャケット」は行かずじまいで、
それから30年以上経ってようやく劇場で観る事ができました。その間、TVやソフト(VHS、LD、DVD)、
配信などで観る事はありませんでした。
スタンリー・キューブリック御大の作品は、
できるだけ劇場で観たいという思いがつのり、
観るまで、えらい時間かかったなぁという感じです。「2001年宇宙の旅」や「時計じかけのオレンジ」は劇場では、"あぁ、またか“というぐらい繰り返し上映されるのに「フルメタ」に関しては、あまり上映される機会がないように思われます。
この作品で象徴されるのは鬼教官によるシゴキ・・・
下半身ネタを連呼しながら行進する海兵隊新兵。
公開当時ゲームソフトのCMでパロディにされてたのを思い出します。
CNNは、この映画を酷評しておりました。
「キューブリックが戦争映画に他の監督と同じように
ロック音楽を使用して凡庸な作品になりさがってますね」
まぁCNNは保守ですから体制批判が根底にある映画は嫌いなんでしょうね。
前半は丹念にストーリーが進み物語に見入っていました。途中キューブリック作品である事さえ忘れてしまいました。
皆の鬱憤がデブでノロマなパイルに向かうシーンは痛々しいなぁ。メル・ギブソン監督「ハクソーリッジ」にも似たようなシーンがあったなぁ。
中盤、えっこうなっちゃうの⁉️
ヒッチコック「サイコ」のような展開に面食い、この後どうなっちゃうのよ❗️
そして後半は激戦地のベトナムが・・・なぜかポン引きの場面から始まる下世話な会話。
実は私このシーン(2回目のサングラス娼婦のやりとり)だけTVで見ており、あれっ違う映画かな?それがフルメタの一場面とは信じられずスチール写真でお見かけする鬼教官のシゴキやトイレで微笑む(?)パイル、負傷兵を抱き抱える兵士達🪖、機関銃を構える少女兵と何か一致しないんですね。
コッポラ監督「地獄の黙示録 特別完全版」での兵士とプレイメイトのやりとりのような美しいシーンでも無いし(ファイナルカットでは結局カットされました)ポン引きシーンは2回も挿入され、それが後半に絡んでくる事もなく何か意味が隠されてそうです。
最後のジョーカーのアップシーンがキューブリックらしい画になっており窓に反射する光が美しいんですが最も悲しいシーンでした。彼の葛藤と銃声が、こだまする何とも言い表わせない無念の気持ちが込み上げました。
兵士たちのミッキーマウスの唄で終わりローリング・ストーンズ「黒く塗れ」でエンドロールを迎えます。今までこの曲(ストーンズ)聴く機会がなかったのですがマジいい曲です。
見終わった後、ズシーンと鉛のようなものが心に残りました。長年キューブリックと組んでおられた撮影監督ジョン・オルコットが亡くなられたため、この作品に携わることができませんでしたが、この作品の撮影監督ダグラス・ミルサムもいい仕事をされております。キューブリック作品の中でも「フルメタ」は比較的、分かりやすい作品です。映像作家というより人間として何かを訴えかけられてる作品でした。
たった一人で戦っていたベトナム女性狙撃兵に想いを寄せ…
言わずと知れた、「2001年宇宙の旅」の
スタンリー・キューブリック監督作品だが、
前半と後半がガラリと切り替わる二部編構造
であるのは、同じベトナム戦争を背景とした
「ディア・ハンター」と似ている。
正直なところ、再鑑賞するまでは、
その両作品ともに特徴的な
前半と後半の落差について、
「ディア…」が“日常生活と戦場”
という異質な環境であることに対して、
この作品では“新兵訓練所と戦場”
という言わば同質の環境。
従って、そのインパクトの強さでは、
平和な日常生活から
いきなり戦場に叩き込まれる「ディア…」
の方が優れていると思っていた。
勿論、今回の鑑賞で
その前後編の落差の点での印象に
違いが出た訳ではないが、
この作品が、その「ディア・ハンター」や
「地獄の黙示録」及び「プラトーン」
と並ぶベトナム戦争を描いた超傑作映画
であると再認識する今回の鑑賞となった。
前半の訓練のシーンでの
教官から発せられる言葉と肉体的暴力は、
エンターテイメント作品であることもあって
ディフォルメ感満載で過激だが、
作品全体では、
新兵の前半のこの訓練施設での描写に加え、
計算尽くされたような
リアリティ溢れる戦場の映像と共に、
徐々に戦闘兵器化していく人間の変貌描写を
見事な演出の中に感じ取ることが出来た。
ところで、再鑑賞する私は、
小隊を狙撃するのは、
たった一人の女性兵士であることを
知っている。
主人公らの小隊のメンバー以上に、
彼女がどんな孤独と恐怖の中で戦っていた
のかに想いを寄せる時、
改めて戦争の悲惨さに胸の苦しみを覚えた。
ランボーとの比較
ベトナム戦争のあと10数年後に製作された作品
巨匠であり奇才であるキューブリックの晩年作品として心して鑑賞しました
最初に感じたことは、時期的な事情もあって撮影セットが豪華!とにかく金が掛かってる、その割にストーリーがチープ。
当時のピッピーファッキン文化を過剰なまでに出して表現してたが、後味に残るのは軽い気持ちで行って命を落としたり、トラウマを抱えて帰国する末路が待っているのを案じていない。
このあたりの詰めの甘さはキューブリックらしくない作品でした。戦後5年程度で描いたランボー1のような、ベトナム戦争の無情さをもっと表現できたと思う。
とはいえベトナム戦争を描いた作品としてはプラトーンに並ぶ金字塔だけに、批評するのはこの辺りにしておきます。
これが戦争の真実なんだろうな
長々と続くいじめ、シゴキの兵隊訓練
精神に異常をきたす訓練生が出ることも当たり前
敵を何人殺したか、
女こども、老人まで射殺したことを自慢する兵士
戦場の異常な環境も、人はあっさり慣れていく
ミッキーのマーチを
兵士たちが歌いながら進んでいくラストシーン、
戦場にいなければみんな普通の若者なのだと思い起こさせる
戦争は本当にやめてほしい
人間が狂う
戦争という現実(リアル)の中で、死に向き合う時・・・
戦争映画ってのは、どうも好きになれないんだけど、何故か何度も魅入ってしまう一本です。
難解な作品が多い事で名高いスタンリー・キューブリック監督ですが、この作品は単純で分かりやすい。ただひたすら戦争の悲惨さを見せ付けているんじゃないだろうか。
前半は海兵隊の訓練の様子。
長髪をバッサリと坊主頭にするシーンから、いきなり始まり、パワハラ極まりない教官の叱咤が延々と続く。こんな時代だったんだよね、全てがまかりとおる。(今もこうなのかは解らないけど)
鬱積された不満はストレスとして、弱者へのイジメに繋がっていく。全てを背負わなければならなくなった者は、精神的に追い詰められ、自ら死を選択した。
そして、訓練を終えた兵士達は戦場(ベトナム)へ向かう。
見るからに凄まじい戦場がそこにあった。
【ネタバレ】
後半は、ただひたすら戦場の兵士たちを映し出す。目の前で当然のように繰り広げられる命のやりとり。今まで普通に会話していた仲間の、突然の最期。歩き進む先で、突然突き付けられる銃弾。
どちらが正義でどちらが悪なのかなんて、全く触れない。ありのままの争いが目前で繰り広げられていく。
ラスト、正体不明の狙撃者に突如襲われ、仲間が命を奪われる。
リベンジに奮いたった兵士達の目前に現れた狙撃者は、一人の若い女性だった。銃弾を浴び瀕死状態となった彼女は、自らを撃ってくれと訴える。
敵も味方も関係なく、目の前で繰り返される人間の死。
進軍する兵士達が口ずさむミッキーマウス・マーチ。荒れ果てた戦場に夢の国の、希望に満ちた歌が虚しく響く。
一本の映画としてではあるが、ベトナム戦争に触れた気になる感覚だった。
どうしようもなく、呆気なく、失われていく命。そして、奪っているであろう命。
人の一生を奪う行為が正当化される戦争という事象に、全く関わることのなかった自分の人生。ただ、それだけでも幸せだったのかもしれない。
アメリカの男性が「一人前」として生きることがいかにきびしくてさびしいことなのか
この映画はベトナム戦争時代にアメリカ海兵隊に志願した若者たちの群像劇です。
冒頭、次々に頭を丸刈りにされていく若者たち。彼らの背景、志願動機、人物像は描かれません。彼らはこれから8週間にわたり、海兵隊新兵訓練キャンプで地獄の訓練に耐えることになります。
訓練の目的は普通の若者を冷徹かつ正確無比な殺戮マシーンに変えること。そのためには参加者の人間性や個性や思想が徹底して否定されます。上官には絶対服従。訓練兵は名前も剥奪され、「ウジ虫」または「侮蔑的なあだ名」で呼ばれます。一切の反論や口答えは認められていません。彼らはライフルへの愛、国と海兵隊への忠誠心を叩き込まれていきます。
鬼教官ハートマン軍曹を演じたR・リー・アーメイは本職の俳優ではなく、本物の海兵隊の訓練教官経験者で、演技指導に来てもらったところあまりの迫力にキャスティング変更し採用されたとのこと。彼の罵詈雑言はもう「話芸」です。彼の下品で侮辱的な言葉は嫌味を通り越してユーモアにまで昇華されています。本作の真の主役はアーメイさんだと思います。
訓練兵達の中に二人の異物がいます。一人はパイル(ヴィンセント・ドノフリオ)、もう一人はジョーカー(マシュー・モディーン)。
パイルはデブで、運動能力が低く、不器用で、集団の足を引っ張る存在です。ジョーカーは「聖母を敬え!」と迫るハートマン軍曹に「自分は神を信じません!」と言い張り、その根性で班長&パイルの指導役に指名されます。
パイルはジョーカーの助けで少しずつ成長を見せますが、トランクに隠していたドーナツが軍曹にみつかり、以後パイルのヘマの罰は本人ではなく、他の隊員全員に与えられることに。そのストレスが頂点に達し、パイルは他のメンバー全員から暴行を受けます。この事件を契機にパイルの顔からは笑顔が消え、目には殺気が宿ります。
何一ついいところのなかったパイルは射撃の腕を見出され、軍曹からお褒めの言葉をかけられるように。そんなパイルはブツブツと独り言を喋りながら自分のライフルをまるで恋人のように撫で回します。
8週間の訓練を終えた修了式。やっと彼らは一人の人間、しかも一人前の海兵隊員として扱われるようになります。特にパイルは軍曹からまたもお褒めの言葉を頂戴します。そして彼らは家族よりも濃厚な仲間として海兵隊に迎え入れられます。この関係性は死んでも消えることはなく永遠だと強調されます。
いろんな大切なものを捨てて彼らが得たもの、それは「一人前の海兵隊員としての誇り」です。アメリカの若い男性は、こんな過酷な通過儀礼を、軍隊は言うに及ばずアメリカ社会のいたるところで経験するのでしょう。ヤワな自分を捨ててタフな一人前の男になること。それができないとオカマ扱いか子ども扱い。個性や人間性は二の次三の次。アメリカの病根とも言えるこの構造とマッチョ信仰をわかりやすく批判的に描いた本作は、そのおかげで普遍性を獲得しました。
成長の度合いが最も著しく一人前の殺戮マシーンになったパイルは、自分を一人前にしてくれた恩人である軍曹を射殺して自殺します。結局彼は仲間たちと和解することはありませんでした。
ハートマン軍曹役のR・リー・アーメイとパイル役のヴィンセント・ドノフリオの二人が退場した本作の後半部分、映画の緊張感は一気に緩んでしまいます。それほど本作に命を吹き込んだ二人の大熱演は観る者に忘れられない印象を残します。
もう一人の異物であったジョーカーは、高校時代の新聞部での経験を買われ、軍の情報誌の報道員としてベトナムへ送られます。ここから本作の舞台は訓練キャンプを離れベトナムへ移ることになります。
ジョーカーはヘルメットに"Born to kill"、胸にはピースマークのバッジを付けるという2面性を持った男であり、シニカルな批評精神を持った男です。報道員である彼の目を通して傍観者的立場で残酷な戦場の有り様が描かれていきますが、とてもこの後半部分がベトナム戦争の実相を十分に捉えられたとは思えません。
上司に反抗的なジョーカーは前線の取材に送られます。そこで親友"cow boy"の戦死を目の当たりにして、やっと戦争の厳しさを体感したようです。親友の敵を取るために残った兵士たちとともに狙撃兵のいる廃墟へ突入します。
狙撃犯(軍服を着た兵士ではない)は若いベトナム人女性であり、彼女はすでに瀕死の重傷を負って倒れています。彼女は何度も「Shoot me!」と口にし、止めを刺すよう頼みます。ジョーカーは悩みに悩んだ挙げ句、周囲に促され、しぶしぶ彼女に向けて拳銃を発射します。彼の初めての殺人シーンであり、彼にとって最大の葛藤シーンでしたが、実践経験のない彼のナイーブさが強調されたシーンでもありました。古参兵にとってはおそらくありふれた場面でしょう。ジョーカーは、格好は一人前でも軍人としてはまだまだ未熟のようです。
本作の中で鬼軍曹が後にテロリストとなった二人の元海兵隊員の話をします。軍曹は彼らのことを優秀な海兵隊員として称揚しますが、実像は自分を除け者にした社会に復讐を図ったテロリストです。この映画はアメリカの男性が「一人前」として生きることがいかにきびしくてさびしいことなのか、教えてくれます。彼らはもしかしたら死んで始めて「一人前」なのかも知れません。
追記
「アメリカの過酷な通過儀礼」
どんな文化にも青年が一人前の男になるためには乗り越えるべき「通過儀礼」があると言われますが、本作で描かれるアメリカの通過儀礼は過酷です。頭を丸め、8週間キャンプに閉じ込められ、「ウジ虫」または「侮蔑的なあだ名」で呼ばれ、一切の口答えは許されず、暴力体罰当たり前。この訓練を通して普通の若者たちはナイーブさを捨て、ライフルと祖国への愛と海兵隊への忠誠心を身に着け、冷徹な殺戮マシーンへと成長していきます。この通過儀礼を終えて初めて彼らは名前で呼ばれ、一人前の男として扱われ、家族よりも濃い「永遠の仲間」を手に入れます。
日本ではとっくにそんな通過儀礼はなくなりました。今そんなことをすればすぐにパワハラ・セクハラで訴えられます。もはや過去の遺物です。ではわれわれは幸せになったのか。悲惨な目に合わなくて済むかわりに、一生を幼稚なままで信頼できる仲間も持たずに過ごすのが今の私達なのかも知れません。
本作は集団の中の異物である二人の若者にフォーカスします。一人は通過儀礼そのものを通過できません。彼に逃げ道はありません。もう一人は要領よく通過儀礼をくぐり抜けたものの、現実社会である戦場に出て葛藤を経験します。ナイーブで個性的だった青年たちはいつしか「部品」や「消耗品」となり摩滅しながら生きていくしかない、そんな厳しいアメリカの現実が描かれています。そして悲しいのは、この通過儀礼が人間的な成熟とは全く関係がないという点でした。
わたしは・・・こうして生きている
サウスカロライナ州の海兵隊新兵訓練基地。
「 貴様らは人間では無い 」、パワハラ・モラハラ・セクハラ言葉を吐き続ける鬼軍曹ハートマンのもと、苛酷な訓練を重ねる志願兵の青年達。
米軍機関誌「 スターズ & ストライプス 」の報道員としてダナン海兵隊基地に配属された通称ジョーカー( マシュー・モデイン )は、前線での取材を命じられ、小隊と同行することに。あちこちで炎が上がる廃墟の中を進む兵士達。目の前に居た仲間が次の瞬間銃弾に倒れる。
リアルな映像に息を潜め画面を見つめていた。
仲間を見殺しにするのか、自身はどう行動するのか、目の前に現れた人間を撃ち殺す事が出来るのか。戦場に赴いた者にしか分かり得ない苦悩が其処にあった。
NHK-BSを録画にて鑑賞 (字幕)
何度見ても発見がありますね
初公開時に鑑賞、DVD、BD、4KUHDとソフトが出る度に買ってる気がしますが
ムービープラスでの副音声解説と同時期にNHKで!の放送があったので立て続けに視聴して改めて戦争映画の傑作だと思いました。
キューブリックが極端な飛行機嫌いと自宅から通える距離で撮影したいと言う条件の為原作第3部のジャングルでの戦闘は全てカット
結果同時期のベトナム戦争映画とは違う戦場シーンは全てロンドンロケの市街戦が中心の映画になったそうです、本編中にスモークがやたら焚かれて居るのも遠景にロンドンの市街地が映るのを隠す為だったとか
びっくりなのは撮影の順番はベトナムの戦場シーンを撮り終えてから訓練所のシーンを撮ったんだそうです
それで軍事アドバイザーのリー・アーメイが作品の製作途中でハートマン軍曹役に抜擢された経緯がしっくりと来ました
俳優さんたちはカットの繋がりがおかしくならない様に毎日頭を剃り、撮影が終わり髪を伸ばし始めた時期に呼ばれて最後に撮ったカットはOPの散髪シーン…
コレで撮了だったそうで、髪を刈って解散だったと言う俳優さんたちがちょっと可哀想と思いました
訓練終わりだけは違っていた
世界の名画…なの?
東京にある名画座にて、この映画を観て「世界の名画」と評される理由が
分からず、この一件を自分の中で「フルメタルジャケット事件」として、
世界で評価されている映画が、よく理解できない状況に陥る…
これはネタバレしなきゃ評価できない作品で、ラストまで書く。
ベトナム戦争に出る若者達を前半の部分で、鬼軍曹がシゴく場面が
描かれるが、そこで一番の出来損ないデブが、結局自決する事に
なるのだが、その話は後半では無かったことになる。
ベトナムの敵、スナイパーの正体が子供だったとの事が、世界では
高く評価されている様だが、日本で戦争を扱ったアニメでは、とっくの昔に
子供が銃で人を殺すなんて表現は多くあるわけで、この作品の公開当時
1988年に観ても、衝撃は受けない。
ラストは、米兵達が世界で一番知られている名曲「ミッキーマウス」の
歌を唄いながら戦場を歩いていくわけだが、本当の歴史を知らない人が
見たら、アメリカはベトナム戦争で勝ったと誤解されかねない描写だ…
はっきり言って、この作品のオマージュである「フルメタルパニック」の
アニメ、1話から7話を見る… もしくはネットフリックスで配信中の
3DCG作品の「機動戦士ガンダム・復讐のレクイエム」の方がマシだ…
炎のミッキーマウス・マーチ
初っ端から創作でも聞いたことないレベルの口汚い罵倒の連続に笑ってしまう
なのに誰も笑わないからか訓練の厳しさがリアルに伝わってくる
だから笑ってしまうけど真剣に見入ってしまう
主人公のジョン・レノン似のジョーカーに裏切られた微笑みデブがタイトル回収するシーンから暗転して、第二部に移る
しかしあの大事件がなかったかのように、同期は仲良しのままで過去を振り返るシーンは最後まで挟まれない
一部に戻ると、主人公はデブを最後にしこたま殴ってたのにその後耳を塞いでいた
サイコパスと言ってしまえば簡単だが、キューブリック監督は終始つかみにくい主人公のキャラクターで戦争の狂気を表現しているんだろう。
また凄惨なベトナム戦争で死体がゴロゴロってより、兵士たちの幼稚さを多く映し出していた。
この映画はヒロイズムなどではなく実際の戦争の一面、狂気と幼稚さにフォーカスすることで、戦争の下らなさを描いた作品なんだと思う。
また名言、見どころも多い。
最後のミッキーマウス・マーチを歌いながら行進するシーンは、正にこの作品のテーマを象徴している。
難しい映画
全101件中、1~20件目を表示