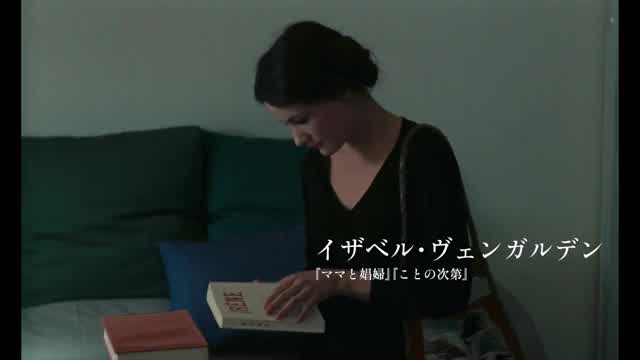白夜(1971)のレビュー・感想・評価
全4件を表示
幻燈のような恋の妄想
「白夜」という神秘的なタイトル、原作のドストエフスキーという名前に惹かれたが、原題は「夢想者の四夜」なのだそう。
街で出会う女性と自分が恋をする妄想に取りつかれ、昼も夜もないといったところだろうか。寒い地域の話ではなく、恋の予感が騒ぎ出す初夏を思わせる映画だった。
主人公のジャックは都会の川で身を投げようとしている若い女性のマルトを救い、身の上話を聞く。1年前に留学先に旅立った恋人を待っているのだという。
恋人は、マルトは隣の部屋に間借りしていていた下宿人。同じ家に住んでいる間は彼を拒否していたのに、留学することがわかると運命を共にすることを願う。壁一枚をはさんで、顔も見ようとしなかった彼の存在が徐々に浸透してくるような関係が面白い。
ジャックにしてみれば、すでに恋人がいる女性が自分に振り向いてくれるという妄想が一番の好物なのだろう。テープレコーダーに自分の妄想を吹き込んでは巻き戻してリピートしていたのだが、やがて「マルト」という一言を繰り返すようになる。
そんなマルトに寄り添ううち、ジャックにもチャンスが訪れたように見える。ジャックは途中で「君は彼のことを好きなままでいいのに、その気持ちを隠そうとするから失望した」みたいな複雑な話をするのだが、要は恋の駆け引きをしてみたいということなのかな。
最後はマルトの恋人が現れ、マルトはあっという間に彼と立ち去ってジャックの恋は終了。
人間、他人のものが欲しくなるという心理が描かれている気もするけれど、たぶんリアリティよりも画面の綺麗さのための映画だろう。パリの街も女性も、妄想の中だから美しい。
タイトルなし(ネタバレ)
鑑賞するのはのは今回が2度目。
初鑑賞は、日本初公開の翌年1979年、ルイ・マル『鬼火』と2本立て、大阪の大毎地下劇場だった。
パリはセーヌ河に架るポン・ヌフ橋界隈での初秋の四夜の物語。
第1夜。
画家志望の青年ジャック(ギョーム・デ・フォレ)は、身投げしようとしている少女マルト(イザベル・ヴェンガルテン)を救う。
翌日、同じ時間に同じ場所で会う約束をする。
第2夜。
身の上を語り合い、マルトには恋する相手がいたが、彼は米国へ留学した。
1年後にここで会おうと約束したが彼は現れない。
マルトは彼が帰ってきているのは知っている。
待って3日。
彼が帰ってきたら必ず立ち寄る親友のところへ、この手紙を届けてほしい・・・という。
第3夜。
手紙を届けたことをマルトに告げるジャック。
マルトはジャックに「あなたを愛している。彼があなたみたいに優しかったなら」といい、ふたりは青年の存在を不安にしながらも恋人同士のように時を過ごす。
第4夜。
前夜のように恋人同士な雰囲気のふたり。
ジャックもマルトに愛を告白し、美しい月を見上げたとき、件の青年が大通りの中を通り過ぎる。
見つけたマルトは青年のもとに駆け寄ってゆく。
という物語。
わかりやすい話なのに、ブレッソンは手強い。
人物にフォーカスせず、どことなくフェティシズム感が漂う被写体の切り取り方で、物語に入るにはもどかしい。
しかしながら、映像そのものは翳の濃い魅力的なもの、随所に織り込まれる流しの音楽も雰囲気はよい(ただ少し過剰な気はする)。
十代の頃に観た自身の感想が「どこがどうというより、全体の雰囲気がいい」としか評していないのもよくわかる。
物語に入り込めない(入り込ませないようにしている)のは、被写体の切り取り方だけでなく、ジャックとマルトの人物造形によるかもしれない。
最終的に残酷さを示すマルトはどちらかと言えばわかりやすいが、ジャックの方はややつかみづらい。
原題の「夢見る男の四つの夜」の「夢見る」青年なのだが、巻頭の道で見初めた女性の跡を執拗についていくシーンなどは、いま見るとストーカーにしかみえないし、画家志望にもかかわらず(スケッチではなく)テープレコーダーで自身の思いを録音して何度も何度も聴いたり、ちょっと偏執っぽい。
にもかかわらず、彼が描く絵はポップな感じ・・・
ややイケてないとはいえ、ティモシー・シャラメ似なのに、「うーむ、どうもなぁ」な感じだぞ、ジャック。
本作、自身のなかではいまひとつ肚に落ち切っていないので、今後どうするか。
パンフレットなどで他者の解説を参照するのが手っ取り早いのだが、そういうことはあまりしない方。
ドストエフスキーの原作は読んだし、他のブレッソン作品と比べるのも手だが、その前に同じ原作をヴィスコンティが撮った『白夜』と比べてみようと思う。
男性の妄想を映像化したかのよう
独特の雰囲気を醸し出す映像、音楽は良かったと思いますが、
高評価の中に、女性が投稿したものがあるのでしょうか
フェミニズムではありません
が、
マルタは男性の理想なのでしょうか こういう作品が名作と謳われていることを残念に思いました
ここから先はネタバレになると思いますので、細かい内容を知りたくない方は
スクロールしないでください
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
見知らなぬ男性にまるで恋をしているかのような、突然のフルヌード
会ったこともない男性に、若い女性が「連れ出して」?しかも肌を許す?
エレベーターを止めて閉じ込める、放置したのに愛され続ける...
下宿人も、そんな男を愛する設定も、
男性本位の身勝手さ、女性を軽視しているような視点が不快でした
パリの街に音楽が流れていた
19世紀のペテルブルグではなく、20世紀のパリのポンヌフ(第9橋)で、現れない恋人を待つ女性と画家の青年が出会う。
彼女は存在そのものが美しい芸術のようだけどロマンティストではない。彼はとても孤独で貧しいけど悪意はなくロマンティストだ。
60年代後半のパリの街には音楽があふれている。吟遊詩人のように街角でギターやバイオリンや笛を演奏する人たちもいる。
セーヌ川を行く船も音楽と共に流れていく。
そうして彼と彼女の束の間の時間も流れて消えていく。
唯一音楽だけがそれを知り惜しんでくれるかのようだ。
なにも救いがないほどつらい孤独の中で、20世紀と言うさらに人間をコンクリートで囲ってしまう孤独の檻の中で、彼はなんとか持ち堪えているんだ。共感しないわけがないじゃないか!
40年前に見た映画だからあいまいなところはあるけど、心に染み付いている。10代のころ、4,5回は見に行ったと思う。池袋に文芸座とかいう映画館があった時に。
流れて過ぎていったあれらの音楽の曲名を知ることはできないだろう。DVDも発売されていないから二度と聞くこともできない。
だからこそ、一層懐かしく、胸がしめつけられる。
記憶が確かなら、あれは1968年のアカデミー賞芸術作品賞かなんかだったような気がします。最高に芸術的であることには間違いないと私も思う。万人に理解されるかは別として。
全4件を表示