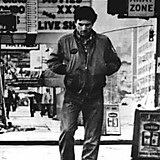ネットワークのレビュー・感想・評価
全27件中、21~27件目を表示
大胆で奇抜なテレビ業界の内幕暴露映画の真面目な風刺劇
テレビ界の出身で法廷劇の代表的名作「十二人の怒れる男」を発表した監督シドニー・ルメットは、そのデビュー作の実力を継続することが出来なかったが、1964年にロッド・スタイガー主演の力作「質屋」で片鱗を見せ、最近ではアル・パチーノ好演のリアリズムの社会派映画「セルピコ」と「狼たちの午後」で復活してきたと思われた。しかし、今度のテレビ業界の内幕を衝撃的に暴いたこの話題作は、あまり感心出来ない。勿論「十二人の怒れる男」には遠く及ばず、「狼たちの午後」にある予測不可能なストーリーの面白さも欠ける。深刻なドラマ「質屋」とも、重量感では敵わない。キネマ旬報の1977年度ベストテンの第2位に選出されているが、これは全く理解できない。ルメット監督なら、もっと完成度を要求しなくては意味が無いと思うのだが、どうしたのだろう。
視聴率獲得に血相を変えて人間性喪失の失格人物たちが、カメラの前とスタジオ外で子供じみた戦争ごっこをするのは、それはそれで面白いと思う。しかし、それを表現するのに大人の視点や批判が演出に欲しかった。ニュース報道部の主任ウイリアム・ホールデン始め、この作品でオスカーを得たフェイ・ダナウェイやピーター・フィンチの主要人物をそれなりに現代マスメディアの人間として描いている。しかし、何かに取り憑かれたようなニュースキャスターのフィンチとその扇動に共感し支持する客席の民衆とのスタジオシーンは、その社会性より皮相的な作り話の可笑しさしかない。この風刺にはルメット監督の良さが出ていないと思った。ダナウェイの熱演については改めて感心したが、でもこの程度の演技は彼女にとって普通だし、フィンチもこの役柄のお蔭でアカデミー賞を受賞したと思わせる。アカデミー賞の悪い一面が出たか、他に評価すべき俳優が居なかったのか、そのどちらかだろう。テレビはメディアの中で独立した強大な武器になることは理解する。その点を付いた大胆で挑戦的な制作意欲は買うが、内容が幼稚ではないだろうか。そこにアメリカらしい皮肉もある。ただ個人的には響かなかった。
テレビ出身のルメット監督が成し得る初めてのテレビ内幕暴露映画だが、結末が安易すぎてしっくりこない。また、その結末のスキャンダル性と、後半の社会批評に風刺の説得力がない。それでもフェイ・ダナウェイの熱演でラストまで引きずられる面白さは久し振り。どうせ皮肉ならば、テレビの世界を知り尽くしたルメット監督の遊びが出来たのではないかと惜しまれる。
1978年 5月18日 池袋文芸坐
ブラック
『TV業界の今日を予言した一作』
自宅にて鑑賞。TV業界作り手の裏側や恥部を告発、昨今の醜態を予言した様な一作。ボテッとしたフォントのオープニングロールとタイトルコール。狂える男の一言は低迷する報道部や製作部、果てはテレビ局にとって、降って湧いた様な千載一遇のチャンスとなる。そこから始まる狂乱とも呼べる局内外の権力争いと影響される視聴者に世論。唯一の良識と思える男は派閥(権力)争いに巻き込まれ馘になってしまう。全篇に亘り、BGMはTVから流れるCMや番組テーマ曲のみで構成されている。かなりイカレた内容だが、マスメディアに興味がある人にはマストな一作。80/100点。
・アチラを見てもコチラを見ても始終、写し出されるのはおじさん達ばかりで、地味目の画面が殆どではあるが、'76年と云う時期に、コンプライアンスを声高に唱える反面、数字に取り憑かれ狂騒を繰り返すメディア業界の今日を連想させる本作を作った意義は大きい。ぜんざいの甘さを引き立てるのは添えられた一片の塩昆布であり、現実離れしたのが数多く描かれる映画(エンタメ)界にも、派手さには欠けるものの本作の様な渋めの一作は貴重なビター・スパイスである。
・余り乗り気でなかったが、観始めると描かれている内容にグイグイ惹き込まれた。明確な善人や悪人は登場せず、各々がそれぞれの立場で奔走ずる姿は、部外者からは滑稽で狂気にも通ずる感覚を憶える。テンポも悪くなく、ほぼ無駄が無い引き締まった展開は、観ている者を飽きさせない。人気者が出る甘いばかりのラブストーリーやお伽噺にしか思えない青いアニメ、超人達が翔び交うヒロイックものも悪くはないが、たまには武骨で骨太な本作の様な渋い一作も観ておくべきである。自称“バリスタ”が淹れる中途半端なコーヒーよりもウンッと目醒めが佳い事は保証する。
・求心力が人一倍強く、上昇志向の塊の様な女。そんな女に惹かれ、25年築き上げた家族を顧みない哀しい初老の男。顛末に救いらしきモノは存在しないが、鑑賞後の後味も悪くない。ただともすれば古臭く感じてしまう画面をどう感じるかによる。よく見ると、何度か登場する「ハワード・ビール・ショー」内の観客席には毎回、複数の同じ客(長髪に髭を伸ばした男性や白地に赤い縦縞のカーディガンを羽織る女性等)が見受けられる。
・本作はP.チャイエフスキーのオリジナル脚本が基となっているが、'74年7月15日、米国のABCテレビの関連会社WXLTテレビ(現WWSB)のトーク番組「サンコースト・ダイジェスト」の生放送中に女性キャスターC.チュバックが拳銃自殺を遂げた(彼女を題材にドキュメンタリー『Kate Plays Christine('16・R.グリーン監督)』と『Christine('16・A.カンポス監督)』の二本が映画化されている)。当初、P.チャイエフスキーは否定していたが、後にこの事件に触発され、本作の脚本を書き始めたと認めた。
・F.ダナウェイの“ダイアナ・クリステンセン”は、伝説のTVプロデューサー、リン・ボーレンがモデルになっているとされている。亦、M.ワーフィールドが演じている“ローレーン・ホッブズ”は、共産主義者としてメディアに迎合し、取り込まれた感のある実在した政治活動家アンジェラ・デービスがモデルとなっている。
・犯罪者自らが撮影したフィルムを鑑賞する際、話題に出ていたパトリシア・ハーストは実在の女性(身代目的で誘拐された後、誘拐犯側の一員になったストックホルム症候群の富豪令嬢)である。K.クロンカイトが演じている“メアリー・アン・ギフォード”はパトリシア・ハーストがモデルと思われる。亦、彼女の実父ウォルター・クロンカイトは“ハワード・ビール”役をオファーされたが、興味が持てず断ったとされている。
・P.フィンチが演じた“ハワード・ビール”はH.フォンダにオファーされたが、余りにもヒステリック過ぎるとの理由で断られたと云う。J.スチュワートも言葉が汚いとの理由で断ったとされる。この役は、(上述の)W.クロンカイト、(脚本も読まず辞退したとされる)G.C.スコット、G.フォード、G.ハックマン、J.チャンセラーにオファーされたらしいが、脚本執筆時のP.チャイエフスキーは、H.フォンダ、J.スチュワート、P.ニューマン、C.グラントを思い描いていたと後にインタビューで答えている。
・“マックス・シューマッカー”には、W.マッソー、G.ハックマンがオファーされたと云う。最終的にG.フォードとW.ホールデンが最終候補として残され、W.ホールデンがこの役を得た。
・第49回(1976年度)アカデミー賞主演男優賞 にノミネート直後、“ハワード・ビール”役のP.フィンチは心不全で急死したが、その後受賞し、アカデミー賞史上初の死後受賞となった(後に死後受賞したのは『ダークナイト('08)』のH.レジャーが二人目)。亦、W.ホールデンの“マックス・シューマッカー”の女房“ルイーズ”役そしてB.ストレイトが同年同賞の助演女優賞を受賞したが、アカデミー賞史上最も短い出演時間(約五分半)での受賞となっており、'19年8月現在、この記録は破らていない。
・'07年に千五百人以上による投票により決定されたAFI(American Film Institute)が定める「AFIアメリカ映画100年」の64位にランクインしている。米国を代表する映画評論家R.エバートの「最も素晴らしい映画ベスト100(Great Movies:The 100 by Roger Ebert)」にもランクインしている。亦、映画プロデューサーのS.ジェイシュナイダーによる「死ぬまでに観たい映画1001本(101 Gangster Movies You Must See Before You Die by Steven Schneider)」にもランクインしている。
マスメディアのモラルの崩壊
暴走する映画
総合:60点
ストーリー: 55
キャスト: 70
演出: 55
ビジュアル: 70
音楽: 0
視聴率を巡っての厳しい競争にさらされるテレビ業界。途中まではなかなか面白かったのだが、CCAの会長のジェンセンがビールを豪華な会長室に呼びつけて、急にどこかの舞台俳優さながらにわけのわからない観念的な思想を叫ぶところが理解出来ない。ビールは元々精神的におかしくなっていたとはいえ、あれだけですっかり会長の話に洗脳されてしまって制御出来なくなってしまう。また、いかに彼が自分の会社に都合の良くない放送を前回したとはいえ、会長も何故自分のところの看板番組をあのように手をかけて潰すようなことをするのかもわからない。彼に前言を撤回させるように命令するか、番組から降ろせば済むだけのことだろう。
テレビ業界の何でもする汚い視聴率競争の裏世界を描きたいのだろうが、手が込みすぎていてわかり辛かった。物語の後半からは大袈裟な表現や演出が目に付くようになって、あまり自然な感じで見られなかった。物語が暴走するテレビ業界の裏側を描くということなのだろうが、映画そのものも暴走したような感じ。
全27件中、21~27件目を表示