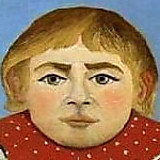シン・レッド・ラインのレビュー・感想・評価
全5件を表示
【“実存と内省。”今作は、激烈なガダルカナル島での日米の死闘を描きながら、兵士の頭に過る想い、恐怖、生と死、虚無、善と悪を印象的なショット、多数のモノローグを交え描いた異色の戦争映画である。】
ー 今作では、多数の有名俳優が登場する。
ショーン・ペン、ジム・カヴィーゼル、イライアス・コティーズ、エイドリアン・ブロディ、ジョン・キューザック、ニック・ノルティ、ジョン・C・ライリー、ジャレッド・レト、ウディ・ハレルソン、ジョージ・クルーニー、ジョン・トラヴォルタ・・。
だが、頻繁に逃亡を繰り返すウィット二等兵を演じたジム・カヴィーゼルや彼を担架兵として使うウェルシュ曹長を演じるショーン・ペン、軍功を上げようと無謀な作戦を指示するトール中佐を演じたニック・ノルティ、兵を護るためトール中佐の命令に従わないスタロス大尉を演じたイライアス・コティーズ以外は、ワンショットでの出演のみである。
まるで、戦争における兵士は劇中で語られるように”幾らでも代わりがいる。”とでも言うように。ー
■1942年。アメリカ軍は日本軍の駐留するガダルカナル島を、太平洋戦争の重要な拠点と見なしてその占拠を計画する。
ウィット二等兵やウェルシュ曹長をはじめとするアメリカ陸軍C中隊の面々も作戦に参加し、彼らを乗せた上陸用舟艇が美しい島に上陸すると、そこは静寂に満ちていた。が・・。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・今作の特徴は、激烈な日米の死闘を描きながら、随所で米兵たちの心理がモノローグで語られる事である。
例えば、軍功を上げようと無謀な作戦を指示するトール中佐は”ここまで来るのに、おべんちゃらや屈辱を感じながら来たんだ・・。”など。
つまりは、兵士の表面の姿だけでなく、内面も描いているのである。
・印象的なのは、その戦闘シーンの合間に描かれるガダルカナルの豊かな自然である。青い海、ワニ、梟、まるで闘いとは無縁のシーンが挟み込まれる事で、戦闘の異常さ、恐ろしさが対比されるのである。
・日米の兵士関係も、米軍=善、日本軍=悪という表層的な描かれ方はしない。どちらの兵も、死に面しては恐怖の表情を浮かべ、唯々死んでいく。
印象的なのは、ウディ・ハレルソン演じるケック軍曹が"新兵のような手榴弾の鍼管を誤って抜いてしまい、下半身を怪我して死ぬ”シーンである。
戦場には、唯々、死があり、僅かな差で生があるのである。
その僅かな差が”シン・レッド・ライン”なのだろうか、などと少し考える。
・又、ベル二等兵が夢想する妻との愛撫シーンが度々描かれるが、後半彼の元にその妻から別れの手紙が来るシーンも、何ともシニカルである。
彼は、愛する妻の元へ無事に戻る為に、戦っていたのではなかったのか・・。
<そして、今作のラストでは、兵士たちは舟に乗って島を出るが、日本軍に勝利したのかはまるで描かれない。そして、ウェルシュ曹長を演じるショーン・ペンの表情は嬉しさの微塵もなく、虚無的にも見えるのである。
今作は、戦争という行為を兵士の内面にまで踏み込んで描いた、従来にない異色の戦争映画である。分厚い本を読み切ったかのような感想を得る作品でもある。>
勝者だからこその戦争観か?
静かな戦争映画が第一印象。爆発音や阿鼻叫喚は控え目か。それでいて淡々とそれぞれの心の声が聞こえる。これに徹したのはすごいと思う。戦場の実際は表現しきれないと割りきったのかな?
さらに、違和感は戦勝国の驕りというか優越感だね。敗戦側は今この瞬間で精一杯、生きるが最優先だったはず。この目線がしっくりこないのは、敗戦国民の僻みだけじゃないと思う。
愚かな上官も勝てば英雄、負ければ犯罪者。この構図は今も繰り返されるのがなんとも悲しい。戦場に英雄は要らない。
特筆はキャスティング。良く揃った感じ。エイドリアン・ブロディの次の成功を予想させる妙な存在感。ワンカット的なスター登場はおまけだな。
タイトルに込めた思い
RED LINE には一線を越える、の意味。
THIN RED LINE には少数精鋭、の意味。
そして超えてはならない一線の意味もある。
生と死の境なのか、平常と狂気なのか、光と闇なのか。何故このタイトルにしたのか、その思いは如何に。
(ワーテルローの戦いやクリミア戦争のことは分からないので置いておく)
ラストでウィットが光を失ってしまったことを揶揄したのか、激しい戦火をものともせず日常を送る島民や美しい自然との境なのか。解釈が多数あり、映画をシンプルに観たい人には眠い作品だと思う。
退屈なほど抽象的なシーンも多く、まるで戦争と平和を描く宗教画のような作品。
国破れて山河あり
この映画、人間の視点・時間軸では描かれていない。
じゃあ何の視点・時間軸かと問われても正解はない。
敢えて言えば神の視点・時間軸だろうか。(あまりにもベタ過ぎるので書いていて恥ずかしいのだが、分かりやすい例として挙げておく)
生けとし生きるモノ全てを並列に描いている。
苛烈なガナルカナル島の戦闘も、美しき島の自然も、ラストシーンで海に漂うヤシの実も。
国破れて山河あり。
人間同士が壮絶に闘い殺しあっても、想像を絶する苦難を伴って死んでいったとしても、厳然と存在し続ける山河。太古の昔から、そしてこれからも。
ラストシーンのヤシの実は新しき命の誕生の象徴なのか。人間の苦難にかかわりなくこの世界は続いていくということなのか。
これを希望とみるか虚無とみるかは観客の側に委ねられている。
睡魔との激戦
退屈。冗長。
ここまでで苦痛な映画はなかなかないかも。
戦争映画でありながら、象徴的な映像と詩的な独白が延々と続く。
そういった抽象的な演出によって、生と死を考えさせる映画なのだろうが、実質的にはストーリーはないに等しく、余程感受性な人でないとそんなレベルに至らない。
加えて、取り立ててフォーカスされるキャラクターもいないせいか、誰が誰だかわからなくなってくる。
唯一、残してきた奥さんについて散々妄想していた彼がその奥さんに裏切られるところのみ、ドラマを感じた。
全5件を表示