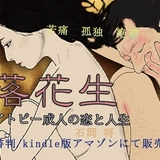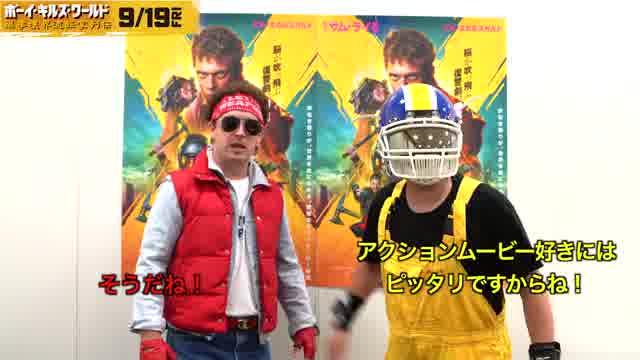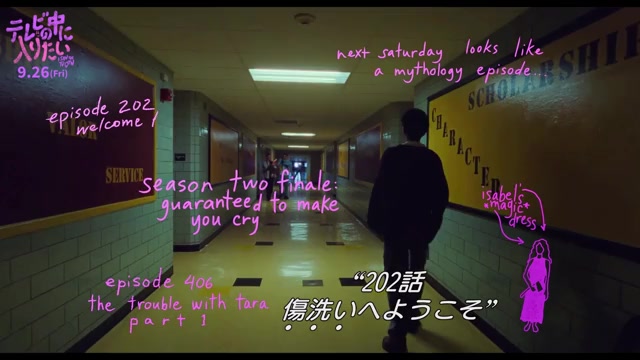テレビの中に入りたいのレビュー・感想・評価
全63件中、21~40件目を表示
ミスター・メランコリー
徹頭徹尾、暗い、マイナー、登場人物でミスター・憂鬱(メランコリー)という謎のキャラが出てくるが、この映画を象徴している
中2病みたいな映画なので、50過ぎて観るには結構きつかった…
まさにThe A24映画、刺さる人には刺さる作品か、と
渦にハマってく感じ
個人的にはぶっ刺さった。
【まず初めに】
この映画の解釈は観る人にだいぶ委ねられます。
それゆえ抽象的、分かりにくいといった感想を抱きやすいです。
※私も観終わった直後は「なんやこれ」って感じでした。
ただ、監督自身がわざと余白を残して作成した、と答えているのでそれがこの映画の狙いでもあります。 ※cinraというサイトにインタビューが載っています。
あとbgmが凄くいいので、soundtrackもオススメです!
【以下、整理用の備忘録】
「The Pink Opaque=理想郷」
理想郷=自分のセクシュアリティを開示しても受け入れられる世界。
TVの中にはいる=トランスやクィア的アイデンティティを発見・解放する比喩。
ピンクは性的マイノリティのシンボルカラーでもあり、冒頭のバルーンの色もジェンダーフラッグの色を意識している。
【オーウェン】
主人公のオーウェンは内気でクィア、家庭にも問題がある。
母親は過保護で支配的、冒頭の選挙日にも自分が望む候補者を指示するなど。
父親は保守的でオーウェンと会話らしい会話をせず、畏怖の存在として描かれている。オーウェンがテレビの中=理想郷にはいろうとすると無理矢理引きずり出す。
このような環境では自己肯定感が育つわけもなく、オーウェンはより内気で自ら選択ができないまま大人になる。
例えば、マディの1回目の誘いの時、友人宅の母親に僕が外出禁止になるようにして!と懇願したり、2回目の誘いの後、マディが来るまで家に引きこもるなど。あと、映画館がつぶれたから上司と一緒にゲームセンターに就職するとか全体的に他人まかせ。
その結果、オーウェンは理想郷に行けず、クソな現実にとどまることを選ぶ。
「男にならなきゃ」「家庭を持った」は現実で受け入れられる"異性愛者である普通の男性"として自身を偽ることの表れ。
でも、偽り続ける日々も長続きせず、誕生日パーティーでの絶叫シーンにつながる。
その後のトイレシーン、お腹の中のtvの光は理想郷であり、オーウェンが自身のクィア性、トランスジェンダーであることを解放したがっていることを示す。
【マディ】
一方、マディはオーウェンとは対照的で「解放された人」として描かれている。
レズビアンとしての自己を肯定できたキャラクター
数年後に再登場した彼女は、外見・態度からも「解放された姿」で示されている。
だからオーウェンを助けに来る=「あなたもtvの中(理想郷)に来られるよ」という手を差し伸べている。
が、オーウェンは自身のセクシュアリティを認める自己肯定感が育ってなかったので2度マディの誘いを断る。
→オーウェンは誰かに助けをもとめ、謝り続ける人生をおくる。
観た直後は、マディ=精神異常者
つまり、彼女もまた家庭の抑圧から逃れられず、「ここではないどこか」への願望を拠り所にしていた。そこで自身をお気に入りのtv show の登場人物である。ということにして自身の精神性を保っていた。
中盤の「tvの中に入っていた」は虚言。
本当は地方を放浪しながらどこにいっても現実は変わらないということに絶望して、オーウェンに会いに来た。
その後の穴=死のメタファー
※これは偽りの自分を殺して、本来の自分として生き返ることにもみえる。
と思ったんですけど、これはあまりに暗すぎかつ救いのない感想なのでなし。
でも、保守的な家庭に育ったオーウェンからみると自らのセクシュアリティを認められたマディは狂人にみえるかもしれない。
なぜなら、彼にとって自分のトランス性を認めるのはありえない、狂気じみた行為だから。
面白くなりそうでならない
個人的に深く刺さるところまでは行かなかったけど 独特過ぎる世界観と...
淡いポップ感で進む普遍的な文化愛のブルース
なんとかジェンダーとかなんとかクライシスとか
10月のファーストデーはバタついてて1本のみ。
冷静に考えると各映画館のサービスデーの方がお得なんだよね。
とはいえなんか1日に映画をハシゴする習慣は気に入ってたり。
さて、本作のレビューは他の方が語っているのでお任せするとして、少し前にネットでバズってたクソださいジェイデン・スミスのほうがウィル・スミスの息子で、ジャスティス・スミスは全然血の繋がりがないことがわかってほっとしました。
あんな有名人二世拗らせた承認欲求の塊みたいにダサい人がこんな演技できるのかー、って思いながら観てたので。人の顔がイマイチ見分けられないのは本当に映画好き向いてないですね。
向き不向きとか好き嫌いとか価値観とか倫理観とか…一度立ち止まってしっかり自分のアイデンティティと向き合うことは大事だなと思いました。
そういや最近ぼーっと光る砂嵐のモニター見てないな…。
それではハバナイスムービー!
A24らしい作品でもこれはストーリー無茶苦茶
A24作品はエブエブや愛のステロイドのように話が複雑でも最後はしっかりまとめる作品も
あれば、関心領域のような歴史や現代社会のガチの作品と幅広い。今回の作品はA24らしく
話が複雑。確かに話は複雑で後半はホラー要素も満載だったが、気になったのはストーリーが無茶苦茶。残念。オチも首をひねる内容。いくらA24でもこれは不出来。今年のワースト作品有力候補。
人生何処かで断絶している気がしてくる
クィア映画を初めて見た。
クィア映画を初めて見た。こういう感じなのか。
TV番組「ピンク·オペーク」にハマる2人、オーウェンとマディ。「ピンク·オペーク」では、敵のボスMr.Melancholyが毎週色んな怪物を登場させ、それをちょっと臆病なイザベルと自由で解放されているタラが、退治していることになっている。
マディはタラと同化し自分自身を見つける(=クィアであることを自覚)が、オーウェンは卵の殻に閉じ込もっていて、臆病なまま。
あなたは孵化しますか?
それともMr.melancholyのLunaJuiceを飲み続けて「甘美な」監獄に居続けますか?
と問いかけられているような気がした。
自分自身(59才男)のことを考えると、小さい頃から疑いもなく男として育ち結婚し子供も3人いるが、割合乙女チックなところもあり、多少理解はできるかな。
A24史上最高の憂鬱
1回目の鑑賞で1mmも理解出来ませんでしたので、再鑑賞しました。結果3分の1ぐらいには理解度が深まりました。
全体的に負のオーラは感じましたが、ノスタルジーやエモーションはほぼありません。中二病ほど知ったかぶりしてる風でもないし、リンチワールドも望めません。映像美に浸るほどでもない。
ただ独自の世界観を最後まで押し通せる力量は、ある意味逞しいと言えます。
中高生時代のマディの口元にうっすらと髭が生えているように見えてしまい、ずっと気になっていました。たまたまそう見えるだけなのか、セクシュアリティの表出なのか。
オーウェンが中年になって胸を割いても、やっぱり空っぽでTVの光しかないっていうのは、ちょっぴりペーソスを感じました。
音楽はよかった。特にパンクボーカルにはとても惹かれました。
【ピンクの混沌】今作品は居場所がTVのみだった少年が、成長する中でも閉塞感を脱せないまま、年齢を重ね、精神に異常を来すメランコリックスリラーである。
ー 1990年代のアメリカ郊外を舞台に、自分のアイデンティティにもがく若者たちが深夜番組の登場人物に自らを重ねる姿を、不穏かつ幻想的に描いたメランコリックスリラー映画。ー
■冴えない毎日を過ごすティーンエイジャーのオーウェン(ジャスティス・スミス)にとって、毎週土曜日の22時30分から放送される謎めいたテレビ番組「ピンク・オペーク」は、生きづらい現実を忘れさせてくれる唯一の居場所だった。
オーウェンは同じくこの番組に夢中なマディ(ジャック・ヘブン)とともに、番組の登場人物と自分たちを重ね合わせるようになっていく。
しかしある日、マディはオーウェンの前から姿を消してしまう。
残されたオーウェンは、自分はいったい何者なのか、知りたい気持ちとそれを知ることの怖さとの間で身動きが取れないまま、時間だけが過ぎていくのであった。
◆感想
・今作品はA24本来の、若手映画製作者に思った通りに作品作りをさせるスタイルを貫いている。
・故に、アーティスティック過ぎるシーンも多数あるが、私はこれで良いと思う。
・今作品では、劇中に流れる曲も格好が良い。特にゴシックパンクの曲を演奏するシーンかな。
◼️劇中で、歳を重ねたオーウェンが昔、夢中になって観た"ピンク・オベータ"を観て、”全然面白くない"と呟くシーンがあるが、それはオーウェンが成長した事を意味しているのだが、彼は自分の成長を受け入れられず、精神を病んでいくのである。
そして、それは、失踪したマディも同じなのである。
<今作品は、青春期の閉塞感から抜けられずに、年齢のみを重ねた男女の姿を、シニカルに描いたメランコリックスリラーなのである。>
<2025年9月28日 日本最古の営業映画館長野相生座・ロキシーの相生座にて鑑賞>
<2025年9月29日 追記>
◼️さあ、今から宴会じゃなかった、歓迎会だあ。お仕事、お仕事。呑み過ぎ注意だね!と昨晩書いたけれども、飲み過ぎた・・。
残念ながら、私には向いておりませんでした。。
短い期間で続々と公開が続いているA24作品、ハピネットファントム・スタジオさん、頑張ってます。
以前に一度だけ劇場でトレーラーを観た記憶がある本作。その時はあまり自分向きな作品ではないように思えていたのですが、公開が近づくにつれて評判が聞こえだし、特に業界方面はザワついている様子。と言うことで、用途が決まらないまま使用期限切れが目前に迫ったU-NEXTポイントを使い、ヒューマントラストシネマ有楽町で鑑賞することにしました。
毎週土曜日22時半。謎めいた深夜のテレビ番組『ピンク・オペーク』に激しく傾倒している少女/女性・マディ(ジャック・ヘブン)。そして、そんなマディと出会い彼女に“通じるもの”を感じて自らの意思で『ピンク・オペーク』にのめり込んでいく少年/男性・オーウェン(ジャスティス・スミス)の30年に渡る人生。時代の変遷とともに“見方・見え方”も変わり、戸惑いつつも自分の本質についてこだわって探し続けるオーウェンの“行き着く先”は…
と言うことで感想ですが、、惨敗ですね。ごめんなさい、私には正直解りませんでした。。元々「理屈」に頼るタイプの私にとって、この手の作品はいちいち自分が解らないことにこだわってしまい、ストーリーやその中にあるメッセージについていけなくなりがち。本作の場合、冒頭の展開までは問題ないと思っていたのですが、全般を通して独特すぎる表現や編集のアレコレに理解が追いつかなくなり、自己防衛本能が働いて正直何度か気を失っていたような気がします。
勿論、理解できないものに対しそれだけの理由で作品を否定する意図はありません。むしろ、「あゝ、これこそA24作品だな」と感じるようなクリエイター・ファーストを地で行く(将来的にも)重要な作品なのだと思います。ただ、トレーラーを観た際の印象は間違ってはおらず、“自分向き”な作品ではなかったと言うこと。なので、低い点を付けてしまうこと、何卒ご理解いただけますと。。ご容赦ください。
TV Maniacs
予告すらほぼ見ないまま鑑賞。
自分は22時半で“深夜”番組ということに驚きを隠せない夜型人間ですが。笑
『ピンク•オペーク』をきっかけに親しくなったオーウェンとマディ。
番組を見るためにオーウェンがマディの家に訪れるところから話が動いていくが…
正直よく分からないし、まったく刺さらなかった。
オーウェンの疎外感や閉塞感は台詞のみでしか語られず。
“2年後”の会話や他の映画評から、ジェンダーアイデンティティを扱ってはいるらしい。
しかし抽象的過ぎて自分には理解が及ばない。
更に“8年後”、戻ってきたマディは「『ピンク•オペーク』の世界こそ現実だ」と言う。
これを妄言として突き放したオーウェンの元には、二度とマディは戻ってこない。
それが真実かどうかは多分どうでもいいのだろう。
そこからまた20年も時間を飛ばし、その中でオーウェンは妻子をもったことが語られる。
ただ、意味深にもこの“家族”は影すら映らない。
最後は錯乱したオーウェンで終わり、これはアイデンティティと向き合わなかった末路か。
表現が分かりづらい上に、ひたすら横顔のアップを映すマディの一人語りなど退屈が過ぎた。
独白もモノローグもあるのに、第四の壁を越えた語りかけまであって胃もたれ。
あと個人的にはせめて“8年後”までで締めてほしい。
少なからず存在するのだろうが、おっさんになってまだ現実と折りあえてない様は見てて痛かった。
テレビの中に入りたい(映画の記憶2025/9/28)
シーズン5で1000話超え!?
アメリカの郊外で暮らす中学生の男の子が、同級生の女の子に教えてもらったTV番組「ピンク・オペーク」にハマって行く話。
マディの家にお泊りに行って、毎週土曜日22:30から放送されるヒーロードラマ?「ピンク・オペーク」をオペークを教えて貰ったけれど、オーウェンの就寝時間は22:15と決められており観られません!ってことで、録画して貰ったビデオで鑑賞!となって行くけれど、見る順番はぐちゃぐちゃなので?そして良くわからないけれど初回はPILOT?
なんだか不思議な女子2人組ドラマのピンク・オペークを観続けたけれど、環境が変わってマディは引っ越してしまい、取り残されたオーウェン君ががるぐるぐるぐるぐる…そしてマディが現れこいつマジか!?
現実とドラマが交錯しなんだか良くわからないことになっているけれど、アイデンティティ云々ってそういうこと?
スリラーといえばそうなのか?
どういうことかはなんとなくは分かったつもりだけれど、ちょっと自分には理解できない話しだった。
全63件中、21~40件目を表示