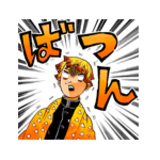おーい、応為のレビュー・感想・評価
全292件中、101~120件目を表示
葛飾北斎と娘、応為の話
まさみちゃんは抜群に美しい。
映画の始まりでカメラワークが酔う系かーと気合いを入れる、生活音?が結構大きい、映画は淡々と進むなぁと思いつつ、ラストに向けて絵描きの描写で没入していった。
葛飾北斎の絵は赤富士とか波のヤツしか知らないけど、北斎は視える人で降りてきた何かを表現したのだろうか?
ひょっとしたら日本人は北斎の絵と認識しないで沢山作品を目にしている可能性有り。
アニメの方が良かった
2025年劇場鑑賞291本目。
エンドロール後映像無し。途中で1回だけ絵が出てきます。なんであのタイミングでこの絵なんだろうとは思いましたが。
北斎の娘の話ってなんか観たことあるな、と思ったら2015年にアニメ化された百日紅 Miss.HOKUSAI と同じ原作なんですね。あちらは杏と松重豊が親子を演じていて、杏のお栄がカラッとしたキップのいい感じだったような記憶があります。ストーリー全然覚えてないけど・・・。でもなんか明るい記憶があって、今回のこの映画みたいなどんよりした空気感じゃなかった気がするんです。
実写とアニメの違いはもちろんあるのでしょうが、杏の持つ陽の感じと松重豊の温かみのある雰囲気に対して、コメディに結構出ているけど1回も笑わせてもらったことのない長澤まさみと、出るだけでその作品を3割暗くする永瀬正敏というキャスティングで今作が全体的に「真面目か!」というテイストに自分は感じて今ひとつでした。
へたくそな漫画みたい
麿赤兒と大森父子。
応為の歴史を知れる
仕事の極道
広く知られている葛飾北斎と、まだそれほど知られていない娘、葛飾応為(お栄)の物語。
焦点は二人の日常生活に当てられている。
女優の美しさは観ている側に取って邪魔になる時がある。
美しさがストーリーやキャラクターとシンクロしていれば無敵だが、映画やドラマの多くは日常が描かれる事が多いわけで美男美女が演じている事自体無理がある。
そういった意味では主演の長澤まさみさんは、存在感と演技でその違和感をねじ伏せていると思う。
時代考証は大事だと思うけどね。でもそれが
中心になる必要はない。
前田利家の身長の様な例もあるわけで、江戸時代にモデルのようなプロポーションの女性もいたかもしれない。それがたまたまお栄だったと言う楽しみ方もある。実際はともかくとしても。
1番印象に残ったのは、お栄と盲目の妹お猶(おなお)のシーン。普段は無頼の様なお栄だが、その優しさが強く表現されている。ほんの少しだけ自分も似た経験があるので、画面が見えなくなるほど感情移入してしまった。
お栄は綺麗なものと一緒にいたかったんだろうな。
恋をしていた相手。北斎の描く絵。北斎の絵に向き合う姿。それが見える隣に居たかったんじゃないかと思う。
芸術の極道の様な葛飾北斎に永瀬正敏が嵌まっている。いや永瀬さんが嵌めているわけだが、もう少し若い頃からの北斎も見たかった。
最後にあの年号だけはいただけないなあ。
誰か進言する人いなかったの?
圧巻の永瀬正敏
北斎の影に生きた女絵師・応為を描く──映像と音楽の調和が光る作品
先日の『トロン アレス』同様、今回の『おーい、応為』もあまり期待せず、肩の力を抜いて鑑賞した。というのも、過去の『北斎漫画』(1981)や『HOKUSAI』(2020)が正直どちらも印象に残らず、期待値が上がらなかったため。
しかし、本作は良い意味で裏切られた。秀作というより“好感度の高い作品”と呼ぶのがふさわしい。その理由をいくつか挙げたい。
●リアルな日常描写
食事風景や衣装、会話のひとつひとつまで、北斎や応為を含めた江戸庶民の暮らしが丁寧に描かれている。他の作品にありがちな、蔦屋重三郎や歌麿、馬琴、十返舎一九といった人物の“顔見せ的クロスオーバー演出”がなく、あくまで北斎と応為の関係に焦点を絞っている点が好印象だ。
●画家のまなざし
物語は父娘ふたりの絵師に徹底して寄り添い、画家がどのように風景や人々を見て、頭の中で浮世絵として再構築していくのかを映像化している。これは他の北斎作品にはなかった視点であり、実に新鮮だった。
●映像と音楽の妙
日本の四季や庶民の生活を背景に、トランペットとギターによるアンサンブルなJAZZが流れる。意外な組み合わせながら、映像に見事に溶け込み、心地よいリズムで物語を支えている。
特にラスト近く、望遠レンズで捉えた富士山の夕景は圧巻。構図・光・色彩、どれを取っても息をのむ美しさだった。
●二人の俳優
応為を演じた長澤まさみ、北斎を演じた永瀬正敏。
永瀬は海外映画『パターソン』で日本人詩人を演じた頃から演技の深みが増した印象があり、本作でも自然体のまま50代から90歳までを見事に演じ分けている(そのために8kg減量したという)。
一方の長澤まさみは、本作で新たな境地を見せた。男勝りで“べらんめぇ”な気風を持ちながらも、ふとした瞬間に女性らしい色気が漂う。特にキセルを操る所作の艶やかさは、まさに浮世絵的といえる。
総じて『おーい、応為』は、派手さはないが、映画好きの心には確かに響く作品だ。例えるなら、かつてのATG(日本アート・シアター・ギルド)作品のような静かな余韻と趣を持っている。観る人を選ぶタイプの映画だが、じっくり味わうにはうってつけだと思う。
何が描きたいんですか
ちょうどいい時間にやってたから、という適当な理由で特に期待もせず鑑賞
いや、ただひたすらに退屈でした…。
わたしはフランス映画なども観るほうで、静かな映画は嫌いじゃないんですが、それでも退屈すぎて2回ほど寝ました。
静かにしても心情描写がなさすぎる。
長澤まさみの演技は単調で、べらんめえ口調でかっこつけてるか怒鳴るかの二択
何を考えているのかも表情などでは伝わってこず、主人公なのにペラペラの人物像
序盤の火事のシーンなど、火事に対してどう思っているのかが伝わらず、のちのセリフで(ああ、火事が好きなのね、ちょっと表情ではわからなかったな)と困惑しました。
なにかが起きてもそれに対してなにを思っているのかが伝わらなかった。
北斎のほうは一貫してたのでまあ、という感じ。
ただ汚い家で偏屈に絵描いてるだけの人ではあったけど。
ほかの登場人物も、物語にとって別にいてもいなくても変わらない人間たち。必要なのはお母さんぐらいか。
彼らとの交流で心情描写が深まるっていうこともなく、ただ少し普通にちょろっと話して終わり。
だから死んでも(ああ死んだんだな)という感想しか抱かないし、悲しんでる親子を見ても そこまで深い交流があったわけじゃないのになんで悲しいのかわからない、という感じ。
前半に心情描写が深まっていないのに後半に急に心情描写が出てくるので、急にどうした?と思います。
そして浮世絵師の話なので、作品に対する思いとか制作の苦労とかの話があるかと思いきや、なんか絵描いてるな、っていうだけ。
2時間の尺ですが、ほとんどのシーンが心情描写やのちのストーリーには関係なく、ずーっと日常風景を見せられていただけでした。
終盤親子の絆みたいなのを描きたいのかな?ってやっとちょっとわかったけれど、それまでに親子が交流したりお互いを気にしたりするシーンもほとんどなかったなと。
そして、長澤まさみはひとりだけ老けなさすぎて不自然。
ホタルのシーンも安っぽい演出すぎてびっくりしました。あんなんならあのシーンいらなくない?
セリフ回しもなんか江戸っ子っぽいところと現代女性っぽいところがあって、統一感がないなあと思いました。
散々酷評しましたが、まあ強いて良いところを挙げるとすれば、
・犬がかわいい
・エキストラの人や街のセット、部屋のセット、遠くで聴こえる雑音がリアルな江戸な感じがして良い
・北斎の老け方が良い
以上です。
あとは特に見どころはないかな、ひたすらに眠かったです。
一筋縄ではいかないリアルな会話の面白さ
一筋縄ではいかない会話がほんとうに楽しい。
父子の悪口の言い合いも、怒ったり、泣いたり、笑ったり、
とにかくいろんな感情のバリエーションがあって面白いが、
応為が一方的にしゃべって、北斎がなにも答えないシーンが不思議と印象的。
そうそう、人間の会話は、
いつもテンポよく理路整然とやりとりされてるわけじゃなく、
図星を突かれて黙り込んだり、ムッとしたり、
ちょっと考え込んだりすることあるよね、と改めて気付かされるし、
そんなリアルな間が存分に盛り込まれた会話にすごく引き込まれた。
だから、物語は、駆け足に北斎と応為の半生を点描で辿り、
あまり大きな起伏はないけれど、最後までほんとうに面白く観た。
後半の人生を象徴するかのような富士山のアップの描写は大胆。
大友さんのジャズの音楽も喜劇的な感じが合っていた。
そんな感じかー
大友良英さんの音楽を鳴らしすぎる
葛飾北斎の娘の映画。
予告の感じだと娘も天才の父親の影響で絵を描く人みたいで、父と娘の関係性みたいなところが主題なのかしらと眺めてたら、冒頭からドキュメンタリー映画みたいに手持ちカメラでゆらゆらした映像だわ、娘は全然絵を描かないのに周りの男の絵をけなし人格否定する。これパーソナリティ障害なのかしら。
大友良英さんのどこかノスタルジックなユーモラスなジャズは嫌いじゃないけど、シーンの切り替えのたびに鳴らすので、引越しのシーンもチンドンやの行列のように見えてしまう。
序盤は引きつけて後半だれる映画はよくみるけど、珍しく前半から突き放されて、睡魔におそわれる。
後半は、北斎が出てくるたびにどんどん老けていくのがおもしろい。長澤まさみは全然老けない。このあたりから固定カメラに切り替えてようやく落ち着く。そして、娘が絵に目覚めて、父親に対してもさりげなく愛情を示す。
応為の描いた絵に驚かされる。この時代に光源を意識したグラデーションを表現している。北斎は後にカメラアイと呼ばれる瞬間を捉える天才だったが、娘も光や色彩の天才だった。
タイトルがトリッキー
葛飾北斎の娘、お栄は三流絵師のもとに嫁ぐが、父親は言うまでもなく自分よりも画力が劣る夫に嫌気がさして父の元に出戻ってくる。何人かの子どもの中で唯一北斎の画才を引き継いだお栄は絵を描きながら父の世話をする。常に「おーい、飯!おーい、筆!」のように北斎に呼び付けられていたお栄にはやがて「葛飾応為」という画号が与えられる。
この応為の話だと思って観ていると、応為の修行している様や創作過程の苦しみなどが描かれる訳でもなく、肩透かしを喰らうかも知れない。
タイトルが示すように「おーい、応為」と言っている行為者は他ならぬ北斎であり、応為は北斎の最後を看取るまで献身的に付き添い、一緒に旅をし、共に創作活動に励んだに過ぎない。
そう考えれば、本作の主人公はあくまで北斎である。しかしながら、その北斎も応為の存在がなければ90歳で大往生するまで作画を続けることは出来なかったに違いない。
エンドロールで応為の作品をもっとたくさん次々と見せれば、それでもしっかり絵師としての才能を磨いていたんだ、という説得力を持たせられたはずなのに、しっかり見せるのが一つだけなのは残念。
観る前は「大河に乗っかった企画か?」とも思ったが、そこは長澤まさみ主演なので不問に付す…。
「応為」の生き様
長澤さんと永瀬さんの親子良かった。
江戸の人ってそんなに蕎麦食べたの?と思うくらいに
蕎麦食べること強調してる感じでしたが
しゃがんで食べる長澤さんの俺っぷり良かった。
大道芸の飴屋と金魚やなど江戸を強調するシーンが多かったのに、北斎の絵を描く凄さは強調されずに長澤さんとのやりとりでだけ強調された。最後の方の小屋のシーンには泣けた。最後の最後に北斎っぽいのがいい
普通であることは不幸か、それとも幸福か
物語構成にはせず、アルバムをめくるように、その時々の応為と父・北斎の生活が描かれる。
せっかくの北斎なのだから、一枚ずつ絵を眺めるように、とでも言いたいところだが、写真のほうが近い。
凝縮されたものはなく、写真のように、蓮っ葉な態度を貫く応為は、普通なのである。
それなりに期待もしたのだろう結婚は破綻し、恋しい人には想いを伝えることすらできず、応えるだけで得られた幸福を掴むこともしなかった。
家族を普通に愛し、また家族からも愛されていた。
その普通さが、やけに侘しく感じられてしまうのは、傍にずっと北斎がいたからか。
絵に対する感性もあり、それなりに父や周囲に認められもした。
けれどーー彼女は北斎のレベルからは程遠い。
本人が一番それを解っていたのだろう。
北斎が何度も自分の傍から応為を離そうとしたところは印象的だ。
それでも応為は父の傍から離れなかった。
離れられなかった。
面白くはあったが…正気言えば眠くもあったかな。
波が収まっていくように、話の起伏が進むにつれて小さくなっていったから。
いつでも幸不幸ともに抱える応為のように、面白さと退屈さが常に同居していた…そこがいいとも言えるのだが。
役者陣は皆、素晴らしかった。
全292件中、101~120件目を表示