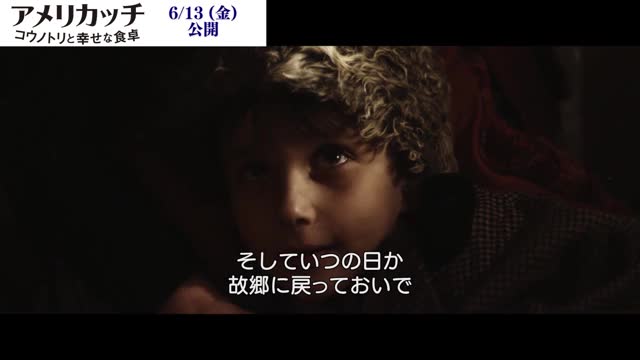アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓のレビュー・感想・評価
全28件中、21~28件目を表示
お国柄、お人柄
幼い頃、トルコからのジェノサイドを逃れて一人「ある特殊な方法」でアルメニアを離れ、遠くアメリカへ渡ったチャーリー(マイケル・グールジャン)。その後、ソ連の統治下となったアルメニア・ソビエト社会主義共和国が「離散したアルメニア人を呼び戻す」ために打ち出した政策に乗じ、微かに記憶に残るメロディーの一節を頼りに、故郷を求めてアルメニアを訪れます。ところが、度重なる意思疎通の齟齬によって「すれ違いコント」さながらにおかしな展開から収監されてしまうチャーリーは、突然に発生した天災がきっかけで起こる「奇跡」によって、自分の牢の窓から見える「向かいの部屋の様子」に気づいて興味を持ち始めます。
言葉や立場などが障壁となってもどかしい状況が重なり、時に死んでしまいたくなることもありますが、その都度、小さな希望を見出しては這い上がろうとするチャーリー。そもそも、自分の祖国でありながらも殆ど記憶や知識がないため、この土地での慣習や振舞い方すらわからない彼は、窓の外に見える「世界」からヒントを得ることで祖国を知り、そして自分の故郷をイメージして思いを馳せます。
一方、作品中の殆どの時間をチャーリーと向き合う役人たちが、「良い意味」でステレオタイプなキャラクターが揃っていて、地味になりがちなシチュエーションを見事に展開させていく役割を担っています。むっつりして如何にも俗物といった感じも、モスクワと妻には頭が上がらず立場の堅持に必死な高官。日和見で処世術に長け、即断即決することでリスクを取らない所長。モスクワ色強くて融通が利かず、目付け役でありながら隙さえあれば虎視眈々と出世も狙っているであろう副所長。そして、最初こそチャーリーに意地悪な仕打ちもするが、どこか牧歌的でまた人情にも厚い属吏達など、モスクワとの距離感も判るような「地方」だからこその世界観と、厳しい歴史が続いたお国柄、お人柄が見えて味わい深く映ります。或いは、彼らと関わりの強い「女性陣」がいずれも(この時代にあって)男勝りで主張が強く、影響力があるからこそ、惑いがちな男達の箍(たが)となって支えているようにも感じます。
決して劇的な感動はありませんが、しみじみ感じ入るような作品性と、グッと掴む「決定的な瞬間」に思わず涙腺を刺激され、チャーリーに引っ張られるようにアルメニアへの興味も沸いてきます。ラスト、これで終わりかと思うシーンからもう一つ、少し先の「未来」が描かれます。早まって席を立たれませんように。良作でした。
愛溢れる視線で周囲を見つめるチャーリーにハラショー!
アルメニアの悲しい歴史は知りませんでしたが、オスマン帝国に大量虐殺され、国を追われた人々を「夢の国へようこそ!」の如き甘い言葉で招き入れ労働力として利用するソ連に胸クソさを覚え、刑務所職員やチャーリーを陥れたドミトリー達のいかにも劇チックな演技に多少閉口しましたが、それを遥かに上回るチャーリーの優しい表情に終始キュンキュンしっぱなしでした。
言葉は通じなくても優しさは伝わるもので、日を重ねるほどチャーリーの身の回りに幸せが溢れてくるのが何とも言えず、こちらにも幸せが乗り移って来るようです。
そして窓越しに繰り広げられる刑務所の看守ティグラン夫妻の日常、会話の内容は聞こえてこなくても、そこで起こっている葛藤などがチャーリーの目を通してワタシの胸にもビンビン届きました。
予告編を見た限りでは、ヒューマンドラマだろうがそれほどでもないのかな、なんて思っていましたが、とんでもない!大きな感動をもたらしてくれました。
エンディングでアララト山をバックに民族衣装と楽器で唄い・踊り・演奏する人たち、その姿や旋律からはソ連なんて一切想起させられない、全く別物の文化や歴史のある国だということが理解できます(作品中でも囚人仲間が、いかにアルメニアという国が世界に先駆けた者や由来があるのかと自慢するのも、オラが国への誇りからくるものなのでしょうね。)。
そんな国が力によって支配されてしまう、本当に戦争はイヤだ(そう言っている間にも北や中東ではたくさんの命が奪われている現実)、その嫌な世界を忘れさせてくれそうな、生きているって、希望を持つって、誰かを愛するって素敵だな、そう思わせてくれる作品でした。
ピーピング・チャーリー
セザンヌが描くサント・ヴィクトワール山と思っていたら…
アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓
アメリカからソビエト社会主義共和国連邦統治下時代に故国アルメニアに帰還した男の話。
塀の向こうの夫婦生活が、蒲焼きの匂いをオカズとしての牢獄暮らし、
恋があり、ホームパーティーあり、夫婦喧嘩あり、歌や別れもあり…
のぞき生活も楽しそうだが、ヒッチコックの「裏窓」を思い出しながら、類似性は思い出せないが、見てはいけないものを見過ぎではないかと思いつつ、盗撮者の楽しんでいる姿を見ている自分も恥ずい。
それにしてもアルメニアって何処なんだ?
こんな国だよっと、
上手い掴みで、
しっかりとアルメニアの歴史と文化を勉強させてくれます。
その一つが、何といっても世界で最初にキリスト教を国家宗教として採用した国で、今も息づいているのが誇りなんだろう。
しかも、何千年も昔からあの紛争地帯でアルメニア人一民族国家として成立しているのだからこれは凄い。
だからこそ、アルメニア人は柔軟で、したたかで、愉快なんだろう。
そして、過去からコウノトリなんだ。
でも、映画としてラストを一つに絞りきれずにどれも白昼夢となったのが残念だ。
そこがまたアルメニア。
それは、エンディング後のおまけの背景には、
日本の富士山の様な、
雄大なアララト山5,137mを故国と讃えていた情景がコウノドリ民族と彷彿させていた。
( ^ω^ )
アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓
ソ連統治下のアルメニアを舞台に、無実の罪で収監されたアメリカ人男性が、
牢獄の小窓から見える部屋に暮らす夫婦を観察することに幸せを見いだしていく姿を描いたヒューマンドラマ。
幼い頃にオスマン帝国でのアルメニア人迫害から逃れアメリカに移住したチャーリーは、1948年、自身のルーツを知るため祖国アルメニアを訪れる。
そこはソ連統治下にあっても理想の故郷のように思えたが、チャーリーは身に覚えのないスパイ容疑で逮捕・収監されてしまう。
悲嘆に暮れるなか、牢獄の小窓から近くのアパートの部屋が見えることに気づいた彼は、そこに暮らす夫婦の生活を観察しはじめる。
チャーリーは想像力を研ぎ澄ませ、まるで夫婦と同じ空間にいるかのように彼らと一緒に食事をし、歌を歌い、会話を楽しむようになる。
しかし夫婦仲がこじれて部屋には夫だけが残され、時を同じくしてチャーリーのシベリア行きも決まってしまう。
移送の日が迫るなか、チャーリーは夫婦を仲直りさせる作戦に乗り出す。
アルメニア系アメリカ人のマイケル・グールジャンが監督・脚本・主演を務めた。
ウッドストック映画祭長編映画賞・審査員賞など、世界各地の映画祭で数々の賞を受賞。
アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓
Amerikatsi
2022/アルメニア・アメリカ合作
(^_^)
アルメニア共和国はユーラシア大陸に位置し、黒海とカスピ海にはさまれた南コーカサスの国です。
アルメニアは、北にグルジア、東にアゼルバイジャン、南にイラン、西にトルコとそれぞれ隣接してお り、海の無い内陸国です。
首都は、エレバンです。
「アルメニア共和国」はアルメニア語では「ハヤスタン」と言います。
人の幸せを妬んでいる限り幸せにはなれない…
浅学にしてアルメニアの近代史について全く知識がありませんでした。
オスマン・トルコによる虐殺、ソビエト連邦による支配、
強国の都合で振り回される小国の国民たち。
けれどどんなところであっても故国は故国で、魂が帰るところなのかもしれません。
とにかく主人公のポジティブっぷりに圧倒されます。
痛めつけても痛めつけても幸福を見つけ出す主人公に苛つく悪役たちの気持ちも分からなくはないですが
人の幸せを妬んでいる限りいつまで経っても彼ら悪役たちが羨望し、憧れている幸せはかえって手に入れられないということが悲しくなります。
そんな理不尽な暗い状況を描いているのですが、大真面目なゆえに逆に愉快なシーンが背景設定の暗さを和らげる灯火となり、映画の雰囲気を穏やかなものにしています。
独房の模様替えを眺めているだけでなんだか幸福感に満たされました。
アルメニアを舞台にした映画を初めて観ましたが、エキゾチックな異国情緒が興味深かったです。
チャーリーとティグランの間に「言葉」はいらない
君をよくわかっているのは僕の方だよ
「アメリカッチ」という音の響きの可愛さに惹かれて見た。そんな軽い感覚で見始めたら、どんどん引き込まれ、声出してたくさん笑い、不安になり恐怖に陥った。それでもチャーリーの明るさとユーモアと想像力と前向きが、大きな幸福感と力をもたらしてくれた、自分でも驚く程の号泣の嵐を越えて。
アルメニアの色々な音楽、女声の歌が、痛くて寒くて空腹で理不尽で辛い心とからだを暖め続けた。音楽とダンスと笑顔と絵画と美しいアララト山(一瞬、富士山に見えた)のおかげで、不条理な世界、残酷な環境から、チャーリーと一緒に生還できた。安易な機械仕掛けの神様頼みの映画でないことは、チャーリーのその後の生き方でわかる。
世界中に散らばったアルメニア人に呼びかけた帰還プロジェクトのことを初めて知った。収容所でチャーリーと共に労働させられていたアルメニア人のおじいさんは、アルメニアの文化についてたくさん知っていてチャーリーに教えていた。私も教わった。
おまけ
1)映画「ANORA」でロシア人大富豪の息子のお守り役三人組のうち二人がアルメニア人で、そのひとりがカトリックの神父である理由というか背景を「アメリカッチ」を見て納得できた!嬉しい
2)チャーリーを演じたマイケル・グールジャン(監督・脚本・編集も!)の顔、特に目、そして口と鼻が、知り合いのドイツ人にとても似ていたから余計に感情移入してしまった。キビキビした体の動き、頭が良くて理系でユーモアたっぷりで手が器用!実用的な可動式ベッドや洗濯干しロープ有りの部屋(独房だが)などもその友人なら作りそう。向こうのお家でティグラン夫妻が何を話しているのか、想像で再現するファンタジー能力も似ていた!
傑作に近かった
全28件中、21~28件目を表示