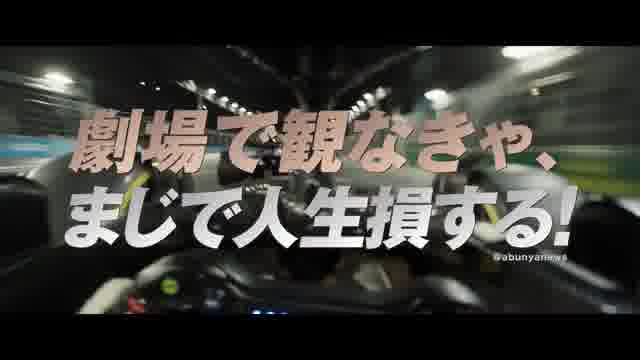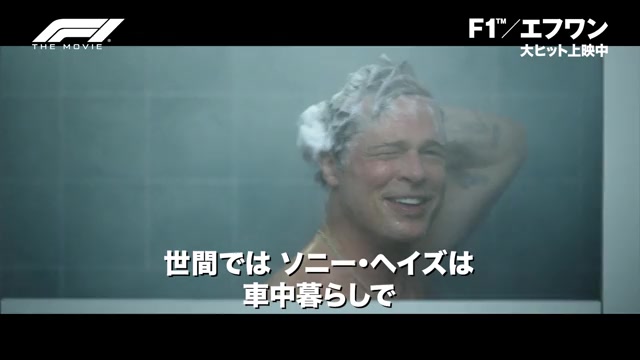映画「F1(R) エフワン」のレビュー・感想・評価
全676件中、121~140件目を表示
究極のイケメン。中身も
もう最高。ブラピに限らずそれぞれのキャラが、最初は「自分は自分の仕事するからお前らは口出しすんな」のスタイルだったのが一歩ずつ心開いたりして、でもまた一歩戻っちゃったりもしてもどかしい。3時間には感じなかったし、各レース「もう終わってしまうんじゃないか、まだ勝つなよ」と思い巡らせてしまった。地上版トップガンとの触れ込みだが、「Fly」するシーンもあるので、むしろ地上に閉じ込められるような描写ではない。あとIMAXを一番オススメする作品。
完全にデザインされた高品質エンタティメント
今、モータースポーツ界で最も人気の高いF1が全面協力し、さらに人気の裾野を広げるべく製作された完璧なエンタティメント映画。
トップガン マーヴェリックの監督のジョセフ・コシンスキー、プロデューサーのジェリー・ブラッカイマー、脚本のアーレン・クルーガーチームで製作されており、考え方はほぼ一緒で戦闘機をF1に置き換えた。安易とも言えるが確信犯的安易であり、内容は文句のつけようがないくらい面白いのだから驚く。
過去にその世界でトップを目指せると言われたヒーローが何らかの理由で挫折し、その世界から姿を消したのが、熟年になってカムバックし今の時代の期待の若手と確執しながら、実は経験と叡智で組織を蘇らせ、若手からも信頼を得る。そこに恋愛要素も盛り込まれる、という正に雛形通りのストーリーでありながら、退屈せず引き込まれ2時間30分があっという間というマジックのような映画なのだが、それはなぜなのか・・
まずはF1が全面的に協力する舞台設定の緻密さリアリティ、そして魅力的なキャラクター設定の緻密さ。とりわけソニー(ブラッド・ピット)のキャラクターはブラッド・ピットならではで、彼以外にこの映画の主役は考えられないくらいにはまっている。
旧友でチームオーナーのルーベン(ハビエル・バルデム)はF1ドライバー時代のチームメイト、若手レーサーのジョシュア(ダムソン・イドリス)は黒人でマザコンのファッショニスタ。チーフエンジニアのケイト(ケリー・コンドン)は元宇宙工学のエンジニアからの転職で離婚歴のある女性(イケオジの大好物)とメインキャラクターが作り込まれて魅力的なところがストーリーは単純だが感情移入できるのだ。
そして最大の魅力は惜しみない費用を注ぎ込んだ完璧な映像にある。実際のF1パイロットやスタッフ、実際のグランプリに乗り込んだリアルな撮影。本物のレーシングカーをピットが運転し撮影したレーシングシーンにVFX。
ハンス・ジマーによる大音量の音楽、ビートはさらなる高揚感をもたらす。
逆に言うと大画面と大音量でないと面白さは半減する。
たった500円ほどの追加で観れるので強力にIMAXでの鑑賞を推奨する。
しかし、戦略的にこうした映画を製作できるハリウッドはやはりエンタティメント製作に関しては頂点であることにゆるぎない。
トップガンとの違いはエモさ?
映画館の大きなスクリーンと音響で観てこその映画かな。
実にアメリカ的なてらいのない派手さ、わかりやすい対立からの和解とか予定調和だけどそれでも退屈しない。レースの場面はハラハラしながら観たし、運転席からの景色は、迫力満点。
トップガンマーベリックの陸上編といっていいと思うけど、比べるとやっぱりトップガンに軍配があがる。1作目から続くストーリーがあるぶん、こっちが不利かな。
空と陸がきたので次は海の乗り物?船?ヨット?じゃあ迫力に欠ける気するし、なんでしょうねえ。
面白かったが、現実離れした部分も。。
90年代はフジテレビで夢中になっていたF1ファンです。現在のF1は熱が冷めてNETFLIXで見ている程度ですが、最新のF1ドライバーやチームスタッフがそのまま出演しているのには驚きました。それなりに面白かったのですが、やや現実離れした部分があり、違和感が拭えませんでした。
野球で言えば、90年代にランディ・ジョンソンと投げ合った投手が、奇跡の復活を遂げてドジャーズの大谷やヤンキースのジャッジと戦う、その決め球がバットを避ける魔球の大リーグボール第3号、というような内容でした。
良かった
通常スクリーンで鑑賞
IMAXで見るべきだった!
見に行こうと思いながら遅くなり、IMAX上映を鬼滅などに取られてしまった(笑)。
とは言え、凄く良かった。
IMAXでなくても充分見る価値ありです。
トップガンも良かったが、自分的にはこちらの方が良かったので、★5をつけざるおえません。
ブラピ、トムに負けてませんね。
サーキットの臨場感、ヒューマンドラマ、よだれの出るマシンと風洞実験室などのテスト模様、あげればきりがない位良いとこだらけでした。
ハミルトンがアドバイザーになってるだけあってリアリティ感も凄かった。
でも、1番自分が共感できたのはソニーがほんとに走ることが好きなんだなーと伝わって来る所、自分もスピードの世界の端に居る人間として、音が無くなるとか一瞬が永遠にも感じる時があるとか、ジーンと来てしまった。
最後に出てきたバハ1000、懐かしいですね、エンデューロやってる頃さんざん見てました、ブラピがハンドル握ってるところから文字通り金じゃない喜びが痛いほど伝わってきました。
分かる人がいるのだろうか?
F1の轟音で暑気払い
ブラピ氏は直球ど真ん中の正統派ヒーローではなくてちょっと斜な役が好きなのかな。本作で演じるのはぶっちゃけ一時代前に終わってるおじさんドライバーだ。でも、ブルージーンズがほんとに映える、いなせな彼が演じると、さすらいのガンマン、というか、伝説のダークヒーローになる。ソニーのレース戦略はあまりに無茶なので、エンジニアの人達みたいに相当ハラハラしながら観た。
そして終わってみれば、暑い季節に熱いレース。乙な暑気払いだった^^
ブラピの「かっこよさ」を堪能
意外にリアル感がありました!
監督をはじめ主要スタッフは『トップガン マーヴェリック』と同じだけあって、カメラワークと音楽の迫力に圧倒されました。
「セナ、マンセル、プロスト、シューマッハと走った」という台詞から察せるように、50歳を超えたブラッド・ピット演じる元レーサーがF1に復帰するという、大胆な設定。ルールの裏をかいた奇想天外な戦略による、あり得ないようなレース展開の連続だったけど、実際のF1コースを使い、本物の現役ドライバーや監督が他チームのメンバーとして登場することで、意外な程にリアルさも感じました。
通常スクリーンで見たため、個人的にはF1マシンのエンジン音の“圧”をもっと体で感じたかったけれど、映像も音も、十分すぎるほどの迫力で楽しめました。
ハリウッド王道の安定した映画
ブラピ演じる老獪なドライバーと若手ドライバー、そしてチームの成長と成功の物語。恋愛やお色気ももそこそこに、テレビで流れても安心安全な出来栄え。
ブラピはジジィになってもかっこいい。見るだけでも目の保養になる。
緊迫感のある一人称視点のカメラワークや、爆音、そして疾走感を味わえるのは映画館ならでは。
クライマックスシーンでは「よしっ!」とつぶやく人が何人かいた。自分も思わず身を乗り出して、安堵とともに椅子をガタつかせてしまった。
そんな一体感を赤の他人と味わえたのも良かった。
ちょっと気になったのはF1のルールを知らない人が観たらどうだったのか。分からなくても何となく勢いで分かってもらえそうな気がするが、もう少し解説ターンがあっても良かったかもしれない。
トムクルーズ?いやいやブラット・ピットだって負けてない!
24時間の耐久レースのル・マンを描いた「フォードVSフェラーリ」
superGTのゲームから実際のプロレーサーになった実話「グランツーリスモ」
そして、今回最速速度300km/hを越える世界最高峰のレース「F1」の映画を、世界中を注目させた「トップガンマーヴェリック」のジョゼフ・コシンスキー監督が今度はブラット・ピットと挑む。
物語は・・・
元天才レーサーのソニーは、チームを持つ旧友との再会により一度去ったF1の世界に戻る。参加する最下位のエイペックスには才能あるが経験が浅いジョシュア共にチームの復活を目指す。
王道・王道・王道のストーリー展開にも関わらず、最高だった。
まずなんといっても、ソニー・ヘイズの人柄に惚れてしまった。
勝つためには手段を選ばず、乱暴で攻撃的な男に見えるが、プロ意識はずば抜けいる。
事前にレース情報を確認するのはもちろん、実際のレース場を歩き、走りコースの細かい特徴まで頭に叩き入れる。レースが終わった後は必ずクールダウンする。勝負もわがままなプレーに見えるが、ただ本当はチームの勝利を最も優先している熱い想いを抱える人物。
これをブラットピットが演じているだけで惚れてしまいます。
ベテランが若者に負けずに、派手な努力ではなく、地道な努力をする姿だけで応援したくなる。
相棒となるジョシュア演じるダムソン・イドリスも素晴らしかった。才能はあるものの、結果がでず、フラストレーションがたまり、焦っていく姿にヒヤヒヤさせられる。
ソニーと出会い、少しずつ変化する心情にも心熱くなっていく。
主演となる2人の魅力はもちろん、迫力のレース映像にも興奮させられる。
今回、F1全面バックアップのもと、実際のレース中にも撮影しており、世界各国のサーキットコースも利用とのこと。
マシン内からのカメラだけでなく、マシン外からの映像、どうやって撮ったの?って衝撃を受けたシーンなど、さすがトップガンマーヴェリックの制作チームだ!っと言いたい。
トップガンマーヴェリックではあり得ない無謀な挑戦にトムクルーズが挑み、見事にこなした最高の作品。
本作F1ではブラットピットが61歳には、これまた無謀な挑戦へ挑んだ。ブラピは事故やスピン以外はスタンドドライバーではなく自身で運転していたらしい。
プロデューサーに位置するあのルイス・ハミルトン自身「レース映画史上最もリアル。F1をなんとなくしか知らなくても楽しめる。」とのこと。
インタビューで監督曰く、既に続編の構想があるらしい。「観客が見たいと思うかどうかにかかっています」ってことなので、ぜひ続編も見てみたい!
Whole Lotta Love
全676件中、121~140件目を表示