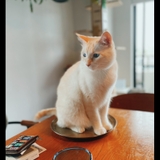夏の砂の上のレビュー・感想・評価
全128件中、41~60件目を表示
暑い
渇くことの厳しさと潤うことの大切さ
不思議な作品です。
生きることに疲れた男と、その家に預けられた姪の話。
二人とも、とことん不器用で生きるのが下手なんだが、絶望まではしていない。お互いに接点を持たないように生きていながら、共に暮らしていることで絆が生まれていきます。
渇水の長崎を舞台に二人の先の見えない生活が続きます。渇いた街の渇いた生活。
二人が少し前向きになったとき、ついに長崎に雨が降り、二人の微かな絆が確かなものになります。
男はいくつかのものを失い、姪は新たな街に旅立ち、二人の短い共同生活は終わりますが、それは二人のこれからをしっかり支えるものとなっていくでしょう。
何かが明確に起こるわけではなく、わかりやすい説明もない。それでいて見たことで心にしっかりと残る作品でした。
ミニマリズム文学? よくできた短篇小説のような潔さが光る佳作 でも時代感覚にはズレ
映画を観ている最中に私が30年ほど前に読み漁っていたレイモンド•カーヴァーの短篇小説群のことを思い出しました。その頃の私はこの映画の主人公 小浦治(演: オダギリ•ジョー)ほど酷くはないにしろ、公私ともドツボはまりの状態にありまして、当時の気分にぴったりだったカーヴァーの短篇を次から次へと読んでいたという次第です。
レイモンド•カーヴァーは1970-80年代に活躍したアメリカの短篇作家で1988年に50歳の若さで亡くなっています。日本には村上春樹が翻訳して紹介されました。アメリカの「立派ではない」人々の人生の断片を切り取って淡々と描写した短篇を得意としていました。彼の短篇にはこの映画の主人公の小浦治のようなドツボにハマってる人物もたびたび登場します。彼はミニマリズム文学の代表的な作家とされています。簡潔で直接的な表現で登場人物の日常生活や内面を淡々と描写しました。
この映画は戯曲が原作ということもあり、なんだかミニマリズムっぽい感じです。ちょっと閉塞感のある地方都市•長崎での、主人公とその周辺にいる人たちのある夏の日々が現在形で淡々と描かれてゆきます。
主人公の治はかなり酷いドツボはまりの状態にあります。息子を亡くし、職を失うというダブルパンチのあとに、妻の恵子(演: 松たか子)に逃げられて塞ぎ込んでいたら、妹の阿佐子(演: 満島ひかり)がやってきて彼女の娘の優子(演: 髙石あかり)をしばらく預かってくれないかと押し付けられる始末です。阿佐子と優子の年齢差からいって、阿佐子はいわゆる「ヤンママ」(「ヤン」は「ヤング」のヤンとも「ヤンキー」のヤンとも言われておりました。昭和末期の頃の流行語)のなれの果てといった感じで、男癖があまりよくない雰囲気も漂っております。私はここで治にとっては姪にあたる少女の名前「優子」に軽い違和感を覚えました。ヤンママの娘の名前が優子ってけっこう古風だな、と。あ、そうか、’80年代の始め頃にヤンママが生んだ娘なら優子って名前はありだよな、ということで、’90年代後半頃のお話かな……
実はこの映画の原作は1998年初演の戯曲です。ということで、90年代後半頃を舞台にしているらしいことは納得できます。登場人物の女性たちの名前が「…子」ばかりであることも、バブル経済崩壊後で造船業が不況に陥ったことも。ところが、映画のほうではスマートフォンが出てきたりして現在の長崎を舞台にしている模様です。なんだか30年前の物語をムリやり現在に移植した感があってそこだけが少し残念でした。
でも、私はこの映画の表現スタイルはけっこう好きです。今そこにある現在だけが頭から順に淡々と現在形で描写されてゆきます。説明的な回想シーンとか入りませんし、時間軸を弄ったりもしません。時折り優子の視点が入りますが、基本的に治の視点で余計な説明抜きで簡潔に直接的に表現されてゆきます。
あるドツボはまりの状況下にいる中年男のもとに、運命に弄ばれ漂流している感のある彼の姪がやってきて少しの間だけ時間を共有するーー両者にとってたぶん忘れることはないであろう、長崎でのあの夏の日々…… 人生の断片をスパッと切り取って余計な装飾を施さず、簡潔に描くーーそこによくできた短篇小説のような潔さを感じました。
長崎の街並みが美しい
雨が降らず乾き切った長崎の街を舞台にそれぞれの男女の人間模様を描いたヒューマンドラマ。主演と共同プロデューサーを兼ねたオダギリジョーと絶賛売り出し中の高石あかりの共演が見どころで雨のシーンが非常に印象的でした。長崎の街並みを映した景色も非常に美しく見栄えのする映像です。
2025-104
オダジョーさん、大丈夫か?
とても良かったです。
あれ程の短期間に、あのような出来事が立て続けに起こって、これからどうやって前向きに生きて行くか、オダジョーさん、本当に大変だと思いました。
鑑賞動機は松田さんの原作だからです。古い話ですが、黒木和雄監督との作品は大好きです。今作ももし黒木監督が生きていたらどんな演出をするのだろうかと、最初は考えながら観ていたのですが、直に玉田監督の演出に引き込まれました。
坂の演出が素晴らしいですね。室内シーンもロケでしか出せない生活感が漲っていました。
キャストはもちろんオダジョーさん、あの飄々とした佇まい、寂しそうで、無気力に見えて、でも優しくて、雨水のシーンの楽しそうな顔。やっぱり主演俳優はこうじゃなくちゃと言った感じです。
髙石あかりさんは、例のアクション映画は最初の1本でつまらなくてギブアップしたので主演級で観たのは初めてでした。なんか、危なっかしい演技が絶妙でしたね。おいおいおいおい、高校生がいいのかよ!? って何回も思いました。最後、「残れよ!」と感じたわたしはハッピーエンド支持者です。
松たか子さんは南果歩さんかと思いました。なぜあの佇まいだったんでしょうか。満島さんの作品は久々に観ました。篠原さん、とても良かった。最近は、欠かせない女優ですね。
演出では、「暑さ」を余り感じなかったのがどうかなぁと思いました。歩く、食べる、働く、喧嘩する、Hする(途中までですけど)、どのシーンも汗を感じませんでした(と言うか、汗かいてない。クーラーない設定でしたが)。意識的なんでしょうか。
いやー、でも長崎の街は魅力的ですけど住むのは大変そうですね。断水は日常的なんですか。旅行で行くなら寒い時期にします。
まとめれば、もう一度見たくなる素晴らしい作品でした。
「この映画を観ていていいのかな」何故か感じた焦り
カンカン照りの真夏の長崎を舞台に、心に様々な痛みや後ろめたさ、だらしなさを抱えた男女が交差するお話です。
一言で言えば「人のグズグズを描いた映画」なのですが、非常に丁寧に撮られていたと思います。俳優さんもそれぞれの思いの表現が細やかでした。人の心のそんなどうしようも無さを描くのは映画の大切な仕事の一部だし、僕はそんな作品が好物でもあります。でも、何故なのでしょう。
本作を観ながら、「国全体が大きく転がり落ちようとしている今、こんなにも狭い世界を撮る必要があったのかな」「それを観ていていいのかな」の疑問が拭い去れず、妙な焦りを感じてしまったのです。
「いや、そんな時代だからこそ個の心を見つめる作品が必要なのだ」
と制作者は考えられたのかも知れません。また、「今、こんなチマチマした映画を作って」という声は、ひっくり返せば「こんな時局にこんな不健全な映画を撮るなんて」という戦前の映画ファシズムの時代に繋がり兼ねないので注意が必要です。
一体、この作品の何がそう思わせたのでしょう。僕の個人的な心理状態を反映しただけなのかな。疲れているのかしら。
坂道を登って降りて、登って降りて……ふぅ。
どのように鑑賞すべきか迷ってしまう…。
酷暑続きで、家にいても暑すぎるので涼みに映画館に足を運んだ。
特にこの映画に思いれがあったわけではないが、心に刺さった作品。
どのように感想を表現しようかと迷ったすえに、映画・COMの解説を読んでしまう。
愛を失った男、愛を見限った女、愛を知らない少女…
なるほど、そのように鑑賞すればよかったのかと感じ入った。
男の身の上に降りかかる不幸の連鎖。5歳の息子を不注意から亡くし、誇りをもっていた職場は閉鎖、妻には見限られ、同僚の男に寝取られる。前職の親しい先輩の死。寝取られた同僚の妻からの罵詈雑言。新しい職場では、事故で指を三本も失ってしまう。そのうえ、やんちゃな妹の娘(姪っ子)を預かることになる。たんたんと描かれるけど、どれも精神に相当な負担がかかる出来事ばかり。自分ならどうだろうと思ってしまうが、オダギリジョーの演ずる小浦治は…。ほんとに人がいい。
100分あまりの映画では描き切れない部分は、鑑賞者の感性で補うしかないから、ぼさっと見ているわけにはいかず、小説なら、もっと、姪っ子優子と治の交流も書き込んでくれてわかりやすかったのだろうと思う。
松たか子の中年女性の疲れっぷりの演技は秀逸すぎて、一瞬だれだかわからない程。愛を見限った女に対する、愛を知らない少女の心の動きもとても興味深い。
少女が言う。こんな街をでてどこかへ行こう…。治の我慢し続けて来た感情の爆発。そこへ酷暑で雨が降らない長崎に、雨が降り、爆発した心情が鎮められ、きれいに流され、また新しい明日が始まる。新しい世界が開ける。
禍福は糾える縄の如し。他人がとやかく言うことではないし、自分にしかわからない世界、幸福があってもいいのである。
オダギリジョーがお子さんを亡くされていたことを後から知った。
長崎は今日も雨だった
わずかな心情の変化。そこから生まれる行動の変化。彼らの暮らしをやさしく見守っていたい。
延々と続く違和感の連鎖はどこへ向かう?
一つひとつのセリフや仕草が、役者のチカラで"絵"にはなっている。何らかの"雰囲気"はある
しかし、それらの間に脈絡は乏しく、その人物はなぜそう動き、そんな顔をして、そんな事を口走るのか、きわめて不自然で、シーンとしてはほぼ意味不明。というか、作り手にそれを分かりやすく説明する気がハナから全然ないことだけは途中からはっきり認識できました
そんな違和感の連続が延々とひたすら続く映画。いや、本当に映画なのかも定かでない感じがしてくる
ほぼ全ての人物が、日常の中で逃げ場のない抑圧の中にいることだけが共通点。そして、進んで感情移入したくなるような"好人物"はひとりも登場せず、ワクワクするようなシーンや状況も全く描かれない
途中から、これは何かの"実験"なのか?という気がしてきました
エンドロールで原作が戯曲であることはわかりました。舞台なら成立するのかな?コレ
主役のオダギリジョーさんが製作側にも名を連ねていることもわかりました。ということは、彼はこの役をはじめから納得ずくで演じている???
人間は理解できないモノを無意識に否定し、遠ざけようとする生き物です。娯楽である映画鑑賞に於いては、そうする自由はありますよね
というわけで、私はこの映画が好きではありません
淡々と描くこれからも続く人生
なんでもない誰にでも起こる人生での出来事。観ている時は単調に感じましたが鑑賞後長崎の風景やセリフなどを思い出します。
高石あかりさん奮闘。松たか子さん貫禄あり。光石研さんの九州弁が一番自然に見えました。オダギリジョーさんは演技が物足りなかったかな…
どうかこれから少しでもいい人生でありますようにとオダギリジョーさんの後ろ姿見て思いました。
高石あかりの予習と復習
松たか子、満島ひかり、オダギリジョー…
好きな役者の揃い踏み。
しかも先日見て大興奮した「たべっ子どうぶつ The MOVIE」でペガサスちゃんの
声優、来シーズンの朝ドラの主役を演じる高石あかりが出るってことで
とても期待して見に行きました
若い頃の宮﨑あおいに見えるときがある
この作品では あまり魅力がわからなかった
ちょっと前のミニシアター系のどんよりした
ストーリー展開で、少し古さを感じたけど
丁寧に作られていてこれはこれで良し~って感じ。
「少年と犬」の高橋文哉の演技パターンは
そのまま。
森山直太朗に似た役者に目を引かれた。
似てるなぁ~と思ったら本人だった
オダギリジョーのノープレスのリネンのシャツの着こなし!!
スタイリスト名 チェックしておこうと思う。
沁みた。烏滸がましくもオダギリジョーさんに自分を投影したみたい
映画館で見るともなしに見た予告編と映画館のポスター以外は、内容についての事前情報を得ずに鑑賞(まぁそういうことが多い)。ポスターにいる4人は皆さんとても好きな俳優さんなので、観ないという選択肢はない。今年だけで何度目よ?の光石研さんもいるのね…。
…沁みた。エンドロールまでは淡々と観てたのに、劇場内が明るくなったらどうやら心が動いていることに気づいてちょっと驚く。とりあえずパンフを買った(まだ読んでいない。これもあるある。結局読まないこともある)。映画館から新宿駅まで歩いているうちに込み上げてくるものが。かなり驚き。自分が乾いていることを自覚した。
50を過ぎて作品中の人物と自分を重ねるようなことがほぼなくなっていて、そんな見方をすることすら忘れていたし、この映画も観ているときに共感共鳴しているわけではなかった。ところが、終わってから1分2分と時間が経つごとに映画の描写が、オダギリさん演じる小浦治の心情が思い浮かんで、じわじわと心に浸透してきた。楽しそうに行き交う人をよけながら一人歩く新宿東口界隈の景色が滲んだ。
主人公の年代、姪っ子という存在、兄弟との関係性、夫婦のかたち、失った仕事、労働意欲、海が近くて坂がちな田舎町、その田舎町の狭い人間関係…自分の過去と現在の状況が時系列や程度は違っても多くの要素で重なっていることに思い当たる。いやー、オダギリジョーさんに自分を投影するなんて烏滸がましいぞ🤛💢
オダギリさんと髙石あかりさんが、それぞれ不思議で微妙な感情を持つ人物を本当にうまく演じていたと思う。クライマックスの待望の雨のシーンについては、優子が鍋やたらいを並べる場所がそこなの?で、あそこで溜まった水なの?という疑問が浮かんでしまったけど、そこは目をつぶって、その後の居間でのあのシーンの素晴らしさ!あれは現実だろうが心象描写だろうがそんなのはどちらでもいいって思えるくらいの名シーンだった。
ラストの別れは、そう来るよねって思ったので、意外ではないけどやっぱり好き。
誰もが好きと言うような作品ではなく、誰にでもおすすめできる作品ではないのかも。人を選ぶ分、選ばれた人間には、深く沁み込む作品だと思う。
雨うまかあ
丁寧に紡がれる時間
全128件中、41~60件目を表示