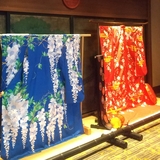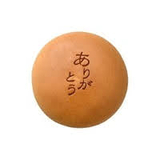ルノワールのレビュー・感想・評価
全154件中、41~60件目を表示
不穏な空気がずっと続く
観客にとって面白い映画と映画祭で評価される映画は全く違う。
この作品の不穏な空気や違和感は賞を取った者故の審査員への忖度の結果なのかもしれないと思ったり思わなかったり。
とにかく主人公の感情はチラホラ見えるが本意はわからない。
愛を知らないから愛せないのか、
愛を知らないから愛されたいのか、
愛を知らないから試したいのか、
愛を知らないから壊したいのか。
まったくわからないまま話は進んでいく。
まったくわからないから絵作りの昭和のディテールへの病的なこだわりに目が行き、主人公が橋を颯爽と漕ぎ渡る自転車の「昔オカンが乗ってたやつ」との完全シンクロに脳みそをぶん殴られる。そんな映画でした。
とにかく導入の夢のシーンからもう本当に胸糞悪い気分でそのまま最後まで行ってしまった感じ。
ポスターの多幸感と実際の内容がここまでかけ離れてるとそのシーンが映された時の驚きと違和感は半端ないな。
取り留めないけどこんな感想の映画もあるよね。
あと大好きなベンジー出てた!やっぱ彼のダメ男役最高だ!
それではハバナイスムービー!
空虚をまとう「芸術風」への怒り
私はこの映画を全く評価しない。最大の問題は、この映画が観客の知性や感性をまるで信頼していないことにある。題名は「ルノワール」。しかし、その名が意味する絵画的背景や人物像、芸術思想に踏み込む描写は極めて乏しく、ジャン・ルノワールの絵画を父の病室に飾る、ただそれだけに等しい。それは“ルノワール”という看板を借りた、まやかしのブランドにすぎない。
確かに、演出は一見「印象派的」だった。だが、そこに明確な意図や構造美があったとは到底言えない。無音とノイズを用いた場面転換は単調で、リズムの変化も読めてしまう。演出意図が透けて見えるほど浅く、むしろ想像力を萎えさせる。物語も問題だらけだ。起承転結がなく、一貫性も欠けている。自由奔放な少女の心象世界を描くためにあえて構造を破壊したのだとしても、それが成立しているとは思えなかった。類似の構造を持つ作品「怪物」は、あどけなさや危うさを描きながらも、大衆映画としての体裁を保っていた。この映画はそれすら持たない。終盤の“家出”が夢オチであるという演出も、明確な伏線や文法的示唆がなく、観客の理解に委ねすぎている。たまたま私には読み解けたが、同行した母は「どうやって帰ってきたの?」と私に尋ねた。そこに対し「夢オチなんだよ」と説明することはできたが、それは観客に課すには過酷すぎる読解の強要だった。加えて、時代設定にも整合性がない。1980年代という設定の中で、「コンプライアンス」や「パワハラ」への言及が登場するのは、あまりにも安直な現代性の押し込みである。まるで時代に対する理解や敬意が感じられない。
私がこの映画に向ける怒りは、ただ「つまらなかった」というような感情的なものではない。これは映画という形式に対する冒涜だ。映画は芸術であっていい。しかし、同時に「娯楽」としての顔も持っている。観客がいてこその映画であり、独りよがりのオ○ニー作品を観客に強いることは、「映画」という形式そのものを裏切る行為である。私はこの作品を見ている間、ひどい前衛音楽のコンサートに閉じ込められたような、不快さを覚え続けた。形式に酔い、意味を殺し、感性を麻痺させるその手法は、もはや虚飾でしかなかった。仮にこの映画が賞を受賞したとしても、私はその審査員やその賞の価値を疑わざるを得ない。なぜならこの作品は、賞を得るために「らしさ」に全振りした、空疎な模倣品にすぎないからだ。
「意味はなく、その時間を感じるだけの映画」その時間は私にとって、ただ無意味な苦痛でしかなかった。
懐かしき時代
かわいい
198✗
響かなかった
長かった〜という印象でした。
いろんなエピソード(制作側が入れたいこと全部)が繋がることなく、並べられている感じで⋯
私の心には響いて来なかったです。
伝言ダイヤルのパートも出来事だけだし、他のパートも人の心の機微が見えない。
フキなどは、大人が作り上げた子どもを演じている感じが強くて、ナチュラルじゃなかったんだよなぁ⋯。
円卓のが面白かったなー、とか比べるところでもないけども、なぜか思い出してしまいました。
あと、なんか嫌だなーと思う人が多くて⋯
お父さんの部下とか、お母さんに薬を買わせる人とか、伝言ダイヤルの男とか⋯
って、全体的に、みんなのキャラが薄いのかも⋯
11歳の子どもの父親は、もう少し若いほうがリアルだなぁ⋯と。
リリーさんは、おじいちゃんにも見えなくもないのよ。
石田ひかりさんは、良い感じに歳を重ねてらして⋯
お母さん役もっとみたいかもー。
少女から大人への間の光と影
少女から大人へ移ろう瞬間の日常を光と影を織り交ぜて繊細に点描する、「PLAN75」の早川千絵監督の長編2作目。2作連続で今年のカンヌ国際映画祭出品作品となった。
11歳の少女フキ(鈴木唯)は発想豊かで個性的な小学5年生で周囲からは少し浮いている。
末期がんで余命わずかな父親(リリー・フランキー)と管理職で忙しくいらいらしがちな母親(石田ひかり)の間で比較的放任され自由に育っている。英語教室で出会う裕福な家庭の同級生、過去を抱える同じマンションの女性(河合優実)、母親が通うセミナー講師(中島歩)、伝言ダイヤルの男性(坂東龍汰)などとフキのエピソードが点描される。
どのエピソードでもフキは奔放で配慮がない。それは純粋さと無意識の残酷性を併せ持ったこの歳頃の少女特有のものとして瑞々しく描かれている。
オーディションで選ばれたフキ役の鈴木唯は観ていてハラハラするようなシーンを伸び伸びと演じ切っていて驚く。
時代背景の80年代後半は携帯電話もスマホもインターネットもない時代。超能力やUFO、心霊現象や怪しげな健康食品など怪しげなもので溢れ、嘘と事実が混濁しどこかしら牧歌的な時代であった。フキの奔放さはこの時代背景だからこそ引き立つ。
そして「ルノアール」というタイトルは早川監督が映画のイメージを限定させないために、あえて物語と関連性がないタイトルを付けたと語っているが、フィルムルックなコントラストの映像といい、フキが自転車で駆け抜ける広々とした郊外の川沿いの夕景など、屋外の情景を光と影で描いた印象派を想起するものとなっている。
監督の評価は保留にしたい
かなり難しい。上映中から大いに頭を悩ませた。
この映画の作者が何を言いたいのか、何を訴えたいのかはぼんやりとわかったつもり。それを言葉にしてこのレビューに残そうと思うといろいろと悩んでしまう。それが難しいと言った点。
ぶっちゃけで言ってしまえば早川千絵監督の個人映画であり、今の自分自身の残しておきたい映像を鈴木唯の姿を借りてフィルム(現代はフィルム撮影ではないよというツッコミはさておいて)に残せたわけだから、その意味でこの作品は大成功。どこのどんなツテを使ったかはわからないがそれがカンヌまで届いたのだからこれまた成功。過去にこんな手法で世に出た監督がいたなぁと思ったら河瀨直美の顔が浮かんできた(苦笑)。
彼女同様に早川監督は「撮れる」という評価はできるが、観客にどう伝わるかという考察が足りないのではないか?だから商業的に見ると当たり外れが大きい。最後まで僕を椅子に繋ぎとめておいたのはティーザーにも使用された楽しそうに踊るカット。これが最後の方にちょっとだけ出てきて、その印象だけで映画が終わる。論理に裏付けられた思考がないから論理ではなくただの印象だけで「良かった」「悪かった」と論じるしかない。それはこちら側も問題かもしれないが正直に。
全体を見るとここでも指摘の通り「お引越し」や「こちらあみ子」などの影響も感じる。もっとも「お引越し」は古すぎてこちらの記憶も定かではないすまん。
唯一、おそらく誰もが指摘するであろう技術的短所が整音だ。BGMがセリフに丸かぶりしたりきちんと拾えていなかったり。これは日本映画共通の弱点ではあるが今回は顕著だった。どうにかならないのかな。
ともかく、自己顕示欲丸出しのような今回の作品でも一定の評価は得たわけだから、早川監督には「伝える」技法をもっと研鑽していただき、真の評価は次の作品まで待ちたいと思う。
どう読み取るか
共感するしない。
それは正に個々の思考の問題であって、相違があれば焦燥感や孤独感・痛みを味わい不安に駆られ、合致すれば歓びや哀しみを共有し安心感・幸福感をもたらす。
その最たるものが、エンディングでのフキの微笑みであり、催眠術であり、伝言ダイヤルであり、森のくまさんだったのでは。
多感な時期を過ごすフキ。その心の移り変わりを唐突に場面転換で表現していると思うと、一見、脈略ない転換に見えるが腑に落ちる。
そして、その対局にあるのが父圭司。
死という現実を突きつけられ、向き合い受け容れる。ただ死という一点だけを見つめて病室で過ごす日々。
人は目まぐるしく思考している。その思考の中で立ち位置を探し、もがき苦しむこともあれば歓喜することもある。
「幸福の画家」と呼ばれるルノワール。
それをタイトルに持ってくるあたりも巧妙。
いろんな要素が鏤めてあり、なかなか欲張りさんの物語。
それこそ思考が重なり合えば、こんなに奥深い作品はないだろう。
難しい。
感受性の豊かさに共感
自分を客観視するのは難しい
風変わりな小学五年生の女の子の話。
2022年公開の『こちらあみ子』っぽい。
あみ子は自分の行動がどういう結果をもたらすかわからずやってるけど、フキはある程度わかってやってると思うので、こちらの方が悪質(笑)
自分が不遇な環境に置かれた状況を想像して作文に書いたり、友達の家族の秘密をそれとなく伝えたり、伝言ダイヤルに興味をもったり…
子供なのもあって、フキに何か起こることは少ないけど、大学生との交流はかなり危険なことに。
フキ以外の家族がまともかというと、それぞれ秘密を持っていたりして、みんな他人に厳しく自分に甘いのだなと思う。
描写が最小限なので、よくわからない部分もあったけど、フキの視線で見る大人の世界が面白いので、そういうのが好きな人なら。
配役について、リリーフランキーが父親に見えない。おじいさんかと思っちゃった。
徒然なるままに‼️❓よじれた心のちびまる子ちゃん‼️❓
ただ一人、いつまでも生きていてほしいと願う人
オープニングから衝撃的な展開で始まるのは、早川千絵監督の前作『PLAN 75』と同様。
映画全体を通して説明は最小限に抑えられているが、観客がその意味を想像できるよう巧みに作られており、個人的には好みの作り。
舞台は昭和末期だが、女子たちが黒魔術に夢中になる様子を観ていて、かつて流行した「こっくりさん」を思い出した。
予告編を見た際、「“哀しみ”を知り、少女は大人になる」というメッセージから、2015年のピクサーアニメ『インサイド・ヘッド』と類似したメッセージを感じた。
しかし、実際に鑑賞してみると、その印象は異なっていた。
『インサイド・ヘッド』が「哀しみ」の必要性を描く一方で、本作は少女が「哀しみ」を初めて知るまでの過程を描いていた。
本作には、大きく分けて二つのテーマがあると感じた。
一つ目は、『PLAN 75』でも描かれた「年寄りは早く世の中から消えてほしい」という世間の風潮について。
リリー・フランキー演じる主人公フキの父親は、末期癌を患いながらも生きることを決して諦めない。
あらゆる治療法を試し、闘病中でありながらも仕事に励み、社会復帰を諦めていない。
しかし、映画が進むにつれて、周囲の人々の思惑が異なることが明らかになる。
妻や仕事の同僚からは表面上は励まされているものの、その内心では見捨てられていることが見て取れる。
この事実が判明してからは、父親の必死に抗う姿がより一層切なく胸に迫る。
そのような周囲の人々の思惑とは裏腹に、フキだけは言葉にはせずとも、父親にいつまでも生きていてほしいと心から願っていることが伝わってくる。
暇を見つけては病室へ赴き、父親に寄り添うフキ。
ある時、父親が急遽自宅に立ち寄ることになり、部屋の明かりをつけた際に壁に吊るされた喪服を見て愕然とする。
その様子に気づいたフキが、そっと部屋の明かりを消す場面では、思わず胸が締め付けられた。
フキと父親が遊園地で過ごす場面で、父親が一人ベンチでぐったりしていると、数名の若者が父親をからかい始める。
この光景は、2021年の西川美和監督作『すばらしき世界』に登場する、介護職員が患者を陰で嘲笑する戦慄の場面を彷彿とさせた。
その時、フキが取った行動には「いいぞ、もっとやれ!」と心の中で喝采を送ってしまった。
もう一つのテーマは「小児性愛」について。
河合優実は『PLAN 75』でも印象的な脇役を演じていたが、本作でも前作とは全く異なる雰囲気で登場。
彼女の登場シーンは短いながらも、この映画では珍しく長台詞があり、彼女の台詞を要約すると「どんなに愛する夫であっても、小児性愛者と判明したら、気持ち悪くて無理」というもの。
今年公開の『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』でも河合優実の長台詞は出てくるが、社会的メッセージとしてはこちらの方が強烈。
舞台が昭和末期のため、出会い系アプリの代わりに伝言ダイヤルが登場。
フキが興味本位で吹き込んだ「小5…」という短いメッセージに男が食らいついてくる様子は、2021年にチェコで制作された衝撃的なドキュメンタリー『SNS 少女たちの10日間』を想起した。
近年、未成年の少女を自宅に連れ込み逮捕される男のニュースを頻繁に目にするが、本作の後半の展開はまさにそれを映像化。
そうしたニュースが報じられた際のヤフコメを閲覧すると、男側に言及する意見は少なく、大半が少女やその親を非難する内容ばかりであることに、毎回驚きを禁じ得ない。
そのたびに、「本来ならば男側が大問題であるはずなのに、なぜこれほどまでに男側に甘いのか」と感じてしまう。
「おそらく、ヤフコメに書き込む層の中には、少女を自宅に連れ込みたいと考える人々が多いのだろう」と勝手に推察。
被害女性やその親を非難する人々は、この映画の後半の展開を観ても、被害者側を叩こうとするのだろうか?
全154件中、41~60件目を表示