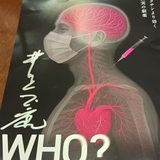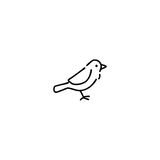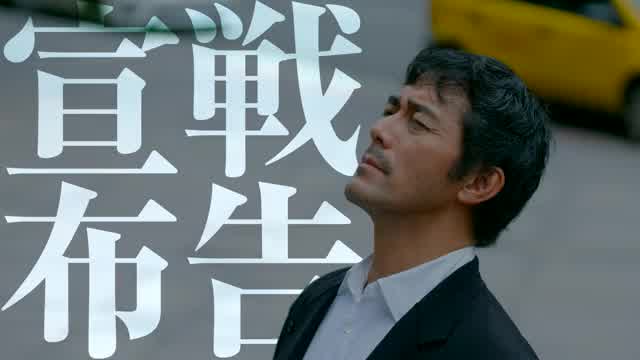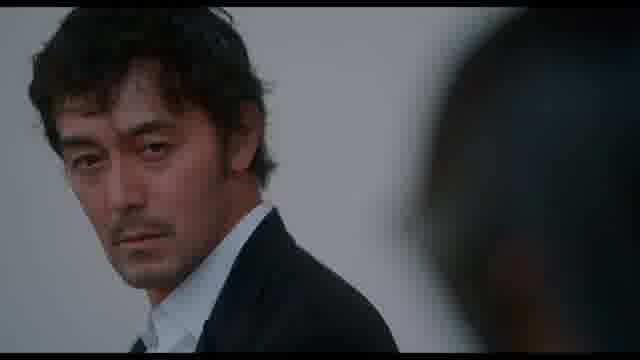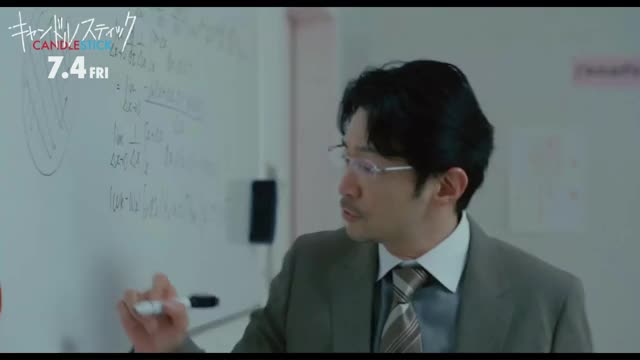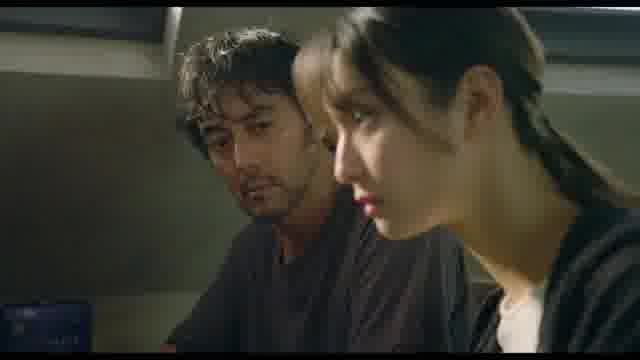キャンドルスティックのレビュー・感想・評価
全52件中、1~20件目を表示
粗削りな意欲作の割に俳優陣がかなり豪華。国際合作の新たな可能性も
日台共同製作で、日本、台湾、イラン、ハワイを舞台にストーリーが展開する、なかなかの意欲作だ。メディア向け資料によると、「従来の製作委員会方式などから離れ、“インディペンデント×メジャー”の形を志す製作会社ジャズインベストメントによる新たな映画ファンド」。ジャズフィルムのチーフプロデューサーである小椋悟が脚本も担っている。FXを題材にしたノウハウ小説を原作とし、大胆にアレンジしたストーリーだという。
キャストも、阿部寛、菜々緒、サヘル・ローズ、津田健次郎となかなかに豪華。台湾のアリッサ・チア、リン・ボーホン、タン・ヨンシュー、イランのマフティ・ホセイン・シルディら外国のキャストも、日本での知名度は低いものの自国では人気の俳優のようだ。コロナ禍の影響で撮影は各国で個別に進められ、俳優たちの国際的なコラボレーションは少ないものの、オンラインビデオ会議などを活用して国ごとのエピソードをうまく繋いでいる。コロナの時期にビデオ会議が普及し、国際合作の作り方や見せ方の可能性が広がったことを確かに示す映画と言えるだろう。
長編映画デビューとなる米倉強太監督による映像のルックも悪くない。ただし、FXとハッキング、大きくくくれば金融とハイテクを題材にしたサスペンスドラマなのに、作り手の知識不足や事実誤認によってストーリーに真実味が欠け、多少なりとも金融やテック系の知識がある観客にとっては興ざめするエピソードや描写があるのがもったいない。
特に気になった点を挙げる(ここからネタバレ含みます)。
1. 2014年の株価操作に野原らと関わった元同僚でハワイ在住のハッカーが言う「当時はネットの法律もないし厳密には犯罪じゃない」
→事実:不正アクセス禁止法が2000年から施行されており、野原らが外部のシステムにハッキングを仕掛けて(=不正にアクセスして)株価を操作したなら、2014年時点でも違法。
2. ハワイから日本へ急いで大金を送るよう要求される場面で、「国際送金はどうしても数日はかかる」
→事実:ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)を買って送金すればほぼリアルタイムの受け取りと換金が可能(相場による多少の価格変動はあるにせよ)。仮想通貨取引は世界で2010年代初頭から、日本でも2014年頃から普及しており、金融に明るい彼らが2019年時点で仮想通貨での送金を考えないのは不自然。
3. 野原によるFXハッキング作戦の説明:フェイクニュースをネットに流しFX投資プログラムAIを騙して円安にする(この時点で「円を買う」よう野原は杏子に指示する)。その数秒後に先のニュースが誤報だったと流して円高にする(ここで円を売る)。FXの取引画面では、(米ドルとの為替相場が)110円台だったのが107円台になり、その後115円になる。
→事実:円安局面では1ドルあたりの円の交換レートは増え、円高局面では逆に下がる。つまり、110円→107円は円高進行、107円→115円は円安進行なので、野原の説明と真逆。杏子が実行したように、1ドル=107円のタイミングで円を買い、1ドル=115円のタイミングで売ったら、実際は損をする。
つまり、素人や初心者が勘違いしがちなポイントなのだが、外国為替相場とはA国の通貨とB国の通貨を売買する時の相場であり、ドルと円の取引でドルを基準として考える場合、円の価値が上がると円の額面上は下がり(2010年に80円台で超円高だった)、円の価値が下がると額面上は上がる(ここ最近は140円台で超円安と言われている)。別の表現で説明すると、1ドルを買うのに140円かかるのと、1ドルを買うのに80円かかるのでは、後者のほうが円の価値が高い(=円高)ということ。野原の説明と画面上の描写を一致させるなら、フェイクニュースの影響で110円→115円と円安になり(ここで杏子が円を買う)、その後115円→107円と円高になる(ここで円を売る)とすべきだった。
4. 野原がリンネにリベンジするため仕掛けたトリックとは、USBメモリに仕込んだ隠しプログラムでリンネの「PCの時計を10秒遅らせる」というもの。「だから叔母さんがキーを押した時には 現実には10秒遅れていた」とルーは説明する。
→事実:FX取引のシステムはFX取引所を運営する会社のサーバの時間に基づいて稼働しているので、クライアント(ユーザー)側のPCの時計がずれていようが、取引画面にもキー操作にも影響しない。だからもし、実際に野原がリンネに10秒遅れの取引をさせるつもりなら、FX会社の取引システムを稼働させているサーバをハッキングし、取引システムがリアルタイムの相場より10秒遅れのデータをクライアントに送るようにするプログラムを仕込む必要があった。
3や4などは特に大事な部分だが、そこでの初歩的なミスはいただけない。金融系とテック系の監修をつけていたら防げたはずで、残念に思う。とはいえ、粗削りながら国際合作の新たな可能性を示すことができた映画でもあり、課題や反省点に真摯に向き合って将来の製作につなげてもらいたいと期待する。
サヘル・ローズがそもそも胡散臭い
2025年映画館鑑賞72作品目
7月15日(火)シネマ・リオーネ古川
ポイントカードデイ1400円
監督は今回がデビュー作となる元モデルで映像作家の米倉強太
演出スーパーバイザーに『ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影』『七瀬ふたたび』『ぼくが処刑される未来』『VAMP』『劇場版 シルバニアファミリー フレアからのおくりもの』で監督を務めた小中和哉
脚本は『幸福の鐘』『下妻物語』『魍魎の匣』『七瀬ふたたび』『ラビット・ホラー』でプロデューサーを務めた小椋悟
女に裏切られ逮捕された大企業のプログラマーが出所後また同じ女に儲け話を持ち込まれまた騙されるふりをして逆に騙して復讐する話
国際的な作品
海外映画を観てるようでやっぱり邦画作品
炎上ではない阿部寛
今回の菜々緒は地味な雰囲気
菜々緒の祖母好みの菜々緒ではなかろうか
共演したヒゲ野郎面々が濃すぎるだけかもしれない
菜々緒といったらドSなキャラの方が好きだけど
特にバイプレイヤーズの劇場版で古風な映画監督コスプレをしていた濱田岳にツッコみまくるところとかたまらない
全体的に人物の設定に無理がある
教会の牧師として孤児院を営みながらプロレスラーをしている人も世の中にはいるし無理が通れば道理が引っ込むので致命的欠陥とは言えないが
だがそれでも説明不足な面もあるしいかがなものか
熟練した売れっ子脚本家に頼めなかったのか
自分はFXなんて全く知識がない
FXを全く知らない人々でこんな映画を作ってしまった
そう言えば『キャプテン翼』の原作者高橋陽一はサッカーなんてあまり知らないのに漫画が大ヒットしたわけだからFXが理解できていなくても問題ないのかもしれないが
全体的に評価はとても低い
現時点で2.2
それもまた仕方がない
FXに詳しい人なら耐えられる内容ではなかろう
自分はFXの知識が無いに等しいのでそこそこ楽しめた
物語を楽しむうえで教養が邪魔になる時はしばしばある
バカで良かった
裏切りは女のアクセサリーとルパン三世は名言を残すが逮捕され刑務所暮らしで目の下にやつれがあってはサマにならない
その点では峰不二子は逃げ足が早い
ずらかるのも仕事のうちと彼女は心得ている
野原賢太郎の愛車のナンバーは1696
日本語が殆ど喋れない人がちょっと日本語話すだけでなぜか親しみが湧く不思議
トーマス・オマリーのヒーローインタビューも同様
サヘル・ローズといえば外国人犯罪に対する一部民衆の不安や怒りである
怒りの原因の殆どは理解不足でありそういった方々に上から目線で苦言を呈したり頭ごなしに激怒してみたりすれば当然のことながら逆効果になることを東京のインテリたちはなぜ気づかないのだろうか不思議でならない
炎上商法だとしたら嘆かわしい
組織に染まることが出世の糸口なんでしょうか
明治大学は身内の出身大学で親しみがありそれを思うと残念で仕方がない
あの痛ましい殺害事件で加害者側に共感する者たちに作家の岩井志麻子が大胆にも寄り添う発言をしたがそれでだいぶ収束したことを思えばTBSの対応は誤りであり火に油を注ぐ行為であり知的なようで全く知的ではない
その時の記事の写真の岩井志麻子には失笑だけど
配役
前科持ちの天才ハッカーの野原賢太郎に阿部寛
FXトレーダーの杏子に菜々緒
「夜行ハウス」の職員でモデルのファラーにサヘル・ローズ
「夜行ハウス」の園長でFXセミナー講師の吉良慎太にYOUNG DAISに吉良慎太
イランのハッカーでファラーの友人のアバンにマフテェ・ホセイン・シルディ
杏子の元夫で数学者の望月功に津田健次郎
日本企業を買収した台湾の大企業の副社長でホステスから成り上がったリンネ・ライにアリッサ・チア
リンネの15歳の娘で父を自殺に追い込んだ母を恨んでいるメイフェンにタン・ヨンシュイ
リンネの甥で賢太郎とは友人で同じ職場の同僚だったルー・ウェイシンにオースティン・リン
ルーの部下にクン・リンユァン
賢太郎の元部下でハワイ在住のシステムエンジニアのロビンにデイヴィッド・リジッズ
同居しているロビンの母にインゲM
国税局の捜査官の鈴木なつこに夏井世以子
鈴木に同行した国税局の捜査官の福田に間根山雄太
杏子と契約する不動産屋のMIOKO
看守の小関にイザベル矢野
夜光ハウスの子供達にラド・ドルサ
夜光ハウスの子供達にネザモルアルサラミ・パルナズ
夜光ハウスの子供達にコナ
夜光ハウスの子供達にサイドラヒ・アリアン
夜光ハウスの子供達にネマトラヒ・メヘラド
夜光ハウスの子供達にタジック・アリア
次々に場面展開するけど、テンポが良い!
先見の明あり
この作品、おそらく一年以上前からの撮影で、脚本はそれよりさらに前。相場の荒れや、イランロケを入れるなど、今に通じる点が織り込まれ、製作陣の先見の明に関心した。少しだけFXや株をやったことがあるが、美しい曲線とは、上から短期線、中期線、長期線のもとで上昇トレンドを描くチャートのことだと記憶している。映画は説明の代物では無いので、想像するしかないが、美しい曲線の有り様を少し説明してくれると(野暮かもしれないですが)フックが出来てさらに面白く見られたと思う。ただ、目を皿のように見開いて物語を辿って行くとなかなか面白い。私が好きだったのは最後、阿部寛と菜々緒のシーン。セリフの音量を敢えて大きくしなかったところが洒落ていて心憎い演出だった。若い映画人に声援を送りたい。
個人的には好きな終わり方
キャラ渋滞問題とストーリーテリングが最悪で、FXの演出もファンタジーで救いようがない
2025.7.10 一部字幕 T・JOY梅田
2025年の日本&台湾合作の映画(93分、G)
原作は川村徹彦の『損切り:FXシミュレーション・サクセスストーリー』
ハメられた天才ハッカーが復讐のためにある計画に参加する様子を描いた金融系スリラー映画
監督は米倉強太
脚本は小椋悟
物語の舞台は、2019年5月の東京・兜町
かつてホワイトハッカーとして活躍していた野原賢太郎(阿部寛)は、株価操作の疑いで逮捕され、懲役を終えて出所していた
彼には恋人の杏子(菜々緒)がいたが、彼女は数学者・望月功(津田健次郎)の妻だった
望月から呼び出された野原は、そこでコップの水をぶちまけられるものの、望月はこの闘争は終わりだと告げた
杏子はFXで生計を立てるためにセミナーに参加していて、そこで野原と出会うことになった
杏子は「数字に色が見える」という「共感覚」の持ち主で、野原にもその特性があった
その後、関係が深まったのちに、望月との確執が生まれるようになったのである
一方その頃、杏子が通うセミナーの講師・吉良(YOUNG DAIS)は、自身が経営する施設「夜光ハウス」の資金繰りに窮していた
仲間のファラー(サヘル・ローズ)とともに孤児たちを育てていたが、国税局の査察によって解散に追い込まれそうになっていた
一攫千金を狙ってFXに投資をする吉良だったが、想定外の動きに全財産を失い、途方に暮れることになったのである
映画は、出所した野原の元に、かつての同僚で今は台湾で起業しているルー(オースティン・リン)から連絡が入るところから動き出す
ルーは叔母のリンネ(アリッサ・チア)からある計画を打診されていて、そのために野原のハッキング能力が必要だった
一緒に働いていたSEのロビン(デヴィッド・リッジス)も加わるものの、「AIを騙すためのプログラム」は難航を極めていた
彼らの計画は、AIにフェイクニュースを感知させ、それによって不穏な売買が起き、それが修正されるまでの10秒を狙うというもので、そのプログラムはイスラム圏では正常に反応しなかった
そこで、ロビンはイランの友人アバン(マフティ・ホセイン・シルディ)に協力を要請するのだが、彼は友人のファラーが金策に困っていることを知っていた
そこで、ロビンたちに協力する代わりに金銭を要求することになり、ファラーもその計画に参加するようになる
さらに、野原は杏子にもその計画を打ち明けていて、彼女にもレバレッジ500倍の取引をさせようと考えていたのである
映画は、FXの知識があると困惑する内容で、劇中では円安になるフェイクニュースを流すと言っていたと思う
だが、チャートは下落(円高)の方に動き、その落ち切ったところでドルを買って、上がりきったところで売るという演出になっていた
円安になったところを捉えるならば真逆のチャートになると思うのだが、そこはドル円ではなく円ドルのチャートだったかもしれない
だが、実際の映像では「チャートの下落が107円20銭ぐらいで、それが反発して113円ぐらいになる」というチャートだった
これは110円ぐらいだったレートが一旦107円まで円高になって、その後AIがニュースをフェイクと判断して、正常値に戻そうとするものの、113円まで反発して円安に振れたというものだった
なので、フェイクニュースによって「円高に作用した」というものなので、真逆のことが起こっていると言える
さらに言えば、FXのチャートを見たことがある人ならばわかると思うが、おそらくあのチャートは1分足(10秒の取引のために日足を使う人はいないと思う)のようなスケールの小さいものだった
それまでの動きというものは20〜30銭ぐらいの値幅で折れ線になっていたが、一気に値幅5円の動きが出ると、それまでのローソク足はスケールが一気に変わるために「ほぼ直線」になってしまう
雇用統計などで1円動くだけでも心電図フラットみたいなチャートになってから噴き上がる(あるいは奈落)になるので、それまでのローソク足の動きが残ったまま表示されることはない
このあたりの雑な演出を見ていると、FXをやったことがない人が作ったんだなあと思ってしまった
ラストでは、リンネを嵌めるために「彼女のプログラムに10秒だけ遅延させて表示させる」みたいな暴露があり、さらに横領に関しては娘のメイフェン(タン・ヨンシー)が行ったみたいなことが描かれていた
10秒だけ表示を狂わせるというのはほぼ不可能なテクニックで、取引ツール全体を偽装しつつ、リンネが取引できる状況を作らなければならない
FXには契約しているところが発行している取引ツールを使うことが一般的なので、そのサーバーをハッキングして、偽の取引ツールを表示させていることになる
この不正アクセス自体が容易にできるとも思えないので、ざっくりしているなあと思った
いずれにせよ、なんちゃって金融映画として楽しむしかないのだが、シナリオの構築があまりにも酷く、開始20分で主要キャラと物語の方向性を提示できていないのは痛い
無駄な水ぶっかけとか、瀬戸際で数学者の発表した謎理論で打開したみたいな流れになっているのも無茶で、その理論でどうやってイスラム圏のAIにフェイクを信じ込ませたのかもわからない
フェイクニュースで為替が動くのはたくさん見てきたが、その初動はAI自動売買ツールというよりも、その動きに便乗する個人投資家とか、フェイクニュースを知った上でインサイダーを行うヘッジファンドだと思う
そう言った観点からも、AIを騙すというところからリアリティがなく、むしろ「石油精製施設のシステムをハッキングして稼働が止まる」みたいなことをやった方がマシだし、要人を脅して無茶な発言をさせる方がリアリティがあったりする
日本の元号が変わったぐらいで全世界のAIが反応するということもなく、そこは普通に西暦を使用していると思うので、なんだかなあと思う
色々とアレな作品だったが、AIにシナリオを書かせた方がまだマシなものになったんじゃないかなあと思うし、そもそも2019年の設定でAIを騙す話を作るというところもピントがズレているなあと思った
マネーサスペンスと謳っていましたが、、
リゲインがなきゃ戦えません
株価操作の前科があるハッカーが、かつての仲間たちとFXで一儲けを企てる話。
口八丁のFX口座?と状況が良くわからない段階での氷抜きの洗礼から始まって、強欲婆とその甥っ子が絡み巻き起こっていくストーリー。
AIを騙すとかさぞかし凄いことするのかと思いきや、えっ!そんなもん!?
強欲婆の描き方もお仕置きがあるのはみえみえの人物像だから、どんな方法かというところが焦点だけれど、それにしてもやっぱり、えっ!そんなもん!?
過去に何があったのかをなかなかみせず、勿体つけて小出しにしていなかったら相当あっさりなんじゃね?
テンポが良いのは良いけれど、何もかもがすんなり進んじゃってダイジェストでもみている様な感じだし、サスペンスというにはあまりにもあっさり過ぎてもりあがらなかった。
どっちつかずな印象。
I need you
予告は面白そうだなと思いつつ、あらすじだったり制作チームを眺めているとどうしても不安がつきまといましたが、案の定その予想通り、いや予想を超えるトンデモな作品でした。
散々貶してしまいたくなるくらい酷いわけでもなく、笑い話にできるツッコミどころがあるわけでもなく、シンプルにおもんないっていう珍しい映画でした。
序盤からダラダラしており、水をぶっかけるくだりなんてさっさとやってしまえばいいのに、しっかり準備をして、しっかり構えて水をかけるという本当に93分の作品か?ってくらい尺の使い方がもったいなかったです。
そこからダラダラ登場人物を見せていき、ダラダラと計画を語っていきともうダラダラしっぱなしなので目が当てられません。
国際的な作品なので様々な国のハッカーたちと協力していくシナリオになってはいるんですが、他国の面々が強烈に関わっているわけではなく、日本でやれば良いのでは?という疑問符がどうしても拭えませんでした。
様々な国と時系列をシャッフルしまくってるせいでややこしくなっていますし、カウントダウンも鬱陶しい事になっていたりとどうしてこれで良いと思ったのか甚だ疑問です。
肝心のFX描写も希薄で、やってる風、知ったかぶってるみたいな取引のシーンばかりで緊張感がありませんでしたし、もうやり取りの全てがおままごとにしか見えなかったです。
天才ハッカーという設定がまるで活かされていないキャラクターばっかりで、パソコンをカタカタターン!というよくある邦画でインテリ系のパソコン出来る人のイメージそのままがそこにあったので安っぽく感じましたし、このままエンターでも押してスッキリした顔でもしようもんなら劇場を後にしていたと思います。
FXの変動や数字が色で見えて分かるという設定も別に…といった感じで必殺技というよりかは状況を見極めるためのものというのも迫力に欠けたと思います。
FXできっちりリベンジを果たしてスカッと終わる!みたいな感じで終わればまだ良いかなと思ったらスッと終わってしまい、スタイリッシュを目指したかったのかは分かりませんが、そんな達成感のない終わりをされても見る側は困るんだが…となりました。
ラストシーンの引きの絵も中々にダサかったですね。
本当にMVとか撮ってる人なのか?ってくらいダサく締めていきました。
邦画も素晴らしい作品が誕生している中、こういう作品が生まれてしまうのかという絶望に叩きのめされながらも、FXって遊びだと思って手を出すと痛い目に合うぞ!っていう警鐘を鳴らすための映画ならまぁまぁ良かったと思います。
多分そんなこと無いので大問題作です。
鑑賞日 7/5
鑑賞時間 17:40〜19:25
全52件中、1~20件目を表示