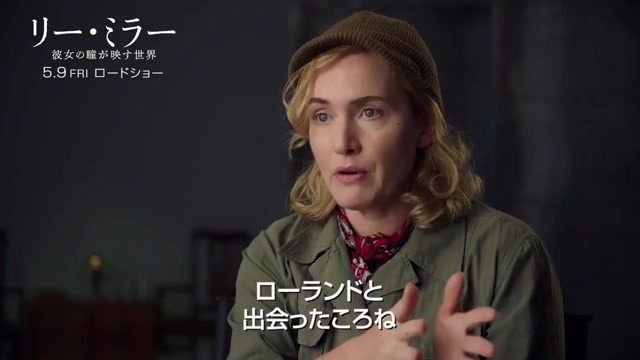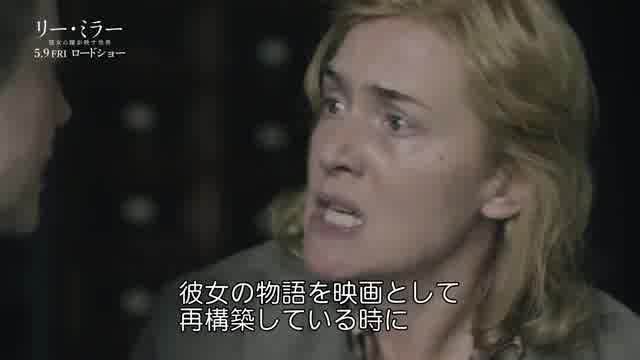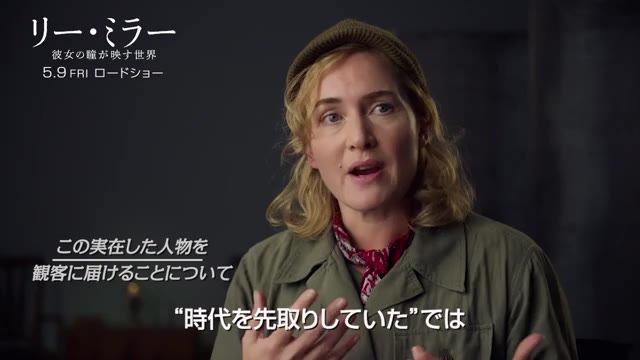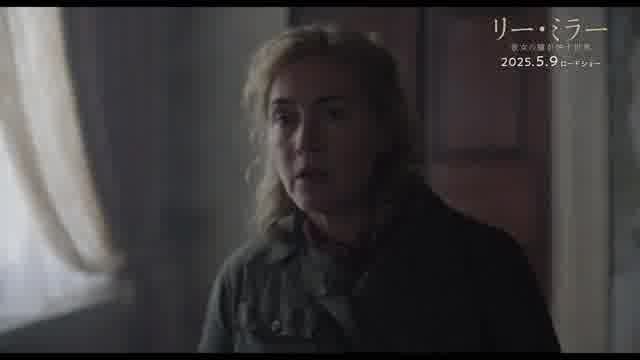リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界のレビュー・感想・評価
全98件中、61~80件目を表示
小さな痛みに向き合う
リー・ミラーが残した戦争の実相の記録が、
ケイト・ウィンスレットと、
監督エレン・クルス(『エターナル・サンシャイン』等ミッシェル・ゴンドリー作品のD.O.P.時代はなぜかクラスではなくクルス、馴染み深いので以降クルスで)
の卓越した手腕によって、
単なる伝記映画の枠を超え、
本作は多くの戦争映画とは一線を画す、
独自の視点と表現で観客の心に迫る。
なぜ、
本作が〈一線を画す〉作品となっているのか。
具体的に触れていこう。
それは、
歴史の表舞台を飾るスクープや大事件を安易に追いかけることをせず、
むしろ「小文字」の現実に目を向ける徹底した姿勢にある。
パリ解放、
青酸カリで自決した家族の顛末、
あるいは収容所の惨状といった、
歴史的にも有名な出来事をなぞるように描きながらも、
それらをセンセーショナルに消費することなく、
そこに隠されている個々の、
名もなき人々の「見えない傷」や「深い痛み」を、
リー・ミラーのまなざしを通して写真に残していく過程を丁寧に描写する。
ナチス、A.H.、チャーチル、スターリンといった「大文字」で語られる権力者(他の例、トランプ、プーチン、ゼレンスキー)の影に隠れた、
市井の人々の心の動きこそが、
この映画の主題であり、リー・ミラーが追い続けた【伝えるべき事】なのだ。
エレン・クルスの演出(撮影は別のスタッフとはいえ影響は大だろう)、
そのリアリズムと暗部の描写において、
本作の主題と見事に同期する。
ストロボを焚く光の閃光、
あるいは、
丹念に光量を計測する仕草、
といった写真撮影の現場における細やかな演出は、
単なる描写を超え、
リー・ミラーが実際に残した【歴史的な写真群と、
今我々が目にしている映画の映像の絶対温度をシームレスに繋ぐ】役割を果たす。
それは、クルス特有の技術が織りなすリアリズムであり、
観客はあたかもミラーのレンズ越しに、
あの時代の生々しい光景と感情を追体験するかのようだ。
(ゴンドリーのシームレス手腕も凄かった)
それぞれの「小さな痛み」にしっかりと軸足を置くことで、
個人の悲劇がやがて普遍的な歴史の「大文字」へと繋がっていく様を鮮やかに描き出す。
これは、ドキュメンタリー、フィクション、
そして伝記作品のいずれの分野においても「教科書的手法」と言えるだろう。
類似作品が数多く存在する中で、
本作がひときわ「出色の作品」として輝くのは、
その手法が表層的な模倣に終わらず、
人間の尊厳と痛みに向き合っているからに他ならない。
そして何よりも、
リー・ミラーという写真家、
ケイト・ウィンスレットというプロデューサー兼俳優、
エレン・クルスという監督、
の三位一体となった「ひとの痛みに向き合う」それを観客に自分事として、
目撃者として、
知らなかったとは言わせないように、
突きつける、
という揺るぎないスタンスこそが、
本作に深いメッセージを与えている、
それは、単にひとの傷みを伝えるという行為に留まらない。
映画やドラマといったフィクションの枠を超え、
ニュース、報道、雑誌といった、
あらゆるメディアの「存在意義」そのものも問われる、
極めて今日的で普遍的な問いを観客に投げかける。
果たしてメディアは、
表面的な出来事や大きな物語の裏に隠された真の人間性を掬い取れているのか?
この問いかけは、
我々がさまざまな情報と向き合う現代社会において、
看過できない重みを持つ。
本作は、単なる戦争の記録ではない。
それは、
時代と人間を見つめ続けた一人の人間の魂の軌跡であり、
観る者に痛みを伴う深い情動を促し、
メディアの根源的な存在意義をも再考させる、
極めて意義深い作品である。
その「小文字」の描写にこそ、
戦争の真の顔と、
人間の強さ、
そして脆さが凝縮されている、
と言われているような気がした。
【蛇足】
まんが、「ゴルゴ13」で、
デューク東郷の出生の秘密やルーツを追う作品はいくつかある。
ルーツを追うものは必ずゴルゴ13によって消される。
その中でも「日本人 東研作」「芹沢家殺人事件」
「ミステリーの女王」はなかなかスリリングな内容だ。
「ミステリーの女王」の中で、
ゴルゴを小説化しようと試みるマッジ・ペンローズ、
作家ペンローズは、
夫の名前繋がりと、
真実を追う姿勢で、
リー・ミラー説があったが、
讃美歌13番が鳴り始める前にやめておこう・・・
ケイトウィンスレットに興味あり観に行った
カメラマンを通して描く戦争映画です。
考えるな・感じろ!なのか?自分の目で確かめろ!なのか?行動あるのみ
舞台の中心は1944年~終戦に向かうフランス。ギュッと集約された濃密な期間を、主人公が撮影した写真と共に観る者も同じ時間を過ごすかのような作品でした。
戦争を終えてから、史実と共に振り返るのではなく、自身が戦地に赴き肌で感じ、被写体を選んでいるだけに、戦争の悲惨さやナチスの非道さが際立ったような感じがします。
その一方で、息子との間で繰り広げられるインタビュー(?)シーンは、時を行ったり来たりであるとか、何のためのやり取りだろうとかに気を取られがちで、ワタシ的には要らなかったかなと感じました。
後は、あれだけ広い地域で戦闘があったのに、それでも「彼の地」で起こっているかのような感覚のズレというのは国は違ってもあるのだなと、驚きでした。
いずれにしても戦争は良くない。そんな過去の教訓を何故人は活かせないのでしょうね。
驚きのポスター
リー・ミラー(映画の記憶2025/5/11)
人間リー
終生VOUGEにリーの戦場写真を載せられなく
後悔したというオードリー。
君のことが心配だ。と言う言葉でしか
リーを乞うことができなくなったローランド。
など人間リーに豪快に振り回された人物の葛藤が
興味深かった作品だった。
が、それを良しとするか良しとしないかで
自己のコーカソイド濃度が測れるんじゃないか?
と思うほど、争い多き彼らの特性をリーに見て取れた
ような気がしてならない。
歴史上では、史上最悪最狂の人物として描かれるAHも
後世のテクノロジー検証と残置物から
高度の薬中だったことが見て取れるが
全ては隠蔽された歴史が拓けば分かる事実なんだと思う。
戦争とメディアはセットで悪巧みを行う。
と言うことに気付かせてもくれた静かな告発映画◎
その点で僕は本作を評価したい。
圧力と理不尽という波に抗い続け、真実を写真に収めた偉業
【イントロダクション】
トップモデルから写真家へと転身し、20世紀を代表する女性報道写真家となったリー・ミラーの数奇な人生の一時代を描く。
リー・ミラー役のケイト・ウィンスレット『タイタニック』(1997)は、主演の他に製作も務める。
監督には撮影監督としてキャリアを積んできたエレン・クラス。脚本に『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』(2017)のリズ・ハナー、『ホテル・ムンバイ』(2018)のジョン・コリー、マリオン・ヒューム。
【ストーリー】
1977年イギリス、ファーリー・ファームの自宅にて、老齢の女性リー・ミラー(ケイト・ウィンスレット)は若い男性(ジョシュ・オコナー)からインタビューを受ける。気難しく、「質問される事が嫌い」だと言う彼女は、素直に応じようとはしない。だが、次第に彼女が写真家として活躍した第二次世界大戦時代について語り始める。
1938年南フランス。リーは芸術家や詩人仲間と共に、優雅な生活を送っていた。ある日、リーは芸術家のローランド・ペンローズ(アレクサンダー・スカルスガルド)と出会い恋に落ちる。
時を同じくして、ドイツのアドルフ・ヒトラーが政権を掌握し始めていたが、リー達はそんなヒトラーの台頭を何処か現実味のない出来事に感じていた。しかし、やがて戦火はリー達にも迫り、穏やかな日常は一変していく。
1939年。リーはローランドとロンドンへ移住。仲間達はレジスタンスに参加し、皆離れ離れとなってしまう。
翌1940年、リーはかつてモデルとして活躍した『VOGUE』の英国編集部に、今度は写真家としての仕事を求めて訪れる。最初は断られたが、女性編集者のオードリー・ウィザーズ(アンドレア・ライズボロー)と出会った事で仕事が舞い込むようになる。
写真家として活動する中で、リーは米国従軍記者のデイヴィッド・E・シャーマン(アンディ・サムバーグ)と出会う。
1942年。リーは戦場に赴く事を希望するが、英国軍の規定により女性の戦地への参加は認められない。そこで、リーはデイヴィッドの機転により、アメリカ軍の従軍記者となる事で戦場へ赴く。
1944年。リー達はアメリカ軍が解放したパリを訪れ、かつての友人であり、やつれて変わり果てたソランジュと再会する。夫のジャンはゲシュタポに連行され、自身も強制収容所に入っていた事を聞かされる。そこで初めて、リーは強制収容所の存在と、ユダヤ人をはじめとしたナチスに抵抗・反発する人々が姿を消している現実に直面する。
やがて、真実を明らかにしなければならないと使命感に駆られたリーは、ローランドの要望を無視してでも、先に待ち受ける“この世の地獄”を目指す決意をする。
1945年4月30日。ヒトラーが妻のエヴァと共に地下壕で自殺した日。リーはデイヴィッドと解放されたブーヘンヴァルトとダッハウ強制収容所を訪れ、惨劇の痕を写真に収める。そして、2人はミュンヘンにあるヒトラーのアパートを訪れ、彼の浴室で写真を撮る。
【感想】
昨年公開された『シビル・ウォー/アメリカ最後の日』の戦場カメラマン、リー・スミス(キルスティン・ダンスト)のモデルにもなった人物。また、脚本家にリズ・ハナーやジョン・コリーという実力派の起用。主演のケイト・ウィンスレットが製作まで務めた意欲作とあり、俄然興味が湧いた。
リーの肖像を調べると、トップモデル時代の写真に見覚えのあるものがあり、更に驚いた。
これはまさしく、リー・ミラーという1人の女性、そして報道写真家として真実を求めて戦い続けた人間の功績を讃え、権力により隠されてきた真実を明らかにしていく作品だ。
作品は1977年を現在と仮定して、謎の若い男性によるリーへのインタビューと、それによる1938年〜1945年までの8年間をリーが過去回想する構成となっている。リーの過ごした年や環境の変わり目には時を現代に戻し、度々男性とリーの問答が行われる。そうした現在と過去を行き来する構成には映画としての作りの巧みさはあまり感じられなかったが、そうではなく、1人の人間の人生における最も重要な時期を、場面毎に切り取って見せているのだと感じた。
「傷にはいろいろある。見える傷だけじゃない」
リーによる、まさに本作を象徴する台詞である。リーの強気で物怖じしない性格は、彼女がこれまでの人生において男性優位社会の圧力に屈せざるを得なかった、“見えない傷”の積み重ねから来る反骨心なのだ。それは、幼少期の男性からの性暴力に始まり、恐らくモデルとして華々しく活躍していた裏で男性から好奇の目で見られる苦痛、そして写真家として活動する中で経験したあらゆる理不尽についてもだ。
そんなリー・ミラーを全身全霊で演じ切った、ケイト・ウィンスレットの憑依とも言えるほどのエネルギーが凄まじい。特に、ダッハウ強制収容所で暴行されて怯えているユダヤ人少女の写真を見つめる際の表情、少女の悲痛な経験に自らを重ねずにはいられないでいるであろう僅かな目の演技、不安と恐怖を払拭するかの如く絶えずタバコを吹かす仕草は本作でもピカイチ。
また、彼女は単にジャーナリストとして真実を伝えようとしたのではない。その奥底には、ヒトラーという独裁者の誕生前夜に「彼が政権を手にするなどありえない」と、何処か現実味を抱けずに仲間と楽しく過ごしていた無知な自分に対する罪悪感と、「自分に近しい人が犠牲になった」という非常に個人的な要因が存在すると感じた。しかし、だからこそ彼女は「真実を明らかにしなければならない」と使命感に突き動かされ、ローランドの願いを拒否して強制収容所という“この世の地獄”へと足を進める事になる。他人事ではないと確信したからこそ、行かないわけにはいかないのだというその姿勢は、非常に人間味に溢れ、だからこそ信念に満ちている。
リー・ミラーという女性について鑑賞前に調べる事をしなかったからこそ、ラストでインタビューしていた男性がリーの息子であるアントニー・ペンローズだという仕掛けは面白いと感じた(途中、彼が母について語り出した辺りから匂いはした)。また、リーは既に亡くなっており、全てはトニーが屋根裏部屋で発見したリーの足跡を基に行われていた一人芝居だと判明するのには驚いた。このラストの驚きについては、映画的な面白さが感じられ、「息子と完全な和解を果たせずにこの世を去った母親」というほろ苦さを感じさせる締めが印象的だった。
個人的に、こうして文章にして作品のレビューを書いている身としては、戦場の悲惨さをどう文章にして表せば良いか分からないリーに、デイヴィッドが掛けた台詞が心に残る。
「まず真実を書いて、その後で磨けばいい」
ところで、本作の1番の肝とも言える「ヒトラーのアパートの浴室で写真を撮る」という行為の意図について、私は判断しかねている。
トニーの言うように、彼女のアーティスト性から来る衝動的な行動か、あるいは戦争の終結、1つの惨劇の終結を告げる為の彼女なりのファンファーレか。
いずれにせよ、あの浴室での行動は、当事者から証言を得られない以上、あくまで写真を基に我々一人一人が想像を膨らませるしかなく、それこそが彼女の、また本作を製作した人々の狙いかもしれない。
【総評】
リー・ミラーという、数奇な人生の果てに「20世紀を代表する女流写真家」としての評価を得た彼女が、どのようにして真実を追い求めたのか。その軌跡を追体験出来る作品だった。
時代の荒波、男性優位社会の圧力や理不尽、そうした苦難を乗り越えて真実を掴み取った彼女の偉業は、主演・製作のケイト・ウィンスレットが語るように、今日を生きる我々にも伝えられるべきなのだろう。
最後に彼女の思いが浮かびあがる
不勉強者の私には、大戦当時の米・英・仏・独がよく分からず、彼女の真意も掴めないまま、中盤辺りまでなんとなくフワフワと眺めていた。
「フワフワ」の原因は、やはりこのリーミラーが「シビルウォー」の主人公のモチーフだということも大きい。
報道というものの暴力性が、私にはやはり従軍記者・ジャーナリストという人々についてはいつも気になってしまう。
もちろん戦場で実際に起こっていることを世界に知らしめることの意義は絶大だ。
しかし、それがジャーナリストの私欲や単なる自己実現のためのプロセスとしてのみ機能しているなら、それは「暴力」になりうる。
「シビルウォー」は報道の正義を描きながら、そこに呑まれていく人々も視野に入れているという意味で価値があったと思う。
そして本作。
主人公のリーは、比較的奔放で自意識が強く、自立していてバイタリティもある活動的な女性として描かれる。
撮られる側だった彼女が撮る側に回り、戦地を撮ることに心を奪われていく。
いかにも、(あえてこの言葉を使います)「男勝り」な女性が他の反対を押し切って、活躍の場を求めていく感じ。
正直、途中までは若干「ノれないな」、と思いながら観ていくと、彼女のバイタリティがちゃんと「報道の正義」に繋がっているのが徐々に伝わってくる。
終盤、Vogueの事務所に怒鳴り込み、編集長を前にした自分語りで彼女の行動の根拠となる過去が示されて、それまで私の中でフワフワとしていたものが、まるで印画紙に焼き付けられる様に実体化する。
確かに、彼女のレンズは戦地においても「破壊」や「兵器」といった加害者側ではなく、いつも弱者に向けられていた。
その弱者の存在を世界が認知することで、彼女自身が強制的に葬ってきた過去にも決着がつけられると信じた。
彼女の残した写真が、彼女の死後、ようやく歴史的に大きな意味を持つものとして脚光を浴びるのは皮肉ではあるが、だからこそ報道が「自分だけのためではない」ということを示した本作の価値は重要なんだろう。
ただ、やはり私には彼女の意図を図りかねる行動なんかもあって、自分が彼女、ひいてはこの作品をちゃんと理解しているとは思えないってところも多い。
パンフレット買って知識を補強せねば。
彼女の強さと弱さ
彼女の伝えるという強い使命。そしてクリエイティブであるという姿勢に心を打たれた。
LEEに VOGUE LIFE
戦争の最前線でバリバリなお話かと思いきや、そうだった時代は戦時中性差別が激しい頃であった ましてや女性が最前線行ける訳なかった、否それでも戦場カメラマン先駆者的な方なのでしょうね 愛用のカメラが印象的 いつもタバコに思い立ったら即行動とっても姉御肌で頼もしいそうな性格、シスターフッド的なものも感じました 序盤のトップレスの集いは監督何のサービスかいなと思ったけど、最後の映像で!?ってなった リーさんのお話だけどLIFEの編集長役の人良かったな そしてまるでどんでん返しみたいな作り
彼女の苦悩を伝えきれていない
女性初の戦場カメラマン。第二次世界大戦時にこんな女性がいた事に驚きであった。彼女は戦場で何処に行くにも女性と言うだけで止められていた。それらを跳ね除け彼女は突き進む。
もっと主人公の内面を深く抉って欲しかった。何故彼女がそこまで突き進むのか本質的な確信が欲しかった。彼女が編集長に話した子供の時の悲痛な体験談だけでは余りに弱かった…。
だって人間の所業とは思えぬホロコーストの現場と沢山の遺体を目撃したのである。その異様な光景。それは正しく地獄その物である。そしてその強烈な死臭まで。その割には主人公はある意味平然としている様に見えた。だから彼女の苦悩と苦痛をもっと描き出す必要があった。それが圧倒的に弱いのだ。
信念を貫き時代を駆け抜けた女性写真家
予告で興味をもち、公開2日目の朝イチで鑑賞してきました。客入りはそこそこあり、主演のケイト・ウィンスレット目当てか、作品の魅力かわかりませんが、9割は中高年男性でした。
ストーリーは、とある男性からの取材を受けた報道写真家リー・ミラーが、過去を回想しながら、トップモデルのキャリアを捨てて写真家となり、芸術家ローランド・ペンローズと出会って恋に落ち、ほどなく始まった第2次世界大戦で従軍カメラマンとして戦地に赴き、そこで味わった経験や撮影した写真について噛み締めるように語るというもの。休日の朝イチで観るにはなかなかヘビーな内容ではありましたが、それだけ見応えのある作品でもありました。
リーは、ナチス・ドイツからのパリ解放を通して、戦争の悲惨さや平和の大切さとともに、女性や子どものような弱者の救済をとりわけ強く強く訴えかけていたように感じます。戦地の惨たらしさ、戦争の愚かさを、文字通り命懸けでフィルムに収めたリー。それなのに、戦後の編集側の意図に合わず、その写真が一切掲載されなかったことに対する、リーの怒りと悲しみの慟哭が心を揺さぶります。戦中の生々しい現実をオブラートで包むように封印し、あたかも元どおりの平和が戻ったかのような印象を与える雑誌に、抑えきれない憤りと深い悲しみや絶望を感じたのではないでしょうか。
それは、深く傷つきながらも母によってなかったことにされた、少女期の忌まわしい経験と重なり、リーにとって許し難いものだったに違いありません。序盤に語られた、「見えない傷もある」と言う言葉が思い出され、観る者の心に重くのしかかります。戦争は人を殺し、街を壊すだけでなく、人々の心にも一生癒えることのない傷を残しているのです。酒に逃げているようにも見えるリーの姿から、彼女自身も戦地で心を蝕まれたことが窺えます。
一方で、写真や記事はどこまで現実を伝えられるのか、その可能性と限界に挑み続けたリーの姿がまざまざと描き出されているように感じます。本作のキービジュアルともなっているヒトラーのアパートの浴室での写真。撮影時に、ブーツの泥であえてバスマットを汚していたのが印象的です。支配者ヒトラーが汚れを洗い流していた浴室を、罪なき人々がホロコーストに遭った地の土を持ち込んで汚したように見え、彼女の抑えきれない怒りと被害者への鎮魂の記録のようにも感じます。
戦後、彼女は自身の仕事や業績について生涯語ることはなかったようです。それはささやかな抵抗であったのか、思い出したくない過去を封印したかったのか、今となってはわかりません。ただ最後に、リーに取材をしていると思われた男性は、実はリーの息子であり、彼はリーの死後に残された膨大な写真との対話から彼女の生涯を辿っていたことが明かされます。写真を捨てなかったリーは、たとえ日の目を見なくても、残すべき事実を、残すべき相手に託したかったのかもしれません。
鑑賞中、トップモデルから写真家への転身の理由をもう少し丁寧に描いてほしかったと思っていたのですが、ラストで明かされる彼女の生い立ち、後半生の生き方からは、その理由を推しはかれるような気もします。
主演はケイト・ウィンスレットで、信念を貫き時代を駆け抜けたリーを熱演しています。脇を固めるのは、アレクサンダー・スカルスガルド、アンディ・サムバーグ、マリオン・コティヤールら。
リー・ミラーの気持ちの揺らぎと一緒になって
説明もなく唐突にお話しが始まって、第二次世界大戦開始での転換を経て、ノルマンディー上陸作戦の後に物語の核心的な部分に進んでいく。
リー・ミラー本人の気持ちの揺らぎと一緒になって戦場を進んで行き、史実を目撃していく感じがする。
実在の人物を題材にした物語として、非常に面白かったと思います。
主演のケイト・ウィンスレットは、久しぶりに見たけれど、「タイタニック」の頃とは結びつかないくらい、ものすごく逞しくなっている。
劇中、惜しげもなく上半身裸になる場面が2回あったけれど、役柄と相まってそのボリューム感には圧倒されます。
戦場報道官としてのバディを演じたアンディ・サムバーグの演技も良かった。
副題がちょっとミスリード。
チラシの写真のイメージと合わなさすぎる。
ケイト・ウィンスレットの熱演が光るが。。。
報道写真家のレゾンデートル
撮られる側から撮る側への転身は、
過去からも耳目にするところ。
至近の例では『安珠』だろうか。
2023年に「CHANEL NEXUS HALL」で
個展も開催されている。
が、やはり慣れ親しんだ人物を被写体にするケースが多く、
『リー・ミラー』ように「報道写真」、
それも「戦場」をフィールドに選択した例は少ないのでは。
とは言え、
主人公が何故そこまで執心したのかは詳らかにはされず、
かなりもやっとした思いがわだかまる。
今よりも更に女性に対しての差別が甚だしい時代。
彼女の従軍は「D-デイ」には間に合わない。
その間に『キャパ』は
最前線で〔オマハ・ビーチ〕の写真をものし
名声を上げている。
しかし、『リー(ケイト・ウィンスレット)』の足跡は
次第に東進するアメリカ軍の進攻に追い付き、終いには先陣にまで。
そこで目にするのは、
世界の人々がまだ認識していない「ホロコースト」の実態。
再現映像でも目を背けたくなるような惨状は、
いくら強靭な精神の持ち主でも
その後の人生に影響を及ぼすに違いない。
一例を挙げれば、アルコールへの逃避、だろうか。
彼女の視線は、敵味方の枠を越え、
常に弱者である女性に向けられる。
常でも差別され虐げられているのに、
戦禍の非常時ではそれが更に際立つ。
痛みを一方的に受けることへのやり場のない憤りが、
幾つもの写真から溢れ出す。
本作は基本的に『リー・ミラー』への賛歌。
主演の『ケイト・ウィンスレット』が
製作にも名を連ねていることからも、
並々ならぬ入れ込み具合は判ろうというもの。
その一方でショッキングな映像、
独軍への協力を疑われ、頭を丸刈りにされる女性や、
解放軍のはずのアメリカ兵士に、まさに犯されようとしている女性など、
ショッキングな場面は多い。
主人公の戦場での体験を際立たせるためのエピソードの数々も、
次第に実録モノと区別がつかなくなり、
彼女のキャラクターが埋もれてしまう難点になってしまうのは難点で
この匙加減はむつかしいところ。
もっとも印象的な写真は
〔ヒトラーの浴室〕だろう。
ベルリンで『ヒトラー』が自殺した日に
彼のアパートのバスタブで湯あみをする彼女の姿は、
官能を感じさせつつ、
独裁者に対しての反抗心が如実に現れている。
戦場を撮っていないのに、
戦争の不毛さをこれほど端的に表現した一枚が嘗て有ったろうか。
ウイットに富みながら、反骨の精神をまざまざと感じる、
『リー・ミラー』を象徴する一枚だ。
奔放かつ果断
あの光景を目の当たりにしたら人間というものを信じられなくなってもしょうがない。
奔放かつ果断なリー・ミラー。20世紀を代表する女流写真家とのことだが、今回初めて知った。
ケイト・ウィンスレットの体あたりの演技は、リー・ミラーその人であろうと感じさせる凄さがある。特にヒトラー総統邸のバスタブであの写真を撮ろうと思いついた時の表情は、いたずらを思いついた少女のよう。
構図が頭に浮かんでしまったからには、撮るしかない。根っからの写真家のリー・ミラーを感じた。
インタビュアーの質問に対してリー・ミラーが答える。彼女の回想をベースに物語は進んでいくが、ちょっとしたトリックがある。そのことを暗示する会話への引っ掛かりが、大きな余韻を作る。
すごい生き様だ❗️しかし 描写は極めて表層的 普通作品
ホームページが情報多くて その上に有料パンフ🈶
あっ ホームページ熟読すれば 敢えて有料パンフ🈶要らないカモなぁ
しかし、有料パンフ🈶を購入して読むレベルのお客さん向け。有料パンフ🈶嫌う買わない人には 相性があるカモ🦆。
①パリ🇫🇷NY🇺🇸でトップモデル
②パリで写真撮影修行 一部被写体 NY
③エジプト🇪🇬→パリ🇫🇷【ここから作品は事実上始まる】→ロンドン 英国🇬🇧版『VOGUE』カメラマン→英国で許可が降りず 米軍従軍記者 『アメリカ『LIFE』記者と共動』
そして ドイツ🇩🇪へ
【ほぼホームページ🏠に載ってます】
というだけで すごい人生だよ
映される側より 写す側
彼女の人生 ①第二次世界大戦の壁 ②軍隊は男社会 という 二つの壁 に立ち向かった【ホームページ・コメントに載ってます。】には感嘆した。
しかし 彼女の生き様 写真 俺は知らなかった。
それが知れただけでも良かった。気迫を感じた
当時のマスコミの動静も良かった。
『ノエミ・メルランさん🟰正月🎍に観た『エマニュエル』さん』頑張って👍
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』キルスティン・ダンストさんの役と似てるなぁと思ったら そのベースとなった人物。
『タイタニック🚢』ケイト・ウィンスレットさんが製作・主役で 独擅場。
それは相違ない。
ただ ナチスの強制収容所の惨状 ほか ほぼほぼ知ってたから 特筆すべき点は無かった。
まあ ヒトラーのアパートの写真も ミュンヘンだから 俺的には弱いメッセージ。米軍といえども
どうせなら ソビエト赤軍が 死闘の上確保した 最後の地下壕だよねぇ。ベルリン。勿論ソ連占領だけども。
ミュンヘンは安全地帯すぎ
それから 申し訳ないけど 従軍記者やカメラマンというのは 最前線では足手まといで 兵隊の士気も下がるから
最前線ではなく 若干後方の戦線に配置なんだよね。
まあ 俺には葛藤が表層的 かつ 描写が リアルに描けば描くほど 平板 安全。
で 多分 少し🤏盛ってる可能性あるから 普通の感想作品でした。
まあ 主人公ケイトさんのこだわり 硬派は感じました。あっ テンポはそこそこ。
ケイト・ウィンスレットの演技
全98件中、61~80件目を表示