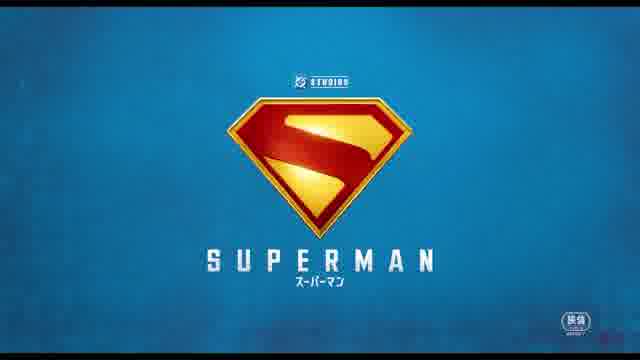「オトナになったジェームズ・ガン」スーパーマン 蛇足軒妖瀬布さんの映画レビュー(感想・評価)
オトナになったジェームズ・ガン
旧シリーズのスーパーマン像に慣れ親しんだ観客と、
ジェームズ・ガンの個性的な作風に惹かれる観客の間で、
作品への期待値は大きくかつどんな物語になるのか、
期待度は高かったのは事実だろう。
ジーン・ハックマン演じるレックス・ルーサー、
マーロン・ブランドの実父、
グレン・フォード継父、
地球にたどり着くまでの約1時間、
牧歌的なドラマの世界観を、
じっくりと堪能したいと願う観客にとって、
違和感はあるだろうし、
一方で、
ガン監督特有の躊躇なく「サクサクザクザク」とどんどん進むテンポと、炎上も辞さないブラックユーモアを期待していた観客は、
その品行方正な抑制ぶりに驚くことだろう。
あるいは更に若い観客に向けて、
共通前提の説明を大胆に省き、
いきなり「転生したら地球だった」とか、
薬屋はクリプトナイトを処方してくれるのかとばかりに、
いきなり物語に飛び込む姿勢は、ある意味で潔い。
今作のジェームズ・ガンは、「大人になった」。
極悪党たちを縦横無尽に暴れさせ、
オトナ限定のユーモアを炸裂させる手腕は、
今作では随分と控えめだ。
その裏には、リチャード・ドナー版や、
ジョン・ウィリアムズの音楽への深いリスペクトが垣間見える。
随所に散りばめられたアレンジやグラフィックは、
オールドファンへのメタ的なメンションとしても機能している。
プロデューサー、そして一社会人としての「ちゃんとしてます感」が、
監督としてのガンの持つ愉しさを半減させているように感じるのは否めない。
しかし、これはDCEU全体の再構築を担う彼にとって、
避けられない選択だったのかもしれない。
その証拠に、新たな布石としてのヴィジョンは確かに存在する。
グリーンランタンやミスター・テリフィックといった個性的なキャラクターをキャスティングし、
まるでルーザーのようなウォッチメンのように彼らを物語に溶け込ませる手腕はさすがだ。
彼らを現代社会が抱える分断、私的制裁、排外主義といったテーマへのシナリオと、
巧みにチューニングしてスーパーヒーロー映画の枠を超えた社会的なメッセージをしっかりと打ち出している。
スーパーマンが「異星人」として、
不信の目を向けられる描写は、
まさに現代社会における移民問題のメタファーとも読み取れるだろう。
移民もエイリアンも極悪党も、
困ってる人たちの前では協力する、
知らんぷりができないルーザーたち。
本作は、古き良きスーパーマンへの【メタ的な意味での】の目くばせを忘れずに、
現代的な課題にも切り込む意欲作といえるだろう。
今の時代に求められる独特の「希望」の物語として、
私たちに語りかけてくる。
独特の希望。
現在のMCUとDCEUは、
かつての成功体験から脱却し、
新たな方向性を模索しているように見える。
「欧米が【浮世絵】に気づき、【忍者】に魅せられ、
【アニメ】を知り、
そして【演歌】というルーザーの悲哀の領域に入ってきている」
「敗者の物語」、
つまりは悲哀や挫折といった人間の深い感情に根ざした表現へと傾倒している状況、方向を模索しているのではないだろうか。
これまでのアメコミ映画は、
強大な力を持つヒーローが悪を打ち倒し、
勝利を収めるという構図が主流だった。
しかし、
観客はもはや単なる勝利の連鎖だけでは満足しなくなってきている。
完璧なヒーローよりも、悩み、苦しみ、
失敗を経験しながらも立ち上がろうとするキャラクターにこそ、共感し、
感情移入するのではないだろうか。
例えば、DCEUでは『ジョーカー』が大ヒットを記録した。
社会から疎外され、自己の存在意義を見失った男が、
最終的に「悪」へと堕ちていく過程を描いている。
MCUにおいても、『サンダーボルツ』改め『ニューアべンジャーズ』
でもヒーローたちの内面的な葛藤や弱さが深く掘り下げられ、
新たなファン層を獲得しようとしている。
古今東西の物語を紐解くと、
普遍的なテーマとして「敗者の物語」が繰り返し描かれてきた。
ギリシャ悲劇から日本の古典文学、
そして現代のドラマや映画に至るまで、
挫折や喪失、そしてそこからの再起や、
あるいは救いのない結末を描くことで、
人間存在の深淵に迫ろうとしてきた作品は多い。
MCUやDCEUがこの「敗者の物語」へとシフトしているのは、
単なるトレンドではなく、エンターテインメントビジネスの根幹に立ち返ろうとする動きなのかもしれない。
なぜなら、敗者の物語は、
観客に強い感情的な共鳴と深い考察を促すからだ。
共感は物語への没入感を高め、考察は作品の奥行きを広げ、
長期的なファンを生み出す土壌となる。
問題は、この「敗者の物語」、
つまり、
暗くてつまらない(日本映画のような)とさんざん言われてきた物語が、
これまでの「勝者の物語」のように大量動員が可能なビジネスモデルとなり得るかという点だ。
今後、MCUやDCEUは、単に「敗者の物語」を描くだけでなく、
それをいかに普遍的なテーマとして昇華させ、
多様な観客に訴えかけるかが問われるだろう。
ヒーローの脆弱性、社会の不条理、
人間の心の闇といったテーマを、エンターテインメントとして昇華させることで、商業的な成功と芸術的な評価の両立が可能になるのかどうか、
オトナ帝国の逆襲が可能かどうか、
You Talkin' to Me?のYouとは誰、何なのか、
ジェームズ・ガンのビジョンと手腕にかかっていると言っても過言ではないのかもしれない。
知らんけど。
コメントありがとうございます。
敗者の物語→ショーシャンク、ノマドランド、ロッキー、他にもたくさんありますが、主人公が自分を肯定する、あるいは観客目線で全肯定感をいかにじょうずに魅せるか、でしょうか。
本作に対して拒絶反応を示す人たちの感想の中に「スーパーマンがボコボコにされるのなんか観たくない」というのが結構あるみたいで、自分としてはヒーローが危機に陥るのがなんでそんなに嫌なんだろう、と不思議に思っていたのですが蛇足軒妖瀬布 さんの「敗者の物語」という鋭いご指摘でハタと膝を打ちました。
世の中には「敗者の物語」の深淵さを受け入れられず、ひたすら単純な「勝者の物語」に陶酔していたい、という人も多いのだと思います。
「敗者の物語」がビジネスモデルとなり得るか、という考察も非常に興味深かったです。