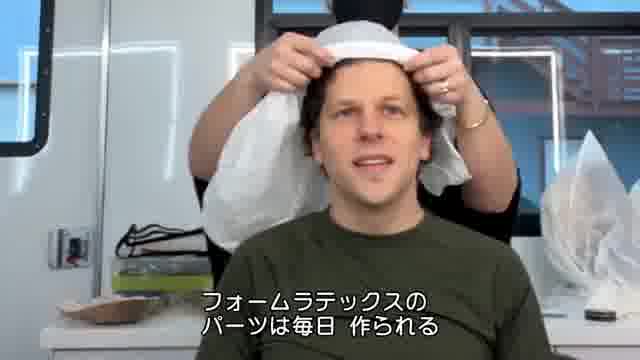サスカッチ・サンセットのレビュー・感想・評価
全59件中、1~20件目を表示
エンドロールの歌はサスカッチ語バージョンもあるよ
謎のイキモノ4頭が森の奥深くをさまよう生態が淡々と描かれて、一体何を見せられているのかと戸惑うばかりだが、しだいに彼らサスカッチが人間と自然をつなぐオーパーツではないかと思えてくる。サスカッチより進化してしまった人間なんて、マジで地球に対して害悪でしかないのではないか。命が生まれて生きて死んでいくサイクルとは、まあ大雑把にこの映画に描かれているようなものではないか。そしてもはやそれは失われてしまったのだと突きつけるラストは宮﨑駿の『もののけ姫』にも通じているのではないか、みたいにどこまでも話の風呂敷を広げていけるだけの奥行きと、それすらもバカげて思えてくるユーモアが同居している。
最初は全然4頭が見分けられなかったので二度目を観てみたのだが、今度はいかに繊細にそれぞれのキャラが演じ分けられ、描き分けられているのかがわかり、最初に思った以上に考え込まれたストーリーであることも判明した。しかし、最後の歌を主演のライリー・キーオに歌わせるだけでなく、サスカッチ語で歌うバージョンも録音したけどやっぱり使えなかったという話が実に可笑しく、ネットにサスカッチ語バージョンもアップされたので聴いてみてほしい。ほんと使えないって思うから。
あとこの監督たち、U-NEXTで観られる怪作ドラマ『ザ・カース』にも参加していたのね。ドラマの舵取りをしたベニー・サフディ、ネイサン・フィールダー、エマ・ストーンの御三方、実に的確な人選だと思いますよ!
我々はずっと何を目撃しているのだろう
ゼルナー兄弟は奇妙な映画を手がけることで知られる人たちだ。奇妙な監督が映し出す、奇妙な人たちの暮らし、人生、運命。しかしその目線は決して被写体を見下すことなく、じっくり愛情をもってスポットを当て続ける。登場人物がサスカッチのみという本作でもスタンスは変わらず。それどころか「セリフを全く用いない」というサイレント映画にも似た趣向によってそのスタイルがより強化されている。面白いもので咆哮や表情や身振り手振りで表現された生態は、序盤こそあまりに生々しいものの、一線を超えると非常にわかりやすい表現となって流れ込んでくるかのよう。彼らが我々と同じ猿人仲間の「ニア・イコール」な存在だからこそ、やや理解不能の味わいを残した「遠くて近い」関係性が共感と共振を呼び起こすのだろう。本作を楽しめるか、もしくは怒り出すかは観客次第。その反応をじっと伺っているのはスクリーンの向こうのサスカッチ自身なのかもしれない。
勘違いしたまま観ていて、“未知との遭遇”に驚喜
自分のぼんやりっぷりを白状するようで恥ずかしくもあるが、同じ体験をする人もいるかもしれない。次の段落から本作のある設定に言及するが、それを事前に知らずに観るかどうかで鑑賞体験が変わるポイントでもある。未見の段階でこのネタバレありのレビューを開く人はほとんどいないとは思うものの、もしそうなら、できれば観たあとで再訪していただけるとありがたい。ちょっと変わったコメディが好きなら、予備知識を仕入れずに本編を鑑賞すると結果オーライになる可能性は大いにある。
私のぼんやりというのは、映画冒頭で登場する毛むくじゃらの4人(4頭)が、現代人の祖先のような存在で、太古の森の中で暮らしていると勘違いしてしまったのだ。ちょうど「2001年宇宙の旅」の序盤でホモサピエンスの祖先が道具を使い始めて進化したように、この映画も「はじめ人間」的な彼らが、食う、寝る、交尾の牧歌的な生活の中で、少しずつ文明や文化を獲得していく話かなと、勝手に思い込んで前半を眺めていた。
だが、ちょうど本編の真ん中あたりで、太い立ち木の幹に真っ赤な「X」の印、明らかにスプレーか何かで描かれたその印を彼らが目にするとき、あれ、自分が思い込んでいた前提が間違っていたかもという疑念が。次に彼らが森を分断する道路に遭遇して驚愕するシーンで、疑念は確信に変わる。そうか、彼らが暮らすのは太古の世界ではなくて、現代の人里離れた山奥にある森だったんだと。
思えば、タイトルに含まれる「サスカッチ」がビッグフットや獣人の別称でも知られるUMAの呼び名であることを認識していたら、あるいは最初から現代の話として観ていたかもしれない。だが思い違いをしたことで、怪我の功名というか、思い込んでいた世界がまるで違うものだったと悟ったときの驚きは、鮮やかにだまされたと気づいたときの快感にも似た喜びだった。過去作でたとえるなら、M・ナイト・シャマラン監督作「ヴィレッジ」やジェラルド・ブッシュ&クリストファー・レンツ監督作「アンテベラム」に仕込まれたサプライズに近い効果があったというか。
ここからは日本の配給や宣伝への苦言になってしまうが、映画の公式サイトや予告編、それに当サイトの作品ページの上部に表示されるキービジュアルでも、サスカッチがラジカセを持っている、つまり現代の話であることを明示しているけれど、これは本作の楽しみを少なからず損なっているのではないか。比較のため英語版の予告編をチェックしたら案の定、時代設定は巧妙に伏せられている。現代の設定とは知らずに、サスカッチに同化して大自然の中で生きている感覚を素朴に楽しんでいたほうが、現代人の文明に遭遇したときの驚きも一緒に味わえる気がするのだけれど。
もちろん配給や宣伝の方々も実績のあるプロの集まりだし、洋画興行が厳しい昨今、作品の鍵となる設定やあらすじのかなりの部分を前宣伝で開示しないと興味を持ってもらえない、といったデータや経験則のようなものがあるのだろうと推測する。ましてや本作は、ジェシー・アイゼンバーグやライリー・キーオといったスターが出演しているにも関わらず、特殊メイクで全編ずっと識別不可能なままだし、売り込みも相当苦労しているのではなかろうか。
あまり本筋に触れないままのレビューになってしまったが、ほのぼのとしたユーモア、穏やかな人間風刺、そして作り手の並々ならぬサスカッチ愛が詰まった本作、私は大好き。“変”の方向性は若干違うが、ダニエル・クワン&ダニエル・シャイナート(通称:ダニエルズ)の初長編監督作「スイス・アーミー・マン」に近い、「久々に変な映画を観たなあ」という感動があった。
Parallel Stupidity
Sasquatch Sunset is a quirky comedy of errors that feels like a short film concept stretched to feature length. The irreverent, gross-out humor is reminiscent of Jack Black's Year One, but the film’s lack of dialogue elevates it to something approaching higher art, akin to the ape sequence in 2001: A Space Odyssey.
The biggest laugh came when I realized Jesse Eisenberg played one of the sasquatches, adding an unexpected layer of humor to the film. Produced by Ari Aster, Sasquatch Sunset succeeds with its "less is more" approach
なんとも言えない感覚
ヤラセ環境保護活動の落日
ジェシー•アイゼンバーグやライリー•キーオの特殊メイクに一体何時間かかったのだろうか。ほぼ原型をとどめないほどメイクされているため、雪男一家の長男がアイゼンバーグで、お母さんがキーオと言われなければ、誰が誰だかわからない。俳優としての知名度が作品に影響を与えないように配慮された非商業映画ということなのだろう。
全編台詞なしという演出も、これまた斬新といえば斬新だが、聾唖おじさんのうめき声にそっくりな鳴き声をあげるビッグフッド•ファミリーが、何に興奮し、怒ったり、発情したり、拒否ったりしてるのかが今一わかりにくい。一見この映画、自然環境破壊に警鐘を鳴らしているような気がしないでもないのだが、その本気度が全く伝わってこないのである。
『猿の惑星』のシーザー役の俳優さんが、まさにチンパンジーになりきって演じていたのとは正反対に、このサスカッチファミリーの所作は誰がどう見てもイベント会場や野球場にいる着ぐるみと同等のレベル。放置された人工物やまったく車の通っていない道路で、放尿したり脱糞をかます(余計環境を汚しているような気が💦)は、変なキノコを食べてピューマのメスに欲情するは、その動きはまさに“人間”そのものなのである。
過去に夢みがちな日本人OLを小馬鹿にした映画を撮ったこともあるゼルナー兄弟(しかも制作総指揮はあのアリ•アスター?!)だけに、本作は眉に唾をつけて観る必要があると思うのである。何が言いたいのかというと、世界各国で環境保護や人道支援活動を繰り広げているグレタさんのようなリベラル系アンティファの面々を思い切りこき下ろした1本なのではないだろうか。あんたたちのやってることは所詮“猿芝居”に過ぎないんじゃないのかい、と。
故に、動きを猿に近づけるリアリティ演出にこだわることもなく、わざとビッグフットの着ぐるみを着た人間のように振る舞わせたのではあるまいか。普段はベジタリアンのように大人しいくせ
にヤク(🍄)が入るとあたり構わずフリーセックス。子供さえ授かれば後は発情した雄などに用はないフェミニスト。そもそも人間がいないこの場所で、何がどう環境に悪いのかも詳しく説明できないまま大騒ぎ。それじゃまるで、観客が誰もいないのに博物館の前で客寄せ(大衆の目をこちらに向けるため)シンバル(警鐘)を鳴らす🐒のおもちゃと一緒じゃないか。環境保護というよりも、結局のところ金が目当てなんじゃないの。ね、グレタさん?
いろいろ出しまくる
生態
UMAサスカッチの生態を鑑賞する映画。
生も死もあり、生殖行為も排泄もある。
喜びと悲しみも勿論。
動物的に楽しめて、その世界に入る
込めるかどうかがポイント。
本能的に没頭か抑制か。
初めて見る舗装道路で興奮する
姿がインパクトがあったなぁ。
環境破壊や開発に追いやられた
動物達の身代わり的にも感じられ
社会派要素も入っていた。
私なりの考察
見る側一人一人の受け取り方がちがうというのは映画の醍醐味ではあるが、製作者が十何年も時間を費やしたというこの作品は、ただの自己満足ではなく、何か大きな伝えたいことがあるのではないかと私は考えた。
私が思う、この映画の伝えたかったメッセージというのは、人間の一方的な都合によって破壊される環境や土地開発への警告ではないかと考えた。それもこの映画のすごいところは1時間30分の時間の中に緻密に、かつ考察の余地を残しつつ沢山散りばめれているところだ。
至極当たり前に浸透している環境破壊やエコロジーについての人間の認識は、結局一人一人の意識を変えないと地球という大きな星は変わっていかない。それを映画という媒体で、それに興味がない人間にも考えさせるようにしむけているように思えた。その内容も、人間と野生動物の丁度狭間のようなサスカッチが主人公なのである。逆に上記のようなメッセージを来場者に伝えようとしたとき、主人公が人間であってもシカやクマなどの野生動物であってもサスカッチ程強く伝えることはできないであろう。
彼らは、見た目や生活は人と同じように生き、習性や本能は野生動物そのものだ。人間だけが進みすぎているがゆえに忘れかけていた皆同じ動物だという認識を、人と近い生き物とすることで植え付けつつ、皆が共生すべき世界を人間の都合だけで侵食し続けている現状へ警鐘を鳴らしているのだ。
においをかいで、口に入れて確かめるその習性が一環に描かれていたのは、人間が生み出し自然を侵食する無機物が本当に野生動物の習性を理解したうえで彼らにとって安全なものなのか見直すべきなのではないかという疑問の描写に思えた。
予兆もなくあっけなく死んでしまうシーンが見受けられながらも子育てや出産に苦難するシーンが印象的だったのは、ただでさえ自然界で子孫を繁栄していくことは難しいことを伝えるための描写であるように思えた。
自分以外のサスカッチが3匹しかいないがために数を3までしか数えられないシーン(鏡をみて驚いたシーンも含め)や、定期的に音を鳴らして仲間を探すシーンは、そのような環境でも絶滅がたとえ近くても希望を捨てず生きようとする野生動物の静かな叫びを描写しているように思えた。
もしこの映画に訳がつくのであればサスカッチは何を話していたのだろう。言葉が理解できない映像であるからこそ、本来の自然が生み出す緊張感が演出されていたような気がする。
私の考えがどうであれ、他人の考えがどうであれ、私はこの映画を見たことをずっと忘れないだろう。
私は私がうけとったままのメッセージを誰かにも伝えていくことにする。
そんなことを考えながら、本作品と好きなセレクトショップとのコラボレーションTシャツを一枚購入し、映画館を後にした。
セリフなしでも興味が維持できる映画です
元々観るつもりは無かったのですが、買い物ついでに初めて寄ったシネコンで会員証を作り、一番上映時間の近かった本作を鑑賞。
私もサスカッチの意味を知らないまま鑑賞しましたが、やはり、その方が楽しめました。
意味を知らない方は、調べたりせずに鑑賞するのがお勧めです。
言葉を持たない類人猿の物語で、セリフは、うー、おー、ほっほ、といったうめき声のみ。解説のナレーションも無し。でも、最後まで興味深く観ることができました。観てよかったと思える良作です。
公然と行われる排泄や性欲処理など、なんとも恥ずかしくいたたまれない描写もありましたが、それらを無い事にして生きている現代人も、実は日常的に隠れて行っている事であり、類人猿も現代人も変わりはしない、同じ生き物だと思い知らされ、やがて映画の中の類人猿たちに共感し始めました。
太古の昔、まだ言葉を持たない類人猿たちは・・・という雰囲気で映画は始まります。退屈そうな映画だなと思ったら、その後の展開にグイグイ引き込まれ、あっという間に物語は終盤を迎えます。
最後は、ああ、そうなのか・・・と謎の満足感に満たされましたので、個人的な評価は星5つです。
バカバカしい作品をシッカリ撮り切る事こそアメリカ映画の底力
ヒマラヤの雪男と並ぶ有名UMA(未確認生物)であり、アメリカ北部の森林に生息すると言われるビッグフット家族の四季を追った物語です。食う・寝る・やるだけの生活が台詞は一切なく唸り声だけで描かれます。でも、子供を可愛がり、死者を悼む彼らの精神世界が少しずつ伝わって来ます。とはいえ、やはりバカバカしい映画で、それが魅力でもあります。
傑作!とは思いませんが、「アメリカ映画界は凄いなぁ」と感じっ放しでした。こんな作品、日本ならば企画会議にすら上らないでしょう。でも、予算が付いて、名だたるプロデューサー・俳優が配され、情感溢れる音楽も響かせてこんなバカな映画をしっかり撮り上げているのです。こんな作品がある事が映画文化の豊かさの証なんです。
生きるって大変だ
サスカッチの生態を通して、生きることの厳しさを思い知らされた作品。
CGで良さそうなサスカッチだが、人間が演ずることで
動物らしさのリアリティがハンパなく出ていると思う。
サスカッチにとっては生きることに必死だが、
それが観ている人間にとってはコミカルに映ったりもする。
かたや自然界の厳しさも痛感するシーンも多々用意され、実にせつない気持ちにもなる
という、セリフが一切ないのに感情が激しく揺さぶられる秀逸さだ。
ラストシーンは実にシニカルに感じたが、うまいオチであるとも思う。
観客の中に、パパと息子(年少さんかな)がいたのだが、
息子にはツボに入るシーンが多々あったらしく、ケタケタ笑っていたのが印象的だった。
実に斬新な作品で一見の価値あり。
もっとふざけた明るい映画かと思ったら、真面目で悲しくなる映画だった。
情報一切なしでの印象から、社会風刺が効いたブラックコメディかと思っていたら、「サスカッチ・サンセット」は、その名の通り最後のサスカッチの黄昏の物語。
深い森林で仲間を探しながら移動するサスカッチ一族4人の生活を、四季を通して描く。
春夏では食事や性交など滑稽な場面から、大自然の中の危険でシリアスな場面に移っていく。
秋冬では、人間がいた「形跡」と接触し始める。
これまでUMA(未確認生物)を描く場合は、人間からの視点ばかりだったのに対し、本作では、UMA側から描いているのがミソ。
こちら側から観ても、ごくまれに目撃するだけ出るのと同様に、向こうから観てもすぐに直接接触出来たりはしない。
予備知識シャットアウトで観ていたので、てっきり大昔の話と勝手に思っていたら、中盤で現代であることが判明。
(ここで、とあるシャマランの映画を思い出す。)
いつ見つかってしまうのではないかと、ハラハラして観ていた。
そして最後、彼らは呆然とする。
とても悲しいラストは想定外。
排せつや性交など、人から見ると露骨な表現はあっても、動物の生態だと思えば普通のこと。
もっとふざけた明るい映画かと思ったら、真面目で悲しくなる映画だった。
彼らはその後、広大で深遠な山奥に戻って、数少ない仲間に出会って幸せに暮らしてほしい。
真面目にふざけてる
雄大な自然の中で暮らす毛むくじゃらの生物・サスカッチ(ビッグフット)の冒険を、圧倒的映像美と幻想的な音楽によりドキュメンタリータッチで描いた異色作。(公式より)
なんとか、頭を捻って説明文を絞り出したな公式の人。
間違ってはない、間違ってはいないが!
とにかくこの、サスカッチ・サンセット。監督と、オス・サスカッチ役のジェシー・アイゼンバーグとメス・サスカッチ役のライリー・キーオはノリノリで楽しんで撮影していたに違いない。
ウホウホ言いながら「交尾をする」「マーキングでシッコとウンチをぶり撒く」「股間を掻いた指をすんすん嗅ぐ」描写が必要以上に執拗でお下品。
野生の自然な営みと見せかけて、よく考えたら誰もサスカッチの生態なんて知らないんだから、ここぞとばかりに悪ノリで演じてるでしょこれ。
こんな演技は「サスカッチ・サンセット」以外の現場で披露しようが無い。
サスカッチの中身が「ソーシャル・ネットワーク」のザッカーバーグと「怒りのデスロード」のワイブスだと考えたら頭がクラクラしましたよ。
オス・サスカッチの亡くなり方も最低で最高!
メス・サスカッチから交尾を拒否され、怒って巣を破壊したら子供サスカッチ達からも「出てけ!ダメ親父」とばかりに逆襲され、ふてくされて森に出奔。
森でキノコを食べてラリって肉食獣に交尾を迫り、逆に食べられてしまうという、「どこが、自然の厳しさやねん!」と吹き出してしまいました。
映像自体は美しいのに内容のギャップ。これは監督が真面目にふざけている。決して半笑いで作った作品ではないのが伺えて好感は持てます。
「いったい、自分は何を観せらていたんだ…」と呆然とする観賞後感。異色作としか言いようがない。
全59件中、1~20件目を表示