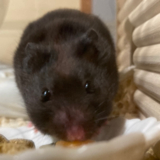フロントラインのレビュー・感想・評価
全574件中、41~60件目を表示
マスコミの存在意義
面白かった。脚色はしていると思うがダイヤモンドプリンセス号でこんなことがあったのかなと感じさせられた。専門ではないDMATが自分達しかいないと奮起して活動しているのは見ていてわかる、もし自分が乗船員だったら感謝しかない。
マスコミは視聴率気にするとこちらを煽る偏重的な放送はするんだろうなあ、数字が取れなければ担当者は大変かと思う、それは世の中の営業マンと同じ。数字があってこその仕事だが、では世の中のサラリーマンが数字取るために欺瞞や詐欺、嘘で固めた仕事をしてまで数字を取るかと言われるとほとんどの人はしないでしょう。もししたら新聞、テレビなどのマスコミさんで報道されかねない。やっていいことと、悪いことの区別くらい人として持っている方々が多いと思う。最近ではオールドメディアと呼ばれるマスコミはやってはいけない一線を越えているような気がする。
感染症対策がメインだったがそこが1番考えさせられる映画だなと思った。
乗客と接する最前線のヒロコ(森七菜)
大画面で観て正解でした。臨場感を楽しめました。長回しワンカットもあり、カメラワークが見ごたえがあります。
ヒロコに扮する森七菜さんが沢山登場して良かったです。
仙道(窪塚洋介)が好きです。キャラクターが窪塚洋介さんらしくて良かったです。
苦悩する結城(小栗旬)が主人公というところもポイントで、純粋で真っ直ぐな性格で好感が持てました。『シン・ゴジラ』(2016年公開)のパニック感を思い出したり、ゴジラつながりで『ゴジラVSコング』(2021年公開)に出演した小栗旬さんの変顔を思い出したりしました。
ダイヤモンド・プリンセス号の乗客が亡くなったとしても、DMAT隊員のせいでも受け入れた病院のせいでもありません。
この映画は、いろんな状況に置き換えて考える事ができて素晴らしいと思いました。
-- 妄想 --
①ダイヤモンド・プリンセス号が日本の横浜港に来たタイミングで騒ぐ計画。
②PCR検査というキャリー・マリスの発明をマッチポンプのために使用する。
③マスコミであっても例外は無く、組織の頭は身内以外には冷酷非情である。
④COVID-19は特許が存在する人工的なウイルスで、本当に怖いのは人である。
悪くはないが…。
作品性はひとまず置いといて、DMATの真実を描くという意味においては思惑通りの作品に仕上がったのだろう、という印象だ。
この作品を語る際に、当然ながら全員が当時のコロナウイルスやパンデミックの恐怖、感染への不安、当時の首相による「緊急事態宣言」などの話になってしまうと思う。だって皆が実際にコロナ禍を体験している「当事者」だから。つまり全員に「思い出」があり、誰もがコロナ禍を振り返れば何らかの感傷的な思いに浸ってしまうはずだ。
ただここで考えさせられる。
実際に体験して得たこれらの個人的なエモい感情と、いち作品に対する評価をどこまで混ぜ合わせるべきか、そのさじ加減がとてもとても難しい。例えば自分の友達が芸能界デビューしたらめっちゃ応援してしまうだろうが、その目線で盲目的にタレントとして褒めちぎってしまうと、友達としては正しくても何かしらの評価を下す人間としてはどこかフェアじゃない気もしてしまう。個人的な思い入れも大切だが、映画を観たときのレビューは基本的にフェアにしたい。そう考えるとこの作品に対する評価はそれほど高くはならないのだ。
あの時何が起きていたのかを知れたのは良かったし、DMATの活動には本当に敬意しかない。もしこれがドキュメンタリーだったら高評価に出来たのだが、あくまでも映画作品として冷静に観てしまうと「それなり」という印象に落ち着いてしまうわけで、それが面白くもあったが残念でもあった、というのが僕の正直な感想だ。
あの事件の再検証 「映画の持つ力」
映画『フロントライン』──人道と不可知の境界で
2025年公開の映画『フロントライン』は、2020年2月、日本で初めて新型コロナウイルスの集団感染が発生した豪華客船「ダイヤモンド・プリンセス」を題材に、未知のウイルスに最前線で立ち向かった医師や看護師たちの闘いを描く。
この作品は単なる再現ドラマではない。
脚本家が実話を基にオリジナルを書いた理由は、「正しい事実」を伝えないメディアに代わり、事実を再検証するためだったのだろう。
私たちは「正しさ」について思案する。
しかし、誰も一歩を踏み出さない。
踏み出した者を報道がどう扱うか、その反応が読めない怖さがあるからだ。
開業前の病院が感染者を受け入れた勇気ある行動も、報道次第で意味が変わる。
かつて「ペンは剣よりも強し」と謳われた言葉は、今や死んだ。
正義を語るはずのペンは、同意しない者を罰する暴力に成り下がった。
LGBTやSDGsの名の下に行われる「同調圧力」と同じ構造だ。
映画は、メディアの腐敗を鋭く突く。
DMAT統括の結城が「面白がってるんじゃないか?」と記者に向かって吐き捨てる場面は、報道の本質を暴く一撃だ。
だが、脚本は単なる批判に終わらない。
上野記者の葛藤に、不可知論的な「希望」を忍ばせる。
人間は完全な正義を知り得ない。
それでも、期待する心が物語を支えている。
思い出すのは1995年の地下鉄サリン事件だ。
聖路加国際病院の院長・日野原重明は、正体不明の物質に怯まず、献身的に治療に当たった。
あの人道的対応は、失われてしまったのか?
コロナでは、ウイルスの正体が判明していたにもかかわらず、医師たちは受け入れを拒んだのか?いや、そうではない。メディアが家族を危機に追い詰めるからだ。
本作が描くのは「責任」だ。
検疫官の責任、厚労省の責任、DMATの責任、現場の責任、そしてクルーズ船クルーの責任。
それぞれが負うべきものと、立場上負えないもの。その狭間で、人道的な正しさが問われる。
正しさは時代によって変わる。
しかし、人道的正しさには普遍性がある。
法律やルールがあっても、人道こそ最優先されるべきだ。
映画の終盤、六歳前後の外国人兄弟を分断せず、陰性でも陽性の弟と一緒にいさせる判断が描かれる。
もしそれが事実なら、日本を誇りに思う。
リアルホスピタリティは、単なるジャパンクオリティを超えた行為だ。
『フロントライン』は、歪んだ報道への一槍であり、「正しさ」の再考察である。
そして何より、人道的視点に立った行動が窮地を救うことを示す映画だ。
この魂が、「今現在」の日本にまだ残っていることを願ってやまない。
パンデミックで世界は何を失ったのか
世界中の人がリアルタイムで体験し、社会が変わったパンデミック。日本にとっての始まりだったあのニュース。あれから時は経ち、とは言ってもほんの4年程度。気がつくといつの間にか感覚的には「完全過去」な感じ。あの騒ぎは何だったのか?って思ってしまう間違った感覚が怖くなりました。
世界中で多くの人がなくなり、外に出ることも出来ずにじっと家の中に閉じこもりの生活。人と接するのはオンラインが当たり前な社会に突然変化して、そしてほんの(たった)4年でまた元の社会に戻ってきている現在。。。
実話なので救いもなく話が淡々と進むところに、逆に色々と考えてしまいました(映画として一部脚色してるので話としてはハッピーエンドで明るいです)
あの頃、自分はどう思っていたか?
誹謗中傷や差別、偏向報道は許せない。
でも頭では分かっていても、携わってた関係者やその家族が身近に居たら怖いという感情は仕方ないし、
この頃の報道を見てどう思ってたのかは覚えてないし、
実際まだ対岸の火事、どこか映画の世界みたいな感じでネタにしてたような気もするし、
件の医師の動画が報道され(それすらあまり覚えてない)対応が悪い何やってんだとか思ってたのかもしれないし、
少なくとも尽力してくれたクルーや医療関係者の事を思いやった事は確実にない。
なのでこの映画を見て、マスコミはクズだとか、携わった医療関係者の家族を差別するなんて酷いとか、思ってはしまうけど、結局のところ自分も同じ穴の狢だな、
と思い知らされました。
とにかく尽力してくれた方々に敬意を
それだけでも有意義な映画だったと思います。
知らんけど
医療従事者にもっと敬意を
2020年、ここから始まったような気がするダイヤモンドプリンセス号のコロナ騒動、医療関係者の命がけの活躍で、被害は最小限に留まったように思う。
DMATはこの時、初めて知った。
全世界が同時にパニックに陥ったが、得られた教訓は活かされているのだろうか。
コロナ禍
自分も当時のことを思い出してみると、ニュースをただ観てる側だったので
最前線(フロントライン)に立っておられる方々の苦労にまで考えが及ばず
ただ『未知のウイルス』というだけでかなりの恐怖だったのを思い出します。
今では遠い昔のようですが、5年前は、分散勤務やテレワーク、コロナ休暇のような制度もあり、三密や濃厚接触者とか様々な言葉が飛び交っていた気がします。
マスコミが全て悪いとは言えませんが、映画で出てくるように悪意というか面白く視聴率が取れるだけのニュースを求めている大衆心理も問題なのかもしれません。
いずれにせよ、自分の身をなげうってでも危険に対し、困っている方々を救おうとする人を外野から非難するのではなく
後方支援とは言えないまでも、せめて温かく応援できる人間になりたいなと思います。
予告見た予想とは違かったけよかった。
まだまだ記憶に新しいけど、これからも忘れてはだめ
映画館での公開を見に行こうと思っていて、行けなかった作品。VODに出てきたので早速視聴です。
このダイアモンド・プリンセスでのCOVID-19集団感染が起きた時点では、まだ日本では対岸の火事だったんだよね。この作品でも描かれているように、藤田保健衛生大学病院に収容して、暫く日本国内は(表面上)何とかなっていたけど、その後は日本国内に蔓延して行ったのは歴史の通り。
確かにこの時点では、この作品で得かがれている要因DMATがなって無いとかいろいろと言われていた。でも、いみじくも小栗旬演じる結城が言う通り、人道的に正しいのは、このDMATの活動だったんだろうな。だって、感染症専門医も撤退してたからね。
それと、藤田保健衛生大学に搬送中、急変があったという事は、この作品で初めてしりました。このあたりは、一般のテレビとかではほとんど報道されて無いんじゃないかな。大変だったな。
最後に。この作品でめちゃめちゃ興味深かったのは、厚労省の立松を演じていた松坂桃李。本当にあんな無茶する官僚がいるのかと思うけど、どうなんでしょうね。でも、なんの力も無い官僚だったわけではないだろうから、課長代理くらいだったのかな??それだと偉すぎ?物語終盤『踊る大捜査線』の青島と室井の約束の如く、結城が立松に「偉くなれ。そうすれば現場がやりやすくなる」というのは、中々面白かった。
新型コロナウイルス感染症の初期段階、横浜港に停泊した「ダイヤモンド...
新型コロナウイルス感染症の初期段階、横浜港に停泊した「ダイヤモンド・プリンセス号」で起きた集団感染。
その最前線に立った医療従事者・関係者たちの知られざる奮闘を描く社会派ドラマ。
当時はウイルスの正体も不明で、効果的な治療法も確立されていない“手探りの戦い”。
限られた情報と圧倒的な不安の中で、現場の医師や看護師、保健所職員、自衛隊、検疫官たちはただ目の前の人命を救うために奔走していた。
作品は派手な演出に頼らず、現場の緊張感、疲弊、葛藤、そして使命感を淡々と積み重ね、観る者の胸に“当時の空気”を確かに呼び戻す。
医療従事者に、ただ敬意を。
この言葉に尽きる作品だと思う。
忘れかけていたあのときの状況を、誇張せず、過度に感情的にならず、真摯に描き切った力作。
もっと多くの人に観てほしいと強く思わせる1本。
伝承としての映画の役割
レジリエンス
コロナ禍の往時は、「今は距離をとって」が合い言葉になり、会合・集会の類(たぐい)は中止、大型商業施設も「自粛」で、休業したり、営業時間を短縮したり…。
本当に、散々たった記憶が脳裏から拭えません。
しかし、中世ヨーロッパに黒死病(ペスト)が流行した当時は、感染の収束を祈って皆で教会に集り、そのことが、いっそうの感染爆発を引き起こしていたのではなかったか―とも思われます。
それから時代を下って、令和になっていた今回のコロナ禍―。
いわゆる「三密」を避けて、少しでも感染のリスクを下げることを思いつくことのできた人類は、知恵がついて、往時よりは(少しだけ?)賢くなっていたと言えるのかも知れません。
人間は、経験から学ぶ生き物ですけれども。
こういう試練を経て、社会的動物としての「ヒト」はレジリエンス(困難や逆境への適応力、困難や逆境からの回復力)を高めて、令和の今まで生き延びて来ることができたのだろうとも、評論子は、思います。
本作の画面からも、その試練ー困惑と緊迫感、そして苦悩とか、犇々(ひしひし)と伝わってくるようにも、評論子には思われました。
新型コロナウイルス(COVIT-19)の感染拡大を素材として、そのことを見事に描き切った一本としては、充分に佳作としての評価に値するものだったとも、評論子は思います。
なお、このレビューを書くについてに、後記のとおり参考にさせていただいたレビュアー・しゅうへいさんには、末筆ながらハンドルネームを記して、お礼としたいと思います。
(追記)
「災害は忘れた頃にやって来る」というのは、物理学者・寺田寅彦のことばだそうですけれども。
実は、お役所などの災害対応は、未経験の職員での対応を余儀なくされるのが普通です。
大きな災害は滅多に起こらないので、いちど大災害を経験した職員は、その後異動したり退職したりしていなくなり、いざ発災した時には、前回発災の後に異動してきた、未経験の職員ばかりでの対応を強いられるということです。
結局は、経験のない中で、経験がないなりの知恵を絞って、未曾有の感染拡大に対応しなければならないということでしょう。
その意味では「マニュアルの無い未曾有の事態に直面すれば右往左往してしまうのが官僚」というレビュアー・しゅうへいさんの指摘は、正鵠を得ているというべきでしょう。評論子も(自身を含めて)「まさに、そのとおり」と思います。
なお、医療機関の世界とて、その「ご事情」は、あまり変わらないのではないかと、評論子は思います。
(追記)
いわゆるDMATは、もちろん災害医療チームとして編成された組織ではあるのですけれども。
設立にあたって想定されていたのは、大地震や集中豪雨などの自然災害(物理的な事象を伴う災害)だったことは間違いがなく、今次の新型コロナウイルスといった、大規模感染症の流布は、「災害」として想定されていなかったことも、間違いがないことと思います。
それゆえDMAT自体、おそらくは外科医や整形外科医、救急救命士といったスタッフ中心に編成されていたことでしょう。
最近は、大規模災害時ても精神科領域もクローズアップされているようではありますけれども。
これも「社会手なレジリエンスの強化」の一場面と言えるのかも知れません。
(追記)
本作については、コロナ禍のときのマスコミ報道についても、いろいろとコメントが寄せられていますけれども。
評論子も、これには苦々しい思いをした記憶があります。
ひところのテレビでは「新型コロナウィルスの致死率は季節性インフルエンザの数倍」と放送されていましたが…。
そもそも、厚生労働省の資料では、季節性インフルエンザの致死率は0.01%のオーダー(多くは基礎疾患を有していると思われる60歳以上でも0.55%=肺炎を併発して亡くなるケースが多い?)
その「数倍」といっても、もともと高が知れていたというべきでしょう。
そのことにはいっさい触れずに、ただ「数倍」とだけ喧伝(あえて「喧伝」といいます)するテレビの姿勢には鼻白む思いをしたことが、評論子には思い起こされました。
(追記)
冒頭に記したとおり、コロナ禍の当時は、街中に「今は、距離をとって」という掲示が、いたるところにありました。
昔むかし、同じクラスの女子に、思い切って声をかけてみたということが、ありました。
極度の緊張とあまりの衝撃に、アタマが真っ白になってしまい、彼女の一言一句は覚えていないのですが、要するに「今は、距離をとって」というような返事だったことを、かすかに覚えています。
それが、やおら半世紀を経てから、まるで評論子に対する当てつけであるかのように、どこに行っても「今は距離をとって」…。
公権力に逆恨みされるような心当たりは少しもないのに…と思う評論子でもありました。
(追記)
ペストはなぜ黒死病と呼ばれたか―。
ペストは中世ヨーロッパで大流行し、人口の約4分の1が命を落としたといわれています。
ペストが「黒死病」と呼ばれるのは、感染者の体に現れる症状に由来します。
ペスト菌に感染すると、リンパ節が腫れ、やがて破れて化膿し、皮膚が黒く変色していきます。特に脇の下や足の付け根に腫瘤ができ、強い痛みを伴いました。その後、高熱や全身の倦怠感が現れ、急速に悪化していきます。
このように皮膚が黒色に変わっていくため、人々は恐怖を込めて「黒死病」と呼ぶようになったのです。
[出典:『知って得しない話』北嶋廣敏・著/グラフ社・刊]
全574件中、41~60件目を表示