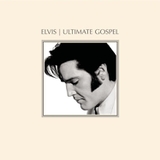木の上の軍隊のレビュー・感想・評価
全249件中、221~240件目を表示
上官の心境の変化や、作品のメッセージがよく分からない
木の上に身を潜めた2人が、虫を集めたり、ソテツの団子を作ったりして飢えをしのぐ序盤の展開には、生きるための切実さを感じるし、米軍のゴミ捨て場から食料や日用品を拾い集めて生活を安定させる中盤の様子からは、のどかで穏やかな雰囲気を味わうことができる。
伊江島育ちの新兵が抱く、親友とその妹を亡くした悲しみ、米兵を殺してしまった罪悪感、故郷が殺し合いの場になってしまった悔しさも、ずっしりと心に響いてくる。
その一方で、米軍の缶詰を食べることを拒否するほどの国粋主義者だった上官が、おそらく終戦を知ってお祭り騒ぎをしている米兵達を見て、米軍の残飯を漁るようになったのは、果たして、米軍と戦うために生き延びようと決めたからなのか、それとも、ただ生き延びるためだけに思想や信条を捨てたからなのかがよく分からなかった。
彼らが、島民との置き手紙のやり取りを通じて終戦を知り、上官が新兵の姿に自分の息子を重ね合わせたところで、ようやく投降の意思を固めたのかと思ったら、そこから、新兵がハブに噛まれたり、上官がゴミ捨て場で島民と遭遇したり、あるいは、新兵が書き残していた日記を発見したりといったエピソードが続いて、なかなか投降に至らない展開には冗長さを感じてしまう。
ここでも、上官が、如何なる心境の変化で、投降することを決意したのかがよく分からなかったので、例えば、新兵の日記がきっかけであるならば、そのことを、もっと分かりやすく、シンプルに描けなかったものかと思えてならない。
観終わった後も、単に、サバイバルの様子を通じて命の大切さを伝えたいだけだったのか、それとも、兵士に投降することを許さなかった日本軍の非人道性や、信念のために困苦を耐え抜いた日本人の辛抱強さを描きたかったのかがよく分からず、そうした作品のメッセージが感じ取れなかったところには、物足りなさを感じざるを得なかった。
木の上と海と花と帰りたい顔!
戯曲が作品として完成されているので基本形には非の打ち所がない。
こまつ座、井上ひさしにハズレなし。
演劇は観るものが木の上の様子や死体の山も海も想像力で補う必要がある。そこが演劇の良さだけど、これを映画で撮る意味はやはり演劇では表現できない臨場感のある映像の部分になるかと思う。
木の上の再現度がすごい!どんどんユートピアになっていくその変化が面白い。
最初は頑なにアメリカの缶詰を拒んでいたのに、木の上はどんどん豊かなアメリカになっていく。
後半の海や沖縄の鮮やかな花が美しい。堤真一と山田裕貴の表情のアップもいい。舞台ではこんなに拡大した表情の変化は眺められない。
2人の素晴らしい演技に涙がつーっと頬を伝った。
後半、こまつ座にも出ている山西惇も好演。いい映画に仕上がっていて嬉しくなった。曲がもっとかっこよかったら満点だなあ。
戦争の悲劇を忘れてはいけないが、賛否両論になる映画だと思う
堤さんと山田くんのTV番組での宣伝と、子供達を含めて沖縄本島の方々も観に行かれているし、沖縄戦から80年なので公開初日に観に行きました。
2週間前に沖縄に行って伊江島を見てきたので余計に感じたかもしれませんが、「島民」の方々の標準語が気になりました。
勿論うちなーぐちでなくても、イントネーションや、〜さぁ〜等、もう少し「沖縄」を感じさせて欲しかった。
なので、途中から何処の戦地だっけ?、2年間って事だけど「横井庄一さんは30年弱だったなぁ」って、余計な事を思ってしまった。
また、蛆虫が湧いたから「足を切断する」って思ったら大丈夫だった。不思議。
演技の方では、山田くんが「帰りたい」を連呼したシーンでは他の方々も涙していました。
あと、他の方もレビューしていましたが「プレイボーイ」の部分は必要だったのか?
結論。何に対しても「当たり障り無い」戦争映画でプラスアルファが欲しかった。
【今作は沖縄戦で孤独な戦いを続けた二人の兵士の姿を描いた井上ひさし原案の同名舞台の映画化であり、戦争の愚かさや生き抜く大切さを描いた作品。戦後80年を迎えた日本に反戦メッセージを伝える映画でもある、】
■1945年。
沖縄の伊江島で日米両軍による激しい攻防が続いていた。敗戦濃厚な中、本土から来た山下少尉(堤真一)と、伊江島生まれの新兵アゲナセイジュン(山田裕貴)は、大きく枝を広げるガジュマルの木の上に身を潜める事になる。
◆感想
・今作は、冒頭で実話と出る。戦争終結を知らずに生き抜いていた兵士と言えば横井庄一さんや、小野田寛郎さんの事を思い出すが(と言っても、年代的に後年知った。)沖縄でも期間は2年だが、同じような人たちが居た事に驚く。
・最初は、厳しさを見せていた山下少尉が、アゲナセイジュンが折角見つけて来た米軍の缶詰に手を付けなかったり、山下とセイジュンとの関係が上官と部下だったのが、時が経つにつれ、セイジュンが栄養失調になった山下に、わざわざ日本の缶詰の中に米軍の缶詰の中身を入れて食べさせたり、島の食べ物やハブについて教えていく過程の中で、関係性が変わって行くのが面白かったな。
・戦争が終わった事も知らずに、ガジュマルの木の上で生活をする中で、山下少尉も笑顔を見せるようになり米軍のゴミ捨て場でアメリカのエロ本を見つけて嬉しそうにしたり(男だったら、気持ちは良ーく分かるぞ!)、山下少尉が上手そうに残飯のスパゲッティを食べる姿も、何か可笑しかったな。
ここは、軍隊の階級の愚かさと、その柵が無くなれば只の人間同士っていう事が言いたかったのではないかなあ。
■今作では、名優堤真一を相手に、アゲナセイジュンを演じた山田裕貴の演技がとても良かったと思う。
米軍の爆弾で死んだ母や妹や戦死した戦友与那嶺(津波竜斗)の幻影に悩まされる彼が、最初は玉砕を唱える山下少尉に”生きましょう””帰りましょう”と訴えかける姿や、後半は自らの想い”生きたい!””帰りたい!”と口にする姿は沁みたな。
そして、アゲナセイジュンは、全ての武器を捨てて海に入って行くのだが、それを必死に追う山下少尉の姿は、最早階級を越えた親友を助ける姿だと思ったなあ。
<今作は、沖縄戦で孤独な戦いを続けた二人の兵士の姿を描いた故、井上ひさし原案の同名舞台の映画化であり、井上さんが終生抱いていた戦争の愚かさや生き抜く大切さを描いた作品である。>
「戦争映画」というより「生きる」を考える映画
太平洋戦争終結から80年。当時0歳の赤ちゃんが80歳の老人になるほどの年月。地球上から戦争が完全に無くなったわけではないが、日本では戦争を体験として語れる人は少なくなった。
私自身、直接身近な人から戦争の話を聞くことは出来なくなって久しい。どうして祖父からもっと聞いておかなかったのだろう、と思うと同時に、どう話していいのか祖父自身もわからなかったのかもしれない、とも思える。
「木の上の軍隊」は終戦を知らずに2年間、ガジュマルの枝に身を隠した2人の物語だ。元となった舞台版には無い、伊江島の戦闘シーンから始まり、次々と制圧され、仲間を失い、木の上に身を潜めることになる。
ここまでは記録ドラマのように感じるが、実際に伊江島のガジュマルの木の上で撮影された2人の潜伏パートからは、2人の個性がぶつかり合い、互いの価値観の違いがにじみ出た見応えあるドラマへと突入していく。
本土から来た上官役の堤真一、現地の新兵役の山田裕貴。最初は窮屈な木の上で息を潜めていた2人が生き残るために木の枝を増やし、敵の目を掻い潜って水や食料を探し、そうこうしているうちにだんだんガジュマルに馴染んでいく様も面白い。
この映画では「生きる」ことが最大の目的で最大のテーマだ。
生きる。戦争を諦めないために。生きる。死んでいった仲間たちのために。生きる。おめおめと戻れはしないのに。生きる。帰る家もないのに。生きる。何もかも変わってしまったのに。
生きる。何のために?
上官と新兵、年齢も、出身地も、考えてることも、今までの人生も全然違う。そんな2人のサバイバルを通して、生きることの難しさ、何でもない日常の尊さを観る側に投げかけてくる映画だった。
同時に、山田裕貴扮する新兵は「沖縄」そのものを表している。彼は言う、「失くした靴を見つけた丘は、今は米兵を殺した場所です。もう元には戻らないんです。」「僕の帰る場所はここしかないんです。」
いろいろな出来事があって、支配者も変わり、恐ろしい出来事も多く、今でも望まぬ変化に晒されながら、それでも沖縄の人にとって、沖縄はかけがえのない故郷で、家だ。
だから、「帰りたい」と思う。例え誰も待っていなくても。
映画の最後まで、新兵は名前を呼ばれない。映画の中で2人は個人ではなく、2名の日本兵として戦争の縮図、本土と沖縄の縮図として存在し続けた。
上官である山下少尉が心の底から敗戦を認め、生き残るために支え合ってきた彼を「安慶名」と呼んだ時、「もう帰ろう」と呼びかけた時、初めて2人の戦争は終わったのだと思う。
沖縄ロケ、沖縄のスタッフ、沖縄出身の俳優やアーティストが多く起用され、遠のく戦争の記憶を「他人ごとじゃないんだよ」と呼びかける良作だった。
真剣だからこそ思わず笑えてしまう部分もあり、誰でも見やすい映画に仕上がっていると思う。
個人的には多少見づらくなっても、編集でテンポにメリハリをつけた方がいいんじゃないかと思ったが、「誰でも見やすい」方がテーマにはあってるのか、とも思えてきた。
戦争=地獄
前半は米軍との戦い、後半はまさにサバイバル生活でした。原作は見読ですが、2年程このサバイバル生活を送っていたとは驚きです。
特に大したことは起きないし、けっこう長く感じましたが、戦争の悲惨さは伝わってきました。
米軍の爆撃で耳から血を流して死んでしまう女性は、とてもショッキングでした。
『ニッポン』という国が見ている幻影
恥ずかしながら帰ってまいりました!
終戦を信じられず(知っていた⁉)グァム島のジャングルで28年間、暮していた残留兵、横井庄一氏の帰国第一声である。彼を迎い入れるニッポンという国は、彼にそう
“言わせた!“
太平洋戦争の南方戦では、日本軍の人肉食話が多く報告されたが、本作はその範疇ではない。時折、堤真一のコメディタッチも、のぞかせながら重くならず観られる。
弱っている上官•山下(堤)を救おうと、大和煮カンヅメの缶に“敵製品“を入れ替えて食べ続けさせていた安慶名(山田)、それに気づいた山下は、ふいに拳銃を安慶名に突き付けつけたりするが、米軍の宴会騒ぎを目撃し、彼等が去ったあとの残飯に飛びついて飽食する。物語は、上官•山下の精神的支柱である軍人勅諭の“かたくなさ“が氷解してゆく過程を丁寧に描いていて、堤真一はさすがの演技!
樹上の2人の会話は、もはや、戦時中という現実世界を離れ、次第に角が取れて、にんげん対にんげんの禅問答の様相を帯びることさえあるが、時には、大声で“キレ”て、胸の裡を吐露し、心の平衡をなんとか保とうとする。
だが、あの手紙によって終戦を知らされ、目的を失って愕然とする。自分達の時間はなんだったのか?もう、敵は去った。空虚さは埋めようもない。全編通じて上手いと思ったが、この辺の山田裕貴は絶妙!
安慶名に自分の息子を重ねていた上官、またヨナミネの幻影を多く見てきた安慶名、2人は手を取り合って帰ろうと言う。
この映画は沖縄戦の悲劇を十全に伝えるものではない!
しかし、堤真一、山田裕貴の演技は素晴らしかった。
こんにち、世界がまた、分断及び右傾化の流れに拍車をかけ、紛争も常態化しているなか、本作をこの時期公開の季節性のものと侮ってはならないと思った。
決してシチュエーションとかではなく
異常なくらい傑作が多い今年の邦画でまた素晴らしい一品
実話を元にした物語。小野田少尉か横井さんか。こう言ってピンと来る人は同年代。
そういうサバイバル・ドラマは昔すでに作られたと思うし、TVでいわゆる再現ビデオ風のをいくつも観ているので新味がないかも、と感じていたが、かつて井上ひさし原案で舞台化されていた、加えてこの2人の名優が演じる、となれば観ないわけにはいかない。
そして、出来は期待以上だった。
一般に「2人だけのチームは良くない」と言われる。反目し始めたら収拾がつかないからだ。
しかし、どうしようもなく2人で居ざるを得ない、逃げ出せない極限状態で、人間はどうやって折り合っていくのか。
飢えているのに、敵の捨てた残飯なんか食えるか、と日に日に衰弱していく山下少尉(演: 堤真一)。
お願いですから食べてくださいと懇願する新兵の安慶名(演: 山田裕貴)。
そして安慶名は一計を案じて山下を救う。
しかしこのようなシーンによって時系列で単純に和解が進むわけではない。全編を通じて、2人の権力勾配は微妙に崩壊し逆転し、そしてまた復活する。
徹頭徹尾、山下は上官らしく居丈高だ。そこに地元出身の安慶名の、独特のおおらかさがまったく噛み合わない。
上官の概念的で狂信的な「撃ちてし已まん」「生きて虜囚の辱めを受けず」の軍国世界観と、新兵の地に足を付けた「ねぇ、生きましょうよ」「帰りたいです」という切望が鋭く対比される。
そう、まさに安慶名は木の上ではなく、大地に足を付けたかったのだ。
こうして反目と協力、いがみ合いと慈しみ合いが何度も交錯する。
この一筋縄ではいかない揺り戻しに観客は振り回され、結末を最後まで予想できない。
堤真一は、この人しかこの役はやれんだろう、と思うほど適役。
山田裕貴の演技はもう何も言うことない。ただただ、揺さぶられる。いい役者だなぁ、本当に。
敗戦80年の今年、これ、絶対にオススメです。
日々の暮らしに感謝して
今この自由で平和な世界に生きている事に感謝する為に、時々このような作品を観ることにしている。
この時代に生きた人々がどんなに辛かった事か。
もし戦争になったら?
自分がこんな状況になったら?
想像しながら観ていると怖くなってくるが、時々笑えるシーンがあったり、外国の映画でよく描かれるような激しい戦闘シーンも無くホッとする。
主演2人の演技も素晴らしい。
頑固上官の都合DAYS。
太平洋戦争末期の1945年の沖縄県伊江島、米軍襲撃でたった二人の軍隊となり木の上に潜伏する上官・山下と、地元沖縄の新兵・安慶名セイジュンの話。
終戦してることを知らず木の上に身を潜めた2人の2年、実話に着想で見せる。
米軍の攻撃、見つからない様にと木の上に身を潜める姿にはハラハラ、木の上の生活に少し慣れ米軍の動き緩まりで、少し噛み合わない2人のトーク、ふいに戻ってきた米軍から隠れれば小便かけられ笑える。
落下傘下にあった食料見つければ米軍食料だからと拒む上官の頑固さにも笑えるし上官都合のルールで送る日々、拾った洋エロ本からの流れのタバコの下りはさらに笑えた。
作品として笑えるシーンはあったものの実話作品、ホントは家に帰りたいが見栄と頑固さで帰りたいと言えない上官と、早く帰りたいと思うセイジュンと見せたが、まさかのハブの伏線。
途中からはほぼ2人の劇になってしまったけど2人のやり取りの面白さ、飢えからの知恵、戦争と追われる恐さ、面白かったって言い方は違うかもだけど面白かった。
知らなかった人達
1945年6月23日。日本軍沖縄最高司令官の自決。だがその際に武装解除の命令はされなかった。だから日本軍は戦い続けた。最も全軍に通達する手段があったかはまた別の話になるが。
この物語は終戦を知らず二年間、二人でガジュマルの樹の上で過ごした人達の実話を元にしている。安慶名のモデルとなった佐次田さんが生前「2年が10年のようだった」と語る言葉が重い。沖縄戦の中で人々はどのようにして終戦を知ったのかは調べていないが、二人のようにある程度の時間、ガマや森で息をひそめていた方々がいたのではないかと思ってしまう。
安慶名役、山田裕貴さんの瞳の何と見事なことか。笑い、戸惑い、涙し、自己を失う様子をセリフがない時でも大いに語る。対する山下役の堤真一さん。軍人としての崩さない姿勢を背中で表す。その堤さんがラスト、懸命に「安慶名」とだけ言葉を繰り返しながら、すっかり猫背になり砂に足を取られつつ海の中にいる安慶名に近づくシーンが強烈だった。走り寄るとか駆け寄るのではなく、まるで安慶名にすがりに行くように見えた。この時の二人がもう銃を持っていないことも印象的だ。距離を取って安慶名に声を向ける山下の瞳。今までの上官気質はどこに行ったのか。さすがだった。
与那嶺役の津波竜斗さん、良かったよ!
戦争映画というより人間ドラマかと。
横井庄一さん、小野田寛郞さん以外も太平洋敗戦を知らずに潜伏した方がおられたんですね
生前何度かお目にかかった劇作家の故井上ひさし先生が太平洋戦争敗戦後も敗戦を知らず沖縄伊江島のガジュマルの樹上に潜んでいたと云う実話を元にした舞台劇を作られ。
それを今回映画化されたそうなので早速観てきました。
私は1957年生まれですが、私の太平洋戦後の記憶は「小笠原返還&沖縄返還」と「残留兵士の横井庄一さんがグアムで小野田寛郞さんがフィリピンルバング島発見されたこと」です。
お二人の潜伏から帰還までは数年前に映画化されましたが、お二人以外にも沖縄伊江島にも残留兵士がいたと云う話は初めて知りました。
主演の堤真一、山田裕貴の演技も素晴らしかったけど、あの美ら海水族館の沖に浮かぶ伊江島でこんな壮絶なことが起きていたことに驚き、やはり戦争はいけないと改めて感じました。
横井庄一さん、小野田寛郞さんのことも是非知って頂きたいと思います。
“生きること”を巡る普遍的な人間ドラマ
戦後80年を迎えた今年。沖縄戦といえば少年兵に爆弾抱えさせて敵戦車の下に潜り込み自爆したり、住民がガマ(自然洞窟)で集団自決するなど戦争の極限状況が目に浮かんでくる。本作は、そうした悲惨な“戦争そのもの”よりも、人間のモラルが破壊されるような戦争の情況のなかでも“生きること”を巡る普遍的な人間ドラマ を描き出している。歴史やイデオロギーを超えて“相手を知ろうとする心”と“日々の小さな喜び”の積み重ねこそが、最も根源的な「戦争への問い」と「人間の希望」を問いかけている。
戦禍より“生命の営み”
深く掘り下げて描写
物語は、太平洋戦争末期の沖縄・伊江島。アジアでも最大級の滑走路建設工事に駆り出される住民たち。だが、突然の敵機来襲で、苦労して整備した滑走路を自分たちで爆破し使用不能にしなければならない徒労感。本土から赴任した陸軍少尉・山下一雄(堤真一)は、「これから地獄が始まる」と覚悟を決める。その言葉どおり激しい艦砲砲撃が始まり、現地徴兵され戦場を知らない新兵・安慶名セイジュン(山田裕貴)は、海上に広がる摘艦隊の数を見て愕然とする。6日間続いた激しい艦砲砲撃と上陸した米軍との地上戦の最中に、山下少尉と安慶名は前線に取り残され、ガジュマルの巨樹に登り生い茂る枝葉に身を隠して援軍を待つ決断をした。砲撃が止む夜になると木から降りて食料になるものを探しまわる。山下少尉はプラムに似たソテツを見つけてきたが、安慶名に独抜きに数日掛けてでん粉にしないと食べられないと教えられる。やがて艦砲射撃は止み銃撃戦の音も途絶えた。ある夜安慶名は、パーティのように酔って踊っている敵軍陣地をみて腹立たしい思いをした。それでも二人の精神モードは戦闘状態。伊江島の戦闘は止んでいるかもしれないが、本島は続いている、援軍は必ず来ると信じて…。
本土の陸軍士官学校出身の山下少尉は、「生きて虜囚の辱めを受けず」の戦陣訓を叩き込まれ“投降は恥”とし、国のために戦い、死ぬことを美学にしているような上官。伊江島に生まれ育った安慶名は、闘うために援軍を待つ思いとともに、伊江島で謳われてきた“ヌチドゥタカラ”(命こそ宝)の想いは、なぜ生まれ育ったこの故郷が戦場なのか、この故郷に帰るという希望にすがって生きる。
伊江島戦で実際にガジュマルの木の上に隠れ、敗戦を知らず戦時態勢のまま二年間過ごした実話の舞台劇を、沖縄出身の平一紘監督が映画化した作品。井上ひさしの原案は二行のメモだった。そこから井上の娘・井上麻矢が社長を務める劇団こまつ座が戯曲化して上演。平監督は、「<争いの最小単位>としての二人の対立と和解」こそが本作の核心という。両者は互いに自らの「正しいこと」を主張し合い、価値観もバックグラウンドも異なるが、やがて極限状態の中で<相手を知ろうとする心>が芽生える過程を描くことに意義を見出した。そこには、戦中・戦後の価値観の波に飲まれない“人間の善意”を描くことを意図しているかのようだ。戦争という極限状態の中で「水を飲む」「少しの食事を摂る」といった“日常の奇跡”を積み重ねる行為は、“ヌチドゥタカラ”の実践であり、いかに明日へつながるかを映像化している。これまでとは異なる沖縄戦映画の視座が感じられた。
全249件中、221~240件目を表示