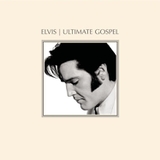「“生きること”を巡る普遍的な人間ドラマ」木の上の軍隊 JC-LORDさんの映画レビュー(感想・評価)
“生きること”を巡る普遍的な人間ドラマ
戦後80年を迎えた今年。沖縄戦といえば少年兵に爆弾抱えさせて敵戦車の下に潜り込み自爆したり、住民がガマ(自然洞窟)で集団自決するなど戦争の極限状況が目に浮かんでくる。本作は、そうした悲惨な“戦争そのもの”よりも、人間のモラルが破壊されるような戦争の情況のなかでも“生きること”を巡る普遍的な人間ドラマ を描き出している。歴史やイデオロギーを超えて“相手を知ろうとする心”と“日々の小さな喜び”の積み重ねこそが、最も根源的な「戦争への問い」と「人間の希望」を問いかけている。
戦禍より“生命の営み”
深く掘り下げて描写
物語は、太平洋戦争末期の沖縄・伊江島。アジアでも最大級の滑走路建設工事に駆り出される住民たち。だが、突然の敵機来襲で、苦労して整備した滑走路を自分たちで爆破し使用不能にしなければならない徒労感。本土から赴任した陸軍少尉・山下一雄(堤真一)は、「これから地獄が始まる」と覚悟を決める。その言葉どおり激しい艦砲砲撃が始まり、現地徴兵され戦場を知らない新兵・安慶名セイジュン(山田裕貴)は、海上に広がる摘艦隊の数を見て愕然とする。6日間続いた激しい艦砲砲撃と上陸した米軍との地上戦の最中に、山下少尉と安慶名は前線に取り残され、ガジュマルの巨樹に登り生い茂る枝葉に身を隠して援軍を待つ決断をした。砲撃が止む夜になると木から降りて食料になるものを探しまわる。山下少尉はプラムに似たソテツを見つけてきたが、安慶名に独抜きに数日掛けてでん粉にしないと食べられないと教えられる。やがて艦砲射撃は止み銃撃戦の音も途絶えた。ある夜安慶名は、パーティのように酔って踊っている敵軍陣地をみて腹立たしい思いをした。それでも二人の精神モードは戦闘状態。伊江島の戦闘は止んでいるかもしれないが、本島は続いている、援軍は必ず来ると信じて…。
本土の陸軍士官学校出身の山下少尉は、「生きて虜囚の辱めを受けず」の戦陣訓を叩き込まれ“投降は恥”とし、国のために戦い、死ぬことを美学にしているような上官。伊江島に生まれ育った安慶名は、闘うために援軍を待つ思いとともに、伊江島で謳われてきた“ヌチドゥタカラ”(命こそ宝)の想いは、なぜ生まれ育ったこの故郷が戦場なのか、この故郷に帰るという希望にすがって生きる。
伊江島戦で実際にガジュマルの木の上に隠れ、敗戦を知らず戦時態勢のまま二年間過ごした実話の舞台劇を、沖縄出身の平一紘監督が映画化した作品。井上ひさしの原案は二行のメモだった。そこから井上の娘・井上麻矢が社長を務める劇団こまつ座が戯曲化して上演。平監督は、「<争いの最小単位>としての二人の対立と和解」こそが本作の核心という。両者は互いに自らの「正しいこと」を主張し合い、価値観もバックグラウンドも異なるが、やがて極限状態の中で<相手を知ろうとする心>が芽生える過程を描くことに意義を見出した。そこには、戦中・戦後の価値観の波に飲まれない“人間の善意”を描くことを意図しているかのようだ。戦争という極限状態の中で「水を飲む」「少しの食事を摂る」といった“日常の奇跡”を積み重ねる行為は、“ヌチドゥタカラ”の実践であり、いかに明日へつながるかを映像化している。これまでとは異なる沖縄戦映画の視座が感じられた。