ネタバレ! クリックして本文を読む
角野隼人さんのピアノ演奏を初めてライブ鑑賞したのは2021年夏。
それは、読響をバックに演奏する、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番だった。
私は偶然にも最前列の真正面の席で、立って手を伸ばすと届きそうな距離でピアノを演奏する角野さんの指捌きをじっと見ていた。
それまでYouTubeでは見ていたが、クラシック音楽の現実の世界で、彼がこんなに認知されているとはその時まで知らなかった。
たまたま座った私以外の最前列付近は、角野さんの追っかけ風のファンの人たちばかりで、その熱烈な応援ぶりは、それ以前もそれ以降もクラシック音楽コンサートで出会うことのないタイプのものだった。
ファンの人たちは、目をキラキラ輝かせ、前のめりで角野さんの姿を凝視し続けていて、一番近い場所に淡々と座っていることが申し訳なくなるほどだった。
そんな角野さんのドキュメンタリー映画は、特別料金にもかかわらず連日たくさんの人が観に行っているようで、席を確保するために何日もサイトの空席状況を確認しなければならなかった。
角野さんの人気は、私が目の前で演奏を見た時から、ショパン国際ピアノコンクール出場を経て、何倍も何十倍にも拡大し続けているということを感じた。
映画は、ドキュメンタリー映像というより、友人が撮影したホームビデオのようで、演出も編集も最低限の内容で、彼のここ数年の活動の裏側を彼と同じ目線で垣間見えるものだった。
角野さんも肩肘張らずの雰囲気で、カメラで撮影しているということをそれほど意識することなく、常に自然体で、ありのままの自分をスクリーンを通して公開してくれていた。
角野さんのファンで、彼のことをいろいろ詳しい人が見れば、もしかすると『せっかく映画化したのにちょっと物足りないな……』と感じるかもしれない。
けれど、演奏以外はほとんど知らない私のような立場の人間が見れば、若くして常に自分を客観視し、自分の足りない部分を自覚し、その克服と更なる成長のために淡々と努力できる人間の立ち振る舞いや考え方を知ることができるという意味で楽しめた。
映画はエンタメであり、ある程度観る側の感情を揺さぶる仕掛けをするのが製作者としての義務だと考えている人にとっては、この映像は映画ではないと感じるだろう。
それくらい、製作者の意図や仕掛けが感じられない、まっすぐな映像を単純に撮影した時系列に寄せ集めただけにも見える。
けれど、最初からエンタメ的要素を全く期待せずに見れば、まっすぐな映像だからこそ感じられる、角野さんの人柄や思考がダイレクトに伝わってきて、たくさんの気づきや示唆を得られる内容だと、私は感じた。
映画を鑑賞して数日後、ひさびさに角野さんのピアノ演奏をライブ鑑賞する機会が訪れた。
新日本フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会。
指揮者は久石譲さん。
演奏曲はメシアンのトゥーランガリラ交響曲。
個人的には最高の組み合わせで、どんな演奏になるのか興味津々でコンサートホールに向かった。
ミニマルミュージックを追求した久石譲さんが、メシアンのトゥーランガリラ交響曲をどう料理するのか?
そして、この難曲を角野さんがどう解釈し、どんなピアノ演奏を聴かせてくれるのか?
会場内は上演前から期待感に満ちていた。
これまで何度かライブ鑑賞したことのあるメシアンのトゥーランガリラ交響曲は、オンド・マルトノ以外のピアノや鍵盤楽器がオケの端に配置された並びばかりで、ピアノ演奏の様子が見えず残念に思っていた。
しかし、この日は、ピアノとオンド・マルトノなど鍵盤楽器を最前列に配置した並びで、ステージ最前ギリギリに置かれたピアノを演奏する角野さんの指さばきがはっきりと見える配置で、視覚的にも聴覚的にも、ピアノを存分に楽しめる形だった。
相変わらず、というよりも角野さんの人気はそれ以上となっていて、お堅い人が多いクラシック音楽ファンにも、彼のことを評価し、受け入れている雰囲気を感じて、日本のクラシック音楽界の大きな変化を垣間見たような気がした。
久石譲さんは、改めて書くまでもなく、ジブリ音楽で世界的評価を得た大作曲家であり、現在は指揮者としても世界の名だたる一流オケの公演会で指揮をとっている。
角野隼人さんも、youtubeで圧倒的人気を誇り、現在は海外の一流オケの演奏会にゲストとして呼ばれて、ピアノ演奏のため世界中を飛び回っている。
二人とも共通するのは、これまでの日本のクラシック音楽の世界で活躍する人たちが歩む王道ではないルートで、業界の頂点に立つまでに至ったことだ。
もちろん二人にはそれだけ才能があり、たまたま若い頃に進んだルートが、今まで王道だと考えられていた一流音楽学校で良い成績を残し、一流音楽大学を出て海外で武者修行しながらコンクールで結果を出してチャンスを掴む……という流れではなかっただけの話だ。
もしかすると、もう少し時代を遡れば、このような亜流の天才たちが保守的な世界でスポットライトを浴びるチャンスを得ることができなかった空気が強かったかもしれない。
しかし、時代は変わったのだろう。
クラシック音楽ファン以外の世界で絶大な人気を誇る天才たちが、真剣にクラシック音楽に向き合ってくれることを、保守的な考えの人たちが多い世界でも歓迎する流れは今後も増していくだろう。
なにより、お二人をはじめ、たとえ主流を進んでいない人たちでも、真摯に芸術に向き合い、心も技も磨き続けようとしている天才たちを受け入れることが、自分が愛する世界にとってプラスになることを、本当にその世界を愛するファンならすぐに理解できるはずだ。
メシアンのトゥーランガリラ交響曲の演奏が終わった瞬間、会場は拍手喝采、大盛り上がりとなった。
カーテンコールで何度もステージに立つ角野隼人さんは、素晴らしい演奏をした直後にもかかわらず肩の力の抜けた飄々とした感じで、自然体で礼儀正しく挨拶していた。
おそらく角野さんにとって、この演奏も毎日のチャレンジのひとつであり、このスタンディングオベーションも成長の過程の中間評価でしかないのだろう。
映画の中でも、実際のステージ上でも、「今の自分のできることを最大限に発揮する」ことに集中している人だということがヒシヒシと伝わってくる。
見栄も張らないし、大風呂敷も広げない。
自己演出も必要ないし、無駄な謙遜も不要。
ただシンプルに今の自分の力のMAXを表現する。
今できないことは自分の中で正直に認めつつ、それを取り繕うとはせず、多くの人の目に晒すことも厭わない。
それは、もしかすると、YouTube時代から積み重ねてきた、彼なりのマイルールのひとつなのかもしれない。
彼の澄んだ目の奥には、「今はできないこと」が必ず近いうちに「できること」に変えることができる自信の炎が溢れている。
私を含め、少なくない人が「オープンにするのは、できるようになってから」「できないことができるまで、オープンにしない」という思考に縛られがちだ。
しかし、じつはその「できるようになった」はいつまでもやって来ない。
自分から舞台に立つ確信はずっと持つことはできないまま、ただ時間を浪費し、歳をとっていくだけで、後になって後悔の念に押し潰される。
角野さんを見ていると、自分を客観視する思考が素晴らしいと感じる。
「今の自分は決して完璧ではない」
という前提を持ちつつ、でも、それができるようになるためには、この未完成な状態でチャレンジするしか打開する方法はない、と確信している。
未完成な面だけを見るのではなく、「今できている自分」に正当な評価を出せる。
今すぐに学ばなければならない思考であり、今すぐに実践しなければいけない行動指針だと、なかなか重い腰を上げられない自分は痛切に思う。
天才と呼ばれる人たちは、もちろん天賦の才もあるだろうけれど、それ以上に、自分の夢や目標に正直に向き合える思考がある人たちなのだろう。
自分の夢や目標を綺麗ごとにして神棚に飾って眺めているだけの凡人のままは、いつまで経っても自分の夢や目標を叶えることはでできないよ……。
角野さんの澄んだ目を見て、そう感じた。

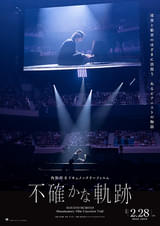

 ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド セッション
セッション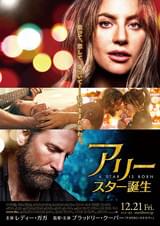 アリー/ スター誕生
アリー/ スター誕生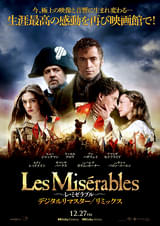 レ・ミゼラブル
レ・ミゼラブル SING/シング
SING/シング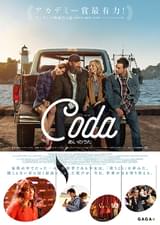 コーダ あいのうた
コーダ あいのうた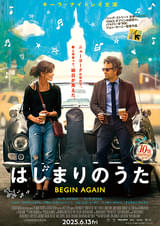 はじまりのうた
はじまりのうた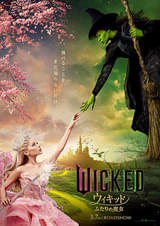 ウィキッド ふたりの魔女
ウィキッド ふたりの魔女 ウォンカとチョコレート工場のはじまり
ウォンカとチョコレート工場のはじまり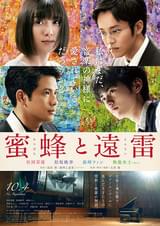 蜜蜂と遠雷
蜜蜂と遠雷












