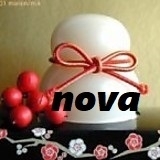蜘蛛巣城のレビュー・感想・評価
全52件中、1~20件目を表示
シンプルなストーリーに重ねられた「蜘蛛の巣」のモチーフが魅力。
〇作品全体
個人的に響いたのは、蜘蛛の巣というモチーフ。この作品通して武時は物の怪の予言に翻弄されているけれど、予言の外に出られなくなっているさまは蜘蛛の巣にかかった虫のようでもある。森のシーンで手前に蜘蛛の巣のように伸びる木々を再三映しているのも、蜘蛛の巣のモチーフの一つなのだろう。
シーン単位で見ていけば、武時が初めて北の館に入ったシーン。妻・浅茅に謀反を唆され浅茅に導かれるように畳の上へあがる武時は、1畳の畳の上に捕らえられたかのように映る。縛られているのは物の怪の言葉だけではなく、誰かの思惑もまたしかり、といった感じの印象。
物の怪に始まり浅茅、義明の亡霊…望みがかなえられて行っているように見えて終始何かに縛られ、怯える武時にまとわりつく蜘蛛の巣のような存在が、モチーフに上手く活かされていると感じた。
三船敏郎演じる鷲津武時の心変わりがそのままプロットポイントになっている作品で、暗い感情が物語を動かす軸になっているんだけど、終始映像美を感じる画面作りも印象的だった。
作品名であったり、モノクロの画面であったり、三船敏郎の鬼の形相から「重さ」を感じてしまうように思えたけど、ファーストカットからある霧の白さであったり、舞台や小物を使ったフレーム内フレームの演出から美しさが存在する気がした。
ストーリー自体はすごくシンプルで、途中登場した三木義明の嫡男・三木義照が予言を信じる義明へ向けた一言、「物の怪に操られ、おのれの手でその予言のままの事実を作り、予言が当たったとお考えなさる。正気の沙汰と思えませぬ」がすべてな気がする…。
〇カメラワークとか
・ファーストカットで霧を見せ、城址を見せて、霧でつなげて時代を遡行、城を出現させて物語の時代に入っていく…この演出がすごくかっこよかった。ナレーションを使ってもいいし、テロップを使ってもいい場面を、画面演出だけで観客を物語の中に引き込んでいっているような感覚。映像体験って感じがしてすごく良い。
・黒澤映画はたまに猛烈にカッコいい影の使い方をする。今回は主君・国春を殺すために奥の部屋から槍を持ってくる浅芽のカット。闇の中へスッと浅芽が入っていき、少し時間を空けて出てくるのだけれど、再び現れた浅目の闇から浮き上がってくるかのような登場の仕方にゾッとした。手前、奥を使った影の演出は『隠し砦の三悪人』でもやってたっけな。
・カメラを動かすときに必ず理由がある映像作品ってやっぱ好き。TU、TBでカメラが動いた時の緊張感が半端ない。この緊張感が自分の快感に直結してるような気もするなあ。
持続する緊迫感。
有名な『マクベス』を翻案した映画。
だから大筋は判っているのに、次はどうなるのかと魅入ってしまう。
黒澤監督の映画に何を求めるかで、評価が変わってくる。
ある夫婦の破滅の物語。
この世の総てを手にするはずだったのに。
あるきっかけで、心の奥底に眠る感情に翻弄され…。
欲望・疑心暗鬼、驕り…。
『七人の侍』『隠し砦の三悪人』『用心棒』『椿三十郎』『赤ひげ』等の、黒澤映画に期待する陽のエンターテインメントは皆無。
この顛末を勧善懲悪と見れば、すっきりとするのかもしれないが、
唖然とする圧巻な幕切れ。”信”を失った男と女の落ち行くところ。
(ラストは若干、『マクベス』とは変えてある。『マクベス』では、予言された、あり得ないはずの男が現れるが、この映画では…。こちらの方がより現実的で、こうなるよなと思いつつ、主人公の立場になれば怖い。)
能の様式美を取り入れた作品。
人形が動くか如く、衣擦れの音はすれど、すっと動く。座っている姿から、「よっこらしょ」なんて言葉は不要に、すっと立ち上がる。三船氏だけではない。山田さんも。他にも他にも。皆さま、どれだけ体幹を鍛えていらっしゃるのか。
馬の躍動感。
なのに、静かな、静かな印象。
雲海に囲まれた城。
迷いの森。
夫婦によって囁かれる謀議の部屋は暗く、その外は陽光溢れ、家臣たちが伸びやかに日々の備えの最中。
謀反を犯した臣が処罰された血が残る部屋、そこで行われる所業。
楽しいはずの宴席の冷めきった様。
有名な奥方の狂気。
キリキリとして、押し付けられるような絵の連続。
そして、ラストはあの有名なシーンが炸裂する。
オープニングとエンディングは諸行無常。後味が…。
監督もすごいが、この役者なくしては成しえなかった映画。
物の怪の老婆を浪花さんが雰囲気たっぷりに、この映画の世界に誘ってくれる。
終盤ではワンシーンなれど、志村さんがとても力強くて、頼もしい。
そして主人公・鷲津を演じられた三船さん。豪放磊落にして小心者。野望を叶えたい気持ちと、人としての信義の中で揺れる様子、転落していく様子。馬鹿な男と笑い飛ばせない何かが惹きつける。
とはいえ、最高勲章は山田さん。この不気味さ。なのに、事を為した後に戸惑い。そこから一転した、あの狂気。
語り継がれる映画。
人の、心の奥底に眠る、人を押しのけても栄華を希求する気持ちが刺激されて、
同時にその顛末も明らかにしてくれて、
何のカタルシスも得られないけれど、忘れえぬ。
鑑賞して何日も経つのに、心がざわめいて止まらない。
黒澤だ
人間は本当に自由なのか?
黒澤明は『七人の侍』で「理想の秩序」を描いた。だが本作『蜘蛛巣城』では、人間が「選択」を通じて自らを崩壊へと追い込んでいく過程を描き出している。
霧の荒野にそびえる蜘蛛巣城。三船敏郎演じる武将・鷲津は、森で出会ったあやかしから「城主になる運命」を告げられる。しかしこの予言は、未来を決定する予言ではなく、「道を誤らせる甘い囁き」にすぎない。そして背後では、妻・浅茅(山田五十鈴)の冷徹な誘導が、鷲津の背中を押していく。こうして鷲津は、主君を討ち、城を手に入れる──そこから破滅へと転がり始める歯車を自らの手で回していく。
主君殺しという最初の選択によって、以後の選択肢は次々に狭まっていく。親友・三木の処刑。その実行役となった部下の粛清。猜疑心は加速度的に膨れ上がり、自己正当化の繰り返しが「もうこれしかない」という心理状態を生み出す。自らを省みる心(ネガティブ・フィードバック)は消え、猜疑と支配への依存(ポジティブ・フィードバック)だけが肥大化していく。
やがて鷲津は、恐怖と猜疑でしか統治できなくなる。その果てに、予言された「森が動く」現象(部下たちにとっては敵軍の襲来であるのだが)が現実となり、恐怖で硬直した部下たちの裏切りによって、矢の雨に倒れる。
本作では登場人物が極端に絞られている。鷲津の孤独を浮き彫りにする狙いもあるだろうが、志村喬や千秋実を除けば、黒澤映画の常連たちはほとんど登場しない。その代わり、霧、森、鳥、矢といった自然の象徴が、鷲津の内面と運命を語り続ける。
森:迷路のように出口が見えない選択の混迷
霧:判断力の曇り、先が見えない混沌(クラウゼヴィッツの「戦場の霧」)
鳥:破滅の予感(察知されながらも意図的に無視される危機信号)
矢:猜疑心の暴走が最後に己を貫く「粛清の刃」
三船敏郎の鷲津像は、彼が一貫して体現してきた「正義・信義・誠実さ」を裏切る役柄となった。そこに生まれるのは、黒澤映画では珍しい堕落の美・破滅の美である。
黒澤はここで「独裁者の自壊モデル」を実験的に構築している。勝つために支配を強め、猜疑を重ね、純度を高めれば高めるほど、逆に統御は失われていく。まさに「完全なる支配は死をもたらす」構造そのものである。そこには戦後日本の混乱や、黒澤自身の共産主義・スターリン体制への複雑な感情も重ねられている。
黒澤はカオスを描こうとした。しかし彼の職人的な統御志向ゆえに、それは「コントロールされたカオス」に留まってしまう。ここに黒澤の限界と誠実さが同時に表れている。
人は自由に選んでいるつもりでも、選択が次の選択を呼び、猜疑心が猜疑心を増幅し、閉じていくカスケードの果てに袋小路に追い込まれていく。『蜘蛛巣城』は、選択・因果律・破滅を描いた、黒澤明の思索と造形美が極限まで研ぎ澄まされた傑作だ。
4K UHD Blu-rayで鑑賞
94点
シェイクスピア演劇に対峙した黒澤監督の作家証明と名優三船敏郎・山田五十鈴の気迫
シェイクスピアが執筆した四大悲劇の最後の戯曲「マクベス」(1606年頃)に黒澤監督が本格的に取り組んだ正攻法の演劇時代劇。娯楽時代劇の金字塔「七人の侍」始め、翌年の「隠し砦の三悪人」のユーモアとアクション、そして監督50代の成熟期の「用心棒」と「椿三十郎」とは趣を異にする、真剣勝負な映画作品でした。これら5作品の時代劇でも其々に特徴を持って、その他のジャンルにも傑作を数多く遺したのですから、黒澤監督の幅広い教養と知識、特に文学と絵画への才覚には敬服するしかありません。この作品でも、イギリス演劇の権威とも言えるシェイクスピアを日本の時代劇に翻案するにあたって、日本の伝統芸能の能の研ぎ澄まされた演技と様式美で対抗しています。これによって独特な緊張感を持った黒澤映画になっていました。
日本の戦国の世は、出世功名の為には親族同士でも殺し合う道義のすたれた権力闘争の時代。また洋の東西を問わず、家臣が謀反を起こし主君を討つ下克上がありました。主人公鷲津武時の妻浅茅の言葉にあるように、所詮人に殺されぬためには人を殺さねばならない。しかし、やるかやられるかの殺し合いでは国は成り立ちません。武時の言うところの、大逆(人の道にそむく最も悪質な行為)を犯しては何の名目も立たない。つまり友誼(友情)や情誼(友人・師弟間の情合)に報いてこそ、組織の結束力も固まるというものです。夫の武時に一国一城の主から天下人になって貰いたい野心家浅茅の貪欲さと冷徹な独占欲に誘惑され、洗脳される武時は、戦闘能力が高いも気が弱い性格の持ち主。この夫と妻が企み権力を掌握するも、謀反を犯した人間の宿命のように自滅していく物語には、古典に相応しい普遍性があります。
映画の特徴は、マクベスにあたる武時とマクベス夫人の浅茅のふたりのシーンを、能の様式に模した演技にした黒澤演出です。日本映画として、貴重な見所と思います。能面のようなメーキャップで演じる三船敏郎と山田五十鈴は、最小限に抑えた身体の動きと表情の僅かな変化で感情を表す繊細な演技です。それでいて重厚さがあるシーンになっているのは、日本伝統の詫び寂びの美しさと幽玄さからくるものでしょう。興味深いのは、城内のシーンで2人に他の登場人物が加わると、能と時代劇演技の中間の芝居を三船と山田がしていることでした。名優だから出来る切り替えの巧さと、室内シーンを自然にみせる見事な演出です。勿論蜘蛛巣城の城外の演技は通常の時代劇演技です。この点からも演劇時代劇としてのユニークな面白さがあります。そして改めて感じるのは、三船敏郎の圧倒的存在感です。眼力のある表情を維持するのも、相当な集中力を必要とすると思われます。そしてこの三船の存在感に負けない山田五十鈴の貫禄のある演技の素晴らしさ。死産した後の肥立ちが悪かったのか、子を失った悲しみに己の貪欲さを恨んだのか、発狂して手に付いた血を何度も水の無い鉢に手を入れ落とそうとするその仕草に、常軌を逸した表情の凄さ。この短いシーンに賭けた山田の真骨頂の演技でした。
この名優2人の演技の見所と並ぶのは、美術村木与四郎と監修江崎孝坪、そして中井朝一の撮影でした。古色蒼然とした蜘蛛巣城と北の舘のデザインの良さと本格的なセット建築。霧の蜘蛛手の森の中を馬が疾走するシーンのカメラワーク。霧で視界が悪くなり、それでも馬の姿が微かに見えるモノクロ映像のトーンと雰囲気の醸成。二度登場する森の老婆のシーンの神秘的且つ不気味な感覚の映像美。蜘蛛巣城に寄せて来る蜘蛛手の森の丁寧で雄弁な映像作り。そして、三船敏郎が役として精神的に追い詰められた、無数の矢を射るクライマックスの迫力と、全編に渡りあります。
シェイクスピア戯曲に挑戦して、日本的な伝統芸能と黒澤監督得意の時代劇の見事な融合を成し遂げた意欲作にして完成度の高い作品でした。そして何より、日本映画を代表する名優三船敏郎と山田五十鈴の気迫ある演技に賛辞を送りたい。
黒澤監督が描いた人の世
見応えのある映像を堪能
もう矢だぁ!もう矢だよぉ!
脚本監督、黒澤明。
シェイクスピアの『マクベス』が作劇のベース。
【ストーリー】
戦国。
鷲巣武時(三船敏郎)と三木義明は、主君・都築国春の命により、"北の館"にて謀反を起こした藤巻を討伐する。
国春の根城、"蜘蛛の巣城"にもどる道すがら、"蜘蛛の手森"にて嵐にあい、そこで奇妙な老婆と出くわす。
老婆は言う。
「鷲巣は北の館の主となり、やがて蜘蛛の巣城の城主となるであろう。三木は一の砦の大将となり、その子供は蜘蛛の巣城の城主となるであろう」
気がつくと老婆は居なかった。
不気味さに怖気をおぼえつつ、二人は蜘蛛の巣城へとたどり着く。
二人に国春は言う。
「鷲巣は北の館を、三木は一の砦を守護せよ」
北の館に居を構えた鷲巣は、妻の浅茅にあの夜の出来事を話す。
浅茅は言う。
「であれば、都築を暗殺なさいませ」
マクベス読んでませんごめんなさい。
マクロスなら……あほう!
この超時空あほう!
終盤のあのシーン、本当に無数の矢にさらされて、主演の三船敏郎がのちにお宅までいって「死んじまえ黒澤!」ってキレまくったそうです。
なにせ大学の弓道部員を何人と用意して、打ちまくったそうで、本当に生きた心地しなかっただろうなあ。
すんごいおもしろいシーンなんですけど、演じる側はたまったもんじゃないよなあと。
クロサワ・お公家眉ヒロインでも最怖なのが、山田五十鈴演じる妻・浅茅。
能の動きをとり入れたすり足で、すべるように移動し、時武をそそのかし、謀殺にまで手を染めるその攻撃性と狂気。
クロサワ闇系ヒロインだぁ……。
よほど印象が強かったようで、ロンドン映画祭に呼ばれた際、『風と共に去りぬ』のスカーレット・オハラを演じたヴィヴィアン・リーに、メイクのことをやたらと訊かれたそうです。
ヴィヴィアン・リー、舞台でマクベス夫人を演じていたので、それつながりで気になったんでしょうね。
浅茅、こわいもんね。
あんまり浅茅がこわくてあんまり見返す気は起きないんですが、あの矢のシーンだけはくり返し見ちゃったりします。
悲劇にひたりたい夜なんかに、よかったらどうぞ。
馬 馬 馬
黒澤明の最高傑作の1つだ。
黒澤明監督が、シェイクスピアの戯曲『マクベス』を、日本の戦国時代に置き換えた一大叙事詩。三船敏郎の狂気に満ちた熱演が印象深く、映画史上最高の死のシーンとも言われている。
原作の文言を使うことが無く、シェイクスピアが持つ詩情を削除する一方、それを補って余りある、鋭敏で刺激的な映像に満ちている。原作やシェイクスピアに詳しくない方でも、十分に鑑賞できる。
黒澤作品の中でも、特に冷酷でダークな世界観に満ちた作品だ。シェイクスピア作品の翻案としても、見事に成功している。原作への忠実さにこだわらず、黒澤明による『マクベス』の再解釈が全開している。
野心を突き詰めた人間の、避けがたい因果応報を、独自の鋭さと映画的な感覚による脚色で描き切り、生々しさと力強さを併せ持った、黒澤明の最高傑作の1つといえる。
黒澤ホラー
原作に触れることなく鑑賞。物の怪や予言など、オカルト・ホラー要素の強い作品。演出もかなりホラー寄り。
三船敏郎と山田五十鈴の演技がとにかく素晴らしく、引き込まれます。焦燥感、恐怖心、狂気に取り憑かれていく様を迫真の演技で表現しており、この二人の俳優が生み出す緊張感がクライマックスへ向けて張り詰めていきます。
そのクライマックスですが、見どころ満載の名シーンの連続!目が離せません。演出や映像技術も素晴らしく、今観ても「どうやって撮ったんだ?これ。」なシーンは驚愕。有名な矢のシーンでの三船のリアクションはガチだったんでしょうか(笑)むちゃくちゃやりやがるぜ…。
ホラー演出がかなり目を引きます。白黒だから余計に怖く感じました。本作では作品の構成や人物の表情や動き、撮影技法などに能の様式美を取り入れているとのことで、そのせいか緊張感のある作品になっております。
若干冗長に感じるシーンがいくつかありましたが、それも能を意識して作られたからでしょうか。個人的にはもう少し削っても良かったかな?って世界の黒澤に向かって何言ってんだって話ですよね、はい、すみません。
ホラーがどうとか言ってますが、結構大掛かりなシーンが特徴的でもありまして、騎馬隊による進軍のシーンは大迫力です。よくあれだけの馬と乗馬出来る俳優を集めたものです。
見どころ満載の黒澤ホラー。……ホラーでいいのかな…?私は怖かったぞ😱
物怪に誑かされる話
感想
野望と疑心暗鬼、神も仏もない戦国下剋上の世。
霧の中、蜘蛛城趾の碑が現れる。諸行無常、世の中は繰り返しの連続であるという呪文のような譜が流れていく。再び霧が流れ、濃霧になる。その霧が次第にはれるうちに、目前に、巨大な城が現れる。
戦は続く。北の館の主、藤巻の謀叛を鎮圧した一の城主、鷲津武時とニの城主、三木義明は時の蜘蛛巣城主で主君の都築国春へ出向途中、蜘蛛手の森で路に迷い、ふとした機みに老婆の姿をした奇々怪界たる雰囲気漂う物怪に出会う。物怪は、今宵より鷲津は一の砦の城主、三木はニの砦の城主。その後、鷲津は蜘蛛巣城主、三木は北の館の主となり、その息子は鷲津の次の蜘蛛巣城主になるだろうと言付ける。
夢か現か、物怪の話を聞き受け信じたために、その言付けは現実のものとなる。同時に鷲津の野望が悪霊を引き寄せ、己とその妻の性格を変え、数奇で残酷な人間の欲と業のなせる、怖ろしく醜い都築への下剋上を実行することにより、三木をも巻込み、二人の命運はいにしえより残されている蜘蛛手の森の数多の落命し悪霊となった者ども同様に命運が尽きることになる。
いにしえの世より続く戦、無念、非業、そして怨みを重ねて、死んでも死にきれない多くの成仏することの出来ない魂が集まり、悪霊、怨念をもつ蜘蛛手の森の物怪となり、下剋上の世を生き抜く者たちを誑かし、まさに蜘蛛の巣に虫類が繋るがごとく、その術中に嵌り、己の身をも自身の欲望に任せた諸行により、破滅に向かわせてしまう無常で不可思議な物語である。
配役は
物怪に謀られる武将鷲津に三船、千秋は三木を演じた。小田倉に志村喬。他、藤原釜足、土屋嘉男、稲葉義男、加藤武など黒澤組常連の壮々たる俳優陣。さらに鷲津を翻弄する女房、浅茅に山田五十鈴。物怪に浪花千栄子、また武将の怨霊で中村伸郎、宮口精二、木村功が怪演しておりあらためて観ても重厚でファンタジックな映像が展開され新鮮で素晴らしいと感じる。監督助手はのちにウルトラQ、ウルトラセブンの演出で名を馳せる若き日の野長瀬三摩地が担当し、蜘蛛手の森が動き出すがごとく、木々で擬装した都築、三木、小田倉の軍勢が城に押し寄せる映像や飛び矢の特殊効果を創り上げた。
黒澤監督はウィリアム・シェークスピアのマクベスを元に能楽の要素をマリアージュして、おどろおどろしい脚本を小國英雄、橋本忍、菊島隆三の各氏と書き上げた。撮影も壮大なセットを富士山の裾野に構築、騎馬武者隊の進軍シーンも豪快な撮影で素晴しい。
⭐️5
迫力ある三船敏郎
【主君に忠誠を誓っていた武将が、妖や妻の囁きにより忠誠心から下克上、更なる立身出世を求める心に変遷していく様をおどろおどろしく描いた作品。初期邦画ホラーといっても良い世界に誇る逸品でもある。】
■謀反を鎮圧した武将・鷲津武時(三船敏郎)と三木義明(千秋実)は、主君である城主都築国春(佐々木孝丸)が待つ蜘蛛巣城へ馬を走らせていた。
だが雷鳴轟く森の中で道に迷ってしまう。
そこで武時と義明は1人の老婆と出会い、不思議な予言を告げられる。
その後、2人は予言の通りに出世することになるのだが。
◆感想<Caution! 内容に触れています。>
・多くの諸先輩がこの作品に対する感想を述べているのでシンプルに示す。
・この作品で描かれる三船敏郎演じる武将・鷲津武時が主君に反旗を掲げる姿は、現代社会でも日常的に起こっている事である。
ー 父親が一代で築き上げた家具屋を、実の娘が経営方針に反旗を翻し、裁判沙汰になったケースや、老舗京都の店の様々な後継者争い・・。
普通に継いでいれば何ら問題はない筈なのに、後継者の心に生まれた”魔”が惹き起こした泥沼の争いである。-
・今作でも、忠臣であった三船敏郎演じる武将・鷲津武時が森で出会った妖や、妻浅茅(山田五十鈴)の甘言により、徐々に欲望の心に乗っ取られ、忠臣の心を失って行く様は、正にホラーである。
ー 特に、夫の立身出世を願う妻浅茅を演じた山田五十鈴の姿はとても怖い。-
■凄いと思ったのは、現代邦画では原田眞人監督位しか描けていない、馬を乗りこなす事の出来る俳優の多さとそのスケール感である。
更に言えば、武将・鷲津の心の変遷を表すような、耳障りな高音のギャーギャーと鳴く鴉の声や、台詞無き”間”のシーンの挿入タイミングの巧さである。
そして、随所で観られる躍動感溢れる馬を中心にした武将たちの姿である。
<彼の有名な、ラストの雨霰の如く降り注ぐ矢の中で、三船敏郎演じる武将・鷲津武時が全身針鼠のようになっていくシーンもホラーである。
そんな中でも、世界の三船が放つ響き渡るテノールボイスの狂気性を帯びた笑い声。
今作の様な作品を鑑賞すると、現代世界の名だたる監督に、”影響を受けた監督は誰ですか?”という問いに対し、”動は、クロサワ。静は、オズ。”と告げる多くの監督の感想が改めて良く分かるのである。>
シェイクスピア原作映画化の最高峰‼️
昔も今も変わりなし。人の心が一番怖い。
ロンドンの王立劇場の柿落としで上映された際、恐怖のあまり失神者が続出したと言われる、なるほど怖い。怖いだけでなく、最初から最後まで一瞬の遊びもユーモアもなく(黒澤作品には珍しく)緊張が強いられる。疲れた。
そりゃ失神するわ。
黒澤作品は、若い頃は「用心棒」や「赤ひげ」などの分かりやすくて面白いのが好きだったけど(「七人の侍」は別格)、年とってくるとこの作品が一番すごいんじゃないかと思ってきた。
一番繰り返し観てるかもしれない(「七人の侍」は別格です)。
初めて観た時(もちろん初公開時じゃなくてリバイバルか名画座で)は、物の怪と騎馬での疾走と蜘蛛手の森とラストシーンがあまりにもインパクトが強く気付かなかったことが多かったけれど、観るたびにすごいことに気付かされる。
三船敏郎すごいけど、山田五十鈴すごいなぁ。でもやっぱり三船敏郎すごいや。ってすべてがそんな感じ。
スタッフもキャストもすごい。物の怪おちょやんやし。
CGのない時代(CGもすごい技術がいるんだとは思いますが)、ひとつひとつのシーンにかける時間、労力、知恵が現在とは比べものにならなかったのだろう。
面白くなるはずだ。
三船さんはアクションスターだ。
「影武者」「乱」、そして「スター・ウォーズ」も三船さんが出てたらもっともっと面白くなってたろうなぁ。
4Kリマスターで劇場で観ることができるしあわせ。
午前十時の映画祭ありがとう。
ただ、観客三人。もったいないなぁ。もっと映画館を選べないのかなぁ(劇場のスタッフまるでやる気なし)。上映館増やしてほしいなぁ。上映時間も朝一度だけでなく夜の回でもやってほしいなぁ。
東宝さんも、アニメやテレビドラマの劇場版に力入れるのはいいけど、自社の宝物再上映すればいいのに。
宣伝費かけて「七人の侍」IMAXで全国公開したら絶対ヒットするよ。劇場で映画を観る楽しさ気づいて映画人口も増えると思うけどなぁ。
怖いのはもののけより人の心〜
せっかくのリバイバル上映なので見てみました!
主人公の武将は山の中で出会ったもののけの予言に取り憑かれ、奥方の誘導にそそのかされるまま主君をあやめてしまい、結局その亡霊に悩まされ、奥方も気がふれてしまうという。。
今の世も、もののけではなくても占い師に傾倒する芸能人や大物政治家とかいそうだし、いやニュースにならないだけで一般人も下手に占いにハマったら危ない。
最後、山が動くわけないやーん、主人公の見た幻か?と思ったら敵方が主人公のその予言内容を知ってあたかも実現してるように見せかけて、惑わせた。。でしたか!占いを信じすぎると足元すくわれて怖いですね。
そしてこれだけの映画を60年以上前に作ってたのが凄い。多少、滑舌の悪さか録音技術の限界か、セリフの聞き取りにくい箇所はありましたが、
三船さん濃いし重厚だし、若い時分の演技がスクリーンで見れて良かったです!
山田五十鈴さんは衣擦れの音だけで彼女の登場が分かる演出も、夫を焚き付ける演技もさすが。もしや奥方がもののけの本当の正体なんじゃないか?と思ったほど。
罪悪感からか、手の血のりがいくら洗っても落ちないと幻影が見えてしまうのが物悲しいし、夫婦そろって自業自得なんでしょう。。。かつての映画番組で放送されていたら、有名なプレゼンターさんの感想で「いや〜怖かったですね~~」が聞こえてきそうでした。
最後の矢の場面、そこまでやるんだ〜!と思いました。
「マクベス」→「蜘蛛巣城」→「ダースベイダー」
黒澤明監督がシェークスピアの「マクベス」を
ほぼそのまま、日本の戦国の下剋上の連続で
血みどろの時代に置き換えて作られた映画。
クライマックス、主人公が多数の矢の攻撃で
壮絶に死んでゆくシーンで、
撮影用では無く、本物の矢が飛んで来ていた!
と言う話が有名ですね。
欲望に負けてしまう人間の愚かしさと
自身が望んで犯した罪なのにその重さに
自身が負けてしまう弱さを描いた映画です。
重厚なお話ですが、最後まで息の抜けない緊張感と
早い展開に案外とお話はサクサク進んでゆきます。
4Kデジタルリマスターで画像はかなり綺麗な
モノクロ映画となってます。
セリフも戦国の伝令などは、怒鳴るような話し方なので
聞きとりにくい所も若干ありますが
それ以外はかなりはっきりと聞き取れます。
原作本を読むより分かりやすいかも〜
シェークスピア入門におすすめです。
また、主演の三船敏郎はもちろんですが
主人公をそそのかす妻を演じた山田五十鈴の
まるで能面のままの瞬きを一切しない怪演も
見事です!要注目!!
で、月に8本ほど映画館で映画を観る
中途半端な映画好きとしては
黒澤明の映画を観るたびに
引き合いに出して申し訳ないけど
ジョージ・ルーカスが作り上げた
最初の『スター・ウォーズ』の三部作が
いかに黒澤映画の影響を受けているか
どうしても発見してしまうのです。
今回も『スター・ウォーズ』の中の
「暗黒面に落ちる」と言う表現。
「蜘蛛巣城」の中で「欲望に負けての闇落ち」が
どこかヒントになってる感じがします。
ジョージ・ルーカスともなれば
シェークスピアも
読んでたとは思いますが....
兜を恭しく一段高いところに飾ってある光景は
『スター・ウォーズ』のダースベーダーのマスクで
再現されてる気がするし
ストームトルーパー達が時におバカなのも
黒澤映画の雑兵達が時に同じようにおバカだったりして
どこかその感じが引き継がれてる感がありました。
優れた監督の映画が優れた監督によって
繰り返し引き継がれて行く。
とても分かりやすい良い例だと思います。
ぜひ映画館でお楽しみ下さい、。
全52件中、1~20件目を表示