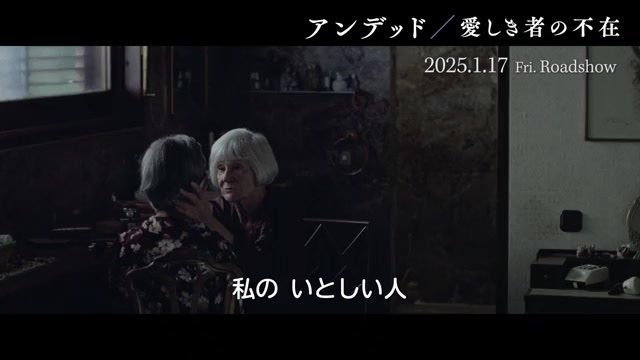アンデッド 愛しき者の不在のレビュー・感想・評価
全16件を表示
期待度◎鑑賞後の満足度△ このところ佳作が立て続けに公開されている北欧映画群だから期待したのにやや失望。サイレント映画みたいなところはちょっと面白いけど。
①イヤに勿体ぶっているけれども結局ゾンビ映画じゃん、というのが鑑賞直後の印象。
②表面だけ見たら怖くない『ペット・セメタリーみたいな映画だけれども、ただ、『ボーダー』の原作者の小説が原作だから、それだけじゃないてしょ、とつらつら考えていて思い当たったのが、鑑賞中ずっと違和感があったのが、
愛しき者の不在、という邦題がが秀逸
邦題がこの作品の本質を突いていると思い、感心しました。
A.父と娘:娘の男児がゾンビ化
B.高齢女性:女性のパートナーがゾンビ化
C.父と母と娘と息子:母がゾンビ化
という設定で進行していきますが、
それぞれゾンビ🧟化が異なるんですよね。
オスロで大停電が発生して、
なんかゾンビ化する死体が出てきた的な感じです。
Aは墓地から音が聞こえるのを不審に思った父(つまり爺さん)が
墓を掘り起こし、息子(つまり孫)を連れて帰る。
この息子くん、腐りかけていておそらくすごい腐臭がしているんだと思いますが
母親(娘)もお人形のように扱い、最終的には川へ沈めてしまいます(父がゾンビに襲われるのを見て悟ったんでしょうね)。
そして父がゾンビに襲われてゾンビ化するんですよ、この設定いらなーいと思いました。
ゾンビにビジュアルもしょっぱいし、下手なホラー要素は蛇足です。
Bは勝手に家に入ってきちゃっていたんですよね。
で喜んだ女性はやはり人形のように扱うのですが、最終的には噛み殺されてしまいます。
いや、そのうちゾンビ化するのかもしれません。
Cは交通事故で亡くなった直後に息を吹き返す母なのですが、
ペットのうさぎを絞め殺すという凶暴さを見せて、家族も母ではないことを悟ります。
愛しき者は帰ってこない、それでも前を向いて生きていく、というのが通底するテーマであるはずなのに(勝手にそう思っています)
ゾンビが人を襲う設定はマジで不要と思いましたし、作品の一貫性を欠くことになってしまい、大変残念でした。
途中までは新しい切り口の作品だなぁと思っていたので、非常に残念でした。
レビュー未反映の為、怒りの再投稿
謎の停電後、事故死した二児の母・埋葬したての老婦人・土葬されて暫く経った男児が
唐突に生き返る(老婦人は自力で帰宅した模様)
当初はハエがたかった状態でボーッとしてアウアウアー状態だったが、
次第に見舞いに来た子供のウサギを圧殺したり(二児母)、同居の老婦人を噛み殺したり(老婦人)
と徐々にエンジンかかってきた模様・・・
唯一腐り具合が進行しすぎだったのかゾンビ本能の芽生えが遅かったのか男児のみ依然寝たきりゾンビ状態。。。
色々あって男児の母が湖だか海に男児を沈めて終劇・・と実に微妙なゾンビものでした。
やりたいことは何となくわかるけど、ちょっと悪趣味な精神実験かなあと思った
2025.1.30 字幕 アップリンク京都
2024年のノルウェー&スウェーデン&ギリシャ合作の映画(98分、G)
愛する人がある出来事によって蘇り、それと対峙する家族を描いたスリラー映画
監督はテア・ビスタンダル
脚本はヨン・アイヴィデ・リンドクビスト&テア・ビスタンダル
原題は『Handtering av udode』、英題は『Handling The Undead』で、「不死の処理」という意味
物語の舞台は、ノルウェーのオスロ
ある出来事によって、愛する人が死んだ時の状態で生き返る様子を描いていく
ひとつめの家族は、息子エリアス(Dennis
Østby Ruud)を亡くした母アナ(レナーテ・エインスベ)と彼女の父マーラー(ビョーン・スンクェスト)の物語
ふたつめの家族は、パートナー・エリーザベット(オルガ・ダマーニ)を亡くした老女トーラ(ベンテ・ボシュン)の物語
みっつめの家族は、母エヴァ(バハール・パルス)を亡くした夫ダヴィッド(アンデルシュ・ダニエルセン・リー)と、その娘フローラ(イネサ・ダウクスタ)、息子キアン(キアン・ハンセン)の物語
それぞれが同時進行で描かれ、ある時に起きた地震後の停電のような天変地異にて、死者が復活していく様子が描かれていく
その時に墓参りをしていたマーラーは、地面の下からエリアスの声を聞き、墓を掘り返して自宅へと連れ戻していた
墓荒らしがバレて、やむなく別荘地へと向い、そこで3人で暮らし始めていく
トーラは、エリーザベットの葬儀を済ました翌朝に、彼女が部屋に戻ってきているところを発見してしまう
エヴァはその瞬間に事故で亡くなり、安置所に夫が来た後に蘇生を果たしていた
それぞれの生き返りは年代がバラバラで、老人、成人、未成年となっていたし、それを受け止める側も、老男女、成人男女、未成年男女となっていた
突然死したのはエヴァで、エリーザベットは老衰っぽいし、エリアスに関しては死因が不明だが、埋葬されてから時間がかなり経っていた
この三者三様が「生き返り」に対してどのような行動を取っていくかという物語になっていて、死の瞬間からの事件経過というものも3家族で違っているように描かれていた
エリアスの死が突然かはわからないが、死後ある程度時間が経っていた
それでも、息子の喪失が尾を引いていて、アナは突発的に死のうと行動を起こしてしまう
マーラーはずっと引きずっていて、アナの身を案じながらも、孫の喪失が親子の仲を疎遠にしていることを憂いていた
エリーザベットは物語の冒頭で葬式が行われているのだが、高齢でもあり、ある程度死を意識する年齢になっていた
それでも、トーラは彼女が戻っても喪失感を拭えないことを悟り、彼女の元に行こうと服薬自殺を図っている
エヴァの家族は、生きているのに会えないという時間が続き、それぞれがどう向き合えば良いのかに悩んでいる
蘇生を目の当たりにしたデヴィッドは希望を持っていたが、子どもたちは信じがたいという感じで、お見舞いの際に「確認」を行うことになる
フローラはそこにいるのは母ではないと悟り、キアンは殺されたウサギと共に母親を埋葬してお別れを告げているようにも見える
また、デヴィッドは2度目の妻の死を目の当たりにしているようで、深い悲しみに打ちひしがれていた
映画は、これらのケースバイケースを描きながら、自分ならどうするだろうかを問うという感じになっている
それでも、あまりにも非現実的過ぎて自分を重ねることは難しく、客観的に見ると、全てのキャラが行なっていることは気持ち悪く見えてしまう
ひとつだけ言えるのは、肉体が戻っても生き返ったとは言えないんだなあということで、生命が維持されている状態でも、意思疎通ができなければ、その認識を拒絶してしまうことになってしまう
ある意味、それを規定するのか自分の心であり、自分の中で相手が死んだと感じれば、そこに肉体があって動いていても、シャットダウンできるということだろう
そして、この心理状態で動いていたのがアナであり、彼女は息子を湖に遺棄するという行動を取っていた
この映画で何を感じ取るかは人それぞれなのだが、やはり愛する人の死に遭遇した人でないとわからない部分は多いと思う
また、アンデッドの行動はまんまゾンビ的なものになっていて、そのコンタクトをどう受け止めるのかは難しい
アンデッドが肉体を食することで生きながらえるのかはわからないが、映画内の印象だと、食することがコミュニケーションの
ようにも思えてしまう
死んだトーラを食べたエリーザベットがその後動かなくなることを考えると、ゾンビが活動するには生命力が必要で、それと精神とが融合してこそ、生物と呼べるのかなと感じた
いずれにせよ、かなり重厚な音楽が鳴り響き、スローすぎるテンポで映像が動いていくので、睡眠不足だと一気に持っていかれる映画だと思う
3家族を交互に描いていくので場面展開はあるのだが、眠気を払拭するようなシーンはほとんどなかったと思う
構成的にも、生き返るのがほぼ中盤で、冒頭のマーラーが娘の部屋に行くだけでも長いシーンになっているので、あの瞬間にリズムを捕捉できる人だけがついていけるのかな、と感じた
テーマは悪くないと思うが、かなり悪趣味な部類になると思うので、不快に思う人もいると思うし、倫理的であるようにも思えない
そう言った点も踏まえて、観る人を選ぶ映画だったのではないだろうか
生けるものと死せるものの境目
北欧ホラーらしい静かな恐怖を描く作品。
人間とは何か? 人間でなくなる条件とは何か? 愛するものをどこまで愛し続けられるのか?
ジャンル的にはゾンビものということになるのでしょうが、愛してる人間が生きてるとも死んでるとも言えない状態になったとき、人は何をするのか?
静かにゆっくりとそれでいて確実な重さを持って問いかけてくる作品です。
タイトルなし(ネタバレ)
死体復活メランコリー映画!
亡くなった人の事は諦めて次の人生を歩む決断が大事、、、
死者から音がする
死体を掘り起こす
孫を掘り起こす
腐乱死体に語りかける
お湯に着ける
ショックでラップ巻き自殺
わたしは最悪
反応する子どもは"生"なのか
死んだ人、お帰りなさい
死体が死体を呼ぶ
ウサギを握り殺す
ママは死んだ
やっぱり死んでる
動く死者は人間では無い
北欧らしい静謐で神秘的な雰囲気に満ちた、異色のゾンビホラー
ノルウェーのオスロで、ある日突然死者が蘇る。異なる3つの家族が、“蘇った死者”となったそれぞれの肉親と触れ合う中で、愛する人を失なった悲しみを癒そうとする。
監督・共同脚本・製作総指揮には、『ぼくのエリ 200歳の少女』(08)『ボーダー 二つの世界』(18)で知られるスウェーデンの鬼才ヨン・アイヴィア・リンドクヴィスト。同じく監督・共同脚本として、本作が長編デビューとなるテア・ヴィスタンダル。
私自身は、ヨン監督作品は初鑑賞。しかし、『ぼくのエリ』というタイトルは知っていたし、ライムスターの宇多丸さんが自身のラジオ番組で『ボーダー』を絶賛していた事もあり、本作に興味を惹かれた。
“恐怖”よりも“悲しみ”が勝るゾンビ映画というオリジナリティが新鮮で、常に画面を漂う不穏な空気が独特の緊張感も生み出している。一時は「コレ、どうやって終わらせるの?」と不安にもなったが、ラストの展開には納得が行くし、個人的には好みだった。
また、そんな雰囲気を演出する音楽の効果が絶大で、担当のピーター・レイバーンの仕事が無ければ、本作の持つ世界観は実現しなかっただろう。特に、事態が動く際の「ヴォオオオン」と響く音が抜群に良かった。
ノルウェーの首都オスロ。息子エリアスを亡くしたばかりの母親アナとその父マーラーは、深い悲しみに包まれ、親子間にも気まずい空気が流れていた。豪華な邸宅で2人暮らしをしていたトーラは、パートナーのエリーザベトの葬儀の直後だった。子供思いの母エヴァ、スタンダップ・コメディアンの父ダヴィッド、反抗期真っ只中の娘フローラ、誕生日を直前に控えた息子キアンの4人家族は、エヴァを突然の交通事故で亡くしてしまう。
しかし、街を大規模な停電が襲った直後、孫の墓参りに来ていたマーラーは、土の中で棺を叩く音を耳にする。墓を掘り起こし、棺を開けると、弱々しくもエリアスは確実に生き返っていた。すかさずマーラーは、エリアスを自宅へと連れて帰る。翌日、トーラの邸宅をエリーザベトが訪れ、病室で息を引き取ったはずのエヴァは指が動き始めた。
街は蘇った死者の対応に追われ、各地でサイレンの音が鳴り響き、静かな混沌が拡がりはじめていた。
台詞を極力廃し(だからこそ、例えばアナの旦那が今どうしているか?等は一切語られない)、映像と音の演出をメインに紡ぎ出される本作の世界観は、不思議な魅力を放っていた。静かな作品ではあるが、決して冗長な印象は与えない。自然豊かなオスロの景色が美しく、街中や墓地にも常に緑がある。アナ達が湖畔の別荘に避難する様子も神秘的。
しかし、そんな美しい世界観の裏には、常に不穏な空気が漂うのだ。その最大の要因は、既にゾンビ映画がホラーの一大ジャンルとして確立しており、長い歴史の中で積み上げられてきた“お約束”があるからこそだろう。「エリアスの腹の音は、腐敗して腹部が膨張したからではなく、人肉を貪り喰らう前の空腹音なのではないか?」「兎を絞め殺したエヴァは、この後急に家族を襲い始めるのではないか?」と、ゾンビが人を襲う瞬間への“前フリ”がキチンと為されている点も、こちらの不安を煽るのだ。
だが、本作はそうしたお約束を見事に裏切り(一部予想通りの展開はある)、決してスプラッターホラーのジャンルには走らず、蘇った死者と接する中で、それぞれが静かに異なる「別れ」を経験するという方向へ舵を切る。それは、愛する者の死を「受け入れた者」、愛する者の手で「命を摘み取られた者」、愛する者に「2度目の別れを告げた者」の3パターンだ。
ダヴィッド一家は、兎を絞め殺したエヴァの物言わぬ恐怖に「母は死んだ」と否が応でも別れを受け入れなければならず、トーラは甲斐甲斐しく世話をしていたエリーザベトに喰い殺されてしまう。そしてアナは、エリアスに「また会えるから」と静かに別れを告げ、湖にゆっくりと彼を沈め孤独に佇む。
ゾンビ映画に於いて、ここまで「別れ」の瞬間にフォーカスした作品も珍しいだろう。しかし、実際には多くの人々は、本作の登場人物達のように愛する人が蘇った際には、似たような反応を示すのではないだろうか?
また、ゾンビとなった人々も、あくまで人間であり、何よりも死者なのだ。だからこそ、超人的な身体能力を発揮したり、凶暴性が増したりもしない。精々がリミッターが外れて力加減が出来なくなる、就寝中の相手や老人を喰い殺すに留まる。
こういった絶妙な“リアリティ”を演出する目の付け所が新鮮だった。
静謐で神秘的ながら、確かな映画的力強さ、メッセージ性をも感じさせる異色のゾンビ映画だった。
見たい絵が続く映画
いわゆるゾンビ映画のような、襲われるので戦う!といったものではない静かな映画です。
ストーリーとしては単純。有名な「猿の手」みたいな感じ
大切な人の死を受け入れられなかった家族のもとに死者が戻ってきたら?そんな3家族が描かれる
最初はただいるだけで嬉しくてたまらない。けれど、蘇った死者は元の「人」ではないおぞましいゾンビなのだ。それに遅まきながら気づかされる家族たち。
ドラマチックな展開は特にない静かな映画だけれど、言語化できないような生理的な気持ち悪さを醸し出すシーンの多さ。音楽も不気味でよかった
腐敗してもLOVE。
ある日電磁波的な事で誤作動を起こすカーデッキとエンジン停止の車s、その流れからの停電で死者が蘇ちゃう話。
ある日、孫の墓参りに行ったマーラーが墓下からの物音に気づき、掘り返したら腐敗はしてるけど呼吸をしてる孫を発見し家に連れて帰ることになるが…。
話を思い出しあらすじを書いてるが…、本作を観てる最中は大筋のストーリーがずっと???で。
蘇った死者、個体に差があり最初から歩く婆さん、呼吸と瞬きする子供と…、何か中途半端な感じなものをずっと見せられ進展なしな感じ。
終盤ラスト別荘に現れたゾンビ、あっ人を襲うのね!てか、その展開を早い段階から見せてくれ!って感じでストーリーにアップダウンの強弱をもっと付けて欲しかったかな。ずっと平坦な一本道みたいで冒頭から観てるのがキツかった。
あの小バエが周りに飛んでる時点でちょっと無理だし最終的に湖に還すなら最初から元の場所へ還してあげたらって感じだった。
タイトルなし(ネタバレ)
墓の下で音がしたら、掘り起こさなければいつか後悔で死んでしまうだろう。その後の経験がどれほど辛くても…父親とすら共有する事を拒み、一人で喪失の中に晒されている母親…最愛の妻、母親、パートナー…
最初から愛しき者を失った壮絶な痛みの中に入り込み、息を呑んだ。
静かな演技が胸をつく瞬間が、最後まで続いた。
愛しき者が帰ったが、満たされる訳では無かった。それでも、目の前の人を愛している。。
この映画は、ホラーではなくて純愛ものか。
そして、最後には二度目の喪失を迎える。
酷い様だけど、悲しみに向き合う事ために必要だったのかもしれない。
その後の、ゾンビが世界を侵食する世界の幕開けは、又他の作品で…ゾンビ映画は大好きなので。
何も楽しいことは起こらない映画
そもそもなぜ死者が蘇るのか。
どうして世の中がそれであの程度の騒ぎで済んでるのか。
死者が生者を喰らうという古典的な所作。
そもそもアレは死んでいるのか生きているのか。
『人』としてではなく生命体として生きていると言うならば、ラストで水中に沈めて、それで殺せるのだろうか。
それともずっと水中で苦しむ(?)のだろうか。
最後にあれだけのことをやらかした爺様があっさり謎のゾンビに食い殺されるとか、もう冗談かと。
正直テーマが重たいので、あの雰囲気を楽しめない人には完全拷問な映画でしょう。
自分は嫌いではないけど、『何故』も『どうした』あそこまで何も説明がないのでは、やはり消化不良は起こす。
退屈だ
格調高いゾンビ映画で眠くなる。ゾンビはほぼ植物人間だ。最後の最後でやっと人にかみつく。実際、愛する家族がゾンビで蘇っても嬉しいの最初の一瞬であとは困るだけで、湖に沈めるのも仕方がない。
良い言い方をすれば... "慎重" に物事が進む作品と言えるかも?
“Handling The Undead” is one of the best novels that I have read over
the better part of the last decade, so I was quite excited for this movie.
To say I was disappointed is an understatement. Not to mention, I was
so confused about it that I was compelled to skim back through the
book to reassure myself that I was correctly remembering what I had
read.
ある国の動画サイトで既にデジタルプラットフォームで配信が始まっている。一視聴者の鑑賞後のレビューの一部を載せてみました。
最後には、"It was not “Handling The Undead.” You have been warned." と言い切るほど失望を隠せないファンのコメント... 正直なところ、この人何かを勘違いしている。というのも本作の脚本はヴィスタンダル監督ともう一人、原作者ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィストが共同執筆をしている。それに彼ら二人して仲良く動画サイトで本作について終始笑顔を絶やさずに抱負を語っていた。"Bookophile" とペンネームで用いるほどの愛読者なのに、そんな事を知らないはずは、ないのだけれど?いつものように話が長くなるので本編に戻ると...
Dr. Pinelli:Her heart rate is very slow, and her oxygen level
is so low that we can't understand how she's still
alive.
・・・・・・・・・・(省略)
David:She's alive, though?
ピネリ医師は続ける...
Dr. Pinelli:Yes, but we've never seen this before.
この映画は、確かに原作とは異なる設定になっている。愛する人を亡くした家族と数千人にのぼる蘇生した人々の事件を解決しようと対処するスウェーデン当局と家族とのアツレキを一切省き、その代わり、残された家族の喪失感から生まれた悲しみや蘇生者(undead)に対しての思慕であり、先行きの不安感、そして誰もが敬意を払う "人への尊厳" などに重点をシフトしている。特に個々の出演者を挙げるとフローラの性格が原作とはかなり異なり、原作ではメインキャラで、しかも本編のように利己的でわがまま娘ではなく、180度違い、賢く、強く、勇敢な十代の理想像として描かれている。
Mom is dead. (※娘フローラによる蘇生者に対する思いであり、ある意味、映画の大まかな包括的メタファーとなっている。)
そして何よりこれより...
個人的には、会話に対してミニマリストとしてアプローチを試み、ストーリーテリングを視覚的に考えると絶妙で微妙なレンズに映し出されるのは、季節の明るさはほとんどなく、すべてが枯れ果てたカーキ色とホワイト・グレーの重圧を感じさせるモノトーンの光に包まれた世界であって、そこには甲高い弦楽器と不協和音のピアノによる苦悩を表現するフィルム・スコアによって時間が存在しないようにゆっくりと進む。それらの効果でも、このような受動的で中間的な生き物に対してできることは限られている。魂のないこれらの体が何らかの生命の模倣に向けて養われ、育てられている間も、家族らには圧倒的な悲しみの感覚が続く。だから、各々のシーンを見ている者がおろそかにできないし、それに応えるように登場する人たちの心理描写が細かく描かれ卓越している。それらの印象が薄ければ "慎重" という言葉ではなく "緩慢" にすり替えられ中身のない、意味に深みのないと捉える人もいるのは許せるのかもしれない。
本作にははっきりとした分水嶺となるシーンがある。
街中に不気味な雰囲気が漂い、突然の停電。群がる鳥。そして終末を告げる車の警報音が静まり返ったオスロの夜の街に響き渡り、生と死の境界が突然この世に現れたのではないかという不安が、より鮮明になる。
繰り返して
Mom is dead. この言葉が本作のトリガー警告となっている。
蘇生者が帰還して以来、彼らの存在の不安定さ... 呼吸や心拍数はあるけども通常では生きていけない程のレベルで、始めから終わり近くになるまでメランコリックな恐怖に満ちていて見ている者としては、出口の見えない不安感にかられ続けられた。
この警告のおかげで、蘇生者が "undead" と位置付けられゾンビ映画として成立したことであたし自身、その事で蘇生者の「どうなってしまうのか?」という本編中、ずうっと続いていた不安感が一掃されたと同時に解放され安どした。
この映画には、もう一つのテーマがある。それは生き返ったパートナーと老婦人がダンスをするシーンにある。その時、流れていたのが、史上最高の歌手ニーナ・シモンによる ♪Ne Me Quitte Pas この歌は「行かないでくれ 忘れるべきだ」という歌詞から始まる。元々はジャック・ブレルという人が女性と別れた後に書いたもので、彼自身「ラブソング」ではなく、「男性の臆病さへ向けた賛美歌 」であると語っている。
この事は、ラストシーンで主人公アナのとった行動に比喩的暗示として反映されている。
聖ならぬ愛
北欧のホラーは静謐で、無駄を省いてテーマを強調するタイプが主流。そして、その琴線に触れたハリウッドの製作者がリメイクを狙うケースが多い。本作はそんな「死者復活」が主題だが、未来的にはゾンビ化するトリガーも弾いている。起伏に乏しい物語がはらむ、近未来の阿鼻叫喚の殺戮への、静かなプレリュードとしての立ち位置だろう。
全16件を表示