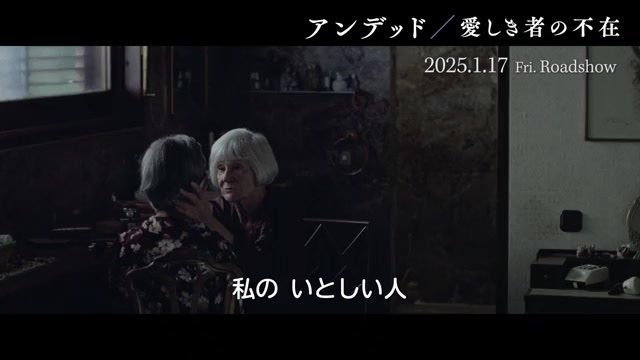アンデッド 愛しき者の不在のレビュー・感想・評価
全45件中、21~40件目を表示
タイトルなし(ネタバレ)
死体復活メランコリー映画!
亡くなった人の事は諦めて次の人生を歩む決断が大事、、、
死者から音がする
死体を掘り起こす
孫を掘り起こす
腐乱死体に語りかける
お湯に着ける
ショックでラップ巻き自殺
わたしは最悪
反応する子どもは"生"なのか
死んだ人、お帰りなさい
死体が死体を呼ぶ
ウサギを握り殺す
ママは死んだ
やっぱり死んでる
動く死者は人間では無い
そしてだれもいなくなる、のか?
北欧らしい静謐で神秘的な雰囲気に満ちた、異色のゾンビホラー
ノルウェーのオスロで、ある日突然死者が蘇る。異なる3つの家族が、“蘇った死者”となったそれぞれの肉親と触れ合う中で、愛する人を失なった悲しみを癒そうとする。
監督・共同脚本・製作総指揮には、『ぼくのエリ 200歳の少女』(08)『ボーダー 二つの世界』(18)で知られるスウェーデンの鬼才ヨン・アイヴィア・リンドクヴィスト。同じく監督・共同脚本として、本作が長編デビューとなるテア・ヴィスタンダル。
私自身は、ヨン監督作品は初鑑賞。しかし、『ぼくのエリ』というタイトルは知っていたし、ライムスターの宇多丸さんが自身のラジオ番組で『ボーダー』を絶賛していた事もあり、本作に興味を惹かれた。
“恐怖”よりも“悲しみ”が勝るゾンビ映画というオリジナリティが新鮮で、常に画面を漂う不穏な空気が独特の緊張感も生み出している。一時は「コレ、どうやって終わらせるの?」と不安にもなったが、ラストの展開には納得が行くし、個人的には好みだった。
また、そんな雰囲気を演出する音楽の効果が絶大で、担当のピーター・レイバーンの仕事が無ければ、本作の持つ世界観は実現しなかっただろう。特に、事態が動く際の「ヴォオオオン」と響く音が抜群に良かった。
ノルウェーの首都オスロ。息子エリアスを亡くしたばかりの母親アナとその父マーラーは、深い悲しみに包まれ、親子間にも気まずい空気が流れていた。豪華な邸宅で2人暮らしをしていたトーラは、パートナーのエリーザベトの葬儀の直後だった。子供思いの母エヴァ、スタンダップ・コメディアンの父ダヴィッド、反抗期真っ只中の娘フローラ、誕生日を直前に控えた息子キアンの4人家族は、エヴァを突然の交通事故で亡くしてしまう。
しかし、街を大規模な停電が襲った直後、孫の墓参りに来ていたマーラーは、土の中で棺を叩く音を耳にする。墓を掘り起こし、棺を開けると、弱々しくもエリアスは確実に生き返っていた。すかさずマーラーは、エリアスを自宅へと連れて帰る。翌日、トーラの邸宅をエリーザベトが訪れ、病室で息を引き取ったはずのエヴァは指が動き始めた。
街は蘇った死者の対応に追われ、各地でサイレンの音が鳴り響き、静かな混沌が拡がりはじめていた。
台詞を極力廃し(だからこそ、例えばアナの旦那が今どうしているか?等は一切語られない)、映像と音の演出をメインに紡ぎ出される本作の世界観は、不思議な魅力を放っていた。静かな作品ではあるが、決して冗長な印象は与えない。自然豊かなオスロの景色が美しく、街中や墓地にも常に緑がある。アナ達が湖畔の別荘に避難する様子も神秘的。
しかし、そんな美しい世界観の裏には、常に不穏な空気が漂うのだ。その最大の要因は、既にゾンビ映画がホラーの一大ジャンルとして確立しており、長い歴史の中で積み上げられてきた“お約束”があるからこそだろう。「エリアスの腹の音は、腐敗して腹部が膨張したからではなく、人肉を貪り喰らう前の空腹音なのではないか?」「兎を絞め殺したエヴァは、この後急に家族を襲い始めるのではないか?」と、ゾンビが人を襲う瞬間への“前フリ”がキチンと為されている点も、こちらの不安を煽るのだ。
だが、本作はそうしたお約束を見事に裏切り(一部予想通りの展開はある)、決してスプラッターホラーのジャンルには走らず、蘇った死者と接する中で、それぞれが静かに異なる「別れ」を経験するという方向へ舵を切る。それは、愛する者の死を「受け入れた者」、愛する者の手で「命を摘み取られた者」、愛する者に「2度目の別れを告げた者」の3パターンだ。
ダヴィッド一家は、兎を絞め殺したエヴァの物言わぬ恐怖に「母は死んだ」と否が応でも別れを受け入れなければならず、トーラは甲斐甲斐しく世話をしていたエリーザベトに喰い殺されてしまう。そしてアナは、エリアスに「また会えるから」と静かに別れを告げ、湖にゆっくりと彼を沈め孤独に佇む。
ゾンビ映画に於いて、ここまで「別れ」の瞬間にフォーカスした作品も珍しいだろう。しかし、実際には多くの人々は、本作の登場人物達のように愛する人が蘇った際には、似たような反応を示すのではないだろうか?
また、ゾンビとなった人々も、あくまで人間であり、何よりも死者なのだ。だからこそ、超人的な身体能力を発揮したり、凶暴性が増したりもしない。精々がリミッターが外れて力加減が出来なくなる、就寝中の相手や老人を喰い殺すに留まる。
こういった絶妙な“リアリティ”を演出する目の付け所が新鮮だった。
静謐で神秘的ながら、確かな映画的力強さ、メッセージ性をも感じさせる異色のゾンビ映画だった。
見たい絵が続く映画
いわゆるゾンビ映画のような、襲われるので戦う!といったものではない静かな映画です。
ストーリーとしては単純。有名な「猿の手」みたいな感じ
大切な人の死を受け入れられなかった家族のもとに死者が戻ってきたら?そんな3家族が描かれる
最初はただいるだけで嬉しくてたまらない。けれど、蘇った死者は元の「人」ではないおぞましいゾンビなのだ。それに遅まきながら気づかされる家族たち。
ドラマチックな展開は特にない静かな映画だけれど、言語化できないような生理的な気持ち悪さを醸し出すシーンの多さ。音楽も不気味でよかった
火葬は正義。
モブも含めて20人も登場人物がいない小規模な映画。
派手なシーンはほとんどなく、大きな音のするシーンも数えるほどじゃないか。
多くの時間帯で画面は静謐で端正。
車の種類からしたら舞台は現代だけどスマホは出てこない。舞台が日本だったら不自然すぎてノイズになりすぎたのでは。そう言うファンタジックな世界なのかも知れない。
死んだはずの人が蘇る。
目に見えて凶暴なわけではないので病院で徹底的に調べられてるのはちょっと面白い。その診断結果が「何でかわからない」なのはちょっとズルい。
失われた物を取り戻したいと願う気持ち。
それが部分的にしか戻ってこなかった時の気持ち。
0か100かではない。閾値の問題。
肉体は無傷でも意識が失われているのは明らかに嫌だ。意識明朗で五体不満足はそれよりも遥かに良い。
主演の女性が「わたしは最悪」の彼女だったとはパンフ読むまでわからなかった。
気になったシーン。
4人家族の娘が裸バイクの彼氏と出かけた先。
やたら柱の多い水場で鳩に餌をやっているところ。
あれは何の場所なんだろう?橋の下?印象に残る画。
彼は自分の母親が死んでいること、彼女の母親が異常な状態にあること、それをジョークにする程度には人非人的でありながら鳩にはわざわざ餌をやるんだ、と言う歪みがあるんだな。
ヒュッテにやってきたリビングデッドに祖父が殺されるシーンは唐突に感じた。結局ゾンビなんかい!人を襲うんかい!とも思った。
静かな静かな怪異譚
説明的なものを省いた、ひたすら静かな怪異譚。
残された人にとってみれば、大切な人が蘇ってくることは単純に嬉しい。
けれど、
蘇った人の状態は様々で、事故に遭い生々しい傷が残る姿。
埋葬されているうちに腐敗が進み、蠅がたかる変わり果てた姿を見せつけられる…
意志疎通のできない、ただただ存在するだけの故人に対する人間の反応を描いたゾンビ映画。
故人と再会できた喜びが、次第に愛も情も伝わらないもどかしさに変わっていく…
故人に執着し続けた者や、改めて死を受け入れた者たちを描いている。
土葬ならではの表現もあり、改めて日本は火葬文化になって良かったとしみじみ
説明不足が助長で退屈と判断する人と、〈死〉について哲学的な問いを見つけ出す人に分かれそうな作品。
喪失感だけが突き刺さる一本でした。
もし自分なら…?
【”愛しい人の黄泉がえり・・。”今作は、愛する人を失った数組の男女の行動を通して、”死者に拘り、過去に執着しすぎると、悲劇が起きる。”という事を超自然的描写を交えて、シニカルに描いた作品である。】
■今作では、
1.姉妹の様なパートナーを失った老婦人
2.妻が交通事故で死んでしまった夫とその娘と息子
3.幼い子供を失った母と、祖父
が、家族を喪失した哀しみと、超自然的な現象で戻って来た希望を交錯させながら、物語は進む。
◆感想<Caituion!内容に触れています。>
・老婦人の元に、葬儀を終えた後にパートナーが戻って来るが、彼女の皮膚の色は生者のモノではない。だが、老婦人はパートナーの身体を丁寧に拭き、パンにマーガリンを付けて食べさせる。すると、それまで無表情だったパートナーは、イキナリガツガツとパンを食べるのである。怖い。そして、予想通りの事が起こるのである。
・妻が交通事故で死んだが、何故か蘇る。だが、妻は一言も喋らない。交通事故に遭う前は口うるさいほどに、家族に色々と注意していたのに・・。
そして、夫とその娘と息子が息子の誕生日プレゼントだと言って持って来たウサギを物凄い力で、絞殺するのである。滴り落ちる血痕。怖いシーンである。
・幼い子供を失った母と、祖父。墓地で不思議な音を聞いた祖父は、独り墓地で棺を掘り出す。そこには、青い色の皮膚をした子供がいる。家に連れて帰るが、子供は目を見開いたまま、仰臥している。
二人は、子供を森の別荘に運ぶが、そこにアンデッドが現れ、老人と取っ組み合いにして殺す。母は、それを見て禁忌を犯してしまったと思い、子供をボートに乗せ湖に再び葬るのである。
<今作は、ジャンルで言えば北欧ホラーになるのであろう。そこでは”忘れる事と、手放すことは違う。”という暗喩がシニカルに描かれているのである。
今作は、”死者に拘り、過去に執着しすぎると、悲劇が起きる”というモチーフを描いた作品ではないかなと思った作品である。>
腐敗してもLOVE。
ある日電磁波的な事で誤作動を起こすカーデッキとエンジン停止の車s、その流れからの停電で死者が蘇ちゃう話。
ある日、孫の墓参りに行ったマーラーが墓下からの物音に気づき、掘り返したら腐敗はしてるけど呼吸をしてる孫を発見し家に連れて帰ることになるが…。
話を思い出しあらすじを書いてるが…、本作を観てる最中は大筋のストーリーがずっと???で。
蘇った死者、個体に差があり最初から歩く婆さん、呼吸と瞬きする子供と…、何か中途半端な感じなものをずっと見せられ進展なしな感じ。
終盤ラスト別荘に現れたゾンビ、あっ人を襲うのね!てか、その展開を早い段階から見せてくれ!って感じでストーリーにアップダウンの強弱をもっと付けて欲しかったかな。ずっと平坦な一本道みたいで冒頭から観てるのがキツかった。
あの小バエが周りに飛んでる時点でちょっと無理だし最終的に湖に還すなら最初から元の場所へ還してあげたらって感じだった。
タイトルなし(ネタバレ)
墓の下で音がしたら、掘り起こさなければいつか後悔で死んでしまうだろう。その後の経験がどれほど辛くても…父親とすら共有する事を拒み、一人で喪失の中に晒されている母親…最愛の妻、母親、パートナー…
最初から愛しき者を失った壮絶な痛みの中に入り込み、息を呑んだ。
静かな演技が胸をつく瞬間が、最後まで続いた。
愛しき者が帰ったが、満たされる訳では無かった。それでも、目の前の人を愛している。。
この映画は、ホラーではなくて純愛ものか。
そして、最後には二度目の喪失を迎える。
酷い様だけど、悲しみに向き合う事ために必要だったのかもしれない。
その後の、ゾンビが世界を侵食する世界の幕開けは、又他の作品で…ゾンビ映画は大好きなので。
何も楽しいことは起こらない映画
そもそもなぜ死者が蘇るのか。
どうして世の中がそれであの程度の騒ぎで済んでるのか。
死者が生者を喰らうという古典的な所作。
そもそもアレは死んでいるのか生きているのか。
『人』としてではなく生命体として生きていると言うならば、ラストで水中に沈めて、それで殺せるのだろうか。
それともずっと水中で苦しむ(?)のだろうか。
最後にあれだけのことをやらかした爺様があっさり謎のゾンビに食い殺されるとか、もう冗談かと。
正直テーマが重たいので、あの雰囲気を楽しめない人には完全拷問な映画でしょう。
自分は嫌いではないけど、『何故』も『どうした』あそこまで何も説明がないのでは、やはり消化不良は起こす。
退屈だ
格調高いゾンビ映画で眠くなる。ゾンビはほぼ植物人間だ。最後の最後でやっと人にかみつく。実際、愛する家族がゾンビで蘇っても嬉しいの最初の一瞬であとは困るだけで、湖に沈めるのも仕方がない。
全45件中、21~40件目を表示