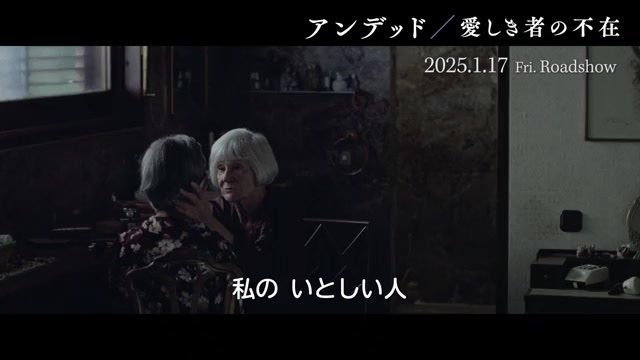「北欧らしい静謐で神秘的な雰囲気に満ちた、異色のゾンビホラー」アンデッド 愛しき者の不在 緋里阿 純さんの映画レビュー(感想・評価)
北欧らしい静謐で神秘的な雰囲気に満ちた、異色のゾンビホラー
ノルウェーのオスロで、ある日突然死者が蘇る。異なる3つの家族が、“蘇った死者”となったそれぞれの肉親と触れ合う中で、愛する人を失なった悲しみを癒そうとする。
監督・共同脚本・製作総指揮には、『ぼくのエリ 200歳の少女』(08)『ボーダー 二つの世界』(18)で知られるスウェーデンの鬼才ヨン・アイヴィア・リンドクヴィスト。同じく監督・共同脚本として、本作が長編デビューとなるテア・ヴィスタンダル。
私自身は、ヨン監督作品は初鑑賞。しかし、『ぼくのエリ』というタイトルは知っていたし、ライムスターの宇多丸さんが自身のラジオ番組で『ボーダー』を絶賛していた事もあり、本作に興味を惹かれた。
“恐怖”よりも“悲しみ”が勝るゾンビ映画というオリジナリティが新鮮で、常に画面を漂う不穏な空気が独特の緊張感も生み出している。一時は「コレ、どうやって終わらせるの?」と不安にもなったが、ラストの展開には納得が行くし、個人的には好みだった。
また、そんな雰囲気を演出する音楽の効果が絶大で、担当のピーター・レイバーンの仕事が無ければ、本作の持つ世界観は実現しなかっただろう。特に、事態が動く際の「ヴォオオオン」と響く音が抜群に良かった。
ノルウェーの首都オスロ。息子エリアスを亡くしたばかりの母親アナとその父マーラーは、深い悲しみに包まれ、親子間にも気まずい空気が流れていた。豪華な邸宅で2人暮らしをしていたトーラは、パートナーのエリーザベトの葬儀の直後だった。子供思いの母エヴァ、スタンダップ・コメディアンの父ダヴィッド、反抗期真っ只中の娘フローラ、誕生日を直前に控えた息子キアンの4人家族は、エヴァを突然の交通事故で亡くしてしまう。
しかし、街を大規模な停電が襲った直後、孫の墓参りに来ていたマーラーは、土の中で棺を叩く音を耳にする。墓を掘り起こし、棺を開けると、弱々しくもエリアスは確実に生き返っていた。すかさずマーラーは、エリアスを自宅へと連れて帰る。翌日、トーラの邸宅をエリーザベトが訪れ、病室で息を引き取ったはずのエヴァは指が動き始めた。
街は蘇った死者の対応に追われ、各地でサイレンの音が鳴り響き、静かな混沌が拡がりはじめていた。
台詞を極力廃し(だからこそ、例えばアナの旦那が今どうしているか?等は一切語られない)、映像と音の演出をメインに紡ぎ出される本作の世界観は、不思議な魅力を放っていた。静かな作品ではあるが、決して冗長な印象は与えない。自然豊かなオスロの景色が美しく、街中や墓地にも常に緑がある。アナ達が湖畔の別荘に避難する様子も神秘的。
しかし、そんな美しい世界観の裏には、常に不穏な空気が漂うのだ。その最大の要因は、既にゾンビ映画がホラーの一大ジャンルとして確立しており、長い歴史の中で積み上げられてきた“お約束”があるからこそだろう。「エリアスの腹の音は、腐敗して腹部が膨張したからではなく、人肉を貪り喰らう前の空腹音なのではないか?」「兎を絞め殺したエヴァは、この後急に家族を襲い始めるのではないか?」と、ゾンビが人を襲う瞬間への“前フリ”がキチンと為されている点も、こちらの不安を煽るのだ。
だが、本作はそうしたお約束を見事に裏切り(一部予想通りの展開はある)、決してスプラッターホラーのジャンルには走らず、蘇った死者と接する中で、それぞれが静かに異なる「別れ」を経験するという方向へ舵を切る。それは、愛する者の死を「受け入れた者」、愛する者の手で「命を摘み取られた者」、愛する者に「2度目の別れを告げた者」の3パターンだ。
ダヴィッド一家は、兎を絞め殺したエヴァの物言わぬ恐怖に「母は死んだ」と否が応でも別れを受け入れなければならず、トーラは甲斐甲斐しく世話をしていたエリーザベトに喰い殺されてしまう。そしてアナは、エリアスに「また会えるから」と静かに別れを告げ、湖にゆっくりと彼を沈め孤独に佇む。
ゾンビ映画に於いて、ここまで「別れ」の瞬間にフォーカスした作品も珍しいだろう。しかし、実際には多くの人々は、本作の登場人物達のように愛する人が蘇った際には、似たような反応を示すのではないだろうか?
また、ゾンビとなった人々も、あくまで人間であり、何よりも死者なのだ。だからこそ、超人的な身体能力を発揮したり、凶暴性が増したりもしない。精々がリミッターが外れて力加減が出来なくなる、就寝中の相手や老人を喰い殺すに留まる。
こういった絶妙な“リアリティ”を演出する目の付け所が新鮮だった。
静謐で神秘的ながら、確かな映画的力強さ、メッセージ性をも感じさせる異色のゾンビ映画だった。