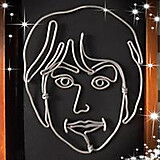名もなき者 A COMPLETE UNKNOWNのレビュー・感想・評価
全338件中、141~160件目を表示
あらゆるジャンルを超えた最高の映画
映画鑑賞後、Sony Music Japanの名もなき者公式予習プレイリストでティモシー・シャラメの映画での歌声とボブ・ディランのオリジナル楽曲を聴き比べしながら余韻に浸っております。
あらゆるジャンルを超えた最高の映画でした。私のベストムービー入りです。オスカーは無冠でしたが、私が審査員なら作品賞、監督賞、主演男優賞賞などすべてトップで推します!
ティモシー・シャラメは5年半をかけボブ・ディランの歌と演奏のパフォーマンスを自分のものにしたとの事だし、モニカ・バルバロもジョーン・バエズになっていた。2人のデュオがいくつも出てきたがその度に痺れたし、初めて「風に吹かれて」を自室でディランが歌った時バエズが追っかけて歌いハモるシーンに鳥肌がたった。スタジオで演奏してた「追憶のハイウェイ61」のディランが吹くあの笛の音や「ライク・ア・ローリング・ストーン」でアル・クーパーが弾くオルガンの高いキーの音など一音で強烈に響くシーンも感涙ものでした。ニューポート・フォーク・フェスティバルでフェンダーのストラトキャスターをかき鳴らし叫ぶように歌うシーンを筆頭にすべての場面で最高のパフォーマンスを観て、聴かせてもらいました。
スージー・ロトロ(映画ではシルヴィの名)との出会いと別れの物語は切ない青春物語だったけど、彼女の気持ち(ディランが遠い存在になっていく)もわかるし、音楽の世界の虜になり彼女だけを見ていれないディランの気持ちわかる。でもディランを社会に目を向けさせたのは彼女であることは紛れもない事実。エル・ファニングには助演女優賞を与えたいと思う。
公民権運動、キューバ危機、ケネディ大統領暗殺など60年代前半のアメリカの背景を差し込みながらも世の中は確実に豊かに向かい、人々が希望に満ちていた頃。日本も同じだったのではと思います。だから、映画を観ていてとってもいい気分になれたのかなぁ、。
タバコを吸う姿がかっこ良
「天才」の孤独を、周囲の「凡人」の視線の集積によって逆照射する、すぐれた音楽映画。
エンドロールのおしまいに流れてきた、
「これみよがし」な楽曲紹介に思わず笑う。
大量に流れてくる楽曲名の最終行に、ぜんぶ
「パフォームド・バイ・ティモシー・シャラメ」
「パフォームド・バイ・ティモシー・シャラメ」
「パフォームド・バイ・ティモシー・シャラメ」
って……(笑)。
あと、たまに
「パフォームド・バイ・モニカ・バルバロ」とか。
要するに、この映画って、歌も演奏も全部「俳優が自身でやってる」んだよな。
しかも概ね、生録りらしい。
それって、すごくない????
パンフによると、コロナとストがあったせいで5年近く撮影が延期されている間に、出演者が猛特訓して、やったこともなかった楽器や歌をマスターしてきたらしい。
ライブシーンを音は後入れでやろうとしたら、ティモシーが「なんのために俺が5年間練習してきたと思ってるんだ、このときのためなんだよ」って、生録音を希望したんだってさ。
やっぱり、ハリウッドの最前線でやってる連中ってのは、モニカ・バルバロやエドワード・ノートンも含めて、モノが違うなあ、と。
ポテンシャルとか、モチベーションとか、目標設定とか。
ただただ、頭がさがります。
― ― ― ―
正直、観る前は、自分にこの映画が愉しめるのか、あまり自信がなかった。
その1。ボブ・ディランに興味がない。
もともとクラシック9割、あとはシャンソンとシナトラ周辺を嗜む程度で、カントリー/フォークにはまったく関心がなく、ロックはツェッペリンとクイーンとプログレくらいしか聴かない人間なので、ボブ・ディランの楽曲全般にピンとくるものがあまりない。
あと、プロテスト・ソング自体、痛々しくて肌に合わないのでめったに聴かない。
なので、出てきた楽曲で聴いたことがあるのは、ボブの代表曲数曲と、あとは「朝日のあたる家」くらい(これ、おんなじことを『PERFECT DAYS』の感想でも書いたなw)。
知ってる人名も、ジョーン・バエズ、アル・クーパー、ジョニー・キャッシュくらい。ジョニー・キャッシュはカントリー歌手としてではなく、「刑事コロンボ」の「白鳥の歌」で犯人役をやっていたから知っているだけである。
その2。ティモシー・シャラメが、あまりかっこいいと思えない。
いい俳優だとは思う。凄い才能だとも思う。でも、顔が苦手(笑)。
なんか、DeNAのバウアーみたいな顔してるし。ちょっと目つきが橋本真也みたいだし。
個人的にはアラン・ドロンや岡田将生のような美形か、リー・ヴァン・クリーフみたいな渋めのおじさん俳優が大好物で、この手の二枚目の「変化球」に即応できないタイプ(だから韓流男性歌手の大半も全く受け付けない)。
その3。『ボヘミアン・ラプソディ』が全く肌に合わなかった。
すべての演出がトゥーマッチで、説明過多で、個人的にはただただ気持ちの悪い凡庸な映画にしか思えなかったので、世間的に大評判になっていて、大きな疎外感を感じた(笑)。
とくにラストライブでカメラをぐるぐる回したり、いちいち泣いてる家族のアップをインサートしたりするのにはさぶいぼが出た。あれがいいってやつは、月9でも観ていればいいとマジで思う。
なので、僕には『名もなき者』はかなり「ハードルが高い」かなと警戒していた。
でも……、いざ観たら、とても面白かった!
ふつうに楽しいし、演出は王道だし、とても映画として「ちゃんと」していた。
なにより音楽映画として、きわめて高い水準の音楽性をクリアしていた。
別にこれを観て、ボブ・ディランのことが好きになったとか、曲を聴いて胸がふるえたとかは残念ながらあんまりないけど、ちゃんとボブ・ディランとティモシー・シャラメの「本気」はビンビン伝わってきた。
おっかなびっくりだったけど、観に行って本当によかった。
ジェームズ・マンゴールド監督の名前は記憶になかったが、後で確認したら、あの本格ミステリー系どんでん映画の名作『アイデンティティー』の監督ではないか。『インディー・ジョーンズと黄金のダイヤル』も、クソミソに叩く声も多かったが個人的には★4.5をつけるくらい楽しめた快作だった。
なるほど、この監督なら「ちゃんと」撮れる人だよな、と腑に落ちた。
― ― ― ―
なにが「ちゃんと」しているかというと、
無理に感動させようとか、盛り上げようとか、
そういう姑息なことを考えていないのが良いのだと思う。
この物語では、60年代前半のボブ・ディランのデビューからロック転向までの5年程度を描いているが、そこに「成り上がり」ストーリーとしてのギラツキや、世間の狂奔はあまり感じ取れない。
つねに、ボブ・ディラン個人と、その周辺にいた人々の目に映る「私」の部分にのみ、焦点が当たっているからだ。すなわち「公」のボブを語ろうとしていない。
「外から」観れば、ヒットチャートを駆け上がり、政治的時代の寵児として君臨したライジングスター、ボブ・ディランを描くなら、もっと描くべきことがたくさんあるのかもしれない。ラジオ出演とか、大観衆を前にしたライブとか、全国ツアーとか、世界ツアーとか。あるいは、彼の政治的な発言とか、公民権運動とのかかわりとか。
でも、この映画では、そういったシーンは極力抑えられる。
かわりに、
●部屋で恋人と過ごすボブ・ディラン
●部屋やスタジオで作曲するボブ・ディラン
●中規模のホールやフェスで演奏するボブ・ディラン
●スタジオで録音するボブ・ディラン
といった、ボブ自身の視点、もしくはボブが連れてきた恋人や友人の視点から見える範囲でのナラティヴに終始していることがわかる。
一瞬、ドキュメンタリー映像のような形で、公民権デモの大観衆のただ中で歌う「ヒーローとしてのボブ・ディラン」が映り込むが、引きで撮った遠望の短いショットに過ぎない。映画が「こういうボブ」からは、あきらかに「距離を取っている」ことが伝わってくる。
(そしてそれは、おそらくジョーン・バエズほどには「骨の髄からの社会運動家」だったわけではなく、あくまで「素材」として政治を歌っていただけだった、ボブ・ディラン自身の政治との距離感でもあるような気がする。)
本作でのボブ・ディランは、
おおむね歌っているか、曲を作っている。
それを身近な誰かが見ている、聴いている。
羨望や、憧れや、妬みや、諦めを胸に秘めながら。
基本的に、この映画はその積み重ねで構成されている。
だから、誇張がなく、内省的で、インティメットな映画になっている。
― ― ― ―
『名もなき者』は、どこまでも「視線」の映画だ。
そして、同時に常に「聞き耳を立てている」映画だ。
誰かが、誰かを見つめるとき。
誰かが、誰かの演奏を耳を澄まして聴くとき。
そこには常に、相手への愛情や友愛の感情とともに、批評的観察や、お互いの優劣を見極めるライバル心が絡んでくる。
見つめること(聴くこと)は、常に二者間の闘争の行為でもあるのだ。
最初のころ、舞台袖で羨望を秘めた眼差しをピートやジョーンに向けているのは、ボブのほうだった。歌に関しても、序盤は人の曲を聴いたり歌わされているシーンが多い。
そこから、オリジナル曲が次第に増えていく。作曲と、録音という、地道な「曲を増やす」作業が何度も何度も丁寧に描写され、やがてボブは完全に自身のオリジナル曲「だけ」を歌う歌手になり(これは当時のフォーク界ではむしろ稀なことだったらしい)、ついには「自分の過去の曲」すら歌わなくなる。
ジョーン・バエズとのデュエットでも、歌うのはボブ作曲の曲になり、いつしかボブの歌を「舞台袖」から羨望の眼差しで見つめるのは、ジョーンのほうになる。
恋人であるシルヴィの、歌うボブを見つめる眼差しも、ボブの出世と交友関係の広がりを受けて変化せざるを得ないし、師匠としてボブを世界に引き出したピート・シーガーが彼に向ける眼差しも、優劣の逆転とともに変化していく。
この「視線」に関して、監督が面白いことを言っている。
「周囲の人々を描くことによって天才とはどういった存在かを理解しようとしている。また、天才を描く方法として私はそういうやり方しか知らないとも言える。(中略)周囲から向けられる視点や感情を描いて、天才の内面を想像させるやり方が、映画として有効なんだ」
さらに続けて、彼は師匠であるミロス・フォアマンの『アマデウス』を引き合いに出す。
要するに、「天才」は「天才」であるがゆえに、凡人にその内面を描くことはできない。
かわりに、その「周辺の人物」の想いを多面的に描くことで、いろいろな方向から天才に光を当て、「外から」立体的に把握しようと試みている、というわけだ。
「立ち位置」と「視線」によって演出を微細に組み立てていく手法は、カール・テオドア・ドライヤー以来の「映画の骨法」でもある。そこが「ちゃんと」しているからこそ、『名もなき者』は140分、ボブ・ディランの5年間を見せて、ぶれない。ゆるがない。
― ― ― ―
音楽映画としての完成度も、十分に高い。
代表曲と画期となる曲の大半をしっかりかけて、詰め込んだ印象になっていないのは、構成の妙といえる。
きちんと全身を映したあと、右手と左手のアップをしっかり見せて、本人が細かい手技まで駆使して演奏していることを強調している点や、必ずしも「歌マネ」をさせていない点にも、制作陣の見識が感じ取れる。監督いわく、「細部を忠実に丁寧に演じる、描くことによって真実が宿るというのがジョニー(・キャッシュ)からの教えで、今も忘れずに守っているよ」とのこと。とくに、当時の録音ブースの再現には力を入れたという。
細かいといえば、「客の反応」の描き方も細かい。
たとえば、終盤のあの有名なライブのシーンで、フォーク寄りの観客がモノを投げたりして反発を見せるのは確かなのだが、結構な観客が手を叩いて喜んでいるのが生々しい。ロック・パートの最後の曲近くになってくると、意外なくらいの数の観客がタテノリしながら曲に興じている様子を、ちゃんと描写しているのだ。
ピートが斧を見て妻のトシに制止されるあたりだけは、僕には演出過剰でちょっと気持ち悪かったが、総じて「無理やり感動させようとしない」抑制された演出が功を奏していたと思う。
― ― ― ―
以下、雑感。
●ボブ・ディランの女捌きがひどい(笑)。
ジョーン・バエズにしても、スーズ・ロトロ(映画では、ボブ・ディラン本人の要請によって名前をシルヴィに変えられている)にしても、もう少しくらいちゃんと扱ってやればいいのに。なんか、ちょっとカミーユ・ビダンみたい……。
●エドワード・ノートンの、ピート・シーガーへのなりきりぶりが素晴らしい。体じゅうから慈父のような良い人オーラが出ているし、出だしの包み込むような愛情と、終盤の焦りを含めた劣等感のギャップが、視線と表情だけで巧みに表現されている。
この人、スケジュールの都合で降りたカンバーバッチの代役だったんだってね!
●車の窓に自作の絵を押し付けてくる女とか、バーで「ファッキン本物がいる!」って叫ぶ女とか、ポイント毎に挿入される「追っかけ」の描写がこわい(笑)。スターと大衆の心理的距離が今より遠かった代わりに、SNSなどで頻繁に交流できないぶん、「生で会う」ことの衝撃性が段違いに強烈な時代だったんだろうなあ。
●僕は未見なのだが、『ウォーク・ザ・ライン 君につづく道』でのホアキン・フェニックスの演じたジョニー・キャッシュと、この映画のボイド・ホルブルックのジョニー・キャッシュって、演出的に共通点とか整合性とかあるんだろうか?
●パンフを読んでいたら、宇野惟正がマンゴールド監督の、こんな発言を引用していた。「自分の映画の主人公は大体、天賦の才の持ち主で、それが仇となって周囲と軋轢を生み、孤立していく人間なんだ」
こういう、「どういう人物像を撮りたい」という核となるものが明確にある監督だからこそ、逆に音楽映画、サスペンス、西部劇から、マーベル、インディー・ジョーンズまで、あらゆるジャンルで仕事ができるんだろうな、と思った。
魂が震える
60年以上前の擬似リアルを少しは追体験できたような気分になれました
学生時代によく聴いた曲ばかりで、思わず声を合わせていました(半径10mに他客がいなかったことは確認済) ‘78年の武道館=初来日で梯子を外されて以来45年!も封印してきたのに意外に覚えているものだ まるで劇中のNewportFesの客席にいるかのような140分で、十分に鑑賞料金のモトは取れましたね
でもこの作品では当時のDylanの心情をなぞることまではできない それどころかDylanの心理・心根をしみじみ映し出すシーンも皆無(滑り出しのデビュー前ではfolkという音楽形態には拘らないとは言っているけど、ホンマでっか?) 果たして当時のDylanがここまでノンポリだったのだろうか プロテストムーブメントには百%ビジネス的関わりであったかのような描かれ方(今ではユダヤ教に帰依、イスラエル支援者だと聞くけど)
デビュー当時の恋人Suze RotoloがSylvie Russoの別名で出てます 他には実名ばかりなので何かありそう 演じたは『I am Sam』のDakotaの妹だったんですね、似てる 劇中一緒に観た映画のBette D.の台詞で決別するのだが、本来なら“Ballad in Plain D”が劇伴挿入されるべきなのにな←歌中でParasite sister(寄生する姉)とされたSylvie/Suzeの姉も数度顔を出したが、それっきり この別名キャラ導入事由と共通事情なのかも 恐らくJoan Baezに関しても完全な事実との齟齬がありそう
Fes前からPete Seegerら運営陣はDylanがアコギとエレキGどっちを使うか気を揉んでいたが、エレキの持ち込みを許し、ステージでもアンプからプラグは伸びており、客席からも”Mr.Tambourine Man”をねだる声も多かったわけだし.....結果、Peteはうちのめされ、袖のPete奥さんToshiが微妙な表情を見せるカットもあって.....演出ありきなのか、正しく全貌を描き出してはいないようだ そもそもDragの存在を黙殺していては真実に辿り着けまい
でも古きを懐かしむ音楽イベントとしては大いに楽しめたので、個人的には無問題とします
興行的には大丈夫かな?
フォークからの自由
Bob Dylanといえば、ガロの「学生街の喫茶店」
あまり響いていこない…
フォークにはまらず
バエズの歌声が素晴らしい
I-MAXで見るべき作品です。1960年前半のディランを当時の音楽、社会、世界情勢などを含めて描かれています。キューバ危機、ケネディ暗殺、ベトナム戦争の時代の中でディランの人間性が作られて行き、フォーク、ゴスペル、ブルース、カントリーなども含まれているディランの音楽が生まれます。映画の中のディラン、ピート・シガー、ジョーン・バエズ、ジョニー・キッャシュ達の演奏は本人よりも出来が良いのでは?と思う程です。ビートルズ、キンクス、PPM、マリア・マルダー等の名前も絡めて当時の雰囲気が完璧に描かれていました。また、ディランとキッャシュが麻薬中毒を思わせるシーンも有ります。コロナ禍とストのため撮影がストップして完成までに5年かかり、この間ギターを猛練習して映画の完成度は上がりました。アカデミー賞は受賞できませんでしたが、バエズ役のモニカ・バルバロの演技と歌声は最優秀助演女優賞の価値があると思います。続編で、ザ.バンドとのベースメントテープ、プラネットウェイブ、全米ツアーまでが同じキャストで作られたら嬉しいです。
シャラメディランが素晴らしい
ティモシー・シャラメの歌、歌、歌
あの時代の曲を映画館で聴けたのが良かった
天才表現者の生き様ムービー
私はボブ・ディランという人をよく知らない。
なので舞台である1950-60年代の曲は全く心が惹かれませんでした。それが全体の3分の1か、4分の1と感じるぐらいあります。その殆どが荒っぽいカントリーソングです。とにかく長いです。文化的や歴史的な意味があると言われても、それ自体を映画の内容に落としてくれないと分かりませんでした。
ただ、その時代に歌が大ヒットして神様みたいな立ち位置に押し上げられたけど、それがイヤ。主人公は心の中を他人から勝手に決めつけられたくない、旅人のような人というのは伝わってきました。むしろ、それしかないかもしれません。
後になって他人から、それまで恋愛ソングしかなかったロックに詩的な内容を込めた先駆けの人と聞いて納得する部分もあるが、やはり、それ自体を映画にしてくれないと分からない。要するにボブ・ディランの軽い自己紹介みたいな映画。
歌唱に聴き惚れ、エモーショナルな描写に酔う
ボブ・ディランが駆け出しからスターダムに登り詰める映画中盤までの描写に圧倒されました。
俳優陣の歌唱はいづれも素晴らしく思わず拍手しそうになりました。また60年代のアメリカの世相や風俗をうまく織り交ぜ、叙情溢れる絵作りになっています。このあたり職人監督マンゴールドの手腕が如何なく発揮されていますね。
終盤は音楽の方向性を巡る対立やニューポートのフェスのシーンに少し時間を割き過ぎたようにも感じましたが、実話に基づく部分だし、必ずしも聖人ではない天才ディランの肝となる部分だったので、これはこれで良かったのかも知れません。
前半ディランとシルヴィがデートで観ていた映画 ベティ・デーヴィスの「情熱の航路」ですかね。映画.comのように感想を交歓する二人の初々しい描写にはほっこりさせられました。
あとタバコのシェアって今流行なのでしょうか?(アノーラでも見たような)
育った場所を超えること、レッテルの拒否。
2024年。ジェームズ・マンゴールド監督。何者でもない若き青年ボブ・ディランが、フォーク界であっという間に注目を浴びて成功する姿と、フォークにとどまらない作品創作の情熱との間で葛藤が生じていく姿を描く。何物にもとらわれない創作意欲は、周囲の人間関係や活動領域を次々と変えていくことにつながるという芸術家の苦悩。1960年代前半の数年間を描いているだけだが、既成の価値観が崩れていき、フォークが反戦ソングとして脚光を浴びていく時代に、意図せずにその体現者となってしまった男の姿が描かれる。
自分の過去を恋人にさえ明かさなかったり、ライブ中に途中退席したり、というお騒がせな言動は「レッテルを貼られることへの拒否」といえそうだが、それが人間関係では交際相手を怒らせ、活動領域では育ての親のフォーク界の大御所を悲しませることになる。天才の悲しい運命。
一度別れた恋人を時間がたった後でもう一度誘う時、二人はバイクに二人乗りする(ニケツというやつです)。このニケツシーンの躍動感がたまらない。明るい光と緑のなかを疾走する二人。ラストシーンでも新しい世界へと飛び出していく姿がバイクに乗る姿として描かれている。この映画でのバイクは「自由」そのものの表現なのだ。
あっぱれ、ティモシー・シャラメ。
ボブディランの若き日を描いた伝記映画。
伝記とはいっても、ほんの数年。しかし、そのわずかな年月に
数々のドラマがあったことがわかる。
ミュージシャンの伝記映画は、いろいろあるが、その中でも
最も心に響いた映画だった。
伝記ものにありがちな、お涙ちょうだいシーンはないし、
ドラマチックな演出はない。実際の話とは違う部分もあるが、
事実を淡々と描いているのが良かったと思う。
しかし、ティモシー・シャラメはすごい。噂通りのパフォーマンス。
ライブ録音らしいが、まさに、ボブディラン。
レジェンド中のレジェンドで、世界の頂点にいる
アーティストを演じ、歌まで歌うということで、相当の
プレッシャーだと思うけど、あっぱれです。
良かった
子供の頃からボブ・ディランの名前は知っていましたが、特に興味は無く、USA for AFRICAで初めて本人が歌う姿を見ても、メロディーに沿ってない歌い方も声も好きになれませんでした。
本作を観ようと思ったのは、予告編のティモシー・シャラメがカッコ良かったからです。
ディランの曲は「風に吹かれて」と「ライク・ア・ローリングストーン」をちょこっと聞いた事があるだけだから、知らない曲だらけで眠くなってしまわないように、前日に30分ほどYou Tubeを視聴しました。歌詞がいいなと思いました。そんな感じで鑑賞です。
まず、「ライオンは寝ている」から始まり、音楽映画として楽しいです。シャラメだけでなく、他の俳優の歌もとても良いです。
本作では若きディランが、才能を見い出されて一気にスターになったものの、周囲の期待と自分のやりたい事とのギャップに違和感を抱いていく姿が見られました。
ボブ・ディランという人は、気難しく、気まぐれで、いい加減な所がありますが、音楽への思いは真剣だと思いました。真面目に努力するというのとは違うかもしれないけど集中力がすごい。
詩のセンス、時代の流れを感じ取るセンスが天才的なんでしょうね。
フォークのファンがエレキギターを嫌うのは想像がつきますが、既存の曲に満足して新しいものを中々受け入れない、新曲さえ、というのはちょっと驚きです。
本作のニューポートフォークフェスのディランの演奏は最高でしたが、ブーイングの嵐が起こると同時に拍手喝采もありました。今の感覚では、これのどこが悪いんだろうと思ってしまいます。
大音量だけど芯の部分はブレていないと感じます。
余談。
子供の頃は地味で暗い、と好きではなかった日本の70年代フォーク。今はメロディや歌詞がきれいだなと思います。日本のフォークは情緒的ですね。
私が本場のフォークの方に興味が持てなかったのは、電子オルガン(エレクトーンの事ですが他社なので)の教材として知ったからかもしれません。シンプルだから、初級用のテキストによく載ってましたが、それだとフォークの魅力が分かりません。フォークは歌詞があってこそだなと思います。
全338件中、141~160件目を表示