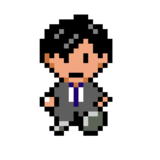名もなき者 A COMPLETE UNKNOWNのレビュー・感想・評価
全400件中、1~20件目を表示
ベロンとした顔の自由で骨太な魂
「その昔ステージで石を投げられたらしいよ」
音楽好きの友人がレコードジャケットを眺めていた私にそんな話をしてきた。「どうして?」と理由を尋ねると「フォークシンガーなのにロックを歌ったから」と友人は答えた。私はそのジャケットに写ったアメリカ人の顔をまじまじと見て「特徴の無いペロンとした顔だな」などと思った。更に別のアルバムジャケットに目を向けると女の子と腕を組んでいるではないか。あはは、なんと軟派な人だろう。
まさにその人物こそボブディランである。
映画「名もなき者」は若かりし日のディランが蘇り歌っているような臨場感がある。
ベロンとした顔立ちにハニカんだ眼差しをした青年はワザと力を抜いたような歌唱法で誰よりも力強くギターをかき鳴らし自作の歌を歌いあげる。私は映画館ではなくライヴハウスに居るような気持ちになり気がつけば劇中で歌うディランに何度も拍手をしていた。いや正確に言うとディランにではない。ディランを演じるティモシーシャラメにだ。
フォークソングにとらわれずブルースやロック、全ての音楽、そして本当の自由を愛したディラン。自由を愛するなんて簡単なことではない。凡人の自分にはまず無理だ。でもそんな彼だからこそ愛する恋人と身を寄せ合う写真がジャケットになり石を投げられてもステージで歌い続ける事が出来たのかもしれない。それをシャラメ青年はしっかり体現し観客を魅了している。
この映画はペロンとした顔立ちの若者がいかに自由で骨太な魂の持ち主であったかを改めて知る機会となった。
それはそうと、帰り道ミスタータンブリンマンを電車内で口ずさんでしまい恥ずかしかったな。
ただ、風に吹かれただけ
私の読み違いをしていたらごめんなさい。洋楽ばかり聴くけど歌詞は理解出来ず、歌詞の理解が無ければ、ボブ・ディランの歌は半分も理解出来てない事になるから。ここから下は、ボブ・ディランに対してではなく、あくまでも、この映画の理解です。
クライマックスのフェスでロックを歌い、大ブーイングを受けたボブ・ディラン。でもそうなることは判っていたかのよう。判っていても、ブーイングを喰らってモノを投げつけられても、それに逆らい続けて歌い通したのは何故か。それは彼が変わらず風に逆らって歌い続けただけでは無いでしょうか。
「逆らって」というと語弊があるかもしれませんが、時代の不安の中で歌ったのが「風に吹かれて」。童謡や唱歌が季節の歌を歌うように、時代に即した歌を歌うのも、ありのままの歌の在り方。だから当然のように時代に応じて「風に吹かれて」という歌が生まれたのではないか。
では、クライマックスのフェスでのロックはどうか。ボブ・ディランの心情はどうか。人気が上がり、ファンに囲まれ、歌をせがまれ、それを喜ぶどころか、なんだか辟易としたような、うんざりしているようなボブ・ディラン。だからフェスで歌った。「もう農場で働くのはゴメンだ」と。もう「風に吹かれて」のような歌は時代が違う。「時代は変わる」と歌えば、みんなも喜んで一緒に歌ったではないか。「手を貸せないのなら、新しい事からどいてくれ。時代は変わっているのだから」と。だから新しいロックを歌った。何が悪い?
・・・ていうのが私が映画で見た限りの理解なのですが、ボブ・ディランは実在の人で、映画はノンフィクションだし、評論家や多くのファン、そしてご本人の意向と全然違ってたらごめんなさい。私はこのような理解で「実に面白い映画だ」と思いました。
女性のところに泊まっても、変わらずギターを握って歌い続ける。ジョーン・バエズと共に歌う姿は正に男女の睦み合いのようで、元?恋人の彼女が幻滅して去って行くのも無理からぬ所。とにかく人気を得ることも、お金を稼ぐことも、ましてや文学賞にも興味が無い(表彰は拒否したそうですね)彼が目指したのは、冒頭のように変わらずエンディングでも訪れたウディ・ガスリーのようでありたかった、ということでしょうか。
ふと思い出してボブ・ディランの楽曲を聴いてみるのですが、やっぱり歌詞が理解出来ないとダメですね。歌声がとても味わい深いんですけどね。和訳を追ってみてもネィティブじゃないと感覚的に理解し得ない気がする。ただ、ジョーン・バエズさんの柔らかく伸びやかな歌声がとても好きです。アルバムはどこを探しても見かけないのでアップルストアから音源を入手しました。かのレッド・ツェッペリンも彼女の曲をコピー(パクリ?)したそうで、それで興味を引いてチェックしたのですが、ボブ・ディランとの繋がりはよく知らなかった。また、ジョーンさんの「ドナ・ドナ」は絶品です。
あと、役者さんについてですが、気が付くと、またしてもティモシー・シャラメさんを見てしまったw 私が見た限りで「砂の惑星」「チョコレート工場」とまったく違う色彩を演じ分ける百面相。これまで映画界で次々と名優達が名を連ねてきたけど、彼もまた新たな時代の風なのでしょうか。今後の活躍をお祈りいたします。
キャストの生歌唱が圧巻、音楽映画として見応えあり
当時のボブ・ディランをリアルタイムで見聞きした世代ではないし、好んで聴いてきたわけでもないので一般常識程度にしか彼の曲を知らない、そんな私だがティモシー・シャラメとエドワード・ノートン目当てで観に行った。
これは、ある程度ディランの知識があること前提で作られているのかな……と思われるくだりがちらほら。詳しい人なら、シャラメの寄せ具合を個人的に評価したり、さらっと流された登場人物について「あーあの人が出てきた」とか「あの笛はあれだな」とニンマリしたりという楽しみ方ができるのだろう。
残念ながらそういう方向性の味わい方はできなかった私だが、ディランがブレイクした時代の空気、そして彼が評価されている理由がこの伝記映画の内容としては短い5年間の物語に詰まっていて、彼のエポックメーカーたる所以を感じることはできた。
それにしても、ティモシー・シャラメの芸達者振りには驚くしかない。歌唱シーンは全てシャラメ自身が歌い、事前録音ではなく撮影現場の生の音源が使われているという。
5年半トレーニングしたからといって、誰もがボブ・ディランを名乗って遜色のない歌唱と演奏をものにできるわけではない。それだけの努力に加えて、これまでの彼の演技の経験が、演奏にオーラをまとわせることに一役買っているように思えた。
ジョーン・バエズを演じたモニカ・バルバロの歌声も素晴らしい。役が決まった時点では、歌も演奏も未経験だったという。いやいや……信じられない。
エドワード・ノートンも、フォークの大御所然とした美声をさらっと披露する。ピート・シーガー役は元々ベネディクト・カンバーバッチが演じる予定だったが、スケジュールの問題でノートンに変更になったという。出演時間は多くはないが、実力派が当てられるところにシーガーという人物の重要性を感じる。
全編にあふれるフォークソングとディランの歌が、彼らのパフォーマンスによってとても新鮮に聞こえ、フォークのよさもディランのロックの新しさも感覚的に分かったような気分にさせてくれた。
しかしまあ、ディランの恋愛スタイルはかなりアレですな。どこまで事実通りかは知らないが。
私はすっかりシルヴィの目線になってしまって、結構きつかった。居候している彼女の部屋にジョーン・バエズを連れ込み、その後帰宅したシルヴィを平然と出迎えるところなどは、なんやこいつ……という目で見ていた。別れたバエズのもとにふらりとやってきてこれみよがしに作曲作業をするところなんかは、冷静に見れば結構イタい。これ、ディラン設定で顔がシャラメだから絵的に許されるやつね(バエズには許されてなかったが)。
確かに、若き日のディラン本人もなかなかのイケメンではある。シャラメは顔の造作はそこまで似てはいないが、眼差しの強さやそこに宿る影は本質的にディランと同じであるように見えた。
物語自体は、割とあっさり流れていく印象を受けた。確かに彼が時代を拓いたことは伝わってはきたが、一方で彼の内面が主観で描かれることはほとんどない印象だ。
彼の無名時代については、ウディ・ガスリーに傾倒していること、かつてサーカス団と共に過ごした時期があったこと(これは調べてみると事実ではないようだが)、本名はボブ・ディランではないことといったほのめかし程度の描写があるのみ。名曲が生まれるきっかけ的なエピソードはない。シーガーとは音楽性において袂を分かったようで、その時の2人の関係の変化はドラマとしては面白そうなのだがそれもない。ノートンの使い方がもったいないように思えた。
ディランに関する知見の少ない私から見れば、映画の中のディランは最初から天才で、天賦の才を世間に認めさせるだけの行動力と運の強さもある人間だった。その彼が5年という短期間でサクサク成功し(たように映画の中では見え)、ロックへ路線変更してゆく(本人はただ良いと思った音楽をやっているだけなのだろうが)が、その過程や心の動きにあまり深入りしない語り方は、いささかカタルシスに欠けた(物語の面だけの話。キャストの歌唱は別)。モデルとなった本人が健在なので、内面に切り込んで解釈をほどこすことは遠慮したのだろうか。
一方で、赤狩りやキューバ危機、ケネディ大統領暗殺といった出来事から感じるあの時代の空気感、その中で生きていた人々にディランのプロテストソングが刺さるのは何となくわかる気がした。
人間ディランの内面のドラマとしては若干物足りないが、ミュージシャン・ディランのすごさや魅力は十二分に伝わってくる、そんな映画。
似ているがゆえの不気味の谷現象
映画.comのインタビュー記事で、監督が「天才がやってきて、事を成して世界を変えて旅立っていく寓話」と表現していて、なるほどと思った。この映画では、登場したときからディランは天才で、その天才っぷりを堂々と見せつけて、次のステージへと進んでいく。表現者の物語として、いささか盤石すぎやしませんかと感じてしまったが、天才が降ってきて去っていく寓話なのだと思えば、合点がいくといえば合点がいく。
とはいえ熱狂的なディランファンではないが、それなりに聴いたり読んだり聞いたりしてきた者としては、あまりにも有名なエピソードが連なっていて新鮮味には欠ける。ディランというひとは究極のカッコつけだと思っていて、実像と虚像の間にある矛盾にこそ興味があるのだけれど、矛盾に踏み込んでいるのはサーカス出身というホラ話くらいで、むしろディラン伝説の背景にいた人たちを通じて時代の空気みたいなものを感じられたことが良かった。
シャラメの演技や歌に関しては、最初に書いたように寓話であるなら納得はできるが、正直、とても似せていることで自分の中で「不気味の谷現象」が起きてしまっていた。街でシャラメが歌うボブ・ディランがかかっていても、劇中の歌に耳を澄ませてみても、どうしても近似値であるがゆえの差異が気になって、「これはディランではない」と思ってしまうのだ。
贅沢を言うと、伝記映画が完全にそっくりである必要はなく、核のようなものをつかんでくれていれば、あとはこちらが脳内補完しながら「この映画のディランはコレだ!」と思って楽しむことができる。例えばオースティン・バトラーの『エルヴィス』は成り切ってはいたがすごく似ているのとは違って、むしろエルヴィスのエネルギーを演じているようなところがあった。コロナ禍で練習する時間がわんさかできて、シャラメがよりディランに近づけて歌ったり演奏できるようになったと聞くが、むしろコロナ禍前の状態で聴いてみたかった気がする。
まあ、この辺の印象は、ディランにどんなイメージを持っているか、持っていないかによって大きく異なると思いますが。
シャラメの弾き語りが素晴らしい、最高の音楽映画
本作については当サイトの新作評論とジェームズ・マンゴールド監督インタビュー記事の2本を寄稿したので、ここでは記事で書ききれなかったトリビアなどを紹介したい。
ティモシー・シャラメがボブ・ディランを演じる本作の企画が始動してから、コロナ禍と業界ストライキの影響で製作が5年停滞し、その期間にシャラメは歌とギターとハーモニカを猛特訓した。シャラメ自身が歌った音源が本編で使われ、それがディラン曲の魅力を見事に表現しており素晴らしいのは各所で紹介されている通り。
ただ、資料などを見てもギター演奏の音源が使われたかどうかは確認できなかったので、マンゴールド監督に直接尋ねてみた。すると、アコースティックギターの演奏も確かにシャラメが弾いた音源を使っているとのこと。ヴォーカルのわずかなピッチのずれやギターの細かなミスタッチなどは録音後にデジタル編集で修正しているものの、間違いなくシャラメ自身の演奏で、プロのミュージシャンによる音源を差し替えたりはしていない。さらに、序盤のウディ・ガスリーの病室で弾き語るシーンでは、修正を一切せずシャラメが弾き語った音源をそのまま採用したことも教えてくれた。
プロのミュージシャンが出演した映画や、元々俳優業と音楽活動の二足のわらじで活躍しているスターの出演作は別として、専業の俳優が自身の歌と演奏を披露した音楽映画としては歴代最高レベルの出来だと個人的に思う。近年ではラミ・マレック主演作「ボヘミアン・ラプソディ」が大ヒットし評価も高かったが、歌はフレディ・マーキュリーの音源に差し替えられており、つまりはフレディの超絶ヴォーカルとクイーンのバンドサウンドの魅力に負う部分が大きい。もちろん、「名もなき者 A COMPLETE UNKNOWN」の場合は扱う音楽ジャンルがフォークだったことも重要だろう。マンゴールド監督はフォークが歌い手のありのままの声を大切にする音楽であり、俳優の演技に別の歌手の音源をあてた映像では真実味から遠くなる、嘘っぽくなるという趣旨のことも話していた。だからこそ、シャラメの弾き語りが単なるディランの物真似でなく、シャラメの人間味を感じさせる表現になることが鍵だったし、彼の特別な献身がそれを可能にしたのだろう。
評論で書いたように、本作は音楽映画としてだけでなく、周囲の人々も描く人間劇、60年代前半の米社会の激動期を伝える実録としても楽しめる。音楽好きのみならず、幅広い映画ファンにおすすめしたい傑作だ。
贅沢で厚みと深みと高揚感に満ちている
ディランについて代表的な数曲くらいしか素養のない自分だが、本作は直球で胸を貫いた。マンゴールドの演出が観客を裏切らない手堅さと人の情を持ち合わせていることは明らかだが、車でフラリと現れる若者がいざ病室でギターを奏でるや、キンと響く歌声がその場の空気を豹変させていく魔法のような瞬間をマンゴールドは不意に涙があふれるほど絶妙に捉えている。これは生まれてから老いるまでを網羅した伝記ではない。描かれるのはキャリアのほんの初期にあたる60年代だ。シャラメは天賦の才能に満ちそれでいて転石の如く変わり続けるカリスマを見事なパフォーマンスで体現。彼ならではのディラン像と独特の歌声が溢れゆく様はどこを取っても至福と呼べるほど素晴らしい。と同時にノートンを始め共演陣がどれも実にいいのだ。彼らがいるからこそシャラメ=ディランは輝く。ゆったりと贅沢で厚みと深みがあり、伝説が生まれる高揚に満ちた141分と言えよう。
フォークのメロディがいっぱいの幸せな人物伝
ボブ・ディランが若い頃から耳に残るメロディで人を惹きつけ、女性たちにも愛され、時代の波を転がりながらサーフしていく。フォークソングの枠に収まることを嫌ったディランは、そうしてジャンルを超えたメロディメーカーとして選ばれた人生を流れるように突き進んでいく。
そんなディランの若き日を監督のジェームズ・マンゴールドはマニアック過ぎず、奇をてらわず、過剰なドラマ演出を排し、時代を彩ったフォークソングを全編に溢れさせながら再現している。そこがいい。これはギターとフォークに夢中になった'60年代世代はもちろん、ディランを知らない世代もギターの爪引きと歌声に取り込まれる贅沢で幸せな時間だ。
だから当然、ディランを演じるティモシー・シャラメをはじめ、実在の人物を演じる俳優たちは全員、吹き替えなしで撮影に臨んでいる。まるでフォークソングで時代を描いた映画のようでありながら、しかし、最後はボブ・ディランという天才の人とは違う生き方に着地させる。さりげなく、巧みな構成は今年のオスカー候補作の中でも抜き出た存在だ。
The Artist's Burden
Chalamet is the weirdo with sex appeal that perfectly matches Bob Dylan's persona. Even if one is not a Dylan fan, Chalamet's guitar and vocal rendition makes it one of the most impressive and toe-tapping musical biopics in God knows how long. Complete Unkown catches the gist of 60's America, culturally revolutionizing itself in the Cold War, while this film is at ease having fun with itself.
音楽は誰のためにあるのか
フォーク界の新星と持ち上げられ、本人も才能を開花させ、
どんどんスターになっていくボブ・ディランを演じるティモシー・シャラメがとにかくすばらしい。
はにかんだ笑顔のかわいらしさがたまらない。
そして、本人さながらの演奏シーンが痺れる。
どうしてオスカーが取れなかったのか甚だ疑問だ。
また、バイクの疾走シーンの心地よさも捨てがたい。
まさに時代を駆け抜ける寵児としてバイクにまたがり、
どこまでもどこまでも走ってゆくのを見ているだけで快感。
後半、ロック色を取り入れて転向したとフォーク界からハブられる様子はもう胸が痛い。
「俺たちの大好きなあの曲を演奏してくれ!」というファンの気持ちがめちゃくちゃわかるからだ。
その曲で救われた人が少なからずいる。その曲を聴くためにチケットを取る人がいる。
わかる!わかるよ!!とフェスのシーンは膝を叩きまくってしまった。
ミュージシャンって罪作りな生き物だな。
映画館で見た
最近感想書くのが遅れて、気が向いた時に一気に書いてるのだけど、U-NEXTの履歴見ながら書いてるから、映画館で見た映画が度々抜けてしまっている、、
U-NEXTのポイントで見た。ノーアザーランド、聖なるイチジクの種と悩んだが、その2つはポイント使えない映画館でしか上映していなかったためこれを見た。
結構PRされてたから少し期待はあったが、そもそもミュージカルはあまり好きではないのでそこまで期待値を上げずに見た。結果まぁまぁだった。
ティモシーの演技が凄いのはわかるんだけど、ティモシーにハマったことないし、ボブ・ディランをほぼ知らないというのもあって感情移入できなかった。
見てから半年以上経ってるから細かいところは忘れてしまった。
映画の内容よりも映画館自体のほうが記憶に残ってるかも。行ったことない映画館に行ってみたくてここにしたが、まさかこんな高いとは知らなかった。ポイント引き換えてから知ってちょっとショックだった、、でもポップコーン食べ放題だったり飲み放題だったりして、ちゃんと満喫すれば元は取れそうな映画館だった。椅子もフカフカだったし、人もいなかった。今の財力ではまた行くかと言われたら行かないと思うが、お金があればずっとここがいい。
歌もいい、ティモシーもイケメンだけど…
映画って奥が深いなって考えさせられました。
歌も素晴らしいし、ご本人もご健在で映画やキャストを誉めてらっしゃった。だけに期待が高まりすぎてしまったのかもしれません。そしてティモシーのことも…確かにティモシーはカッコいいし、なりきってるように感じたのだが実話だからか、あの人がその時に実際に取った行動に共感できないのに、ティモシーがそれを再現してるだけなんだよね。。などの自己の心に茶番感が立ってしまい、若さゆえの行動などに違和感を覚えてしまった。だけどエルは凄くよかった。あの港での表情や言葉、皿の気持ちになれっていうシーンと演技は、よくありがちなシチュエーションなのに秀逸だなと思いました。だけど再鑑賞はなさそうです。
アメリカ現代史とともに歩んだボブ・ディラン
前情報でティモシーがボブディランのイタコ芸するのはわかってたので、まあまあ楽しみにIMAXで鑑賞。
結論から言うと、アメリカの20年代から60年代に生まれた広義の大衆音楽の歴史をディランとともに俯瞰できるという、ついに数多のミュージシャン映画の決定打がでた印象。アメリカ音楽の歴史の目撃者になれる映画と感じました。
正直に言えば、裁判所前でピートシーガーが「我が祖国」を歌ったときにもう泣きました。(その時点ではボブディランはまだ歌ってません笑)そこから始まるボブディランとウディガスリーの出会いの意図や、劇中で語られる音楽について解説します。
ボブディランの憧れの人、ウディガスリーの音楽は、1920年代にまだ荒地のロスアンゼルスに季節労働者として移転してきて、作物が育たないばかりかひどい砂嵐が襲いかかり、貧困にあえいだという経験がバックボーンにあります。映画の中で繰り返し流れる、砂嵐の歌はその頃の経験から生まれたもの。ちなみに冒頭でピートシーガーが歌う「祖国の歌」はウディガスリー最大のヒット曲。明るいメロディですが、実はアメリカに裏切られたという思いを裏に潜ませた曲だと想像することは難しくありません。劇中では、ボブディランがウディガスリーからどういう影響を受けたか語られないため、こちらを補完することをおすすめします。
次にディランがジャンルレスな発想だったことを示すエピソードをきちんと見せた意義は大きいと思いました。黒人教会のライブでディランの次にブルースデュオのサニー・テリー&ブラウニー・マギー が出て、ディランのハーモニカにお世辞をいうなんてブルースファンにはたまらないシーンもあります。
また、ディランが「追憶のハイウェイ61」のためにセッションバンドを組む時に、名指しでマイクブルームフィールド(劇中に名前だけ出てくる白人ブルースバンド、ポールバターフィールドブルースバンドのギター)に依頼するところにも痺れました。ディランが音楽的にブルースに近い距離感だったことがわかりました。
ポピュラー音楽の歌詞の世界に詩的世界観を持ち込んだディランは、サウンドの面でもさまざまなジャンルを取り込み進化させたことが伝わりました。
風に吹かれて
ミュージシャンの伝記物と言えど、
こんなに音楽が流れ続ける映画も珍しいのでは?
体感だと半分以上曲が流れてたような、
それはそれでとても贅沢な時間でした。
ティモシーシャラメの新しい魅力と才能を堪能出来て
眼福でした。
ボブ・ディランを名前だけは知っててどう言う人かいまいち分かってない僕のような人には、とても分かりやすい
映画だったと思う。
天才でありその苦悩も分かるけど、
周りの人の振り回される苦労も大変だったと伺える。
誰もが知っている「風に吹かれて」や「ライクアローリングストーン」「タンブリンマン」を少しだけ聴かせて、
あと全然歌ってくれなくて、ヤキモキしてたら
最後のライブ場面でバンド編成で聴かせる演出は
めちゃくちゃ格好良かった。
音源も残っていて観客からのユダ発言からの嘘つきは
聞いた事があったけど、なるほどこう言う流れで
こうなったのか!と言うのが分かって感動しました。
ただ同時に有名曲をやってくれ!と思ってた自分と
観客が重なって見えて恥ずかしくもなりました。
体制に反発し居場所を見つけたはずが、
ただ自分のやりたい事をやってるだけなのに
観客から裏切り者と呼ばれ、
恋人も去り、天才たちだけが残り、独りになって行く
天才故の孤独。
限られた人にしか出来ないものにとても痺れました。
タイトルなし(ネタバレ)
冒頭の、病室でボブディランがウディガスリーを讃える歌を歌うシーンで、涙がほろっと。「さだまさしみたいだな〜確かにフォークソングだわ」と妙に納得して物語は始まりました。
「あー!この曲の人か!え、これも!?ボブディランの曲だったのか〜〜、へぇ〜驚いた」ていうくらい、ボブディランの名前は知っていたけれど曲とつながっていなかった私。
予備知識ゼロだったのも原因の一つですが、なんかアッサリしてて、彼の何が凄いのか?最後までイマイチ分かりませんでした。
で、色々ググっていくと…
ウディガスリーの映画がどうしても観たくなって、観れないということに膝をついてガッカリ…(ブルーレイプレーヤー持ってないんだよなぁ)ウディガスリーのジュークボックスを自称していたボブディラン、ウディがどんな人でどんな歌を歌っていたか遡ると、フォークというジャンルがどういう音楽だったか、あの時代にフォークのライブでエレキギターを持ち込んで演奏することがどういう事か、ようやく少し分かってきました。
あとは、ボブディランはたぶんユダヤ系の移民3世くらい?だと思うんだけど、時代的なものもあると思うけど、色々辛辣過ぎて、らしいっていうか、さすが移民の国と思いました。
Spotifyで今更ボブディラン聴き始めました。
モニカバルバロの歌声がもう、心が洗われるような気持ち。あと野生味あるのに品があってエキゾチックで、美し過ぎて、私は気絶するかと思った。ほんとにきれいな人だった。
まさに名もなき者として生きたボブ・ディラン
ボブがニューヨークに初めて来た日、彼はずっとリスペクトしていたミュージシャンの見舞いに行く。そこで同じくリスペクトしているミュージシャン、ピートと出会
い親交を深めていく。しかし彼は自分の出自を話さない。
ボブはピートのおかげで初めてニューヨークのステージにあがり歌う。その声と歌詞を聞いてフォークスターであるショーン・バエズが立ち止まって真剣なまなざしで彼を見つめていた。彼は何者かと。
ボブ・ディラン、二十歳。彼の作る歌詞、メロディーに観客は共感していく。彼は二十歳になるまで何を感じ考え生きてきたのかが謎だ。わかっているのは、往年のミュージシャンをリスペクトしていたこと。そして彼の歌は、大勢の人に共感される。ただ彼のメッセージを伝える歌詞とメロディーだけで。
ボブは、シィルビィ、ショーン、二人の女性と付き合う。ただボブは出自についてなにも話さない。ボブは彼女と一緒の時も朝晩構わず曲作りしている。まるで二十四時間、歌詞とメロディーが彼の頭を占拠しているように。そこで二人にはボブの謎がとける。歌を愛し歌に愛されている人間だということを。
彼が歌うシーンはカメラがつねに彼に寄る。まるで彼が横にいて歌っているように。これこそが映画的魅力となり彼の歌に熱狂する観客とともにこちらも興奮する。
ボブは有名になっても決しておごらず、いやむしろ露骨に嫌がる。これも謎だ。フォークというジャンルにとらわれない、新しい音楽のスタイルに自分が考えるように変えていく。人気絶頂の時なぜスタイルを変えるのか、謎だ。
このボブ・ディランの謎を体現したのが、ティモシー・シャラメだ。クールで曲作りに没頭し、新しいチャレンジに貪欲でありつつも、孤独をまとう姿を肉体で表現した。まさに「名もなき者」として生きる姿を。
出自も知れない若者。この映画は、ボブの謎を軸として、曲作り、歌唱シーンから、彼が追い求めていた「名もなき者」として生きる姿を明らかにした。
ラストシーン。ボブはまたミュージシャンの見舞いに来ていた。それが彼のすべてだ。
孤独な旅人
監督も出演者たちも、誰もが知っていて存命中でもある人物を描くことの重さに細心の注意を払っている映画だった。
ディランを聞いたり見たことがある人ならシャラメやエドワードノートンがどれほど当人を模しているかがわかったと思う。
ディランは投げやりで拗ねたような物腰の人で口をあまり開かず語尾を言い切らない感じで喋る。シャラメはそれを周到に擬態していたしピートシーガー役のノートンもChildrens Concert at Town Hallの演奏を彷彿とさせた。
映画からは役者が本人になりきるための監修の綿密さが伝わってきた。
ドキュメンタリーのDont Look Backで覚えているのはディランではなく当時ディランのマネージャーだったアルバートグロスマンである。小太りでメガネをかけた外観は愛嬌もあるし立ち居振る舞いは緩慢なのに反面恐ろしい威圧感があった。クライアントであるディランに対しては羊のように従順であるのに対し、ツアーの障害となることやギャラ交渉には峻厳で容赦がない。その役にノーマジのDan Foglerが充てられていて思わずそうだこの感じだと思った。すなわちアルバートグロスマンでさえ本人に似せてあった。
映画のレビューというものはときとして「おれにはこれがわかるんだ」という叫びでもある。
この映画を見てシャラメが演じたディランがどれほど本人を模倣していたか叫びたくなったディラン好きは多いだろう。そういう確かなディティールをもった映画だった。
ボブディランは反戦や公民権運動の歌も歌ったが、人にあがめられたり社会派に祭り上げられる前にサッと退いてしまうような人だった。偉い先駆者になるのも、イデオロギーがまとわりつくのも、妙に落ち着くのも、スーツを着たお歴々から拍手を浴びるのも嫌で、ノーベル文学賞授賞式も出席しなかった。そんな詩人らしい彷徨の立脚点がよくわかる映画だった。
すなわち映画A Complete Unknownは「全くの無名」な青年ボブディランがピートシーガーやジョーンバエズの助力によって有名になる過程をつづった映画と言える。ところがディランはかれらと共に育んだフォークを裏切って、より儲かる商業的なロックへ転向した、と一部聴衆やフォークミュージシャンからは捉えられた。しかしディランはフォークのプロテストソング=体制批判的な音楽性に辟易しており、且つ、フォークやカントリーやロックというレッテル貼りやジャンルの住み分けに窮屈さを感じ、新しいことをやりたかっただけだ。だからアコースティックからエレクトリックへギターを持ち変え、挑発的なFuzzをがなり立てて、観衆から裏切り者と罵られる1965年のニューポートフォークフェスティバルが映画の結にあり、そこからディランの新しい旅が始まる──という始まりな終わり方になっていた、わけだった。
で、それらの一連の出来事から解るのはボブディランの孤独だった。恋仲といても音楽仲間といても二股していても、いつも孤独で新しい詩を探している。つまり全くの無名から全くの孤高へ至る過程を描いた映画だった、と思う。
人物造形、時代考証、世界観はすごかった。ただ長いのとバエズとルッソの二股描写がくどかった。
imdb7.3、RottenTomatoes82%と95%。
リベラルに捧げるレクイエム
2025年のアカデミー賞にノミネートされた作品の多くが、トランピアンとリベラルの分断から派生した政治問題をテーマに選んでいた。ボブ・ディランのバイオピック(伝記映画)だとつい勘違いして敬遠していた1本なのだが、配信開始となった本作を見てビックリ仰天。時代の変化を敏感にかぎとった曲が次から次へと大衆のハートをつかみ、頂点を極めたシンガーソングライターの目を通じて、監督ジェームス・マンゴールドが本作にこめたメッセージがきわめて政治的だったからである。
病に倒れたフォークシンガーウディ・ガスリーを訪ねてはるばるミネソタからニュージャージーにヒッチハイクしてきたボブ・ディラン(ティモシー・シャラメ)。入院先でプロテストソングのパイオニアとして知られるフォークシンガーピート・シーガー(エドワード・ノートン)と運命的に出会い才能を見い出される。この人、ハーバード大学中退の学歴をもつバリバリのリベラルで、反戦や核軍縮、公民権などの政治運動にも積極的に関わってきたコミュニスト、オバマ大統領就任式にもお呼ばれされたほどの。
1961年から1965年までのアメリカの歴史イベント(公民権運動→ベトナム戦争→キューバ危機→ケネディ暗殺)を織り混ぜながら、その時々に生じた大衆の不安や怒り、悲しみといった心理を歌詞に変えて大衆に受け入れられていく様子を、映画は丁寧に描き出していく。すっかり有名になったディランの歌が、いつしか大衆迎合的なプロパガンダ装置の中に組み込まれていきそうになると、ピート・シーガーが主宰するニューポートのフェスティバルでディランは“クーデター”を起こすのである。
エレキギターを使ったディランのギグに賛否両論の反応を示す観衆は、まさにトランプかハリスかで真っ二つに割れた2024年のアメリカ大統領選挙そのものだ。ギグの直前ザ・リベラル代表のピートがディランに対してこんな要求をする。「傾いたシーソーが水平(リベラル)になるように、みんながスプーンをもって集まる伝統的なフォークフェスだ。正義のスプーン、平和や愛のスプーンやいろいろだ。そこに君がシャベルを持って現れたおかげで目的に一気に近づいた。今夜君がステージに立ってシャベルを正しく使えば(社会を)ひっくり返せる」と。言い換えると、[名もなき者の代弁者]であったはずのディランに[社会全体の代弁者]として正しく振る舞え、ということなのである。それはまた、聖者を気取る“神(シーガー)”とその子供“イエス(ディラン)”の関係と相似形なのだ。
吹き替えなしで歌い上げたシャラメの歌唱シーンばかりが注目されがちな本作ではあるが、それと並行して、シャラメ演じるディランが舞台袖で他の歌手を観察するシーンが非常に多いことに気づかれることだろう。本作は、リベラルの牙城であったデモクラッツ(民主党)が、いかに“立て直さなければならない”ほど民衆の支持を失い凋落せざるをえなかったのかを、観察者ボブ・ディランの唄にのせて語らせた1本だったのではないだろうか。
映画はラスト、アコギ(タンブリンマン)ではなくエレキ(ライク・ア・ローリング・ストーン)を選んで熱唱するディランは、ピート以下フェス主宰側の態度の中に、必ずしも民意を反映していない押しつけがましい偽善を見抜き反乱を起こすのである。浮気相手兼シンガー仲間のジョーン・バエズ(モニカ・バルバロ)がWokeな昔の歌(風に吹かれて)に固執し、恩師ピート・シーガーが教育番組の司会者をつとめ体制に飼い慣らされていくのとは対照的に、“自由”を求めたディランは一人バイクを走らせるのだった。
気をつけろ聖者が通る
もうおしまいなんだベイビー・ブルー(民主党?!)
『イッツ・オール・オーバー・ナウ、ベイビー・ブルー』より
「風に吹かれて」をベッドの上で歌い ジョーン・バエズが「これは、、...
「風に吹かれて」をベッドの上で歌い ジョーン・バエズが「これは、、何?」と言う3分間のシーンにしびれる。
イライジャ・ウォルド著の『ボブ・ディラン 裏切りの夏』を原作にディラン(1941年生)の二十歳ぐらいからの約4年間を描く。
1961年、世の中が大きく変わり始めた激動のアメリカが舞台で、途中キューバ危機が起こり絶望的になった人々も描かれる。
ミネソタからニューヨークへやって来たボブはミュージシャンのピート・シーガーと出会い、彼の導きでプロのミュージシャンとしての一歩を踏み出す。
ピートの妻トシ・シーガーを見た時「あれっ?コン・リー?」かと思ったがそんなわけ無く初音映莉子と言う知らない女優だった。(監督から直接トシ役で指名され一度は断る)
エル・ファニング演じるシルヴィ・ルッソはディランの当時の恋人だったスーズ・ロトロにインスパイアされたキャラクターらしいが、スーズはボブの2歳年下なので、姉の影響なのか かなり大人びた女性。彼女が2歳の頃から見てるがエルの中の最高傑作だと思う。(全てを鑑賞してないが)
エドワード・ノートン演じるピートの優しさも、ジョーン・バエズを演じたモニカ・バルバロの目つきも良かった。
翌日に2回目を鑑賞した。
この映画の事を調べるとネットに「ティモシー・シャラメが劇中で40曲の生歌・生演奏を披露している。」とあった。生歌・生演奏は本当らしくアフレコでは無い。凄い俳優でもうプロの歌手レベル。しかし40曲もあったかな?
グラミー賞、アカデミー賞、大統領自由勲章、ピューリッツァー賞特別賞、ノーベル文学賞等を受賞し、ロックの殿堂入りをしてる人間は世界に一人しかいない。
※2歳くらいのエル・ファニングは『アイ・アム・サム』で姉ダコタの幼少期役で20秒ほど登場。
フォークとは何ぞや
全400件中、1~20件目を表示