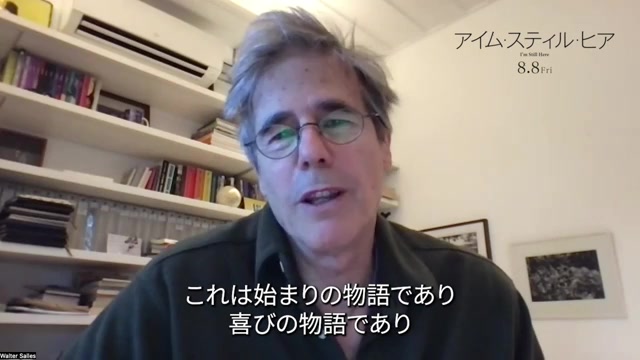アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全29件中、1~20件目を表示
人間社会の罪深い過ちを忘れないために
この物語は、家族の実体験を記したマルセロ・ルーベンス・パイヴァの回想録に基づくものだ。ウォルター・サレス監督は14歳の頃この家族と親交があり、週末毎に彼らの家を訪れていたという。序盤の明るく解放的なパイヴァ家の日常の姿は、監督の記憶に刻まれた風景でもあるのかもしれない。
主役は一家の母であるエウニセだ。夫のルーベンスが行方不明になってからの彼女の経歴には、生半可でない意志の強さを感じる。5人の子供を抱えながら、43歳で大学の法学部に再入学し司法試験に合格。弁護士としての一般的な業務の他に、先住民族の権利擁護や環境保護にも献身的に取り組んでいる。
このようなエウニセの夫失踪後の人生だけでも十分映画になりそうだが、本作ではそこはばっさりと省かれている。四半世紀の長きにわたり連れ去られ殺された事実さえ隠され、国家から存在を消し去られていたルーベンス。愛する夫を、父親を、ある日突然そのような形で奪われることの残酷さと理不尽さに焦点が当てられる。
平和なパイヴァ家の姿やルーベンスの人となりが最初に細やかに描かれたからこそ、それらが全て失われることの痛みがよく伝わってきた。
だが、エウニセは強い。夫が帰ってこず、軍関係者と思しき男たちがずかずかと家に上がり込んで居座ったのに、冷静に彼らの食事の気遣いまでして見せた。ここで取り乱せば、男たちをさらに警戒させてしまう。夫不在の中、彼女はひとりで子供たちを守らねばならないのだ。
やがて彼女も娘と共に拘束され、長期間(パンフレットによると12日間)の厳しい尋問を受ける。ようやく解放され、帰宅したエウニセは子供たちの前では再会を喜びこそすれ、不安に屈する姿を決して見せない。父親についてのネガティブな言葉は、ラジオのニュースに至るまで子供たちには触れさせまいとする。子供たちの心と、ルーベンスがいなくなる前のあの家庭の明るさを、エウニセは守りたかったのかもしれない。
気丈な振る舞いをほとんど崩さなかった彼女だが、そうせざるを得ない彼女の緊張感や苦しさもひしひしと伝わってきた。
それでも、働き手がいなくなった彼らの生活は経済的な困窮により否応なく変質してゆく。まず家政婦の給料が払えなくなり、やがて生活費も苦しくなって新居を建てようとしていた土地を売り払い、親戚のいるリオデジャネイロに転居することになる。子供たちの、恋人や友人との別れが切ない(マルセロが別れを告げた友人たちの中に、幼い日のサレス監督もいたのだろうか?)。ルーベンスがいれば起こらなかったであろう環境の変化に翻弄される彼らを見て、改めて軍の横暴に怒りを覚えた。
誰かが暴力の犠牲になる時、被害は当事者にとどまらない。本人に関わる多くの人もまた、人生が大きく変わるほどの影響を受ける。
それはあってはならないことだが、自分の身にそのような受難があった時、心まで屈することのないようにすることも難しいが大切なことなのだなと思った。成長したエウニセの子供たちが皆明るかったのは、彼女のそうした心の闘いの成果なのだという気がした。20歳の時の事故で頚椎を損傷しながらも作家として成功し明るく生きるマルセロにも、母親の薫陶が感じられた。
2014年の認知症を患ったエウニセを演じたのはフェルナンダ・モンテネグロ。サレス監督の「セントラル・ステーション」でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた名優で、エウニセ役のフェルナンダ・トーレスの実母だ。血の繋がりがあるだけに老いたエウニセとして自然な容貌だったのもよかったが、何よりも目の表情だけでエウニセの感情が蘇るさまを雄弁に表現したその演技力にうなった。
実際のエウニセは、最晩年認知症が進んでからは何を聞かれても「そうね」としか答えなくなったが、感情が高ぶった時にはこう言ったという。
「私はまだここにいる」
夫がいなくなった後の人生を精一杯闘い、平和で温かい家庭を守り抜いた彼女だが、かつての心の傷が癒えたわけではない。病により、それを語ることがなくなっても。
図らずもこの言葉は、軍事政権の蛮行への反省が不十分な現代のブラジルや、ひいては歩み寄りを忘れた世界の様々な対立軸への警鐘にも聞こえるのだ。
母の底力
市民の幸せな生活を一瞬にして崩壊させる独裁国家の恐ろしさをまざまざと感じた。
「強制失踪」という言葉を初めて聞いた。
政府が逮捕を認めなければ、たとえ死んでいたとしても政府には関係ないこと、と責任逃れができる。残された家族は愛する人が生死も含めてどうなっているのか不明な苦しみのほかに、公式には「失踪」状態なので、家族がその人名義の預貯金を下ろすことができないなど、日常生活に行き詰る事態にも陥ってしまう。
ある時突然、家族が連行されてそのまま帰らない、という悲劇は、軍事独裁政権下ではよく聞く話だが、この映画では直面した家族のリアルがわかる。
20年後の次女と長男が、「いつパパが戻らないことを知ったか」と話し合うところで、子供たちが子供なりに事態を理解していたこと、年長の姉妹が、小さい弟妹を気遣って大人の配慮をしていたことが見える。小さい長男も、パパは戻ってこないことが分かっていたが、母を気遣って何も言わず、気づかないふりをしていたよう。
原作が当時子供だった長男の著作とのことで、子供から見た「事件」が描かれている。
母の底力がスゴイ。夫を連行され、自身と次女も連行、取り調べを受けたが、一貫して賢明なふるまいで乗り切り、家族を守り、重要なことは信頼できる友人に相談しながらひとりでさっさと決断する。
夫が健在の際には、家事の大方を家政婦に任せて、スフレを焼くのが得意な典型的な裕福な家庭の専業主婦だが、窮地に陥れば冷静に状況をとらえて賢明な対応で家族を守り、先々のビジョンまで同時に考える。大学に戻って法律を学び、弁護士資格を得て人権活動に乗り出す。すでに夫の生還は諦めたが、国家の弾圧を告発し、誤りを認めさせることで夫を取り返すほうに方向転換、20年の年月をかけて、夫死亡の事実の確定をもって、国家に過ちを認めさせる。
賢く強いママ、家族を守り修羅場を乗り切り、長い年月をかけて国家に一矢。
こういう話とは思わなかった。
夫が政府に批判的な元議員で、海外のメディアを活用できる立場にいたことも、ただの蟷螂の斧にならなかった要因だろう。軍事独裁政権が、海外の(アメリカの?)メディアには手出しをしていなかったようなのは、国際社会への仲間入りを目指しての対外的な評判を気にしたか、アメリカへのおもねりかも。
エウニセたちが夫の死亡証明書を勝ち取った際のひとりのインタビュアーの、「過去の悪事を掘り起こすことよりほかにすべきことがあるのでは」に唖然とした。エウニセは、「過去を反省しないとまた同じことが起きる」と言っていたが、当事者である家族にとっては過去の話ではなく、現在進行形の悪事だ。インタビュアーの感覚がそれに思い至らない程度に他人事で、軍事政権下の圧政が過去のものと認識されているようなところが見えて、こうしてまた同じようなことが繰り返されるのだろうと感じた。
前半の、幸せな一家の生活ぶりの描写がちょっと長すぎ。
半分くらいのボリュームでよかったのでは。
子どもには言えない「大人の事情」
1970年代初頭のブラジルが舞台とのこと。土木の専門家の父のもとで、子だくさんの家族が絵にかいたような幸せな生活を送っている。道を一つはさんだ海に出かけてビーチバレー、家ではレコードに合わせて踊り、サッカーゲームで対戦、母の手作りのスフレケーキ。
「日焼けしたらダンスの先生に叱られちゃうわ」というように、大人に褒められる遊びにも、そうでない遊びにも恵まれた女の子4人、男の子1人からなるきょうだいだ。
ところが軍事政権に父が連れ去られ、生死も不明な状態に。母と次女も捕まって監禁され、ロンドンに逃がされていた長女もそれを知ることになる。
ここで、大人(母)、若者(長女と次女)、子ども(三女、四女、長男)にチームが分かれる形になるのが興味深い。若者は母に「父は一体どうなったのか」と問い詰めるのだが、母は「その話はダメ。子どもが聞いているでしょ」とばかりに制止する。
こうして気丈な母を中心に、一家は「パパを待ち続ける、幸せな家族」を演じ続けるのだ。いや、演技でなく本気かもしれない。政権の不当性を訴えるための記事で、カメラマンに「深刻そうな顔をして」と言われても、みんな笑顔で写真に納まる。
やがて時は流れ、母の長年の活動が実り、政府に「父の死」を認めさせるに至る。あれっと思うのは、いつの間にか「父を待つ」ことから「事件の承認」に目標が変わっていることだ。
成長した四女と長男が「途中からお父さんが戻らないことは分かっていたよね」と話し合うシーンがあった。みんな少しずつ「大人の事情」を理解したということだろう。
全体として政治的な悲劇ではなく、一家のまとまりを描くことに全力を注いだ映画だと思う。しかしそれによって作品の重みが弱まった気がしなくもない。
一方、家族それぞれの思いをもっと知りたかったようにも思う。もしかして母だって父を疑い、恨んだ時期もあるのではないか。きょうだいも、父の死を悟るまでには多くの葛藤があったはず。
一家の正しさを訴えるためには、湿っぽい人間ドラマは余計だったということだろうか。
突然夫(父親)を軍事政権に奪われた家族の人生
ブラジルでは1964年~1985年まで軍部が政権を掌握していた(軍事政権)。5人の子供をもつルーベンス・パイヴァは元国会議員であり、軍事政府を否とする反体制の運動家でもあった。そして1971年彼は何者かに突然連行される。結局彼は妻と5人の子供たちの待つ家族のもとに戻ってくることはなかった。夫の安否を気遣う妻の苦しみ、父親を失った5人の子供たちの悲しみが描かれる。妻は夫の生存を信じ、ただ帰りを待つだけでなく、さまざまな手を尽くして夫を捜し軍事政府にも抵抗の姿勢を示す。しかし、何の手がかりも掴めぬまま、パイヴァ家は生活のために当時首都だったブラジリアにある海辺の家を売り払い、妻の実家のあるサンパウロに引っ越す。友だちと別れ、優しい父親との思い出の詰まった家を離れる子供たちの悲しみは胸を打つ。
そして時は流れ軍事政権は崩壊する。
家族はルーベンスなき後、自分達の人生を健気に全うする。妻はサンパウロで大学の教授として教壇に立っている。長男は作家として身を立て、娘たちもそれぞれに家庭を持ち平穏な生活を手に入れている。そして政府は20年越しにルーベンス殺害を認める。
強引な手法、力で一国の運営を担う軍事政権の恐ろしさと翻弄される市民。この映画は実話として一つの家族にスポットをあて、その残酷さを我々に伝えている。
力で物事を進めようとする人達は、多くの選択肢の中から、最も過激な方法を選択する。少しの間違いも犠牲もやむ無しとする。軍事政権の恐ろしさを改めて実感した。この世の中から軍事政権がなくなることを祈らずにはいられない。
軍事政権下における悲劇
冒頭から幸せそうな家族を印象づけるルーベンス一家が
映し出され、よもやこれから悲劇が起こるとは
父親を除いて誰も予期していなかったであろうと思う。
というのも、父親が仕事以外のこともやっていることは
観客にはわかるからだ。
ある日突然、政府から連行されるルーベンス。
そしてエウニセ自身も連行され何日も拘束され、
テロリストの顔写真を見せられて、知らないか?と
問われる毎日。これは気が狂いそうになるだろうと思う。
エウニセの精神力たるや感嘆の域だ。
後日譚でルーベンスは殺されていたことがわかるが、
子供たちが「パパが帰ってこないといつ思った?」という
会話をするのが切ないし、子どもながらに自分の気持ちと
折り合いをつけていたことが実に悲しかった。
子どもたちを大事に育てながら、
軍事政権の犯罪を明らかにし戦うエウニセの姿に
猛烈に感動した。
フェルナンダ・トーレスの演技に脱帽。
70年代のブラジルの色味、音楽、ダンス、車なども
本作を魅力的にしている要素だと思う。
こういうことは、もうあってはならない。
歴史から学びたいものだ。
アッパレ❗な人生
ブラジルに軍事政権とは? サンバの国に独裁政治? そんな史実事実も興味あり 観ましたが
予想は裏切られ そんな時代に生き抜いた偉人の話しだった 主役の演技は素晴らしい そして、最後の終わり方も👏でした。 さらにエンドロールの家のシーンは激動からの清涼剤のようで音楽と共に楽しめたが 最後のスタッフエンドロールはこれはスクリーンが小さすぎなのか 全く読めないし音楽も重い これはハッピーエンドではないと 我に返らされた この女性の人生とこの役者にアッパレ❗Aleluia
私の本意じゃなかった
こないだ鑑賞してきました🎬
考えさせられる内容です。
エウニセにはフェルナンダ・トーレス🙂
幸せな日々から一転、夫ルーベンスを連行され、自身も尋問を受ける事態に直面します。
しかし彼女はあきらめずに行動し続け、最終的には政府にルーベンスを死に追いやったことを認めさせました。
大変な勇気と胆力、そして不屈の精神が必要だったと推測しますが、それがにじみ出るようなトーレスの演技は見事です🫡
この事実に胸が痛むとともに、今後同様のことが起こらないよう切に願います。
原作者はエウニセとルーベンスの息子さんであるマルセロとのこと。
彼に経緯を表し、ルーベンスのご冥福をお祈りします。
創り込まれた社会派の1本でした。
司法制度のある国で
実話と知らずに評判が良いので鑑賞。
南米には冷戦時代にアメリカの後押しを受けた軍事政権がクーデターで誕生し不当な逮捕、拘束、処刑で多数の犠牲が出て今も実後者や命令者は裁かれていないぐらいの認識。
劇的な展開や説明も極力なく淡々と静かに夫が居なくなり困窮して行く家族を母親を目線で描く。
70年代から90年代、2019年と主人公の母親、子供たちも成長し、やはりと言うか連行された父親の死亡証明書が発行されやっと一区切りが付けられる。
母親のセリフに司法制度のある国なのに不当な逮捕、拘禁が行なわれているには恐ろしくなる。
今も世界の様々な政府では同じ事が行なわれ日本でもこれを支持し賛成する愚か者どもがいる。
決して許してはならない。
明るい色調と暗い色調のギャップが緊迫感をうむ
お盆休みの13日、TOHOシネマズシャンテで見たのですが、ほぼ満席になっているのに少々驚きました。
なにせメジャーな映画ではなく、ブラジル映画にこんなにお客さんが見にくる、2025年アカデミー賞国際長編映画賞受賞作品に敏感に反応する、やはり首都圏のひとは文化度が高いと再度思いました。
この映画よかったです。多くの人に見てもらいたい作品です。
【映画批評】
家族七人が仲睦まじく過ごしている日常生活と父親が突然連行されてから、そして母がリオからサンパウロに転居すると言った以降、映画は三つの色調から成り立っている。
夫婦仲がよく子供五人も両親に愛し愛され穏やかな日常が目に焼き付く。この明るい色調の日常生活があっというまに脅かされる。
軍事独裁政権下、不穏な事件が相次ぎ、日常生活の明るい色調とは真逆の暗い色調と不気味な音が支配していく。車が止まる音、扉の開閉の音に極度に敏感になる。突然父親が誰の指示でどんな用件かわからず連行されてしまう。妻エウニセ、次女のエリアナも拘束され尋問を受けることになる。エウニセとエリアナが視覚を奪われ連行されたことで、ここがどこかわからないことと、尋問を受ける部屋で、牢獄の密室で聞こえる悲鳴、慟哭、叫び。また夫が消息不明であることから、エウニセが抱える不安、これらのシーンで恐ろしいまでの緊迫感につつまれる。不気味な音と暗い色調が恐怖をうみだしている。
映像化されていないが、母と姉が連行されたとき家には四人の子供しかいない。エリアナは一日で帰ってきたが母は帰らない。この時の子供たちの不安さも緊迫感を高めている。この映画は映像だけで語ってはいない。
夫が消息不明ではあるが家族六人生活をしなければならない。エウニセは仲間から夫がすでに死亡していることを聞き、サンパウロに転居し大学に戻り法学を履修し弁護士になる。弁護士は法を盾に取り闘うことができる。エウニセは消息不明者をかかえる家族らの代表となり声をあげ続けていく。
夫が消息不明になってから二十五年後、政府は死亡証明書を発行した。これを境に平穏な日常生活が描写される。闇と闘い、国と闘い、二十五年のときをへてつかみ取った昔の日常生活。また明るい色調が戻ってきた。
闘い、痴呆になり、車椅子に座り、年老いたエウニセ。子供と孫に囲まれ団欒をすごす目に力はないが、彼女が成し遂げたことはこの家族団欒に凝縮されている。夫のために闘い、子供のために生きることが彼女の人生だったのだ。
犬と同じように粗末に扱われた主の家族の場面対比
幸福そうな海辺での家族の姿から始まる。海中から顔を出すエウニセ、子どもたちそれぞれサッカーやビーチバレーボールに興じ、迷い込んだ犬を娘の一人が弟のマルセロに託し、マルセロは家で飼いたいとエウニセやルーベンスにせがみ、二人は最初は断ろうとするが、押し切られる。車に乗って移動中に、娘の一人がムービーカメラを動作しながら、ありきたりの家族や風景を録画していくが、途中のトンネル内で取り調べを受けてから、運命が文字通り暗転していく。
ルーベンスの連行の後、エウニセとエリアナも連行され、女性にもかかわらず、執拗に連日取り調べを受け、帰してもらえない。家に残された年少の子どもたちは、もちろん不安だったろう。母姉の連行前だったかもしれないが、マルセロは健気に監視役の男を相手に、父と同様にゲームで気を引いていた。エリアナが先に帰されたようで、エウニセが戻り、エリアナも安心したのも束の間、年少の子どもたちの不安を慮ったエウニセの心遣いにもかかわらず、エリアナ、そしてロンドンで真実を知った長女のヴェロカとの溝が生じてしまった。
ある日、家の前の道でけたたましい音がして、エウニセが出てみると、飼っていた犬が車に轢き殺されていた。監視役の男たちの仕業らしい。この頃、ルーベンスも殺害されていたのではなかろうか。女中に払う給料の金を得るためにルーベンスの銀行口座から引き出そうとして認められず、外貨両替で凌ぎ、後日ようやく不要な土地の買い取りが認められた。ヴェロカが帰国し、リオデジャネイロの家を引き払って、サンパウロに移ることになり、冒頭場面のように海辺で楽しむことになり、エウニセがまた海中から顔を出し、子どもたちも遊ぶが、ルーベンスの姿はない。
エウニセは大学に戻ると言っていて、研究職かと思ったが、25年後の職は弁護士で、学生に戻ってからということだったようだ。マルセロは電動車いす利用者になっていた。ルーベンスの死亡証明書が発行され、エウニセは、区切りをつけるとともに、国による補償責任を訴えた。
さらに18年後には、子どもたちをそれぞれ家族を増やし、賑やかに集まり、エウニセは年老いて認知症であるようだが、テレビでのルーベンス他の政治犯たちの消息の放送を観て、心が動く様子だった。そしてルーベンスが健在だった頃の録画ムービーが放映され、懐かしげに見入っていた。
フィクションであれば、長い忍耐の末にルーベンスが戻ってきて、家族の幸せを噛み締めるという結末も可能だったかもしれないが、現実はこんなにも過酷で、ちょうど飼うことになった犬の運命と同様に、主が粗末に扱われたということだ。その対比の構図も良かったと思った。本当によくできた政情批判のホームドラマだった。
母であり父になったエウニセ
上映館少なすぎる…でも、ほぼ満員。もっと上映館増やしたらええのに🤨
これが実際に起きたことというのが衝撃的でもあり独裁政権の恐ろしさを認識させられる。この映画のすごいところは、暴力的なシーンはほぼ描いていないにも関わらず背景にある軍事政権の恐怖が伝わってくるところ。
幸せな日常が描かれる前半、そして愛する夫がいなくなり苦悩する後半。幸せな日常シーンはありふれた家族の幸せをこれでもかと描き、ディアーハンターを彷彿とさせる。この前半の対比が後半でありこれから起こる悲劇を予感させる。
あの家族が崩壊せずになんとか生きてこられたのはエウニセの強さゆえやろう。悲しみや憎しみに耐え、ただただ家族を守るために動く。子どもたちも状況がわかっている子、わかっていないけれど様子がおかしいことは察している子それぞれの痛みや苦しみがある。
父のいない家族写真を笑顔で!と言う強さ。憎しみの気持ちに負けず、反骨精神を持ち理不尽に立ち向かう姿勢。心から尊敬する。母であり父になったエウニセ。あの軍事政権化でおかしいと立ち向かおうとしたパイヴァ。感性が似ている夫婦やったんやろうなあと。死亡診断書を手にし、笑顔になるシーンはやっと一区切りしたという安心感もあったのだろう。実際の写真が出てくるが、エウニセが指輪をつけ続けているところに深い愛を感じた。
この映画の原作が、事件当時幼かったマルセロが書いたものというのも感慨深かった。
みてもちろん明るくなる映画ではないし、私はしばらくあの笑顔を引きずるだろうが、歴史を知ることに意味がある。そして考えることに意味があると思いたい。
説明があまりないので
いつもの映画館で夏休みに
チラシで興味がわいた
アカデミーの外国語映画賞だったとか
あと主演女優賞もどこかの映画祭で
で おおむね予想通りなのだけど
説明があまりないので
ん というところが何か所か
突然いなくなう子ども 心配するのだが
次のシーンでは戻っていてストーリーに関係ないような
銀行のシークエンスもいまひとつ理解が及ばず
子どもが5人なので混乱もして
後に息子がこうなるのかというエピソード 印象深い
上映終了後 廊下に張り出してあった雑誌記事の切り抜き
監督のインタビューを読んで あぁなるほどと
そもそも息子との邂逅だったようだ
あと主人公の最後の老け役は母親だと
てっきり本人の特殊メイクかと それをコミで主演賞かと
Torture
アカデミー賞2025の作品の中では最後の上陸かな?ってくらい結構待たされましたが無事鑑賞。
かなーり静かな作品で、父親が突然攫われた一家というのを描いているんですが、いかんせん台詞量が少ないので心情を察するのが難しくて苦しいであろう作品のはずなのにシャレオツ映画に思えてしまいました。
序盤の普通な日常を過ごす一家は美しく、ビーチでやんややんややったり、犬を飼ってみたいと言い出してみたり、家族間での何気ない会話だったり、日常がぶっ壊れる直前とはいえこの日常がずっと続けば良いのになと思えるくらいには良かったです。
ビーチのちゃんねー達がめっちゃ綺麗で、ビーチのシーンでドキッとさせられたのは久しぶりでした。
そこから薬の取り締まりで娘が検問されて不穏な雰囲気が漂いはじめたかと思ったら父親が誘拐されてしまい、行方も分からず、そのまま家族も尋問を受けるという非日常に様変わりしてしまうというところから本筋が始まるんですが、それまでの前振りがちと長いのもあって少しダレてしまったかなぁという印象です。
もちろん、夫を助けるために奔走する奥さんの姿はカッコいいですし、リアルな尋問の様子もスリルがあるのですが、どうしても堅苦しい雰囲気は抜けず、映画というよりかはドキュメンタリーに近いように思えてしまい映画としてはそこまで楽しめなかったです。
心情描写を読み取って行間を埋めるってのを頭の中でやりながら観る作品だとは思うのですが、行間が多すぎて考えが繋がらなかったのもなんだかなぁって感じです。
全体的に音楽はめちゃめちゃカッコよかったです。
プレイリストとてもイカしています。
レトロな絵作りもとても良かったですし、いかんせん内容だけ合わんかったなぁって感じです。
相性の問題であまり乗れずでしたが、合う人には合う作品だと思いますし、ずっしりとくる作品なので、また見直す機会があればなと思いました。
鑑賞日 8/15
鑑賞時間 17:25〜19:45
自ら車を運転して出頭したルーベンスは、そのまま帰ってこなかった。
1971年1月(夏)、軍事政権下のブラジル、かつては下院議員を務め、リオで建築業を営んでいたルーベンス・パイヴァの拘束と行方不明について、その妻エウニセが、どのように行動したのかを描いた、長男マルセロの回顧録に基づく感動作。
その日、ルーベンスは、私服で銃を保持した秘密諜報機関と思われる人物の訪問を受け、自分の車を運転して当局に出頭する。ルーベンスには、水面下での政治亡命者との付き合いがあったようだ。翌朝には、妻エウニセも拘束され、情報の提供を求められる。服を替えることもできないエウニセの独房での拘束と尋問は、12日間に及んだが、ルーベンスの行方は全く不明だった。エウニセは、ルーベンスの生還だけでなく真実を明らかにすることを求めた。そのような活動には危険が伴い、家族間の軋轢もあったろう。実際、この家族は、軍事政権が続いているあいだ、ずっと監視下に置かれていた。しかし、この映画の冒頭でのエピソードが活きてくる。いくら経済的に恵まれているとはいえ、エネルギーに満ち溢れた家族だった。
ルーベンスの生還を待つエウニセは、購入していた土地を売り、邸宅も貸して、お金を作ると、生活費の高いリオからサンパウロの実家に戻り、子供たちを育てながら、大学に復学して弁護士の資格を取り、社会運動に従事した。
25年後の96年、エウニセの活動の結果として、はじめてルーベンスに関する公的な文書が公開される。その時、エウニセを囲んでいたジャーナリストから問われて彼女が返した言葉が、この映画の白眉;(軍事政権が85年に終了した以上)過去の事件を振り返るよりも(今、エウニセが取り組んでいるような)優先すべき事柄がたくさんあるのではないか、との記者の問いかけに対し、彼女は「過去の過ちを検証しなければ、また同じことを繰り返すことになる」と訴えた。実際、軍事政権下で捉えられて帰ってこなかった人たちは2万人を越えたと言う。彼女は、被害者家族への補償を求めたのだ。
大変、驚いたこと、96年の時67歳だったと思われるエウニセは、認知症の症状を示していた。ここで映画は終わりにして、あとは、写真とテロップを示すだけでも良かったのではないかと思ったが、私の言い過ぎか?
ある日突然
前情報もブラジルの歴史もほとんどないまま観て。
ある日突然連行され、てっきり結末迄で戻ってきてくれるのかと思いきや、25年後という残酷。。。
マルセルの事故もだが、淡々と酷い現実。
戦争状態になくても、軍事独裁とか、ほとんどの人には良いことなんか無い。
陽気な国という印象だけど、軍属だと違うんかね、、
戦いなんてしないで気楽にみんなが暮らせるようになればいいのに。
歴史上の事実にびっくりするけど...
今年度のアカデミー国際長編映画賞受賞作品。1970年 ブラジル軍事政権下で起こった民間人ルーベンス・パイヴァの強制逮捕による失踪事件と、彼の行方を追った妻 エウニセ・パイヴァの半生を描いています。原作は彼らの5人の子供の末子 マヌエル・パイヴァによるノンフィクション。
ブラジルにそんな軍圧の厳しい時代があったことすら知らなかったのですが、この作品で描かれていたようなことが、現実として起きていたことにとにかく驚かされます。
一方で物語の展開は、予想していたようなものとは違いました。事件をきっかけに、エウニセは家族の生活も自身の生き方もがらっと変わるのですが、行方不明の夫の捜索にどのような行動を取ったのかはあまり描かれません。
作品の終盤では事件から25年後、さらに18年後の描写があります。物語を締めくくるには必要なパートではありますが、この部分への展開はやや唐突感があり、全体の流れからすると異質に感じました。むしろこの間に何があったのかに、聴衆は興味を持つかなと思いました。
アカデミー主演女優賞にノミネートされたエウニセ役のフェルナンダ・トーレスさん。晩年のエウニセを演じたフェルナンダ・モンテネグロさんはトーレスさんの実母とのことでした。鑑賞中はずいぶんそっくりな役者さんを当てたな、と感心しましたがそういうことだったのですね。
幸せに満ちた日々が一瞬で奪われる恐怖
ビーチでの戯れ、ゲンズブールの音楽に合わせたダンス、スフレを味わう食卓、本当に楽しかった日常を同じ気持ちでは過ごせなくなる、この理不尽さ。
政治的背景や母や息子の後年のエポックメイキングな出来事は敢えて描写しなかったため、映画的にはドラマティックな部分が薄まった感じはあります。一方であくまで家族にフォーカスしたエモーショナルな手法は、名作「セントラル・ステーション」のウォルター・サレス監督らしさとも言えます。
母役のフェルナンダ・トーレスが渾身の演技をみせるのですが、子供達も印象的なシーンを担い、作品に深みを与えています。
母が十数日ぶりに解放され夜中にシャワーを浴びているシーンで、三女ナルがドアの隙間から覗いて、込み上げる感情を抑えている時の表情。
イギリス滞在中の姉からの手紙で、母と次女エリアナが言い合いになります。母は年少者に配慮して事件に関わる箇所には触れませんでしたが、次女は自分も当事者なので何故隠すのかと。双方の気持ちが理解できる辛く、緊張感のあるシーンでした。
そしてリオから引っ越す日、玄関に茫然と座り込む四女バビウ。住み慣れた家を離れる寂しさだけでなく、もう父親が戻って来ないことを確信した虚脱感が溢れるこのシーンは悲しかったなあ。
何気ない日常の大切さを改めて感じさせる力作です。
母ちゃん強し!最強!世界共通やね。
なんもわからんで観たので家族愛しかわからんかったわ。
でも実話なんよね。
エンドロールで色々情報が流れたので奥さんの凄さが改めて思い知ったけど。
作品としてはお勧めはしにくいですけど人として愛する人を思い愛を貫き通す気持ちを大切にする彼女の意思を広めるのには良い教材になります。
淡々とした語り口は胸に染みるものの、その分、軍の非人道性や運命の過酷さが伝わってこない
愛する夫が、ある日突然、連行されたまま、いつまでたっても戻らないという状況に直面した妻の混乱と憤りは、想像するに余りある。
その父親は、明るくて優しい性格で、子供たちにも慕われているのだが、彼が二度と戻らないことを察知した後でさえ、子供たちに取り乱した様子や悲しい顔を決して見せようとはしない、母親としての彼女の気丈さにも心を打たれる。
その一方で、夫を連行するために家に押し入り、そのまま居座る軍関係者は、思いのほか紳士的で、子供の遊び相手になったりするし、妻が尋問を受けるシーンにしても、何日間も不衛生な牢獄に監禁されるのは酷いと思えるものの、取り調べそのものは決して高圧的ではなく、彼女が釈放される際には、担当者が「本意ではなかった」と釈明するなど、それほど極悪非道な扱いを受けたようには感じられなかった。
これは、悪いのは軍事独裁政権であり、末端の軍人はその命令に従ったまでで、個人としては必ずしも悪人ではなかったということを言いたかったからなのだろうが、その分、妻が怒りや憤りをぶつけるべき対象が曖昧になってしまったように思えてならない。
あくまでも妻の視点から描かれているため、夫が拷問され、虐殺され、海中に投棄されるような描写も出てこないのだが、ドキュメンタリーや再現ドラマではなく、フィクションであるならば、この辺りの経緯もしっかりと描くことによって、糾弾すべき軍の横暴や非人道性をもっと明確にするべきだったのではないだろうか?
それから、夫(父親)を失ったことによって、家族の運命が狂わされたのは理解できるのだが、新しく家を建てる予定だった土地や、今まで住んでいた海辺の豪邸を手放して、よその街に引越していくところまでしか描かれないため、彼らがどれだけ苦労したのかがよく分からない。
元々裕福な家庭なので、困窮するようなことはなかったのだろうが、25年後には、事件の後に大学に行き、弁護士となった妻は、それなりに活躍しているようだし、息子は息子で、事故か何かで車椅子生活を送っているものの、小説家として成功しているようなので、あまり「過酷な運命に翻弄された」みたいには感じられなかった
残酷で理不尽な経験をした家族だからこそ、その悲しみや苦しみを乗り越えて、いかにして平穏で幸せな暮らしを手に入れたのか、その過程をもっと知りたかったし、そこのところがほとんど描かれなかったことが、非常に残念に思えるのである。
どこにいるの⁉️
1970年代の軍事政権下のブラジルを舞台に、元政治家の夫を連行された妻と5人の子供たちを描いた作品‼️結局夫は戻って来ず、妻も拘束されたりする。妻は夫の行方を必死に探し、亡くなるまで様々な社会貢献をする‼️終始、妻の表情や佇まいで、当時の社会情勢への不安、恐怖感がイタイほど伝わってくる秀作ですね‼️戦争中の日本や、50年代ハリウッドの赤狩りもそうですけど、今も世界のどこかで同じような悲劇が起きてるのかもしれません‼️
全29件中、1~20件目を表示