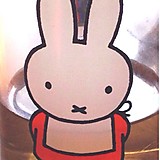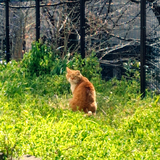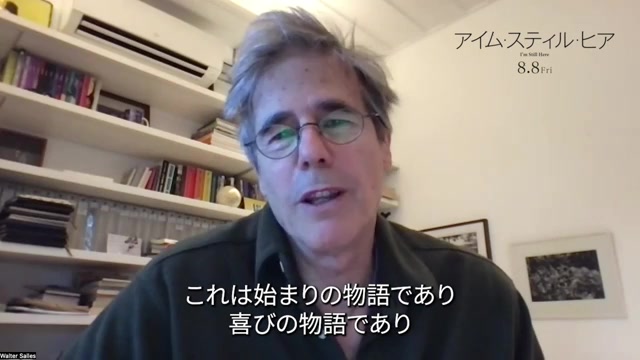アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全97件中、41~60件目を表示
南米の歴史に学ぶ、強くて硬派な作品
『アイム・スティル・ヒア』は、そのタイトルのとおり、静かな闘志で連帯し、決して暴力に屈しない、自分のしなければならないことを全うする主人公とその家族を描いた、強くて硬派な作品でした。
日本だと家族ものの側面でセンチメンタルになってしまう場合もあると思いますが、そこはラテンアメリカの持つ明るさや強さを打ち出した、そういう独特な味わいのある、優れた作品でした。
個人的には、80年代に劇場で見て衝撃を受けた『サンチャゴに雨が降る』や『ナイト・オブ・ペンシルズ』といった、やはり南米の圧政を描いた作品を鮮やかに思い出しました。
1970〜80年代の南米は悲劇と激動の歴史があります。
エヴァ・ペロンの時代の後に到来する、1970年くらいからの一時代は、、「汚い戦争」と言われていたアルゼンチンの暗黒時代です。
(この「汚い戦争」を描いたのが『ナイト・オブ・ペンシルズ』という映画です)
チリも、ピノチェト政権下での民衆がこれでもかと激しい弾圧を受けていた時代です。
ブラジルはチリやアルゼンチンよりはマシだったようですが、70年代〜80年代にかけては軍事政権下での言論統制あったようです。
この映画で見る、主人公の夫が突然軍部に逮捕され二度と会えなくなり、自身も12日間拘留・尋問される場面は、激しい暴力少なめでも本当に恐ろしく描かれていて、「何をされるかわからない」恐怖に戦慄します。
その恐怖を乗り越えて、最愛の夫の最期を確かめようとする、権力の横暴に最後まで立ち向かおうとする、主人公の強さに胸を打たれます。
一つだけ注文をつけるなら、前半の家族の楽しい時間を描く部分が少し冗長で、ここはもう少しコンパクトにして、全体を2時間弱くらいにしても良かったのではないかと。
つくづく思うことですが、どこの国でも、軍隊が力を持つと民への抑圧や暴力が避けられず、悲しい歴史が作られてしまいます(日本の戦時中もそうだったように)。
歴史に学ぶことを忘れずにいる必要があります。
恥ずかしながらブラジルの軍事独裁政権については無知だったのでこの話...
タイトルなし
実話ということもあり、悲しかった。5人子どもがいる大家族とか日本ではもうレア。最後に実物写真が出てくるが、元政治家の父親はそっくり。母親は実物のほうがもう少し美人で穏やかな感。でも女優はうまかった。
子どもたちの世界を守る気丈な母親。
いつ父が逮捕されたと分かったか、後に子どもたちは話し合う。家を移ったとき、父の服を売ったとき。
原作となった母の手記には、家の思い出が書かれていたのだろう。
本当に仲のいい素敵な家族だった。ユーモアと知性があった。そして時代の空気。まだケータイの時代ではないし、レコードである。音楽と8ミリがある。親も子も左翼の世代。
出来事は歴史のトラウマだけれど、この意味でその悲しみを乗り越えていく家族は明るく、特に母は力強い。
「コーヒー好き」
リアルな拉致家族を描く
創作を極力排したということか
あたかもドキュメンタリーのように。
子煩悩で裕福な元議員の夫とその妻、5人の子どもたちとの幸せな日々が描かれる前半、そして突然訪れる夫の逮捕と自身の取り調べを境とする後半。この明暗がくっきりして軍政の非道ははっきりしているのだが、目を覆うようなショッキングな描写はないし、かといって謎解き要素があるわけでもなく、反体制派であることは示されるけれど、夫がどのように落命したのかは不明なままだ。実際によくわかってないから、過度な創作はしないというスタンスだったのだろうと思う。ブラジル含め南北アメリカではよく知られた話なのかな。
ホームムービーや記念写真が効果的に挿入される。思い出は美しい。けれど甘すぎない。釈放後のシャワーシーンが痛々しい。けれど美しい。
観た人には重要なトリビアあり🫡
この作品名作です!
タイトルですが日本語にすると🔥私はここに居る🔥という強い意志を示すような言葉なのでこの作品のテーマを物語ってますねぇ💪✊
まずこの手の作品は居なくなった父親のシーンが普通はあるはずなのに奥さんの目線のみのストーリー進行で父がどうなったのかを全く見せないから何が起こっているのかわからないし主人公が連行された時にあの場所に居る他の人がどんな事をされているのか映像で見せないから一切判らず(とは言っても関心領域みたいに叫び声などで拷問されてるのはわかるんだよねえ🤮)主人公の置かれている状態を疑似体験させられるので連行される、顔に袋を被せられる、尋問される、旦那も娘もどうなってるのか一切判らないし何日居るのかすら判らないとか下手なホラー映画より怖い疑似体験させられて緊張感MAXでしたよ🙀
しかも悪い事してる軍のやつらを追い詰めて行く社会派ドラマって感じで進行する訳でも無くあくまでも家族の物語を見せていくってのが逆に凄いと思ったしみんな演技も自然だし歌や音楽も良かったし写真の使い方で実に上手くて泣かせますって感じのオーバー演出が一切ないのに涙目🥹になるよいたなシーンもあるし名作ですねこれは(母親が尋問された場所から戻って来て風呂🛀に入ってる場面で娘は母が帰って来たって気づくんだけど母親の様子を見て直ぐに声をかけられないって場面やあの家を引っ越しする事になって最後に名残惜しいって感じで娘が家の中を見ていてそのあとみんなが車に乗ってる時のあの表情見るだけで父親との思い出の家🏠を去る悲しみの感情とか🥺色々と演出が上手いんだよねぇ🥺🥺🥺)
ここからトリビア行きます‼️
評論家の人の話を聞いて分かった事ですが作中に使われてる歌を歌ってる人で当時実際に悪い影響を与える歌を歌っていると言う事で国外追放された人が2人いて(その歌を聴いてるヤツも反乱分子だろうって発想で軍の関係者が主人公の家に来た時に悪い影響のある歌を聴いてないかを調べる為にレコードを見てるシーンがあるんですがその予備知識が無いと見逃しますよ絶対に🥶)
あと留学した娘が帰って来て車で帰る時に車の前で父親の話をする時にラジオのボリュームを上げるシーンがあってそこでかかってるのが2+2のようにって曲で歌の内容も2+2は5だけど大丈夫みたいな歌詞で(2+2は5な訳無いんだけど群のやつらが5と言えばそれに従うしかないんだけどそれを大丈夫って歌ってる時点で今の軍事政権をおかしいぞって比喩して批判してる歌があの場面でかかってるそうです😭これはブラジルの年配の人じゃないと絶対に判らないし日本人でそこの説明無しであの場面を観てもわかる訳無いからそれを知ってみると更に面白さが増しますよね)
あと原作者が映画化する条件として母がされた拷問のシーンを描かない事という条件付きで映画化を許可したそうです!
ラストに実際の写真が出て来て ウワッ🥶実際の話だとは知ってたけど写真あるのかよ😱ってなりました(役者さん実際の人にかなり寄せてるよねって思うくらいみんなソックリでした👍)
クニが望むもの ヒトが望むこと
…悲しみが消えることはない。ただ時間と共に小さくなるだけ。いつもそっとポケットにしまってあるだけ。
確か「ラビットホール」に、そんなセリフがありました。お婆ちゃんになったエウニセ姐さんに去就するものは何だったのか、私には、ちょっと想像できないけど。
あまり家族との楽しい思い出が、見当たらない私です。でも、家族なんだよね~。少なくとも、他者の都合で引き離されたことはありません。今にしてみれば、それ自体が凄く大切なことだったみたい。
少しネタバレしますが、序盤の8ミリだか、16ミリで、撮られたフィルムに残る家族の笑顔。未来のお家に、夢と希望を託した笑顔。あれが、何にも替え難い幸せな宝物だったことに、後で気づかされます。
きっと私にも、思い出せないだけで、他に替えられない幸せな宝物、あるんだろうな。それに気づかせてくれた映画に出会えたことに感謝です。ちょっと出掛けるね~って言ったら、渋々許可した家族にも、感謝しないとね。
「アクト オブ キリング」
「ルック オブ サイレンス」
クニの都合でヒトが非道い目に遭う映画は、いくらでもあります。でも、おかしな話だよね。ヒトが暮らし易くするのが、クニの存在理由なのに、クニがヒトを、不幸にする。しかも、組織的にね。
クニが正式に謝罪を表明。時折、耳にしますが、クニって何だろう。クニって誰だろう。
謝罪したクニは、その後、どうすればいい?
謝罪したクニに、国籍を持つヒトは、その後、何をしたらいい?。
このクニの8月は、そんなこと考えてみるのも、いいのではないのでしょうか。
写真撮るよ、笑って!
事前情報ゼロ、歌舞伎の「ぢいさん ばあさん」みたいな話かと勝手に思っていたので、映画見ながら、見終わってからハンマーで頭を殴られた思いでした。なぜ見たかというと、アカデミー賞授賞式で主役のフェルナンダ・トーレスが何度も映り、知的で笑顔が自然で素敵な人だったから。見て本当によかった。
前半はいわゆる「70年代」をたっぷり浴びた。ファッション、車、カメラ、音楽(ビートルズとかT・レックスとかバーキンの例の歌とか)、集合写真とか。そうか、ブラジルでは夏がクリスマスなのか!も新鮮だった。構成も脚本もいろんな意味を持たせている小道具も子犬も、海のそば、広くていつもたくさんの人が居る賑やかなお家や家具の美術セットも、衣装もとてもよかった。子ども達が可愛らしくて笑えるシーンがたくさんあった。そして全編通して一番よかったのが、妻・母・弁護士のそれぞれをある時は混ざりあい、ある時は演じ分けたフェルナンダ・トーレス。それほど台詞は多くなかったように思うのにとても豊饒な饒舌さを感じたのは、彼女の表情と目ゆえだと思う。
子ども達の個性はそれぞれ際立っていて、きょうだいや両親や周りの大人達から愛され大事にされきちんと育てられたのがよく伝わる。小さい組の子ども4人が後部座席に座り、長女ヴェロカが助手席で運転席はエウニセ。引っ越し後に長く続く彼らの生活を暗示していた。
記録、調書、記事、報道、証明書の重要性を実感した。夫関連の資料を時系列に綴じたファイルをエウニセは何度も開き見る。一番最後の紙は悲しいのに、受け取ったエウニセが笑顔だったのがとても不思議で辛かった。
まだ頭の整理がつかないのでパンフレットも読んでない。とても読みごたえのあるいいパンフレットだろうと私の勘が教えてくれている。楽しみに読もう。
映画化された”ショック・ドクトリン”
今年の米国アカデミー賞で作品賞などにノミネートされ、最終的に国際長編映画賞を受賞した本作が、ついに日本公開となりました。私は事前情報をほとんど持たず、ただ「アカデミー賞候補」という程度の認識で鑑賞したのですが、最初に思い起こしたのは、10年以上前に世界的ベストセラーとなったナオミ・クラインの評論『ショック・ドクトリン ― 惨事便乗型資本主義の正体を暴く』でした。
同書は、自然災害・戦争・政変といった「惨事」の混乱を利用し、過激な新自由主義的政策が導入された歴史を丹念に解説した名著です。とりわけチリのピノチェト政権(1973~1990年)の事例が詳しく紹介されていますが、米ソ冷戦下にアメリカの軍事力や経済力を背景とした”反共政権”が強権的に国を統治した点では、本作の舞台となる1970年代初頭のブラジルも同じ状況にありました。
チリが1973年の軍事クーデターでピノチェト政権となったのに対し、ブラジルではそれより9年早い1964年、カステロ・ブランコ将軍がクーデターで政権を掌握します。以後、国営企業の民営化、外資の導入、公務員削減、福祉の切り捨てといったミルトン・フリードマンに代表されるシカゴ学派の影響を受けた新自由主義的政策を推進すると同時に、反対派を徹底的に排除しました。結果、格差拡大に伴うストライキやデモ、ゲリラ活動も起こりますが、ブランコの2代後のメディシ大統領は議員や大学教授の追放など非合法な弾圧を強行しつつ治安を回復。安定した低賃金労働と外資の取り込みで「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度成長を実現しました。(因みに1973年のオイルショックにより、「ブラジルの奇跡」は終焉を迎えます。)
この時代を背景に描かれるのが本作です。物語の中心はパイヴァ夫妻。夫ルーベンス(セルトン・メロ)は元議員で、軍事政権に追放された人物です。1971年初頭、彼が政権に拘束され、その直後に妻エウニセと娘も拘束されて取り調べを受けます。エウニセは十日余りで解放されますが、ルーベンスの行方は不明のまま。彼女はあらゆる手段で夫を探し続けるも、日々は虚しく過ぎていきます。
そもそも本作は、夫妻の長男マルセロ・ルーベンス・パイヴァ(幼少期をギレルメ・シルヴェイラが演じる)の回顧録を原作とする「事実に基づいた物語」です。『ショック・ドクトリン』で語られたような軍事政権の強権的弾圧が映像化され、スクリーンを通して直視させられたことは非常に衝撃的でした。そして弾圧に屈せず、不屈の闘志で立ち向かったエウニセの姿は辛抱強く、時に神々しくすら感じられます。最終的に彼女が夫の「死亡証明書」を笑顔で受け取るという皮肉な結末は、強烈な印象を残しました。
俳優陣では、何と言ってもエウニセを演じたフェルナンダ・トーレスが圧巻でした。夫を奪われた妻の悲しみに満ちた表情から、困難な状況下で五人の子を育て上げる母としての愛情溢れる表情まで、すべてが素晴らしい演技でした。さらに老年期のエウニセを演じたのが、彼女の実母でありブラジルを代表する大女優フェルナンダ・モンテネグロだったというのも驚きです。認知症を患った晩年のエウニセを限られた出番ながら深みをもって演じ、親子共演が見事なキャスティングの妙となっていました。
また、軍事政権側の秘密警察を思わせる人物たちも実にリアルでした。慇懃無礼かつ威圧的な態度で迫る様子は、もし自分の前に現れたらひとたまりもないと感じさせる迫真の演技でした。
そんな訳で、本作の評価は★4.6とします。
軍事政権時代の闇
1971年、ブラジルのリオデジャネイロで、軍事独裁政権に批判的だった元下院議員のルーベンス・パイヴァは軍に連行され行方不明となった。残された妻のエウニセと5人の子ども達はルーベンスが戻ってくることを信じて待ったが、やがてエウニセも拘束され、政権を批判する人物の告発を強要された。釈放された後、エウニセは夫の失踪の真相を求め、活動した、という事実に基づく話。
ブラジルで実際に起きた、軍事政権による理不尽な拷問による元議員の死と、遺された彼の妻子のその後が知れた。
ルーベンスとエウニセの息子であるマルセロの回想録が原作との事。
鑑賞後に調べてみると、ブラジルの軍事政権時代とは1964年から1985年の21年間らしいが、1971年だと軍が1番強力だった頃かもしれない。
後に軍の関与、死亡証明書も勝取り、エウニセは大変な人生だったが、目的は果たせて良かったのかな。
エウニセを演じたフェルナンダ・トーレスは迫力が有った。
予備知識なく観たから、最初は軍事政権下でも楽しく、70年代を過ごす...
予備知識なく観たから、最初は軍事政権下でも楽しく、70年代を過ごす家族を描くのかと思ってしまったが・・・
良心による行動が権力の生け贄にされるのは耐え難いが、それを乗り越えたエウニセの強さに感服した
流れる音楽、部屋に飾られているポスターなど、70年代のリオの雰囲気が良かった
怒りと、二度と起こしてはならない決意と
本作の舞台であるブラジルの軍事政権時代は、韓国やベトナム、ミャンマーなど軍事政権下にあった時期の国々と同様に、政権に都合の悪い人間を暗殺する手口の荒さと、隠蔽の粗く酷い様は筆舌に尽くしがたく。
映画は被害にあった一家がいかに幸せだったかから始まり、どれだけ酷い目に遭わされたかを経て、夫を拉致され殺された妻が認知症になっても怒りを忘れていないところまで、丁寧に掘り下げて描いていました。
国家の暴虐にはげんなりするし、怒りが湧きます。
自分にMCUに出てくる超人たちみたいなスーパーパワーがもしもあったら、こういう軍事政権の中枢政治家や、その命令で動く実行部隊の司令官まで、皆殺しにしたくなりますわ。
(余談ですが、DCのジェームス・ガン監督の新『スーパーマン』はそんな気分をうまく掬ってたと思いました)
人命を軽んじる世には、二度となってほしくありません。
世界あちこちの内戦・紛争・戦争の地の現実と、独裁者による支配地での暗殺の横行に想いを馳せつつ。
25年後
集合写真を撮ろう
南米の軍事独裁政権といえばアルゼンチンやチリが有名だが、ブラジルでも21年間にわたって続いていたなんて。
何も知らされずに底抜けに明るいブラジル人社会、その裏に潜む閉塞感、警察ではなく軍に理不尽に拘禁、殺害された元国会議員とその家族の悲哀、そしてその中からたくましく這い
上がった妻の心情を描いた作品。
エピローグで「何か良い事があった時は集合写真を撮るのが我が家の伝統よ」というセリフにあるとおり、ことあるごとに家族全員で撮る写真がストーリーの根底にある。
今年のアカデミー賞受賞作品であるにもかかわらず、日本での公開がこの時期まで遅れたのは何か思惑があってのことだろうか?
世界各国で民主主義の危機が叫ばれていて、特に今年に入ってからは民主主義を第一に標榜していたアメリカ合衆国にあってもそれを正面から否定するような論調が目立っている。
MAGAの連中よりも金満で凶悪なテックライトTech Rightの連中は民主主義を排し専制政治にすべきと声高に主張している。そのためアメリカのデモ隊のニュースで「No King」というプラカードがよく目に付くようになった。
専制政治の行き着く先は軍事独裁であることは明白であろう。
日本においてもアメリカの風潮を見習っている政党が伸長していて恐ろしい限りだ。
そういう意味では今回の封切は良いタイミングであったかもしれない。
軍事政権、一党独裁政権、独裁者政権はこんなもの。
見て聞いて確認が取れている内容をもとに誠実に客観的に淡々と描く ある家族の肖像とブラジル軍事政権の闇
物語は1970年12月のブラジル•リオデジャネイロの浜辺から始まります(南半球なので12月は夏なんですね)。浜辺でビーチバレーやサッカーに興じている若者たちの様子等のシーンを通して、この作品で描かれることになる家族のメンバーが紹介されてゆきます。
ビーチから道路を隔てて徒歩1-2分といったところに住んでいるパイヴァ家。両親と上から女、女、女、男、女の5人きょうだい、お手伝いさん ひとり、映画冒頭で飼い始めることになる犬1匹。お父さんは土木建築関係のコンサルティングみたいな仕事をしています。序盤はブラジルの子だくさんの裕福な家庭を描くホームドラマみたいな感じで進んでゆきます。長女がロンドンに留学することになり、送別パーティーをしたり、とか。ここらあたりは’70年代始め頃のテイスト満載です。やはり、音楽とか映画とかのサブカルチャーというのは世界の共通言語なんですね。その頃、中学生だったはずの私は、自分がここの家の次女と三女の間ぐらいの年齢なんだろなとあたりをつけました。
でも、幸せな日々は、以前国会議員をしていたという父親がある日突然 数人の正体不明の男たちに連れ去られたことにより、終わることになります。この出来事の影には当時のブラジルの軍事政権がいるみたいで、彼の妻であり、5人の子の母であるエウニセ(演: フェルナンダ•トーレス)も次女とともにしばらくの間、拘束され、当局からの尋問を受けます。で、ここからはほぼ、このエウニセの視点でこの映画は進んでゆきます。
この作品はパイヴァ家の男の子マルセロが長じてから母親のエウニセに取材して著したノンフィクションもとに作られたようで、ウォルター•サレス監督は少年時代、パイヴァ家に出入りしていたみたいです。ちなみにサレス監督は私と同い年なので先述の私の推測が正しければ次女と三女の間ぐらいの年齢でノンフィクションの著者マルセロより3-4歳年長だと思います。この作品の ‘70年代初頭のサブカルチャーの描き方に私が郷愁を感じたのは監督と同い年だからかもしれません。長女がロンドン留学して最初に買ったレコードがT•レックスのものだったり(グラム•ロック! ヴォーカル兼ギタリストのマーク•ボランは事故で早逝したはず)、長女が「ビートルズ」ではなく「ジョン・レノン」にいつも言及しているとかは、その時代っぽいかな。
何はともあれ、ノンフィクション由来で自分も知っている家庭ということで、サレス監督はこの家族の日常を見て聞いて確認が取れている内容をもとに誠実に客観的に淡々と描きます。これがエウニセ役のフェルナンダ•トーレスの好演(お見事!)と相まってとても効果的でした。エンドロールに出てくる実際の家族の写真も本当によくて、この作品を実話をもとにした ある家族に訪れた悲劇以上のものにしています。
この映画はブラジルで大ヒットしたそうですが、たぶんブラジル人にしかわからないような内容を多く含んでいるのではないかと推測できます。映画内のポルトガル語で歌われている ’70年前後のヒット曲は、彼らにとっては、ああ、あれか、みたいな感じになるのでしょうね(日本人がピンキーとキラーズの『恋の季節』が映画内で流れているのを聞いたときみたいな。例えが古くて申し訳ありませんが)。もう一つは政治的な意味です。ブラジルでは2018年の大統領選挙で軍人出身のジャイール•ボルソナーロ氏が当選し、「ブラジルのトランプ」と呼ばれた氏の政権が誕生します。2022年の大統領選挙で彼は敗れますが、選挙の無効を主張し、彼の支持者が議事堂に侵入したりします(その2年前に起きた話に酷似していて、当時ニュースを見た私は不謹慎ながら笑ってしまったのですが)。で、ボルソナーロさん、軍を動かしてクーデターを画策したみたいなのですが、軍は動かなかったそうです。まあ、やれやれといった感じです。軍事政権の何が怖いかって、自国の国民の中に彼らにとっての「非国民」を見つけてそれを排除しようとするんですよね。ということで、この映画には50年ちょっと前にこんなことがありましたという警鐘の意味があったのかもしれません。
《おまけ》
映画内の音楽がなかなかご機嫌なナンバー揃いだったので、Spotify で『アイム•スティル•ヒア』のプレイリストを探し出して何度も聴いています。その中に “Fora Da Ordem” という曲があります。ブラジルの国民的シンガーソングライター カエターノ•ヴェローゾの曲でポルトガル語で歌われています(と思います)。この曲の後半に女性ヴォーカルがフィーチャーされているのですが、そこで日本語で「新世界の無秩序」と歌われているように聞こえてちょっとビックリ!! さらに聴くと、英語で “It is like something has gone out of order” みたいに聞こえる箇所もありますが、小生、英語のリスニングにそれほど自信がありませんので、まあ、たぶん “out of order” とは歌っているだろうな、あたりにとどめておます。「無秩序」と “out of order” ということで、これ、ポルトガル語の歌に外国語を忍ばせて、軍事政権を批判しているのかもと思いますし、別の外国語も忍ばせてあるかもしれません。検索したら、カエターノ•ヴェローゾは当時、政府批判で国外追放されてロンドンにいた、とありました。誰か詳しい方、ポルトガル語等の外国語に堪能な方等、曲を聴いてコメント下されば幸いです。
全97件中、41~60件目を表示