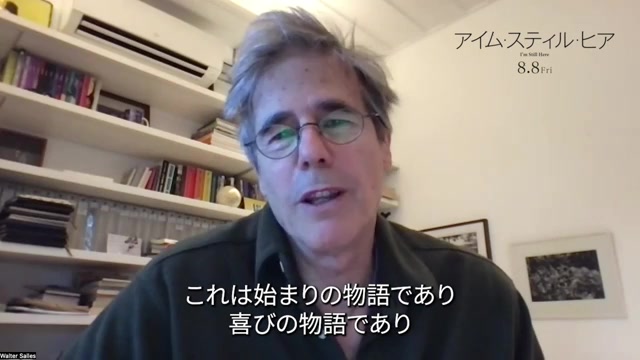アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全126件中、121~126件目を表示
つい最近の知るべき歴史
試写会にて鑑賞。
もっと重いストーリーを覚悟していたが、家族の力強さに焦点があたっているためそこまで後味は暗くなかった。
70年代なんてついこの間、なのに軍事政権下のブラジルでひどい人権侵害、暴力、理不尽に従っていた頃の話。でも国民は明るく音楽をかけて友人を招いて日々パーティー、踊ったり海で楽しく泳いだりな毎日。ブラジル人の明るさと強さを感じさせる不思議な対比。
しかし反政府派は暗躍しており、不条理に捕まった人たちを解放させようとさまざまな運動をしている。そしてその中の過激派が海外の大使を誘拐して釈放を迫っている。
だからこそその活動を疑われた元議員のパパが秘密裏に捕まり、そのまま帰ってこなくても、誰も何もいえない。口座からお金も出せない。そんな中、仲間から裏の活動を知り、覚悟を決める妻、そして五人の子どもたちを守りながら真相を究明する人生へ。おそらく40代くらいの女性だろう、なんと逞しいことか。ベローカ、エミリア、ナル、バビウ、マルセロ、覚えたくなる名前たち。
悲しい顔をするよう言われたのに笑顔で撮った家族写真。彼らの逞しさと覚悟が伝わってくる。二十五年をかけての執念と結果、エンドロールの実際の写真を見て胸いっぱいになった。
このような時代があったなんて…
家族写真は笑顔で。
事前情報無しで観ることをおすすめしたい。
軍事政権下の国では今でも当事者がいるだろうし、過去の有耶無耶にされた事件の真っ只中にいる人達もいる。平和な日本に暮らしてきた自分の能天気さを思い知らされた。強制失踪だなんて言葉も知らなかった…。
父の死亡証明書を勝ち取った夜。お酒を飲みながらマルセロとエリアナは『いつパパが戻ってこないと悟った?』と初めて話す。しんみりした雰囲気ではないのに、これまで簡単に話題にできなかった永い年月を想って涙が。
写真やビデオ映像がとても効果的に組み込まれていた。
忘られないのは記事用の家族写真を撮るシーン。
『悲しそうに』というカメラマンとは対照的に『みんな笑って!』というエウニセ。母として妻として人としての決意を表した笑顔にグッときた。
25年後にビーチで撮った写真を『いつ撮った写真だっけ?』と語るシーンにも涙。
記録は残っているのに人の記憶は曖昧なもの。
2人の子供は思い出せず、問われたエウニセは『ヴェラの誕生日』と答える。
その後エウニセは書斎でルーベンスの様々な記事をまとめたノートを読みながら闘いの日々を振り返る。ノートを閉じた後、あのビーチの写真の裏に『ヴェラの送別会』とハッキリ記す。あの幸せな日を思い出せたのだ。涙涙涙。
観たい映画はあまり事前情報を入れないので、ラストあたりの描写には鳥肌と感動の連続。まさか実話だったとは。あの家族写真が実在しているとは。マルセロが書いた本が原作だとは!
非常に社会的なテーマながら、家族の美しい姿が希望として余韻に残る。ビーチで子を見守る父と母。幸せなアイスクリーム屋の夜。年老いた母を愛しむ子供たちの眼差し。確かに家族がいた空き家になったあの家。時折現れる暖かいリオの海は、ロンドンやサンパウロの街と対比してキラキラと輝いていて、幸せな家族の原風景そのものだった。
平安な家庭が!
1970年リオで。軍事独裁政権の元で:
ビーチでの平和な子供達の遊びから始まるが、長女のベラは映画から家に帰る途中で、軍の検問に遭遇する。家ではクリスマスが近いようでツリーに飾り付けをしている。ニュースでは革命勢力により、スイス大使Bucherが誘拐されたと。結果として、七?人の政治犯と交換にスイス大使は釈放されてチリに。ブラジルの政治緊張は高まっている。日本でもこの時代高度経済成長期における社会の変動だけでなく、安保闘争などで、政治緊張が高まっていた。それに、ベトナム戦争もあった時代である。
父親、ルーベンス・パイヴァ(Selton Mello)は以前、国会議員で(コングレスマン)もう、その仕事は何年も前にやめて(?)現在は公務員として働いているようだ。彼と妻のエウニセ(Fernanda Torres)と子供五人と家政婦と暮らしている。ルーベンスは何か秘密(民主化運動に参加していた)を隠しているようで、家族の誰にもそれを打ち明けていない。寝室に電話がかかってきた時、自分の事務所で電話をとると妻にいうが、妻の表情は夫を疑うようでもない。父親であるルーベンスは子供を可愛がっているようで、末の娘の上に乳歯が抜けた時も、ともに喜び、二人でビーチに埋めた?りする(そう見えたね)。運動家の友達はここは危険だとルーベンスに書斎で言う。妻と相談して、ルーベンスの友達の家族と一緒にベラだけをロンドンに送ることに決めた。ベラにレコードばっかり買うなよって父親に言われる。ロンドンに行ったベラからロンドン生活の八ミリフィルムとT-Rexのレコードが送られる。父親がベラの手紙を読みながら、家族皆で、その八ミリをみる。それにはアビーロードのジャケットのようにビートルズの真似をして歩いている。自分の名前をベラ・レノンとサインをしてる。でも、クリスマスにビーチがないなんて変だとベラは言う。二度目は他の娘が手紙を読んで、八ミリをもう一度見ていた時、ドアベルがなる。
父親、ルーベンスはDepositionと言われて、家族を置いて、車に乗る。妻には不安感がつのる。自称、超心理学者だという不信な男を中心として数人の男に自由を奪われて、家族は生活する。その後エウニセと次女が逮捕され、そこで真相が見えてくる。驚くことに、軍事派は、ルーベンスを共産党と関係があると思っているようだ。時代が時代で,,,,,,反政府主義は全て共産党(日本共産党とは混同してはいけないね)になってしまうのかもしれない。エウニセと次女は家に戻れたが、ルーベンスがどこにいるのかわからない。逮捕された学校の先生が『水をくれ』とルーベンスが言ったことを聞いたと。これを証拠にして、弁護士はルーベンスが逮捕されたという証拠を取る。
ブラジルの歴史の大切な時代なんだろうが、ルラ(2003年から)の時代は少し興味を持っていたが、その前の時代は全く知らなかった。監督は多分、私のような人が多いと理解してか、いやこの家族が西洋のロックなどの文化が好きなのだろうけど、映画のところどころにキューを入れておいてくれる。それが、アルフレッド・ヒッチコックのサイコという映画だったり、ビートルズ後期だったり、キングクリムゾンのクリムゾンキングの宮殿だったりする。いい計らいだ。これで、時代背後がわかるね。検索で分かったことだが、この話の元は一人息子 Marcelo Rubens Paiva(Guilherme Silveira )のI'm Still Hereを元にしたものだそうだ。
ジャーナリストの友人のフェリックスからルーベンスがころされたと。でも、軍は否認を。エウニセはリオの家を売却し、サンパウロに引っ越す。25年後、民主国家となった政府から夫の死亡診断書を受け取る。ジャーナリストに数多くの犠牲者の遺族への賠償や軍事政権の罪などの責任を訴える。
2014年85歳になったエウニセは子供達に囲まれているが、アルツハイマーを患っているようだ。テレビ放送で軍事政権における犠牲者が報道された時、エウニセは反応を示したようだ。1971年、1月21日と1月22日の間に、バラックの中でリオのFirst Army Divitionによって殺されたと。2014年の五人の軍人が暴行と死亡に関わったが、誰も罪に問われなかったと。
エウニセは48歳で、弁護士(Defense Human Right)になる。、ブラジルの先住民Pataxóパタクソ族(1088年に先住民の権利を憲法で認める) の人権に関わる仕事をし、世界銀行、国連の顧問を務めたたと。2018年89歳で他界。アルツハイマーで15年か生きたらしい。字幕に。
エウニセは子供を五人抱えて、夫のために真相を明らかにして軍に責任を追求したとは勇気と忍耐がいったね。賞賛
軍事政権下の「母なる証明」
1970年代の軍事独裁政権下のブラジルにおいて、突如政府に拘束され行方不明となった夫ルーベンス・パイヴァの消息を探し続ける妻エウニセの40年超の闘いを描く。
実話がベースとの事だが、ブラジル事情について知識が疎かったため、その点では観て良かった。韓国の「ソウルの春」もそうだが、軍事政権が市井の人々にもたらす悲劇はどこの国も変わらない。政府からの拷問に近い尋問を受けながらも、子供を守る為、夫の帰りを待つ為に耐えるエウニセ。家族の為に抗う女性の映画を“母なる証明”ジャンルと勝手に銘打っているが、本作もその系譜。女は強し、母は強しだ。
ただ、ルーベンスが行方不明になった序盤の数年間に重きを置いたせいか、それ以降の時代経過が端折られ、終盤は駆け足で進んでしまった感は否めず。それでもエウニセ役のフェルナンダ・トーレスは拍手もの。老年期のエウニセも彼女が老けメイクで演じたのかと思いきや、同じく女優の実母が扮していたと知り驚いた。どうりでそっくりなはずだ。その老エウニセがラストで見せる表情が印象的だった。
全126件中、121~126件目を表示