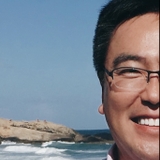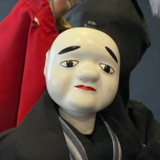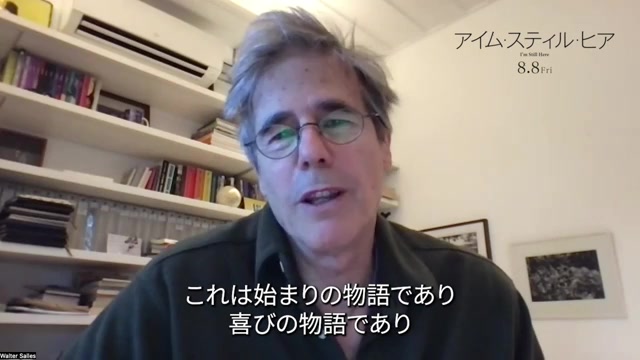アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全126件中、101~120件目を表示
悲惨なのに温かいーー家族の絆と時代の記憶
日比谷の同じ映画館で上映中の『国宝』や『フロントライン』が混雑していたのに比べ、公開間もないにも関わらず空席が目立った。あまりにももったいない。この映画は、実話でありながら、非常に豊かで美しい物語である。ぜひ映画館で観ることをおすすめしたい。
物語の舞台は1970年代初頭、軍事政権下のブラジルのリオ・デ・ジャネイロ。海岸沿いの家に暮らす夫婦と娘4人と息子1人の大家族の姿が描かれる。娘たち息子は私と同世代のはずだ。
劇中にはビートルズやMPBのカエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ジョン・レノンの話題やキング・クリムゾンの有名なジャケットまで登場し、カルチャーを共有している感覚があった。日本とブラジルでは距離も文化も違うはずなのに、音楽は僕らの世代では共通語なのだ。
この映画で印象的なのは、家族の結束の強さだ。
折に触れて親族が集まり、必ず集合写真を撮る。その積み重ねが50年分の家族の歴史の積み重ねとなり、現代に繋がっている。ブラジルは現代に至るまで、独立した家族や親族も近くに住み、誕生日や宗教行事ごとに集う文化が根強く続いているようだ。
翻って、自分の子ども時代を思う。私の家も近所に親戚が住み、特に母方の親族は、夏休みになると祖母の家へ集まり、多い時は10人ほどの従兄弟たちと蚊帳を吊って眠った。近所の親戚はよく家にやってきて、喋って帰って行ったし、僕も気軽に遊びに行った。
だが1980年代に入ると、そうした集まりは減り、住む場所もさまざま遠くに離れ、今では親しく行き来する親戚はほとんどいない。
これは私の親戚だけではなく、日本では多くの家族が経験したことではないだろうか。
一方、ブラジルでは都市化が進んでも、成人後も親と同居する文化や徒歩圏内に住む習慣があるのだという。
この映画の物語は、非常に重苦しく、理不尽な目にあう家族の物語だ。しかし映画全体は、僕から見ると、不思議な温かさに包まれている。
加えて、1970年代のブラジルの風景は、まるで当時撮られた記録映像のような質感で、海風や街の色彩、人々の仕草までが半世紀前の空気を運んできてくれると感じた。
本作は、遠い国の家族の物語であると同時に、私自身の子供時代の記憶ともつながる物語だった。
家族の結びつきの形とその変遷を見つめ直すきっかけをくれたこと、それがこの静かで美しい映画からの贈り物だと思う。
なんだかずっと息苦しい
『JUNK END』とシネマカリテの悲報に、『火の華』公開決定の朗報と個人的に感情が忙しい中、なかなかシリアスな作品。
リオデジャネイロのカラッとしたビーチ近くに住む家族の、和気藹々と楽しい雰囲気の序盤から一変、父ルーベンスが連行されてから一気に物々しい空気が押し寄せる。
今ならSNSで自ら発信する事はできても、時は1971年。
何度も同じ質問をして精神を削っていく尋問に、観ているこっちも削られる。
マスコミすら尻込みする軍事政権下で、どうすることもできない中、なんとか手がかりを模索するエウニセの強さといったら。
下の子2人が無邪気なのが、幸いでもありキツくもあり。
回想録をもとにしているから、フィクション作品のような鮮やかな救出劇や、スカッと勧善懲悪とはいかないのが悔しいところ。
全体的に良かったと思うけど、25年後と2014年のパートが、それぞれもう少し短くても良かったかなと感じのがちょっと残念。
家族が生きていく物語だった
ポルトガル語の原題は、Ainda estou aqui (= I'm still here).
「私はまだここにいる」
原作も同じタイトルで、マルセロ・ルーベンス・パイヴァ著。
2015年刊。
著者は、1971年に拉致され消息を絶ったルーベンス・パイヴァの息子さん
(姉3人、妹1人の5人きょうだい)
2011年に就任したジルマ・ルセフ大統領が創始した「National Truth Commission」のおかげで
過去の軍事政権の記録へアクセスできるようになったことによって、
この本が書けるようになったという。
同時に、マルセロの母、この映画の主役であるエウニセが
認知症を発症して記憶をなくし始めたのが、
記録を残そうと思ったきっかけだという。
邦訳はおろか、英訳も見つからないのが残念。
* * *
ラテンアメリカは一時期、軍事独裁のオンパレードだった。
1954~85:パラグアイ、
1964~85:ブラジル、
1971~82:ボリビア、
1973~84:ウルグアイ、
1973~90:チリ、
1976~83:アルゼンチン。
重なる時期は、米国でキッシンジャーが「活躍」した時代。
米国が「支援」する「コンドル作戦」なんてのもあった。
従わざる者、と見做された者、数万あるいは数十万が、
残虐に殺された。
映画でも「ローマ法王になる日まで」は、
アルゼンチンの「汚い戦争」を――軍事独裁政権の残虐を――リアルに描いていた。
だからこの映画を観るにあたっては、相当な覚悟が必要だろう、
と思って臨んだ。
けれど、趣は違っていた。
むしろ、家族が生きていく物語だった。
* * *
最初の30~40分、
背景に軍部の姿がありつつも、
家族の和気藹々が描かれる。
次の30分ほどで、場面は一変。
短銃をもった男数人がやって来て、
マルセロの父であり、エウニセの夫である
土木技師ルーベンスの出頭を「要請」する。
ルーベンスは以前、下院議員だったのだが、
1964年の軍事クーデター後に「罷免」されている。
そもそも相手は自分たちの身分を明らかにしないし、
連行先も明かさない。
そしてルーベンス連行後もパイヴァ家に居座り、監視を続ける。
挙げ句、数日後には、
エウニセと次女エリアナまで、取り調べのために連行され、
エウニセは幾日も拘留され、執拗に尋問される。
床には血痕、別室からは悲鳴。
夫の消息は杳として分からず。
そういう中でエウニセの心は、
戸惑いと恐怖から、憤りと決意へ、
徐々に変わっていく……
* * *
最も残酷なのは、
ルーベンスを逮捕したことを、政府が認めないことだった。
何日経っても何か月経っても、
友人の弁護士が法的手続きをとって捜索を依頼しても、
政府は知らぬ存ぜぬを決め込む。
のこされた家族は、気持ちの切り替えようもない。
だから救いは、1996年まで訪れなかった。
「政府には今後の課題が山積している中、過去を振り返っている余裕はないんじゃないですか」
とインタビュアーに質問されて、エウニセはこう答える。
「過去の償いをしなければ、再び同じ過ちを犯します」
さらに最終的な救いは、
2014年まで待たざるを得なかった。
薄れゆく意識の中で、エウニセは何を思っただろうか。
質問に答えれば帰れる?"彼ら"を怒らせるな
笑って!軍事政権の犯罪、国家の横暴と愛の強さ・力。ウォルター・サレス監督の力強い語り口に、強く・逞しく(子供たちの為にもそうならざるを得ない)・それら総じて如何なる必死さも本当の意味で美しく作品を引っ張る主演フェルナンダ・トーレスの名演によって、非常に求心力のあるドラマに仕上がっている。
この家族には欠かせないお決まりの家族写真や、劇中何度かある車中ショットが、一種の差異を伴う反復・イメージングシステムのように機能していた。また、こういう歴史ドラマには欠かせない構成ではあるものの、個人的には作中後半で一気に時が経つのが少しハマらないこともあり、本作でもやはりそれまでのパートと比べると緊張の糸が切れたりする感もあったけど、それでも実在の人物の生涯への最大限のリスペクトとテーマ性の打ち出しとして必然性があった。静かなエンディングがまた沁み入る…。
法が統治する民主主義国家あるいは時代の流れとしては、今となっては信じられない出来事であり、決して許すことはできない。ただ、報復を恐れて誰も本当のことを語りたがらないそのあまりに残酷な暴政・暴力の時代に奪われた無数の命と、本当の意味では決して屈せず抵抗した名もなき人々がいたことを、今を生きる私たちは忘れてはいけない。今の時代でも民衆が選挙など権利を放棄し、政治を監視することを怠ったら、知らず知らずの内に民主主義が失われかねず、また民族間の対立を政治のために煽る世の中では、なおも一種の切実なリアリティをもって迫ってくる。
P.S. ほとんど描かれなかった弁護士時代の闘いについても、もっと見てみたかったけど、そこは作品としての取捨選択なのが致し方ない。
最近のリバイバル上映ブームに乗っかってウォルター・サレス監督『セントラル・ステーション』ももっと観やすくならないかな。
アカデミー というより国連
アカデミー国際長編映画賞
観客はそこそこのツウばかり。見事にそれに応えてた
『軍事政権 言論弾圧はいけない』ましてや逮捕状 令状もなく 制服も着てない奴 が勝手に拘束するなよ💢
➕ブラジル🇧🇷70年代 人間模様
アカデミー賞一生に一年くらい 制覇したかった 日本未公開みたいの除いて本作で直近のアカデミー賞🏆ほぼ全部見たこととなる。
映画の知的ファンには満足作🈵 恐竜🦕に歓声あげるような人には向かないカモ。
でも映画のドシロウトの俺には 最後現実的すぎて 説教くさかった。
線香臭いともいう NHKくさいともいう。
でも人間模様の優等生映画 ブラジル🇧🇷の海岸の生活 家族生活が 美しい
懐かしい1970代も良かった。雰囲気が出てた。
若干長いが それ程長さは感じない。
ツウの真面目映画ファンに是非。
俺も目を👀あけて アカデミー長編外国映画賞🏆とは何か❓をしかと確認した。
一応平均点の満足。何かユニセフというかUNというか 正義の国連🇺🇳的
有料パンフは 文字間が多くて読みやすいけど その人による
リオディジャネイロのビーチ、サンパウロ引越し
主人公の老人期 壮年までを 実の母娘が演じ分け
お菓子 とか色々あるぞ でも人による。
まあお盆直前3連休なので 遠征しました。
家族の偉大さと強さ
姉妹4人+末っ子の弟
民主政治がいかに尊いものか
死よりも辛いかもしれない不在
軍事政権下のブラジルで起きた強制拘束による失踪者の家族のその後30年を追った、実話に基づく作品です。
裕福な一家の主の突然の不在。
家族を襲うのは心の痛みだけでなく、経済的な困窮だったのが死と不在の違いを、後者が秘めた打撃をまざまざと提示します。
赤狩り旋風がブラジルだけでなく世界中を席巻した時代。様々な国の映像で「行方不明」者たちの足取りを観てきました。
その中でも本作はホウ・シャオシェンの悲情城市と並ぶ見事さだと感じました。
とりわけ、真実を知った妻の勇敢な生き様は多くの人を勇気づけます。けれどどれ程の偉業を成し遂げようとも人生は余りに短く、人は老いてゆくという残酷な真理とともに。
クラシックなファッションも堪能しつつ、全くその長さを感じさせない2時間半でした。
ビーチとスフレ、そしてアイス
1970年代軍事政権下のリオデジャネイロで、政府に連行された元議員の夫の釈放を待つ妻と子供たちをみせる話。
政権に批判的で罷免されて亡命した過去を持つ元議員ルーベンス・パイヴァが呼び出され、そして程なく妻と娘も連行されて…という話しだけれど、とりあえずことが起こるまで30分超。
そしてことが起こり、妻が色々動いているのはわかるけれど、波があまりなく遅々として話しが進まないイメージ…まあ、事実なかなか進展しなかったんだろうけれど、映画として非常にテンポが悪い。
司法制度がなんちゃらかんちゃら言っていたけれど、軍事政権下ではまともに機能しないのはある意味当然ですよね。
特定の人物のことは全然知らないけれど、当時のブラジルの情勢や失踪者云々は観賞前から知識としてはあったから、なんだか今更感があったし、この作品も半分政治活動的なものなのかなと感じてしまった。
納得の傑作
アカデミー国際長編映画賞も納得の傑作!
平和な生活の中で抱くちょっとした「違和感」から、突然の夫の連行。理由もどこに連れて行かれのかもいつ帰るのかも知らされず、自宅には男たちが居座る。
自分たちも連行されお互いの様子も教えられない。家に戻っても幼い子供たちには言うことも出来ない。そのうち連行したことすら否定する。夫の車は返還されたのに。
韓国映画やナチ映画を参照するまでもなく、戦前の日本の特高も含め、独裁政権のやることはいつも同じだ。
自分たちに都合の悪いことを語らせないようにしようとし、それがかなわないなら消す。そしてそれをすべて否定する。
特に説明も無く妻の視点で語られることで、それがどれほどの恐怖なのか、人権の蹂躙なのかが痛みをもって伝わってくる。
リオを引き払うときの無力感。だからこそのその後の決意と活動だと思うと複雑な思いも抱いてしまう。
これが実話だというのだから酷い。酷いし凄い。
全日本人が観て独裁政権化に備えるべきだと思いますね。
「優しく美しい妻」から「強い母」へ
海岸の陽光と子供達の笑顔
1970年、軍事政権下のブラジルの話
冒頭のビーチで遊ぶ子供達の笑顔が眩しすぎて
子供って大人が隠していることもちゃんと読み取る
がらんとした家を哀しい目で見つめる末娘
晩年エウニセが認知症で扱いづらかったのは
怒りや哀しみ、いろんな気持ちに蓋をして歯を食いしばって生きてきたから
その蓋がはずれたんだと思う
音楽もとても良かった
軍事政権
最近見たボサノバのアニメと似たような話、そしてちょっと前だけどコロンビアの公衆衛生の博士、子沢山ファミリー描いた「あなたと過ごした日に」とも作風が被っているような気がした 南米の当時の事情知らなかったらびっくり、何やってんのこの人達?ってなると思う
70年代の古いフィルムみたいな感じや何かと家族写真撮るのが和やか良い雰囲気だった 5人もお子さん、お手伝いさんとても裕福そうなお家 多分おとんはすぐに...違いないよとは思ったけど、ハッキリしないだけに僅かな希望を持ち続けるのも無理はないかな
インテリ富裕層なお家なだけにその後の母の成り行きもやはり普通とは違っていた
ある「小道具演出」に思わず落涙…
第97回アカデミー賞国際長編映画賞受賞を始め、数々の映画祭・映画賞で高い評価を受けた本作。私はいつもの如く、出来るだけ前情報を避けて鑑賞に至りましたが、この作品で扱われる「事件」について、ある程度は知ってから観れば良かったと思うくらい、劇中で説明されることはそれほど多くありません。(Wikipedia英語版『Rubens Paiva』の項目が参考になります)
舞台は1970年のリオデジャネイロから始まります。若者たちは欧米から届く最新の文化や流行に刺激を受け、活気があって大変に躍動的です。ところがその一方、当時のブラジルは軍事政権下であり、見上げればヘリコプター、公道には軍車両が時折見受けられ、平静時にも拘らず威圧感が拭えません。
なお、本作の主人公・エウニセを演じたのはフェルナンダ・トーレス。カンヌ国際映画祭女優賞の受賞経験もある実力派で、その演技力の高さは言うまでもありませんが、それにも増して印象に残るのは彼女の「目力」。それは「エウニセの意志の強さ」を際立たせて脳裏に焼き付き、気が付けば彼女の演技に支配されてしまいます。
また、「事件」の背景にある問題提起をしっかり訴えつつ、パイヴァ夫妻と子供たち(一男四女)の愛に溢れる「ファミリーの絆」が感じるこのストーリーは、パイヴァ家長男・マルセロ・ルーベンス・パイヴァ(小説家、劇作家、脚本家、ジャーナリスト)の自伝が原作であると知り、「事件」に対するアプローチとそ距離感について、より納得度が高まりました。
そして更に、本作に対して感情移入を助長させる重要な小道具2つ。
まずは、カメラやビデオに使われる「フィルム」。本作は3つの時代で語られる3幕構成となっていますが、物語り中に生じる距離や時間を縮めるツールとして写真や映像が多用されます。(ちなみに、本作のポスターアートやサムネイルで使われるシーンも、1幕目の冒頭において一家揃って訪れた海水浴での「集合写真の一部」)劇中、度々にある撮影機会とその時の状況、時間を経る毎の変化が一見して伝わって言葉が要りません。ただその反面、気になったのは3幕目に交わされる家族の会話シーン。デジタル化によって「データ」と化した写真について「とってつけた取って付けたようなセリフ」の数々は、急に下手くそに見えて苦笑い。。
そしてもう一つ、これは好きなシーンであるため若干ボカしますが、四女エリアナの「あれ」。1幕目、父がそれを密かに回収し、1幕目終盤で母からそれを渡され、2幕目に兄マルセロとの回想で「その時に確信した」と話すエリアナ。その当時は殆どの事を知らされることがなかった年少組の兄妹の会話と、父娘を繋ぐこの「小道具演出」に思わず落涙しそうになりました。
聞きなれないポルトガル語と、地味な作品性に正直1幕目途中頃は眠気も感じましたが、徐々に明らかになる事実と、それに立ち向かっていくエウニセと子供たちに引っ張られていつしか夢中になります。高い評価も納得な秀作だと思います。
家族写真
軍事独裁化のブラジルでも母エウニセの家族への想いに共感
映画を観るとき、ハリウッドだけでなく各国の映画を観るようにしている。その国の
社会や文化を知る上での格好のテキストにもなる。
今回はブラジル。ブラジルのイメージはサッカー、ビーチ、サンバ、音楽だがブラジルが軍事独裁化であることは全く知らなかった。今回の作品は軍事独裁政治のブラジル。当時のブラジル社会や文化を知ることもできた。
作品前半は当時のブラジル文化や社会を知ることができたが、後半はスイス大使誘拐事件を境にブラジルの空気も一変。夫のルーベンスも逮捕される。その中、作品全体を含めルーベンスの妻エウニセの夫や子どもたちを必死に守る姿に胸を打たれたし、共感した。
家族の大切さを改めて再認識した。実話であることにも驚きだし、作品も素晴らしかった。
アカデミー賞国際長編映画賞受賞も納得できる。見事。
全126件中、101~120件目を表示