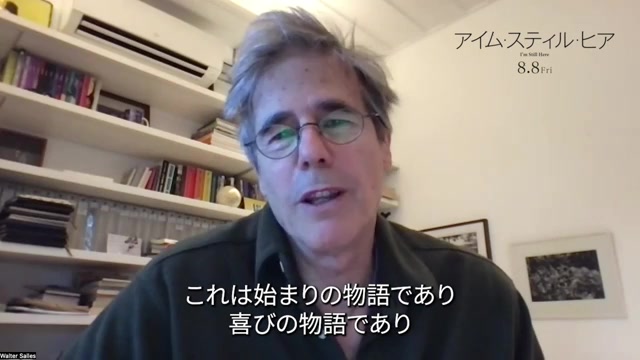アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全126件中、41~60件目を表示
明るい色調と暗い色調のギャップが緊迫感をうむ
お盆休みの13日、TOHOシネマズシャンテで見たのですが、ほぼ満席になっているのに少々驚きました。
なにせメジャーな映画ではなく、ブラジル映画にこんなにお客さんが見にくる、2025年アカデミー賞国際長編映画賞受賞作品に敏感に反応する、やはり首都圏のひとは文化度が高いと再度思いました。
この映画よかったです。多くの人に見てもらいたい作品です。
【映画批評】
家族七人が仲睦まじく過ごしている日常生活と父親が突然連行されてから、そして母がリオからサンパウロに転居すると言った以降、映画は三つの色調から成り立っている。
夫婦仲がよく子供五人も両親に愛し愛され穏やかな日常が目に焼き付く。この明るい色調の日常生活があっというまに脅かされる。
軍事独裁政権下、不穏な事件が相次ぎ、日常生活の明るい色調とは真逆の暗い色調と不気味な音が支配していく。車が止まる音、扉の開閉の音に極度に敏感になる。突然父親が誰の指示でどんな用件かわからず連行されてしまう。妻エウニセ、次女のエリアナも拘束され尋問を受けることになる。エウニセとエリアナが視覚を奪われ連行されたことで、ここがどこかわからないことと、尋問を受ける部屋で、牢獄の密室で聞こえる悲鳴、慟哭、叫び。また夫が消息不明であることから、エウニセが抱える不安、これらのシーンで恐ろしいまでの緊迫感につつまれる。不気味な音と暗い色調が恐怖をうみだしている。
映像化されていないが、母と姉が連行されたとき家には四人の子供しかいない。エリアナは一日で帰ってきたが母は帰らない。この時の子供たちの不安さも緊迫感を高めている。この映画は映像だけで語ってはいない。
夫が消息不明ではあるが家族六人生活をしなければならない。エウニセは仲間から夫がすでに死亡していることを聞き、サンパウロに転居し大学に戻り法学を履修し弁護士になる。弁護士は法を盾に取り闘うことができる。エウニセは消息不明者をかかえる家族らの代表となり声をあげ続けていく。
夫が消息不明になってから二十五年後、政府は死亡証明書を発行した。これを境に平穏な日常生活が描写される。闇と闘い、国と闘い、二十五年のときをへてつかみ取った昔の日常生活。また明るい色調が戻ってきた。
闘い、痴呆になり、車椅子に座り、年老いたエウニセ。子供と孫に囲まれ団欒をすごす目に力はないが、彼女が成し遂げたことはこの家族団欒に凝縮されている。夫のために闘い、子供のために生きることが彼女の人生だったのだ。
闇と光が拮抗する時代と場所を描く
本年アカデミー賞の国際長編映画賞を受賞した作品である。他のノミネート作が「ガール・ウィズ・ニードル」「エミリア・ペレス」「聖なるイチジクの種」「Flow」と秀作揃いの中で堂々たる受賞だと思う。昔と違って国際長編映画賞と作品賞の同時受賞もできる。日本公開はかなり遅く今頃やっと実見したが、作品賞を受賞してもおかしくない出来だった。
ブラジルを軍事政権が支配していた1971年。軍ないしはその影響下にあった政府組織によって拉致され拷問の上殺害されたルーベンス・パイヴァ氏とその家族の物語である。
ルーベンスとエウニセの夫婦には四女一男の子供たちがいる(他にお手伝いさんと犬が一匹)だからこれは何十年にもわたる家族の物語であると位置づける解説もある。長男であるマルセロ・パイヴァ氏の著作が原作であり「家族」という視点が入ってくるのは確かである。ただ、物語の9割以上はルーベンスの拉致直後の時点に割かれ、家族の25年後の姿とさらに20年後の姿は短い尺で加えられているのに過ぎない。だから、本作は、家族の誰よりも、夫を拐われ自分も一時は監禁されて危ない目にあった妻のエウニセがまだ幼い子供たちを抱えながらも戦うことを決意するまでの経緯が中心になっている。
映画の冒頭、リオデジャネイロの海岸に住んでいるパイヴァ一家の日常を描く。裕福で友人たちにも恵まれ子供たちも明るく元気な幸せな家族である。それだけにやがて姿を現す闇の勢力のもたらす衝撃度は大きい。ルーベンスを連行する者たちは武装はしているものの制服姿ではなく一見、町のチンピラにしか見えない。リーダーは名前だけは名乗るものの所属等は明らかにせず、行動の目的も明かさない。ルーベンスの連行後にも家に居座り、妻や娘も一時的に連行する。彼女たちは頭巾をかぶせられて何処かの施設に連れ込まれ意図が不明な尋問を受ける。彼らが法的に不当であることを十分に承知しながら行動しているのは明らかであり徹頭徹尾、不気味で非人間的である。どうしようもない闇の深さが感じられる。
つまりこの映画は光と闇の対立と、その狭間にはまり込んでしまった人間の運命を描いている。もちろんブラジルの旧軍事政権に対する告発、遺族への補償をせよという主張はあるのだけど、これはどこにでも起こり得る、たぶん、今も世界のどこかで進行している人間社会の様相についての精緻な考察であるといってもよいかもしれない。
犬と同じように粗末に扱われた主の家族の場面対比
幸福そうな海辺での家族の姿から始まる。海中から顔を出すエウニセ、子どもたちそれぞれサッカーやビーチバレーボールに興じ、迷い込んだ犬を娘の一人が弟のマルセロに託し、マルセロは家で飼いたいとエウニセやルーベンスにせがみ、二人は最初は断ろうとするが、押し切られる。車に乗って移動中に、娘の一人がムービーカメラを動作しながら、ありきたりの家族や風景を録画していくが、途中のトンネル内で取り調べを受けてから、運命が文字通り暗転していく。
ルーベンスの連行の後、エウニセとエリアナも連行され、女性にもかかわらず、執拗に連日取り調べを受け、帰してもらえない。家に残された年少の子どもたちは、もちろん不安だったろう。母姉の連行前だったかもしれないが、マルセロは健気に監視役の男を相手に、父と同様にゲームで気を引いていた。エリアナが先に帰されたようで、エウニセが戻り、エリアナも安心したのも束の間、年少の子どもたちの不安を慮ったエウニセの心遣いにもかかわらず、エリアナ、そしてロンドンで真実を知った長女のヴェロカとの溝が生じてしまった。
ある日、家の前の道でけたたましい音がして、エウニセが出てみると、飼っていた犬が車に轢き殺されていた。監視役の男たちの仕業らしい。この頃、ルーベンスも殺害されていたのではなかろうか。女中に払う給料の金を得るためにルーベンスの銀行口座から引き出そうとして認められず、外貨両替で凌ぎ、後日ようやく不要な土地の買い取りが認められた。ヴェロカが帰国し、リオデジャネイロの家を引き払って、サンパウロに移ることになり、冒頭場面のように海辺で楽しむことになり、エウニセがまた海中から顔を出し、子どもたちも遊ぶが、ルーベンスの姿はない。
エウニセは大学に戻ると言っていて、研究職かと思ったが、25年後の職は弁護士で、学生に戻ってからということだったようだ。マルセロは電動車いす利用者になっていた。ルーベンスの死亡証明書が発行され、エウニセは、区切りをつけるとともに、国による補償責任を訴えた。
さらに18年後には、子どもたちをそれぞれ家族を増やし、賑やかに集まり、エウニセは年老いて認知症であるようだが、テレビでのルーベンス他の政治犯たちの消息の放送を観て、心が動く様子だった。そしてルーベンスが健在だった頃の録画ムービーが放映され、懐かしげに見入っていた。
フィクションであれば、長い忍耐の末にルーベンスが戻ってきて、家族の幸せを噛み締めるという結末も可能だったかもしれないが、現実はこんなにも過酷で、ちょうど飼うことになった犬の運命と同様に、主が粗末に扱われたということだ。その対比の構図も良かったと思った。本当によくできた政情批判のホームドラマだった。
かなり重い家族愛の作品
思っていたのと違いました
恐いねえ。
奪われてはじめてわかる人権の尊さ
一見、民主主義国で憲法により人権が保障されている自由な国、今の日本で暮らしていて自分の人権が保障されていると日々実感しながら暮らしてる人は少ないと思う。
大半の人が自分の生きたいように生きることができる、自分の意思が権力により抑圧されてると感じてる人間は比較的少ないのではないか。
でもマイノリティの人々となると話は変わってくる。例えばLGBTの人々などは生きていくうえで様々な不自由を感じているだろう。
人は自分の人権が侵害されて初めて人権がいかに尊いかがわかる。たいていはマイノリティの人権が侵害されるため、人権侵害は他人事のようで社会ではなかなか問題視されにくい。
民主国家でない独裁国家でも国家に従っていれば安泰な生活を送れる。しかしそんな国家に逆らえば途端に人権は蹂躙され幸せな暮らしは奪われてしまう。
ブラジルの軍事独裁政権下、韓国の朴正煕軍事独裁政権下にも似た開発独裁の下で飛躍的な経済発展を遂げてブラジル国民の生活は潤った。
そんな経済発展に酔いしれる国民の中で民主主義を否定する軍事独裁政権に立ち向かう人々もいた。
これはかつてブラジルでリベラル派の政治家として活動していた人間とその家族の物語。
彼は軍事独裁政権に逆らう活動家を支援していたがために秘密警察に連行され帰らぬ人となる。そして事情を知らなかったその妻も長きにわたり拘留される。彼女は自分の幸せな家族の生活が奪われ、夫を奪われたことから人権の尊さに目覚めて法科に進み弁護士となり独裁政権と戦う。
長きにわたる戦いの末に夫の死亡証明を取り付けることができた。行方知れずで生死不明の夫、少なくともこの故郷のどこかの地に眠っていることだけは明らかとなった。
このリオの海岸沿いのどこかに眠る夫の亡骸は末娘の抜けた乳歯のようにいずれその在りかがわかるだろう。
夫を奪われたことから、幸せな家庭を破壊されたことから人生をかけて残された家族を守り国家権力と戦った主人公の女性の物語は現代にも通ずる物語だ。
本作の企画を監督が進めていたのがまさにブラジルのトランプとの異名を持つボルソナロ大統領就任の時期であり、彼はかつての軍事独裁政権を賛辞していた。
民主主義で自由の国であるはずのアメリカが独裁者トランプにより独裁国家に陥る危機になるのと同様、このブラジルもかつての独裁国家に成り下がると懸念しての本作の公開となった。
欧州でもいま極右政党の台頭により民主主義の後退が懸念される事態に。この日本もまた例外ではなく先の参院選では人権を否定する極右政党が躍進した。
日本もかつては百年前に制定された治安維持法の下での軍事独裁政権により多くの国民が拷問されて殺された。その被害者たちにはいまだ何ら補償もされておらず加害者が処罰されていないのもこのブラジルの独裁政権下の状況と同じである。
本作が世界的評価を得たのは、いま世界中で同様のことが起きようとしていることへの不安から、かつての過ちを振り返る必要性に迫られてのことであろう。
日本のかつての悪法、治安維持法を賛辞したカルト政党が今回の選挙で躍進した事実。まさに再び我々の人権が脅かされる事態に陥るかもしれない。
普通に人権を享受できていることが当たり前であると思えない時代が再び到来するかもしれない。
今現在平和と思われる生活が所詮かりそめのものであり、何かのきっかけで民主主義から独裁国家へとカードが裏返るようにたやすく転覆する危うさを感じる。そうでなくとも民主主義のこの国では信じられないような冤罪事件で人権が蹂躙される事態も起きている。
だからこそどんな時代であろうともつねに権力に対して訴えねばならない、「私はここにいる」と。けして権力の横暴により我々の人権がなきものにされてはならない。
軍事政権下のブラジルのヒリヒリするような空気感が封じ込められた美しくも重厚なドラマ
1970年のブラジル軍事政権下のリオで突然夫を連行されてしまった妻と子供達の物語。時代背景的にはスペイン産アニメ『ボサノヴァ 撃たれたピアニスト』と通底しているのですが、失踪の謎を追っていく『ボサノヴァ〜』とは違って、こちらは全く異なるアプローチで軍事政権下の過酷な現状を直接見せることを極力排除しサウンドトラックに語らせる。昭和歌謡もそうでしたが70年代はヒットソングが世相を反映していたのでその歌詞とメロディが時代を語るに任せて、その時代を生きた一つの家族は淡々と暮らし続ける。登場人物が多くを語ろうとしても主人公は遮る。残酷な描写は何もない。それがゆえにそこにある虐殺行為がくっきりと浮き上がる。この辺りは『関心領域』に近い感触はありますが、こちらは主人公はあくまでも現実と戦い続ける点が異なります。ずっしりと重い作品ですがサウンドトラックと風景がとにかく美しいのでやはりスクリーンでの鑑賞向き、70年代のリオの眩い風景の再現は見事ですし、曇天のサンパウロの日常がスクリーンに映し出されることはこの国では稀なので激しく郷愁に駆られました。
ところでもうこれ前から言うてることですがラテン系映画に英語のタイトル付けるなっちゅうねん。これは英題をカナ表記してるだけのやっつけ仕事なのでもうちょっと粋な邦題にしてたらもっとヒットしたんちゃうかなと思います。とはいえ主人公の目線だけがこれから起こることを暗示しているポスターは素晴らしいです。
母であり父になったエウニセ
上映館少なすぎる…でも、ほぼ満員。もっと上映館増やしたらええのに🤨
これが実際に起きたことというのが衝撃的でもあり独裁政権の恐ろしさを認識させられる。この映画のすごいところは、暴力的なシーンはほぼ描いていないにも関わらず背景にある軍事政権の恐怖が伝わってくるところ。
幸せな日常が描かれる前半、そして愛する夫がいなくなり苦悩する後半。幸せな日常シーンはありふれた家族の幸せをこれでもかと描き、ディアーハンターを彷彿とさせる。この前半の対比が後半でありこれから起こる悲劇を予感させる。
あの家族が崩壊せずになんとか生きてこられたのはエウニセの強さゆえやろう。悲しみや憎しみに耐え、ただただ家族を守るために動く。子どもたちも状況がわかっている子、わかっていないけれど様子がおかしいことは察している子それぞれの痛みや苦しみがある。
父のいない家族写真を笑顔で!と言う強さ。憎しみの気持ちに負けず、反骨精神を持ち理不尽に立ち向かう姿勢。心から尊敬する。母であり父になったエウニセ。あの軍事政権化でおかしいと立ち向かおうとしたパイヴァ。感性が似ている夫婦やったんやろうなあと。死亡診断書を手にし、笑顔になるシーンはやっと一区切りしたという安心感もあったのだろう。実際の写真が出てくるが、エウニセが指輪をつけ続けているところに深い愛を感じた。
この映画の原作が、事件当時幼かったマルセロが書いたものというのも感慨深かった。
みてもちろん明るくなる映画ではないし、私はしばらくあの笑顔を引きずるだろうが、歴史を知ることに意味がある。そして考えることに意味があると思いたい。
ブラジルサッカーは隠れ蓑
お気楽な国、ブラジル。日系人が苦労し頑張った国、ブラジル。垣根涼介サウダージのブラジル。コーヒーとサンバのブラジル。しかし、こう言う黒歴史があったとは。どの国にも権力による暗黒政治があるのはある意味普遍的なことだが、本作でブラジルにも民主化前に、こう言う時代があったとは。勉強になりました。
説明があまりないので
いつもの映画館で夏休みに
チラシで興味がわいた
アカデミーの外国語映画賞だったとか
あと主演女優賞もどこかの映画祭で
で おおむね予想通りなのだけど
説明があまりないので
ん というところが何か所か
突然いなくなう子ども 心配するのだが
次のシーンでは戻っていてストーリーに関係ないような
銀行のシークエンスもいまひとつ理解が及ばず
子どもが5人なので混乱もして
後に息子がこうなるのかというエピソード 印象深い
上映終了後 廊下に張り出してあった雑誌記事の切り抜き
監督のインタビューを読んで あぁなるほどと
そもそも息子との邂逅だったようだ
あと主人公の最後の老け役は母親だと
てっきり本人の特殊メイクかと それをコミで主演賞かと
Torture
アカデミー賞2025の作品の中では最後の上陸かな?ってくらい結構待たされましたが無事鑑賞。
かなーり静かな作品で、父親が突然攫われた一家というのを描いているんですが、いかんせん台詞量が少ないので心情を察するのが難しくて苦しいであろう作品のはずなのにシャレオツ映画に思えてしまいました。
序盤の普通な日常を過ごす一家は美しく、ビーチでやんややんややったり、犬を飼ってみたいと言い出してみたり、家族間での何気ない会話だったり、日常がぶっ壊れる直前とはいえこの日常がずっと続けば良いのになと思えるくらいには良かったです。
ビーチのちゃんねー達がめっちゃ綺麗で、ビーチのシーンでドキッとさせられたのは久しぶりでした。
そこから薬の取り締まりで娘が検問されて不穏な雰囲気が漂いはじめたかと思ったら父親が誘拐されてしまい、行方も分からず、そのまま家族も尋問を受けるという非日常に様変わりしてしまうというところから本筋が始まるんですが、それまでの前振りがちと長いのもあって少しダレてしまったかなぁという印象です。
もちろん、夫を助けるために奔走する奥さんの姿はカッコいいですし、リアルな尋問の様子もスリルがあるのですが、どうしても堅苦しい雰囲気は抜けず、映画というよりかはドキュメンタリーに近いように思えてしまい映画としてはそこまで楽しめなかったです。
心情描写を読み取って行間を埋めるってのを頭の中でやりながら観る作品だとは思うのですが、行間が多すぎて考えが繋がらなかったのもなんだかなぁって感じです。
全体的に音楽はめちゃめちゃカッコよかったです。
プレイリストとてもイカしています。
レトロな絵作りもとても良かったですし、いかんせん内容だけ合わんかったなぁって感じです。
相性の問題であまり乗れずでしたが、合う人には合う作品だと思いますし、ずっしりとくる作品なので、また見直す機会があればなと思いました。
鑑賞日 8/15
鑑賞時間 17:25〜19:45
自ら車を運転して出頭したルーベンスは、そのまま帰ってこなかった。
1971年1月(夏)、軍事政権下のブラジル、かつては下院議員を務め、リオで建築業を営んでいたルーベンス・パイヴァの拘束と行方不明について、その妻エウニセが、どのように行動したのかを描いた、長男マルセロの回顧録に基づく感動作。
その日、ルーベンスは、私服で銃を保持した秘密諜報機関と思われる人物の訪問を受け、自分の車を運転して当局に出頭する。ルーベンスには、水面下での政治亡命者との付き合いがあったようだ。翌朝には、妻エウニセも拘束され、情報の提供を求められる。服を替えることもできないエウニセの独房での拘束と尋問は、12日間に及んだが、ルーベンスの行方は全く不明だった。エウニセは、ルーベンスの生還だけでなく真実を明らかにすることを求めた。そのような活動には危険が伴い、家族間の軋轢もあったろう。実際、この家族は、軍事政権が続いているあいだ、ずっと監視下に置かれていた。しかし、この映画の冒頭でのエピソードが活きてくる。いくら経済的に恵まれているとはいえ、エネルギーに満ち溢れた家族だった。
ルーベンスの生還を待つエウニセは、購入していた土地を売り、邸宅も貸して、お金を作ると、生活費の高いリオからサンパウロの実家に戻り、子供たちを育てながら、大学に復学して弁護士の資格を取り、社会運動に従事した。
25年後の96年、エウニセの活動の結果として、はじめてルーベンスに関する公的な文書が公開される。その時、エウニセを囲んでいたジャーナリストから問われて彼女が返した言葉が、この映画の白眉;(軍事政権が85年に終了した以上)過去の事件を振り返るよりも(今、エウニセが取り組んでいるような)優先すべき事柄がたくさんあるのではないか、との記者の問いかけに対し、彼女は「過去の過ちを検証しなければ、また同じことを繰り返すことになる」と訴えた。実際、軍事政権下で捉えられて帰ってこなかった人たちは2万人を越えたと言う。彼女は、被害者家族への補償を求めたのだ。
大変、驚いたこと、96年の時67歳だったと思われるエウニセは、認知症の症状を示していた。ここで映画は終わりにして、あとは、写真とテロップを示すだけでも良かったのではないかと思ったが、私の言い過ぎか?
南米の歴史に学ぶ、強くて硬派な作品
『アイム・スティル・ヒア』は、そのタイトルのとおり、静かな闘志で連帯し、決して暴力に屈しない、自分のしなければならないことを全うする主人公とその家族を描いた、強くて硬派な作品でした。
日本だと家族ものの側面でセンチメンタルになってしまう場合もあると思いますが、そこはラテンアメリカの持つ明るさや強さを打ち出した、そういう独特な味わいのある、優れた作品でした。
個人的には、80年代に劇場で見て衝撃を受けた『サンチャゴに雨が降る』や『ナイト・オブ・ペンシルズ』といった、やはり南米の圧政を描いた作品を鮮やかに思い出しました。
1970〜80年代の南米は悲劇と激動の歴史があります。
エヴァ・ペロンの時代の後に到来する、1970年くらいからの一時代は、、「汚い戦争」と言われていたアルゼンチンの暗黒時代です。
(この「汚い戦争」を描いたのが『ナイト・オブ・ペンシルズ』という映画です)
チリも、ピノチェト政権下での民衆がこれでもかと激しい弾圧を受けていた時代です。
ブラジルはチリやアルゼンチンよりはマシだったようですが、70年代〜80年代にかけては軍事政権下での言論統制あったようです。
この映画で見る、主人公の夫が突然軍部に逮捕され二度と会えなくなり、自身も12日間拘留・尋問される場面は、激しい暴力少なめでも本当に恐ろしく描かれていて、「何をされるかわからない」恐怖に戦慄します。
その恐怖を乗り越えて、最愛の夫の最期を確かめようとする、権力の横暴に最後まで立ち向かおうとする、主人公の強さに胸を打たれます。
一つだけ注文をつけるなら、前半の家族の楽しい時間を描く部分が少し冗長で、ここはもう少しコンパクトにして、全体を2時間弱くらいにしても良かったのではないかと。
つくづく思うことですが、どこの国でも、軍隊が力を持つと民への抑圧や暴力が避けられず、悲しい歴史が作られてしまいます(日本の戦時中もそうだったように)。
歴史に学ぶことを忘れずにいる必要があります。
恥ずかしながらブラジルの軍事独裁政権については無知だったのでこの話...
タイトルなし
実話ということもあり、悲しかった。5人子どもがいる大家族とか日本ではもうレア。最後に実物写真が出てくるが、元政治家の父親はそっくり。母親は実物のほうがもう少し美人で穏やかな感。でも女優はうまかった。
子どもたちの世界を守る気丈な母親。
いつ父が逮捕されたと分かったか、後に子どもたちは話し合う。家を移ったとき、父の服を売ったとき。
原作となった母の手記には、家の思い出が書かれていたのだろう。
本当に仲のいい素敵な家族だった。ユーモアと知性があった。そして時代の空気。まだケータイの時代ではないし、レコードである。音楽と8ミリがある。親も子も左翼の世代。
出来事は歴史のトラウマだけれど、この意味でその悲しみを乗り越えていく家族は明るく、特に母は力強い。
「コーヒー好き」
ある日突然
前情報もブラジルの歴史もほとんどないまま観て。
ある日突然連行され、てっきり結末迄で戻ってきてくれるのかと思いきや、25年後という残酷。。。
マルセルの事故もだが、淡々と酷い現実。
戦争状態になくても、軍事独裁とか、ほとんどの人には良いことなんか無い。
陽気な国という印象だけど、軍属だと違うんかね、、
戦いなんてしないで気楽にみんなが暮らせるようになればいいのに。
歴史上の事実にびっくりするけど...
今年度のアカデミー国際長編映画賞受賞作品。1970年 ブラジル軍事政権下で起こった民間人ルーベンス・パイヴァの強制逮捕による失踪事件と、彼の行方を追った妻 エウニセ・パイヴァの半生を描いています。原作は彼らの5人の子供の末子 マヌエル・パイヴァによるノンフィクション。
ブラジルにそんな軍圧の厳しい時代があったことすら知らなかったのですが、この作品で描かれていたようなことが、現実として起きていたことにとにかく驚かされます。
一方で物語の展開は、予想していたようなものとは違いました。事件をきっかけに、エウニセは家族の生活も自身の生き方もがらっと変わるのですが、行方不明の夫の捜索にどのような行動を取ったのかはあまり描かれません。
作品の終盤では事件から25年後、さらに18年後の描写があります。物語を締めくくるには必要なパートではありますが、この部分への展開はやや唐突感があり、全体の流れからすると異質に感じました。むしろこの間に何があったのかに、聴衆は興味を持つかなと思いました。
アカデミー主演女優賞にノミネートされたエウニセ役のフェルナンダ・トーレスさん。晩年のエウニセを演じたフェルナンダ・モンテネグロさんはトーレスさんの実母とのことでした。鑑賞中はずいぶんそっくりな役者さんを当てたな、と感心しましたがそういうことだったのですね。
全126件中、41~60件目を表示