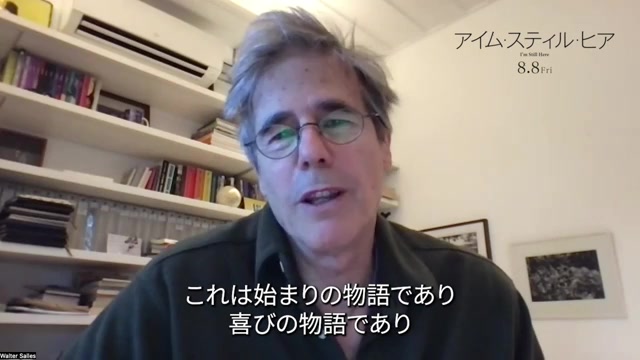「母の底力」アイム・スティル・ヒア かばこさんの映画レビュー(感想・評価)
母の底力
市民の幸せな生活を一瞬にして崩壊させる独裁国家の恐ろしさをまざまざと感じた。
「強制失踪」という言葉を初めて聞いた。
政府が逮捕を認めなければ、たとえ死んでいたとしても政府には関係ないこと、と責任逃れができる。残された家族は愛する人が生死も含めてどうなっているのか不明な苦しみのほかに、公式には「失踪」状態なので、家族がその人名義の預貯金を下ろすことができないなど、日常生活に行き詰る事態にも陥ってしまう。
ある時突然、家族が連行されてそのまま帰らない、という悲劇は、軍事独裁政権下ではよく聞く話だが、この映画では直面した家族のリアルがわかる。
20年後の次女と長男が、「いつパパが戻らないことを知ったか」と話し合うところで、子供たちが子供なりに事態を理解していたこと、年長の姉妹が、小さい弟妹を気遣って大人の配慮をしていたことが見える。小さい長男も、パパは戻ってこないことが分かっていたが、母を気遣って何も言わず、気づかないふりをしていたよう。
原作が当時子供だった長男の著作とのことで、子供から見た「事件」が描かれている。
母の底力がスゴイ。夫を連行され、自身と次女も連行、取り調べを受けたが、一貫して賢明なふるまいで乗り切り、家族を守り、重要なことは信頼できる友人に相談しながらひとりでさっさと決断する。
夫が健在の際には、家事の大方を家政婦に任せて、スフレを焼くのが得意な典型的な裕福な家庭の専業主婦だが、窮地に陥れば冷静に状況をとらえて賢明な対応で家族を守り、先々のビジョンまで同時に考える。大学に戻って法律を学び、弁護士資格を得て人権活動に乗り出す。すでに夫の生還は諦めたが、国家の弾圧を告発し、誤りを認めさせることで夫を取り返すほうに方向転換、20年の年月をかけて、夫死亡の事実の確定をもって、国家に過ちを認めさせる。
賢く強いママ、家族を守り修羅場を乗り切り、長い年月をかけて国家に一矢。
こういう話とは思わなかった。
夫が政府に批判的な元議員で、海外のメディアを活用できる立場にいたことも、ただの蟷螂の斧にならなかった要因だろう。軍事独裁政権が、海外の(アメリカの?)メディアには手出しをしていなかったようなのは、国際社会への仲間入りを目指しての対外的な評判を気にしたか、アメリカへのおもねりかも。
エウニセたちが夫の死亡証明書を勝ち取った際のひとりのインタビュアーの、「過去の悪事を掘り起こすことよりほかにすべきことがあるのでは」に唖然とした。エウニセは、「過去を反省しないとまた同じことが起きる」と言っていたが、当事者である家族にとっては過去の話ではなく、現在進行形の悪事だ。インタビュアーの感覚がそれに思い至らない程度に他人事で、軍事政権下の圧政が過去のものと認識されているようなところが見えて、こうしてまた同じようなことが繰り返されるのだろうと感じた。
前半の、幸せな一家の生活ぶりの描写がちょっと長すぎ。
半分くらいのボリュームでよかったのでは。
かばこさん、こんにちは。コメントありがとうございます。そうですね、ママは子どものこと、夫のこと、そして家族を養う為、権力と闘う為に勉強し働くから顔つきもキリリとしてより美しくなったと私も思いました
共感有難うございます。
前半の一家の描写が長過ぎ、とは、全く同感です。
その分半分くらいにして、時代背景とか、母が弁護士資格を取って人権活動するところとか、を詳しく描いてほしかった。そうすれば、傑作になっていたかもしれない、と思いました。
いきなり老年になってしまうのは、ちょっとガッカリでした。