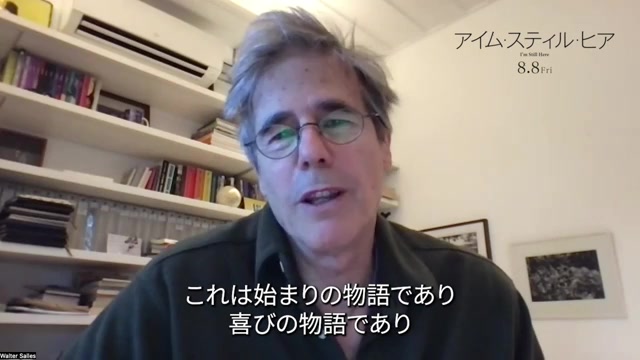「子どもには言えない「大人の事情」」アイム・スティル・ヒア KaMiさんの映画レビュー(感想・評価)
子どもには言えない「大人の事情」
1970年代初頭のブラジルが舞台とのこと。土木の専門家の父のもとで、子だくさんの家族が絵にかいたような幸せな生活を送っている。道を一つはさんだ海に出かけてビーチバレー、家ではレコードに合わせて踊り、サッカーゲームで対戦、母の手作りのスフレケーキ。
「日焼けしたらダンスの先生に叱られちゃうわ」というように、大人に褒められる遊びにも、そうでない遊びにも恵まれた女の子4人、男の子1人からなるきょうだいだ。
ところが軍事政権に父が連れ去られ、生死も不明な状態に。母と次女も捕まって監禁され、ロンドンに逃がされていた長女もそれを知ることになる。
ここで、大人(母)、若者(長女と次女)、子ども(三女、四女、長男)にチームが分かれる形になるのが興味深い。若者は母に「父は一体どうなったのか」と問い詰めるのだが、母は「その話はダメ。子どもが聞いているでしょ」とばかりに制止する。
こうして気丈な母を中心に、一家は「パパを待ち続ける、幸せな家族」を演じ続けるのだ。いや、演技でなく本気かもしれない。政権の不当性を訴えるための記事で、カメラマンに「深刻そうな顔をして」と言われても、みんな笑顔で写真に納まる。
やがて時は流れ、母の長年の活動が実り、政府に「父の死」を認めさせるに至る。あれっと思うのは、いつの間にか「父を待つ」ことから「事件の承認」に目標が変わっていることだ。
成長した四女と長男が「途中からお父さんが戻らないことは分かっていたよね」と話し合うシーンがあった。みんな少しずつ「大人の事情」を理解したということだろう。
全体として政治的な悲劇ではなく、一家のまとまりを描くことに全力を注いだ映画だと思う。しかしそれによって作品の重みが弱まった気がしなくもない。
一方、家族それぞれの思いをもっと知りたかったようにも思う。もしかして母だって父を疑い、恨んだ時期もあるのではないか。きょうだいも、父の死を悟るまでには多くの葛藤があったはず。
一家の正しさを訴えるためには、湿っぽい人間ドラマは余計だったということだろうか。