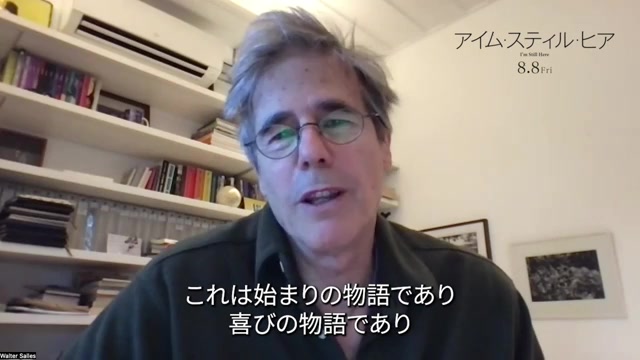「夫を、父を国家的暴力に奪われた家族の記憶を語り継ぐ志が、右傾化する世界へのカウンターになる」アイム・スティル・ヒア 高森 郁哉さんの映画レビュー(感想・評価)
夫を、父を国家的暴力に奪われた家族の記憶を語り継ぐ志が、右傾化する世界へのカウンターになる
のちにブラジルを代表する映画監督になるウォルター・サレスが十代半ばで、「アイム・スティル・ヒア」で描かれるパイヴァ一家と出会い、知識人らが出入りし政治や音楽について自由に語り合うパイヴァ家をたびたび訪れていたという。子供たち5人のうち唯一の男児であるマルセロが後年作家となり、認知症の進行が始まった老母エウニセの記憶を語り継ぐため著した回想録を出版。これに基づきサレス監督が映画化したのが本作だ。監督によると原作自体がエウニセの視点で書かれたといい、映画もおおむね彼女の視点に立つが、息子マルセロの視点も控えめながら混じっていることを意識して鑑賞すると、見える景色が少し変わるはず。
パイヴァ家の大黒柱だった元議員ルーベンスが軍事政権下で不当に連行され行方不明に。絶対に夫を取り戻すというエウニセの不屈の精神と、怒りや不安や悲しみを内に秘めつつ子供らを守り育てる強い母親としての生きざまを体現した、フェルナンダ・トーレスの抑制された熱演が映画を牽引する。この事件を取材しに来た記者とカメラマンから記事に載せる写真を撮影する前に「もっと悲しそうに」と指示されるが、にこやかに拒否し、子供たちに「笑って!」と呼びかける気丈さが胸を打つ。
息子のマルセロは、劇中では成人後に車椅子を使っている姿で描かれるが、20歳の時に湖に飛び込んだ際に脊椎を骨折し、後遺症で下半身不随になった。ラストの家族の集合写真を撮るシーンで、認知症が進んだ老エウニセ(フェルナンダ・トーレスの実母で、サレス監督の代表作「セントラル・ステーション」で主演したフェルナンダ・モンテネグロが演じる)と、マルセロが2人とも車椅子に座った相似形で並ぶ。車椅子使いになった理由は異なるが、図らずも母子で似た姿になったことが、ちょっと哀しくて切ない。
エンドクレジット前の文で、政府がルーベンス殺害を認め、2014年に軍人5人が起訴されたが、いまだに逮捕も処罰もされていないと説明する。サレス監督はインタビューで、極右が台頭している昨今だからこそ、軍政期の国家的暴力を語り継ぎ、同じ過ちを繰り返さないようにする作品の必要性が増しているという趣旨の発言をしている。それはブラジルに限った話ではないし、右傾化する今の世界だからこそ、「アイム・スティル・ヒア」のような映画がカウンター、対抗手段として有効なのだと信じたい。