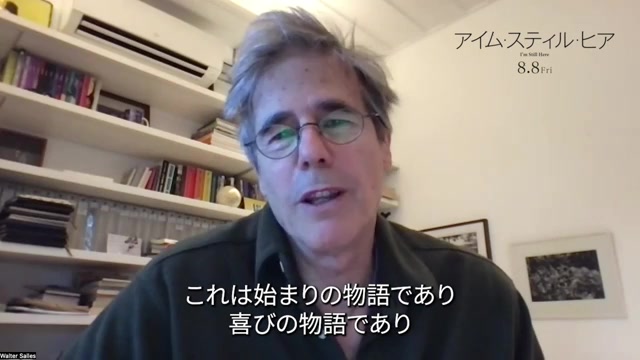「映画化された”ショック・ドクトリン”」アイム・スティル・ヒア 鶏さんの映画レビュー(感想・評価)
映画化された”ショック・ドクトリン”
今年の米国アカデミー賞で作品賞などにノミネートされ、最終的に国際長編映画賞を受賞した本作が、ついに日本公開となりました。私は事前情報をほとんど持たず、ただ「アカデミー賞候補」という程度の認識で鑑賞したのですが、最初に思い起こしたのは、10年以上前に世界的ベストセラーとなったナオミ・クラインの評論『ショック・ドクトリン ― 惨事便乗型資本主義の正体を暴く』でした。
同書は、自然災害・戦争・政変といった「惨事」の混乱を利用し、過激な新自由主義的政策が導入された歴史を丹念に解説した名著です。とりわけチリのピノチェト政権(1973~1990年)の事例が詳しく紹介されていますが、米ソ冷戦下にアメリカの軍事力や経済力を背景とした”反共政権”が強権的に国を統治した点では、本作の舞台となる1970年代初頭のブラジルも同じ状況にありました。
チリが1973年の軍事クーデターでピノチェト政権となったのに対し、ブラジルではそれより9年早い1964年、カステロ・ブランコ将軍がクーデターで政権を掌握します。以後、国営企業の民営化、外資の導入、公務員削減、福祉の切り捨てといったミルトン・フリードマンに代表されるシカゴ学派の影響を受けた新自由主義的政策を推進すると同時に、反対派を徹底的に排除しました。結果、格差拡大に伴うストライキやデモ、ゲリラ活動も起こりますが、ブランコの2代後のメディシ大統領は議員や大学教授の追放など非合法な弾圧を強行しつつ治安を回復。安定した低賃金労働と外資の取り込みで「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度成長を実現しました。(因みに1973年のオイルショックにより、「ブラジルの奇跡」は終焉を迎えます。)
この時代を背景に描かれるのが本作です。物語の中心はパイヴァ夫妻。夫ルーベンス(セルトン・メロ)は元議員で、軍事政権に追放された人物です。1971年初頭、彼が政権に拘束され、その直後に妻エウニセと娘も拘束されて取り調べを受けます。エウニセは十日余りで解放されますが、ルーベンスの行方は不明のまま。彼女はあらゆる手段で夫を探し続けるも、日々は虚しく過ぎていきます。
そもそも本作は、夫妻の長男マルセロ・ルーベンス・パイヴァ(幼少期をギレルメ・シルヴェイラが演じる)の回顧録を原作とする「事実に基づいた物語」です。『ショック・ドクトリン』で語られたような軍事政権の強権的弾圧が映像化され、スクリーンを通して直視させられたことは非常に衝撃的でした。そして弾圧に屈せず、不屈の闘志で立ち向かったエウニセの姿は辛抱強く、時に神々しくすら感じられます。最終的に彼女が夫の「死亡証明書」を笑顔で受け取るという皮肉な結末は、強烈な印象を残しました。
俳優陣では、何と言ってもエウニセを演じたフェルナンダ・トーレスが圧巻でした。夫を奪われた妻の悲しみに満ちた表情から、困難な状況下で五人の子を育て上げる母としての愛情溢れる表情まで、すべてが素晴らしい演技でした。さらに老年期のエウニセを演じたのが、彼女の実母でありブラジルを代表する大女優フェルナンダ・モンテネグロだったというのも驚きです。認知症を患った晩年のエウニセを限られた出番ながら深みをもって演じ、親子共演が見事なキャスティングの妙となっていました。
また、軍事政権側の秘密警察を思わせる人物たちも実にリアルでした。慇懃無礼かつ威圧的な態度で迫る様子は、もし自分の前に現れたらひとたまりもないと感じさせる迫真の演技でした。
そんな訳で、本作の評価は★4.6とします。