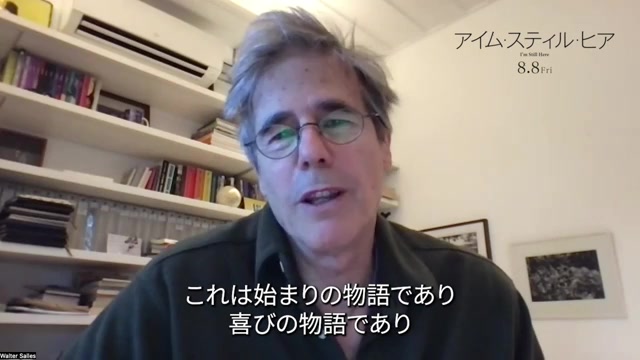「昔のブラジルの軍事政権=今の日本の司法制度」アイム・スティル・ヒア おきらくさんの映画レビュー(感想・評価)
昔のブラジルの軍事政権=今の日本の司法制度
序盤は1971年のブラジル、リオデジャネイロの海岸沿いで暮らす富裕層の家族の、笑顔の絶えない日々が描かれる。
家族構成は父、母、娘4人、息子1人、家政婦、そして犬。
しっかり者でありながら優しさも兼ね備えた両親と、無邪気で元気な子供たちの、毎日海で遊んでいるかのような楽しげな様子が印象的。
特に心に残ったのは、幼い末娘の歯が抜け、父と2人で海岸の砂浜に埋めに行くエピソード。
父親のさりげない行動から、その温かい人柄が伝わってきた。
しかし、家族の幸せな日常が描かれる一方で、テレビからはスイス大使誘拐事件をきっかけにブラジル国内の社会情勢が不安定になっている様子が繰り返し報道される。
この後この幸せな家族に降りかかる出来事を考えると、社会の不穏さに無関心でいると、いつか自分にも降りかかってくるかもしれないという、この映画からのメッセージを感じずにはいられなかった。
ある日、長女は大学の友人たちとドライブに出かける。
ところが、途中で軍の検問に引っかかり、まるで犯罪者のように乱暴なボディチェックを受ける。
長女が軍人から強いライトを当てられ、眩しそうにする場面で、隣の席に座っていた観客が光る機器を操作。
思わず「映画鑑賞マナー違反では?」と感じたが、「もしかしたら、画面の中の長女の気持ちを疑似体験させてくれたのかも」と勝手に解釈。
ちなみに、その隣の観客はその後も上映中に何度も光る機器を操作していて、逆にすごいと思った。
やがて、平穏な家族の日々は終わりを告げる。
拳銃を持った数人の男たちが家に押しかけてきた。
強盗かと思いきや、彼らは軍の関係者で、父親を事情聴取のために連行しに来たのだった。
父親が正装に着替えている間、三番目の娘が学校から帰宅。
事情を知らない娘は、帰るなり父親に小さなおねだり。
父親は快く応じる。
娘からすればいつもと変わらない優しいパパ。
しかし、父親にとって「もう二度と家族と会えないかもしれない」という想いを抱えながらの触れ合いだったと思うと、胸が締め付けられる思いがした。
父親が連行された翌日、今度は母親と次女(長女は留学中で不在)が事情聴取を受けることになる。
車に乗せられ、サイレンを鳴らしながら街中を爆走する車内で恐怖を感じていると、突然車が止まり、2人は真っ黒な袋を被せられる。
スクリーンもまた、しばらくの間、真っ暗になるという演出。
母親が取調室の椅子に座らされ、男との尋問が始まる。
男の口調は冷静沈着で、部屋の中は不気味なほど静かだが、部屋の外からは断末魔の叫びが聞こえてくる。
母親は知っていることを正直に答えるが、男は納得しない。
長時間の取り調べの後、彼女は家に帰してもらえず、手錠をかけられ、汚い独房で拘禁される。
次の日も、また次の日も、取り調べと拘禁が繰り返される様子が淡々と描かれていく。
この場面を観て、多くの人は「ブラジルの軍のやっていることは酷い」と思うだろう。
しかし、自分は一人の日本人として、これは今の日本の「人質司法」と同じなのではないかと感じた。
刑事事件で容疑者が否認や黙秘を続けると、いつまでも釈放されず勾留され続ける日本の現状。
弁護士の付き添いを認めない点もそっくり。
近年、日本では数々の冤罪事件が明るみに出ているが、その温床になっているとされるこの日本独自のシステムは、国際社会から非難され続けているにもかかわらず、行政は無視を続けている。
最近ニュースになった「大河原化工機冤罪事件」では、無実の人たちが11ヶ月間も勾留されていたという(そのうち一人は体調が悪化しても病院に連れて行ってもらえず、胃がんで死亡。酷すぎる…)。
それに比べると、本作のブラジルの軍は母親を数週間で釈放していて、良心的に思えてしまった。
母親が釈放され、帰路につこうとしたとき、彼女を監視していた男の一人が「本意ではなかった」とポツリと一言つぶやく。
散々酷い目に合わせておいて、最後にそんなことを言われても複雑な気持ちになるが、おそらくそれは本音。
彼らはあくまで上層部の指示に従っていただけ。
逆らえば自分の立場が危うくなるため、そうするしかなかったのだろう。
思い返せば、父親が連行された夜、家を監視していた軍人たちが、上司の目を盗んで子供たちと優しく接する場面があった。
もしかしたら悪い人間ではないのかも、と思わせる瞬間。
しかし、そのような人々が、命令だと平気で非人道的な行動を行ってしまう。
人間社会の恐ろしさを痛感するとともに、こうしたことをなくすには、システムそのものを作らせないことが重要だと感じた。
そう考えると、先の参院選で支持を集めた政党が、個人的に「大日本帝国憲法か?」と思わせるような憲法草案を提示していたことに、強い危機感を覚える。
母親への拷問のような勾留を観ていて、ウィシュマ・サンダマリさんのことも思い出した。
ガザで起きている虐殺もそうだが、いかなる理由があるにせよ、無抵抗の人間に対して非人道的なことを行うのはやめるべき。
しかし、世の中にはウィシュマさんの件にしろ、ガザの虐殺にしろ、それを支持する人間が少なからず存在する。
名古屋入管で亡くなったウィシュマさんに対して「詐病」発言で処分された議員が、先の選挙で当選。
日本は1970年代のブラジルの軍事政権を目指しているのだろうか。
母親が家に戻った後も父親は戻らず、家族は経済的に苦しむことになる。
今でも一部の人々から根強く支持されている「男は外で稼ぎ、女は家を守るべき」という考え方の問題点が現れていると感じた。
物語の後半は、軍事政権に対し、報道の力で抵抗していく展開。
今の日本に広がる「オールドメディア」という言葉を使って、新聞やテレビの報道を軽視する風潮に危うさを感じる。
新聞やテレビを「マスゴミ」と馬鹿にし、簡単にデマを生み出せるネットの情報は鵜呑みにする人、逆にすごいと思う。
夫のサインがないと銀行でお金をおろせない場面は、ショックでした。ヨーロッパでも大きい買い物(車とか家とか)では、夫がいないとできなかった(今はどうかよくわからない)時代があったと聞いたことを思い出しました