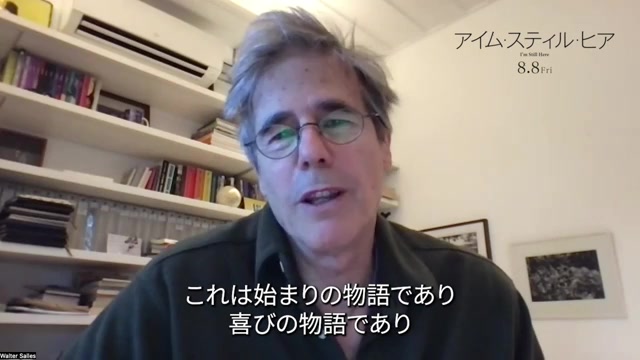「家族が生きていく物語だった」アイム・スティル・ヒア 島田庵さんの映画レビュー(感想・評価)
家族が生きていく物語だった
ポルトガル語の原題は、Ainda estou aqui (= I'm still here).
「私はまだここにいる」
原作も同じタイトルで、マルセロ・ルーベンス・パイヴァ著。
2015年刊。
著者は、1971年に拉致され消息を絶ったルーベンス・パイヴァの息子さん
(姉3人、妹1人の5人きょうだい)
2011年に就任したジルマ・ルセフ大統領が創始した「National Truth Commission」のおかげで
過去の軍事政権の記録へアクセスできるようになったことによって、
この本が書けるようになったという。
同時に、マルセロの母、この映画の主役であるエウニセが
認知症を発症して記憶をなくし始めたのが、
記録を残そうと思ったきっかけだという。
邦訳はおろか、英訳も見つからないのが残念。
* * *
ラテンアメリカは一時期、軍事独裁のオンパレードだった。
1954~85:パラグアイ、
1964~85:ブラジル、
1971~82:ボリビア、
1973~84:ウルグアイ、
1973~90:チリ、
1976~83:アルゼンチン。
重なる時期は、米国でキッシンジャーが「活躍」した時代。
米国が「支援」する「コンドル作戦」なんてのもあった。
従わざる者、と見做された者、数万あるいは数十万が、
残虐に殺された。
映画でも「ローマ法王になる日まで」は、
アルゼンチンの「汚い戦争」を――軍事独裁政権の残虐を――リアルに描いていた。
だからこの映画を観るにあたっては、相当な覚悟が必要だろう、
と思って臨んだ。
けれど、趣は違っていた。
むしろ、家族が生きていく物語だった。
* * *
最初の30~40分、
背景に軍部の姿がありつつも、
家族の和気藹々が描かれる。
次の30分ほどで、場面は一変。
短銃をもった男数人がやって来て、
マルセロの父であり、エウニセの夫である
土木技師ルーベンスの出頭を「要請」する。
ルーベンスは以前、下院議員だったのだが、
1964年の軍事クーデター後に「罷免」されている。
そもそも相手は自分たちの身分を明らかにしないし、
連行先も明かさない。
そしてルーベンス連行後もパイヴァ家に居座り、監視を続ける。
挙げ句、数日後には、
エウニセと次女エリアナまで、取り調べのために連行され、
エウニセは幾日も拘留され、執拗に尋問される。
床には血痕、別室からは悲鳴。
夫の消息は杳として分からず。
そういう中でエウニセの心は、
戸惑いと恐怖から、憤りと決意へ、
徐々に変わっていく……
* * *
最も残酷なのは、
ルーベンスを逮捕したことを、政府が認めないことだった。
何日経っても何か月経っても、
友人の弁護士が法的手続きをとって捜索を依頼しても、
政府は知らぬ存ぜぬを決め込む。
のこされた家族は、気持ちの切り替えようもない。
だから救いは、1996年まで訪れなかった。
「政府には今後の課題が山積している中、過去を振り返っている余裕はないんじゃないですか」
とインタビュアーに質問されて、エウニセはこう答える。
「過去の償いをしなければ、再び同じ過ちを犯します」
さらに最終的な救いは、
2014年まで待たざるを得なかった。
薄れゆく意識の中で、エウニセは何を思っただろうか。