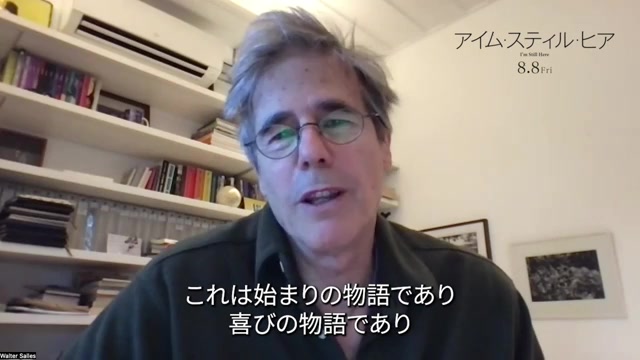「人間社会の罪深い過ちを忘れないために」アイム・スティル・ヒア ニコさんの映画レビュー(感想・評価)
人間社会の罪深い過ちを忘れないために
この物語は、家族の実体験を記したマルセロ・ルーベンス・パイヴァの回想録に基づくものだ。ウォルター・サレス監督は14歳の頃この家族と親交があり、週末毎に彼らの家を訪れていたという。序盤の明るく解放的なパイヴァ家の日常の姿は、監督の記憶に刻まれた風景でもあるのかもしれない。
主役は一家の母であるエウニセだ。夫のルーベンスが行方不明になってからの彼女の経歴には、生半可でない意志の強さを感じる。5人の子供を抱えながら、43歳で大学の法学部に再入学し司法試験に合格。弁護士としての一般的な業務の他に、先住民族の権利擁護や環境保護にも献身的に取り組んでいる。
このようなエウニセの夫失踪後の人生だけでも十分映画になりそうだが、本作ではそこはばっさりと省かれている。四半世紀の長きにわたり連れ去られ殺された事実さえ隠され、国家から存在を消し去られていたルーベンス。愛する夫を、父親を、ある日突然そのような形で奪われることの残酷さと理不尽さに焦点が当てられる。
平和なパイヴァ家の姿やルーベンスの人となりが最初に細やかに描かれたからこそ、それらが全て失われることの痛みがよく伝わってきた。
だが、エウニセは強い。夫が帰ってこず、軍関係者と思しき男たちがずかずかと家に上がり込んで居座ったのに、冷静に彼らの食事の気遣いまでして見せた。ここで取り乱せば、男たちをさらに警戒させてしまう。夫不在の中、彼女はひとりで子供たちを守らねばならないのだ。
やがて彼女も娘と共に拘束され、長期間(パンフレットによると12日間)の厳しい尋問を受ける。ようやく解放され、帰宅したエウニセは子供たちの前では再会を喜びこそすれ、不安に屈する姿を決して見せない。父親についてのネガティブな言葉は、ラジオのニュースに至るまで子供たちには触れさせまいとする。子供たちの心と、ルーベンスがいなくなる前のあの家庭の明るさを、エウニセは守りたかったのかもしれない。
気丈な振る舞いをほとんど崩さなかった彼女だが、そうせざるを得ない彼女の緊張感や苦しさもひしひしと伝わってきた。
それでも、働き手がいなくなった彼らの生活は経済的な困窮により否応なく変質してゆく。まず家政婦の給料が払えなくなり、やがて生活費も苦しくなって新居を建てようとしていた土地を売り払い、親戚のいるリオデジャネイロに転居することになる。子供たちの、恋人や友人との別れが切ない(マルセロが別れを告げた友人たちの中に、幼い日のサレス監督もいたのだろうか?)。ルーベンスがいれば起こらなかったであろう環境の変化に翻弄される彼らを見て、改めて軍の横暴に怒りを覚えた。
誰かが暴力の犠牲になる時、被害は当事者にとどまらない。本人に関わる多くの人もまた、人生が大きく変わるほどの影響を受ける。
それはあってはならないことだが、自分の身にそのような受難があった時、心まで屈することのないようにすることも難しいが大切なことなのだなと思った。成長したエウニセの子供たちが皆明るかったのは、彼女のそうした心の闘いの成果なのだという気がした。20歳の時の事故で頚椎を損傷しながらも作家として成功し明るく生きるマルセロにも、母親の薫陶が感じられた。
2014年の認知症を患ったエウニセを演じたのはフェルナンダ・モンテネグロ。サレス監督の「セントラル・ステーション」でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた名優で、エウニセ役のフェルナンダ・トーレスの実母だ。血の繋がりがあるだけに老いたエウニセとして自然な容貌だったのもよかったが、何よりも目の表情だけでエウニセの感情が蘇るさまを雄弁に表現したその演技力にうなった。
実際のエウニセは、最晩年認知症が進んでからは何を聞かれても「そうね」としか答えなくなったが、感情が高ぶった時にはこう言ったという。
「私はまだここにいる」
夫がいなくなった後の人生を精一杯闘い、平和で温かい家庭を守り抜いた彼女だが、かつての心の傷が癒えたわけではない。病により、それを語ることがなくなっても。
図らずもこの言葉は、軍事政権の蛮行への反省が不十分な現代のブラジルや、ひいては歩み寄りを忘れた世界の様々な対立軸への警鐘にも聞こえるのだ。