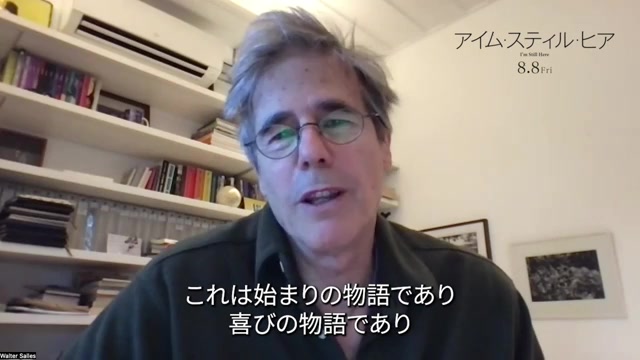アイム・スティル・ヒアのレビュー・感想・評価
全128件中、1~20件目を表示
人間社会の罪深い過ちを忘れないために
この物語は、家族の実体験を記したマルセロ・ルーベンス・パイヴァの回想録に基づくものだ。ウォルター・サレス監督は14歳の頃この家族と親交があり、週末毎に彼らの家を訪れていたという。序盤の明るく解放的なパイヴァ家の日常の姿は、監督の記憶に刻まれた風景でもあるのかもしれない。
主役は一家の母であるエウニセだ。夫のルーベンスが行方不明になってからの彼女の経歴には、生半可でない意志の強さを感じる。5人の子供を抱えながら、43歳で大学の法学部に再入学し司法試験に合格。弁護士としての一般的な業務の他に、先住民族の権利擁護や環境保護にも献身的に取り組んでいる。
このようなエウニセの夫失踪後の人生だけでも十分映画になりそうだが、本作ではそこはばっさりと省かれている。四半世紀の長きにわたり連れ去られ殺された事実さえ隠され、国家から存在を消し去られていたルーベンス。愛する夫を、父親を、ある日突然そのような形で奪われることの残酷さと理不尽さに焦点が当てられる。
平和なパイヴァ家の姿やルーベンスの人となりが最初に細やかに描かれたからこそ、それらが全て失われることの痛みがよく伝わってきた。
だが、エウニセは強い。夫が帰ってこず、軍関係者と思しき男たちがずかずかと家に上がり込んで居座ったのに、冷静に彼らの食事の気遣いまでして見せた。ここで取り乱せば、男たちをさらに警戒させてしまう。夫不在の中、彼女はひとりで子供たちを守らねばならないのだ。
やがて彼女も娘と共に拘束され、長期間(パンフレットによると12日間)の厳しい尋問を受ける。ようやく解放され、帰宅したエウニセは子供たちの前では再会を喜びこそすれ、不安に屈する姿を決して見せない。父親についてのネガティブな言葉は、ラジオのニュースに至るまで子供たちには触れさせまいとする。子供たちの心と、ルーベンスがいなくなる前のあの家庭の明るさを、エウニセは守りたかったのかもしれない。
気丈な振る舞いをほとんど崩さなかった彼女だが、そうせざるを得ない彼女の緊張感や苦しさもひしひしと伝わってきた。
それでも、働き手がいなくなった彼らの生活は経済的な困窮により否応なく変質してゆく。まず家政婦の給料が払えなくなり、やがて生活費も苦しくなって新居を建てようとしていた土地を売り払い、親戚のいるリオデジャネイロに転居することになる。子供たちの、恋人や友人との別れが切ない(マルセロが別れを告げた友人たちの中に、幼い日のサレス監督もいたのだろうか?)。ルーベンスがいれば起こらなかったであろう環境の変化に翻弄される彼らを見て、改めて軍の横暴に怒りを覚えた。
誰かが暴力の犠牲になる時、被害は当事者にとどまらない。本人に関わる多くの人もまた、人生が大きく変わるほどの影響を受ける。
それはあってはならないことだが、自分の身にそのような受難があった時、心まで屈することのないようにすることも難しいが大切なことなのだなと思った。成長したエウニセの子供たちが皆明るかったのは、彼女のそうした心の闘いの成果なのだという気がした。20歳の時の事故で頚椎を損傷しながらも作家として成功し明るく生きるマルセロにも、母親の薫陶が感じられた。
2014年の認知症を患ったエウニセを演じたのはフェルナンダ・モンテネグロ。サレス監督の「セントラル・ステーション」でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた名優で、エウニセ役のフェルナンダ・トーレスの実母だ。血の繋がりがあるだけに老いたエウニセとして自然な容貌だったのもよかったが、何よりも目の表情だけでエウニセの感情が蘇るさまを雄弁に表現したその演技力にうなった。
実際のエウニセは、最晩年認知症が進んでからは何を聞かれても「そうね」としか答えなくなったが、感情が高ぶった時にはこう言ったという。
「私はまだここにいる」
夫がいなくなった後の人生を精一杯闘い、平和で温かい家庭を守り抜いた彼女だが、かつての心の傷が癒えたわけではない。病により、それを語ることがなくなっても。
図らずもこの言葉は、軍事政権の蛮行への反省が不十分な現代のブラジルや、ひいては歩み寄りを忘れた世界の様々な対立軸への警鐘にも聞こえるのだ。
夫を、父を国家的暴力に奪われた家族の記憶を語り継ぐ志が、右傾化する世界へのカウンターになる
のちにブラジルを代表する映画監督になるウォルター・サレスが十代半ばで、「アイム・スティル・ヒア」で描かれるパイヴァ一家と出会い、知識人らが出入りし政治や音楽について自由に語り合うパイヴァ家をたびたび訪れていたという。子供たち5人のうち唯一の男児であるマルセロが後年作家となり、認知症の進行が始まった老母エウニセの記憶を語り継ぐため著した回想録を出版。これに基づきサレス監督が映画化したのが本作だ。監督によると原作自体がエウニセの視点で書かれたといい、映画もおおむね彼女の視点に立つが、息子マルセロの視点も控えめながら混じっていることを意識して鑑賞すると、見える景色が少し変わるはず。
パイヴァ家の大黒柱だった元議員ルーベンスが軍事政権下で不当に連行され行方不明に。絶対に夫を取り戻すというエウニセの不屈の精神と、怒りや不安や悲しみを内に秘めつつ子供らを守り育てる強い母親としての生きざまを体現した、フェルナンダ・トーレスの抑制された熱演が映画を牽引する。この事件を取材しに来た記者とカメラマンから記事に載せる写真を撮影する前に「もっと悲しそうに」と指示されるが、にこやかに拒否し、子供たちに「笑って!」と呼びかける気丈さが胸を打つ。
息子のマルセロは、劇中では成人後に車椅子を使っている姿で描かれるが、20歳の時に湖に飛び込んだ際に脊椎を骨折し、後遺症で下半身不随になった。ラストの家族の集合写真を撮るシーンで、認知症が進んだ老エウニセ(フェルナンダ・トーレスの実母で、サレス監督の代表作「セントラル・ステーション」で主演したフェルナンダ・モンテネグロが演じる)と、マルセロが2人とも車椅子に座った相似形で並ぶ。車椅子使いになった理由は異なるが、図らずも母子で似た姿になったことが、ちょっと哀しくて切ない。
エンドクレジット前の文で、政府がルーベンス殺害を認め、2014年に軍人5人が起訴されたが、いまだに逮捕も処罰もされていないと説明する。サレス監督はインタビューで、極右が台頭している昨今だからこそ、軍政期の国家的暴力を語り継ぎ、同じ過ちを繰り返さないようにする作品の必要性が増しているという趣旨の発言をしている。それはブラジルに限った話ではないし、右傾化する今の世界だからこそ、「アイム・スティル・ヒア」のような映画がカウンター、対抗手段として有効なのだと信じたい。
サレスならではの筆致で描く、人生の歩みを止めない物語
サレスの監督作はいつもゆったりと観客を招き入れ、おおらかに包み込む。代表作の幾つかはロードムービーとして知られるが、しかしそうでなくとも、例えば「ダーク・ウォーター」という一つの場所を舞台にした作品でさえ、そこに至るまでの母娘の長い彷徨を感じさせる。いわばサレス作品は動こうと動くまいと、心と場所の距離移動を大切に謳った物語と言えるのだろう。その点、久々の今作では、独裁政権下で夫を強制連行された妻と子供らの数十年の歳月が織り成される。リオ育ちのサレスは幼少期に彼ら一家と親交があったそうで、まさにこの物語は彼にしか具現化し得なかったものだ。当時の緊張と恐怖、悲しみや怒りに押し潰されることなく、ヒロインは意志と気高さを持って人生を歩む。その生き様は確実に子供たちへと受け継がれている。この母娘、継承というテーマは配役からも窺え、私は久々に「セントラル・ステーション」の懐かしさを思い切り噛み締めた。
家族の平穏を無惨にも奪われた専業主婦が変容していく
革命家、チェ・ゲバラの青春時代にフォーカスした『モーターサイクル・ダイアリーズ』((04年)や、1950年代のビート・ジェネレーションを代表する作家、ジャック・ケルアックの自伝的小説を映画化した『オン・ザ・ロード』('12年)等で、ロードムービーの達人と言われてきたウォルサー・サレス監督。ブラジルに生まれ、外交官の父と共にフランスとアメリカを行き来して育った彼が、ロードムービー、つまり旅する映画にシンパシーを感じるのは必然なのかもしれない。
同時に、15歳でブラジルに帰国したサレスが離れて暮らしていた母国をテーマに映画を作るのも、また、必然。離れていたからこそ見えてくる真実や独特の距離感が、作品に深みと客観性をもたらすこともあるからだ。『モーターサイクル~』はその2つの要素が合体した傑作だと思うし、本作『アイム・スティル・ヒア』は軍事独裁政権下のブラジルに生きた実在の家族に密着して、平和なコミュニティが少しずつ破壊されていくプロセスを計算し尽くされた演出で見せていく。冒頭で描かれる家族の風景が平穏であればあるほど、その後にやって来る暴力の足音が覚悟はしていても、身に沁みて恐ろしいからだ。
元下院議員だった夫が政権に批判的だったことから、ある日突然、軍によって連行される。本作は、残された妻が平凡なハウスワイフから闘う女性へと否応なしに変容していく姿を通して、国家的弾圧にも負けない個人の強さを描いている。妻とは、母とはいかに強靭であるかというパワフルなメッセージだ。
サレスが最後に仕掛けた過去作との見事なリンクに思わず膝を叩く映画ファンがいるに違いない。筆者もその鮮やかさ、旨さにニヤッとしてしまった。
それでも、わたしは逃げない‼️
冒頭は1971~1972年の話しから、始まります。
楽しげに海辺で遊ぶ5人の子供と、その父親と母親。
その平和な日常が、突然の得体の知れない男たちにより、一家の父親ルーベスが
連れ去られます。
男たちは、逮捕?拘束?その理由を全く言わない。
●この映画は母親エウニセ(フェルナンダ・トーレス)の視点を通して
描かれています。
だから“何がどうなって““夫はなぜ連れ去られたか?“
何も分からない視点なので、かなり説明不足だし、時間経過も
定かではありませ。
☆夫は以前の政権の議員で要職にあった。
☆妻にも秘密の地下組織への活動があるらしい、
そのくらいしか妻には分かりません。
●そうこうしているうちに、家のそばには2〜3台の車が停車していて、
家族の行動を監視している。
◆突然、お母さん(エウニセ)と次女(15歳)が監視者に連れ去られる。
♪
♪
ここからが怖かったです。
車に乗せられ施設に着くと、お母さんは黒い頭巾を被されて連行される。
尋問室では、質問は一切禁止!!
夫はどこ?
生きているの?
ただただ、あちこちから拷問らしき悲鳴がきこえてくる、、
一番怖いのは頭巾を被されて暗い狭い部屋に放置される。
着替えも出来ない。
★そして通路を水を流して掃除している姿を目撃する。
(嫌でも、血液や汚物を洗い流してると想像がつく)
お母さんの心配事は別々にされた次女のこと。
この極限状態でもお母さんは負けない。
しかし程なくお母さんは釈放されます。
次女も帰っていました。
この家には5人の子供がいます。
上から女・女・女・男・女の5人。
四番目の男の子でその時小学校低学年だったマルセル。
★マルセルがのちに母から聞いた話を出版したノンフィクションが
この映画の原作になっています。
★監督のウォルター・サレスは、子供の頃、このリオデジャネイロにあった
この一家の家に一度訪れたことがあるそうで、マルセルとは同学年でした。
お父さんが行方不明になり、生活は貧しくなり、一家は転居。
それをきっかけにお母さんは法科大学に入り弁護士の資格を取ります。
そして政府(独裁軍事政権)と真っ向から戦う人権弁護士になります。
5人の子供たちも立派に成長。
◆◆印象的だったシーン。
❶夫の連行を見送るお母さんのこめかみの青スジ。
❷行方不明者の家族として雑誌の取材を受けて、家族6人で記念撮影。
カメラマンは笑い合う家族に「もっと悲しそうな顔で!!」と注文するが、
一家は互いにケラケラ笑い合う《逞しさ》
❸お父さんの死亡証明書を受け取った家族が、喜び合うシーン。
(それほどに辛く長い日々だったのですね)
【締めくくり】
お母さん役のフェルナンダ・トーレスさんの実に冷静でありながら、
毅然とした表情にあらゆる感情(圧政への怒り、憤り、不安)を、
言葉としてではなく表情や仕草で演じて実に見事です。
ゴールデングローブ賞主演女優賞も納得の演技でした。
軍事政権の圧政に立ち向かい一歩も引かない女性を演じて
素晴らしかったです。
軍事政権の抑圧・弾圧そして粛清を描く映画は数多いです。
嘗てのスペイン、ポーランド、中国・・・などなど。
この映画は一人の普通一家の女性の半生を通して一家族の悲しみを
描いていること
イデオロギーの違いで抹殺された人々の現実に、
恐怖と激しい怒りを覚える傑作でした。
【”1970年と2014年の二枚の笑顔の家族写真。”今作は軍事独裁政権下のブラジルで突然、夫を連行された妻と父を失った子供達の長きに亘る戦いを描いた実録ドラマである。】
■元国会議員のルーベンス・パイパの妻、エニウセ(フェルナンダ・トーレス)。夫と5人の子供とリオデジャネイロで暮らす彼女は、軍事独裁政権下に有っても自由な精神を忘れずに、友人や家族と楽しむ時間を大切にする生活を送っていた。
しかし、1971年のある日、突然ルーベンが軍部に連行され、消息を絶つのである。
その時から、エニウセの25年にも及ぶ、目に見えないモノとの戦いが始まるのであった。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・エンドロールで映し出される、実際のルーベンス・パイパ一家の写真から明らかなように、今作は実話である。
それが、よりこの物語に深みを与えているのは、間違いがないであろう。
パイパ一家が、ビーチで寛ぎながら家族写真を撮る際には”笑顔で!”とルーベンスは家族に告げて、笑顔の家族写真が残るのである。
・エニウセが自らも軍の施設に連行されながら、長い勾留から解放された時に、穢れを洗い流すかのように、シャワーを浴びるシーンが彼女の、傷ついた心を物語っている。
・彼女は、何も状況が進展しない中でも、子供達のために生活を前に進めるべく、母親業をこなす姿をフェルナンダ・トーレスが、抑制した演技で見せてくれるのである。
・時が流れる中、彼女はリオデジャネイロからサンパウロへの移住を決意するのである。彼女の中で、夫の生存を諦め家族の為の生活を選択するシーンだと思う。それにしてもエニウセの精神的な強さは感動的ですらある。
■25年後のサンパウロ。エニウセは弁護士として名を成し、到頭、民主化された政府から夫、ルーベンスの死亡証明書を手に入れるのである。
そして彼女は、夜に一人、且つての笑顔の家族写真が貼ってあるアルバムを懐かしそうに見ながら、家族写真のあと、ずっと空白であったアルバムにルーベンスの死亡証明書を貼るのである。
・更に時は過ぎ、2014年。子供達も多数の子供がいる。老いたエニウセ(フェルナンダ・トーレスの母で、名女優フェルナンダ・モンテネグロ)は認知症を患っているが、TVに映された夫のルーベンスの写真に反応をするシーンでは、強い夫婦愛を感じるのである。
そして、再び家族で撮る笑顔の家族写真。
このシーンは、ルーベンス・パイパ一家が軍事政権に屈せずに、主亡き後もエニウセの不撓不屈の頑張りで、更に”家族の木”を大きくした事を示すシーンなのである。
<今作は軍事独裁政権下のブラジルで突然、夫、父を連行された妻と子供達の長きに亘る戦いを描いた実録ドラマなのである。>
ブラジル-アメリカ- そして日本
久々に見応えのある作品に遭遇
すっかりキネマ旬報シアターはホームグランドになってしまいましたね。シャンテまで行こうと思っていたのが行けずしまいで・キネマ旬報シアターでかかったのでいさんで行きました、文春のシネマチャートでも割合好評価だったし、見ても大丈夫かなと思って、
私の映画選定は雑誌のキネマ旬報もですが子供の時からスクリーンの双葉先生が勧めたものを見てました。あとは荻昌弘さんのも淀川先生のもです。情報交換は虎ノ門の映画友の会でした。淀川先生の話も聞けたし、今はfacebookでグループとかでやりとりとかと
キネマ旬報シアターでも映画好きが集まって話したりです
アイムステイルヒアは「ミッシング」の大人版ですね。お父ちゃん帰ってこない、お母ちゃん頑張ると言う実話なのがやるせないですね。丁寧に作っているので好感が持てますね。
繰り返される不条理な世界
ブラジルの裕福な家庭の穏やかな日常がかなり長めに描かれる。どのような国でも豊かなる人々でいられるにはそれ相当の理由があるのだろう。軍事政権であっても夫の元議員の肩書きが効いているのかもしれないし建築技師として有能なのかもしれない。妻と5人の子供は何の疑いもなく、ひたすらに幸せそうである。
そして突然、その幸せそうな穏やか日常は軍政府の横暴で破壊される。夫は軍事クーデターで議員資格を剥奪されたりヨーロッパに亡命したりの過去はあるものの逮捕されるほどの罪は犯しているようには思えない。更に妻と次女も事情聴取と称して連行され妻に至っては12日間も勾留されてしまう。軍事政権が恐れるのは共産主義者やテロ組織だろうが民主化を求めるインテリ層は全て敵対勢力なのだろう。だから彼らが行うことは連行した者に仲間を売るように強要する。
軍事政権では、かつての韓国でも今のミャンマーでも同じように彼らの側から都合の悪い人々は排除し殺戮も厭わない。今、権威主義国と言われるロシアや中国でも言論は統制され秘密裏に不満分子は迫害される。更に自由民主主義のアメリカでさえトランプが政権にいる限り彼の意にそぐわない者は追放されてしまう。日本だって検察の横暴で罪なき人を投獄することもある。
つまり、1970年代のブラジルのこの出来事をブラジル政府も歴史上の小さな話としてるようだし、世界のどの国も教訓と捉えてはいないだろう。そして、残念ながら今後もこのような事は世界の何処かで繰り返されてしまう。
だからこそ、映画やドキュメンタリーで記録に残すこと、そしてそれが遍く多くの人々に知れ渡る事は何より重要である。
事件後、生活の維持が難しくなったエウニセは新居予定の土地も売り、家族で暮らした家も手放すことになる。外国の新聞に告発する為に撮った家族写真で皆が笑いながらカメラに収まる姿は名シーンとなっていつまでも語り継がれていってもらいたい。
母の底力
市民の幸せな生活を一瞬にして崩壊させる独裁国家の恐ろしさをまざまざと感じた。
「強制失踪」という言葉を初めて聞いた。
政府が逮捕を認めなければ、たとえ死んでいたとしても政府には関係ないこと、と責任逃れができる。残された家族は愛する人が生死も含めてどうなっているのか不明な苦しみのほかに、公式には「失踪」状態なので、家族がその人名義の預貯金を下ろすことができないなど、日常生活に行き詰る事態にも陥ってしまう。
ある時突然、家族が連行されてそのまま帰らない、という悲劇は、軍事独裁政権下ではよく聞く話だが、この映画では直面した家族のリアルがわかる。
20年後の次女と長男が、「いつパパが戻らないことを知ったか」と話し合うところで、子供たちが子供なりに事態を理解していたこと、年長の姉妹が、小さい弟妹を気遣って大人の配慮をしていたことが見える。小さい長男も、パパは戻ってこないことが分かっていたが、母を気遣って何も言わず、気づかないふりをしていたよう。
原作が当時子供だった長男の著作とのことで、子供から見た「事件」が描かれている。
母の底力がスゴイ。夫を連行され、自身と次女も連行、取り調べを受けたが、一貫して賢明なふるまいで乗り切り、家族を守り、重要なことは信頼できる友人に相談しながらひとりでさっさと決断する。
夫が健在の際には、家事の大方を家政婦に任せて、スフレを焼くのが得意な典型的な裕福な家庭の専業主婦だが、窮地に陥れば冷静に状況をとらえて賢明な対応で家族を守り、先々のビジョンまで同時に考える。大学に戻って法律を学び、弁護士資格を得て人権活動に乗り出す。すでに夫の生還は諦めたが、国家の弾圧を告発し、誤りを認めさせることで夫を取り返すほうに方向転換、20年の年月をかけて、夫死亡の事実の確定をもって、国家に過ちを認めさせる。
賢く強いママ、家族を守り修羅場を乗り切り、長い年月をかけて国家に一矢。
こういう話とは思わなかった。
夫が政府に批判的な元議員で、海外のメディアを活用できる立場にいたことも、ただの蟷螂の斧にならなかった要因だろう。軍事独裁政権が、海外の(アメリカの?)メディアには手出しをしていなかったようなのは、国際社会への仲間入りを目指しての対外的な評判を気にしたか、アメリカへのおもねりかも。
エウニセたちが夫の死亡証明書を勝ち取った際のひとりのインタビュアーの、「過去の悪事を掘り起こすことよりほかにすべきことがあるのでは」に唖然とした。エウニセは、「過去を反省しないとまた同じことが起きる」と言っていたが、当事者である家族にとっては過去の話ではなく、現在進行形の悪事だ。インタビュアーの感覚がそれに思い至らない程度に他人事で、軍事政権下の圧政が過去のものと認識されているようなところが見えて、こうしてまた同じようなことが繰り返されるのだろうと感じた。
前半の、幸せな一家の生活ぶりの描写がちょっと長すぎ。
半分くらいのボリュームでよかったのでは。
仲間がいる
軍事独裁政権時のリオデジャネイロにて、反政府的だった元議員の旦那が連行され…。残された妻と子ども達の人生を描いた作品。
序盤は家族の幸せな風景が見せられる。家の目の前にビーチ、羨ましい…。友人たちを家に招き、楽しそうに暮らしていたのだが…。
改めて独裁政権、恐ろしいですね。あんな男達がいきなり家に居座って。。
この話は過去のものだけど、別の国では現在もこんな非人道的なことが…。
自身も拘束され、あれだけの恐怖体験をしながらも子どもたちを守る為、そして夫を取り戻すため闘う母の姿。
また、印象的だったのは友人たち。強大すぎる相手を向こうに回してもエウニセに協力してくれる。この場面は目頭が熱くなりました。残酷だけど、最初のマルタの反応を誰が責めることができようか。そんな彼女も遂に…。
政府も政府で必死なのはそうなんだろうけど…。罪もない子どもたちまで巻き込まれるこの理不尽を目の当たりにするのはとても辛いですね。
…なんて言ってられるのも、平和な日本だからなのでしょうか。今の所は…。そして末っ子ちゃん、あの場面で悟っていたのか。
厳しすぎる現実と闘い続ける過酷さと大切さを感じたとともに、観ていてとても恐くなるほど、平和が続いてほしいと願った作品だった。
エウニセの壮絶な人生…せっかくの佳作なのに、邦題が何とかなりませんか?
家族愛が強烈に心に残る
アカデミー国際長編映画賞を受賞したので観に行った。予備知識はほぼゼロ。ブラジルという国自体良く知らない。多民族国家で情勢は不安定。軍事国家だったけど西側。ほんとよく分からない国。
映画は弾圧された市民の様子はほとんど映さない。序盤はブラジルの中ではかなり裕福な家族の日常生活を延々と映す。日本で言えば湘南の海辺のような所で暮らしている弁護士と大学教授の優雅な生活。ここは正直退屈だった。もっと編集で短くしても良かったのではないか?と思っていたが、これが鑑賞後に大きな意味を持つことが分かった。
そして一家の主人である夫が謎の組織に拉致されてからの描写は圧巻。過激な映像描写は皆無なのだけど、演出が驚くほど繊細なのだ。残された家族の母親とその子どもたちの感情と行動が非常にリアルで説得力があり、同時にこれは「家族の絆と愛の叙情詩」というテーマが鮮麗になった。
「国宝」が記録的ヒットで高評価しているからか、来年のアカデミー国際長編映画賞に日本代表作として選出されたが、ドラマのクオリティは月とスッポン。
ただ一つ卑怯なのは子供たちがみんな美人かかわいい子ばかり。これだけは監督の趣味が出たのかな?(笑)
笑顔と強い絆で乗り越える
1 軍治独裁政権時代のブラジルにおいて、主人が当局に連行され行方不明となり、翻弄される一家の姿を描く。
2 映画は、冒頭から町の人々の開放的な場面を写すとともに家族の愛情溢れる温かい有り 様を丁寧に描く。その一方、舞台となった1970年当時のブラジルが強権的で不穏な社会状況にあることも示される。また、この家族の主人が政治亡命者の支援活動を密かに行っていたことがサラリと描かれる。家族はこのことは知らない。妻だけは後日主人の仲間から知らされた。なので、彼が連行された理由を観客は知っているが、彼の家族は分からず混迷する。
3 妻は、主人が拘置されていたことを立証する証言を得て、国に彼の保護や解放を求める訴えを起こしたり、マスコミを利用する。国はそんな妻を一時拘束したり、監視するなどの圧力をかける。そうした中、妻は行方不明中の主人が既に殺されて海に遺棄されたとの未確認情報を得て絶望する。さらに経済的にも困窮し、家を手放し、引っ越す。
4 映画は、そこから約25年後に飛ぶ。1996年、国はようやく主人の死亡に関する公文書を発行し彼の死を認めた。喜ぶ妻と子供達。この間、妻や家族がどんなに苦労して来たかは推察するしかない。この映画は、ブラジルの昔の国家的犯罪を糾す社会派の性格を持っているが、それよりも先ずは、どんな困難にも負ける事なく笑顔と強い絆で乗り越えてきた家族の物語であった。
幸福のすぐ隣には絶望が待っている……?
1970年、軍事政権下で軍部に連れ去られ消息を絶った元国会議員のルーベンス・パイヴァと、その消息を追い続けた妻のエウニセや子どもたちの実話を、一家の長男マルセロが母親の話を聴き取りながら著した回顧録を原作として映像化したもの。
何気なく幸せに過ごす日常生活に突然秘密警察が土足で踏み込んできて、一気に絶望の底に突き落とされる。
夫を奪われたエウニセは武装して軍隊と戦うわけでもなく、法律の知識で身を守りながら静かに訴え続けるのみ。
長い年月の後、ようやく夫の死亡を政府が認めた際のインタビューで、政府の過去の悪事を暴くより大事なことがあるのではないかと記者に問われたエウニセは、過去をしっかりと反省しなければまた同じことが繰り返されると答える。
軍事政権が独裁国家を率いる中で、言論の自由は弾圧され、拷問によって仲間を売ることを強要され、政敵はことごとく排除されていく。それは過去から現在まで何度も繰り返され、ブラジルに限らずどんな国でも起こりうる。
「スパイ防止法」という名のもとで戦前の治安維持法の復活を目論むような政党が選挙で得票を集めるような国では、過去の反省が十分になされたと言えるのであろうか?油断をしていると、幸福のすく隣には絶望が待ち構えていることを忘れてしまうのかも知れない。
骨太に描かれた、家族の歴史の物語
むかし、兵庫県の小さな教会を訪ねたことがある。そこの牧師さんから「教会の歴史」を聞かせてもらった。
― 戦時中、「天皇陛下も神の前には同じ人間だ」と発言したがために警察署に連れて行かれたという その教会の先輩牧師さんのことだ。
シタイヒキトルカ 」
と電報が来て、
署へ行ってみると全裸で転がされていて、牧師の妻は猛抗議で「せめて服を着させて下さい」と食い下がって、“夫”を連れて帰ってきたのだと。子供たちとリヤカーに乗せて連れて帰ってきたのだと。
文書資料では見聞きしていたが、その他ならぬ現地で、そこの関係者から、この「電文」と「閉鎖命令」と「リヤカーの話」を聞いた衝撃は
ちょっと表現が出来ない。
あの時代、日本のキリスト教会の大多数は、官憲に目を付けられて見せしめのためになぶり殺しにされていた その上記のような教会を見捨てしまったのだ。トカゲの尻尾切りで、目をつぶり、国に抵抗したキリスト者をみんなで助けようとはしなかった。
戦後、21年後にその罪責を公に告白し、詫びるまでは。
「黙っていましょう」
「我慢して見ぬふりをしましょう」
「危険に近づくのはやめて!」
と、妻エウニセは夫ルーベンスを止めたかったろうに。
ルーベンスは愛する妻には自分の地下活動の件は一切黙っていたのだった。
映画はブラジルでの実話。
拷問で、死ぬまで殴られるって、どんなに怖くて、痛くて、どれだけ苦しいんだろうか・・
妻子の命も脅かされる。独房では家族の無事がどれだけ気がかりか。エウニセの取り調べのシーンは精神の錯乱の領域まで踏み込む。
・ ・
【原作】末っ子の息子マルセロの手記が原作になっている。その後も政情不安なブラジルなら、息子や妻も命がけだったはずだ
【監督】は、あの「モーターサイクル・ダイアリーズ」のウォルター・サレス。
沈鬱なテーマや悲痛な最期があろうとも、人間には美しくて輝く人生のひとときが同時に必ず伴っている事を、カメラで丁寧に語ろうとする人だ。
【物語】は三分の一ずつの分量で、三つのブロックに分かれて構成されていたように思う、
①夫婦仲は最高で、幸せな子だくさんの弁護士一家。その平和な日常風景。
②家の主の連行と行方不明。
③夫、そして子らにとっては掛け替えのなかったお父さんの不在の日々から〜25年目の「死亡証明書」へ。そしてその後の子どもたちと母の人生の紹介だ。
この映画作品に特別のものがあるとすれば、軍事政権によって亡きものにされたルーベンスの家族が「その後をどう生きていたか」を全体の三分の一をたっぷりと割いて後半で丁寧にエピローグしている点だ。
①と②だけなら類似する構成の告発系社会映画はいくらでもある。
しかし本作は ③=「家族のその後」が殆ど映画の主題なのではないかと思われるほど大きく据えられている。
・警察署から出されて駐車場の見える廊下を歩かされるエウニセの、12日ぶりの呆然とした顔。
・帰宅して子どもたちの寝顔を確認したあとやっとシャワーを浴びて、痩せて疲れ果てた自身の体の黒い汚れをアカスリで落としていくさま。
・「ただ眠りたい」と起きてきた娘に告げるシーン。
・そして夫を取り返すために司法試験に臨む。
強烈だ。
夫を待ち、子どもたちのために耐え、言葉を慎んだ母が強烈だ。
「暗い表情の家族写真が欲しいんです」とリクエストする新聞社に「いいえ、みんなで笑いましょう」と敢えて言う母。しかしこの写真でただ一人最後列で固く強ばった顔で立つ長女。
25年が経ち
末っ子のマルセロに長姉がお酒を注ぎ、そして訊く
「いつお父さんが死んだとわかった?」
「いつ頃お父さんはもう戻らないと悟った?」
・・この、母が席を外した時に姉が弟にそっと尋ねるやり取りには
もう僕はやられてしまった。
なんという家族のリアリズムだろう。
たくさんの実在の写真が、家族の愛の歴史と結束を証明していて、
「アイム・スティル・ヒア」
=私たちは死んでない
=どっこい僕らは生きているぜ
と、弟は家族の記録を著したのだ。
エウニセ役のフェルナンダ・トーレスと、認知症になった後代のエウニセ。=この認知症のエウニセを演じたのはトーレスの実母フェルナンダ・モンテネグロだ。似ているはずだ。圧倒されてしまう。こんな凄い女優たちがこの世にいるのか。
子役たちが成人していく後半でのキャスティングも文句なし。
・・・・・・・・・・・・
今宵の塩尻市・東座。
館主の合木こずえさんは薄いペパーミントグリーンのサマーセーターでした。
猛暑の夏も頑張って良作をかけ続けてくれた。
世に問うべき映画を「これぞ」と見つけて引っ張ってきてくれた。
細身の体を凛とさせて、上映後に客席から出てくる観客をロビーで迎えてくれる彼女。映画ごとに彼女は表情が違う。
闘ったエウニセの面持ちがハッとするほど重なっていて、
かける言葉を失ってしまった。
·
子どもには言えない「大人の事情」
1970年代初頭のブラジルが舞台とのこと。土木の専門家の父のもとで、子だくさんの家族が絵にかいたような幸せな生活を送っている。道を一つはさんだ海に出かけてビーチバレー、家ではレコードに合わせて踊り、サッカーゲームで対戦、母の手作りのスフレケーキ。
「日焼けしたらダンスの先生に叱られちゃうわ」というように、大人に褒められる遊びにも、そうでない遊びにも恵まれた女の子4人、男の子1人からなるきょうだいだ。
ところが軍事政権に父が連れ去られ、生死も不明な状態に。母と次女も捕まって監禁され、ロンドンに逃がされていた長女もそれを知ることになる。
ここで、大人(母)、若者(長女と次女)、子ども(三女、四女、長男)にチームが分かれる形になるのが興味深い。若者は母に「父は一体どうなったのか」と問い詰めるのだが、母は「その話はダメ。子どもが聞いているでしょ」とばかりに制止する。
こうして気丈な母を中心に、一家は「パパを待ち続ける、幸せな家族」を演じ続けるのだ。いや、演技でなく本気かもしれない。政権の不当性を訴えるための記事で、カメラマンに「深刻そうな顔をして」と言われても、みんな笑顔で写真に納まる。
やがて時は流れ、母の長年の活動が実り、政府に「父の死」を認めさせるに至る。あれっと思うのは、いつの間にか「父を待つ」ことから「事件の承認」に目標が変わっていることだ。
成長した四女と長男が「途中からお父さんが戻らないことは分かっていたよね」と話し合うシーンがあった。みんな少しずつ「大人の事情」を理解したということだろう。
全体として政治的な悲劇ではなく、一家のまとまりを描くことに全力を注いだ映画だと思う。しかしそれによって作品の重みが弱まった気がしなくもない。
一方、家族それぞれの思いをもっと知りたかったようにも思う。もしかして母だって父を疑い、恨んだ時期もあるのではないか。きょうだいも、父の死を悟るまでには多くの葛藤があったはず。
一家の正しさを訴えるためには、湿っぽい人間ドラマは余計だったということだろうか。
実話の重み
原作は本作のモデルとなった一家の末っ子マルセロ・パイヴァの手記ということである。父ルーベンスが軍に連行された時はまだ遊びたい盛りの少年だった。一家の大黒柱を失い途方に暮れる家族の不安と悲しみは如何ほどだったろう。きっと幼い彼の心にも大きな傷を残したに違いない。
ただ、物語はマルセロではなく母エウニセの視点で描かれている。母から聞いた話を元にしているのか、それとも想像を交えながら描いているのか分からないが、ともかくエウニセが我が子を抱えながらルーベンスを必死に捜索する姿がじっくりと綴られている。実に気丈で母性の強さが印象に残った。
エウニセを演じたフェルナンダ・トーレスの熱演も素晴らしく、物語に説得力を与えている。
ちなみに、彼女は今作でも語られていた大使誘拐事件をモチーフにした「クアトロ・ディアス」という作品にも出演していた。そちらでは過激派組織の紅一点を演じており、まだ瑞々しい印象だったが、すでに母親役を演じるようになっていて時の流れを感じた。
時の流れと言えば、老年期のエウニセを演じたのはトーレスの実母フェルナンダ・モンテネグロ。彼女を見るのも「セントラル・ステーション」以来であるが、すっかり老いた姿に感慨深くなった。
監督はその「セントラル・ステーション」や「モーターサイクル・ダイアリーズ」を手掛けたウォルター・サレス。過去に観た2作品はいずれもロードムービーだったが、今回はじっくりと腰を据えて語るホームドラマとなっている。安定感のある演出で真摯にテーマに向き合う姿勢は相変わらずで、悲劇に飲み込まれる家族の苦悩が画面からひしひしと伝わってきた。
また、当時の軍事政権に対する告発も力強く発せられており、社会派作品としても意義深い映画となっている。
特に、印象に残ったのは中盤のエウニセの尋問シーンである。彼女はルーベンスが反政府運動に加担していたことを知らない。しかし、軍はそんな彼女から情報を引き出そうと、薄暗い独房に監禁して尋問を繰り返すのだ。その恐怖と緊張感に目が離せなかった。
惜しむらくは、後半の展開がやや性急に感じたことだろうか…。ルーベンスの行方を必死に追うエウニセの孤軍奮闘が描かれるのだが、ダイジェスト風になってしまたために作品としての力強さが失われてしまったように感じた。
彼女の晩年を描く終盤も然り。子供たちは夫々に成長して家庭や仕事を持ち立派に自立している姿を見ると、エウニセの奮闘も無駄ではなかったのだな…と思うが、表層的にしか描かれていないため胸に迫るほどの感動は得られなかった。
もっともこの辺りをじっくり描くとすれば、それこそ前後編に分けるくらいの大作になってしまうので止む無しという感じもする。
最後に映画は事件のその後を簡単に紹介して終わる。これにはやるせない思いにさせられた。と同時に、事件からすでに半世紀以上が経っており、風化を防ぐ意味でも多くの人に本作が届いて欲しいと思った。
全128件中、1~20件目を表示