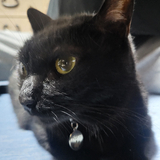クィア QUEERのレビュー・感想・評価
全65件中、41~60件目を表示
開いた扉は、もう閉じない
こないだ鑑賞してきました🎬
リーを演じたダニエル・クレイグが、新境地を開いたという触れ込みに惹かれまして🤔
確かに刹那的な生き方をするリーを、リアルに表現していましたね😀
ユージーンから目が離せなくなる、酒と薬に溺れる男…しかしそれでもどこか魅力的に映るのは、演者の力量でしょうか。
ユージーンにはドリュー・スターキー🙂
確かに見目麗しい青年で、リーへの態度も気まぐれもいいとこ。
しかし南米への旅を受ける辺り、ある程度は本気だったのでしょうか。
彼は追われる方で、リーが追う方なのですが、この構図には妙な納得感がありました🤔
時々この映画は夢なのか現実なのか区別がつかないシーンがはさまれ、かつ説明もなしに進行していくので、私には難解で😰
評価が難しいところですが、確かにユージーンの謎めいた部分は気を引きますし、リーが薬を打つ一連のシーンは緊張感がありました。
なかなか象徴的な1本ですが、地頭が良い人ならなお楽しめると思います🫡
みっともないほど君に触れたい
1950年代の「クィア」の意味を調べないと、ちょっと混乱してしまうかも
2025.5.12 字幕 MOVIX京都
2024年のイタリア&アメリカ合作の映画(137分、R15+)
原作はウィリアム・S・バロウズの小説『QUEER』
クィアを自認する男がある青年の本心を知るために共に旅行に連れ出す様子を描いた恋愛映画
監督はルカ・グァダニーノ
脚本はジャスティン・クリツケス
原題の『Queer』は、1950年代においては「異性愛者以外を指す蔑称」、現在は「LGBT」以外の性的自認のこと
物語の舞台は、1950年代のメキシコシティ
退役軍人で駐在員のウィリアム・リー(ダニエル・クレイグ)は、クィアが集うバーに入り浸っていた
同僚からは「すぐに寝ようとする」と距離を置かれていたが、リーは構うことなく、自分の生きたいように生きていた
ある日のこと、路上の闘鶏群衆の向こうに、凛々しい青年・ユージーン・アラートン(ドリュー・スターキー)を見つけたリーは、一瞬で心を奪われてしまった
親友のジョー・ギドリー(ジェイソン・シュワルツマン)に「彼はクィアかな?」と聞くものの、「直接聞けばいい」と諭されてしまう
物語は、何とかしてお近づきになろうとするリーが描かれ、本心が見えづらいまま、ユージーンとの関係が動いていく様子が描かれていく
3章+エピローグの構成で、第 1章は「リーとユージーンの親睦の深まり」、第2章は「南米旅行の始まり」、第3章は「エクアドルの儀式」、第4章は「その2年後」と言う感じに紡がれていた
第 1章でおおよそ半分くらいの時間を要し、このもじもじ系ラブロマンスが続くのかと思ったら、第3章からは一転して精神世界の話のようになっていた
本心を知りたいためにエクアドルに生息する謎の植物を探し求めるのだが、そこで遭遇する儀式とその後の作用と言うのが奇抜な作品となっている
前半でも、自分の体が幽体離脱してユージーンにさわろうとしたりするシーンが描かれ、良いおっさんが若者に恋をすると言うプロットと、生々しいセックス描写がOKなら大丈夫なのだろう
個人的にはそこまで抵抗はない方だが、のっけからイチモツ丸出しのシーンが連発するので、なかなか強烈だなあと思って見ていた
物語の核は「相手の本心を知れたら」と言うもので、謎の植物によって、テレパシーができると言うトンデモ系のラブロマンスになっていた
リーはその弊害を理解していなかったのだが、儀式によってユージーンもリーの本心というものが見えるので、それをおぞましく感じて距離を置いたのかも知れません
いずれにせよ、クィアというものの言葉の定義を「1950年代」として考えなければならない作品で、現在の「LGBT」以外の姓的自認と考えてはいけない
元々は「不思議な」「風変わりな」という意味合いで、「異性愛以外のもの」を指していた言葉なので、現在のクィアの映画には見えないところだろう
映画内でもある程度は仄めかされているので問題ないと思うが、そのあたりの言葉のタイムトリップが必要なので、知識のダウングレードが要する映画だったのかな、と感じた
第三部は寝たのに好評価です
予告編が名作過ぎてもう泣ける感じで、否が応でも封切りに期待が高鳴るアタシでした。レイトしか都合あわず、後半は睡魔に襲われつつ長い幻想場面に辟易するまでは快調に楽しめました。そういう訳で最後の方は脱力気味になって見終えたんだが、終わった後回想するに、二人がいい感じでいるパートははじめから老境主人公の100パーヤク幻想なのか、小説家の想像力とヤクで掻き混ぜた虚実入り交じりの原作世界やバロウズ本人の精神内外すべてに監督と脚本が格闘してみせたのかとつらつら考えるのが楽し過ぎです。それにしてもダニエル・クレイグは臀部が別格でしたね。ストイコビッチかよと思いました。
バロウズの原作『クィア』(旧邦題『おかま』)の映画化といいつつ、『...
バロウズの原作『クィア』(旧邦題『おかま』)の映画化といいつつ、『ジャンキー』や『麻薬書簡』も折り込んできて三部構成の第3章はトリップシーンとか楽しかったけど、同じルカ・グァダニーノの『君の名前で僕を呼んで』みたいなのを期待していった人は面食らうかもらしれません(日本だけか知りませんがビジュアルイメージとかそれっぽいですしね)。最後"William.S.Burroughs' Queer"て大きくタイトルが出たので邦題も『バロウズのおかま』とかにしてバロウズを強調しとけばよかったのでは(今の御時世許されるとは思いませんが)。
エピローグが感傷的過ぎないかというのと、正直南米旅行が始まるまでは退屈かもという感もありますが、バロウズに青春を捧げた者としては点数は甘くなります。
デカダン満載の白昼夢
「007」シリーズのジェームズ・ボンドがハマり役だったダニエル・クレイグが、クィア役で登場する異色作でした。原作は1950年代のアメリカ文学界において異彩を放ったビートニク文学の代表格であるウィリアム・バロウズの同名小説。同小説は、バロウズの自叙伝的小説とのことで、本作の前半はバロウズが実際に過ごしたメキシコシティを舞台に、主人公・リーの放蕩というか異常な好色を描く展開となり、後半は南米に未知の植物・ヤヘを探しに行く冒険物語となっていました。
とにかく衝撃的だったのは、あの”ジェームズ・ボンド”が男色とドラッグに溺れる様。別に男色だろうと女色だろうと構わないのだけど、昼間からバーに出掛けて好みの男子を物色し、直ぐにベッドインしようとするリーの行動には、唖然とせざるを得ませんでした。
そんな衝撃はさて置いて、各種調査によると、地域により差はあるようですが、概ね全人口の1割くらいがLGBTQ+なんだそうです。昨今LGBTQ+の人達の人権にスポットが当てられ、それをテーマにした映画も陸続と創られていますが、本作の原作は70年も前の話であり、実は普遍的なテーマでもあるんだということを再認識させられました。
また、本作の描き方から察するに、1950年代のメキシコシティというのは、恐らくはアメリカのあぶれ者や放蕩者が押しかけて、好き放題やってたんだろうと想像されるところが非常に興味深いところでした。
話を本作に戻すと、運命の人ユージーン(ドリュー・スターキー)に出会うリー。彼はいつも年上の女性とチェスをしており、一見クィアではないようでいて、リーの色目に呼応したりもする。で、そういう関係になる2人でしたが、ここで気付いたのがリーの好色の動機らしきもの。それはユージーンの見た目がスラっとしている2枚目であり、恐らくは若い頃のリーの姿にソックリだったのではないかと想像できることから、リーの好色は実は自己愛の発露だったんじゃないかということです。物語が後半になり、ドラッグにもハマっていることが判明したリーですが、これなども自己愛から来る自己防衛のためにクスリから離れられなくなったんじゃないかと解釈した次第ですが、勿論本当かどうかは定かではありません。
テレパシーの能力が手に入れられるという植物・ヤヘを、エクアドルのジャングルまで探しに行くというのも、自分と他人の壁を乗り越えることで、他人から攻撃されないことを目指したんじゃないかと思ったところです。ただヤヘ自体は、他人との壁を乗り越えるのではなく、自分の真の姿を鏡に映す効果があるものだったので、リーの夢は実現せず、同一化しようとしたユージーンも自ら抹殺してしまうことになるのは皮肉でした。
因みにバロウズ本人も、メキシコシティで誤って”女性”の妻(変な言葉やな)を射殺してしまったそうで、ユージーンを射殺するシーンはまさにこの体験を写したもののようですね。
以上、好色にドラッグにとデカダン満載の白昼夢のような作品でしたが、ダニエル・クレイグの全力の演技は観るべきものがありました。
そんな訳で、本作の評価は★3.6とします。
永遠の孤独を抱えつつも、その先にある連帯を求める
ウィリアム・S・バロウズ
ダニクレが出てる、原作がビート作家のバロウズである、舞台が50年代のメキシコである、ニルヴァーナが使われてる、以上の理由から観ました。
ホント同性愛の映画が増えましたね…ホント多くなった…
この映画に関しては、バロウズの自伝的小説の映画化で、バロウズが同性愛者だったからだけど、男同士のラブストーリーは、やはり苦手だな…
ダニクレといえば、ジェームズ・ボンド!
007は全て観たけど1番好きな作品は『ノー・タイム・トゥ・ダイ』
最高のボンドだと思ってます。
そんな自分にとってはゲイ役はショック…ボカシが入るようなラブシーンもあるし…
途中で純粋なラブストーリーから展開が変わるけど、ダレてきて時間が長く感じ眠くなってきて、はよ終わらんかな…と惰性鑑賞。
良かったトコは、50年代のメキシコが凄く洒落ててビートニクと聞いて思い浮かべるイメージどおりの町並みだった。
あと、まあ、最後も良かったのかな…
それはそうと、このタイトルを知って真っ先に思い浮かべたのは、パンクバンドQUEERS。
QUEERSのSが1つ足りないだけ、QUEER。
QUEERには、不思議な、風変わりな、奇妙な、の意味もあるらしいから、バンドの方はコッチの意味だと思う。
パンク好きは、みんな思い浮かべたよね?
バンドの方は好きだけど、映画の方は好きじゃないな…(笑)
起承転結がつかめない
気まぐれのように示された情だけが
ベニスに死すを思い出した。
ちょっと苦手なタイプの映画だなぁと思うので、評価はその分下方修正しています。
主人公の恋におちたときの距離の詰め方のへたっぴさが、共感性羞恥で我が身を見ているようで前半は内心ジタバタしながら見てました。
相手の気持ちが自分に添っていないことは、最初から明らかなので、ひたすら内心じたばた。
リーは欲だけならうまいことやることだってできるのになぁ、ああ、退かないで押すのか……と。
後半直接心を知りたいと行動するけれど、相手と融合するような感覚を経てむき出しになった思いは、やはりクイアじゃない、というもの。
最初のシーン、主人公が別の人に言ったセリフを返されるような、互いの間の境界を明確にするような、そのセリフ。
それでも最後のシーンで、一人残された主人公を温めたのは、欲に浮かされた熱でも恋情でもなく、ただただ、無造作に主人公にたいして示されたユージーンの人としての情を示した振る舞いの記憶なのだろうと思った。
【”クィアの陶酔と幻滅。そしてこんなダニエル・クレイグは観た事がない!”序盤は狭義のクィアをルカ・グァダニーノ監督お得意のトーンで描き、徐々に広義のクィアな世界を描いたインパクト大なる作品である。】
冒頭、ニルヴァーナの”オール・アポロジーズ”の女性によるカバー・バージョンが流れる。”これから、クィアの映画が始まるよ!”と、高らかに宣言されるのである。
そして、ダニエル・クレイグ演じるリーは、1950年代のメキシコ市のゲイが集まるバーで、めぼしい男を探すのである。その際に流れるのは、同じくニルヴァーナの”カム・アズ・ユー・アー”である。ムッチャ、脳内で盛り上がる。そう、この映画の音楽はイケているのである。流石、トレント・レズナーである。
リーの服装も良いのだな。上下白のスーツ。シャツはお約束のボタン二つ目迄留めないスタイル。透明な鼈甲縁の眼鏡。”私は、クィアだよ!”と言っているようなものである。しかも品があるのである。この映画の衣装、意匠のセンスがとても良いのであるよ。
リーは百足のネックレスをした一人の男と楽しんだ後に、目を付けていたユージーン(ドリュー・スターキー)に声を掛け、ストレートと思われる彼とベッドインする。
オジサン版「君の名前で僕を呼んで」である。猥雑感なしである。(個人的な感想です。)
因みにこの作品では、百足と蛇が良く登場する。解釈は観る側に委ねられるのである。
で、このまま行くのかと思ったら、そうは問屋が卸さない。
二人は南米に旅に出て、事前に聞いていたテレパシーが得られるという”ヤヘ”と言うドラッグを探すのであるが、この過程がコレマタ面白いのである。
リーは途中で、アヘンが切れて体調を崩すもアヘンチンキを医者から3CCだけ処方されて(クスクス)回復するのである。
リーが、アヘン切れの寒さで震えているシーンで、ユージーンに”傍に行っていいか・・。”と尋ねると、”良いよ・・。”と答えが合って、二人が一つのベッドで同じ向きで寝ている姿が良かったな。
二人は、到頭森に住む怪しげなコッター博士(レスリー・マンビル)の家に到着し、蛇の歓迎を受けた後に、樹木から煮出した”ヤヘ”を飲むのである。
”ヤヘ”を飲んだ二人がトリップするシーンが、もう凄くって、二人の口から赤いドロドロしたモノが出て来て、心臓みたいなモノがドサッと落ちるのである。グロイなあ。幽体離脱かな。このシーンの描き方は凄かったぞ!インパクト大だぞ!
<だが、エピローグで描かれるリーの姿は哀しい。
旅から戻って二年が経ち、ユージーンは既に彼の元を去っており、一人ベッドに横たわるリーはアヘン中毒が過ぎたのか、酒の飲み過ぎなのかは分からないが、別人のように老いているのである。
だが、その横たわる姿は、且つてのアヘン切れの際に、ユージーンの脇で寝た時と同じポーズなのである。絡み合う二人の足の近接ショットが切ない・・。
今作は、序盤は狭義のクィアをルカ・グァダニ―ノ監督お得意のトーンで描きながら、徐々に広義のクィアな世界を描いたインパクト大なる作品なのである。>
ビートニクスの旗手ウイリアム・バロウズの自叙伝小説
前日にウィリアム・バロウズのドキュメンタリー映画「バロウズ」を観たばかりなので、多少のバロウズリテラシーをもって鑑賞に臨めた。
まず最初に主演のダニエル・クレイグとバロウズのイメージが真逆すぎて驚かされる。
バロウズは見るからに知的でガリガリの米国紳士で、狼狽えたり興奮したりせず、常におっとりしたタイプ。
まあ自叙伝と言えど脚色を交えた小説なので全く同じである必要はないが、自分のイメージではキリアン・マーフィかエドワード・ノートンだった。
監督は10代からこの小説の大ファンで映画化をずっと望んでいたというルカ・グァダニーノで、満を持しての映画化だが「チャレンジャー」に引き続き男同士のねちゃねちゃしたディープキスを撮るのが大好きのよう。
クレイグが少女のように恋してはしゃぐ中年オヤジを嬉々として演じているが、なるほど確かにユージーン役のドリュー・スターキーは超美青年で均整の取れた身体も国宝級に美しい。(実際はメキシコ人だったみたいですが)
クレイグのツンデレに振り回される中年おじさんぶりが滑稽で面白い。
後半の南米旅行はまさにトリップ目的w
後先考えず快楽を求め続ける姿勢がまさにビートジェネレーションの象徴的行動。
脳内の映像もぐにゃぐにゃしてたり、身体から何か出てきたり、色鮮やかな爬虫類などバリエーション豊か。
ウイリアムテルごっこで奥さんを射殺したという有名な逸話もユージーンに置き換え映像化。
やっぱどうしても「ベニスに死す」を思い出してしまうが、あれほど惨めじゃなく次に進めそうな感じを残していたので少し救われる。
精神のレイヤーで繋がることの困難さ
1950年代のメキシコシティ、酒とドラッグで退屈な日々を過ごしていたアメリカ人駐在員リーは、若く美しい青年ユージーンと出会う。退屈だったリーの日常は色めき立ち、より刺激を求めユージーンを南米への旅へと誘いだす。原作は「裸のランチ」のウィリアム・S・バロウズ、数奇に満ちた彼の自伝的小説「クィア」の映画化。
特筆すべきは、小さい穴の開いたシャツを着た若き美青年ユージーン役ドリュー・スターキー。若き日のガイ・ピアーズを彷彿させる男前で、今後彼の時代の到来を予見させた。
スタイリッシュで幻想的な世界観、各シーン各アイテムの隠語・隠喩は明確、オープニングから本作の方向性と結末予測はしやすい。
全編に漂うのは、圧倒的な孤独感。刹那的な高揚観は孤独の裏返し。まるで呪いが掛かっているかのように、愛する人へ気持ちを伝えることや精神のレイヤーで繋がることの困難さが随所に伝わり、リーの複雑さは観る者に嘆息をつかせる。
本作はテーマで観る者を選ぶかもですが、わりとわかりやすく飽きずに鑑賞出来ました。
鑑賞後有料パンフを買ってしまいましたが、これを機に原作も読んでみようと思った作品です。
前半と後半でややテーマが異なる点が気になるか
今年122本目(合計1,663本目/今月(2025年5月度)7本目)。
※ 時間調整のため「歌のプリンスさま」を見てからになりますが、憲法論的な解釈が存在しない映画は観てもレビュー対象外です。
他の方も書かれていますが、前半後半と内容が大きく違い(映画としては1作品なので、前半でも後半の話題は出るし、逆も同じ)、前半は映画のタイトル通り、いわゆるLGBTQのQの話ですが、後半はいわゆる違法薬物の話で、前半はまだしも後半は日本ではなじみがほとんどない上に、その摂取を前提として「よくわからない展開」が続くので、そこ、特に後半の理解がかなり難しいのでは(フランス映画のように考えさせる映画に近いといえば近いが、日本では当然違法薬物の所持や使用は禁止なので、追体験も「予習」もしようがない)といったところです。前半のLGBTQの「Q」の部分もモザイクがあったりなかったりと本国(原作)の基準は謎ですが、一応レーティング相当で、そこまで気になるところはありませんでした。
他のレビューでも触れられている通り、本作品は作家のウィリアム・S・バロウズや、その小説(の映画化が、本作品)、特にウィリアム・S・バロウズのことを知らないと詰む部分が多々あり、そこが判断が分かれるかなといったところです。
ただ、人を不愉快にするような発言はほぼないですし、多少社会的にどうかと思われる部分はありますが、レーティング相当ではあるし、不愉快にさせるようなシーンがないというのは減点対象においてファクターをしめますがそれがほぼないこと、また、前半のLGBTQの「Qの部分」の問題提起も理解しなくもない(日本ではそういった作品はどうしてもミニシアター等に回りやすい)ことも考えてフルスコアにしました。
ただ、映画館に「娯楽」を求めていく立場ならちょっとどうかな、といったところです。
ただ君が好きで
ウィリアム・バロウズについて予習必須
中年おじさんと美青年の切ない恋物語…ではなかったです。
「君の名前で僕を呼んで」のようなピュアな物語を期待していくと200%裏切られます。
チラシに騙された!と思って鑑賞後によく見たら、ウィリアム・バロウズの自伝的小説を映画化とあり、そこを完全に読み飛ばしていました。
バロウズについては後述しますが、ここを読んでバロウズって誰?と思った方は名前だけでもググッてから観たほうがよいかと思います。
作品の理解度に大いに関わってくるので。
(ここまで読んで欲しかったので公開していますが以下、ネタバレしています。)
序盤から主人公2人の物言わぬ会話と、暗示的な映像が続きます。
ダニエル・クレイグの役はみっともない中年男性だとはわかっていましたが、リーはメキシコで自堕落な生活を送っているという設定で、見た目も汚らしくてスクリーンを観ていてどんより。
ユージーンの美しさが救いでしたが、こちらはこちらで台詞がなさすぎて何を考えているのかわからない。
舞台が第二次大戦後のようなので、リーは恐らく戦争のトラウマからの薬物中毒なのかな?と推察しましたが、確信は持てず。(後で見当外れだとわかりました)
前半は頭の中に?マークが浮かびながらもなんとかついていきましたが、後半のダウナー系おくすりキメパートは完全に置いていかれました。
結局、純愛とはなんぞや…と頭が??マークでいっぱいのまま、劇場を後にしました。
原作者のバロウズは著作では「裸のランチ」が有名。(D.クローネンバーグが映画化していますが、グロ映画だった記憶)
ゲイ(またはバイ)でジャンキーで、自分の妻の頭にショットグラスを乗せて誤って射殺したという曰く付きの人物。
映画の中の数々の悪夢のような描写にやっと納得がいきました。
インテリ気取りの白人で薬物中毒者って、ほとんどクズ…にしか思えませんが、いちおうカリスマ的作家なんですよね。
映画を作る側、演じる側にしてみれば魅力があるのでしょう。
薬物中毒者の心象風景の映像化がメインで、クイア要素はおまけ、なので、そこを間違わないように。
俳優さんはセックスシーンを頑張っていましたが、モザイクありとなしの基準が謎でした。
全65件中、41~60件目を表示