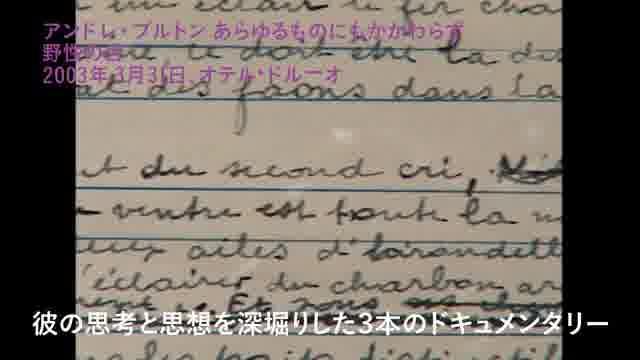「ようこそ、アンドレ・ブルトンの「驚異の部屋(キャビネ・ド・キュリオジテ)」へ!」アンドレ・ブルトン ドキュメンタリー集 じゃいさんの映画レビュー(感想・評価)
ようこそ、アンドレ・ブルトンの「驚異の部屋(キャビネ・ド・キュリオジテ)」へ!
シュルレアリスム100 年映画祭、鑑賞4本目。
アンドレ・ブルトンのアトリエを埋め尽くしていたコレクションを紹介する、三本のドキュメンタリーをまとめた60分ほどのプログラム。
1本目の「アンドレ・ブルトン あらゆるものにもかかわらず」
冒頭に、2003年にパリのオークションハウス「オテル・ドルーオ」にて開催されたブルトンの競売(チラシやHPの説明には「コレクション展」とあるが、一週間の展示のあとの競売で全て売り払われ、60億円もの利益を生み、コレクションは散逸した)を準備する開幕直前の様子を収め、そこからブルトンの生涯と芸術的な寄与について包括的に紹介してゆく。ただ、語り口はきわめて晦渋かつペダンティックで、ブルトンの業績について詳しくない人間が初見で内容を理解するのは、かなり難しいと正直思う。
2本目の「野性の目」
1本目のドキュメンタリーである程度紹介されていた、アトリエ内のコレクションをじっくり見せる内容。あたかもアトリエ内に入ることを許された人間が入念に見て回るかのように、一人称視点のカメラが、いくつかの部屋を行ったり来たりしながら、壁一面を占拠するありとあらゆる文物をねめ回していく。リアルに現場で鑑賞する感覚を共有できる作りだ。
いろいろと発見の多い愉しいドキュメンタリーではあるが、何一つ解説もなければテロップも出ない超★不親切仕様であることに変わりはなく、せめて日本人向けに作品名くらいは出して良いのでは、と思いました。
3本目の「2003年3月31日、オテル・ドルーオ」
前述の「オテル・ドルーオ」でのブルトンのコレクション展&オークションの全貌を記録。こちらも、展示の様子を部屋ごとに一人称視点で見せていくつくりだが、「野性の目」と違って、かなり足早。せかせかと、気になるコレクションに目を留めるひまもなく、駆け足で部屋をフィルムに収めていくことに汲々としている感じで、もう少しじっくりポイントをつくって見せてくれればよいのに、というのが率直な感想だ。
ただ、我々はこの映像を観る際に、これがアンドレ・ブルトンの4000点強に及ぶ巨大コレクションの「最期」であることを胸に刻む必要がある。数日後には好事家たちに全て売り払われてしまったという事実が喚起する「喪失と消失の痛み」を心のうちに抱きながら、眼前の「コレクションの死」をしかと受け止めるべきだろう。
― ― ―
アンドレ・ブルトンという作家・思想家・デマゴーグのありようを考えるうえで、この膨大にして圧倒的な「コレクション」の意味は、計り知れないほど大きいと思う。
ブルトンは、美術家としては必ずしも「実作」がメインの人物ではなかったが(とはいえ、彼の制作したちょっとしたイラストやコラージュは、十分にプロと呼びうる仕上がりだ)、少なくとも「見極めること」と「収集すること」に関しては、まさに人生の全てと生命の全てを捧げた、ホンモノのコノワッサール(目利き)だった。
彼は、彼の美意識とお眼鏡にかなう文物と書物と人物(の作品)を周辺に執拗に集め、それを独自の価値体系のもとにまとめあげて、「ブルトンの小宇宙」としてアトリエ内に「ひとつの美の体系」を形作った。
その在り方は、先鋭的で前衛的だった彼の思想・芸術運動とは対極的に、どこまでも西欧の王侯貴族的であり、復古主義的ですらある。
これはいわゆる、ブルトン流の「驚異の部屋」なのだ。
驚異の部屋。あるいは、ドイツ語でヴンダーカンマー。
澁澤龍彦や種村季弘を読みふけっては、異形への夢想を募らせる妖しい青春を送った僕のような人間にとっては、こたえられないほどに郷愁をそそる言葉だ。
15世紀のイタリアで始まり、やがてドイツで王侯貴族以外に学者や文人にも流布した、私的な「珍品博物陳列室」。それが「驚異の部屋」だ。ちなみにブルトンの母国フランス語では、 Cabinet de curiositésと呼ぶ。
そこでは人工物と自然物の区分もなく、ありとあらゆる「珍奇」なものがコレクションされ、室内を埋め尽くし、嗜好のミクロコスモスを形成した。当時の貴族やブルジョワジーは、金に飽かせて「世界の珍品」を買いあさり、自らのコレクションを形成し、その独自性とセンスと蒐集力を競い合った。
彼らのコレクションには概ね、強烈な博物学的関心と、異界もしくはマージナル(辺境)へのあくなき憧れ、そしてグロテスクと「驚異」への身を焦がすような拘りが刻印されていた。
アンドレ・ブルトンは20世紀初頭において、まさにみずからのアトリエを「驚異の部屋」化しようと試みた「名うての好事家」だった。
彼のアトリエを彩っていたのは、必ずしも盟友であるシュルレアリストや先達の芸術作品だけではなかった(とはいえ目立つところにミロやダリ、ピカソ、タンギー、エルンスト、ムンク、カンディンスキーあたりがかかっているのは、このドキュメンタリーを観た方ならお気づきの通り)。むしろ9割方を占めているのは、ネイティヴ・アメリカンやアフリカのエスニックでプリミティヴな人形や道具、造形品だった。あるいは、野鳥のはく製や昆虫標本といった自然史的な事物も多く蒐集されていた。パンフによれば、はてはワッフルの金型まで86本も蒐集していたという。これはまさに、精神の在り方からして「驚異の部屋」に他ならない。
なぜそこに僕がこだわるかというと、ブルトンを思想的支柱として20世紀に花開いたシュルレアリスム芸術の根幹には、むしろモダニズムとは正反対のゴチック趣味、あるいはバロキシズムがあったのではないかと思われるからだが、ここでは深入りしない。
まずは、20世紀を塗り替えるような芸術運動を率いた人物が、15世紀~18世紀の王侯貴族のようなコレクション活動を行い、その蒐集行為自体が彼の芸術的審美の根幹にあったことが確認できれば十分だ。
なにより、異なるドキュメンタリーのなかで、二度重複してブルトン自身の肉声で、彼にとって最も重大な美的衝動が「驚異」であったことが語られている。
「驚異」。これがキーワードだ。
だからこそ、ブルトンは初期にはダダイズムに傾倒して、ともに立ち上がったのだった。既存の「美」ではなく、「驚き」をも芸術の目的に加えたいと思ったから。
だが、ただ旧来的な価値観を「壊す」だけのダダでは、ブルトンは飽き足らなかった。
きちんとした審美体系として「驚異」を組み込みたかったのだ。
そのために、彼が「引き込んだ」のが、フロイトの精神分析だった。
何よりも、ブルトンが実現したかったのは、バロック的な趣味と精神の中枢ともいえる「驚異の部屋」の幻想を、美の規範としてモダニズムに「ねじ込む」ことだった。
その意味では、この魔法のような「がらくた部屋」にこそ、ブルトンを支えた芸術思想の「核心」があったともいえる。
なんにせよ、ブルトンの「驚異の部屋」のコレクションは、永遠に失われた。
人生を賭して蒐集したとしても、その一生が終われば、いつしか散逸してゆく。
それがコレクションの運命(さだめ)であり、
そのかぎろいの如き一回性のせつなさゆえに、
コレクションは人を魅了するのかもしれない。
このドキュメンタリーは、説明不足で不案内なつくりながらも、ひとつの壮観といっていい個人コレクションの、まさに「最期」の瞬間をフィルムに残してくれた。
そこで表出されているのは、蒐集家ブルトンに対する最大限の敬意であり、
集められ、また離散してゆく「呪物」たちへの、限りなき惜別の念である。