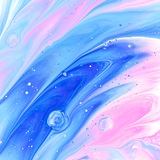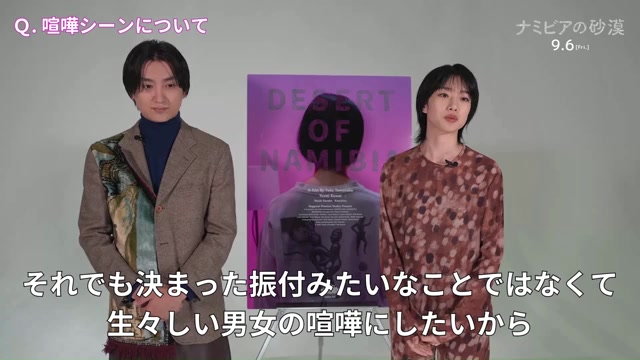ナミビアの砂漠のレビュー・感想・評価
全84件中、1~20件目を表示
現代を砂漠にするのはまだ早い
カナの頭の中は分かった気がする。
頭の中ではランニングマシーンが稼働して、常に世界で動くことが求められる。部屋の中でも、横になっても休めない。精神の疲労を身体の疲労に同期することが求められる。ゆえに暴言を吐き、身体を暴れさせる。
カナと現況が似ている人や、それを現代の若者像と素描したい人には必要であり、求められる物語であるのは一定理解はできる。
しかし私は朝子のように「だから、謝らへん」。
本作を批判的に取り上げるには、3つの障壁がある。それは①河合優実のトップレスをみてしまったこと②男性クリエイター批判があること③精神疾患に物語が回収されていること、である。
この障壁はなかなかに手強い。河合優実の身体のあり様が凄かった。男性クリエイターの性加害やハラスメント問題は全く解決されていないから、それをトピックとして取り上げたのは素晴らしい。カナのような女性像は今まで捨象されてきたから、映画として現前させたことは一つの肯定の仕方でよい。そう言うことはできる。もちろんそれらに反論するつもりはない。しかしそれで全てを済ませていいのか?とも思ってしまう。
まず、カメラが酷いと思うのは私だけだろうか。
手ブレが酷い。冒頭のカフェのシーンのように、なぜ室内のシーンで固定カメラではなく、手持ちが採用されているのかがよく分からない。さらにカメラが移動する際、人物を追えていない。撮り逃しが生じている。その手ブレをカナの精神の不調、カメラワークの酷さをドキュメンタリーらしさということはできる(動物のドキュメンタリーを想起してほしい。カメラが追おうとしたり、ズームをしても何も起きなかったり、逃げてしまうことがある。そういった描写が本作にはある)。
けれどカメラのブレがカナの精神の不調を表現しようとも、それは「カメラが偽装しているカナの精神の不調らしさ」であって、当のカナの精神の不調と全く同期していない。それどころか不和が生じている。さらにカメラワークは例えば、肝心なカナと唐田えりか演じる隣人の女性の想像世界か現実なのか分からないあの幻想的な火の飛び越えを全く綺麗に撮れていないから、単に下手であるという感想しか持ち得ない。
このように本作は全体を通して、カメラが不調をきたしている。だからその不調さに私も気持ちが悪くなって、カナが精神疾患かもしれないと明かされるまで、苦痛な時間を強いられた。
物語それ自体に立ち入れば、本作が道徳とジェンダーロールの転倒をひとつのトピックにしていると解釈はできた。
冒頭のカフェのシーンで、カナの頭の中では知人の自殺と他人の話すノーパンしゃぶしゃぶが同等の話題でしかないことが音声イメージの巧みな表現で明らかになっている。さらにこの道徳の転倒が、カナには安定した彼氏がいるのに別の男がいる性の奔放さや、虚言癖であることのヤバさに結実していくのである。
しかしカナをヤバいと思うのは女性だからであって、上述のことを映画に登場する男たちに置換すれば、紋切り型の話でしかないことがわかってくる。だって、妻子を持った男が、魅惑的な女の虜になって、円満な家庭生活が崩壊していく物語なんて腐るほどあるじゃないですか。
だから男の領分とされた映画において、本作ではジェンダーロールを転倒させ、カナにかつての男を、ヒステリックさを元カレに演じさせる。そして無根拠な暴力に晒されたり、原罪を負わせることを今カレに配置し直す。その試みは面白いとは思う。
だが問題は社会が存在しないことである。彼らが生きている現状は理解した。カナをヤバいと思ってもいいが、それは男一般に言えることだとは分かった。しかしカナたちはどう生きるの?
社会が存在しない世界観はとても現代的だ。新自由主義思想に経済も政治も侵される現代は、市場原理によって全てが統治されて、社会保障は徹底的に削減される。国家も社会も守ってくれない。だから個人の能力と責任で自力に「生き延びるしかない」。
そんな現代に生きていたら、生活と世界が社会を飛び越えてダイレクトに接続される。その様は、カナがソファにくつろぎ、スマホでナミビアの砂漠のライブ映像をみている姿であろう。ダイレクトに繋がると私たちは引き裂かれる。生活と世界の問題は別個であるはずなのに、直接つながる。しかしそれぞれの次元はそれぞれの次元に何ら解決を与えない。それなら問題は解決はされないから生活の何もかもが詰んで、都会であっても砂漠同然となり、精神疾患になってしまうのも当たり前だ。
しかし現実にはやはり社会は存在するのである。だからあたかも社会が存在しないかに偽装する本作はカナらの問題を何ら解決させない/できないし、私たちに慰めを与えるしかできない。
カナと今カレの家賃はどうしているのだろう。東京の郊外であっても、十分な広さがあるファミリー向けの部屋は相当高いのではないだろうか。21歳の脱毛サロンの彼女と脚本を書いているクリエイターもどきの彼にそんな経済力があるのだろうか。彼の実家が裕福な描写はあるから、親の所有する不動産なのかもしれない。ただ仮に彼らが家賃を払っているのであれば、カナの経済状況から容易に辞める選択はできないだろうし、親が所有または家賃を払っているのなら、今カレがカナと別れない理由が分からない。このように彼らの置かれている社会背景が不明瞭であるならば、カナが精神疾患にならざるを得ない現状の訴えに説得力が欠けてしまう気がする。「で、カナは何に悩んでいるの?」で一蹴されてしまう。
「ティンプトン」でいいのだろうか。分からない、分からないと何度も繰り返し、病的で破綻した生活を送れば。でも私はそんなの嫌である。
上述の生活空間の描写のように、本作に登場する彼らー特にカナーはリキッドした学校の中を生きているように思えてしまう。全てが大人に所与されている。部屋も職場も食事も何もかも。まずは自分でご飯を作ってみなよ。バーベキューの準備をしてみなよ。後輩も働きやすい職場をつくってみなよ。全然一からじゃなくていい。上手くなくてもいい。けれどそんな社会への働きが、カナの体調を改善させるのではないか。というか精神疾患で、全ての問題を片付けるな。原因は個人ではなく、社会にもあるのだ。そしてもちろん不調を医学的に診断し、名前をつけ、治療することもまた当然に必要であるが。
そう思うのも、カナの現状を擁護するだけで終わりたくはないからだ。というかそれなら、あまりにも他人事過ぎませんか?カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞したのも、「現代の日本で生きる若者は大変やな。まぁ、私たちの社会には関係ないからあんま知らんけど」とか、本作を評価する親世代以上の人たちも「子どもたちは本当に大変やな。まぁ、自分の子どもはインターに通わせるからあんま知らんけど」であるなら最悪じゃないですか。もちろんこれは私の妄想ではある。しかしやはりカナが生きれる社会をどうつくれるか私は考えたい。
長くなってしまった。カナが脱毛サロンの店員から、「脱毛」を取り巻く社会の強迫観念がもっと主題にあがってくると思っていたしー介護脱毛ではない、広告や若年化、ルッキズムー、カナが仕事を辞めてからはどう脱毛するのか期待していたが、全く後景に退いて悲しかった。けれど「原罪」というのはひとつの主題のような気がした。生えてくるのが罪かのようなムダ毛。そしてムダ毛的な事態は、生きていることが罪かのように、消費活動に駆り出される現代に横滑りする。さらにそんな観念を内面化して、私たちは生まれなければよかったと思ってしまう。反出生主義だ。だが私はもう反・反出生主義者なので、未来を向きたい。
そして現代を砂漠にするにはまだ早い。
戦いに疲れ、傷つき、怒るヒロインは大都会のヌーなのか?
友達からカフェに呼び出され、共通の友人が亡くなったことを聞かされてもどこか虚なヒロイン、カナは、同棲中の恋人に管理されているような生活を続けながら、別の男とラブホデートがやめられない。カナはいったい物事のどこに共感し、どこに自分の幸せを見出そうとしているのか?
途中で見えてくるものがある。友人も恋人たちもみんな自分勝手かつ本音と建前が乖離しまくりで、会話の途中で突然キレることが多いカナのストレスの原因は、どうやらそこにありそうだということが。だが、それさえ世間は躁鬱病という枠内に押し込もうとする。カナの頭の中の?は膨らむばかりだ。
他にも、カナの血族に関するあれこれとか、脚本も兼任する山中遥子監督はヒントになるカードをあちこちにばら撒いて、終始観客の集中力を途絶えさせない。こんな握力がある映画は珍しいと思う。
握力の一端は、カナを演じる河合優実の常に目と唇から力みを取り去った放心状態のような演技にもある。
題名は『ナミビアの砂漠』。劇中で、カナは携帯動画が映し出す砂漠のオアシスに群れるヌーに何を見ているのか?砂漠=現代社会、ヌー=自分と解釈するのは単純すぎる気がする。平日の新宿、劇場は若い女性観客で席の約9割は埋まっていた。
ナミビア砂漠でつかまえて。 確かにあのライブカメラは面白い( ͡° ͜ʖ ͡°)
深い憤りを覚えながら日々を生きる女性、カナの日常を描いたヒューマンドラマ。
監督/脚本は『21世紀の女の子』やテレビドラマ『今夜すきやきだよ』の山中瑤子。
主人公、カナを演じるのは『ちょっと思い出しただけ』『ルックバック』の河合優実。
カナの恋人、ハヤシを演じるのは『おっさんずラブ』シリーズやドラマ『サンクチュアリ -聖域-』の金子大地。
精神科医、東高明を演じるのは『愛がなんだ』『浅草キッド』の中島歩。
第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞するなど、国内外で高い評価を受けた話題作。監督の山中遥子は当時27歳。この若さで長編映画の監督を務め、しかもそれが世界的な名声を獲得してしまうんだからこれはもう大したものである👏
カナを演じる河合優実は、高校時代に山中監督のデビュー作『あみこ』(2017)を鑑賞し衝撃を受け、監督に「将来女優になるので、その時は私を起用してください!」という熱烈なファンレターを手渡ししたのだそう。今回の山中監督と河合のタッグは、その時の縁に由来している。
本作は最初から最後まで河合優実の姿をカメラで捉え続ける。ほとんど彼女の一人舞台であると言えよう。カナは河合に当て書きされたキャラクターであるため、その存在感やリアルさは尋常ではない。彼女の演技力も相俟って、本当にカナという激烈な女性の生態を覗き見ている様な気分になってくる、とにかく不思議な手触りのする作品である。
河合優実と金子大地は『サマーフィルムにのって』(2020)で共演済み。この時はほんわかした高校生を演じていたのに…。『サマーフィルム』は大好きな映画なので、なんだか観てはいけないものを観てしまった気分。
女たらしを演じさせたら、金子大地の右に出るものなし。松居大悟監督のロマンポルノ『手』(2022)でも人当たりの良いクズ男を演じていたが、今回もまぁ憎たらしいいけずを熱演。ハヤシと『手』のクズ男は同一人物なんだと思いながらこの2作を連続鑑賞すると、カナが抱える怒りの解像度がよりはっきりとする事だろう。毎回毎回、羨ましい役どころばっかり…。けしからんぞ!
描かれるのは、東京で暮らす21歳のリアルな空気感。「日本は、少子化と貧困で終わっていくので、今後の目標は生存です」とは強烈なパンチラインだが、これは今の若者なら誰もが共感するのではないだろうか。
若い監督がほぼ同世代の心の声を代弁しているだけあり、時代の切り取り方が上手い。邦画界ではこの前年、ヴィム・ヴェンダース監督による「足るを知る」映画『PERFECT DAYS』(2023)が国際的に評価されたが、本作と比べるとこちらはいかにも爺むさい。全く異なる日本感を打ち出したこの2作を比較すれば、若者世代とシニア世代の隔絶を理解する事が出来るだろう。
映画を支配するのは圧倒的な「怒」の感覚。若い女性の怒りという点ではエメラルド・フェネル監督の『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020)を想起したりもしたが、『プロミシング』が女性への性暴力をはじめとした社会問題に対して怒りを爆発させていたのに対し、本作で描かれているのはカナの抱える個人的な怒り。若さと精神的ストレスでコントロール不全となった彼女の感情の暴走こそがこの映画の推進力になっており、ウーマン・リヴやフェミニズムといった社会性は希薄である。つまりこれは何に対しても苛立ちを抑えきれない、漫画家・荒木飛呂彦の言うところの「怒の季節」を扱った作品であり、ジェンダーではなくメンタルヘルスがテーマとなっていると言えるだろう。
女性映画だと敬遠している男性もいると思うが、この映画は男女の別の無い広汎的な事柄を活写した作品であるので、一度は鑑賞してみる事をお勧めする。
ハヤシと同棲を始めたカナは鼻ピアスをつけ始める。これは彼女のパンクな一面を表現するのと同時に家畜の鼻輪をも想起させる、今後のストーリー展開を示唆する重要なアイテムであるが、それ以前に金原ひとみの「蛇にピアス」(2003)を思い出させた。偶然かな?と思っていたのだが、どうやら山中監督は金原のファンであるらしく、彼女の作品が本作に影響を与えた事を公言している。そう考えると、この鼻ピはあまりにもストレート過ぎる…😓
その他にも、文学からの影響を感じさせる点は多く、例えば元カレのホンダが北海道に出張している間にお腹の子を堕すというのは村上春樹の「ねじまき鳥クロニクル」(1994-1995)にその通りの展開があったし、カナの精神的乱調はサリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」(1951)にルーツがある様な気がしてならない。
また、女性主人公の主観的物語である上に山中監督自身の心境を反映しているのであろう潔癖なクリエイター論が吐露されている点など、太宰治の書く女性告白体小説、特に「きりぎりす」(1940)のスピリットを強く感じる。「メンヘラの暴走」、乱暴な言い方になるが本作はそう言わざるを得ない内容であり、確かに他ではあまり見ないタイプの映画ではあるのだが、文学の世界では太宰が80年も前にすでにやり尽くしている訳で、そこに革新性は別に感じなかった。
〈この世では、きっと、あなたが正しくて、私こそ間違っているのだろうとも思いますが、私には、どこが、どんなに間違っているのか、どうしても、わかりません〉という「きりぎりす」の最後の一文は、本作の全てを表している。やっぱ太宰はええなぁ…。
20代でこれだけの大作を監督したという点は確かに凄い。時代の切り取り方やリアルなキャラクター造形も賞賛に値する。ただ、面白いかと言われると…。全体的にダラっとしていてメリハリがなく、だからと言ってそこに面白みを見出せるほどのユニークさはない。
カナがハヤシにエコー写真を突きつけ、「これ何なんだよっ!!」とブチ切れるシーンは「おっ!やったれやったれ」とアガったりしたのだが、そこが映画のピーク。その後もダラダラダラダラと物語は続く。もういいだろそこで終わりで…。
社会に蔓延る「本音と建前」を許容する事が出来ないカナの愚直さには、『ダークナイト』(2008)のジョーカーっぽさを感じたりもしたので、最終的に銀行強盗したりビル爆破したりしてくれればあげぽよ〜だったのに。いやそういう映画ではないのはわかってるんだけど。こんだけ文学のかほりをさせているんだから、やっぱ最後は檸檬型爆弾で丸善ブッ飛ばすくらいの飛躍を見せて欲しいよね。
90分程の短尺であればあるいは好きになれたのかもしれないが、いくら何でもこの内容で137分というのは冗長過ぎる。無駄に長いというのは昨今の映画の悪癖だが、本作も御多分に洩れずといったところでしょうか。
批評家筋には評判が良いようだが、一般観客にはあまりウケていない本作。正直、自分もこれがそんなに絶賛される程の映画とは思えない。これから先もメディアは山中監督を時代の寵児として持て囃すのだろうが、あまりにもチヤホヤし過ぎると太宰の「水仙」(1942)みたいな事になっちゃいますよ。
※本作の鑑賞によって得た1番の収穫は、ナミブ砂漠のライブカメラ配信というものがあるのを知れた事。水飲み場にやって来る野生動物をただ眺めるだけなのだが、これは確かに面白い!ついつい観てしまう不思議な魔力がありんすね🦒
出演者さんがいい
出ているメイン俳優さんがいいです。
河合さんが出ているので見ましたが、
グランメゾンの俳優さんがより一層いい味が出てる俳優さんになってて、とてもよかったです。
男性2人とも色気がある模写というか、撮り方がうまくて、素敵でした。
河合さんは、歩き方や、仕草、目つきからその人の性格や、素性を表現するのが凄いなぁっておもいました。
始まって瞬間から歩き方がとんでとなくて、こういう感じの人かって言うスタートで見始められました。
上映中の音楽の音と、声の音の高低差がすごすぎて、
ベクトルをどちらかに合わせると、引くほど声がでかいか、引くほど声が小さいかになってしまい、小さくすると本当に全然最後の方とか聞こえなくて、何度も見返しました。
終わり方が突然すぎて、消化不良おこしすぎましたが、こう言う作品なんだなって思って見終えました。
河合さん、素敵です、彼氏役の2人の演技と良かったと思います。
自分自身へというか、自分の元々あった周りの環境コンプレックスがある人なのかなって思いました。
前半は進むので見ていられますが、後半は、私には難しいというか、ハマりませんでした。
結局河合さんの家族の内容はざっくりとしかわからず、自分は浮気しているけど、彼氏が風俗に行ったら別れる女、そして暴力的、
依存体質同士が惹かれ合う恋愛なのかなぁーて。
集中力が切れてしまいちゃんと見れてなかったのかもしれません。
河合優実さんじゃないと成立しない
あんのこと、に続き、またえらいクセのある役柄だなと。
だけど、河合優実さんがやると、
「カナ」として成立する不思議。
結構激しいシーンもあったのに、全体的に淡々と終わりました。
いきなりエンドロールになったのでびっくりして少し戻してしまったくらいです。
河合優実さんの世界観中心に回っているお話なのですが、
他の方のレビューで「唐田えりかの登場に救われた」とあったので
唐田えりかさんの登場で何か大きく動くのかなと思ったけど、
やっぱり淡々としていました。
ただ、カナの気持ちの理解者として、カナの中では大きな安心感があったのかもしれません。
ちょっとしか出なくて特に交流も描かれなかったけど
そういう存在が、双極性障害の人にとっては重要なのかもしれないですね。
とはいえ、病気がメインテーマと言うのでもなさそうだし、
テーマとか考えると難しい内容だと思います。
カナという女性の人生のワンシーンくらいに思って観るといいと思います。
変人オンパレード
詳細は知らずに「あんのこと」の熱演で注目した河合優実目当てで観賞
結局、生きづらさを抱えながら目標もなくただ生きることに注力している女性を描いたんだろうがなんだろう
私には贅沢な悩みを持った甘えた女の行動、言動をただ見せられてるとしか思えなかった
何か趣味を持とうとか仕事を頑張ろうとかもなくただボーっと生きて男を利用しているわがままな女
病気と言ってしまえばそれまでだが、それなら必死に戦う姿を描いてもよかった
この世には病気で生きられない人もいる中でこんなの悩みのうちに入らないよ
ラストあたりて出て来た隣人の唐田えりかさん(お久しぶりです)の言葉が全てじゃないか
現実に居たら同居なんて耐えられないしちゃんと病院に通いなさいよと言いたいですね
よく分からない映画でした
なんて思うのが正解ですか?
なんか、なんやろ
ずっと、ヒリヒリムズムズ、痛くてかゆくて
全員に見覚えがあるし、なんなら私の中にもいるし!
これを精神病の人間を描いた映画だとかいうやつとは仲良くなれないなあ
まあそれはどうでもよくて
うーんいかにも、って感じのような、いやそういうわけでもないな
ほんとうに言葉にできないんだよー
これって私がバカだから?うーーん
でも、見終わった後の心模様はわるくなかったから、それでいいの
ps
youtubeにあのナミビアの砂漠のライブ映像あった
一方そのころサバンナでは…
オアシス
現代のどこにでもいる女の子が、心の病になっていく。
砂漠のような現代の生活を生きる中で、彼女にとってのオアシスだった彼氏がそうでなくなり、新しい彼氏が彼女のオアシスになったけれど、彼氏は自分のことばかりで彼女を見ていない。
心の病と、普通と言われるところの境界線は曖昧ででも明確だなぁ。
最後に、「ティンプトンってどういう意味?」という質問で、彼は彼女の方を向いたんだと思いました。
これが、現代の若者?
わがままでロクでもない女の日常、なんていったら怒られるかもしれないけど、
前半はそんな感じで見てました。過去の映画には、バイオレンス男にすがる女という
ストーリーが溢れていたけど、今の時代は逆なんだということを
描きたいのかな?なんて感じて。
で、医者が出てきて、そういうことか、病気なのか、と見方が変わりました。
不快だったんですよね、それまで、振り回されてる情けない男たちの姿を
見ていられなくて。で、病気ならしようがないと、納得。
それだけ、感情移入していたということかな(笑)。
でも、これを現代の若者の恋愛を視点で描いた、っていうのは違うだろって思う。
いや、思いたい。
河合優実さんの演技は、拍手だと思うけど。
河合優実劇場
実際ミカみたいなメンヘラがいたらまわりは大迷惑。
何一つ共感できない。
幼少期の環境でこういう人間性になってしまったなら少し同情もするけど。
いつもスマホとタバコを片手に、パンツ一丁でウロウロしているのも不快でしかないけど、河合優実だからかっこよく様になっている。とにかく魅力的でつい見とれてしまった。
こんないい男と付き合えるなら、一度河合優実になってみたいものだ。
どういう終わり方なんだろうと思っていたけど、この種の映画はだいだい何も解決せずの終わり方だよね。
ミニスカートにビッグTシャツがよく似合う。
「拾えよ」とか急にキレ出したり、本当に無理。
普通に生きるとは
すごく面白かった。
音の使い方が新鮮、冒頭のカフェのシーンの隣の会話を聞いていて友達の話を聞いていない感覚や、人に強い興味を持たない人の感覚に妙に共感した。
人の過去の過ちを引き合いに出して自分にとって有意な環境を作りだすようなことをしてしまった経験を思い出した
メンタルヘルスや脱毛に懐疑的な目線も何が正しいのか考え直そうという投げかけか?物事を考えることを放棄したくなる人が多いことを問題提起している?監督と共感した
感情が爆発しているようで頭の中は別のことを考えていたりするよなとか
みんな頭の中と表現することは違うものだし、抑制したい感情が表に出てしまうことが病気として扱われてる社会だけど、それって自然なことなの?世界最古のナミブ砂漠ではみんな感情のまま生活してるんじゃないの?的なことなのかなと、思った
それでも生きていくには他者への思いやりや思いやられることが必要だし、
感情的になる理由がわからないときもあるし
理由が何もない時もあるけど何かに叫びたくなることもあるなぁみたいな
言語化できない感覚を表現できるのが、映像なんだからこうゆう映画が増えるといい
全然まとまらないのであとで修正するとして、これは見るべきでしょ
こけおどし
日本映画には映画の品質より「俺様の才能を知らしめたい」気配を感じます。
自己顕示欲がみえてしまうのです。
海外の映画では監督の自己顕示欲がみえてくる映画がないので、これは日本特有だと思っています。
日本の映画監督全員がそうではありませんが、アート系映画のばあいはほとんどが品質の向上より自己顕示欲を満たそうとするタイプの監督だと感じます。
しかし自己顕示欲が旺盛でも能力があるならばいいわけです。たとえば大島渚は能力がともなった自己顕示型の監督でした。
転じて日本映画がだめなのは、ほとんどが自己顕示型なのに、能力がともなっていないからだと思います。
2025年3月17日にPFFが創設した大島渚賞(第6回)の授賞式があり、本作品によって山中瑤子監督が受賞しました。
山中氏は『大島渚監督は、すごく時代と社会を撹拌して転覆させるような映画を作られてきた方で尊敬しているので、身が引き締まる思いで、わたしもそういった映画をつくりたい。いま一つ企画があり、社会を転覆させる映画を作りたいと思っています!』と受賞の喜びを述べたそうです。
山中氏が表明した「社会を転覆させる映画を作りたい」は、海外の映画産業と日本のそれの違いを如実に表していると思います。おそらく、海外の作家は自身の作品世界を追求しようとしているのであって、社会を転覆させたいとは思っていないでしょう。むろん社会を転覆させたいとは衝撃的な映画をつくりたい──の比喩表現なのでしょうが、それにしても、海外の映像作家はそのような中二発言をすることより、具体的な作品のビジョンを述べるはずです。
日本映画では混沌や悪徳や反社会が、監督の自己顕示欲を満たすために使われるという状況があります。歪んでいる世界は、監督が「歪んでいる世界を描ける俺ってすげえだろ」と言いたいがために使われます。
この現象をわかりやすく例えるなら誰かを脅すときに「おれはやくざなんだからいうこときけ」という感じに似ています。
歪んで気持ち悪くていびつで悪辣で、そのような一般人にとって怖くて近寄りたくない世界を描いて観衆を威嚇することで自己顕示欲を満たすわけです。
たとえば北野武監督には自己顕示欲があり映画にもそれが見えます。暴力的な映画をつくってひたすら萎縮させ、菊次郎みたいな映画を望んでいた観衆に対して「ざまあみろ」とうそぶいてみせるのは、作品と自我が一体化した日本の映画監督らしい姿勢です。しかし北野武監督の映画はわりと面白いから大丈夫なわけです。
バイオレンスを通じて観衆を威嚇する代表的監督は園子温です。園子温の映画には前述の例え「おれはやくざなんだからいうこときけ」という感じが顕れています。「おれ」がはげしく絵に顕れる映画であり、バイオレンスや人間の狂った行動は自己顕示欲を満たすためのパラメータに過ぎません。映画を通じて園子温が言いたいのは「歪んでいる世界を描ける俺ってすげえだろ」ということであり、ほかの目的はありません。自己顕示の手段として映画監督をやっているわけです。
これは日本において映画監督という職業があたかも全知全能の才人のように扱われ見られるから──でもあります。映画監督は測ることの難しい能力にもかかわらず、また、人それぞれ評価が異なる能力にもかかわらず、巨匠や鬼才などといった安易なレッテルと相乗しながらメディアの中で常にすごい才人として扱われます。だからこそ映画と自己顕示欲が結びつくという日本特有の状況が生成されてきたのだと思います。
園子温と似たような姿勢・態度が自己顕示欲型の映画監督にはあります。
その結果、日本映画は海外にくらべ、歪んだ世界やバイオレンス映画が多い傾向にあると思います。この惑星でトップを競えるほど平和で安全な国にもかかわらず、歪んだ世界やバイオレンス映画の比率が高いことは、日本の映画監督がいかに自己顕示型の監督で占められているかの証左にもなっていると思います。
無気力なカナ(河合優美)は、最終的には何かにまとめられる人物なのだろうと思って見始めましたが、結局まとめられることはなく、映画も結論を持っていません。
ナミビアの砂漠は、園子温がバイオレンスで観衆を威嚇するのと同様に、エキセントリックな人物像と男女の救いのない取っ組み合いを見せて観衆を威嚇している映画だと思いました。
日本の映画監督には、観衆に嫌悪感を覚えさせ、神経を逆なでさせることがクリエイティブスタンスであるという誤解があります。かれらは、目を覆いたくなるような修羅場をあえて見せることが「鬼才」だと信じています。
この戦略のことを「こけおどし」といいます。
おそらく山中瑤子監督の目的は、エキセントリックかつ胸糞悪い人物や状況を描いて、観衆を苛立たせることです。映画に結論はなく、カナはよくわからない原因とよくわからない結果の間をさまよっているに過ぎません。なぜならナミビアの砂漠はこけおどしによって鬼才感を出すという山中氏の目的のためにつくられているからです。山中瑤子監督は要するに「こんな胸糞人間を描けちゃうわたしってスゴくね」と言いたいのであり、そのためにこれを書いてつくったわけです。
アリアスターが本作をほめたのは中途でボーはおそれているそっくりの客観視点がでてくるからです。ボーはおそれているは、なかばまでボーの主観で描かれていますが、どこかでボーが劇中劇人物になり映画がメタフィクションに昇華されます。
ナミビアの砂漠も中途でスクリーンに小窓が開き、あたかもカナが劇中劇人物であるかのようなメタ表現がありました。アリアスターはボーはおそれているに酷似した展開に反応したのだと思われます。ただし、カナが自分のメンヘラ気質を客観視する描写はそこからどこへもつながることなく、映画は尻切れトンボでおわります。むろんアートハウスは尻切れトンボな映画だらけですが、ナミビアの砂漠は鬼才感のある尻切れトンボな終わり方をします。なんていうか「こういう尻切れトンボな終わり方が鬼才っぽいんだせ」と言いたい感じの超あざとい尻切れトンボな終わり方をします。
俗にそれも「こけおどし」といいます。
もっとも原始的な鬼才感の出し方は、悪い人間に寄せることで、近寄りがたい雰囲気を醸成することです。北野武や園子温のようにバイオレンスを描くと「怖そう」という雰囲気が醸成され、人々は畏怖しつつ、すげえ監督なんだ──という鬼才値を彼/彼女に置きます。
山中瑤子監督は、嫌悪を感じるメンヘラ女を描くことで、バイオレンス描写と同じような効果を狙っています。そこに流行のメタフィクション細工を足して、理解の上つくっている雰囲気を織り込ませています。利口な人ではあるのでしょうが毎度の日本映画でした。
日本映画界が自己顕示型だらけなのは、日本が左翼に席巻されているからだと思います。全メディア、政界、財界、芸能界、映画界、操觚界、学会、左翼だらけです。左翼という言い方が強すぎるならばリベラルでもいいです。
どこかの映画評価機関が2023年のベスト&ワーストとして花腐しがベストでゴジラ-1.0がワーストだと公表していました。信じられますか。ゴジラ-1.0がワーストだとほざいていたんですよ。どう考えても人気作を貶めることで「おれたちは孤高なんだぜ」と気どっている中二でしかありません。個人的にはそんな評価をする人間と同じ空気を吸いたくありません。
左翼やリベラルが目指すのは日本を憎むように仕向けること──からの社会の壊乱です。人間が怠惰になり生産性を欠いた結果、国家が破滅することを望んでいるのが左翼やリベラルです。
こうした目的をもっているがゆえに日本では映画も、反社会やバイオレンスやいびつや悪辣やゆがんだ世界や反日が主流になっているわけです。わたしはなにもカウンターカルチャーがだめだとか悪い世界がだめだとか言いたいわけではありません。しかしいまの日本映画にはカウンターカルチャーのようなアートハウスしかありません。日本はひどい国で、変な人間ばかりで、クソな日常生活しかない──というような日本映画しかありません。
普通の人は映画で悪を打ち負かす勇気や苦境でも何かをまっとうする気骨とかを見たいと思いますが、今の日本映画にはそういった正義や秩序がことごとくありません。
映画監督ならば、なぜゆがんだ人物を描きたいのか考える必要があると思います。監督自身が、苛酷な体験をしたのでないのなら、恐ろしい話はホラーにすべきだと思います。
海外の映画において、ホラー仕立てではなく、現実ドラマで胸糞系がない理由は「こけおどし」になってしまうことを避けるためです。アスターもこれをホラーとみたはずであり、でなければ褒めなかったでしょう。
結局のところ、わざと不愉快な映画をめざしたのでしょうが、普通の人のわたしにとっては、不愉快な映画だった──としか言いようがありません。
デート(恋人間)DVがずっと出てくるのは辟易します
河合優実さんが主役。相手役は「鎌倉殿の13人」で頼家役だった金子大地さん。
難解な映画でした。そして、結論的にあまり面白いとは思いませんでした。
デート(恋人間)DVがずっと出てくるのは辟易とします。主人公の鬱屈を延々と見せられた上に、終わりがあって無いような物語なので消化不良で終わってしまった。
監督が訴えたいものの輪郭は何となく感じるのだけれど、物語として退屈で段々とどうでもよくなってしまいました。
河合優実さんの凄さ際立ち
現代の若者たち(この表現するあたりですでに年寄り?)の不安定な生活および精神状態を、主人公カナ(河合優実さん)と彼女に翻弄される男たちハヤシ(金子大地さん)ホンダ(寛一郎さん)がとても、絶妙に演じられてましたね!?
ちょっとヘタレっぽいロン毛男、佐藤浩市さんのご子息、三國連太郎さんのお孫さん、頑張ってました。『ナミヤ雑貨店の奇蹟』でデビューされてたんですね。(お父さんの方はスポンサーと横浜市消防局の協力が得られずACと番宣ばかりのドラマでさすがの重鎮感、レジェンドしてましたが。)
ここんとこ大ブレークの河合優実さん、さすがの、ある意味貫禄の熱演で、先日やっと鑑賞できた『あんのこと』でも感じた通り作品ごとで『あん』であり『カナ』そのものであることに感動すら覚えました。まさに河合優実劇場だったかと!
ただ彼女および他の俳優さんたちの熱演には惜しみなく拍手を贈りますが、年のせいか実在するであろう現代の若者(また使ってしまった!)の姿には共感できないためか沁みてきません。ごく近くにも情緒不安定な人たちを多々見かけたりする今日この頃、うまく描かれているんでしょうけど、私にはハマらず河合優実さんの凄さだけが印象的でした。
『ナミビアの砂漠』タイトルの意味するところが理解できていないくらいなので作品のレビューになってませんが、好みか好みじゃないかといえば後者でした。昔懐かしATG 映画みたいでした。問題作だとは思うんですけど。
これは精神疾患の女性のハナシですよ
前半は全ての伏線。
映画タイトルが作中の途中で表示されるので、
そこでそれがわかる。
主人公の女性は、その動静から明らかに
境界性パーソナリティや統合失調症を
患っている。
こういう病が一般的に認知されてきたのは
最近のこと。
一昔前だったら、「メンヘラ女子」と
付き合った男が潰れた。くらいのハナシ
にしか見えない。
確かにそういう女性は一見ミステリアスで
魅力的に思え、ハマってしまう男性の心理も
わからなくないわけではないが、こういう
女性と付き合うのはやめた方がいい。
って、自然に観れたのは何故か。
それは河合優実の演技力にあると思う。
あれだけ情緒不安定な感じや、暴れる
感じの演技を、リアルに演じきれている
ところは凄い。
ただ、脚本的には数行のメッセージは
あったものの、結局、何を訴えたかった
のかがわからない。
映画としてはイマイチ。
生きづらい…
後半から一気にカナの苦しいまでの生き辛さが爆発。精神疾患をきたしてしまったのか。かえって元彼と林を行き来してる方が安定していた。仕事してて、あれだけ邪魔されたらたまったもんじゃない。林も酷い男だが、カナの行為はガキそのもの。病気という描写に逃げてる感じもして、全体通してドキュメンタリータッチで、起伏がほしかったがそういう映画じゃないんだなと、何を伝えたいのか分からなかった。
入り込めたわけではないけど時々ハッとする
世代が違いすぎるのか、全体としては入り込める感じではなかった。そもそもなぜそこまで不機嫌なのか、なぜ暴力なのか。正直に言うと,主人公の河合優美の鼻ピアスが受け付けられないのかも。せっかく可愛いのに(笑)
後半になって,少しずつ理解が進んだ。裕福な男の家族に会うシーンの彼女の表情は良かった。そして精神科医の前で箱にはの砂をりかき混ぜ,真ん中に木を1本おくシーンはドキッとした。
社会への、周囲への、自分への思いなど言葉にできないアレコレを抱えて生きていく。河合優美の演技は良かった。
一本の木
「わからない」の一言に
いいようのない虚しさが湧く
それが彼女を表す言葉なんだとかんじた
母との会話がわからない
父のことがわからない
家族というものがわからない
友達が、仲間が、
相手の気持ちが
わからない
夢も愛もわからない
そんな自分が何よりもわからない
持て余した渇き、飢え、諦め、やり場のなさが
暴力や汚い言葉になって彼女から噴出する
自由奔放を貫く姿をみて
通り過ぎながら
痛快、クール、羨ましいと?
彼女は自分の映り方が「わからない」
差し出された木陰や水を乱暴に払いのける自分も
どうしていいか「わからない」
そしてそのもどかしさは
まわりにはなかなか〝わからない〟まま
病の枠の中へ
だけど彼女の本心はひっそりと
砂漠の真ん中に一本の木を置き代弁する
いかされない無邪気な彼女の心や
似たような誰かが
その木を求めているという事実に
小さな希望を繋いで
いつか実感できるしあわせとして
救われてほしい
修正済み
河合さんの自然な演技が魅力的でした
孤独と繋がりをめぐる現代の寓話
物語は、21歳のカナ(河合優実)が、優しいが退屈な恋人ホンダ(寛一郎)との関係に飽き足らず、自信家で刺激的なクリエイター・ハヤシ(金子大地)との新たな関係に踏み出す姿を描いています。しかし、新しい生活を始めたカナは、次第に自分自身や社会との摩擦に直面し、内面的な葛藤を深めていく。
カナのキャラクターは、一見すると無軌道で自己中心的に映るが、その行動の背後には現代社会に対する深い疎外感や孤独感が潜んでいる。彼女がスマートフォンでナミビアの砂漠のライブ映像を眺めるシーンは、現実世界からの逃避や、自分の存在意義を模索する姿を象徴しているように感じられた。
また、カナが関係を持つ二人の男性、ホンダとハヤシは、それぞれ異なる価値観や生き方を象徴している。ホンダは安定と優しさを提供するが、カナにとっては退屈であり、ハヤシは刺激と創造性をもたらすものの、自己中心的でカナの本質を理解出来ない。この対比は、カナが求めるものが単なる安定や刺激ではなく、自己の存在意義や真の理解を求めていることを示唆しいる。
さらに、映画の終盤で明らかになる、「双極性障害」カナの精神的な崩壊やカウンセリングのシーンは、現代社会における若者のメンタルヘルスの問題や、自己認識の難しさを浮き彫りにしている。カナの行動や激しい感情の揺れ動きは、観客にとって理解し難い部分もあるが、それこそが現代の若者が抱える複雑な心情をリアルに表現していると言える。
河合優実の演技は、カナの複雑な内面を見事に体現しており、その存在感は圧巻。彼女の表情や仕草、視線の一つ一つがカナの心の動きを繊細に伝え、観客を物語の深部へと引き込む。また、山中瑶子監督の独特の映像美や演出も、作品全体の雰囲気を高め、観る者に強烈な印象を残す。
現代社会に生きる若者の孤独や葛藤、自己探求の旅を描いた秀逸な作品。観る者に多くの問いを投げかけ、深い余韻を残すこの映画を27歳の山中瑶子、23歳の河合優実という若き才能が描いたことに驚かせられる。
今後も大いに期待を抱かせられた。
蛇足だがカナのイマジナリーフレンド役として、唐子えりかが端役で好演している。過去に色々あってブランクを余儀なくされたが才能ある女優なので今後の活躍を期待したい。
全84件中、1~20件目を表示