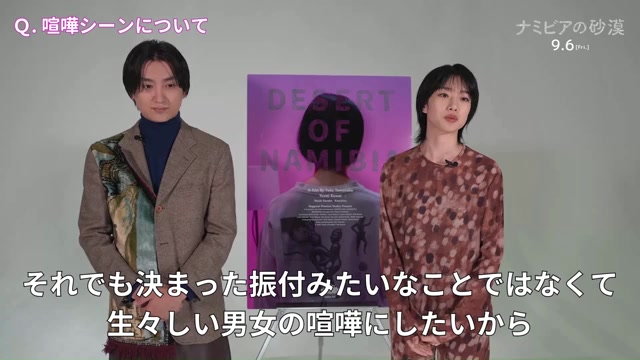「現代を砂漠にするのはまだ早い」ナミビアの砂漠 まぬままおまさんの映画レビュー(感想・評価)
現代を砂漠にするのはまだ早い
カナの頭の中は分かった気がする。
頭の中ではランニングマシーンが稼働して、常に世界で動くことが求められる。部屋の中でも、横になっても休めない。精神の疲労を身体の疲労に同期することが求められる。ゆえに暴言を吐き、身体を暴れさせる。
カナと現況が似ている人や、それを現代の若者像と素描したい人には必要であり、求められる物語であるのは一定理解はできる。
しかし私は朝子のように「だから、謝らへん」。
本作を批判的に取り上げるには、3つの障壁がある。それは①河合優実のトップレスをみてしまったこと②男性クリエイター批判があること③精神疾患に物語が回収されていること、である。
この障壁はなかなかに手強い。河合優実の身体のあり様が凄かった。男性クリエイターの性加害やハラスメント問題は全く解決されていないから、それをトピックとして取り上げたのは素晴らしい。カナのような女性像は今まで捨象されてきたから、映画として現前させたことは一つの肯定の仕方でよい。そう言うことはできる。もちろんそれらに反論するつもりはない。しかしそれで全てを済ませていいのか?とも思ってしまう。
まず、カメラが酷いと思うのは私だけだろうか。
手ブレが酷い。冒頭のカフェのシーンのように、なぜ室内のシーンで固定カメラではなく、手持ちが採用されているのかがよく分からない。さらにカメラが移動する際、人物を追えていない。撮り逃しが生じている。その手ブレをカナの精神の不調、カメラワークの酷さをドキュメンタリーらしさということはできる(動物のドキュメンタリーを想起してほしい。カメラが追おうとしたり、ズームをしても何も起きなかったり、逃げてしまうことがある。そういった描写が本作にはある)。
けれどカメラのブレがカナの精神の不調を表現しようとも、それは「カメラが偽装しているカナの精神の不調らしさ」であって、当のカナの精神の不調と全く同期していない。それどころか不和が生じている。さらにカメラワークは例えば、肝心なカナと唐田えりか演じる隣人の女性の想像世界か現実なのか分からないあの幻想的な火の飛び越えを全く綺麗に撮れていないから、単に下手であるという感想しか持ち得ない。
このように本作は全体を通して、カメラが不調をきたしている。だからその不調さに私も気持ちが悪くなって、カナが精神疾患かもしれないと明かされるまで、苦痛な時間を強いられた。
物語それ自体に立ち入れば、本作が道徳とジェンダーロールの転倒をひとつのトピックにしていると解釈はできた。
冒頭のカフェのシーンで、カナの頭の中では知人の自殺と他人の話すノーパンしゃぶしゃぶが同等の話題でしかないことが音声イメージの巧みな表現で明らかになっている。さらにこの道徳の転倒が、カナには安定した彼氏がいるのに別の男がいる性の奔放さや、虚言癖であることのヤバさに結実していくのである。
しかしカナをヤバいと思うのは女性だからであって、上述のことを映画に登場する男たちに置換すれば、紋切り型の話でしかないことがわかってくる。だって、妻子を持った男が、魅惑的な女の虜になって、円満な家庭生活が崩壊していく物語なんて腐るほどあるじゃないですか。
だから男の領分とされた映画において、本作ではジェンダーロールを転倒させ、カナにかつての男を、ヒステリックさを元カレに演じさせる。そして無根拠な暴力に晒されたり、原罪を負わせることを今カレに配置し直す。その試みは面白いとは思う。
だが問題は社会が存在しないことである。彼らが生きている現状は理解した。カナをヤバいと思ってもいいが、それは男一般に言えることだとは分かった。しかしカナたちはどう生きるの?
社会が存在しない世界観はとても現代的だ。新自由主義思想に経済も政治も侵される現代は、市場原理によって全てが統治されて、社会保障は徹底的に削減される。国家も社会も守ってくれない。だから個人の能力と責任で自力に「生き延びるしかない」。
そんな現代に生きていたら、生活と世界が社会を飛び越えてダイレクトに接続される。その様は、カナがソファにくつろぎ、スマホでナミビアの砂漠のライブ映像をみている姿であろう。ダイレクトに繋がると私たちは引き裂かれる。生活と世界の問題は別個であるはずなのに、直接つながる。しかしそれぞれの次元はそれぞれの次元に何ら解決を与えない。それなら問題は解決はされないから生活の何もかもが詰んで、都会であっても砂漠同然となり、精神疾患になってしまうのも当たり前だ。
しかし現実にはやはり社会は存在するのである。だからあたかも社会が存在しないかに偽装する本作はカナらの問題を何ら解決させない/できないし、私たちに慰めを与えるしかできない。
カナと今カレの家賃はどうしているのだろう。東京の郊外であっても、十分な広さがあるファミリー向けの部屋は相当高いのではないだろうか。21歳の脱毛サロンの彼女と脚本を書いているクリエイターもどきの彼にそんな経済力があるのだろうか。彼の実家が裕福な描写はあるから、親の所有する不動産なのかもしれない。ただ仮に彼らが家賃を払っているのであれば、カナの経済状況から容易に辞める選択はできないだろうし、親が所有または家賃を払っているのなら、今カレがカナと別れない理由が分からない。このように彼らの置かれている社会背景が不明瞭であるならば、カナが精神疾患にならざるを得ない現状の訴えに説得力が欠けてしまう気がする。「で、カナは何に悩んでいるの?」で一蹴されてしまう。
「ティンプトン」でいいのだろうか。分からない、分からないと何度も繰り返し、病的で破綻した生活を送れば。でも私はそんなの嫌である。
上述の生活空間の描写のように、本作に登場する彼らー特にカナーはリキッドした学校の中を生きているように思えてしまう。全てが大人に所与されている。部屋も職場も食事も何もかも。まずは自分でご飯を作ってみなよ。バーベキューの準備をしてみなよ。後輩も働きやすい職場をつくってみなよ。全然一からじゃなくていい。上手くなくてもいい。けれどそんな社会への働きが、カナの体調を改善させるのではないか。というか精神疾患で、全ての問題を片付けるな。原因は個人ではなく、社会にもあるのだ。そしてもちろん不調を医学的に診断し、名前をつけ、治療することもまた当然に必要であるが。
そう思うのも、カナの現状を擁護するだけで終わりたくはないからだ。というかそれなら、あまりにも他人事過ぎませんか?カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞したのも、「現代の日本で生きる若者は大変やな。まぁ、私たちの社会には関係ないからあんま知らんけど」とか、本作を評価する親世代以上の人たちも「子どもたちは本当に大変やな。まぁ、自分の子どもはインターに通わせるからあんま知らんけど」であるなら最悪じゃないですか。もちろんこれは私の妄想ではある。しかしやはりカナが生きれる社会をどうつくれるか私は考えたい。
長くなってしまった。カナが脱毛サロンの店員から、「脱毛」を取り巻く社会の強迫観念がもっと主題にあがってくると思っていたしー介護脱毛ではない、広告や若年化、ルッキズムー、カナが仕事を辞めてからはどう脱毛するのか期待していたが、全く後景に退いて悲しかった。けれど「原罪」というのはひとつの主題のような気がした。生えてくるのが罪かのようなムダ毛。そしてムダ毛的な事態は、生きていることが罪かのように、消費活動に駆り出される現代に横滑りする。さらにそんな観念を内面化して、私たちは生まれなければよかったと思ってしまう。反出生主義だ。だが私はもう反・反出生主義者なので、未来を向きたい。
そして現代を砂漠にするにはまだ早い。