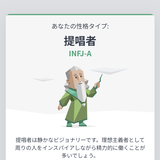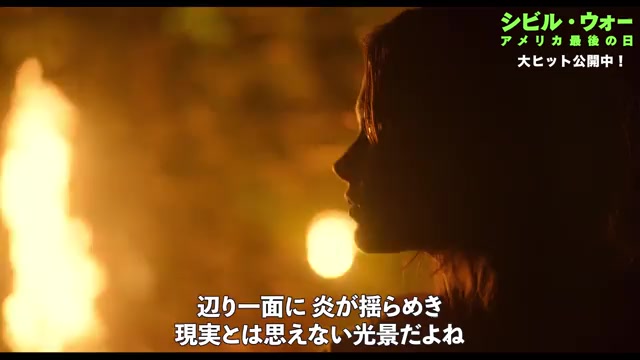シビル・ウォー アメリカ最後の日のレビュー・感想・評価
全232件中、1~20件目を表示
「真のアメリカ映画」
アメリカでは独立を試みるテキサスやカリフォルニアの西部勢力が首都を陥落させようと、内戦が起こっている。そんな状況の中で報道/戦場カメラマンのリーたちは大統領に取材をするためにワシントンに向かおうとする。リーの一向に若手カメラマンのジェシーが加わりたいとお願いする。彼女は戦場でリーに偶然助けられ、またリーを尊敬し憧れているのだ。そんなジェシーをリーは疎ましいと思いつつ、戦闘が繰り広げられるアメリカ横断の旅が始まるのだった。
画の全てが内戦状態だった。本当に報道/戦場カメラマンが現場をドキュメントしているようだったし、報道写真かにみえる構図はどうすれば撮れるのかーつまり登場人物はどう動き、カメラを置けばいいのかーが全く分からなかった。
戦闘シーンも見応えがある。緊張感が張り詰めているし、銃が乱射されている。たくさん爆撃が行われる。もちろんそれは映像イメージの卓越さでもあるが、音声イメージも素晴らしい。遠くで鳴っている銃撃の音など細部のリアリティが素晴らしいから世界観に浸れるのだと思った。
だから映画館で観たほうがいい。内戦状態の描写は娯楽性に富んでいるし、ポップコーンとか食べながらだとさらにいいと思う。きっと本作もそのようにみることを想定しているだろう。
しかしかなりグロテクスな構造だと思う。ポップコーンを食いながら、内戦状態を面白いなーと消費するのは。『虐殺器官』を書いた伊藤計劃なら『プライベート・ライアン』の冒頭15分映画と評していたはずだ。
ただこの構造こそアメリカ的だと思う。巨大な資本で素晴らしくも恐ろしい世界を映画にして、たっぷりな暴力で人をたくさん殺していく。そしてそれを娯楽として提供し、鑑賞者もまた娯楽として消費する。アメリカで内戦が起きたらヤバいけど、まあそんなことないし、というアメリカ/国民=つまり〈私〉の素晴らしさを再確認して劇場を後にする。本当は劇場の外に、内戦が起こる要因なんていくらでもあるのに。
もちろん本作はどちらかと言えば、インテリでリベラルな視点から描かれているとは思う。けれどインテリ層がこんな態度なんだから、アメリカの貧富の格差は拡大して、不法移民の労働力で収益をあげているくせに、国境を封鎖するとか言い出す実業家が大統領になるんですよ。
本作が最も欺瞞に満ちていると思うのは、リーの同僚であるアジア系の二人が射殺される場面である。アジア系の二人とは旅の途中で偶然再会し、車のかけっこ遊びをしていたのだが、一転、アジア系の男とジェシーを乗せた車が西部の人に捕まってしまう。そして死体の山を見てしまったのが原因か、それとも西部の男が単なる遊びでどうかは定かではないが二人を銃で処刑しようとするのだ。慌ててリーたちも救出のために駆け寄る。そして西部の男がある問い質しを行う。「お前は真のアメリカ人か」と。
ここで問題なのはアジア系の男のみを射殺する点であろう。アジア系の男は西部の男に「真のアメリカ人」の構成要件「白人」ではないと判定されて、問答無用で殺される。その構成要件と判定はさておき西部の男の中では理屈が通っている。しかし構成要件は「白人」だけではないだろう。「男性」や「労働者階級」ーというかブルカラーかホワイトカラーか、はたまたインテリかノンインテリか、つまり経済格差を生じさせる階級の要件ーもあるだろう。それなら西部の男に射殺される対象はアジア系の男だけではなく、全員なのである。しかしアジア系の男以外皆が殺されることを免れる。
それは今後の物語における展開の問題ではあるだろう。皆が殺されるべきとも思わない。だが、端役のアジア人なら雑に殺しても構わないという無神経さが透けているし、リーやジェシーが生かされることはいくら物語上で主体性を発揮しても「真のアメリカ人」の庇護の対象という家父長制やジェンダーの問題を隠蔽している。
こういった点から本作が決してアメリカが内戦状態になった原因について、SF的想像力を駆使して提示できているわけでも、オルタナティブな未来を創造しているわけでもない。もちろんSFには多種多様な描き方があり、本作がSF的世界観に埋没して思考実験をするのは構わない。しかしその態度こそ「真のアメリカ人」には決して殺されない語り手の傲慢な立場を明らかにしてしまっている。
そして何より本作の主題である「カメラのドキュメント性」までも毀損している。つまりいくらSF的に未来をドキュメントしようとも、現実さえドキュメントできていないし、カメラが出来事から必然的に遅れること(の反省)をいくら物語っても、何の訴求力も持ち得ないということである。
リーは判断を誤ってジェシーを連れ出し、庇って死んだ。けれどジェシーはもうリーと肩を並べるカメラマンに成長してしまったし、ドキュメントの「遅れ」を取り戻すためにリーの死を顧みることさえしない。そんな悲劇と大統領の死でもって物語は終わる。
残念ながらその切なさと大統領を殺害して撮る記念写真の果てに未来なんてない。待っているのは原因も解決も不明な混沌のみだ。この帰結は本作の判断の誤りと言っていいだろう。
「本作の判断の誤り」と記述できてしまうレビュー。レビューもまた映画から必然的に遅れてしまう行為ではある。だが、その「遅れ」が未来を訂正したり、再記述する可能性に開かれているのなら、悪くはない。
大義名分から遠く離れた最前線で、戦争は容赦なく奪う
本作のメインビジュアルはいかにもハリウッドが作りそうな戦争映画という印象だが、やはりA24は切り口が少し違う。
開幕、既に内戦はたけなわだ。内戦が起こった理由については、最低限の説明しかない。内戦になるまでの政治的な経緯より、内戦になった結果無法地帯と化した最前線で何が起こったかが、大統領に取材するべくニューヨークからワシントンD.C.に向かう戦場カメラマンたちの目を通して生々しく描き出される。
原題に定冠詞を付け「the Civil War」とすると、南北戦争を意味する言葉になる。アメリカ合衆国で独立後に内戦があったのはこの一度だけだからだという。本作の世界線ではその呼び名も変わっているのだろうか。
アレックス・ガーランド監督は、この物語において抽象的な表現をする意図はなかったと語っている。確かに「3期目の大統領任期のために憲法改正をした」という設定からは、容易にトランプ元大統領が連想される。
米大統領の任期は2期8年までと憲法に定められているにも関わらず、トランプ氏は前回の在任中に3期目を目指すことを公言した。自らが立候補した大統領選挙を11月に控えた今も、「終身大統領になりたい」と発言しているという。
本作で大統領を演じたニック・オファーマンの雰囲気も、どことなくトランプ氏に寄せたもののように見える。
連邦議会占拠事件などを目の当たりにした(トランプ非支持層の)アメリカの人々の目に、この物語は日本の観客には計り知れないほどの不気味なリアリティがあるものに映るのかもしれない。
ただ私には、現在世界で既に起こっている紛争の舞台をアメリカに置き換え、彼の地での残酷で理不尽な犠牲を、自分ごととして考えるべきだという教訓めいたメッセージを、ダブルミーニング的に孕んでいるようにも見えた。
監督の意図からはズレるのかもしれないが、それだけ紛争がもたらす悲劇には普遍性があるということだろう。
いずれの勢力にどんな正当性があろうと、ひとたび武力での対立になれば前線の行き着くところは、大義名分の高潔さからかけ離れた破壊と非人道的殺戮だ。草原に伏せて銃を構えていた2人がジョエルに答えたように、自分が撃たれそうであれば、相手の正体が分からなかろうと撃つしかない。
殺すか殺されるかという状況は簡単に人間性を奪い、動物的なエゴをむきだしにさせる。ジェシー・プレモンスの演じた兵士が象徴的だ。ダンプから無造作に穴に放り込まれた遺体の山を背景に、彼は無抵抗なジョエルの友人を脈絡なく撃ち殺す。記者たちに出身地を問い、香港と答えた記者を殺す。もはや大義はなく、ただの人種差別だ。
洗車機に瀕死の男2人を吊るして、平然と写真を撮らせていた兵士もそうだ。彼らはリーたちが運悪く出会ったサイコパスではなく、紛争の極限状況が生んだ悪魔と言っていい。
(それにしてもプレモンスはああいう不気味な役が本当によく映える。妻のキルステン・ダンストのつてでカメオ出演することになったという。カメオ出演ってだいたいはもっとチョイ役で、というイメージなのだが、彼が演じたあの兵士は一般的なレベルのカメオを超えて作品に不可欠な存在になっている)
リーたちが道中で立ち寄る異様にのどかな街の、内戦に無関心な住民もこれまた象徴的だ。なるべく関わらないようにしている、と呑気に答える服屋の店員とリーたち一行の緊張感のコントラストに胸がちくりと痛んだ。私自身は、明らかに店員の側の人間だと思う。
記者たちの悲惨な道中記は、武力衝突の制御不能な一面を見せるためのサイドストーリーのようなものだが、兵士と違って戦闘行為の当事者ではなく、かといって無関心な傍観者でもない記者の目線で至近距離から描かれる内戦は、独特の緊張感があった。
当初の印象に反して、ジェシーはある意味リー以上に逞しくなっていく。ホワイトハウスの攻防の現場で「feel alive」とつぶやく彼女には、頼もしさとかすかな怖さを感じた。
だが、映画「マリウポリの20日間」が顕著に示したように、誰かが撮らないと私たちはそこで起こったことを真に知る由もない。銃弾に倒れるリーにもレンズを向ける彼女の姿は、あなたも戦争の現実に向き合ってと、こちらに訴えかけているようだった。
余談
パンフレットのバーコードのところに昔ながらの値札シールがあったのでつい爪で剥がそうとしたら、貼ってあるのではなくそういうデザインだった。電気供給が安定しない(バーコードが使えない)作品世界を表しているのだろうか。
ヘルメット被れーーー!
この映画の予告を作った人、評論をした専門家、全員クビにしたいwww
「対立と分断」がテーマかと勘違いしてました。あたかも、トランプへの当て擦り的、グローバリストの映画かと思って、A24としては珍しくスルー。
配信に回って来たし、キルステン・ダンストとケイリー・スピーニーを観たくて鑑賞したところ。全然、主題違うやんwww
建て付けはロードムービー。主題は「継承」。物語の軸は「女性の記者としての成長」。
自分を見いだしてくれた先輩記者であるサミーの死で、鋼の精神を持つかの様に見えた、リー・スミスの戦場カメラマンとしての精神は瓦解。銃弾の飛び交う中に飛び出す勇気は消失。「そこで起こっていることを記録するだけ」と言う、極めてクールな考え方も消え、後輩記者の命を救おうとする人間性を取り戻すが、それが仇となり命を落とす結果となる。一方、新米記者のジェシーは、リー・スミスの魂が乗り移ったの如く、戦場を駆け巡る
前々回の大統領選時、群衆がホワイトハウスになだれ込んだんで、軍なら突入出来るだろ。とか、チャウセスクは、即刻射殺さてたんで、まぁ、似たような事が起きても良いだろ、とか。ミリタリー的には、結構トンデモ設定でしたが、テンションが調度良い塩梅で、普通に入り込めました。
面白かった。
割と。
運が良かっただけのスクープ写真
戦場カメラマンに憧れるジェシーがNIKONのフィルムカメラFE2を使っていたのでびっくりしましたが、電源を確保するのが難しい状況ではアリなのかもと理解しました。
最後ジェシーは大統領射殺のスクープ写真を撮ることに成功しますが、先輩カメラマンにお膳立てしてもらって運よく撮れただけなので、その後も調子に乗って戦場に行けばすぐ死亡するのが目に見えています。
大統領の行方を自分で嗅ぎ当てていれば違った印象になったと思います。
新人カメラマンの成長を描きたかったのであれば失敗でしょう。
壮大な内輪揉め
何があったかわからず二分化された国の話。南北戦争→東西戦争に?なったということか。どんなアメリカ人?というセリフがあったが、肌の色で差別する様子は描かれていないから現代的な争いだとわかるが、戦争の悲惨さを若い世代が聞いた情報を現代に落とし込んで戦争するとこうだろうなーという描写は正確だと思う。
結局のところ価値観の押し付け合いで、承認欲求の成れの果てで、価値観の多様性を受け入れているように見えるが、「どんなアメリカ人?」の返答次第で生死が決まるシーンは、戦争は多様性を奪い単一性に矯正・強制的に執着させようとすることなのだなと。
多様性を嫌う人間が、受け入れられない人間が、起こしがちなのが争いなのかなと。
テーマはいいですが、現代のジャーナリズム精神の希薄さの描写もいいですが、エンタメとしてはうーん
思ってたんと違ったwww
ジャーナリスト目線で治安が終わってるアメリカを巡る旅してる映画です。結構地味な作品なのでながら見にちょうどいいです。仕事しながら見てました。予告見た時から「あ、これ、c級映画だ…」って予感当たってました。
主人公は撮りたいものが撮れれば倫理は割とどーでもいい女、
バディの男はまあまあ普通の人間倫理、
↑2人とマブダチな老人(死に確)、
そして映画内で一緒に旅し始める新米ジャーナリストの少女の4人で旅します。
⚠️後半らへんで少女が大量に殺戮された死体の上転がされて知り合いも目の前で殺されてショックで車内で吐いてしまう描写あるので苦手な方ご注意です。
PG12なのはいろんな殺し方や簡単に人の命を奪うやつらが蔓延っているからかな、結構血も出てたけどスプラッターではなかったです、ドチャーって感じの、致死量だねーくらいの血です。
アメコミのシビル・ウォーと全然違うのでそこはほんらいのシビル・ウォーの意味なのかなあ?とか思ったけど作品を区別するにはまぁよしかな、くらいです。
主人公は最後自らが撮られる側になって物語は終わります。撮影者は新米ジャーナリストの少女です。
この映画以前にナイトクローラーという映画も見ていたので、ナイトクローラーとほぼ同じ展開になるんだろーなこれ!と冒頭で察して案の定だったので特に感情移入とかはなく淡々と観てました。
ナイトクローラーのほうがはるかにおどろおどろしく、ハラハラ、脚本や構成、夜の恐ろしさなど描写がわかりやすかったですが笑
同じジャーナリズムを扱ってる作品なので、シビルウォーより、ナイトクローラー、お勧めしますね!
アメコミのシビル・ウォーもオモロいです!
割とこの通りだから困るアメリカ
今の分断したアメリカ見る限りでは本作
極めてリアルで明日にも起こり得る話
アメリカの郊外には
ミリシアと呼ばれる私設民兵組織がいて
銃器どころか爆弾まで持っているという
そういう連中が軍の基地とか占拠すれば
クーデター可能な軍備を揃えることは容易だ
さて本編のストーリー見ると
荒廃した町を行く4人組という構図は
ジョージ・A・ロメロ監督の「ゾンビ」を思い出させる
今の人から見れば
ギャグ要素の無いゾン100という感じかな
あと自分を助けて死んだ瞬間のリーを撮影し
師の死を乗り越えて一人前になるジェシーは
「北斗の拳」のサウザーの南斗鳳凰拳を思い出す
(目隠しして師匠と戦って倒したら伝承者になれる)
ただ「こんなに苦しいなら愛など要らぬ」と泣いたサウザーと違い
ジェシーは達観したのか壊れたのか
無の境地に達していた感じだが
タイトルを回収すると
あの赤いサングラスの男の意味不明さに
呆然とした人も多いと思うが
実はアメリカという国には
現実にあの手の異常者がいっぱいいる
1割の天才やエリートや富裕層と
9割の貧困底辺層やバカや異常者で出来てると言われてる国だし
(普通の人はいないのかよ)
この映画の状況でなくても
アメリカの田舎の街に迷い込んだら
あの赤サングラス級の異常者に遭遇する可能性大
「イージーライダー」や「悪魔のいけにえ」など
田舎に行った主人公がいろいろひどい目に遭う映画が
アメリカでは定期的に作られてるのは
多くのまともなアメリカ人にとっては事実だからだ
ひとつツッコミ入れるなら
あの大統領がトランプ級の独裁者ならば
アメリカ国内でも平気で核兵器使用すると思うのだが
カメラでシュートするマカロニ・ウェスタン
アメリカでCivil Warといえば、南北戦争。
この映画は、言ってみれば
南北戦争を背景にしたマカロニ・ウエスタンの現代版。
ただし主人公はガンマンではなく、
Nikon FE2 + Ai Nikkor 35mm F2 (なんと!広角レンズーーめっちゃ寄らないとまともに撮れない)
+ モノクロフィルムという古式ゆかしい「武器」を手に
戦場カメラマン・デビューを果たす
23歳女子ジェシー(ケイリー・スピーニー)
カリフォルニア+テキサスという西部軍が、
南北戦争で南軍の最前線だったバージニア州シャーロッツビルまで進攻し、
合衆国の首都ワシントンD.C.を目の前にしている中、
ロイターの記者とフォトグラファーが
ニューヨークからD.C.へ行く車に
便乗したジェシー。
途中、マカロニ・ウエスタン風の
「おらぁ悪役だぜ、文句あっか」的ならず者たちと遭遇しつつ、
同行者を殺されたりしながら、何度も命の危険をくぐり抜けて、
合衆国の最後を見届けるまでが描かれる。
とにもかくにも、
マカロニウエスタンだと思って観るのが肝心。
つまりは、
なぜそうなった、とか、
人があっさり死にすぎじゃね?とか、
そんなバカなことしたら絶対死ぬでしょ、とか
その他もろもろ難しいことを
考えてはいけないのです、きっと。
憲法を書き換えちゃったらしい
3期目の独裁的大統領が、
ホワイトハウスに突入した西部軍によって
射殺される瞬間をフィルムに収め――
そのとき台詞はないんだけれど、ワタクシには
「カ・イ・カン」
と聞こえたのであります。
ワタシゃ快感は感じなかったけど。
タイトルなし
勝手にエイリアンの出てこない「インデペンデンス・デイ」みたいな痛快作品だと思い込んでいた。そして今日観たかったのは、そんな痛快な作品だったのに、蓋を開けてみれば感染者の出てこない「28日後…」みたいな、ずっと静かな緊張感が漂う全く違ったジャンルの作品だった。鑑賞中は、ずっと「28日後…」が頭の中に有ったんだけれど、後で調べてみれば監督が「28日後…」の製作総指揮と脚本やっていて納得。
派手さは無いが、やたらリアルで、どこに行っても危険な所っていう緊張感が常に有る。
なんでも有りみたいな情勢で知らない奴が出てくると一気に緊張感が高まる。ピンクのサングラスをした金髪軍人は大っ嫌い。車に吹っ飛ばされていたけれど、是非とも◯んでいて欲しい。きっと太々しく生きてるんだろうけど。
登場人物の方は構成的に最後まで生き抜き変化を見せる奴、途中で退場する奴、最後に退場する奴って感じで、チームが結成した辺りから話の展開はバレバレだった。
終盤、先輩カメラマンそっちのけで写真を撮りまくる若手カメラマンが凄まじく、倒れ行くキルスティン・ダンストにカメラを向ける姿には狂気を感じた。
戦争映画は沢山作られてきたが、ほとんどの作品が過去の戦争を描いたものに対して、この作品は完全なフィクションであるにも関わらず、そう遠くない未来に起こりえそうな恐ろしさが伝わってくる。この感想を書いている短い期間の中でも、アメリカの民主党議員が暗殺されたというニュースが入ってきているし、デモでアメリカ人が石を投げ合っている映像なんかも流れてくる。こういった作品は戦争抑止には少なからず効果を出していると思っているのだが、世の中が争いに向かっていくスピードを、ほんの少し緩める程度の力しか無いんだなという現実を突きつけられた気がした。
嗚呼!戦場カメラマン
日本の報道レベルの低さに嫌気がさし、彼等を見習って欲しいと願った戦場カメラマン
彼等は、戦争の惨さを伝えるためという尊い志で命がけで赴いてるのだと思いきや…………
実は大金を儲けるため、スクープ写真を取るためのただの’野望’しか持っていなかったのか
そう思わせる映画だった
実際は違うことを願うのみ
主役のキルステン・ダンスト
どこかで見たなぁと思って調べたら
スパイダーマンの彼女役だった
スパイダーマン当時からさほど美人ではないのに、なぜ抜擢されたのかと思ってたけど、演技力でのし上がってきたのかもね
独裁的な大統領のせいで分断されるアメリカ
これはトランプを揶揄してるのだろうか?だとしたら、歴代大統領の中でもかなり「まとも」な大統領だと思っているので、憤慨してしまう
まぁそれはともかく、映画中の糞みたいな大統領のために命を張る意味がどこにあるのだろうか
生きるか死ぬかの瀬戸際でさえ「わたしを56させるな」と上から目線で一介のカメラマンに言う大統領なのに
56されると分かっていても、身代わりとしてホワイトハウスを大統領専用車で出る側近達
降伏を宣言しながらも最後まで抵抗し殺戮を繰り返す警護官
同じ4なら、それだけの価値ある人の身代わりになりたい
恩師サミーの死に際の写真を削除するリー
自分をかばってうたれて倒れる彼女を撮影し続け、声さえかけないジェシー
もうそこには人間の心は存在してない
56し合う軍人や情けない大統領と同じ
戦争とは本当に恐ろしい!!
4人がD.Cへ向かう途中、突如通った一見平和そうな田舎町を見ていると、結果的に’無関心な者’こそが漁夫の利を得るのだと言いたかったのか、かなり意味深なシーンではあった
それにしても、ドリームの国の同じ国民同士が、ある日突然憎しみ合い56し合うなんて‼️
勿論、諸悪の根源は、金儲けのために安全な場所にいて戦争を仕掛ける奴等なのだけど
人類の悲しい未来が、人間の性が描かれた作品です
戦場での打ち合い等が行われているまさにその時に、カメラマンによって撮られた瞬間、白黒となった映像が止まるシーンが何度もある
それがまた、戦場の臨場感をリアルに伝えてくる気がした
戦いのシーンとのどかな自然風景の対比
そして、幸福感さえ感じるギャップのある挿入曲が印象的だった
未来予想のアメリカ東西戦争をリアルに描くも、映画的帰結に曖昧さが残る
南北戦争(tha Civil War/American Civil War1861年~1865年)以来の国家を二分する大規模な内戦に陥ったアメリカ合衆国の近未来を想定した戦争アクション映画。主人公は女性報道カメラマンとして活躍するリー・スミスで、記者のジョエルと恩師サミーと共にニューヨークから大統領取材目的で首都ワシントンD.C.に車で向かいます。そこにリーに憧れる新人写真家ジェシーが加わり、彼らが悲惨で危険な戦場や無政府状態の国土を辿るロードムービーにもなっています。戦争の発端は、独裁者の大統領が憲法を反故にして3期目に就任しFBIを解散させたこと。これに怒り独立したテキサス・カリフォルニア連合WF(Western Forces)がフロリダ同盟と手を結び、政府軍と激しい攻防戦を重ね、最後は敵連邦政府が殲滅するまで死闘するという、斬新奇抜で刺激的な作品でした。それで監督と脚本兼ねたアレックス・バーランドと撮影と音楽までの主要スタッフがイギリス人で占められている。流石に政治的な隠喩を連想してしまう内容だけに、アメリカ人の制作では難しかったかと想像します。主要キャストはアメリカ人の他に、ブラジル人、日系イギリス人、台湾系カナダ人と多様でした。
映画的な迫力と衝撃度の点で、前半の凡庸さと後半の緊迫感の差が大きいことが挙げられます。先ず内戦状態の敵味方分からない不安感が一気に増す中盤、彼らの知り合いであるアジア系ジャーナリストと偶然出会い、謎の兵士に捕まり危機に瀕するシークエンスが、実に怖い。お道化たユーモアからカーアクションのスリル、そして兵士に脅される戦慄の息詰まるタッチと、ここのバーランド監督の演出には一目置かざるを得ませんでした。その後の夜の山火事の中を車が走る異次元的で幻想的な美しさのあるシーンが素晴らしい。そして一機のヘリコプターが道案内するかのような朝焼けシーンからシャーロッツビルWF前線基地に辿り着く映画的な流れもいい。
それでもこの映画の見所は、夜の首都ワシントンD.C.で繰り広げられる激しい市街戦のクライマックスでしょう。光るワシントン記念塔を見せ、その前にあるリンカーン記念堂の攻防から、ホワイトハウスに突撃するまでの映像の迫力は、正にアメリカ映画の力量を見せ付けます。装甲車や攻撃ヘリコプターの活躍に続く、逃走する大統領専用車のアクション。遂にラスボスの大統領を捕まえるまでの銃撃戦と、息つく暇もなく圧倒されました。
このアクションシーンの見応えに対して、主人公リー・スミスの最期は、ジェシーの身代わりになる映画的な帰結に収めた作為を感じます。リアルを追求する表現に対して、彼女の思いが描き切れていない不満が残りました。折角キルスティン・ダンストが良い演技を見せているだけに、主人公としてもっと大事に扱って欲しいと思いました。ジョエル役のヴァグネル・モウラ、ジェシー役のケイリー・スピーニーもそのバックグラウンド含め人物の深みに物足りなさが残ります。それと巨漢の老体であるサミーが最後までいるとなると、動きの鈍さで不自然になり、それで脚本上途中で消したのではないかと思えてしまいます。現場の臨場感が写真の価値とは言え、命を賭けた兵士の邪魔にもなるジャーナリストの使命とは何かまで考えると、この脚本自体の強引さも指摘せざるを得ません。また象徴的なラストカットは、アメリカの観客がどう観たのかも気になるほど、西部劇に出てくる写真のように見えて、不謹慎ながら少し可笑しかった印象を持ちました。
昨年の大統領選挙で明らかになったアメリカの政治的分断を思い起こす野心的で、警告的なアメリカ映画でした。
国を世界を混乱させた罪を思い知れ
実写洋画がヒットしない昨今の日本興行。
昨秋の公開時、週末ランキング初登場1位。人気シリーズ新作や大ヒット作の続編でもない洋画実写オリジナル作品で、これは近年異例の事!
インパクトある題材や浸透しつつあるA24スタジオへの信頼だろう。
意欲的な作品を発表し続けるA24が、同社最大の製作費を投じて贈るのは…
もし今、もしくは近い将来、アメリカで内戦が起こり、分断したら…?
実にセンセーショナル。邦画でも新海誠監督で南北に分断された近未来の日本(その世界で生きる若い男女たちの恋と青春)を描いた作品があったが、現リアル独裁者の強引な政策で、ただでさえアメリカ国内や世界が揺れている今。決して起こり得ない絵空事ではない。
今も国が分かれ、睨み合い続くと言えば、韓国と北朝鮮。
アメリカも100年以上前、北と南に分かれた内戦があった。
それらの事が、今アメリカで起きたら…?
アメリカ、そして世界はどうなってしまうのか…?
鬼才アレックス・ガーランドが描く!
…のだが、やはり鬼才は変化球。
もっとポリティカルな作風かと思ったら、ジャーナリズム映画。プラス、ロードムービー的。
結構賛否分かれてるようだが、なるほどそれも納得。見る前とはちょい違った印象。
憲法違反の3期目、FBIを解体など独裁体制の大統領。
19の州が分離独立を表明。テキサス/カリフォルニアから成る“西部勢力”とフロリダ~オクラホマから成る“フロリダ同盟”は連邦政府軍を撃退し、首都ワシントンに向かっていた。
戦場カメラマンのリー、記者のジョエル、リーの師でもある老記者のサミー、道中出会った新米カメラマンのジェシー。4人はNYを発ち、ワシントンに向かう。大統領への独占直撃インタビュー。
大陸横断の道中、内戦~分断~無政府状態となったアメリカの姿を目撃する…。
荒廃した町。
道端には死体が無造作に転がり、目を覆いたくなるような光景。
内戦に関わらないようにし、以前のように穏やかな町でさえも。
そこかしこに屯する人々もとっくに正気を失っている。
道中、所属不明の兵士に捕まる。どの“アメリカ人”か、聞く。“アメリカ人”でなかったら、容赦なく処刑される…。(ジェシー・プレモンズ怪演)
殺伐とした雰囲気、異様な雰囲気、失われた雰囲気…。
それらをリーたちはカメラに収めていく。
一個人としてはトゲがあり、自己中的でもあるリー。大統領インタビューも独断。
が、ジャーナリストとしては信念あり。フィルター越しに世界(アメリカ)を覗いて。
ジョエルもサミーも振り回されつつも、サポート。
当初は何かを犠牲にしてまでカメラを向けるリーを理解出来ないでいたジェシー。
若い彼女も信念あるカメラマンになりたい。
次第にリーの姿を見つめ直していく。
リーが問う。私が死ぬ時もカメラに撮れる?
その時は答えられなかったジェシーだが、まさしくそれがクライマックスに…。
ほぼ4人の動向が主軸となり、とりわけキルスティン・ダンストとケイリー・スピーニーの熱演光る。
思ってた作風とはちと違ったが、それでも臨場感、緊迫感は圧倒的。特にクライマックスに近付くほど。
遂にワシントンへ。首都は激戦真っ只中。音響、映像、編集…戦場の渦中に入り込んだかのよう。
ホワイトハウスに突入。隠れていた大統領を見つけ出す。
銃を向けられ、最期の言葉は、陳腐な命乞い。
国を世界を混乱させた罪を思い知れ。
劇中の架空の大統領に言ってるのではない。
ジェシーのカメラは、我々の目は、その瞬間を逃さない。
民意の先
アメリカの歴史と地理を知ってることが前提となるが、大統領の選択する未来が国民と乖離した時の行動は民意なのか?
民意とは何か?その疑問と選ばれた人物の選択が国の方向性を決める難しさを如実に表している。
圧倒的な民意から選ばれた人物の居なくなった現代社会において、映画の世界がより現実的に感じられその選択により選ばれなかった民意をどう扱うのか?
大統領となった人物の難しさを浮き彫りにしている。
どの国でも同じなのかもしれないが、手綱のない暴馬のごとく、暴走したものの行き着く先には何も残らないのかもしれない。
そして荒れ果てた大地に残されたものは、その力に抗えない者たちの悲しみと虚しさが広がる世界と様に感じられた。
うーん、
重い作品ではあったけど、アメリカ国内の「内戦」のことで、カメラマンに焦点をあてた内容。
緊張感なくはしゃぐ若者、銃を持つことで強くなったと勘違いする赤メガネ、なにかと「あーあ」ってなシーンもあったり。
たまに流れる挿入曲はいらんだろ、とも思ったり(笑)
そして終盤には丸腰の記者がホワイトハウスに入っていく、そして「あんな終わり方」という。
そこまで大統領を攻めて、そこまでその大統領はひどいことをしてたのか、よくわかんない終わり方だった。
「もし内戦みたいになったら」ってなことかもしれないし、その状況はひどく過酷ではあるけど、報道、カメラマンメインの映画そのもの、その演出、ストーリーとしては、んー、「そこまでは」というかんじか。
最初は「★3つくらいか」とも思ってがんばって最後まで見たけど、「そこまでは」なかった。
個人的には。
「A24」らしい尖った映画
ハリウッド大作かと思ったら、昔で言うところニューヨーク派的な、インテリ的な映画でした(ジム・ジャームッシュみたいな)。
その辺が面白かった。
まあホラー映画並みに怖さのある映画でしたし。
監督は、小説家、脚本家で、「エクス・マキナ」(未見です)の監督(アレックス・ガーランド)だそうで。
制作会社があの「A24」です。A24らしく尖った映画でした。
「プリシラ」で主役を演じたケイリー・スピーニーが準主役で、可愛くも、いい演技をしていました。主役のキルスティン・ダンストは貫禄が出てきたな~と思いました。ケイリー・スピニが駆け出しの報道カメラマンで、憧れの報道カメラマンがキルティン・ダンストで、その関係が短い間に成長していく様がいわば話の背骨になっていました。
見応えがあり、ちょっとスタイリッシュで、ちょっと怖い、リアルな近未来映画でした。
どんな意味を込めて“記録”するのか
戦場カメラマンは酷な仕事である。目の前で人が死ぬ。死ぬ様子を撮る。死んだ顔を撮る。殺した人を撮る。殺す時の表情を撮る。淡々と。
人道とはかけ離れた行為を記録する。何のために?
「シビル・ウォー」は近未来のアメリカで内戦が起こった、という状況を戦場カメラマンの目線で描く社会派映画だ。
主人公であるカメラマンのリーは言う。「祖国への警告として写真を撮ってきた」と。紛争地域でのあらゆる悲惨な現実を記録し、それを目にすることで紛争地域とは遠く離れた祖国・アメリカに「軍事介入」や「空爆」などの字面では掴めない恐怖や痛みや苦しみを想像してもらいたかったのだと思う。
だが、リーの思惑は外れ、アメリカが紛争地域となった。その虚無感はいかほどだっただろうか。
自分の命も危険に晒しながら、切り取り続けたおぞましい光景は何の役にも立たず、目の前で消えていった命が彼女に託したものは、彼女の祖国に届かなかったのである。
ベテランのリーと対比になるのが、戦場カメラマンを夢見るジェシーだ。最初は近づき過ぎて怪我をし、給油所ではカメラの存在も忘れるド素人のジェシーだが、徐々に慣れてきたところで一行は最大のピンチを迎える。
内戦に乗じて差別的な根拠による殺戮を行っていたと思われる連中に襲われ、間一髪で危機を逃れるがジェシーと同様にリーと同行していたサミーが銃弾を受けて亡くなる。サミーはリーの師である。
ここがターニングポイントとなって、リーとジェシーの行動が変わる。
ジェシーは奇跡的に生き残った経験から肝が据わってガンガン前に出るようになる。序盤、リーが銃撃戦の間隙を縫って写真を撮りまくっていた時のように。もう同行する記者・ジョエルのガイドも必要ない。誰よりも近くで、誰よりも早く、この場で起きていることを全て、撮り続けることだけに集中しているようだった。
一方で、師を失い自分が写真を撮る最後の意味を失ったリーはほとんどシャッターを切れずに、圧倒的な暴力の嵐の中をついて行くのがやっと、の状態になっていた。“記録”したい、という目的と覚悟が消え去って、惰性でカメラを構えるだけだ。
そんな状態のリーが、写真の事しか考えずに飛び出たジェシーを庇ったのは、“記録”よりも残したいものとして“未来”を、つまり若いジェシーを選択したからだと思う。
ジェシーがこの先戦場カメラマンとして、どんな意味を込めてシャッターを切るのかはわからない。金や名声や、或いはジョエルのようにスリルと高揚を求めて戦場へ出ていくのかもしれない。
だが、リーが成そうとして成し得なかった「祖国への警告」を別の形でジェシーが届ける未来だってあるはずだ。
映画の中でジェシーが撮ったモノクロの写真には、いつもリーやジョエルやサミーが一緒に写りこんでいた。ジェシーの世界にはいつも支えてくれる先輩がいる、という証左である。
だがエンドロールの写真にジョエルはいない。ジェシーが独り立ちしたからと考えるのか、それとも「大統領の死と兵士たち」という写真は祖国に何の意味も与えられないのか。ジェシーが写真を撮る目的が明確になるまでそれは分からないかもしれないが、せめてリーが望んでいたような美しい未来につながればいいと思う。
【蛇足】
戦争映画へのオマージュ的なシーンも含め、世界中で起こった様々な戦争、戦争にまつわる出来事が近未来のアメリカという一つの国で起こるところが面白い。
嘘まみれの大本営発表、混乱に乗じた殺戮、差別主義者の台頭、物資の不足、貨幣価値の暴落。
そして、そんな状態なのに「我関せず、が一番良いかなって」という態度の市民がいたりする。
産油地域や聖地の近くや東側国家で起こっているんじゃない。違う国民が争ってるわけでも、宗教対立でもない。同じ国の人間が殺し合う中で、正義と悪を単純に決められないから、アメリカ国民は震えるのだ。いつもはアメリカが正義でそれ以外は悪、という二元論で良いからね。
映画そのものが、リーと同じ「祖国への警鐘」という目的で作られていて、それが伝わらないんじゃないか?(映画の中では内戦が起きてしまっているので)という皮肉も含めて、本当によく出来ていると思う。
最後の「大統領の死と兵士たち」の写真に、薄ら寒いものを感じたのは私だけだろうか。人間の死体を前に笑顔で写真を撮れるほど、勝利って良いものだろうか。
どこかの大統領は「勝つまでやれば負けない」が信条のようだが、勝てば何しても良いわけじゃないはずだ。「勝てば官軍」の考えで進んで行く世界の未来が、美しい未来だとは思えなかった。
起こりうる不気味さ
アメリカ大統領が憲法を変えて三選をし、反発する二州が反旗を翻す。政府はFBIを解体する。現実はトランプが圧勝したように見えるけれど実際は投票率を数パーセント上回っただけだったようだ。実は国民は半分に分断されている。トランプはFBIを解体し、憲法改正で三選目を目指すらしい。ありえない設定や空想とは思えない不気味さがある。自国民に銃を向け、おまえは何アメリカ人だと迫る。アメリカ出身者以外は撃たれる所はショックだった。戦闘場面も現実にウクライナやパレスチナで目にするように極めてリアルで残酷だ。最後のホワイトハウスの攻防戦もたっぷり描かれる。大統領がテロリストや反乱政治家に攻められる話はあったけれど大統領自体が失望をもたらす映画は珍しい。こうなったらどうするのだと国民に問いかけているのだ。
考えさせられる名作
ストーリーは「内戦が起きたアメリカで写真家の主人公たちが大統領の元へと行く」というもの。
この映画の『実際に起きてもおかしくない』という感じは凄まじく。まさしく映画館で見るべき映画でしょう。
ストーリーはかなり練られており、なぜアメリカで内戦が起きたのかという理由も納得できるものです。
しかしラストで悲しい展開が起きるのですが、主人公の若い女性は前に進む道をとったのは感心しました。それでこそジャーナリスト。(比喩表現ではなく本当に前に進んだ)
他の映画なら打たれた仲間を抱きかかえたでしょう。しかしこの映画ではしなかった。
映画館で観たらきっと迫力があったのでしょう
映画の中で説明されると思い予備知識無しでAmazon鑑賞。アメリカの情勢やら何やら理解してないと難しい映画なのかなーっという印象。ジャーナリストの報道の無力さを感じる主人公の報われなさとかじゃあこの内線のあとはどうなるのかとか全体的にボヤケているなぁと感じてしまう。戦争ジャーナリストの話だからストーリー全体というよりこの戦争を伝えたいと足掻く姿が痺れました。そういう映画なのだろうと解釈。でも最後に主人公死んじゃうのは何故?あんなに後輩に防弾チョッキとヘルメット言ってたのになんで後半、後輩も本人も防弾チョッキもヘルメットもしてないの???インタビューの人もだけど。と「ええぇ……」と納得出来ない。
戦場のリアルさと主人公たちの足掻く姿で★3
全232件中、1~20件目を表示