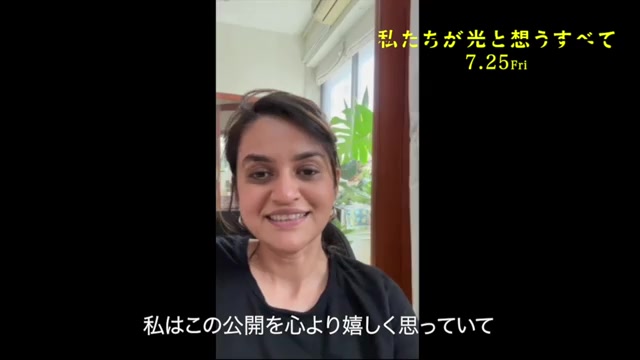私たちが光と想うすべてのレビュー・感想・評価
全118件中、81~100件目を表示
ムンバイの雑踏に入り込んだよう
ムンバイの騒がしさ
臭い、暑さが生々しく感じられた。
海辺の田舎町は鬱蒼と生い茂る木々の香り、潮の香りがするようだった。
プラバは笑わないねんな。悩みを抱えているからか始終陰気な印象。対照的に年下の同僚のアヌはイケイケな感じで明るい。なんで一緒に暮らしてるんやろ?
運命に抗えない女性達がなんか悲しい。
終盤で
全く刺さらなかった
神にでもなろうとしている人達
商業大都市ムンバイの病院で看護師として働くプラバ、彼女の同僚で年下のルームメート、アヌがこの映画の主人公。
プラバには結婚式以来、長い間会っていないドイツの工場で働いている夫がいる。1年以上電話の連絡さえもしてこない夫を待ちつつ、同じ病院の食堂で働くパルヴァティ、彼女は高層ビル建設のために何十年も住んでる住居の立ち退きを迫られているが、プラバはそんなパルヴァティに何かと世話をする優しい女性だ。
アヌには周囲に隠して交際している男性がいる。彼はムスリムでヒンドゥー教が主要な宗教であるインドでは異教扱い、風当たりが強い様だ。アヌは自由でいられる場所が何処かないものかと思い悩んでいる。
彼女達を抑圧しているものは慣習、規律、宗教観でそれは親、お金持ち、国家でもある。
しかし劇中で彼らの姿は出て来ない。
パルヴァティが言う、「神にでもなろうとしている人間達」。日常、時間、意志を奪い続けている見えない力と見えない姿。
何だか眉間にしわの寄る話続きの様だか微笑ましい場面や笑えるシーンもある。
まさか外国映画で「写真で一言」が観れるとはね。反則でしょ。
高層ビルによる深く長い影、モンスーンによる大雨と暗い空。人口密度の高さによる熱気と圧迫感。そんな暗闇の中、彼女達のまなざしの先には様々に美しく差す光。
僕が生きている間に人口やGDPによる変化ではなく、規制や制約に収まらない本当の変化がインドで起こったら、真っ先にこの映画が思い浮かぶだろう。
ドイツ製炊飯器と子持ち猫
女性の強さ
日常を懸命に生きている人々の作品が好きなので、今までは観ることの無かった、インド女性の生活を垣間見た感じて良かったです。
旦那様から送られてきた炊飯器を抱きしめるプラバの姿は切なすぎました。
でも職場の友人女性と共に行った海辺の町で、心の中で夫と決別をした姿は女性の強さを感じ感動しました。
また、一緒に同行したアヌも困難な道を彼氏と進むと決めたようで、また違った強さを感じました。
最後の海辺でみんなが話すシーンは景色も波の音も全てが美しく、彼女たちのまだまだ続くであろう道のりの休憩時間として、心に残りました。
刺さりませんでした
「花嫁はどこへ?」がすごく良かったので期待して観ましたが、盛り上がりのない淡々としたストーリーにうとうと。
海で溺れた知らない男の人がいつの間にかドイツにいるはずの夫になってて、何を見逃したのかと思いましたが、帰宅後ネット検索したらただの幻だとのことでした。ちょっとわかりにくかったです。
全体的に登場人物の心理描写も不十分な感じがしました。
それから、インド映画であのような男女の絡みは初めてでした。あんなに性に奔放な女性もやっぱりいるのですかね。
平日の昼間なのに劇場は満席でした。
鑑賞後に感じる深い余韻でとんでもない名作を観たのではないかと感じさせる一品
この映画、鑑賞後感が非常に良くてちょっとびっくりしました。映画を観ている最中にはそれほどでもなかったのですが、エンドロールをぼーっと眺めていると、あー、今日は本当にいい映画を観たなぁという満足感に全身が包まれてゆきます。晩ご飯の後に飲んだ一杯のお茶のようにこの作品の持つ滋味が五臓六腑にしみわたり、まあ人生ままならないこともいろいろあるけど、明日からも生きてゆくかという気分にさせてくれます。
主な登場人物は看護師の同僚で住処をシェアしているプラバ(演: カニ•クスルティ)とアヌ(演: ディビヤ•プラバ)の二人、そして彼女たちの勤める病院でまかないの仕事をしていたけど、住まいの立ち退きを要求されて郷里の海辺の村に帰ることになったパルヴァティ(演: チャヤ•カダム)。この女性3人を中心に物語は進みますが、前半を引っ張るのはムンバイの街です。ムンバイはインド最大の都市で人口2000万弱とのことでケタ違いの大都会。この映画では特にその夜の喧騒をよく捉えています。また、ムンバイを走る電車の捉え方が秀逸です。夜のムンバイを走る、東京で言えば京浜東北線か東海道線のように都会の中心と郊外を結ぶ電車。警笛を鳴らしながらガタンゴトンと走る、外から見たロングショットもいいですが、中の様子を撮したショットもいい。大都会の電車には人がたくさん乗っていてもなんともいえない寂寥感と哀愁があると思うのですが、これはインドでも日本でも同じなんだと感じました。
その電車に乗って、異教徒の恋人の住む街へその恋人に会いに行こうとするアヌ(ヒンズー教徒でしょうね)。彼女は「スパイになった気分」と言い、店でムスリム女性が身につけるブルカ(例の全身を覆うあれですね)を購入し、それに着替えて電車に乗ります。色は黒で外からは目の部分しか見えませんでした(結局、事情があってその日は会えなかったんですけど)。異教徒と恋愛をするというのはこういうことなのだ、それを簡潔に映像で表現していて見事でした。
郷里の海辺の村に帰ることになったパルヴァティ。プラバとアヌもその海辺の村へと旅行します。前半のムンバイの喧騒とは打って変わって後半は海辺の村の幻想的なシーンが続きます。そのコントラストがいいです。特に秀逸なのが終盤に登場する浜辺に建てられた「海の家」の紛い物みたいなふた部屋続きの横長の掘立て小屋みたいなお店。その小屋の前にテーブルや椅子が並べられて飲み物が提供されるような感じのお店なのですが、インド洋からの強風であっという間に飛ばされそうな造りです。でも夜に電飾を施されるとなぜか美しい。郷愁も感じます。メインの3人の女性とアヌの恋人が夜、その店に集うのですが、なぜか目頭が熱くなりました。この先、この人たちの身の上にいろいろなことが起こるでしょう。思い通りに進まないことのほうが多いかもしれません。でもどうか、今日よりはよくなる明日を信じて前進してほしいと心から願いました。
本当にとんでもない名作なのかもしれません。
終盤の意味が分からない
私の理解力/感性不足なだけかもしれませんが…。
電車のシーンが結構多かったように思いますが、車窓を流れる街の景色や、ひとり電車に乗っているときの何とも言えない孤独感、のようなものは日本と変わらず同じなんだと共感しました。
また、ムンバイという都心を幻想と喩えていたシーンには、この映画のタイトルに込められた想いの片鱗を感じました。主人公の暗い気分とはまるでかけ離れた、お祭り騒ぎの街並み。ちょうど京都も祇園祭の真っ最中だったので、じんわりと心髄にその場面が染み込んできました。この映画で一番印象的だったのは、こういった都会のにぎやかな町の空虚さです。
一方で、主人公たち女性の心はかなり沈んでいるように映ります。が、あまりにも淡々とドキュメンタリー風に話が進むので、イマイチその心情に入り込むことができません。プラバもアヌも、互いに恋愛に関して悩みを抱えていることはわかるのですが、気づいたら田舎の村へ行っていて、隙を見ては彼氏とイチャイチャするアヌ、漂流してきた瀕死の男と謎の会話を繰り広げるプラバ。最後はアヌだけ無事ゴールイン……?
私が今絶賛失恋中なことも影響しているかもしれませんが、結局は素直で陽気な女が幸せになるのね…と、なんだか沈んだ心のままエンドロール。飛ばして帰りたいと思うくらい、最後の展開が腑に落ちませんでした。
この作品は物語というよりかはドキュメンタリーちっくなので、ありのままに、よくわからないまま終わるので良いのかもしれませんが、ポスターに書かれた『運命から解き放たれる』とは、いったい……?私にはプラバもアヌも、運命から解き放たれたようには見えませんでした。とりあえず、人生にはやはりお酒とダンスが必要そうですね。
中だるみがあり、長く感じた
閉じ込められた女神
言語化できない強い余韻──インドと日本の現在をつなぐ映画
言葉にして感想を書いてしまうと、何か大事なものが抜け落ちてしまうような、言語化できない強い余韻を残す映画だった。
いつまでもそれがなんなのか考えてしまいそうだから、とりあえず鑑賞直後の感想を書いてみたい。
インドの映画はこれまで何本も観ているけど、エンターテイメントの極致のような映画ばかり。本作は、そうしたエンタメ性は全くない。
ただ、この映画を観てはじめて、僕らと同じく、現代を生きる困難や葛藤を抱えて一生懸命生きている個人、国籍は違えど同じ悩みを持つ同志として話してみたくなる個人としてのインドの人の姿を教えてもらった感じがした。
映画の冒頭で、正確な言葉は覚えてないが「この町で暮らして10数年以上になる。でもこの街を故郷と呼ぶには躊躇してしまう。いつお前はここからででいけ、と言われるかわからないから」
こんなようなモノローグが街の風景をバックに流れる。
これは、自分が安心して所属していると思える場所などないんだという本作の1つのテーマの提示ではないかと思った。
そしてその後のストーリーで、凄まじい発展の最中の現代のインド社会の様子が丁寧に描かれていく。
僕はインドに行ったことがない。敬愛する藤原新也の「インド放浪」(彼が20代、1970年代に出版された凄本)の近代以前の価値観が色濃く残る時代のイメージでインドを捉えがちな僕の認識もひっくり返してくれた。
今のインドは、日本で言えば、明治の近代化、戦後の民主化と自由主義と経済発展、さらに男女雇用機会均等法とグローバル化の影響が同時に訪れているような状況なんだと思う。
基本的にはポジティブな発展ではあるけれど、そこで起きている共同体の喪失や個人が機能として能力で測られること。自分らしさを自分で見つけてそれにしたがって一人一人が自分で人生を切り開かなければいけない……そうした困難が丁寧に描かれた映画だと感じた。
しかし、そうした時代の中でも、資本の論理で人を機能としてみるような流れに飲み込まれず、本来の人間らしい関わりを大事にしている。そんな人としての強さも強く感じさせられた。
ここらかは余談になるけれど、先日、永田町にある自分の会社の近所のコンビニでそんな体験があった。
飲み物と電子タバコを買ったら、レジの外国人の若い女性(おそらくインド出身)が「マスカットがお好きなんですね」と話しかけてくれたのだ。
? 何を言われたのか一瞬わからなかった。そして手元の商品を見て気付いた。僕の買った電子タバコがマスカットフレーバーで、飲み物がマスカット味のいろはすだったのだ。
なんかすごく嬉しかった。それに何か大事なことを教えてもらったと思った。
店員と客で、コンビニは資本主義な等価交換の場。忙しい店だから効率が大事。そこに個人的な、相手のその人らしさを見て、それを承認するというようなことは、なかなかできることではないと思う。
だいたい僕らは会社員として、有能で成果を出しているか、組織に与えられた役割と責任を果たしているか……そんな画一的評価の中で生きているから、自分が他の人とは違う個性のある人であるという自己重要感が得られなくなっている。それが現代の発展の裏にある大問題であると思う。(庵野秀明のエヴァは、そうした彼の個人的欠落感を、キャラクターたちに反映させて、そこからの救済の可能性を探る作品でもあると思う)。
そうした僕ら日本人の現代の課題にも通じる普遍性を持った素晴らしい映画。満席だったから、すでにその評判は周知されているのだろうけれど。
さらに余談。
こんな感想を映画を観たあと小伝馬町のインド料理店「デシ タンドール バーベキュー」で、ビリヤニ付きのちょっと贅沢なランチを食べながら書き始めていた。
ビリヤニが素晴らしく美味しかった。会計の時にそんな話を店員さんにした。僕はチャーハンみたいなものだと思ってたけど、大間違い。2〜3時間も手間のかかる炊き込みご飯のようなものなのだとか。冷凍のお店も多いけど、味が落ちるから、彼の店ではやらない。人気でもたくさん出せないのだそうだ。
彼の仕事にかける意気込みと倫理観、誇りに触れて感激。握手して店を後にした。
映画の感想からずいぶん離れてしまったけど、直接その素晴らしさを語れない、でも何かが強く心に残る、そんな映画でした。
インド市井の女性たちが織りなす静謐なドラマ
◾️作品情報
監督・脚本はパヤル・カパーリヤー。主要キャストはカニ・クスルティ、ディヴィヤ・プラバ、チャヤ・カダム、リドゥ・ハールーン。2024年・第77回カンヌ国際映画祭でワールドプレミア上映され、グランプリを受賞したフランス・インド・オランダ・ルクセンブルク合作映画。
◾️あらすじ
ムンバイで看護師として働くプラバと年下の同僚アヌはルームメイトだが、それぞれの人生にはままならない現実があった。真面目なプラバは、親が決めた相手と結婚したものの、ドイツに住む夫からは長らく連絡がない。陽気なアヌはイスラム教徒の恋人と秘密の恋愛をしているが、家族に知られることを恐れている。そんな中、同じ病院の食堂で働くパルヴァティが立ち退きを迫られ、故郷の海辺の村へ帰ることを決意する。プラバとアヌは、ひとりで生きていくというパルヴァティを村まで見送る旅に出る。神秘的な森や洞窟のある別世界のような村で、彼女たちはそれぞれの人生を見つめ直す。
◾️感想
インド映画と聞くと、華やかなダンスと歌のイメージが先行しがちですが、『私たちが光と想うすべて』は、そんなインド映画のイメージとは一線を画す、静かで内省的な作品です。ムンバイの喧騒の中で生きる市井の女性たちの日常を、まるでドキュメンタリーを観ているかのように、ありのままに穏やかに描き出しています。
真面目で内向的なプラバと、奔放で現代的なアヌ。対照的な二人の看護師の姿は、現代インド社会に生きる女性たちが抱える息苦しさと、そこから抜け出したいと願う自由への希求を、等身大で誠実に浮かび上がらせています。彼女たちの心情に寄り添い、その微細な揺れ動きを丁寧に捉えるカメラワークは、観る者の心に静かに染み入るようです。
しかし、その抑制された演出ゆえに、物語の展開は時に淡々とし、退屈に感じてしまう面もあります。ドラマチックな起伏は少なく、観客自身が彼女たちの感情に深く潜り込み、共鳴できるかどうかに委ねられる部分が大きいと感じます。それでも、ラストに向けて見せる二人の変化、特にプラバの内面の解放が詩的に描かれる場面は印象的で、静けさの中に確かに灯る希望の光を感じさせます。
大都市ムンバイで、既存の枠に自分をはめることで心の安定や社会的体裁を保ってきた三人の女性たち。彼女たちが、事情は違っても、内に秘めた息苦しさ、生きづらさに共感しあい、海辺の村で自身を解放する姿が眩しく映ります。光は、都会の幻想ではなく、彼女たちの心の中にあったのでしょう。
とにかく、この邦題に惹かれて
見事!ドキュメントタッチでもどこか温かい作品
インド映画はダンス、アクションのイメージが強いが本作品は正統派作品。ドキュメントタッチでインドのカースト制度の現実に直視しつつも恋愛したい、夫と会いたい看護師姉妹の生き方に好感。ラストシーンは◎。看護師妹もカースト制度の厳しい中、素敵なボーイフレンドと出会えて良かったなと感じた。
異文化を知るには映画を観るのが一番だが、本作品はインド社会を知る上で最適な作品。
眠かった・・・
諦観と自己肯定と開放
淡々とし過ぎていて私には合わなかったかも
壁に立ち向かう2人に幸あらんことを
インド南西端、ケララ州の公用語、マラヤーラム語の原題の意味は(Chat GPTに訊いてみたところ)All that imagined as Prabha だという。
つまり「プラバとして想われるすべて」。
そしてPrabhaは、lightを意味する名前なんだそうな。
プラバは、主人公の名前である。
「光さんの想いのたけ」ということか。
もちろん英語圏でもあるインドなのだから、
All We Imagined as Lightという英題にも
監督の意思は反映されているだろうけれど。
大都市ムンバイの病院で「シスター(字幕は"姉さん")」と呼ばれる看護師プラバは、
謹厳実直で禁欲的。
同じ職場で働き、なぜかプラバと部屋をシェアするアヌは、
ちょっとだけ無邪気で、思った通り行動したい。
2人の出身は、ケララ州。
この2人と、もう1人、
病院の食堂で働いていて、
富裕階級のためのマンション建設で立ち退きをくらう
パルヴァティという寡婦のおばさんが、話の中心。
* * *
プラバはかつて、
親から突然呼び出され、帰省したら結婚相手が勝手に決められてた。
その夫は、その後すぐドイツへ行ってしまって、
最近は1年以上音沙汰がない。
だからプラバには、恋愛という経験がない。
そういう彼女へ、(おそらく同郷の)医師が(控えめな)告白をする。
アヌはといえば、今まさに、
プラバと同じように、親から見合いの相手を提示されているのだが、
それとは関係なく出会った彼氏(こちらもたぶん同郷)との付き合いに夢中。
だがその彼氏はムスリムで、
ヒンズー教徒であるアヌの両親が、アヌを嫁に寄越すはずがない。
――という状況で、さて彼女たちの未来はどうなるのか。
* * *
(ここからネタバレあります)
* * *
この映画が投げかける主な問題は、
男女・結婚・家族・宗教をめぐる古い価値観と、
最近のインド政権が明確に打ち出しているヒンズー教指向および
それにともなうイスラム教との摩擦の先鋭化だろう。
プラバは、
男女・結婚・家族をめぐる古い価値観に絡め取られ、
遠くドイツにいる名ばかりの夫に縛られている。
プラバよりいくつか年下のアヌは、
その古い価値観に絡め取られまいと抗っているが、
宗教をめぐる大きな壁にぶつかっている。
ただ、壁は宗教だけではない。
ムスリムの彼氏は、
「君の親を説得しに行こうか?」とは言うものの、
「僕の親を説得するよ」とは決して言わない。
つまりそこには、旧態依然たる男女の問題が、
大きな壁として立ちはだかっているんである。
* * *
後半、
立ち退き要求に抵抗できず、あきらめて
故郷のラトナギリ近くの村に帰るパルヴァティを、
プラバとアヌは休暇をとって送ってゆく(引っ越しの手伝い)
よくアヌが来たな、と思ってたら、
ちゃっかり彼氏を呼び寄せ、こっそり会う筋書きを立てていたという寸法。
他方、プラバは、
海で溺れた男性を、看護師として救命する。
病院もないその村で、その晩の看護もつとめるんだが、
そこからが、幻影? 妄想?
記憶を失っている男性が、
いつのまにやらプラバの夫に……
いやまさか、
ドイツから泳いできたはずはなくw
地元のおばあちゃんが2人を夫婦と誤解したことをきっかけに、
プラバの脳内でそういう会話が生まれたんだろうと、
思っておくことにする。
ただいずれにしろここでプラバは、
名ばかりの夫に抑えつけられ続けることを拒否する。
こうして、
前途はむちゃくちゃ多難だけれど、
プラバもアヌも、
それに立ち向かって生きていくことを、決意したんだろう。
たぶん。
2人の前途に幸あらんことを。
* * *
ちなみに、
アヌを演じた役者さんの名前が、
ディビヤ・プラバ――苗字が「光さん」――
なんだね……
全118件中、81~100件目を表示