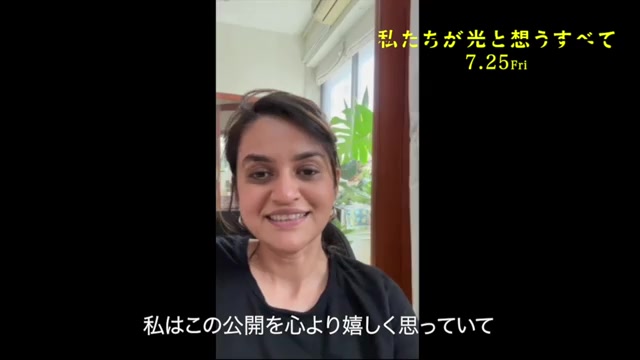「ムンバイに生きる市井の女性の心模様を繊細に綴る日常系インド映画」私たちが光と想うすべて ニコさんの映画レビュー(感想・評価)
ムンバイに生きる市井の女性の心模様を繊細に綴る日常系インド映画
オープニングからの数分、湿度を感じる雑踏とそこで生活する人々の数節の言葉で、訪れたことのない街ムンバイのイメージが胸の奥に広がった。
日常系インド映画とでも言おうか。説明的な台詞を極限まで排した脚本とキャストの自然な演技には、パヤル・カパーリヤー監督がこれまで手掛けてきたジャンルであるドキュメンタリー映画に通じる雰囲気が漂う。
現代インドの女性たちの生活文化や恋愛観をほとんど知らなかったので、新鮮に感じる場面が多かった。
考えたら自然なことだが炊飯器を使うんだなあ、とか(ちなみに90年代にインドに炊飯器を普及させたのはパナソニックだそうだ。それまではガスか薪で炊いていた)、好きな相手にお菓子はともかくポエムを贈る男性って、インドの女性にはウケるのかなとか。
彼女たちの置かれている環境も社会的・宗教的背景も私自身とは随分違うのに、彼女たちが抱く感情には不思議なほど垣根を感じなかった。
その理由は、特に主人公のプラバについて顕著だが、彼女の心の揺れについての説明的な描写がほとんどないからだと思う。彼女が働く姿、アヌの態度や炊飯器を抱く姿を見て観客はプラバの心境を想像する。もちろんそういった描写には監督の意図が内在するが、観る側の想像と解釈の余地が大きいということは、そこに観客自身の価値観が映り込みやすくなるということであり、垣根を感じなくなるのは自然なことかもしれない。
一方、奔放なアヌの行動についてはちょっとハラハラさせられた。ヒンドゥー教信者がムスリムと交際することは社会的にNGのようだったが、どれほどのレベルのタブーなのか、アヌの様子だけでは測りかねた。親から交際を反対されており人目を避けてデートしていることはわかったが、割とオープンな場所でキスしたりもしてたし……インドの観客ならこの辺は肌感で理解するところなのだろうか。
タブーレベルに迷いながら観ていたので、終盤ラトナギリの海岸で誰かが救助された場面では、もしかしてアヌとシアーズ(アヌの彼氏)が心中したのだろうか、実は二人ともそこまで思い詰めていたのだろうかと嫌な想像をしてしまった(もっともイスラム教では自殺は禁忌らしいので、これは見当違いの予感だったのだろう)。
この遭難者、当初はプラバと全く面識のない男性なのに周囲が夫と勘違いしている、という様子だったが、いつの間にかプラバは彼と夫婦として対話していた。この辺、観ている間は正直よくわからなかった。あれ? さっき勘違いされてるとか言ってたよね? ドイツから戻ってきてたの?
恥ずかしながら後でパンフレットのコラムを読んで、このシークエンスが「幻想」だったことを確認した次第だ。ここはもうちょっとわかりやすくしてもらってもよかったかなと思う(読解力のない人間の勝手な言い分です)。
とはいえ、それまで社会的な慣習に押し付けられた形だけの結婚に甘んじてきたプラバが、この対話で自らの状況にようやくキッパリNOと言えたことはよかった。
彼女は、職場の医師にフランクに接するアヌを「誘惑している」と非難したこともあったが、後で思えばそれは彼女自身が、自分を抑圧する古い価値観に無抵抗になってしまっていたことの表れだったのではないだろうか。
ラストでプラバはアヌとムスリム彼氏の交際を受け入れ、カラフルなイルミネーションに彩られた海辺の店でスタッフの子が踊る(典型的インド映画とは別系統の作品とわかっていても、インド映画のDNAに触れたような謎の安心感)。自己肯定と受容が重なりほのかにあたたかい気分になるエンディング。
ひとりの女性の小さな心の成長をたどる繊細なドキュメンタリーを見たような気持ちになった。