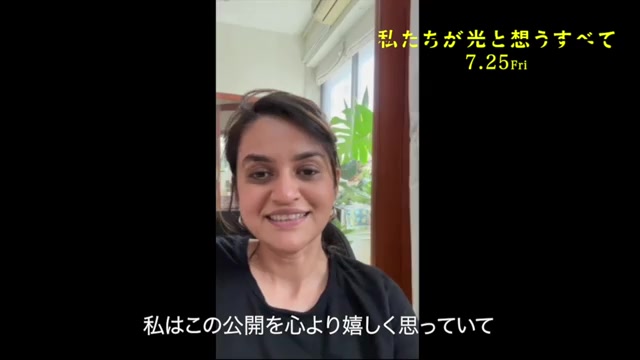「静かに、でもはっきりと表明されるプラバの「NO」」私たちが光と想うすべて あんちゃんさんの映画レビュー(感想・評価)
静かに、でもはっきりと表明されるプラバの「NO」
こんなに静かな語り口のインド映画は初めて観た。もちろん世界に冠たる映画大国だから歌い踊り闘う以外の作品もあるのは当然なんだろうけど。長編第一作とはいえ、俊英女性監督の脚本、演出ということで、なかなかの切れ味を隠し持った作品だった。
プラバは医者や同僚からも頼られる優秀な看護師である。また時として家賃を踏み倒されながらも後輩のアヌとルームシェアし、病院で賄い婦をしているパルヴァディが家を追い出されそうになれば相談にものってやる頼れるお姉さんでもある。
でも、彼女がモヤモヤしているのは、ドイツにいる夫のこと。元々、夫とは勝手に見合いさせられ、よくお互いを知らないうちに結婚させられたのだが、ドイツの工場で働くうちに最近では電話一つよこさなくなった。
この夫がいきなり電気炊飯器を送りつけてくるエピソードがある。この炊飯器が赤色で〜私は小津安二郎の映画の茶の間や台所に配された挿し色を連想したが〜言ってみれば妻を家庭に縛り付けておきたいという夫からのメッセージにみえる。まあとんでもない野郎なのだが、映画のこの段階ではプラバはこの炊飯器を抱きしめて泣き崩れるのである。
ただ、アヌやパルヴァディとともに苦境をくぐり抜けていくうちにプラバはだんだん強くなる。そしてパルヴァディの故郷の海沿いの村で過ごすうちに、海から上がってきた(何か怪獣みたいだけど)夫、もしくは夫の幻影と対峙することとなる。プラバは、溺れて怪我もした夫の命は助けるが、彼を受け入れることははっきり「NO」という。
映画の前の方で出てくる、恐らくはプラバに惚れた医者もそうなんだけど、彼らが利用しようとしているのはプラバの母性であったり包容力であって、ブラバの人格や職能を評価、尊敬して、対等な関係で愛し合うということではない。そこがブラバには見透せたので「NO」ということになったのだと思う。
近年のインド社会の状況はよく知らないけど、インドでも中国、韓国でも、そして日本でも、アジア的な夫婦の関係というのは似たりよったりだと思う。そこに一石を投じている気持ちの良さはあるよね。
そうそう、最後の海辺のバー(といっても海の家に電飾している程度なんだけど)の映像の美しさは素晴らしいです。ここだけでも観に行く価値はあるよ。