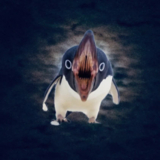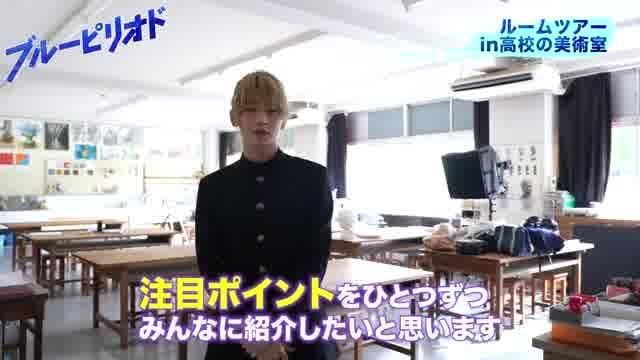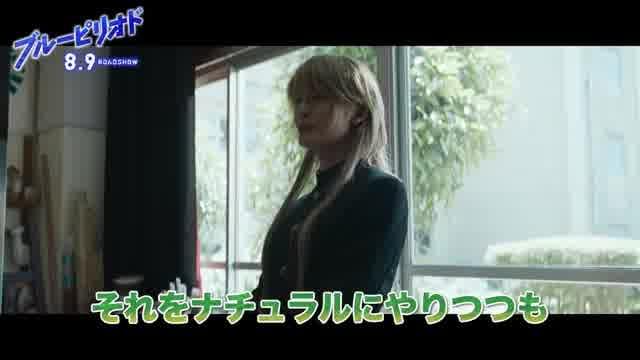ブルーピリオドのレビュー・感想・評価
全75件中、41~60件目を表示
NOISE
実写化される範囲の原作を読んでから鑑賞。
簡略化こそされていましたが、原作の良さを引き出しつつ実写ならではの体現もしっかりされていて、総じて良い実写化だったなと思いました。
美大に入るまでに振り落とされる残酷な様子はそれはそれは生々しく描かれていて、受験での落第とかに遭わずに過ごしてきた自分でもウッと胸を押さえてしまうくらいには辛い描写が多かった気がします。
どれだけ自分の全てを詰め込んだ絵だとしても、言葉一つであっという間に駄作に思えてしまって全てを投げ出して逃げてしまいそうになるリアルさはジャンルは違えど体験したことがあるので、スポーツなり文学なり熱中して挫折をしたことがある人間なら誰しも刺さるんじゃないかなの連続でやられっぱなしでした。
八虎をメインに描くというところで仕方ないっちゃ仕方ないんですが、どうしても原作では重要な立ち位置なんだろうなというキャラが背景とまではいかないまでも細かく描写されないので、物語上機能している風には見えませんでした。
予備校での出会いとかもっと描かれていたら八虎の成長をグンっと感じられただろうなと思うと勿体ないと思ってしまいますが、それをやってしまうと1本の映画には収まらない気もするので仕方なしかなとは思いました。
おそらくフィクションなんかじゃ刃が立たないレベルの難しさである藝大合格までの流れがサラッといってしまったのだけは勿体ないなと思いました。
時間の制約という厳しい問題はありましたが、八虎に焦点を当てるがためにそこへの努力する人たちがサクッと描かれていたのはこの作品の重みがうまいこと伝わらないんじゃないかなと思いました。
森先輩とのエピソードが端折られているせいか、絵を描く事への熱がどうにも削がれてしまっていたのはかなり気になりましたし、桑名さんとのやりとりも少数だったせいか戦友みたいな感じの雰囲気を出されてもう〜んとなってしまうのが残念でした。
原作者が実写の世界を尊重してくれたおかげで、コスプレ感のない仕上がりになっていたのは唸りました。
郷敦くんの飢えに飢えた感じの無気力さから熱を帯びる姿までどれも見事に演じきっていて凄かったですし、高橋くんなんか本当の女子なんじゃレベルの細さと振る舞いが本当に素晴らしく、ゼロワンの時からのお付き合いですが本当にすごい役者さんだ〜となりました。
江口のりこさんの先生の雰囲気も踏襲されていてお見事〜ってなりました。
ブルーピリオド入門編のような立ち位置で、原作にそこまで触れてない自分でも若干の物足りなさを感じましたし、原作を愛読している人は難色を示す作りなんじゃないかなとは思ってしまいました。
とはいえ、一つの物事に打ち込む熱はしっかりと感じられましたし、原作の世界を壊さないように慎重に作られた丁寧な実写だったと思います。
続編も期待したいところですし、ドラマとかでやってくれたらな〜と思いました。
鑑賞日 8/12
鑑賞時間 16:15〜18:25
座席 F-3
うわっ! 凄く混んでるロビー。
それも若い客が多い。お盆はヤング狩り放題かな、じゃあシニア割の年齢とか上げないでくれよ・・。
上手くまとまってたと思う、さすがに合格で良かったよ・・キャストも体温低そうなゴードンくん、魔性桜田さんのフェミニン変化、「からかい上手」とは全然違う文哉くんとハマっていた。
ちょっと気になる江口さんのキャストかぶり、「愛に乱暴」も控えてるのに。
特別良いという所がなく悪い所もなく普通
美大受験経験者なのですが、現実ではこんな素直に絵に一生懸命な子なんて本作の予告でも言ってた現役の合格倍率の200倍と同じ200人に1人とかです
私は芸大に本気で合格したい子を見てきましたが、その子はというかみんな自分の作品にこだわりを持ってます
何言ってんだ?と思いますが、みんなそんな感じで先生のアドバイスを受け入れずにやってきて二浪三浪でようやく合格できます
原作、アニメも見ましたが、八虎くんは凄いですね
私も一次試験を2度ほど受けましたが、あの空気はとてつもなく緊張しました
そして私はそんな空気に耐えられずどちらも失敗しました
そんな経験があったので八虎くんの凄さを感じました
しかし尺があるのはわかっていますが、実写ではとんとん拍子で芸大合格まで漕ぎ着けたのはちょっと疑問を持ちました。
まず受験というものは勝者がいれば敗者がいます
今回のブルーピリオドのメインキャラでは橋田くんと桑名さん、もっと言うと桑名さんです
彼女は原作だと合格発表見て悔しくてライブ帰りに泣いてしまう
私はなんとなくこれが受験というものだと思いました
しかし実写の彼女は正直存在感なさすぎると思いました
橋田くんも特に親しく名前を呼んだりせずなんかずっと馴れ馴れしくてうーんと思いました
また私は八虎くんと同じように油画科でした。
油絵、デッサンには絵作りというものが必要です。
過去の合格作品を見るとみな何か狙いという物があり、それを見て勉強します。
これもまた尺が限られてるのはわかってますが、経験者としては納得できない部分でした。
以前ブルーピリオド(原作)のことが話題になった時、私が通ってた予備校ではあまり良い反応はされてなかったので今回の実写ではどうなのかちょっと気になる…
天国で地獄
直向きな情熱が迸る。
予告で見た「情熱は武器だ」に偽りはなかった。
前田郷敦を初めて見た気がする。
彼はとても綺麗な目と美しい手を持った役者さんだった。美しい指先を持つ俳優は男女を問わず惹かれてしまう。
物語は静かに始まる。
まだ何者でもなく、何者にでもなれる季節。情熱の行き先や所在を探しあぐねてる世代には無茶苦茶刺さると思われる。
「好きな事をする努力家は最強」だったかな、薬師丸さんが八虎に向かって言う台詞なんだけど、ホントその通りだと思う。おまけに彼はそこに飛び込む勇気も持ってた。
絵の事はよく分からないのだけど、芸事になると終わりはないし、完成もない。ましてや好きな事となると、妥協は出来ないし嘘もつけない。そして、努力を努力とも思わない。
至って普通にのめり込む。
その有り様は、外野から見ると狂人にしか見えない事もある。けれど本人はソレを苦とも思わないし、足りないと思うし、渇望に似た貪欲さを発揮したりもする。やってもやっても辿り付かない。どこまでやっても満たされない。何地獄なんだとも思うけど、本人達には天国だ。好きな事にひたすら集中し埋没していける環境はあるが、全ての人に居住権が与えられるわけではない。存在意義を賭けた生存競争に絶えず晒される。
周りは言うし、本人も言う。
「そんな事で食べていけるの?」
金を稼ぐのは大切な事だ。生きていく為には必要不可欠だ。けれど、ソレよりも大切だと判断してしまったなら突き進むしかない。むしろ、そういう輩しか入ってきちゃいけないと思う。
どこで野垂れ死のうが自業自得だ。
バカと狂人しかいちゃいけない世界なんだ。
郷敦氏は灼熱の如き情熱に絆された八虎を好演してた。ご本人境遇とリンクする箇所もあったのかもしれないが見事だった。
加速していく展開も好きで、彼が抱えていた葛藤と闘争を端的に見せるカットも盛り込んであるのもいい演出だったと思う。
失敗と挫折は付きもので、それすら踏み越えてまたは引きずってでも進む。
決意を告げられた夜に、何度も何度も頷いてようやく絞り出したか細い「うん」って描写が胸を撃つ。
そして彼は扉を開けた。
果てしなく続く坂道の麓に立った。
好きな事に向き合って自分と対峙し続けた結果だ。
物語はちゃんと敗者も描く。
誰しもが鍵を手にするわけではない。必ず優劣は存在する。それを認めるか認めさすかは別問題だ。
ジェンダーの彼なんかは「普通」って価値観とも戦ってて彼の口から発せられる言葉はどれも切実だった。
誰もが通る分岐点。
その分岐点に立つのは、果たして幸運なのか不運なのか?選ぶのは自分だ。
なんとなくお利口で冷めた時代だと思っていたけれど、そんな風潮に一石を投じるに値する作品だった。
何者にでもなれる期間は存在するが、有限でもある。葛藤と情熱に身悶える世代に見てほしい。
この作品を見て、引き返す選択をしたとしても、それはそれで幸運な事だと思う。
なんせ、彼らの進む道は死ぬまで地獄だ。
ただその地獄を嬉々として楽しめる素質がある一部の狂人には天国に等しい。
そんな事まで感じさせてくれた監督に感謝だ。
見応えありました。
あ、後BGMの入りが良くてどれも素敵だった。
オープニングとか、なんだかザワザワする。
芸術を感じられる人と一緒に見よう
美術館へ行った時のような感覚になりました。
実物の絵画にはパワーがあります!!!!!
全ての俳優の表情がすごい細かい。なぜそこまで表現できるの…。
少し美術を齧ったことがあるので、どういう気持ちで絵に向き合っているのか分かるし、あの空間の匂い(画材とかの)も分かるし、何を表現してあの絵になるのかとかも少し分かる。エンディングで紙と画材の擦れる音だけになるのがにくい演出!
ですが、単に俳優目当ての人と観に行くと少し窮屈です。「分かんなかった…あの絵怖かったよね…唐突に裸婦出てくるしさ…」と言われて困った。恐らく普通の反応?なのか?
マイノリティの描き方が少し物足りないのと、原作を知っているので、先輩や周囲の登場人物との絡みが端折られていたなと感じます。主人公の蕁麻疹とか原作ではもっと苦しんでる。仕方ないですが。(実物龍二の小田原でのシーンはビクっとします。脚綺麗!)
ルックバックも観ての感想ですが、芸術に焦点を当てた作品が何を訴えかけてきているのか考えてしまいます。「絵なんてさぁ、何になるの?」という問について意識させられる。深く考えすぎ?
あとは、普通()の良い所へ就いて欲しい母がなぜ息子にそんな名前付けたの?っていうツッコミ。
ゴードンさんの横顔美しい。
その一本の線の生命に 心が開花し それに震えた!
前に ”線は、僕を描く” を観たけども
あれ以来だろうか、こんな思いにさせてくれたのは。
今日は「ブルーピリオド」観に行ったのだわさー。
チョット気になってて、毎度何も予備知識一切持たずに作品鑑賞に挑むのやけども、この東京藝術大学に行こうって言うのに惹かれちゃってね。
ただそれだけっす。
美術のネタものってあんまり無いかな。向き合う姿勢ってのが観ていて好きでね。
どうしてもネタ的に 理数系、スポコン系は多いのやけど、
こう言う 一般人がボ-っと見ても良さが伝わり難いので競うのが 更にイイかな。
漫画アニメの作画系ネタは有るけど、結局視聴率とか購買数とか数値で競ってるから理数系の流れでしょかね。
誰なんよ この白髪頭の主(矢口八虎)は??
あぁ~ 眞栄田郷敦さんなのね。歳は別としてカッコイイね。
そして、高橋世田介:(板垣李光人さん)メッチャ賢そう。
森まる:(桜田ひよりさん)主より歳上には見えんなぁ。
大葉真由:(江口のりこさん)居そうな先生。
佐伯昌子:(薬師丸ひろ子さん)配役 そう来ましたかって感じ。
兎に角、絵を描いて、描いて 描きまくる!!
この熱意には恐れ入った。
普通の受験勉強じゃ絶対受からない。
記憶する勉強なんて意味が全くなくて それがまた興味そそる。
自分で常に考えなくっちゃイケないんだね。
ほぇ~ って感心するばかりでしたわ。そこが衝撃的かな。
(良かった所)
・ブル-タス像のスケッチをさせた時、皆のを一堂に並べて視てゾクってしたな。
主のは わざと下手に描いてあった。
高橋くんのは スッゴィ 一目で感動したな。
確かに 心打つよね。皆 同じ石膏像なのに。この違いw
ここのシーンは ホントに絵を描くって凄さが心底に刺さったね。
・母が東京藝術大学への進学を反対して 諦めさせようとした時、主の心が折れたのを察して友人がスイ-ツ店へ誘った所かな。友人が言う~
お前は何やっても天才で何処か手を抜いてて、楽勝で大学進学するだろうと思ってたけど、真剣に絵に向き合った姿勢を見て凄く震えたんだよ。
だから俺は大学行かずにパテシエに成るって決めたんだ!
ここの 友人の矢口に向けた言葉は深いなと思ったな。
・母が疲れて台所のテーブルに伏せて寝ているスケッチを 母に見せる場面。
両親とも一生懸命働いてくれて 国公立大学なら何とか行ける様にしてくれていて、自分の将来が母の思う方向に重なって無くて ゴメンと言う所ですね。
あそこは 心から泣けましたわ。
そして母に絵の方向(東京藝術大学)に進学することを認めて貰う・・・。
(もうちょっとな点)
・ユカちゃん:(高橋文哉さん)の存在が 案外重いのだけども、人物の背景描写があっさり目かな。もう少し深めで出てる方が良いと思うのだけど。
二人して脱いだ点に目が行ってしまって、この感情が惜しいかなと感じましたね。
・最後の試験に合格した絵。
これが どうも私的には仕上がりに納得できてなくて。なんでコレ?って思ってますね。特に下半身なんですよね。うーーん?って言う表現に思えました。
それと肌の色ね。 こう言う点が難しい所でしょうかね。
言葉やセリフじゃなくて 描写(絵)で総てを描き切る。
眞に映画の神髄。チョイと難しいかもだけど
そう想えた所がGoodでしょうか。
興味ある方は
是非劇場へ!!
原作よりリアルな人間のリアクションになったが
漫画表現の歪さや、女性作家から見た男性像の歪さが映画でどうなっているのか気になったので観てきました。
ほぼ歪さが無くなって、キャラの感情がスムーズに共感できるようになった反面、絵の技術に対する情報が削られて魅力が減ったように感じがしました。60点の仕上がりで、昨今の原作無視批判を気にしている感じがしたのは残念です。
個人的に引っかかったのは、ヨタスケ君が主人公を嘲笑ったシーンと、二人が全裸になってスケッチをしたシーンで。
ヨタスケ君は自己の価値観にほぼ完結している人間で他人の作品を嘲笑う姿に違和感があり、恋人でもない2人が全裸を見せ合う事に違和感がありました。原作では視線はほぼ遮られていたと思います。相手を性として捉えるなら配慮が必須で、配慮しまくる主人公とは思えない行動に感じました。そこだけが残念でした。
原作の良さが伝わってこない
作中で描いた自画像やヌードの絵は迫力があり劇場で観る価値があると思います。キャラクターも実写化によくある違和感みたいなのは少なかったです。
肝心の内容はとりあえず受験の最後までやった、という感じで薄っぺらく感じました。
原作を読んで感じた良い所が映画では端折られていたり変わっていたのは残念です。(恋ちゃんとのシーンとか2次試験の描き方に辿り着くまでがあっさり過ぎる…)
合否結果を観に行くとこの橋田と桑名さんも緊張感0に見えますし…
あと世田介くんが徹底的に嫌な奴にされていたのは何なんですかね?出てくるたびにイラッとしました。
「カンハレ」 鑑賞動機:予告7割、原作2割、ユカちゃんを相応の説得力持たせて実写にするのって難しいのでは1割。
映画予告に触発されて原作の一部(4-14巻)を読んだ状態で臨む。(大事なところ読んでない…。)
「カンハレ」では、濁点からいくかそのまま本体へいくかドキドキしてしまった。いただきまーす♪
国立大学で芸術を学べるところは、別に藝大以外にもそれなりの数あるだろうに(筑波の芸専とか)と思ってしまうが、教育学部の系統とは方向性が大きく違っているのだろうか。
眞栄田郷敦は安心して見ていられる。モノローグで補強されてるとはいえ、視線の彷徨わせ方とか、目の泳がせ方とか、特に自身の気持ちが定まらないときの表情はよい。
高橋くん、いやユカちゃんは役柄として非常に難しかっただろうけど、一人称をおそらく意図的に変えていて、揺らぎというかグラデーションをうまく出せていたと思った。
色々と削ぎ落としたことで、特に脇役陣の人物像が薄くて物足りなく思うところもあるが、セルフヌードの場面は…途中驚いたけど納得です。ああっ?! 郷敦が鏡に!
でも好きなことが仕事になると、それはそれで逆に辛くなることもあるからなあ。
描くと言う事
原作はずっと気になって、買うか迷ってたヤツ。本作を観るにあたって2冊だけ試し読みした。
本作は勉学も人間関係もノルマをこなすのは得意ではあるが、ふとしたきっかけで美術の世界にふれ、芯の無い自分に気付いて絵にのめり込む主人公と周りの人々の話で、原作は群像劇的部分もあり既刊15巻でまだ続いている。
映画は東京藝大受験をメインとしている。
映画鑑賞中ずっと思っていた事は、芸術大学を目指した人以外はどう感じ、面白いのだろうか?って気になってました。
主人公が絵を描いてみて、初めて他者に理解される所が原作より割とアッサリ描写されてて、もっとエモーショナルな演出を予想してたので、透明じゃ無い自分の発露から描きまくるには弱いと思いました。
藝大の存在を知り予備校に通いだす中で、主人公以外の人の絵をちゃんと見せないので(石膏像デッサンは比較描写があるけど)、他者の技量や才能の差が分からない。
予備校内での順位に説得力が無いので、高橋クン(原作ではデッサンは抜群だが色を塗るとそれほどでは無い)が予備校を辞めるのも唐突に感じました。
新しい世界を知った主人公が、その熱量で才能を超えた努力(それも才能だけど)で成長する様で見る者を引っ張り結果感動する話なのですが、映画においては結局、勉学や人間関係のノルマを起用にこなす様に受験をこなしたとも感じました。
高橋クンの言う『美術じゃ無くても良かったクセに』は正にその部分で、その熱量が自己表現から受験にすり替わってる指摘と私は思ったのですが、映画の主人公は怒るだけでした。
原作は15巻も続いているので、触れていると思いますが、受験に於ける自己表現や対策等と自分の作品と言える自己表現は根本が違う事が映画では誤魔化されていると感じました。
主題や課題を他者に与えられて描く事と、自分の内や外の問いや答えを魂から引き出し描く事は全く違ってて、それこそ芸術に正解は無いところです。
映画で表現されてた事は、自己表現の喜び苦しみから、いつの間にか受験合格がゴールの様になってました。
そこに感動を持ってくるとお受験映画になってしまいます。
これから始まる自己との戦いを匂わして終わって欲しかったです。
皆の望みが叶うわけじゃない、未来を手に入れることはできない、でも諦めることはできない
主人公は、ある日、打ち込めるものを見つけてしまった、絵を描くということ。
でも人より少し上手い、周りから褒められたからといって順風満タン、何事もなく進むわけではないし、そんな中、気持ちが折れそうになったり母親から言われて心がぐらつく様子は観ていて、なんだか身につまされてしまった。
主人公の気持ちもわかる、でも母親と同じ年代の自分としては芸大に行くというリスキーな未来に向かう息子を心配する気持ちもわかるのだ。
絵の上手い人間はいくらでもいる、それで食べていけるのか、仕事にできるのか。
好きなだけでは駄目だ、才能がないからやめろ、他人や周りから言われなくても本人は自覚していると思う、だからといって捨てること、やめることはできない。
主人公は今回、無事に合格、でも周りの人たちの悩みとか赤裸々です。
望む未来を手に入れられるわけじゃない。
合格はできなかったけど、あの二人は絵を描くことをやめたとして、関わることはやめられないのかもしれないとか。
色々なことを想像してしまいました。
教師って、改めて尊い職業だと思った。
読んだことはないけれど、シーモアで表紙はよく見かけていた「ブルーピリオド」。
映画館で予告編を観た時に、まるで漫画のキャラを再現したかのような眞栄田郷敦さんに目が釘付けになった。
素直に、公開初日のレイトショーに行った♪
何だろう、画面の色味もアーティスティックで、登場人物が妖精のように感じた。
特に高橋文哉さん演じるユカちゃん!
そりゃ、ナンパもされるでしょうよ。
そして、ナンパした男性も、美少女ユカちゃんが男と知って驚愕するでしょうよ!
眞栄田さん演じる八虎も、スポーツバーでオールで友人と遊んでるし。
なんかもう、40年前の高校生とは色々違いすぎてビックリ…私は、高校時代ミスドも親と一緒にしか行かなかった。
全く芸術方面詳しくない私でも、八虎の芸大合格はあり得ないと思うけど、好きなことに突き進む彼の生き方に、心が動いた。
薬師丸ひろ子さん演じる佐伯先生が、八虎にかけた言葉「あなたがそう見えるなら、りんごもうさぎも青くていいんだよ」、好き。
ユカちゃんと八虎の海のシーンも、色々エモーショナル。
八虎が、ユカちゃんの電話を受けた後、ユカちゃんのいる海に走り出したところ、かっこよかった。
こんなふうにむき出しの本音を伝えあえる関係、貴重だよ。
来年、子どもたちが就職し、人生で1番したかった子育てが完了する予定。
その後は、私も、ずっと胸の奥で眠っていた自分の夢を追いかけることに決めた。
あー、八虎の今後が気になる。
シーモアで「ブルーピリオド」を買いそうな気がする(*^^*)
プロモーションとしては、この映画、大成功と思う。
或る街の群青
原作・アニメ共に未見、キャラデザや設定も確認してないため、再現度なども不明。
入試までに絞って上手く纏めたんだろうな、という印象。
良くも悪くも派手さはなく、森先輩の絵との出会いや描画シーンなども演出は薄い。
その割に挿入歌演出が多用されるが、これが上手くない。
ダイジェストのような勢いやテンポ感はなく、音が大きいせいで台詞が聞き取りづらい。
短いカットの連続で八虎の努力を表現するような、ベタな使い方でよかったと思う。
ユカちゃんや森先輩はキッカケを与える装置のような立ち位置だし、予備校同期も特にエピソード無し。
級友や高橋くんの絡み方も中途半端で、あくまで八虎の話に絞られている。
尺の関係で仕方ない部分もあるのだろうが、脇キャラの扱いは少し残念だったかな。
とはいえ演技は全体的によかったし、石膏デッサンの力量差などは非常に分かり易かった。
八虎が渋谷の絵を描く前の演出も面白い。
ただ、最後のヌード画の良さが素人目に伝わらなかったし、タイトルの意味も分からず終い。
2次試験の体調不良や腕のアレは必要あったかな。
家計に余裕がないにも関わらず渋谷で飲み歩き、キャンバスや絵の具を買い漁るのも違和感アリ。
(オール明けに八虎だけ毎回制服になってたのは何?)
旅館の宿泊費は誰が出し、何故裸を描く時に電気消した?
細かいこと気にせずサラッと見る分には、後味もいいし十分楽しめる。
八虎は、龍二じゃなくてユカちゃんと呼んであげよう。
受験のヒリヒリ感と芸術の魅力が楽しめる傑作!
東京芸術大学に合格するまでの苦闘と(本人は苦闘とは思っていない)、人間的成長、努力と天才とは、そして芸術とは一体何なのか、という大きなテーマのストーリーは、ずしりと観るものに感動を与えてくれました。そして、言霊が凄いです。『絵は言葉ではない言語』(絵は表現方法の1つ?)。『好きなことをする努力家は最強なんです』(かつての偉人たちは皆さんそうかもしれません?)この二つの言霊は、高校の美術教師の薬師丸ひろ子が呟きますが、心にグサリと刺さりました。そしてもう一つ。『絵を描くことは人の幸せを祈ることである』という先輩女子の言霊。なんて素敵なのでしょう!これが最強の芸術家の魂なのかもしれません。私見ですが(信じなくても良いです)、人間一人一人には必ず守護するものがついています。そして何か仕事を成し遂げる人には、その人を最高のレベルに持っていくために、やはり高度な守護するものがついていると考えます。その守護するもののレベルが高いときには、その人のなす仕事は天才的に見えるのでしょう。どんなに努力を重ねてもなかなか伸びないのは、守護するもののレベルが弱いのかもしれません。ですので、天才か努力家の差異は、ひとえにその守護する力のレベルの差としか思えません。そして、今世で努力家の域を出なかったものは、来世に生まれ変わって天才に近づくのでしょうか。
追記 めちゃくちゃ泣いたのは、母が息子が好きなことをやろうとすることを許すシーン。これが本当の親子の愛なのだと気付かされました。好きなこと、楽しいことを選ぶことを許す時代に突入しているのでしょう。
凄い面白かった
原作は既読です。
気になった部分もあるけど、それ以上にワクワクしたり面白いと思った場面が多かったので、とっても楽しめました。
原作は群像劇みたく様々な要素が込められているので、どうまとめるんだろうと気になっていました。その点、実写は主人公である矢口八虎周りのエピソードに絞って、藝大受験までを描ききったのが好印象です。
音楽の使い方も個人的に好きでした(けど過剰だと思う人の気持ちもわかります)。特に序盤から青い渋谷を描くまでは、カメラワークも相まってゾクゾクしました。
やはり気になったのは予備校の面々や高橋くんといった、八虎周りの存在を上手く扱えていなかった部分です。喋らせるなら喋らせるで、きちんと役目を作ってあげて欲しかった(尺的に難しいのは理解してます)。加えて、その他複数のキャラの解釈が少し違うような気もしました。
ですが気になった点は全て私の主観的な意見です。なので本作を一つの映画作品として見た時の、素晴らしさや面白さの方を尊重したいです。
エピソードだけなら、映画。背景やキャラを知りたいなら漫画へ
シーズン1を2時間に収めるなら、こうなるしかない。
作中出好きな作品をカラーで拝めたので、私は満足しています。
オープニングの作り方、音楽から、原作への愛を感じますし、私が好きなエピソード(八虎に影響を受けた友達がパティシエ目指すって言った)やシーズン1の名言は、ほぼ全詰めでしたね。
その分、それぞれのキャラが薄くなるのは仕方ない。だから、この映画をみて、ブルーピリオドに興味出た方は、是非漫画へ。
原作では目立たないはずの八虎パパのずんのヤスさんが濃すぎた…
八虎というより、眞栄田八虎という感じがして、昨今のコスプレ実写化ではないところに、彼の俳優としての凄さを感じました。
自分がやりたい事を探し、自分を信じ、突き進め❗️
学園ものの映画🎞だと、愛だの恋だの。。。チャラチャラしてるのかな❓(^◇^;)💦思いきや。。。そうでなかった。真栄田郷敦演じる、矢虎主人公が、自分のやりたかった夢を見つけ、いろんな人と出会い、夢を実現する為に奮闘し、努力し、苦悩し、もがきながらも最後は、自分のやりたかった事をやる❗️(合格する)物語。 全体的に爽快感があって、観てて楽しめました✨
脇役の俳優人が豪華❗️薬師丸ひろ子、石田ひかり、江口のり子❗️それぞれが味がある役者さんで演技が上手❗️観て良かったです✨
江口のりこのバイプレーヤーぶりがすごい
原作一巻の途中までは読んだ。映画の冒頭はほぼ原作トレース。でも中盤から後半って結構はしょってるんじゃないかなあって。父親のキャラ、結構変わってて。あのキャスティングだと父はあまりからまないよね。
女の先輩とか予備校の天才くんとかとの絡みが中途半端なのは、やっぱ時間の関係なのかな?全体的にエピソードがつながってない感するのも、そうなのかな?って。
あと、出てくる作品に「すげえ!オーラ」がないんだよなあ。
でも、講師役の江口のりこさんってすごいよね。すごく作品を引き締めてた気がする。存在感あるよね。主役じゃないからこそ出せる存在感はすごいなあって思った!
んで、テーマ曲は「群青」が良かったんだけどなあ
全75件中、41~60件目を表示