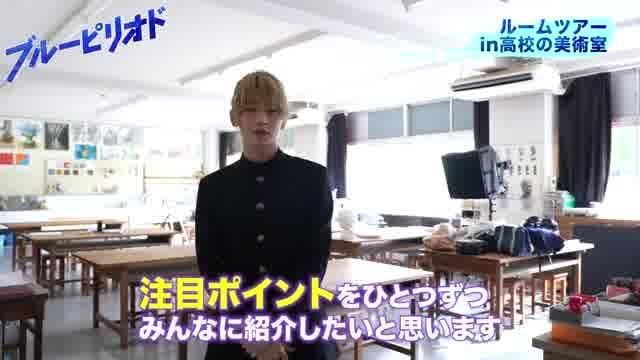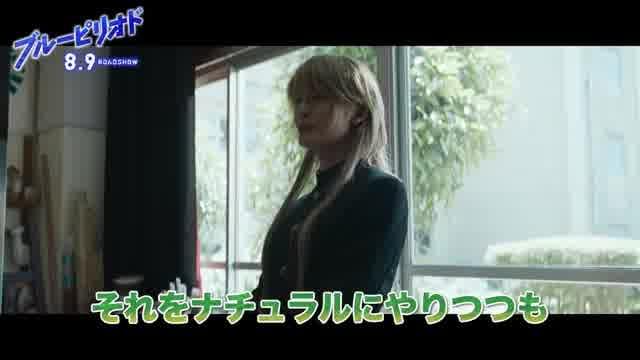ブルーピリオドのレビュー・感想・評価
全301件中、21~40件目を表示
主人公の熱は感じるけどストーリーは平坦
ストーリーは良かった
絵を描きたくなった
最初は眠くなるが絵を描き始めてからはおもしろい
原作未読で映画のみ見ました。
最初はヤンキーぶった中二病ドラマか??というくらい面白くなかった。
金髪に染めて遊び散らかして頭いいですみたいなよくある少年マンガのキャラクター。
成績が良いのだったらお勉強シーンをもっと入れてほしい…遅くまで遊び歩いて成績がいいわけないじゃん。
高校生がタバコ…おっぱい…
どこが青春や…不真面目なシーンばっかり…ここで眠くなりDVDをいったん中断し睡眠。
そしてせっかく借りたし…見るか…と、なあなあな気持ちで再開。
絵を描き始めてからは面白かった。
江口のりこさん演じる先生がすごくいい味出してた。
板垣李光人さんというライバルが出てきて空間が引き締まった感じがした。
ユカちゃん役の子誰だと気になって検索かけてしまった。
仮面ライダーの方なんですね。そりゃジャンプとかうまいわ。
しかしユカちゃん役の子をもう少し掘り下げて詳しく背景を表現してほしかった。
親と仲良くないんだよんね~というくらいじゃ映画ではうまく伝わらなった。
ユカちゃんに関して悲しみや苦悩の表現がもっと欲しかった。
美術は自分と向き合うところがたくさんあると思う、精神的に追い詰められる人もいると思う、
どんどん減っていく仲間というのも(7人の侍みたいで)寂しさと覚悟が極まってきて良かった。
みんな苦悩する様子もちゃんとあってよかった。
ヤンキー仲間も、仲間(主人公)が付き合い悪いの良く許したなと思う。
田舎のヤンキーなら一人だけ真面目になるなんて許さないと言わんばかりのもめるシーンが絶対入ると思うけど都会という設定だからまた違うのかな。
親が都合よく理解ある人で良かったが、もっと戦う設定でも良かったかも。
親の希望を押し付けてくる親って結構いると思う。あんなにすんなり理解してくれるってありえるんだろうか。
理解ある親役に芸人さんを起用したのは良かった。
どことなく親近感のあるお父さんだった。
とりあえず必死に絵に向き合ったのなら髪は染めないで黒くなっていくようなシーンがあってもよかった。
最後までずっと金髪だったのはなんだかなあと思った。
東京芸術大学に興味ある人や美術系大学を受けようか悩んでる人におすすめです。
参考になるシーン多数あると思います。
好きなことをする努力家
マンガ大賞なんですね。物語の骨格がとてもいいなと思いました。青春映画というと恋愛ものが多い中で、自分の進路を探求するというもう1つの大きなテーマを真正面から描いていて、共感しました。萩原健太郎監督作品は初めて観ますが、好みの演出かなと感じました。特に間の取り方に好感を持ちました。過剰なほど膨大な情報にさらされる現代人は、いかに短時間に情報収集・取捨選択するかというタイパに追われていて、映画でさえ移動時間中にスマホで観たり、倍速で観る人ももはや珍しくないようです。でも、「たくさん知ってる」だけで心底満たされることはないだろうと思うことがあります。今作は、主人公・矢口八虎(眞栄田郷敦)が青い絵を描く前と後の変化が見所でした。前半のスピード感とは変わって、自分の課題に向き合う後半は、答えに窮し、思うように進めなくなり、じたばたする反面、地に足が着き、自分の本心を言葉を選んでしっかり間をとって話すようになります。その時々の郷敦の表情がいいのですが、とりわけ美術教師・佐伯に扮する薬師丸ひろ子との対話がよかったですね。恩師との出逢いが人生を変えることがある、ということをいくつかのシーンでしっかり描いていて、心に響きました。とても好感がもてる作品でした。
引きこまれたけど、もう少し見たかった
主人公に関わってくれる人たちの前向きな言葉や行動で葛藤しながら成長していく姿に、大人になりすぎた自分には眩しくも羨ましくもあり、最後は私もガッツポーズしそうになりました。
映画製作の都合もあるのでしょうが、主人公と関わる人たちの成長や心の中ももう少し見たかったです。
原作読んで、って事なのかな?
圧倒的な熱量で描く青春
主人公を完ぺきに自分目線で観ていました。
八虎の焦燥感、葛藤、決意、喜び。
多感な高校生を勢い良く表現していて素晴らしいです。
才能なんかなくていい。
自分がこれがやりたいと決めたら、その思いで突き進めばいい。
龍二の言葉じゃないけど、
「悔しいと思えるならまだ闘える。」
そう信じて努力を重ねる八虎に心を揺さぶられます。
特に印象的だったのが、親友とタルトを食べてるシーン。
母親に反対され、失意の中で彼を奮い立たせたのは、絵に打ち込む姿を見てパティシエになることを目指す、友達の言葉だったというくだりです。
自分の歩んでいる道は間違ってない。
そして友の優しさに、思わずタルトを無我夢中でかぶりつくしかない。照れながら。
「これ旨いぞ」という所が八虎の人柄が垣間見えて熱いです。
そんな純粋な思いだから、受験に反対していたお母さんをも味方にできたんですね。
母親演じる石田ひかりさんが、息子への接し方や空気感が凄く素敵でした。
息子の進路に理解を示した最後
に、書いてくれた絵を見つめ一言、
「ご飯食べなさい」
もう最高です。
母ちゃんはこうなんです。
久しぶりに泣いてしまいました。
話の時間経過があっという間でポンポン進んでいくのに、1つ1つ丁寧に作られているから、どのシーンも見応えがあります。
そして何より、東京芸大合格を単なるサクセスストーリーのような共感しにくい物語ではなく、人間ドラマとして昇華させたのは、ひとえに八虎演じる眞栄田さんの作品に没入する熱量だと感じました。
いい映画でした。
とても上質な映画で驚いた
タイトルなし(ネタバレ)
こんなに薄っぺらい話だっただろうかと思った。
2時間という短い中で、起承転結を作ろうと思うとこうなるのかな。
もっと世田介くんと八虎との関係とか、八虎のじんましんがでるほどのストレスとか、深いところまで描かいて欲しかったなと思う。
物足りないが
原作既読。
個人的には、重要なシーンを2時間に上手くまとめられてたように思う。
実写だからこそ、彼らが描いた絵や見ている絵を映像で見られるのが良かった。
こちらも八虎が見ているものを一緒に見ることで、彼の感動や思いを直に感じ取れた気がした。
ただ、映画に詰め込むために登場人物同士の絡みが薄いし、それぞれを掘り下げないため各々が抱えてる葛藤が見えづらかったのが残念。
キャストはみなさん素晴らしかった。
特に大葉先生は原作そのまま。
眞栄田郷敦くんもピッタリで、彼が八虎役で良かったなと思う。
原作と比べると物足りない感は否めないが、作品としては好きです。
また観たい。
最強論 ~美術編~
原作が好きで、期待値が高過ぎました
原作を読み高く評価しています。アニメは観てません。予告編を見て本作は気になっていましたが、劇場で観る機会がなく、最近、アマプラの配信開始を機会に鑑賞することができました。
眞栄田郷敦の風貌は矢口八虎によく似せてはいるものの、矢口は原作で不良という設定だったっけ… ほかにも原作のイメージとは異なるほどに、話の展開が単純化されて淡白で、原作に対する愛おしさが感じられず、本作は原作の味わいと無縁のものになってしまっているのが残念です。作品によっては映画化されて、映画独自の魅力が創造された結果、原作とは別物だけど高く評価できるものもありますが、そうでもなさそうです。郷敦以外のキャラにはいずれも魅力が乏しく、演出は平板で、原作のドキドキ、ワクワク感がありません。郷敦の無駄遣いとも思いました。もったいないです。
好きな事に一番ウエイトを置く
眞栄田郷敦扮する不良優等生の矢口八虎は友人達とスポーツバーで盛り上がったりしていたが、日頃から手ごたえの無さを感じていた。
眞栄田郷敦主演作は初めて観るな。若いのに渋いなと思ったよ。大学進学について家庭の事情から国公立じゃないと無理と言われるのは辛いね。美術教師役で薬師丸ひろ子登場。自分が描いた絵が褒められるのは嬉しいだろうな。絵を描くのが好きだからといって美大を目指すのは如何かな。好きな事に一番ウエイトを置くなんて先生のアドバイスは罪だと思うよ。東京芸大受けるなんてさ。才能一本に賭ける、だけどそれも他人事の青春か。親ならたまったもんじゃないな。悩ましいね。でも息子に懇願されたら反対出来ないよな。なかなか説得力あったよ。
全301件中、21~40件目を表示