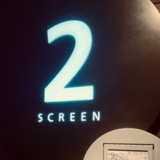国宝のレビュー・感想・評価
全566件中、161~180件目を表示
光は見せたが、境地は描けず
映画『国宝』は、人間国宝という称号に至る芸道の苦しみと、その背後にある人間的な業を描き出す意欲作である。吉沢亮をはじめとする俳優陣の演技は迫真に満ち、舞台シーンには息を呑む迫力があった。
小さな注文をつけるならば、義母(寺島しのぶ)、義父(渡辺謙)、そして小野川万菊(田中泯)へとつながる人間関係が簡略化されていた点は惜しい。ただし、尺の都合上やむを得ない部分もあっただろう。
しかし看過できなかったのは、隠し子との対面という局面で娘が父に向かって発する「役者としての賛辞」である。あまりに安易で説明的であり、業を背負いながら舞台に立ち続ける人間国宝の姿を象徴的に描ききるはずのラストを、陳腐な和解と感動の演出へと引き寄せてしまった。
さらに言えば、業の深さを超えた先にある「国宝にしか辿り着けないはずの」澄み切った境地を、光一本の暗示にとどめるのではなく、確かな像として描き出してほしかった。
俳優陣の努力と舞台シーンの緊張感は確かなだけに、ラストの安易な謝辞と境地描写の不足が、作品全体の美しさに水を差した。業の深さそのものは見事に表現されていたが、それを超えて芸道に昇華する崇高さが、最後まで届かない。その不在こそが、本作を惜しくさせる最大の要因である。
何がこの映画を特異にしているか
2回目の鑑賞(前回は8月1日)。1回目は主人公の喜久雄に感情移入していたようで、最初の道成寺で泣き終えて、そのあとはやや感動の押し売りの感がしたが、今回はシュン目線でも観れたせいだなのか、後半も泣けた。
>>『国宝』は若いアイドル的な俳優が主演とあって、若い観客層を動員している
そういう地域もあるらしい。わたしが見た回は2回とも間違いなく50代以上がほとんどだった。(ブログの書き手にとっては50代は若いんだろ、との忠告も頂いた。確かに。)
嘘つきや裏切り者に罰があって観る側は満足するわけで、裏切りがあるとすれば万菊と春江になる。2人への罰を望むむきはまずないだろう。この作品の何が観客に満足を(満たされない現実生活の救いとなるものを)与えているか。そこを考えるときに、ワイドショーの観客インタビューにあるような映像の美しさとか役者の芸達者ぶりということを書くつもりはない。
自分が役を獲るために、息子に役を与える為に、権謀術数をめぐらしライバルを蹴落とすことがない。登場人物にさまざまな障害が降りかかるが、陥穽にはまるわけではない。おかみさんは菊ちゃんをキタナイと言うが息子に対してもキタナイと言う。
この映画は、嘘も策略も皆無ながら観客を飽きさせないという意味で、清廉潔白だと言えるだろう。「てな感じで言ったら(怒ったら)オモロいんやけどな」の台詞のとおりに、僻むにしてもありきたりな僻みはない。勧善懲悪を目指すドラマティックな展開と一線を画している物語の清浄さが多くの人を魅了して飽きさせないモトなのかもしれないと思った。
血と芸と犠牲と惚れと…
跡取りとすべきなのは血か芸か?
母性で考えると圧倒的に血一択。
父は死ぬ間際に息子の名前を連呼していたので、やはり本音では血が本命であるものの、糖尿病を患い敢えて、血を選ばなかったのか?
万菊も血が本命ではあるが、糖尿病の遺伝を見越して3代目を呼び戻したのか?
物事を極める時、周りの人は犠牲になっても仕方ないのか?
圧倒的に極める時、犠牲になった人さえ惚れてしまうのか?
極めたものにしか見えない景色がここにある。
原作が良すぎる分どうしても…
原作を読む前に一回鑑賞をし、原作を読んでから二回目の鑑賞をしたレビューになります。
どうしても、モヤモヤが消えないのが正直な所です。やっぱり徳次がいない、彰子がいなくなる、客席との境界が消える、喜久雄が俊介のような時期を過ごし、歌舞伎から離れているような描写がある、そこから復帰、足の切断までが早すぎる、喜久雄の辿り着いた先が違うなど、原作との相違点が多すぎてしまい、作品に没入出来ませんでした。
やっぱりNetflixなど、資金を投じてドラマで見たい、それか原作のように上下で分けて欲しかったです。徳次がいたから喜久雄はやっていけていましたし、彰子さんは喜久雄を支え続けていますし、何なら綾乃との関係も無くなっていません。原作のネタバレになるので控えますが、喜久雄はもっと歌舞伎に身を捧げて、ずっと躍り続けます。それが無くなってしまっているのが一番寂しかったです。
色々と書きましたが、それでも歌舞伎のシーンは素晴らしいです。徳次のセリフも、他のキャラが言っていたり、暖簾にも徳次の名前があったりということはありましたし、三時間で徳次は無理だったんだろうなとは思いました。
本当に演技なりセットなり音楽なりと、様々な熱量が素晴らしい分、脚本が気になってしまうというのが正直な今の感想です。
人生の縮図
1.運命と犠牲
人には変えることのできない運命があるが、抗うことはできる。
ただし、何かを得るには何かを犠牲にしなければならないこと。
喜久雄は家族を捨てる選択をするが、国宝という名誉を受け取ることができた。
その後、娘と再会。
娘は、父としては認めないが、歌舞伎役者としては認めた。
倫理的に家族を捨てることは間違っているが、喜久雄がとった選択は間違っていなかったとも言える。人生において、あなたは何を選びとりますか?と問われているようだった。
2.友情
喜久雄と俊介は意気投合するも、互いに嫉妬をする。
喜久雄→俊介の血筋、家族の存在
俊介→喜久雄の演技の才能
途中は蹴落とすようなシーンもあったが、最後にまた同じ舞台に立つことができた。
互いに憎むこともありながら、リスペクト故と感じた。
3.圧倒的演技力
吉沢亮と横浜流星の作り込みに驚嘆。
どれだけ練習したんだろうかと思うほどの圧倒的演技力だった。
もう一度観たいと思える良作。
熱?圧?
原作未読。
画面から演者の熱と言うか、圧を凄い感じる。ほぼ、狂気と言うのを吉沢亮が発してる。
ただ、原作未読なので何とも言えないんだが、コレ凄い原作カットしてるんだろうなぁ。
俊介と春江の駆け落ち(で良いのか?)のくだり、俊介が逃げ出すのは分かるんだが、春江はなんで?でっ、何年の経って帰って来たら、即復帰出来る。多分、この辺の二人と喜久雄の葛藤って(原作で)凄い大事に書かれてるんじゃないかなぁ。
しかも、半二郎が死んだ途端に、喜久雄が干されるって。いや、ホンマに血の世界だよなぁ。
人間国宝の万菊が木賃宿みたいな所に住んでるって・・・・・この人も血の外の人だっけ?
でっ、その人の前で踊ったら、突然に(彰子利用した事)許されて復帰。
高畑充希も、えっ、その役ですか?って感じがする。嫌いじゃないし、むしろ好きな役者だけど、その役ですか?
寺島しのぶはなんか・・・・ガチ過ぎて怖い。
納得の高評価 ストーリーはあえて単調で良い
公開から2ヶ月以上経ってしまったが、映画館で鑑賞できて本当に良かった。配信されてからでいいと思っている人は、できれば映画館の音響と大きなスクリーンで観てほしい。歌舞伎を観るという観点からも、観客席に近い環境が大事だと思う。
一見、「わかる人にはわかる」系の映画かと思うが、意外にも理解しやすく、一般の視聴者でも場面ごとのテーマを感じ、考察しやすいのも大ヒットの理由の一つと考える。それが物語に空白がないとか、ストーリーが単調だという一定の低評価にも影響しているが、個人的には歌舞伎という馴染みがなく難しい題材だからこそ、良いバランスだと考えている。
また色も重要なテーマの一つで、真っ白な雪の庭の中、真っ赤な鮮血が流れる父が撃たれるシーンと、女方の真っ白な肌と真っ赤な唇・隈取はリンクしている。父が撃たれた悲しみを感じながらも、あの光景は喜久雄にとって最も鮮烈な記憶であり、どこか美しさも感じていたのではないだろうか。
血統に守られ苦しめられた俊介についてや、喜久雄に打ちのめされた俊介と春江が共鳴し合ったこと、二代目半二郎の役者としてと父としての苦悩、女性たちを敢えて深く描かないこと、など多く考察されている点については、概ね他の人の意見に同意する。
ただ、前述したようにストーリーが単調だという意見に対しては、ドロドロした人間模様や騙し合い、あっと驚く展開は作品をチープにしてしまうと思い同意しかねる。逆に登場人物全員が悪意を持って行動していないのが、この作品の長所だと思う。
歌舞伎に対しての知見は全くないことを最初に断っておくが、吉沢亮と横浜流星、また子役の2人の演技は圧巻だった。
吉沢亮さん、ただの超絶イケメンだと思っててごめんなさい。万菊さんの言う通り、顔があまりにも良すぎると芸を見てもらえないこともあるんですね。
そういえば、喜久雄(キクオ)と万菊(マンギク)の音が共通していることは何か意味があるのか。少ない登場人物の中、音を重ねず名づける方法はいくらでもあると思うが...
魅入られし者
凄かった。
吉沢亮は天才なのか?
素人目には全くもって歌舞伎役者のしかも女形の逸材に見える。首の角度から指先に至るまで、全身に纏う所作事に見事なまでに隙がない。
横浜氏もいい仕事してた。
最後の曽根崎心中には家系の血統を感じた程で、才能でも凌駕できない何かを見たような気にもなった。
晩年の白虎を演じた謙さんは仲代さんを彷彿とさせるし…なんか色々凄まじかった。
それを演出した李監督の凄まじさよ…。
魂でも焼き付けろと言わんばかりの構成だった。
3時間の長丁場なれど、生き様を描くわけだからそれでも足りないぐらいであろう。
世襲制の歌舞伎界に、稀有な才能を有する逸材が取り込まれていく。花井家の御曹司とそこに引き取られた養子の話だ。よく出来てた。
御曹司の劣等感も、養子の狼狽も。
節目の曽根崎心中で魅せた吉沢氏…アレを作り上げるのにどれ程の稽古をしたのだろう。役作りって言葉を当てるのが申し訳ない程で、それこそ劇中にもあったけど骨格から変えていったと言われても納得してしまう。
曽根崎の初演…そりゃ御曹司も居た堪れなくなるわ。
舞台に立つ吉沢氏は、役に必要なもの以外何も見えてないくらいの没入感があった。
海外の役者のソレとは違い、内に内に掘り進めるような没入感だった。
2人とも挫折と葛藤を繰り返すも歌舞伎から離れようとはしない。御曹司は離れられないような部分もあったけど、吉沢氏の方はしがみついてるようでもあった。
ストイックって言葉を使いはするが、そんな類いのものではなく、何かを我慢するのがストイックだとは思うのだけど、それしか要らないはストイックとは言わないんじゃないかと思う。
他に欲しいものがない。
「神様に頼んだんやない。悪魔と約束したんや」
抜群に的を得た台詞に思う。
またこの2人が仲が良いのが小憎らしい。
名代を奪われるって「死」と同義な世界だろうとも思うのだ。が、飲み込む。
吉沢氏に朱を差す横浜氏は…どんだけいい奴なんだと思う。押し潰されそうな吉沢氏から始まるこのシークエンスはとてもお気に入りだ。
作中の時間はどんどん過ぎて、吉沢氏が人間国宝に認定される。ホントに見事だなぁと思うのだけど、吉沢氏の衣装を直すカメラマンが娘さんならいいのになぁなんて事を思う。彼に触れる指先がなんかとても優しかった。そしたら、娘さんだった。
「あんたの事、お父ちゃんやと思た事は一度もない。色んな人傷つけて何が人間国宝や。せやけど、そんなあんたの舞台を見て気がついたら無茶苦茶拍手してた。お父ちゃん、ほんまに日本一の役者にならはったんやなあ」
こんな台詞が、楽屋から舞台袖にスタンバる吉沢氏とカットバックされる。
「隔世」って言葉を思い出した。
仏教用語だったか、現世とは違う冥界だったり幽界だったりを差す言葉だったか、また神の視点から見る現世を示す言葉だったか定かではないし、こんな漢字だったかも覚えてない「幽世」こんな感じだったかもしれない。
が、舞台に向かう役者の心情ととてもリンクしてて、舞台の上には一切を持ち込まない覚悟なのか礼儀なのか、そんなものを感じてた。
国宝と呼ばれるに相応しい佇まいをその姿から感じてた。
いや、ホントに凄かった。
題材が題材だけに、説得力が必要不可欠で、踊りもそうだし、発声もそうだし、何より芝居が誤魔化せない。
舞台であるならばUPがないからソレを表現する事は出来る。が、客に目の奥まで覗き込まれるようなアングルでは逃げようがない。
逃げる気も更々無いんだろうけど、地力が問われるというか、真価を量られるというか…今後の役者人生を左右される程の現場ではなかったのだろうか。
今までJOKERを演じたホワキン・フェニックスが鳥肌立つくらい圧巻だったんだけど、日本の芸能界にもそこに並び立つ逸材がいたと思えたわ。
あと…田中泯さんの悍ましさが群を抜いてて、彼1人で歌舞伎界の因習だったり系譜だったりを一身に背負ってて、闇が深かったわー。
やー、あてられっぱなしだったなぁ。
最後のインタビューん時の吉沢氏の肩幅とか、もっと撫で肩になってる方もいるけれど骨格を制御しなきゃ出来ない姿だったもんなあ…凄かったです。
吉沢亮さんや横浜流星さんの演技に圧倒されました。
3時間という長い時間が、あっという間に過ぎ終始見入ってしまいました。特に歌舞伎の舞台での演技が、本物の歌舞伎役者さんかと思うほどでした。
内容は小説の本筋とおおよそ同じなのですが、映画の中での俊介の母の性格、中間部分の喜久雄が一般の人から受ける暴力シーンなど小説にはない部分に少し残念な感想を持ちました。また、その暴力のきっかけとなる事柄については、ラストの喜久雄に関わる大切な部分となる事柄だと思っていたのであの様な形のシーンに変えられたのは本当に残念な感想を持ちました。
それでも、全体的にとても素晴らしく映画のラストでの喜久雄の舞いは見ているだけで涙が出そうなくらい感動しました。
時間があれば、もう一度劇場に観に行くつもりです。
日本版「セッション」
血と盟友と家族、すべてのものを悪魔に捧げて初めて辿り着ける境地、人間国宝。
「セッション」では成長や努力といった狂気を巧みな映像表現によって描いていたが、本作では「血筋への渇望」や「継父、盟友との死別」など、かなり記号的なストーリー上の事実を積み重ねているだけのように感じる。
芸を極めるために、家族を捨てることで得たもの、継父や盟友との死別を乗り越えた先で得たものというのが描かれていない。芸に邁進する姿というのも中盤以降あまり描かれず、
なぜ人間国宝に辿りつけたのか、辿り着けなかった者と何が違うのか、かなり不明瞭に感じる。
芸以外のものをなぜ捨てる必要があったのかを描かないと「つらい経験をして人間として強くなった」という非常に曖昧な結論にしか辿り着けず、説得力に欠けると思う。
画作りは圧倒的にきれいで、役者の演技も素晴らしいのでぱっと見は良い作品に見えるが、冷静に考えるとストーリーの重要なところは非常にぼやけている。
極めつけは最後の鷺娘。このシーンは歌舞伎以外のすべてを捨てた結果を示す、本作で最も重要なシーン。息を飲むような、あるいは息をすることすら忘れさせるほどの演技、演出が必要になるだろう。
しかしこのシーンではBGMを大音量で流していた。私にはBGMでごまかしているようにしか見えなかった。音楽が大音量で流れているから感動するような、そんなに簡単に人の心は動かない。実際の歌舞伎で流れるはずのない音楽を流すことで凄みを嵩増しして人間国宝を表現しようとするなんて、安直すぎる。
セッションと同様のテーマにしては説得力に欠けるし、そうでなければただ主人公の皮肉めいた人生を描くだけの作品に成り下がる。
画作りがすごくよく、役者の演技も良かったと思う。この映画独特の雰囲気がかなりあっただけに残念な一作。
吉田修一のスゴさとヌルさ
面白いよね。
観てて「さすが芥川賞を獲ってからエンタメ路線に転向した作家の作品」と思ったもん。
でもグレてしまった横浜流星が戻ってきて、今度は吉沢亮が追放されてしまうあたりで「ん?」と思うのね。
なんとか吉沢亮も戻ってきて、そしたら横浜流星が足を切り落とさないといけないってとこで「んん?」と思うの。
しつこいんだよね。この作品、そこまで「こっちを苦しめます、はい、次はこっち、ついででもう一回こっち」ってやらなくても描けそうな気がすんだけど。
普通のエンタメ作家がやってるなら気にならないんだけど、吉田修一だからね。《パークライフ》で芥川賞とった。ちょっと一言いいたい。
同じことの繰り返しになっちゃってる気もするけど、みんな繰り返し好きだから、多分、いいんだろうな。
みんな、なんとなく収まるところへ収まっていくけど、森七菜が可哀想だね。
完全に利用されただけだもん。「お、森七菜でてきた」と思ったら利用されてるからね。
役者はみんな良かったけど、なかでも高畑充希よかったな。
横浜流星が逃げ出す前後の演技がすごかった。久しぶりに高畑充希を観た。
吉沢亮は、芸に精通するにつれて、色んなものを失うんだよね。
見上愛は最初から「二号さん、三号さんでいい」って吉沢亮と真剣に愛し合おうとしないし、高畑充希は結婚を申し込まれても身を引く形で断る。
この辺が不幸といえば不幸だけど、自ら望んだ不幸で、芸を手に入れたからいいんだってことだね。
最後に三浦貴大が「あんな風には、生きられねえよな」と我々を代表して言ってくれるね。
観てる間『こんなシビアな世界に身を置かなくて良かった』と思いながら観てたからね。
ラストで出てくる瀧内公美もさすが。
これだけの出番で、とても大事な台詞をビシッとやり切れるのは瀧内公美ならでは。
あと映像観てて、1970年代の日本はきれいだなと思った。
日本の勢いが衰えていない頃というのが大きそう。
それでファッションがいまとほとんど変わらないね。横浜流星や吉沢亮の衣装でそのまま令和に来ても違和感ないもん。二周回ってトレンドになってんの。
そして映画は大ヒットしてるけど、分かる。
令和の映画といったら《国宝》が挙がる作品になる気がする。
李相日監督の手腕も確かだね。
題材の歌舞伎は日本人のDNAに刻み込まれてると思うんだよね。ここを扱うと響きやすいんじゃ。
それに「芸のために全てをささげる」っていう、なんなら「芸道」の感じが、日本人はそもそも好きだった。
芸に身を捧げて舞台上で死ぬのも好き。
世襲のボンボンを叩き上げの実力者が倒す構図も大好き。
こういうのを集めて、きちんと捌く吉田修一は凄い!
でも、そういうのは直木賞作家に任せておいて、芥川賞作家はもっと文学っぽい作品を書いてくれないかなあ。なあ、修一!
非常に質の高い人間劇
素晴らしいの一言。
題材の歌舞伎にまつわるシーンも素晴らしいが、人間劇の見せ方演技から役者の空気感から何もかも素晴らしかった。シーンの構成も冗長にならず、次次進んで視聴者に想像の余地を与えており、長時間の映画にも関わらず間延びは殆ど感じさせなかった。
主人公喜久雄の華やかな部分も暗い部分もそこに集積するいいことも悪いことも離れていくことも全てが喜久雄という人を魅せている。
また演者が完璧にセリフにコメられた感情、意図をこちらの想像を上回る演技の巧さで表現してきて、過剰さや作り物感がない。
一番心に残ったのは、途中曽根崎心中の代役を任され、本番前、眉を引くのに手が震えてうまく引けない後のシーン。複雑な立ち位置で切羽詰まった喜久雄の溢れ出た感情から出る台詞を見事に表現できていたと思う。このシーンは下手な役者が演じていたら絶対うまくいかなかっただろうと思う。
『半』が『全』になる
『説明不足、時間の流れが早い』等と散見しましたが、自分は想像の余地が有るあの位が好きです。
芸と血……二人の『半二郎』が、「目指していた景色」「上のほうの光」に共に到達する事で『全』になり、それこそが国宝なのかなと思いました。
※以下、自分なりの解釈と感想です。
①曽根崎心中に被せた逃亡の心理
喜久雄を通して結び付き、辛い現実から共犯(共感)者として逃げたように思いました。
俊介の「逃げたんちゃう」も芸自体からは逃げておらず、春江も「喜久ちゃんの一番のヒイキ」のままの気がします。
②いつ「全部捨てて良い」程になったのか
万菊の鷺娘が雪中の父の死を見せて、無意識に面影を追い始めた気がします。
安宿で野垂れ死ぬ万菊は、喜久雄の将来(全て捨てた姿)の暗喩なのかな。
③女性陣の存在
俊介母、春江、愛人、ドサ回り女、喜久雄の娘……女性を通して、役者の業と厳しさが見られました。
女性が可哀想だけど、男性陣もそれぞれが報われず、男女共に孤独だと思いました。
男自らが女達を捨てると言うより、失っていく感じがします。
④血統
喜久雄は芸で血統(俊介)に打ち勝ちますが、自身の血統(ヤクザの血と父の面影)からは中々逃れられず
鷺娘を舞う姿は『芸で仇討ちしたらええんや』を果たし、血としがらみから遂に解放された姿に思えました。
全て捨てて(失って)到達した舞はこの映画の一番の見所で、その余韻のままエンディングを迎えたのが良かったです。
一方で俊介は、血統で生かされ、その血統(糖尿病)で死んでいきますが、芸を全うする最期は、重すぎる血統に遂に打ち勝った瞬間なのかなと思いました。
残った脚も壊死してた時は泣けた。
⑤まとめ
対局のライバルの苦悩と決別がよく描けていて、最終的に到達した極致は、エンディング曲の歌詞『痛みも恐れも無い 光の果て』で再び出逢うようで素晴らしかった。
日本でしか作れない映像美と演技で、映画館でみるべき映画でした。
劇中・劇後の音楽も俳優さんを引き立てていたし、俳優さんの目の演技や所作は、本物の歌舞伎役者に見えました。
あ、あと着物もとても良かった。
ある意味、幸せな人たち
人生かけて芸に身を預ける?こがす?ことが出来てある意味とても幸せな人たちではなかろうか?田中さんのそれこそ人間国宝がおどろおどろしかった。芸に体も心も乗っ取られた感じがした。
前半の良さが最後まで引っ張ってくれた
全然俳優さんの名前とか知らないからずっと子役で成長物語かと思って見に行ってた。 オーブニングのカチコミというのかなのセットも良かった。 子役がまた良い。 彼らが一生懸命歌舞伎の練習をして型を身につけようとしているから色々説得力がでてくる。 国宝の歌舞伎俳優の演技を観て感動したりするのも練習の賜物だしなぁとか。 肉体の酷使とか見てると演技と言っても歌舞伎は西洋でいうところのバレエに似てるのだなと思った。 主人公が歌舞伎一家の跡継ぎに選ばれるまでは本当に面白かった。その後ちょっと中だるみしたように思ったりもしたしラストは何となくこうなるなぁという展開だった気がする。何処か中国映画の覇王別姫を思わせる。観てない人は見て欲しい。良い映画。製作側としては歌舞伎も世襲ではなく実力でしょ、
が裏のテーマかなと思った。露骨に言ったら歌舞伎界も協力してもらえないけどまあよくある話なんでしょうねで進めたのかな、と思った。 憧れの国宝の俳優さんも最後老人ホームにいるところを見るとあの人も実力でトップまでいったけど天涯孤独の人だったんだ、何処かの家の人じゃなかったんだなと合点がいった。 主人公のライバルの跡継ぎになる筈の人が贅沢三昧で糖尿病で足を失うという所に因果応報とか家柄より実力という裏テーマを感じた。 親が息子でなく主人公を選ぶ所にもう少し葛藤があってもとか思ったが難しいかな。原作読まないとね。 江戸時代の頃は家は法人みたいなもので優秀な人間を養子に入れて後を継がせるなんて当たり前だったようだけど歌舞伎はどうだったんだろう。血の繋がりを意識しはじめるのは明治以後だそうだけどね。
とても悲しい映画でした
前半はすごく面白くて涙もしたんですが後半が睡魔に襲われそうになりました…。10代から初老なるまでを描いているのですが、もう少し時代を絞って心情を深く描いて欲しかった(なぜ父親は息子に継がせなかったかの描写など…息子が将来病で足を切断する未来までわかっててそうしたのか、単にキクオの才能が並外れてたからなのか)けど、歌舞伎の素晴らしさを伝えるにはこの長さは必要だったのかもしれないです。
吉沢亮も横浜流星も素晴らしいのですが、子役の子も素晴らしいです。調べたら怪物に出てた子ですね。
映像の強さが素晴らしい。タイトルの意味を考える。
国保は邦画(というか、日本)でしか描けない画面とストーリーラインが素晴らしい映画だった。
何よりも素晴らしいのカメラワークだ。
歌舞伎の舞台の映像も素晴らしいが、練習や喜久夫が放浪しているときの、屋上での踊りの映像は息を呑む。
さて、個人的なポイントを忘備録がわりにここに残しておきたい。
この映画タイトルは「国宝」なんだけど、ふつうに考えたら「人間国宝」を意味している。
「国宝」というタイトルは人間を失った物質的なニュアンスがあると感じた。
つまりはこれは人間失格・国宝合格みたいな話で、人間を辞めていく話なんだろう。
ラストシーンについて。
あれは、喜久夫は死んでいるんだと思う。
何故なら、作中で亡くなった人はみんな畳の上で死んでない。舞台の上で死んでいる。ならば、喜久夫もまた舞台で死ぬのが必然だ。証拠はないが物語上そう解釈せざるを得ない。
師匠半二郎と半弥はともに舞台で死んでいる。
国宝としての先輩の万菊は、その立場に相応しくない粗末な所で最期の時を過ごしている。
この描写は不自然ではあるが、「役者はまともな死に方できない」という物語の必然を表すためだと思う。
そして、ラストシーン直前に私生児の綾乃とともに話す「歌舞伎が上手くなるなら、何も要らない」という「取引」の話から、国宝になって歌舞伎が上手くなった喜久夫は悪魔の取引により、何かを奪われているはずだ。それ以前もさまざまなものを失っているが、最後に奪われるものは、もう命しかないだろう。
そして、次のテーマの血である。
表面上は半二郎と半弥の親子の血とそれを持たない喜久夫の対比的テーマに見えるが、また、喜久夫もまた血に囚われてしまう。
一つは極道の息子という血。
これは物語中盤にスキャンダルとして現れてしまう。これは半弥が親子の血を大切にしていたゆえに、半二郎が代役を喜久夫にしたときの葛藤と同じく逃れられない運命として現れる。
そして、喜久夫は極道の息子として、親の仇を討つという運命も持っている。そもそも半二郎のところに行く動機の一つに仇討ちに失敗したからだというのがある。もし、仇討ちよりも芸事の関心が高ければ、仇討ちを試みずに直接、半二郎のもとに向かうはずだ。
そして、劇中で、半二郎から「芸は刀や鉄砲よりも強い。芸事で仇討ちしろ」という趣旨のことを言われている。ある程度、弟子になってから後のシーンだったので、喜久夫の中に親の仇という運命はずっと燻っていたのだろう。
「悪魔の取引」をしてまで、歌舞伎に没入していくのは、喜久夫が歌舞伎が好きだというのも、もちろんあるが、それと血による運命もあると思う。
半二郎と半弥の血のつながりは美しい繋がりと一見見えるが、これもまた負の側面がある。
それは病気だ。半弥は若くして糖尿病で足が壊死してしまい、それが原因で死んでしまうが、父、半二郎もまた糖尿病で目が見えなくなってしまう。これもまた逃れられない血の運命を象徴している。
また、背中の入れ墨のミミズクについて。
劇中では恩を忘れないという説明がされている。
これは少年時代の極道の息子として入れ墨を入れているから喜久夫の信念のはずだ。そして、ミミズクの説明したときに、半弥に「ヘビやらネズミやらお返しするんや」と言って「そんなの嫌だ」と返事されている。これは喜久夫の生き様を象徴していて、恩を返すつもりが実際には望んでないものを返してしまうという喜久夫の生き様が表れている。悪魔の取引とすれ違いのミミズクの恩返し。これが喜久夫の波乱を根底にある。
あと芸事に対して飛躍するのは、舞台や稽古だけでは務まらないというのもなんか意味のあるテーマかもしれない。半弥も喜久夫もどっちもドサ周りして、真の芸を身につける。半弥も失踪した後に、急に帰ってきて「プリンスの帰還」みたいな扱いは受けるが、若い頃のぬるさがドサ周りで解消されたから、のちに白虎を襲名できるほどのレベルに達したんだろう。一方で、喜久夫はあの屋上で、森七菜演じる彰子を失ったところで覚醒する。あれも「悪魔の取引」だが、半弥も同じような経緯を辿っていることをみるに、日陰や歌舞伎界を離れての経験がなければ、国宝レベルの芸は身につかないんだろう。それを示唆するものは僕では読み取れなかったが、また見たときにそれを読み解きたい。
あと、超蛇足だけど、この作品は昭和時代の描写が多いし、歌舞伎が女性を排除してきた歴史的経緯もあり、男性中心的な作品になっている。
女性の描写も個人を掘り下げるよりも、道具や物語上の構造に置かれているというポリコレ的、フェミニズム的批判もたぶんあるんだと思う。そういうことをいう人がいそうな映画ではある。
ただ、そういうこと言いたい現代的な感覚もわかるが、これは歌舞伎時代がかなり無理な構造で成立していて、そしてそれが次世代に続かないであろうことも示唆されている。半弥の息子が歌舞伎にそこまで関心を持たないことから、おそらく丹波屋も血筋の継承は途絶えるであろう。よって、ポリコレ的にどうなんだという批判は、この映画自体が、歌舞伎のポリコレ的限界による苦境を表している映画だと思う。
抽象的な物をどう理解するか
いわば現代アートのような抽象性があった気がします。いかに寛容に柔軟に内容を受け止められるかが重要なのかなと思いました。
飛び飛びでわかりにくい部分が多かったです。説明されないと気持ち悪いともう方も少なからずいらっしゃると思います。
しかし、ここに「想像することが出来る」というものが隠れているような気がしました。やはりこうなるのか、いやこの事があったからこうなるのか。など3時間があっという間でした。
音楽が素晴らしかったですが少し頼り過ぎでもあるのかなと思いました。ただ、音楽に頼らないきめ細やかなセリフのみのシーンはそれに負けないくらいとても綺麗でした。
気楽に、見たものを自分の中にすっと落とし込むことではまる映画だと思います。そうすることで自然と鼓動が映画についていってました。
想像できるという一面もありましたが、ただただ美しかったです。
なぜ国宝となったのか?
国宝を初視聴。
ポップコーンとコーラを購入し臨んだが、ほとんど手をつけずに終わったほどに、あっという間の175分だった。
視聴後も気づけば小一時間ほど各種歌舞伎の場面が頭をよぎる時間が続き、心地よい放心状態だった。
落ち着いて映画を振り返って気になったことがひとつ。
なぜ喜久雄は、血の繋がりが無い中で数少ない歌舞伎界の味方であった俊介が逝去した後、国宝となれたのか?
血の繋がりは喜久雄が映画を通して求めてきたものであるにも関わらず、結局それが無い中で大成出来たのには、どのような行間があったのか。
劇中劇を通して、裏方にハイライトが多く当たっていたように感じた。歌舞伎の一舞台には多くの人が関わっているのだと思った。
普通に考えると、必須なのは血の繋がりではなく人との繋がりであり、血はその手段でしかないのではないかと思う。
国宝となるためにも人との繋がりが必須なのだろうか。
喜久雄は国宝へとなる過程で、何をもって人との繋がりを築くことができたのか。
無粋と承知で、何があったかを知りたいと思ってしまいました。
総じて良かった
今は、独り者なので、書き込みさせてください。
皆さんがおっしゃるように、映像美は素敵です。表現スタイルはオーソドックスで、古い感じもあります。脚本で残念なのは、ヤクザにピストルとドスで仕返しに行っても1年後は歌舞伎の道に行く点。未成年で未遂だったとしても落とし前はどうしたの?後ろ盾を無くしてごめんなちゃいでは済まないはず。演出で残念なのはラストシーン。舞台で横たわる後ろ姿、呆然とした立ち姿、最後の一言が全部、男。素に戻った自意識の吐露はわかるけど、舞台の上では女形に徹して。後は直接関係無いけど、猿之助が気になった。世襲に反旗を翻し始めて大当たりするも東大卒の息子に事実上殺され、因縁のようなものを感じた。生き延びた息子はどんな思いでこの映画を見たか。
全566件中、161~180件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。