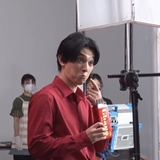国宝のレビュー・感想・評価
全2354件中、1041~1060件目を表示
上質な芝居!
ちゃんとエンタメ作品なのに
まるでドキュメンタリーを
観ている様なとっても上質な芝居!
見ているこちらに緊張感がひしひしと伝わってくる
見終わった後にぼーっとしてしまう作品は
本当に久しぶり!!
普段はヨリが多い作品好きじゃないのですが、
周りの状況とか物語とかではなく、
役者の表情が全てを物語ってくる。
吉沢亮と横浜流星の組み合わせが最高に良い。
2人の役の感情がシーソーの様に入れ替わるのに、
ちゃんとどちらにも感情移入出来る。
どっちつかずにならず素晴らしい。
田中泯と黒川想矢も良い。
とにかく全員のお芝居がとても良い。
映像も良き塩梅でテンポが早い訳じゃないのに
全く3時間を感じさせない秀逸な作品でした。
強いて言うと、
もっと盛り上げるとこ盛り上げて感動というか、
泣きにいかせてもと思う箇所があったなぁと。
ただそれをやってないからエンタメに振りすぎず
ドキュメント感があったのだろうとも思う。
歌舞伎って何処が良いの?な私は・・・
圧巻
期待し過ぎたところがあり…
観たい観たいと思い続けて1ヶ月半、壮大な期待を持って臨んだ鑑賞だったのもあり、それを超えることがなく終幕を迎えた。役者の演技力も全体の構成も演出も最高だけどストーリー展開としては心が震えるとかグッとくるところがあまりなかった。でも歌舞伎には大いに興味を持った!
吉沢亮と横浜流星が競う美
国宝
本当に吉沢亮と横浜流星始め、俳優さんたちの演技力の高さに度肝を抜かれました。とても薄い感想のように聞こえると思うのですが、冗談抜きで今まで見てきた映画の中で本当に1番と言える映画でした。
わたしにとって歌舞伎という存在は遠い、教科書に載っているものという認識しかなく、歌舞伎俳優さんたちがドラマや映画で出ていると演技すごいなあという感想しかなかったです。ただ、この映画ではその歌舞伎俳優たちが何を目指し、何を想いながら演じ、何を叶えるのか、何を犠牲にするのか、など描かれていました。特に、喜久雄がお初を演じたシーン。師匠である半二郎のお初の代役を任せられた覚悟、化粧する時の手の震え、本当に自分にお初が勤まるのか、俊ぼんでなくていいのかの葛藤、台が上がっていくときの沈黙、観客が見えた時の緊張感、そのシーン全て全てに臨場感があって気づいたら息をするのも忘れ、目に焼き付けていました。幕が上がる瞬間、まるで自分が喜久雄の立場に立っている感覚に陥り、心臓が口から出そうなほどでした。化粧しようとしても震えが止まらなくなっているときに俊ぼんがきて、喜久雄の「怒らんで聞いてくれるか」という言葉に微笑みながら紅を指し、「今、1番俊ぼんの血がほしいねん」(セリフ曖昧でごめんなさい)のシーン、胸が苦しくなりました。その後の俊ぼんの「芸があるやないか」という言葉でさらにやられました。血筋はないけれど天性の女形の才能を持つ喜久雄に対して、大きな血筋と地位はあるけれど喜久雄に芸は劣る俊ぼんという対照的な描写が本当に苦しかったです。良くも悪くも「血」でした。半二郎が糖尿病にかかり、舞台の上で吐血し、最期であろうときに口にしたのは「俊ぼん」だったのも、その俊ぼんが戻ってきて2人で道成寺をやったときに倒れて同じく糖尿病になったのも、舞台の上で倒れたのも、結局血でした。喜久雄には極道の「血」が流れていて、周りを全て犠牲にしてでも不幸にしてでも人間国宝になっていくのも、息子ではなく娘(綾乃)がいたのも、病気にかからなかったのも全てが血だということを感じました。
屋上のシーンはアドリブだと聞いて震えました。彰子が泣きながら「どこ見てんの?」と言って離れていったあと「どこ見てんねやろ」と泣きながら笑い、舞うシーン、本当に辛くて虚しくて、ただただ美しかったです。
吉沢亮の演技を見ている、というより喜久雄の人生をぎゅっと纏めたもの、いわば走馬灯のような3時間でした。役者というのはこんなに汚く美しいものなのか、これほどまでに残酷で虚しくやるせなく、美しい世界があるのかというぐちゃぐちゃな感情になりました。
本当に素晴らしい作品だったのですが、何個か気になった点がありました。森七菜演じる彰子はどこに行ってしまったのか、藤駒も舞台を見に来たりしているのか(綾乃が舞台を見て気づいたらめいっぱい拍手をしていたと言っていたため)、なぜ最初抗争が起きてしまったのか、春江はどんな気持ちで俊ぼんのところへ行ったのか、どうやって俊ぼんと喜久雄は仲直りしたのか、などというところが細かいのですが気になる点でした。
わたしなりに春江が俊ぼんのところに行ったのはきっと喜久雄の演技をずっと傍で見ていたかったからなのかなと思いました。喜久雄の結婚しよっかに対して、「今は喜久ちゃんの役者としての上り坂やねん。今よりいっぱい稼いで1番のご贔屓さんになろ。(略)ペルシャ絨毯買うたろ」とやんわり断ってそれを理解した喜久雄が家を出ていき、春ちゃんが泣いてるシーン。きっと、春江的には喜久雄の奥さんになりたかっただろうけれどこれからどんどん歌舞伎に夢中になって自分のことをいつか見てくれなくなるのでは無いのだろうか、という気持ちでいたときに喜久雄のお初を見て劇場を抜けた俊ぼんの「逃げるんとちゃうで、本物の役者になりたい」という言葉に同じ気持ちを見出して2人で逃げ出す=心中したのではないかと思いました。血筋がない喜久雄と結婚したとしてもどうやったって歌舞伎の血は流れず跡継ぎはできないから、それならば確実に血が流れていて、地位のある俊ぼんの丹波屋に嫁いで喜久雄を入れることでずっと喜久雄の演技を見ることができると判断したのかなあと。映画終盤の喜久雄が演じた鷺娘のシーンの春江の表情はきっと、昔の喜久雄を見てる時と同じ表情をしていると思いました。喜久雄と同じように背中に刺青を入れた春江は、大好きな喜久雄の夢を叶えるためなら、離れていようが、自分も喜久雄のためになんだってする、という気持ちがあったのではないのでしょうか。
という本当に感情がぐちゃぐちゃになる素晴らしい映画でした。今年の色んな賞を総なめするでしょう。楽しみです。
原作とは違う。でも満足度はかなり高い
評判通り、劇場で観て本当に良かった。上下巻の原作、歌舞伎役者の50年の歴史を3時間におさめると、省略される部分は仕方ないと思う。
それでも、昭和の西日本の、重くて濃密すぎる家族の雰囲気が、リアルに伝わってきた。
柄物いっぱいの洋服も、一昔前のクローゼットが再現されているようで楽しい。
芸だけを求め、最後はたった1人、別の世界に立っている喜久雄の空気を、美しいと思うことが不思議だった。
吉沢亮の、孤独であること自体にも興味がなさそうな、虚無の表情は良かった。
冷んやりキリッとした清潔感と、角がない柔らかさが同居している存在が、国宝なんだなと感じる。
小説を読むのとは別の、映像で体験するいろいろな感情が十分に味わえて、本当に良い作品だと思った。
私たちの世代が生きている中で、1番有名な日本映画になるような気がする。
ー「景色」というのは、全てをも犠牲にした人間が何か一つを極めた先で...
ー「景色」というのは、全てをも犠牲にした人間が何か一つを極めた先で見られるものだ。「芸」以外のものを犠牲にし、「悪魔」とまで取引をして日本一の芸者になった喜久雄は本当に幸せだったのだろうかー
私は「歌舞伎」という日本に古くから伝わる伝統芸能に触れたことも、目にしたこともなかった。この映画を観るにあたり、私と同年代を含む多くの人が「歌舞伎を見たくなる映画だった」と評していた。3時間という長尺の映画を鑑賞したことがなく、最後まで座っていられるのか不安だった。しかし、そんな不安とは裏腹に、3時間はあっという間に過ぎていった。映像も音も大変に繊細で、綺麗で、それぞれの登場人物の心情や表情を大きいスクリーンで観ることで、自分もその作品の一部なのではないかと錯覚させられた。
この映画に役者として演じている俳優たちはみな、顔が綺麗なのは当然のこと、演技力がピカイチだった。それがまた、私たち視聴者の心を揺さぶり、それまで見向きすらしたことなかった歌舞伎の世界に片足を出そうかという思いにさせたのだろう。
歯車が狂い始めたのはどのあたりだろうか。映画鑑賞後、友人が「俊介の血筋が不幸を招いたのね」と言っていた。確かにその通りで、努力でのし上がった喜久雄と違って、初めから歌舞伎役者の名の下に生まれ育った俊介は一度は失踪したものの、父亡き後には歌舞伎役者として再び戻ってきた。それに引き換え、喜久雄は半二郎就任直後に歌舞伎の世界から干されている。
糖尿によりこの世を去った父同様、俊介も若くして糖尿にかかり、歌舞伎役者として舞台に立ち続けることが難しくなっていく。「遺伝」してしまった「血」は、俊介にとっては自分の歌舞伎役者としての人生を保証するものであったのと反対に、喜久雄が喉から手が出そうなほど欲しがったものだ。
映画鑑賞後、私たちは「この映画を一言で表すなら」と、「一番可哀想な人と一番残酷な人は誰か」という話で持ちきりだった。単なる「ヒューマンドラマ」や「成長物語」と謳うにしては、この映画の良さは何一つ伝わらない。人に勧められるに値するキャッチフレーズがなかなか思い浮かばない。私がそこで出した答は「人生と犠牲」だったが、それだけではネガティブな印象になってはしまわないだろうか。結局、その問いに対する私たちの答えは出ないまま解散してしまった。では、「一番可哀想な人と一番残酷な人は誰か」に対して、一番可哀想なのは、森奈々演じる彰子なのではないだろうか。喜久雄のいわば「道具」にしか過ぎないように感じた。喜久雄が歌舞伎の世界に戻るために彼女をものにしたのにも関わらず、俊介が歌舞伎役者として活躍する今、小さな劇場等で自分たちの力で営業をして出向くしかなかった。森奈々はそのどれにもついて行くが、2人の関係に「愛」があるとは見受けられなかった。彼女は都合の良いように利用され、そして喜久雄の元を去っても未練すら抱いてもらえない可哀想な存在だった。森奈々はインタビューで以下のように語っている。
「表現を追い求める先にあるものが楽園への道とは限らない。それでも人生を賭ける理由がこの世界にはある」と。
喜久雄の「悪魔との取引」は成功して、最後には「国宝」として日本一の歌舞伎役者になった。それまで、歌舞伎以外の全てを犠牲にして。喜久雄が娘のあやめと再開するインタビューのシーンで語った「未だ見ぬ景色」は彼が「国宝」となって舞台に立った頃、ようやく現れた景色だ。それが彼にとってのさらなるスタートラインとなっただろう。
ようやくスタートラインに立つことができた彼は、幸せだったのだろうか。原点でもある「景色」を見させてくれたかつての「国宝」のように、喜久雄も死ぬ間際には「綺麗なもの」が何もない質素な部屋で生涯を終えるのだ。
まずこの時代に歌舞伎役者というものを題材に人気若手俳優を起用したの...
チュニジア人カメラマン
歌舞伎への積もる思ひは、果敢なき
日本人であるので、この題材は観ておかなければいけないと思い、本作を観ました。
原作未読 歌舞伎・梨園の緒事情を ほぼ知りませんが、
本作を鑑賞後に、坂東玉三郎さん演じる「鷺娘」と人形浄瑠璃「曾根崎心中」を配信で、観させていただきました。
本作では、喜久雄と市駒との関係が、少し薄い気がしたのが残念でしたが、
これ以上作品を膨らませると、4時間超え映画になってしまうので、致し方あるまい
義兄弟を扱った映画は多々ありますが、義兄弟故(ゆえ)に、"ひとつ"しかないものを、2人で奪い合う宿命に成るが、
本作での、他に類を見ない"唯一無二な展開"は圧巻な脚本でした。 <原作賞><脚本賞><監督賞><作品賞>
この大作を演じた 吉沢 亮さん、横浜流星さん、のおふたりの演技は、
歌舞伎役者そのものの域にまで達しており、実に見事でした。 <主演賞><助演賞>
映画の撮影も、無理なライティングをせずに、やさしい光の中に、的確なカメラ配置を行った撮影は素晴らしかったです。<撮影賞>
「ずっと見たい景色」とは、男が女方を演じる歌舞伎において、更にその先にある域は人間でもない 孤高の白鷺(国宝)であり、下手(しもて)の非人間世界なのではないでしょうか。
この無双な映画を観たら、並ぶ映画は在りません。
よって、歌舞伎を扱ったドラマ「タイガー&ドラゴン」を観ると、本作と同じに、うまい"枕の扱い方"に注視する事が出来るでしょう。
あまりにも凄くて、こわかった
素晴らしかった。初めから終わりまで鳥肌がたち、涙が出てました。
吉沢亮さん、本当に本当にお疲れ様でした。
目や表情が凄くて終盤はもう怖かったです。悪魔と取引してましたね。
また、喜久雄の幼少期を演じた黒川想矢さんの出てきた時の色っぽさにギョッとしました。
個人的に見上愛さんが好きなんですが、演技もとても良かったです!
というか、みなさん凄かったです…、お疲れ様でした…。
ここ数年で一番の傑作邦画
歌舞伎映画でここまで人が映画館に足を運んでいるのが嬉しい
「歌舞伎」という文化遺産というテーマで、一般大衆をこれだけ沸かせることができたのがすごい。目を見張るその映像美は、『アデル、ブルーは熱い色』の撮影を担当したソフィア・エル・ファニの魔法もあったか。歌舞伎への情熱と愛を感じる。
最初の雪の中のシーンから、心震える。今作の1番の好きなポイントは、セリフに頼らずに歌舞伎を通して、語られるそのストーリー。言葉では表しきれない複雑な思いをスクリーンから感じることができる。特に「曽根崎心中」のシーンには、感情を揺さぶられずにはいられない。
ストーリーライン的には、驚きがなく確かに単純なところがあるが、それでも歌舞伎に興味がない層にもその3時間飽きさせないというのが今作の力か。
前回、ここまで満席の映画館を見たのはいつだろう。やはりみんなでこう映画を楽しめるのが何より嬉しい。
表情がいい
歌舞伎のことはほとんど知りませんでしたし、時間的には長い映画でしたが出演陣と映画の中の役者の熱量が非常に高く感じられ目が離せなかったです
体感は2時間くらい
そりゃ、年末の不祥事は(そこまでのものでもないけど)あっという間に解決させるわ
こんないい映画、見なけりゃ
ストーリーは細かく言えばよくわからないところがちょくちょく見かけられましたが、そんなところを深掘りしてたら5時間を超える映画になってしまうだろうかと
人間のひたむきさ、努力する姿、ずるさ、傲慢さ
とても人間の良さも悪さも描かれていて良かった
人間の汚さを(私にとってはですが)美しく表現されてる感じがしました
印象に残ったのは
大抜擢され、楽屋で手が震えるところと、あの台詞
化粧を代わりにしてやる表情
悪魔に魂を売ったベッドの上でのあの表情
どれもこれもたまらん
歌舞伎のことを知っていれば舞の素晴らしさとかわかったかもしれないですなぁ、そこは力不足の客ですまん、と思う笑
でも、2人とも美しいなぁとは思ったです
これから、ババンババンパイアに行くんだけど、どんな気持ちで観ればいいの?笑
飽きさせない長編…ただし私は
原作のダイジェスト、でもとても面白かった。なぜ、女が来るのか、出ていくのか、そうなることの理由が観客の知識と経験に任されるところが、いいのか悪いのか。
ツレの女性の感想として、とにかく吉沢亮が美しいとの声があるが、男の私にはそれは分からない。脇役、四代目鴈治郎が出てくるだけで上方歌舞伎の雰囲気がピリッとしまる。この役が二代目であればいうことなし。叶わぬ夢だが。さらに歌舞伎界ではないが、田中泯の演技が素晴らしかった。彼の演技だけでも、もう一度見てみたい。
…
ここからは余計なコメント。
時代考証が甘い。都市の景色、人々の服装、髪型、努力はしているが、リアリティを損ねてしまう。主人公が私と同世代。そして大阪と京都。戦後日本の時代の変化と街の有りようをもっと緻密に描いてくれたら、ストーリーにさらに没入できたのだが。
全2354件中、1041~1060件目を表示
映画チケットがいつでも1,500円!
詳細は遷移先をご確認ください。